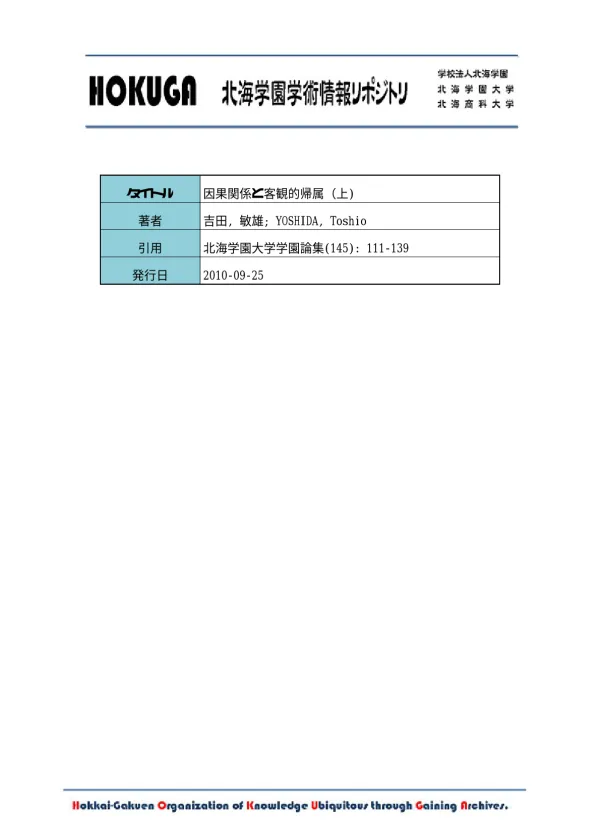
因果関係と客観的帰属:刑法における責任
文書情報
| 著者 | 吉田敏雄 |
| 専攻 | 刑法学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 820.96 KB |
概要
I.因果関係の理論 条件説と合法則的条件論
本論文は、刑事法における因果関係(Inka Kankei)の認定をめぐる諸理論を分析しています。伝統的な条件説(Jouken-Setsu)は、結果発生に不可欠な全ての条件を原因とする等価説ですが、競合的因果関係(Kyougou-teki Inka Kankei)や仮定的因果関係(Kateiteki Inka Kankei)といった複雑なケースには不十分です。そのため、より実証的な合法則的条件論(Houhou-teki Jouken-Ron)が提唱され、自然科学的法則に基づく具体的因果関係と一般的因果関係の峻別が重要視されるようになりました。裁判官は自由心証主義の範囲内で具体的因果関係を認定しますが、一般的因果関係の定立はできません。この理論では、行為と結果の間に自然法則的な連関が存在するかが判定基準となります。
1. 条件説の限界と自然法則的連関の重視
刑事法における因果関係の認定において、従来の条件説(Bedingungstheorie)は、仮定的因果関係や競合的因果関係といった複雑な状況下では不十分であることが指摘されています。 具体的には、結果の発生に寄与した全ての条件を同等に原因とする条件説では、複数の原因が絡む場合や、行為が結果に直接的に結びついていない場合に、因果関係の有無を適切に判断できないという問題点があります。そのため、行為と結果の間に自然法則的な連関が存在するかどうかが、因果関係を判断する上で決定的に重要であるとの認識が高まりました。この考え方を基盤とする合法則的条件論は、自然科学的法則に基づいて、行為と結果の因果関係を検証しようとするものです。この理論では、個別事例に適用可能な自然科学的因果法則(一般的因果関係)と、具体的事態をこの因果法則に包摂する過程(具体的因果関係)を明確に区別します。裁判官は自由心証主義に基づいて具体的因果関係を認定できますが、一般的因果関係を自ら定立することは許されません。乙の打撃を丙の肩にそらせた甲の行為も、丙の傷害という結果に因果関係があるとされる点も、条件説の限界を示す一例として挙げられています。
2. 合法則的条件論 自然科学的法則と因果関係
合法則的条件論は、行為と結果の間に自然法則的な因果連関があるかどうかを検証することで因果関係の有無を判断しようとする理論です。具体的には、ある行為に続いて、その行為と自然法則的に結びつく時間的に後続する外界の変化が生じたかどうかを問う「合法則的条件の公式」を用います。この公式では、因果関係を判断する上で、既知の因果法則や確実な経験的認識が前提となります。そのため、専門家の専門知識に基づく判断が重要になります。この合法則的条件論は、複数の原因が相互に独立して作用する競合的因果関係においても、それぞれの原因と結果の間に自然法則的な連関があれば、因果関係を肯定的に判断することができます。ドイツ連邦通常裁判所の判例にあるように、製造物責任において原因物質が特定できない場合でも、製品の性質が被害をもたらす原因となっていることが認定されれば、因果関係が認められる可能性があります。疫学的な因果関係の認定基準も提示されており、原因とされる因子が発病前に作用すること、因子の作用の程度と発病率の関連性、疫学的な流行特性との整合性、生物学的な作用機序の説明可能性などが挙げられています。ただし、疫学は病気の予防を重視する学問であるため、刑事事件への適用には慎重な吟味が必要です。特定の化学物質の反応や長期効果など、自然法則自体が不明確な場合は、因果関係が否定される可能性があります。
3. 合法則的条件論と等価説 条件説 の関係
合法則的条件論は、等価説(条件説)を基礎としつつ、その欠陥を補う理論として位置付けられています。等価説は、形式的な消去手続きに基づいて因果関係を判断するため、実際の自然科学的因果連関を無視しているという批判があります。一方、合法則的条件論は、自然科学的法則に基づく実質的な因果連関を重視し、行為が結果を実際に惹起したかどうかを検証します。そのため、等価説の消去手続きは完全に放棄されるわけではなく、問題のない事例では補助的な手段として活用され、疑問がある場合にのみ、自然法則に基づく因果関係の検証が優先されます。不作為犯においても、合法則的条件論の公式は、仮定的因果関係の検証に用いられ、必要であった行為を付け加えることで、結果を回避できた可能性を検討します。この場合も、自然法則的な連関が引き続き因果関係の尺度として機能します。つまり、等価説と合法則的条件論は、互いに補完し合う関係にあると捉えることができます。
II.相当因果関係説とその他の理論
**相当因果関係説(Souto Inka Kankei-Setsu)**は、一般的生活経験上、結果発生に適さない条件は結果帰属の基礎とはならないと主張します。しかし、危険減少事例など、この説の曖昧性や限界も指摘されています。また、**重要性説(Juuyou-sei-Setsu)**は因果関係と結果帰属を区別しますが、実質的な規準に欠けるとして批判されています。これらの説は、**客観的相当因果関係説(Kakkan-teki Souto Inka Kankei-Setsu)**や主観説、折衷説といった様々な立場から議論され、判例においても様々な解釈が示されています。
1. 相当因果関係説の概要と問題点
条件説の限界を克服するために提唱されたのが、相当因果関係説です。この説は、一般的生活経験上、特定の結果を惹起するのに適さない条件は、結果帰属の基礎とはならないと主張します。つまり、異常で非蓋然的、非類型的因果経路は、構成要件該当性の段階で排除されるべきだとするものです。これは、構成要件段階での責任限定を試みるもので、肯定的に評価できる側面があります。しかし、問題点も指摘されています。例えば、危険減少の事例では、相当性連関が否定されず、故意責任が問われることになります。また、「一般的生活経験」という基準が曖昧で、そこから一義的な結論を導き出すことが困難であるという点も課題です。さらに、因果関係を基礎として責任の範囲を限定しようとする試みもなされてきましたが、刑法規範の性質上、構成要件的不法結果を招いたというだけでは、規範違反とは言えないため、この試みは成功しませんでした。客観的構成要件要素の認識・意欲があれば故意が認められるという考え方では、危険減少事例における責任の所在が曖昧になります。
2. 重要性説の批判と客観的帰属論
メツガーの重要性説は、因果関係の問題と結果の帰属の問題を区別しようと試みました。しかし、この説は具体的事案において有用な結論を導き出すだけの理論的展開を欠いており、結果に対してすべての原因が同じ価値を持つという前提から、それらが帰属のための等しい法的重要性を持つわけではないと主張するに留まります。相当因果関係説の蓋然性判断とは異なり、法規定の意味や目的に対する違反という観点から可罰性を検討する目的論的解釈に基づいています。しかし、実質的な規準を欠き、「規制的法治国原理」として批判されています。刑法における責任の限定という重要性説の関心は、現代刑法理論においては客観的帰属論に吸収されたとされています。
III.作為犯と不作為犯における因果関係
作為犯では、現実の因果連関が重要視されます。条件説は、消去法を用いて因果関係を検証しますが、限界があります。一方、不作為犯では現実の惹起行為が存在しないため、擬似因果関係という仮定的な因果関係の概念が用いられ、自然法則に基づく予測可能性が重要となります。合法則的条件論は、作為犯と不作為犯の両方において、自然法則的な因果連関を重視したより厳格な因果関係の認定基準を提供します。
1. 作為犯における因果関係の認定
作為犯においては、結果に効果を及ぼした現実の因果連関が重視されます。伝統的には、条件説(Bedingungstheorie、等価説)によって因果関係が認定され、ある結果の原因となるのは、その結果をその具体的形態において消滅させることなくしては取り去って考えることのできない全ての条件であるとされています。この検証方法は、消去手続きと呼ばれ、実在の因果過程と、行為が無かった場合の仮定的経過を比較することで因果関係を判断します。具体的結果が当該行為が無かった場合には生じなかったと言える場合、当該行為は原因とされます。しかし、条件説には、経験的因果関係の範囲内で因果関係の諸要素を区別することが論理的にできないという批判があります。また、条件公式は、結果が複数の相互に独立した行為によって影響を受ける場合(競合的因果関係)や、ある行為が他の同じ結果とは独立して同時に直接的に作用連関において結果を招来した場合(狭義の仮定的因果関係)にはうまく機能しません。これらの場合、条件公式では因果関係が否定されてしまい、合法則的条件説に頼らざるを得なくなります。修正された条件公式では、行為の原因性は常に事象のあらゆる事情によって個別化された結果と関係しなければならないとされていますが、それでも限界は残ります。被害者の異常体質や、異常な因果経路(例:交通事故の後、病院で焼死)、被害者の不適切な行為や第三者の介入行為によって因果連関が中断されることはありません。
2. 不作為犯における因果関係 擬似因果関係と自然法則
不作為犯では、現実の惹起行為が存在しないため、条件説による因果関係の検証は困難です。「無から無は生じない」という簡潔な結論に達してしまいます。しかし、行為と結果の間に社会的、規範的な相関関係は認められうるため、存在範疇を超えた考察が必要です。そこで、行為者がしなかった行為をすれば結果を回避できたという仮定に基づいた擬似因果関係が導入されます。この場合、自然法則の連関が、間接的ながら因果連関の尺度として引き続き役立ち、自然法則の連関が予測判断に影響を与えます。従って、経験に基づいた法学的範疇としての因果関係と考えることもできます。仮定的因果関係とは、実際に具体的結果の発生に効果のなかった行為について、その結果発生に効果を及ぼしえたと云える場合に用いられる表現です。作為犯においては、実際に効果を現した原因だけが重要であり、仮定的因果経路は因果関係が否定されます。諜報機関員が追跡対象を射殺したが、その対象が乗る予定だった飛行機が墜落して全員死亡したケースでは、射殺行為がなくても死亡したという仮定は考慮されません。
IV.判例と因果関係の認定
日本の戦前・戦後の判例では、条件説が基本でしたが、相当因果関係説の影響も認められます。重要な判例として、浜口首相暗殺事件、神水塗布事件、アメリカ兵ひき逃げ事件、夜間潜水訓練事件、大阪南港事件、高速道路進入事件、トランク監禁致死事件などが挙げられます。これらの判例は、第三者の行為介入、被害者自身の行為、予見可能性など、様々な状況における**因果関係(Inka Kankei)**の認定について示唆を与えています。千葉大チフス事件のような疫学的証拠に基づく因果関係認定の判例も存在します。
1. 戦前 戦後の判例における因果関係の認定
日本の戦前、判例は例外を除き、基本的に条件説に基づいて因果関係を認定していました。昭和3年4月6日大判(刑集7巻7号291頁)では、被告人が被害者を極寒の戸外に遺棄した結果、被害者が肺気腫が悪化して死亡した事案において、条件説を直接適用し、遺棄致死罪の成立を認めました。この判決は、犯罪行為と重大な結果の間に、前者がないと後者もなかったであろうという関係があれば、犯罪行為が結果の直接的原因であるか否かを問わず、結果的加重犯が成立すると判断しています。また、昭和5年10月25日大判(刑集9巻761頁)の重症脳震盪事件では、被告人が被害者を殴打して川に突き落とした後、被告人の配下の者が被害者を再び川に投げ込み溺死させた事例において、最初の殴打と溺死の因果関係を肯定しました。さらに、被害者の行為や第三者の行為が介入した場合でも、因果関係が中断されるとは限らないとされた判例があります。大判大正12年7月14日(刑集2巻658頁)の神水塗布事件では、被害者が傷口に神水を塗布したために丹毒症になり死亡したケースでも、被告人の暴行と死亡の因果関係を認めました。同様の事例として、大判昭和2年9月9日(刑集6巻343頁)の火傷事件、最判昭和25年11月9日(刑集4巻11号2239頁)の暴行と転倒による負傷事件などがあります。これらの判例は、条件説を基礎としながらも、結果発生への多様な要因を考慮していると言えるでしょう。
2. 相当因果関係説の導入と判例への影響
戦後、相当因果関係説が導入され、判例にも影響を与え始めました。浜口首相暗殺事件では、第一審が殺人既遂を認めたのに対し、控訴院は相当因果関係説に基づき殺人未遂としました。この事件では、被告人が浜口首相を射撃後、首相は約9ヶ月後に死亡したのですが、死亡原因となった放射状菌感染が銃創によるものか否かが争点となり、日常経験上一般的でない稀有な事例として因果関係が否定されました。しかし、戦前においても相当因果関係説的な言い回しが用いられた判例が存在しました。例えば、「吾人ノ智識経験ニ拠リ之ヲ認識シ得ヘキ場合」「社会生活上ノ普通観念ニ照シ」「死ノ転帰ヲ見ルヘキハ実験則上明ナルカ故ニ」「常在ノ事実ニシテ稀有ノ現象ニ非サルヲ以テ」といった表現です。アメリカ兵ひき逃げ事件では、第三者の行為(同乗者の暴行)が介入した場合にも因果関係を肯定する判例が出ています。また、東京高判昭和41年10月26日において、同僚兵士が被害者を自動車から引きずり落としたことで死亡に至った事件では、一審二審が因果関係を肯定したのに対し、最高裁は相当因果関係説を採用し、業務上過失致死罪を認めず業務上過失致傷罪のみを認めました。これは、引きずり落とし行為が経験則上予想されにくいと判断されたためです。その後も、様々な事例で相当因果関係説が適用されていますが、その解釈には幅があります。
3. 具体的な判例分析 第三者行為 被害者行為 予見可能性
判例では、第三者の行為介入や被害者自身の行為が因果関係に及ぼす影響が検討されています。例えば、大阪南港事件では、被告人の暴行で被害者が意識不明となり放置された後、第三者による暴行で死期が早まったケースにおいて、最初の暴行と死亡の因果関係を肯定しました。高速道路進入事件では、被告人の暴行から逃れるために被害者が高速道路に飛び出し死亡した事例で、暴行と死亡の因果関係を認めました。治療拒否事件では、被害者が無断退院し、治療用の管を抜いたことで死亡したケースで、最高裁は因果関係を否定しました。トランク監禁致死事件では、被告人が被害者を車のトランクに監禁し、追突事故で被害者が死亡した事例で、監禁行為と死亡の因果関係を肯定しました。これらの判例からは、第三者の行為や被害者自身の行為が介入した場合でも、当初の行為と結果の間に因果関係が認められるケースと、認められないケースが存在することが分かります。因果関係の認定においては、予見可能性が重要な要素であり、客観的相当因果関係説では、行為当時一般人が予見できたか否かが基準となりますが、判例によって判断は様々です。未知の結核性病巣事件のように、被害者の特殊な体質や病状が結果に影響を与えるケースでも、因果関係が肯定される場合があります。
V.ドイツ判例と因果関係の理論
ドイツの判例は、条件説(Bedingungstheorie)を基本としつつ、自然科学的因果連関の重要性を重視しています。ライヒ裁判所や連邦通常裁判所の判例は、条件説に基づき、結果の消滅を伴わずに行為を消去できない場合に因果関係を肯定しています。しかし、複雑な状況下での因果関係の認定には、依然として議論の余地が残されています。
1. ドイツ判例における条件説の適用と因果関係の認定
ドイツの判例は、遡及禁止論を一貫して採用しておらず、条件説(Bedingungstheorie, 等価説)を基本として因果関係を判断しています。ライヒ裁判所や連邦通常裁判所の判例では、傷害致死が認められるのは、致死の結果を除去することなしには傷害行為を消去して考えることができない場合とされています。これは、条件説によれば、当該結果が消滅することなしには消去して考えることのできないいかなる条件も、刑法上重要な結果の原因となるという考え方によるものです。具体的には、RGSt 1, 373; RGSt 44, 137(139)といった判例に見られます。BGHSt 1, 332では、傷害行為が負傷者の死を惹起したか否かの問題は条件説によって判断されなければならないとされています。これらの判例から、ドイツにおいては、条件説に基づいた因果関係の認定が中心となっていることが分かります。ただし、条件説に基づく因果関係の判断は、必ずしも自然科学的な因果連関を直接的に取り上げているわけではなく、形式論理的に実際の事象と仮定的事象を比較することで、実在の作用行為の因果関係を推論するという特徴があります。この点は、日本の判例と比較検討する上で重要な点となります。
2. ドイツ判例に見られる因果関係中断の否定と具体的な事例
ドイツの判例では、故意行為の介在によって因果関係が中断されない場合、過失行為が介在した場合も因果関係が中断されないとされています。例えば、RGSt 61, 318では、許可されていない火災に弱い建物を建築した者が、後に発生した火災で死亡した居住者の死に対して原因責任を負うと判断されています。これは、火災が第三者の放火によるものであっても、建物の構造上の欠陥が死亡に寄与したとされたものです。RGSt 64, 370では、愛人が夫を殺害するために夫に毒物を渡し、夫がその毒物で妻を殺害したケースで、愛人に死を惹起した責任が問われています。これは、毒物の使用目的を知らなくても因果関係が認められた例です。さらに、BGHSt 10, 291(堕胎と乳児殺害)、BGHSt 24, 342(拳銃放置と自殺)といった判例も、故意行為の介在による因果関係の中断を否定する事例として挙げられます。RGSt 34, 91(劇場の拳銃)、BGHSt 4, 360(貨物車の照明欠如と追突事故)といった判例は、第三者の行為や過失行為が介在した場合でも、最初の行為と結果の間に因果関係が認められることを示しています。これらの判例は、ドイツにおける因果関係の認定において、条件説が広く適用されている一方で、結果に繋がる一連の事象全体を包括的に検討する傾向があることを示しています。
