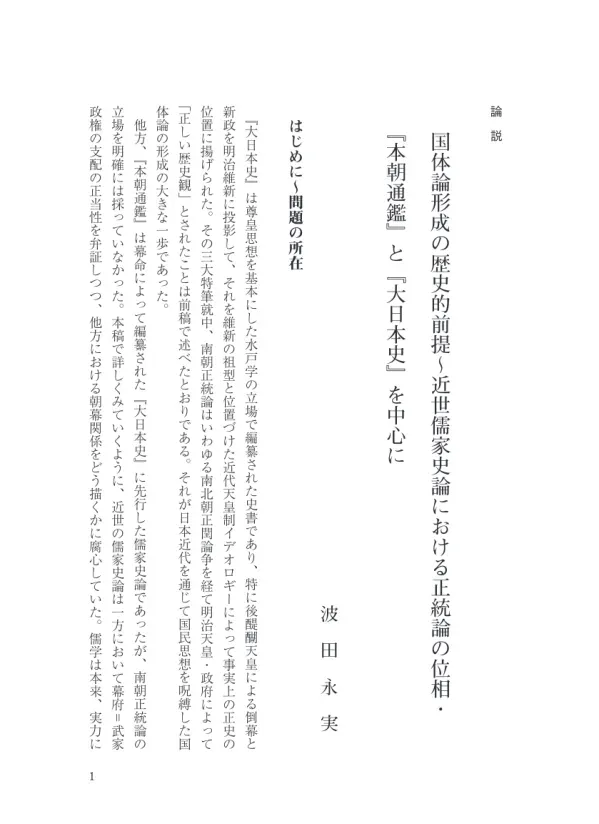
国体論と正統論:近世儒家史学の研究
文書情報
| 著者 | 安川実 |
| 専攻 | 歴史学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.10 MB |
概要
I.林家史学と 本朝通鑑 の南北朝認識
本稿は、林羅山を祖とする林家史学と『本朝通鑑』、そして徳川光圀による『大日本史』を比較検討し、南北朝正閏論におけるそれぞれの歴史認識を明らかにする。特に『本朝通鑑』が『通鑑綱目』的史観から『資治通鑑』的史観への転換を示す林羅山の思想的変遷と、その歴史叙述への影響に焦点を当てる。安川実の『本朝通鑑の研究』を参考に、林羅山と林鵞峰の南北朝認識、特に後醍醐天皇と光厳天皇の扱われ方、そして南朝と北朝の正統性の問題を分析する。呉太白皇祖説の採用や近親婚への批判など、林家史学の特徴を踏まえながら、『大日本史』との比較を通して南北朝期の歴史叙述における相違点を解明する。
1. 林家史学と 本朝通鑑 南北朝正閏論における立場
この節では、林羅山を祖とする林家史学とその代表作である『本朝通鑑』における南北朝正閏論の扱われ方を分析します。戦前の通説では、『本朝通鑑』は『大日本史』と比較して大義名分に乏しい史書と評価されていましたが、安川実の『本朝通鑑の研究』は、この評価を体系的に論じています。林羅山が慶長17年(1612)に著した『倭賦』における記述が、その評価の根拠となっています。『倭賦』は一種の日本文明論であり、日本の国体と皇統の連綿性を強調しつつ、武家の勃興による皇室の衰退を指摘しています。羅山は記紀神話を荒唐無稽とみなし、天孫降臨説を否定して呉太白皇祖説を採用したことも重要な点です。これは、儒学、特に朱子学の普遍主義的な論理に基づいており、皇統の無窮性を天孫降臨の神勅ではなく、太白の至徳に由来すると考えていたことを示しています。呉太白皇祖説は羅山独自の説ではありませんが、徳川光圀が林家史学から離脱する契機の一つとなったことは確かなようです。さらに、羅山は『倭賦』において、古代天皇家の近親婚を厳しく批判し、壬申の乱についても大友天皇の即位を認める記述が見られます。これは朱子学的倫理観に基づいた歴史認識を示唆していますが、南北朝正閏問題において明確な南朝正統論を唱えなかった理由については、明確な理論的必然性を見出すのは困難だとされています。
2. 林羅山の史学転換と 本朝通鑑 の史観
安川実の研究によれば、林羅山は五十歳代後半に『通鑑綱目』的史学から『資治通鑑』的史学へと転換したとされています。初期の羅山は『通鑑綱目』的史学を基盤としていましたが、『資治通鑑』を読破したことで、客観的・学問的な史学に開眼したと推測されています。安川は、この転換を時系列的な一直線的な変化ではなく、両史観が重層的に併存し、その総合の上に独自の儒家史学が形成されたと解釈しています。これは、道学主義的な一面と史的真実の厳密な検討を重視する儒教的現実主義・合理主義の両面を持つ歴史観と言えるでしょう。旧記・実録を用いた批判的・実証的な研究方法も駆使しており、事実と伝説を峻別する姿勢が見られます。結論として、安川は羅山が『資治通鑑』の正閏論に拘泥せず史実を客観的に叙述する歴史主義、資料博捜主義、そして厳密な史実検討を重視する考証的精神の影響を受けて学問的史学へと転換していったと論じています。しかし、林家史学は羅山・鵞峰ともに個人としては南朝に同情的であり『通鑑綱目』的史観を基本としていたものの、幕命を受けて修史にあたるときは北朝正統の立場を取っており、その基盤は『資治通鑑』にならった歴史観にあったと結論づけられています。
II. 大日本史 の編纂と南朝正統論
徳川光圀の『大日本史』編纂事業は、南朝正統論を基軸としながらも、北朝への配慮や政治的現実との葛藤が複雑に絡み合っている。安積憺泊ら前期水戸学の史臣たちは、鎌倉幕府以降の武家政権と朝廷の関係、そして南北朝の正統性問題という難題に直面した。将軍伝の設置や続編問題など、編纂過程における課題と、光圀の南朝正統論と儒教的歴史観のずれを考察する。江館(彰考館)と水館(彰考館)間の書翰などから、『大日本史』の編纂における政治的制約と史学上の困難さを明らかにする。
1. 大日本史 編纂の目的と南朝正統論 光圀の構想
この節では、『大日本史』編纂事業の目的と、その中で重要な位置を占める南朝正統論について、徳川光圀の立場を検討します。光圀自身は、『大日本史』に紀伝体を採用し、皇統を南朝正統として本紀を立てることを意図していたと推測されます。これは、林家による『本朝通鑑』の編纂が『通鑑』を規範として先行していたこと、そして光圀自身の価値観を反映した『綱目』史観的立場に沿ったものであったと考えられます。しかし、実際の編纂作業にあたった史臣たちは、光圀の南朝正統論を徹底的に貫徹すると、歴史叙述に矛盾が生じ、政治的な問題を引き起こす可能性を認識していました。特に、閏統とされた北朝の扱い、叙述の下限、そして必然的に生じる続編の編纂という問題が大きな課題として浮上しました。光圀の死後も、この問題は容易に解決されないまま残された最大の難題であり、前期水戸学の史臣たちは、このアポリアから逃れることができなかったのです。 つまり、南朝正統論という建前を維持しつつ、北朝にも配慮した記述を行い、北朝の御裔である現朝廷への献進を実現する必要があったのです。
2. 大日本史 続編問題と史臣たちの葛藤 正徳五年の書翰
『大日本史』の編纂において、大きな問題となったのが続編問題です。1715年(正徳5年)11月、江戸の彰考館(江館)から水戸の彰考館(水館)へ送られた書翰は、この問題を具体的に示しています。この書翰は、南北朝期の歴史叙述における様々な論点を提示しており、近世前半の儒者史学にとって最大のアポリアであった点を浮き彫りにしています。それは、天皇中心の皇統観を前提としつつ、鎌倉時代以降の全国的統治権を実質的に武家政権が握っていたという歴史的事実を、どのように論理的に整合性のある形で記述するのかという問題です。これは、『本朝通鑑』と『大日本史』の双方にとって共通の課題でした。三宅観瀾が提唱し、安積憺泊が賛同した将軍伝、将軍家族伝、将軍家臣伝という部立ては、この問題への一つの解答でしたが、同時に「南朝正統」論と朝廷への献進という政治的配慮との間で、史臣たちは大きな葛藤を抱えていたことを示しています。近衛家の家士進藤夕翁からの書翰も、南朝正統論を貫徹した『大日本史』が朝廷に献上されるのが困難であることを示しており、この問題が『大日本史』編纂開始以来、光圀の死後も解決されないまま残された最大の課題であったことを物語っています。
3. 大日本史 における正統論と歴史記述の矛盾 後堀河天皇と光厳天皇
『大日本史』における正統論と歴史記述の矛盾は、後堀河天皇と光厳天皇の扱いにおいて顕著に現れています。後堀河天皇は承久の乱後、北条義時によって立てられた天皇であり、「叛臣の立つる所」と評されています。しかし、後醍醐天皇を廃位し光厳天皇を立てた北条高時も同様に「叛臣」と言えるにもかかわらず、叛臣伝ではなく将軍家臣伝に分類されている点に矛盾が見られます。また、『大日本史』は神器の保持を正統の証とみなす一方で、後亀山天皇から後小松天皇への神器譲渡を「天命既に去るを知れば」と説明している点にも、歴史解釈の複雑さが表れています。この矛盾は、光圀自身の南朝正統論と、実際の歴史叙述の間に生じたずれを示唆していると言えるでしょう。光圀は紀伝体を採用し、南朝正統論を建前としていたものの、史臣たちは、その論理を厳密に適用すると歴史記述に矛盾が生じ、政治的な問題を招くことを危惧していたと考えられます。北朝の扱い、叙述の下限、そして続編の問題は、まさにこの葛藤を象徴するものでした。
III. 大日本史 における南北朝期の歴史叙述と解釈
『大日本史』における南北朝期の歴史叙述は、後醍醐天皇と建武中興を巡る評価に特徴がある。後醍醐天皇の新政の挫折原因を、『太平記』などの史料に基づきながら、後醍醐天皇自身の失政や建武中興の失敗に求める記述がなされている。この記述に対する後期水戸学からの批判、特に安積憺泊の建武中興批判における史料解釈の問題点なども検討する。後小松天皇への皇統の継承や、神器の扱われ方を通して、『大日本史』の南北朝認識の独自性を考察する。また、美福門院や後白河天皇の記述を通して、『大日本史』における倫理観や歴史観を分析する。
1. 大日本史 における南北朝期の記述 後醍醐天皇と光厳天皇の扱い
この小節では、『大日本史』が南北朝時代をどのように記述しているのか、特に後醍醐天皇と光厳天皇の扱われ方に注目して分析します。巻一百二十一から、後醍醐天皇と光厳天皇の両名が並記され、光厳天皇の履歴が簡潔にまとめられています。重要な記述として、「無先帝譲位之儀。而北条相模入道高時立之」があり、後醍醐天皇からの譲位がなく、高時が光厳天皇を立てたこと、つまり権力が武家にあったことが明記されています。年号も「後醍醐帝元弘二年 光厳帝正慶元年」と後醍醐天皇を先行させて並記されています。その後、後醍醐天皇が六波羅に囚われ、光厳天皇が即位したことが記され、さらに後醍醐天皇が隠岐に流された記述へと続きます。楠木氏らの反幕府勢力の活動、倒幕後の後醍醐天皇の帰還、そして「逮先帝重祚」という重要な記述がなされています。建武元年以降の記述では、巻一百二十九の一三三六(延元元)年十二月まで後醍醐天皇のみが記述され、「春正月庚寅朔。百官朝賀。公家一統之政。復古制。天皇親萬機。」という新政開始の記述から始まります。しかし、巻一百二十九の十二月には後醍醐天皇が吉野へ逃れて南朝を建国し、光明天皇が後醍醐天皇による官位・人事を取り消したことが記されています。この記述からも両天皇の並立が淡々と記されています。後醍醐天皇の重祚は光厳天皇の即位を認めることになり、さらに光明天皇の即位も認めることになります。巻一百三十以降も、後醍醐天皇と光明天皇が並記され、光明天皇の即位が尊氏によるものであることが明記されています。北朝天皇名と年号が先行し、南朝年号は小さく後に続く記述方法も特徴的です。一三三九(延元四)年八月、後醍醐天皇の死後、後村上天皇が即位しますが、一三四〇(暦応三)年正月からの巻一百三十二からは北朝を正統視する記述へと移行します。
2. 大日本史 における南北朝正閏論と歴史解釈 正統性の基準
『大日本史』は、後醍醐天皇を正統とし、光厳天皇を閏統として扱っています。しかし、「天皇」と「帝」の使い分け基準は不明確です。元弘の乱における後醍醐天皇の行動は「天皇御謀叛」と記述される一方で、持明院統と幕府は両統迭立の原則を守ろうとしていたことが伺えます。光明天皇については、後醍醐天皇から神器を受け、太上天皇の尊号を与えられたと記されています。 後小松天皇本紀の冒頭には、「皇曾祖光厳帝」とあり、現皇統の祖であることが明記され、南北朝時代の記述において北朝正統観が明確に示されています。後醍醐天皇の吉野遷幸後、南朝南帝と呼ばれるようになったと記述された後、「按後醍醐帝延元元年遷幸吉野。自是有南朝南帝之称。然後醍醐無譲位之儀。光明帝為尊氏被立。則終後醍醐之世。乃帝統之正。可在吉野。至後村上則不可無都鄙之辨。況北帝運。傳至今日哉。故至此。以北朝為正。附南朝於其間。」という重要な記述があり、最終的には北朝を正統とし、南朝をその間に位置づけていることがわかります。この記述は、人心の向背が神器の軽重を決定し、人心は明らかに北朝へと向かっていたという光圀の南朝正統論を「中和」する論理を示しています。そして、「天は惟れ一、道器は二ならず。」という一節から、最終的に後小松天皇への皇統の統合を記述し、北朝正統観を明確に示しています。この記述は、南朝が神器を保持していたとはいえ、人心の離反によって正統性が失われたと解釈していると言えるでしょう。
3. 後醍醐天皇と建武中興への批判的評価 史料批判と歴史観
『大日本史』における後醍醐天皇と建武中興への評価は、必ずしも肯定的ではありません。新政の挫折や原因について、『論賛』だけでなく、後醍醐天皇本紀や諸臣伝、后妃伝、将軍伝などにおいて、後醍醐天皇の失政・失徳が指摘されています。この記述は、光圀の薫陶を受けた史臣たちが相次いで亡くなったことなども影響していると考えられています。また、『太平記』の記述についても、盲目的に信じるのではなく、誤謬を看破する必要があるとされています。近代水戸学派は、『論賛』が享保本以前の紀伝の記述を基に執筆されたこと、そして後醍醐天皇や建武中興についての研究が不十分な時期に書かれたことを指摘し、批判的に評価しています。『大日本史』における後白河天皇の記述では、後白河法皇が三十年以上院政を行い五人の天皇を擁立したこと、そしてその結果として武臣が台頭し大権が武家へと移行していった過程が簡潔に記述されています。この記述は、保元の乱や承久の乱など、武家台頭へと至る歴史的過程を客観的に示していると言えるでしょう。また、美福門院の賛では、後白河法皇の兄弟間の後継問題への批判が儒教倫理に基づいてなされています。これらの記述は、『大日本史』における歴史観や倫理観の一端を示唆しており、後醍醐天皇や建武中興への評価と合わせて、同書の歴史叙述の特徴を理解する上で重要な手がかりとなります。
IV.水戸学と国体論への展開
『大日本史』の編纂と水戸学の展開は密接に関連しており、尊皇思想と国体論の形成に大きな影響を与えた。後期水戸学の代表者である会沢正志斎、藤田東湖、豊田天功、青山延光らは、『大日本史』の編纂事業に携わりながら、現実政治にも深く関わった。野口武彦の『江戸の歴史家』などを参考に、前期水戸学から後期水戸学への発展過程と、尊皇思想を中核とした政治イデオロギーとしての後期水戸学の成立を、歴史認識と政治との関わりという視点から考察する。建武中興と維新イデオロギーの関係性も触れる。
1. 水戸学と 大日本史 前期水戸学の史観と課題
この小節では、『大日本史』編纂の中核を担った水戸学、特に前期水戸学の史観と、編纂過程で直面した課題について論じます。通説によれば、『大日本史』は『本朝通鑑』と同様に『資治通鑑』の書法に則って書かれており、『通鑑綱目』とは異なるという見解があります。この説の根拠として、藤田幽谷の『修史始末』に引用された安積憺泊の記述が挙げられており、憺泊が前期水戸学の中心人物であったこと、そして彼の他の著作からも『資治通鑑』の書法を踏襲していたことが明らかであるとされています。しかし、徳川光圀が目指した南朝正統論と、鎌倉時代以降の武家政権による支配という歴史的事実を、どのように論理的に整合性を持たせて記述するかが、大きな課題でした。これは、後堀河天皇以降の皇位継承における問題、特に承久の乱以降の北条氏による天皇の廃立、そして南北朝時代の正統論争と深く関わるものでした。光圀自身は、紀伝体を採用し、南朝正統論を貫く一方で、武家政権の正当性も考慮する必要がありました。史臣たちは、光圀の南朝正統論を徹底的に貫徹すると、歴史記述に矛盾や政治的な問題が生じることを認識しており、北朝の扱い、叙述の下限、そして「続編」の編纂という問題に苦慮したと推測されます。将軍伝、将軍家族伝、将軍家臣伝という部立ての提案は三宅観瀾によるものでしたが、安積憺泊も賛同しており、武家政権の正当性を形式的に担保しようとする試みが見られます。しかし、幕府と朝廷への献上という政治的配慮と、「南朝正統」論という建前との間で、史臣たちは大きなジレンマを抱えていました。
2. 水戸学における正統論と歴史記述 矛盾とアポリア
この小節では、『大日本史』における正統論と、実際の歴史記述における矛盾、そしてその背後にあるアポリアについて考察します。後堀河天皇は承久の乱後、北条義時によって立てられた天皇であり、「叛臣の立つる所」と評されていますが、同様に光厳天皇を立てた北条高時も叛臣伝には含まれていません。この点に、『大日本史』の論理的矛盾が見られます。神器保持を正統の証とするならば、後堀河天皇の正当性も問われなければならず、論理的一貫性に欠ける部分が存在するのです。さらに、後亀山天皇から後小松天皇への神器譲渡についても、「天命既に去るを知れば」という説明がなされていますが、この歴史解釈は、光圀の南朝正統論を完全に反映しているとは言えません。前期水戸学の史臣たちは、南朝正統論という建前を維持しつつ、北朝にも配慮した記述を行い、現朝廷への献進を実現するという困難な課題に直面していました。武家政権の正当性は将軍伝の設置によって形式的には担保されましたが、「南朝正統」論は『大日本史』全体の根幹であり、その建前を維持しつつ北朝への配慮を欠かすことのできない状況に、史臣たちは苦慮していたのです。このことは、正徳5年の江館(江戸の彰考館)と水館(水戸の彰考館)間の書翰からも明らかです。書翰は、南朝正統論を堅持することの困難さを示唆しており、この問題が『大日本史』編纂における最大の難題であったことを示しています。
3. 後期水戸学と国体論 尊皇思想と現実政治
この小節では、前期水戸学から後期水戸学への発展過程、そして尊皇思想と国体論の形成について論じます。後期水戸学は、単なる歴史思想ではなく、尊皇思想を中軸に据えた政治イデオロギーの体系であったと野口武彦は指摘しています。会沢正志斎、藤田東湖、豊田天功、青山延光といった後期水戸学の代表的なイデオローグたちは、史館勤務と藩政担当者を兼任し、現実政治にも深く関与していました。彼らの尊皇論は、前期水戸学の歴史的個体性の模索という基盤の上に成り立っており、広義の国学からの思想的影響も受けていました。後期水戸学の成立過程においては、歴史についての原理的思考が、アクチュアルな歴史意識を引き出してゆく過程を見ることができます。つまり、歴史を思考することが、同時に同時代の現実に関与することに繋がっていたのです。後醍醐天皇の新政が王政復古として未完に終わったこと、そして維新の志士たちが楠木正成ら南朝の「忠臣」になぞらえられたことは、維新のイデオロギーが国体論へと転化していく第一歩となりました。このように、『大日本史』の編纂と水戸学の展開は密接に関連しており、尊皇思想と国体論の形成に大きな影響を与えたと言えるでしょう。
