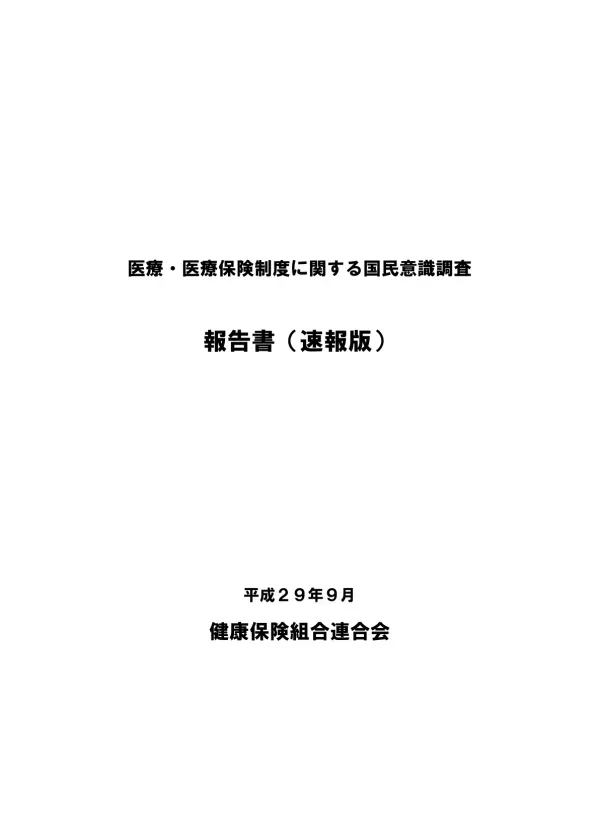
国民意識調査:医療保険制度への意識
文書情報
| 専攻 | 公衆衛生学、医療経済学、社会医学など |
| 会社 | 楽天リサーチ株式会社 |
| 文書タイプ | 調査報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.12 MB |
概要
I.医療保険制度への満足度と課題
本調査「医療・医療保険制度に関する国民意識調査」では、2000人の全国モニターを対象に、日本の国民健康保険制度に対する意識を調査しました。保険者別満足度では、共済組合が最も高く57.6%、国民健康保険は36.3%でした。ジェネリック医薬品の利用状況や、かかりつけ医の有無、医療機関の選び方なども調査項目に含まれ、国民の医療費負担の重さに関する認識も分析されました。特に、保険料の高騰に対する不満が顕著で、その抑制策として後発医薬品の普及や残薬の解消などが挙げられました。医療費の高騰や介護費の高騰に対する負担感についても調査が行われ、その財源確保について国民の意見が分析されました。消費税や所得税の増税への意見なども含まれています。
1. 医療保険制度への満足度
本調査では、国民健康保険制度への満足度を、加入している保険者別に調査しました。調査対象は、楽天リサーチ株式会社が保有する全国モニター2000名です。その結果、「かなり満足している」「やや満足している」と回答した割合は、共済組合が57.6%と最も高く、次いで組合管掌健康保険が48.0%、後期高齢者医療広域連合が47.0%、全国健康保険協会が37.2%、国民健康保険が36.3%という結果でした。この結果は、国民の医療保険制度に対する満足度に、保険者間で差があることを示しています。特に、共済組合加入者における高い満足度は注目に値し、その要因分析が今後の課題となります。また、国民健康保険加入者の満足度が比較的低いことも重要なポイントであり、その改善策を検討する必要があります。この調査結果は、今後の医療保険制度の改革や改善の方向性を示唆する重要なデータとなっています。
2. ジェネリック医薬品に関する意識
ジェネリック医薬品(後発医薬品)に関する意識についても調査が行われました。ジェネリック医薬品への切り替えを医師や薬剤師に要請したことがあると回答した人は15.8%でした。一方、ジェネリック医薬品の軽減額通知を受け取っているにもかかわらず、先発医薬品からジェネリック医薬品に変更するよう医師や薬剤師に要請したことがない人は、7.8%にとどまりました。この数値から、ジェネリック医薬品の普及率はまだまだ低いものの、一定数の国民がジェネリック医薬品の利用を検討していることが分かります。しかし、多くの国民がジェネリック医薬品について十分な知識や理解を持っていない可能性も示唆されます。そのため、ジェネリック医薬品の有効性や安全性の情報提供を強化し、国民の理解促進を図ることが重要となります。今後の啓発活動や情報提供方法の改善が、ジェネリック医薬品の更なる普及を促進する鍵となるでしょう。
3. 医療費負担に関する認識
国民の医療費負担に関する認識は、本調査の重要な分析項目です。日本の医療費総額や一人当たりの医療費負担について、「非常に高い」「やや高い」と回答した割合は約70%に上り、国民の医療費に対する負担感が強いことが示されています。年齢別に見ると、60代・70代で「非常に高い」と感じる割合が高く、医療費負担の重さを特に強く感じている層であることがわかります。また、医療費負担の重さを感じる点について、「保険料」が60.1%と最も多く、次いで「医療費そのもの」が53.6%、「自己負担費用」が43.4%という結果でした。これは、国民が医療費の高騰を実感しており、保険料の高さがその負担感を増幅させていることを示しています。この結果から、医療費抑制策の検討が喫緊の課題であり、国民の負担軽減のための具体的な施策が必要であることが改めて示されました。保険料の抑制や医療費の適正化、自己負担の軽減などが、今後の重要な政策課題となるでしょう。
4. 医療費負担の財源に関する意見
増加する医療費の財源確保について、国民の意見を調査しました。医療費抑制策としては、「後発医薬品の普及」46.6%、「残薬の解消」34.5%、「病気の予防」29.1%が支持されており、国民は医療費の抑制に積極的な姿勢を示しています。一方、保険給付範囲の縮小や自己負担増といった負担増加につながる選択肢は支持が低く、国民は医療へのアクセスを維持したいという強い意思を持っていることがわかります。高齢者の医療費財源については、「税金による負担を増やす」23.8%、「高齢者自身の保険料負担を増やす」21.1%、「現役世代の保険料からの支援金を増やす」7.2%という結果でした。この結果から、高齢化社会における医療費財源の確保は、国民の間で多様な意見が存在することを示しています。税制改革や保険制度改革など、多角的な視点からの検討が必要となるでしょう。特に、現役世代と高齢世代の世代間公平性の問題をどのように解決するかが、今後の政策課題として重要になります。
II.医療機関の利用状況と選定基準
外来医療の受診率は71.1%で、複数医療機関の利用経験者は32.2%に上ります。複数受診の理由は、医師への不満や専門性の高い検査を求めるためです。かかりつけ医を持つ割合は高く、その理由として通院の利便性や医師への信頼感が挙げられています。医療機関の選定基準としては、インターネットの情報や口コミが重要な役割を果たしていることが分かりました。特に、医療機関の情報サイトや医療機関のホームページの利用率が高いことが示されました。
1. 医療機関の利用状況 複数医療機関受診の実態
本調査では、過去1年間に外来医療を受診した経験のある人の割合が71.1%であることが分かりました。注目すべき点は、同じ傷病で同時期に複数の医療機関にかかった経験のある人が32.2%もいたことです。これは、平成23年度調査の24.4%と比較して増加しており、医療機関の選択に関する国民の意識の変化を示唆しています。複数医療機関受診の理由としては、「先に受診していた医療機関・医師からの紹介で、他院で専門的な検査等を受けた」が47.5%、「先に受診していた医療機関・医師の診察内容等に不満があり、自分の判断で他院を受診した」が41.6%と、紹介と不満が主な理由となっています。特に30代以下では、医師の診察内容に不満を感じて他院を受診した割合が高く、若い世代では医療機関への満足度が低い可能性を示唆しています。この結果は、医療機関のサービス向上や患者満足度向上のための施策を考える上で重要な示唆を与えています。
2. かかりつけ医の現状と選定理由
一方、日頃から決まって診察を受ける医師・医療機関がないと回答した人は32.7%にのぼりました。その理由としては、「その都度適当な医療機関を選ぶ方が良い」や「適当な医療機関をどう探してよいのかわからない」といった意見が多く挙げられています。これは、医療機関選びに困難を感じている人が一定数存在することを示しています。 一方、「いつも相談し、診察を受ける医師がいる」と回答した人は、その理由として「自宅から近く通院が便利である」を71.2%が挙げ、利便性が最も重視されていることが分かりました。 その他、「医師が信頼できる」「医師の人柄が良い」「病気や治療についてよく説明してくれる」なども重要な理由として挙げられており、医療機関の選択においては、医師との信頼関係やコミュニケーションの質も重要視されていることがわかります。全回答者への期待についても同様の傾向が見られ、医療機関選びにおける利便性と信頼性の重要性が改めて確認されました。これらの結果は、医療機関の立地や医師とのコミュニケーションの質の向上、医療情報提供の改善が重要であることを示しています。
3. 医療機関の情報収集方法
医療機関を選ぶ際に参考にするものとしては、「インターネットの情報を調べる」(45.3%)、「家族、友人、知人からの意見を聞く」(42.9%)、「病気になるといつも相談し、診察を受ける医師に相談する」(36.4%)が多く挙げられました。インターネットの情報源としては、「医療機関に関する情報サイト」「医療機関のホームページ」「医療機関専門でない検索サイト」がそれぞれ50%強の割合を占めており、インターネットが医療機関選びにおいて重要な情報源となっていることがわかります。特に、医療機関に関する専門サイトやホームページの情報が信頼されている傾向が見られます。医療機関の情報として特に欲しいと思う情報としては、「診療科目」「医師の専門分野」といった診療分野や専門性に関する情報に加え、「必要な費用の概ねの金額」も36.5%と高い割合を占めており、費用に関する情報へのニーズも高いことがわかります。これらの結果は、医療機関がインターネット上での情報発信を強化し、正確で分かりやすい情報を提供していくことが重要であることを示唆しています。
III.薬局の利用状況と薬剤師への期待
薬局の利用状況では、受診した医療機関近くの薬局を利用する人が61.0%と大多数を占めています。かかりつけ薬剤師制度の認知度は低く、薬局の利用においても利便性が重視されていることが示唆されました。薬剤師への期待としては、処方された薬の詳しい説明や、自宅からの近さなどが挙げられています。お薬手帳の利用状況も調査され、高齢者ほど利用率が高い一方で、若年層では持ち忘れが多いことが分かりました。
1. 薬局の利用状況と利便性
病院や診療所受診後の薬の受け取りについて、調査が行われました。最も多かったのは、「受診した医療機関の近くにある薬局で薬を受け取っている」という回答で、61.0%を占めました。一方、「いつも決まった薬局で薬を受け取っている」と回答した人は13.4%にとどまりました。この結果は、薬局の利用においては、利便性が強く意識されていることを示しています。いつも決まった薬局を利用する人の理由は、「自宅が近いから」(56.7%)、「以前からよく利用している薬局だから」(43.7%)が主なものでした。これは、薬局選びにおいても、医療機関と同様に地理的な近さが重要な要素となっていることを示しています。さらに、「かかりつけ薬剤師」制度を知らないと回答した人が62.3%にのぼったことから、薬局における継続的な利用関係の構築や、かかりつけ薬剤師制度の認知度向上のための取り組みが課題として挙げられます。薬局の利便性向上と、かかりつけ薬剤師制度の普及啓発が、国民の薬剤利用の質向上に繋がるでしょう。
2. お薬手帳の利用状況と年齢層の違い
お薬手帳の利用状況について、48.2%が「お薬手帳を持っており、薬を受け取る際には必ず提示するようにしている」と回答しました。年齢が高いほどその割合は大きくなっており、高齢者層ではお薬手帳の利用が定着しつつある一方、若年層では「お薬手帳を持っているが、持ち出し忘れなどのために提示せずに薬を受け取ることが多い」という回答が相対的に多く見られました。この結果は、年齢層によって健康管理への意識や行動に差があることを示しています。高齢者層では、服薬管理の重要性を理解し、お薬手帳を積極的に活用している一方で、若年層では、お薬手帳の利用が必ずしも習慣化されていない状況がうかがえます。お薬手帳の利便性を高める工夫や、若年層への啓発活動が、より多くの国民によるお薬手帳の活用を促す上で重要となるでしょう。
3. 薬局 薬剤師への期待事項
薬局・薬剤師への期待事項については、「受診している病院・診療所から近く、処方された薬をすぐ受け取れる場所にあること」(51.0%)、「自宅や勤務地に近いなど、立ち寄りやすい場所にあること」(49.0%)、「服用方法や副作用、注意事項など、薬について説明してくれること」(41.8%)が多く挙げられました。これらの結果から、薬局の利便性と薬剤師による丁寧な説明が、国民にとって重要な要素であることがわかります。薬剤師への期待としては、薬の服用方法や副作用に関する説明だけでなく、ジェネリック医薬品に関する説明や、処方された薬以外の医薬品や介護用品に関する相談にも対応できることを期待する声も少なくありません。 この調査結果を踏まえ、薬局・薬剤師は、アクセスしやすさや説明の分かりやすさといった利便性に加え、専門的な知識に基づいた的確な情報提供と、患者一人ひとりのニーズに応じたきめ細やかな対応を心がけることが重要となるでしょう。特に、ジェネリック医薬品に関する正しい情報提供は、国民の理解促進に大きく貢献すると考えられます。
IV.高齢化社会における医療 介護費の負担
医療費負担に関する意識では、「非常に高い」「やや高い」と感じる人が約70%に達しました。負担の重さを感じる点としては、保険料が最も多く、医療費そのものや自己負担費用が続きます。高齢者の医療費増加への対策として、後発医薬品の普及、残薬の解消、病気の予防などが支持されています。介護保険サービスの自己負担については、比較的低いと感じる人が多いものの、利用者負担の増加を望む声も少なくありませんでした。介護サービスの充実を求める声も強く、特に特別養護老人ホーム等の施設へのニーズが高いことが分かりました。
1. 医療費の高騰に対する国民の認識
日本の医療費総額と国民一人当たりの医療費負担について、国民の認識を調査した結果、「非常に高いと感じる」「やや高いと感じる」と回答した割合が約70%に上りました。年齢別に見ると、60代、70代で「非常に高いと感じる」割合が高く、医療費負担の重さを特に強く感じている層であることが分かります。医療費負担の重さを感じる点としては、「保険料」が60.1%と最も多く、次いで「医療費そのもの」が53.6%、「自己負担費用」が43.4%という結果になりました。この結果は、国民が医療費の高騰を実感しており、その負担感の大きさを示しています。特に保険料の高さが負担感を増幅させていることが示唆され、保険料の抑制や医療費の適正化が重要な課題となっています。また、医療費負担の重さを「重いと感じる」「やや重いと感じる」と回答した割合は40代、50代で比較的高いことから、働き盛り世代における経済的な負担も無視できないことがわかります。
2. 医療費抑制のための国民的意見
増加する医療費の抑制策として、国民はどのような方法を支持しているのかを調査しました。その結果、「後発医薬品の普及」(46.6%)、「残薬の解消」(34.5%)、「病気の予防」(29.1%)といった回答が多く、医療費抑制に積極的な姿勢を示していることが分かります。一方、保険給付範囲の縮小や自己負担増につながる選択肢への支持は低く、国民は医療へのアクセスを維持したいという強い意思を持っていることが示唆されます。これは、医療費抑制において、国民の負担を増加させる方法よりも、効率的な医療提供や予防医療の推進を優先すべきであるという国民の意見を反映していると言えるでしょう。医療技術の進歩と保険適用の在り方については、「医療費の額に関係なく保険を適用し、進歩した医療技術を受けられる機会を確保してほしい」という意見が多く見られました。国民は、医療技術の進歩による恩恵を享受したいという強い願望を持っている一方で、その費用負担については慎重な姿勢を示していることがわかります。
3. 高齢者の医療費負担に関する意見
高齢者の医療費増加への対応として、国民はどのような負担方法を支持しているのかを調査しました。その結果、「高齢者の医療費の財源として税金による負担を増やす」が23.8%、「高齢者自身の保険料負担を増やす」が21.1%、「現役世代が支払う保険料からの支援金を増やす」は7.2%にとどまりました。年齢階級別に見ると、「税金による負担を増やす」という意見は年齢が高くなるほど多くなり、「患者の自己負担割合を引き上げる」という意見は年齢が低いほど多くなる傾向が見られました。これは、高齢世代は税金による負担増加を比較的受け入れやすい一方で、若年世代は自身の負担増加には抵抗があることを示唆しています。高齢化社会における医療費財源の確保は、世代間における公平性の問題と深く関わっており、国民全体の合意形成が不可欠であることがわかります。この課題に対しては、世代間負担のバランスや、医療費抑制策の効果的な組み合わせなどを検討していく必要があります。
4. 介護費負担に関する意識と意見
増加する介護費の負担方法についても調査が行われました。その結果、「利用者負担を増やす」が30.3%、「税金を引き上げても国・地方自治体の負担金を増やす」が24.6%、「保険料を引き上げる」は10.2%と少数にとどまりました。「税金による負担を増やす」と回答した人のうち、財源として所得税を挙げた人は55.3%、消費税を挙げた人は42.9%でした。平成23年度調査と比較すると、消費税が所得税を上回っていたのが逆転しており、消費税率の引き上げの影響が考えられます。年齢階級別に見ると、「税金による負担を増やす」は高齢者に多く、「利用者の支払いを増やす方がよい」はほぼすべての年代で最も多かったことから、介護費負担の増加については、利用者負担の増加が最も現実的な方法として認識されている一方で、税金による財源確保への期待も一定数存在することが示唆されます。介護保険制度の持続可能性を確保するためには、利用者負担、税金負担、保険料負担のバランスをどのように取るかが重要な課題となります。
V.終末期医療への意識と希望
終末期医療に関する希望としては、疼痛緩和中心の症状コントロールや精神的援助などを希望する人が60%近くに上ります。終末期医療を受けたい場所としては、「自宅」や「ホスピス等の緩和ケア施設」が挙げられています。また、終末期医療に関する意思確認書の作成意向も調査されました。
1. 終末期医療における希望 症状コントロールと延命治療
痛みが伴い治る見込みがなく死期が迫っているケースを想定し、終末期医療に対する希望について調査しました。回答者自身と回答者の家族の両方について、約60%が「疼痛緩和中心の症状コントロール、精神的援助、家族への援助など」を希望しており、一方「病気の治療を目的とした検査・手術・延命処置など」を希望する割合は約10%にとどまりました。この結果は、終末期医療においては、患者の苦痛の軽減と精神的なケアを重視する傾向が強いことを示しています。延命治療よりも、残りの人生を少しでも穏やかに過ごすためのサポートを望む人が多いという結果から、質の高い緩和ケアの提供が重要であることが示唆されます。また、この傾向は回答者自身と家族の両方で共通しており、終末期医療における共通の価値観が存在していることがわかります。今後の終末期医療の在り方について、この調査結果を踏まえた検討が求められます。
2. 終末期医療に関する意思確認書の作成意向
自身の終末期医療に対する希望に関する意思確認書について、すでに作成している人は2.3%、作成したいと回答した人は50.7%でした。これは、終末期医療における意思表示の重要性への関心の高さを示しています。多くの国民が、自分自身の終末期医療に関する意思を明確にしたいと考えている一方、実際に意思確認書を作成している人の割合は低いという現状が明らかになりました。このギャップを埋めるためには、意思確認書の作成を促進するための啓発活動や、作成を支援する仕組みの構築が重要になります。意思確認書の作成は、本人だけでなく家族にとっても、終末期の意思決定をスムーズに進める上で非常に役立つものと期待できます。作成を促進するための取り組みは、本人や家族の安心感の向上に繋がるでしょう。
3. 終末期医療を受けたい場所 自宅と緩和ケア施設
終末期医療を受けたい場所として、「自宅」(29.2%)、「ホスピス等の緩和ケア施設」(27.8%)を希望する人が多く、自宅での看取りと専門的な緩和ケア施設の利用が、国民にとって重要な選択肢となっていることがわかります。自宅での看取りを希望する人の割合が高いことは、慣れ親しんだ環境での最期を迎えたいという国民の強い願望を反映していると言えるでしょう。一方、ホスピス等の緩和ケア施設を希望する人の割合も高いことから、専門的な医療やケアが必要な場合においては、適切な施設へのアクセスが求められていることが示唆されます。これらの結果から、在宅医療とホスピス等の緩和ケア施設の両面を充実させることが、国民の終末期医療ニーズに応える上で不可欠であることがわかります。今後の医療政策においては、在宅医療体制の整備や緩和ケアの充実、そしてそれらへのアクセスを容易にするための仕組みづくりが重要になります。
