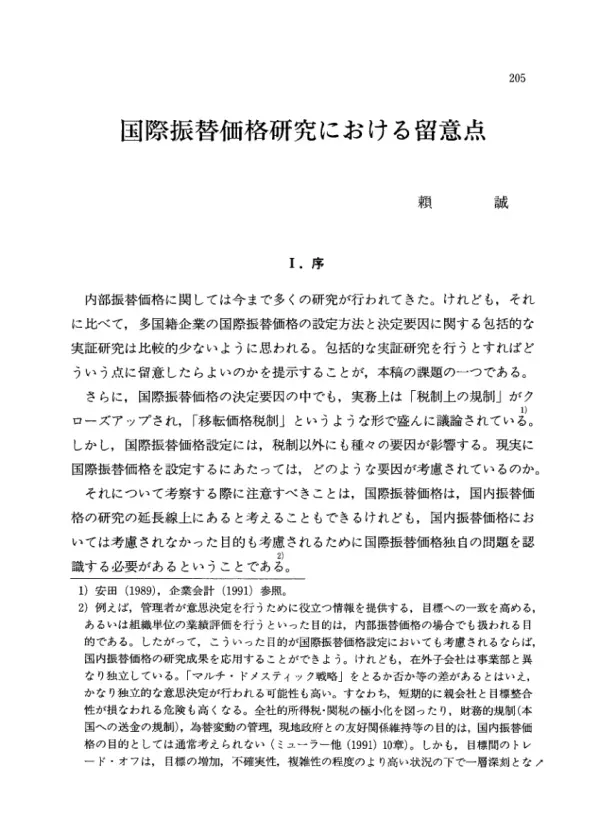
国際振替価格研究:留意点と課題
文書情報
| 学校 | 不明 |
| 専攻 | 会計学、経済学、経営学のいずれか |
| 出版年 | 不明 |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.50 MB |
概要
I.国際振替価格設定における主要要因と目的の分析
本論文は、国際振替価格(kokusai furitsuke kakaku)設定における主要要因と目的を、既存研究のレビューを通して分析する。特に、多国籍企業(takokuseki kigyou)の税制(zeisei)戦略、特に節税(setsuze)目的と、アームズレングス価格(arms length kakaku)遵守との間のトレードオフに焦点を当てている。分析対象となる研究には、Arpan (1972), Kim and Miller (1979), Salem (1988), Yunkerらの研究が含まれ、内国歳入法第482条(Naikoku saisunyouhou dai 482 jou) の影響についても考察されている。これらの研究は、利益の送金制限、為替管理、関税、所得税、ジョイントベンチャー規制などが国際振替価格設定に影響する主要要因として挙げている一方、研究手法や対象企業の違いにより、要因間の重要度や相関関係に差異が見られることが指摘されている。
1. 国際振替価格設定に影響を与える要因の多様性と研究結果の差異
このセクションでは、国際振替価格設定に影響を与える要因を複数の研究結果に基づいて分析する。まず、内部振替価格における目的(意思決定支援、目標への整合性向上、組織単位の業績評価など)が国際振替価格設定においても考慮される点を指摘する。しかし、各研究で用いられる調査対象、調査方法、問題意識、アプローチが異なるため、研究間の比較可能性は低い。例えば、5点スケールを用いた主観的調査結果の信頼性にも限界がある。それでも、多くの断片的な結果を統合することで、新たな仮説の発見や一般化の可能性を探る。 Kim and Miller (1979) の研究では、受入国での利益送金、為替管理、ジョイントベンチャー規制、関税、受入国・米国での所得税負担、米国での割当規制などが国際振替価格設定要因として挙げられ、その重要度が各国ごとに比較されている。特に利益送金制限と為替管理が上位を占め、これらが外国資本の流出抑制手段として機能している点が注目される。しかし、内国歳入法第482条によるアームズレングス価格の義務化により、価格操作には制約がある。製品の品質、売上高、市場の変動、管理・技術サービス・財産権に関する価格設定・費用配分の複雑さも考慮すべきである。K&Mは、国際振替価格政策は企業の全体的な財務戦略と整合性を保つべきだと主張し、在外子会社への資金残高や税金支払い延期といった戦略と、全体的な財務目的との両立可能性を重視している。アームズレングス価格の選択基準が明確でない点も課題として挙げられる。また、米国親会社は受入国の資本流出制限に対抗するため、振替価格を高めに設定する可能性があるが、在外子会社や受入国との関係悪化リスクも存在する。
2. 既存研究 Arpan K M Salem の分析とそれぞれの限界
このセクションでは、Arpan (1972)、Kim and Miller (1979)(K&M)、Salem (1988) らの研究をレビューし、それぞれの研究方法と結果、そして限界を分析する。Arpanの研究は、米国に100%子会社を持つ欧州の多国籍企業を対象としたものであり、K&Mは1973年以降の国際環境変化を考慮し、発展途上国への投資を行う米国企業の長期的な財務的意思決定政策の一部として国際振替価格政策を捉えている。これにより、Arpanとは異なる結論に至っている。K&Mは、多様な要因(利益送金、為替管理、ジョイントベンチャー規制など)を考慮し、それらの重要度の順位付けを行っているが、米国税制の影響を大きく受けている。Salemの研究は、米国親会社とエジプト子会社間の国際振替価格に焦点を当て、エジプト政府の投資促進政策や規制の緩さが振替価格設定に影響を与えている点を分析している。Salemは、親会社と子会社の関係の密接度、事業形態(ジョイントベンチャー、支店、完全子会社など)、市場シェアなども考慮した分類を行っている点が特徴的である。しかし、これらの研究は、多国籍企業の定義の曖昧性、米国企業への偏り、主観的調査への依存など、比較可能性や信頼性の問題を抱えている。そのため、これらの研究結果を踏まえつつ、より詳細で信頼性の高い分析を行うためには、新たな研究枠組みが必要となる。
3. 国際振替価格設定における目的間のトレードオフと政策的側面
このセクションでは、国際振替価格設定における複数の目的間のトレードオフ関係について考察する。企業は、様々な要因の中で操作可能な要素を選び、自社にとって重要な目的を設定するが、これらの目的にはトレードオフが存在する。例えば、節税と業績評価はトレードオフの関係にある。様々な統計的手法を用いた分析が行われているが、その信頼性や妥当性には疑問点がある。 Yunkerの研究では、子会社の自律性政策、業績評価政策、振替価格決定政策といった政策変数と、外生要因(市場規模、政府規制など)の関係、そして政策変数間の関係が分析されている。振替価格の一般的目的(全社利益増大、適用簡素化、管理者業績評価容易化など)と、用具的目的(売上税削減など)についても調査されており、特定の目的達成のための価格操作は限定的であることが示唆されている。また、規模や外国との関係の密接度といった要因が、市場価格の利用や用具的振替価格設定に影響を与えることが分析されている。これらの研究は、統計的技法やデータ解釈における問題点を含むものの、国際振替価格設定メカニズム解明への第一歩として評価できる。
II.既存研究のレビューと限界
既存研究のレビューでは、国際振替価格設定に関する様々な要因(企業規模、海外進出段階、信用状態、政府規制など)と目的(節税、業績評価、マネジメントコントロールなど)が検討されている。しかしながら、研究間の比較可能性の低さ、有効回答数の少なさ、主観的調査結果への依存など、多くの限界が指摘されている。特に、米国企業を対象とした研究が多いことから、日本企業への適用可能性については更なる検証が必要である。Salem (1988) の研究は、エジプトにおける国際振替価格設定を分析した点で特筆すべきであり、特定国の環境が振替価格設定に及ぼす影響を検討している。一方、Yunkerの研究は、政策変数と外生要因の関係を分析し、振替価格変数間の相互関係、特に市場志向的振替価格と非市場志向的振替価格間のトレードオフを明らかにしている。
1. 既存研究の概要と共通の限界
このセクションでは、国際振替価格設定に関する複数の既存研究をレビューする。これらの研究は、多国籍企業における国際振替価格の決定要因や目的を明らかにしようと試みている。具体的には、Arpan(1972)、Kim and Miller(1979:K&M)、Salem(1988)といった研究が取り上げられ、それぞれの研究で用いられた手法や得られた結果、そしてその限界が分析されている。Arpanの研究は欧州企業、K&Mの研究は米国企業、Salemの研究はエジプトにおける事例を対象としているなど、研究対象やアプローチに違いが見られる。K&Mの研究では、利益送金、為替管理、ジョイントベンチャー規制、関税、所得税負担といった要因が挙げられており、その重要度が各国間で比較されている。しかしながら、これらの研究は共通して、多国籍企業の定義の曖昧性、調査対象企業の偏り(特に米国企業に偏っている)、主観的な調査データへの依存といった限界を抱えている。そのため、研究間での比較可能性が低く、結果の一般化可能性や信頼性にも疑問が残る。有効回答数の少なさも、結果の信頼性を低下させる要因の一つとして指摘されている。これらの研究は、国際振替価格に関する知見を提供するものの、その限界を踏まえた上で、より精緻な分析を行う必要があることを示している。
2. 個別研究の深堀り Arpan K M Salemの分析
このセクションでは、Arpan、K&M、Salemの3つの研究を個別に詳細に分析する。Arpan(1972)の研究は、米国に100%子会社を持つ欧州多国籍企業を対象に、国際振替価格設定の実態を調査している。一方、K&M(1979)は、1973年以降の国際環境の変化を踏まえ、発展途上国への投資を行う米国企業の長期的な財務戦略の一部として国際振替価格政策を位置づけている。彼らの研究では、利益送金制限や為替管理が特に重要視され、外国資本流出の抑制手段としての機能が強調されている。しかし、内国歳入法第482条によるアームズレングス価格の遵守義務も考慮する必要がある。Salem(1988)の研究は、米国親会社とエジプト子会社間の国際振替価格に焦点を当てている。エジプト政府の投資促進政策や規制の緩さが、振替価格設定に影響を与えている点が分析されている。Salemは、親会社と子会社間の関係の密接度、事業形態、市場シェアなどを考慮した分類を行っており、多国籍企業を一律に扱うのではなく、多様な側面を捉えようとしている点が評価できる。しかし、これらの研究はいずれも、調査対象の限定性、データの信頼性、研究方法の限界といった課題を抱えているため、その結果の解釈には注意が必要である。
3. 研究の限界克服に向けた展望 より精緻な実証研究の必要性
上記でレビューした既存研究の限界を克服するために、本稿ではより精緻な実証研究の必要性を強調する。既存研究の主な限界は、多国籍企業の定義の曖昧性による比較可能性の低さ、米国企業への調査対象の偏り、主観的な調査方法への依存、そして有効回答数の少なさである。これらの限界により、研究結果の一般化可能性や信頼性が低いという問題点があった。 そこで、今後の研究においては、企業特性(業種、海外進出段階など)による分類、企業を取り巻く環境要因間の関係の明確化、そして振替価格設定基準だけでなく、設定主体、修正頻度など多角的な視点からの調査が必要となる。 また、質問票調査だけでなく、インタビュー調査などを併用し、仮説の修正や検証を行うことで、より質の高いデータの収集を目指すべきである。 特に、日本企業を対象とした研究が不足しているため、日本企業独自の状況を考慮した分析を行うことが重要である。これにより、国際振替価格設定に関するより深く、信頼性の高い知見が得られると期待できる。
III.今後の研究課題と分析フレームワーク
今後の研究課題としては、より多くの日本企業を対象とした実証研究、企業特性や環境要因を考慮した分類、振替価格設定主体や修正頻度に関する調査などが挙げられる。特に、日本企業特有の状況を考慮した新たな分析フレームワークの構築が重要である。これは、既存研究で得られた知見を基に、国際振替価格設定のメカニズムをより深く理解し、日本企業における最適な振替価格戦略を策定するための重要なステップとなる。また、移転価格税制の改正動向や、受入国の経済状況なども考慮する必要がある。
1. 既存研究の限界と今後の研究方向
本セクションでは、国際振替価格に関する既存研究の限界を明らかにし、今後の研究の方向性を示す。これまでの研究では、Arpan(1972), Kim & Miller(1979), Salem(1988) といった研究が挙げられるが、これらの研究は、多国籍企業の定義の曖昧性、調査対象の偏り(特に米国企業に偏っている傾向)、主観的な調査方法への依存、有効回答数の少なさといった共通の限界を抱えている。これらの限界から、研究間の比較可能性が低く、結果の一般化可能性や信頼性に課題がある。例えば、5点スケールを用いた主観的調査は、信頼性の点で限界を持つ。しかし、これらの研究は国際振替価格に関する貴重な知見を提供しており、その限界を踏まえた上で、より精密な分析が必要となる。今後の研究では、これらの限界を克服するために、企業特性(業種、海外進出段階など)による分類、企業を取り巻く環境要因間の関係の明確化、振替価格設定基準、設定主体、修正頻度など多角的な視点からの調査が必要となる。さらに、質問票調査だけでなく、インタビュー調査などを併用することで、より質の高いデータ収集が期待できる。
2. 分析フレームワーク構築の必要性と具体的な提案
国際振替価格設定メカニズムの解明のためには、新たな分析フレームワークの構築が不可欠である。既存研究では、Burnsの研究のように企業をグループ分けして外部要因の影響を受けやすさを比較したり、Yunkerの研究のように政策変数と外生要因の関係を分析する試みが見られる。これらの研究は評価できるものの、より包括的な理解のためには、より体系的なフレームワークが必要である。具体的には、企業の特性(業種、海外進出の段階など)を考慮した分類、企業を取り巻く環境要因(政府規制、税制、経済状況など)の相互関係の明確化、そして振替価格政策に関する詳細な調査(設定基準、設定主体、修正頻度など)が重要となる。 特に、日本企業を対象とした研究が不足していることを考慮すると、日本企業独自の状況(海外進出戦略、組織構造、企業文化など)を踏まえた要因の選定と、目的間のトレードオフ関係の分析が必要となる。内国歳入法第482条やそれに類する法律の存在も考慮し、節税目的の達成が規制により困難になっている現状も分析に含めるべきである。 最終的には、これらの要因と目的を階層的に整理し、日本企業における国際振替価格設定メカニズムを解明するための分析フレームワークを構築することが、今後の研究の重要な課題と言える。
3. 日本企業への適用と今後の実証研究への示唆
本稿でレビューした研究を基に、日本企業の国際振替価格設定に関する実証研究を行う際の留意点を提示する。既存研究では、米国企業を対象としたものが多く、日本企業の場合とは海外進出方法や経営戦略が異なるため、そのまま適用することは難しい。そのため、日本企業独自の状況を考慮し、不要な要因は削除し、新たな要因を追加する必要がある。 具体的には、企業の戦略(本国志向型、現地志向型、地域志向型、世界志向型など)、組織構造、そして意思決定者の個人特性といった要因も考慮すべきである。これらの要因は、振替価格設定の基準、主体、頻度などに影響を与える可能性がある。 また、移転価格税制の改正動向や、受入国の経済状況(発展途上国と先進国で異なる対応が必要)なども考慮する必要がある。 今後の研究では、これらの点を踏まえ、より多くの日本企業を対象とした大規模な実証研究を行い、より精緻な分析モデルを構築することで、日本企業にとって最適な国際振替価格戦略を提案することが期待される。
