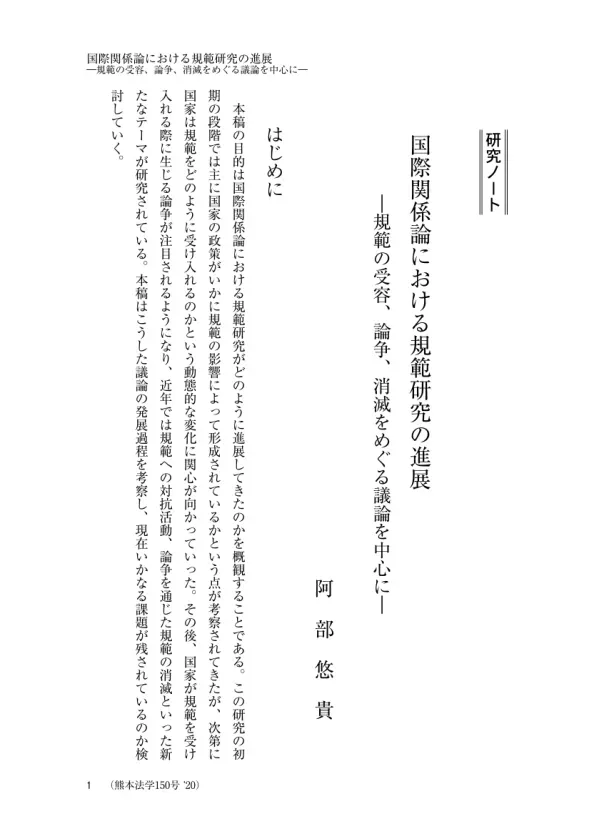
国際関係論:規範研究の最新動向
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.21 MB |
| 著者 | 阿部悠貴 |
| 専攻 | 国際関係論 |
概要
I.規範の受容 国際関係論における規範研究 の進展
初期のコンストラクティヴィズム研究は、国際規範の影響力に焦点を当てていたが、その後、「規範ライフサイクル」モデル(Finnemore & Sikkink)が提案され、規範の生成過程が体系的に説明されるようになった。しかし、第二波のコンストラクティヴィズム研究では、「規範がどのように重要なのか(How norms matter)」という問いに重点が移り、規範の受容プロセスに関する研究が盛んになった。規範受容のアクターの主体性(Cortell & Davis)、国内規範との親和性(Price, Farrell, Sundstrom)、手続き的正義(Dembinski)といった要因が、規範の拡散に影響を与えていることが示されている。さらに近年は、規範の受容を偽る行動(Cloward)についても研究が進んでいる。
1. 規範研究の初期段階とFinnemore Sikkinkモデル
国際関係論における規範研究は、初期においてネオリアリズムやネオリベラリズムといった既存の理論への反論として発展しました。規範、理念、アイデンティティといった非物質的要因が国際政治に大きな影響を与えているという主張がなされ、様々な研究が発表されました。その中で、マーサ・フィネモアとキャスリン・シキンクによる「規範ライフサイクル」モデル(Finnemore and Sikkink 1998)は大きな影響を与えました。このモデルは、規範起業家が提唱するアイデアが国内で支持を集め、国際的に拡散し、最終的に各国が内面化するまでの段階を明らかにし、規範の生成過程を理解するための重要な枠組みを提供しました。このモデルは、規範形成のプロセスを理解する上で広く参照される理念型として定着しました。しかし、この初期の研究は、規範の重要性を示すことに重点を置いており、規範がどのように国際政治に影響を与えるのかというプロセスそのものへの考察は不十分でした。
2. コンストラクティヴィズム第二波と規範受容プロセスの解明
事例研究の蓄積により、コンストラクティヴィズムの分析視角が国際関係論において確立されていく中で、初期研究の限界が指摘されるようになりました。「なぜ規範が重要なのか」という問いから、「どのように規範は重要なのか(How norms matter)」という問いへと研究の焦点は移っていきました(Kowert and Legro 1996)。これは、コンストラクティヴィズムの「第二波(second wave)」研究の始まりを告げるものでした(Acharya 2011b; Cortell and Davis 2005; Wiener 2004)。第二波研究は、規範の受容プロセスに焦点を当て、アクターの主体性や、国内政治構造、組織文化といった要因を分析対象としました。具体的には、アンドリュー・コーテルとジェームズ・デイヴィスは、政策決定者が規範を採用する際に、自らの利益を考慮している点を指摘しました(Cortell and Davis 1996, 2005)。湾岸戦争におけるアメリカの行動や、アメリカの半導体産業によるGATT自由貿易規範の活用などが例として挙げられています。
3. 国内規範との親和性と規範受容条件
国際規範の受容条件に関する研究では、国内規範との親和性の重要性が議論されました。リチャード・プライスは、NGOが既存の規範に「接ぎ木(grafting)」を行う戦略が、新たな規範の拡散に重要であると主張しました(Price 1998)。セオ・ファレルは、国際規範が国内規範と親和性を持つ場合にのみ「移植(transplantation)」が可能であり、規範受容の条件となることを指摘しました(Farrell 2004)。リサ・サンドストロームのロシアにおける徴兵制廃止運動に関する研究は、国内規範との整合性が規範受容に影響を与えることを示しています(Sundstrom 2005)。また、マークス・コーンプロブストは、国際規範が浸透するのは、受け入れ国の重要な信条が侵害されない場合であると論じています(Kornprobst 2007)。これらの研究は、国際規範の受容が、単なる国際的な圧力や説得だけでなく、国内政治状況や文化的な要因に大きく依存していることを明らかにしています。
4. 手続き的正義と規範の適用プロセス 規範受容の偽装
マティアス・デンビンスキは、規範が適用される過程における「手続き的正義(procedural justice)」の重要性を指摘しました(Dembinski 2016)。コートジボワールとリビアの内戦への軍事介入を例に、手続きへの参加の有無が規範の受容に影響を与えることを示しています。一方、モナ・クロックとジャッキー・トゥルーは、規範が固定化された概念として伝播するのではなく、形成途上の過程(works-in-progress)として広がることを論じています(Krook and True 2010)。 彼らは「言説的アプローチ(discursive approach)」を提唱し、規範起業家の戦略を分析しています。近年では、カリサ・クロワードによる研究のように、国際規範の受容を「偽る(misrepresent)」という側面にも注目が集まっています(Cloward 2014, 2016)。ケニアの村落における調査を通じて、国際的な接点が多い地域ほど、実際には存在する慣習を否定する回答が増えることを明らかにし、規範受容の複雑さを示しています。
II.規範と論争 国際規範 をめぐる 対抗活動 と 規範の消滅
第二波の研究では、国際規範の伝播が単線的ではないこと、規範自体が変化し、論争を引き起こすことが指摘されている。現地化(localization)(Acharya)のプロセスを通して、国際規範は各国独自の解釈で受け入れられる。アンツェ・ウィーナーは規範の論争を体系的に分析し、「根本規範」「標準化された手続き」「組織化された原則」の三つのタイプを提示、それらの間の正統性の乖離が論争の根源であると論じている。クリフォード・ボブは規範に対する対抗活動(rival activism)の存在を指摘し、規範をめぐる論争が規範の消滅、あるいは強化につながる可能性を考察している。サンドホルツは、規範の中身は時代と共に変化していく「規範変化のサイクル理論」を提示している。
1. 規範の非線形的な拡散と論争の発生
第二波のコンストラクティヴィズム研究は、従来の規範研究が規範の伝播を単線的に捉えている点を批判しました。FinnemoreとSikkinkの「規範ライフサイクル」モデル(Finnemore and Sikkink 1998)や「スパイラル・モデル」(Risse, Ropp and Sikkink (eds.) 1999)などは、規範が段階的に拡散していく過程を説明していますが、そこでは論争や抵抗といった要素が十分に考慮されていませんでした。第二波研究では、規範の拡散過程において規範自体が変化し、論争を引き起こすこと、そしてその論争を通じて新たな規範が生まれる可能性が指摘されています。これは、国際規範がそのままの形で受け入れられるのではなく、現地の文化や既存の規範と相互作用しながら再構成されることを意味します。Amitav Acharyaは「現地化(localization)」という概念を提案し、OSCEの「共通安全保障(common security)」規範がASEAN諸国においてどのように受け入れられ、ASEAN Wayとして再解釈されたかを分析しています(Acharya 2004; 2011b)。
2. アントイェ ウィーナーによる規範論争の分析
Antje Wienerは規範論争(contestation)に焦点を当てた独自の研究を展開しています。彼女は「論争的受諾(contested compliance)」という概念を提示し、中東欧諸国がEU規範に抵抗しながらも、論争を通じて受け入れていった過程を分析しました(Wiener 2004)。さらに、彼女は規範を「根本規範(fundamental norms)」、「標準化された手続き(standardised procedures)」、「組織化された原則(organised principles)」の3つのタイプに分類し、異なるレベルで作用する規範間の対立が論争の原因となることを示唆しています(Wiener 2014)。「保護する責任」規範は、人道主義という根本規範と武力不使用規定という標準化された手続きの対立を仲介する組織化された原則として誕生したと分析し、環境問題におけるCBDM(共通だが差異ある責任の原則)も同様の枠組みで解釈しています(Wiener 2014)。Wienerは、規範論争が国際問題のガバナンスにおいて重要な役割を果たしており、妥協点を探る場となっていると結論づけています。
3. 規範変化のサイクル理論と対抗活動
Sandholtzは、規範が「規範ライフサイクル」モデルが想定するような段階的なプロセスで形成され、最終的に固定化するのではなく、その中身が疑義が投げかけられるたびに改変されていくことを主張しています。彼は、実施、討議、ルール変更の循環によって規範が発展する「規範変化のサイクル理論(the cycle theory of norm change)」を提示しています(Sandholtz 2007, 2008; Sandholtz and Stiles 2009)。 一方、Clifford Bobは、ある規範が提唱されると、それに反対する「対抗活動(rival activism)」が展開されることを指摘しています(Bob 2012)。 例えば、アメリカにおける銃規制や同性愛者の権利運動に対する反対運動、あるいはブラジルにおける銃規制反対運動とNRAとの連携などが例として挙げられています。この対抗活動は国内にとどまらず、国際的なネットワークを通じて展開されることがあることを示しています。
4. 規範の消滅可能性と戦争に関する規範
規範をめぐる論争が、規範の消滅につながる可能性も議論されています。近年、戦争に関する規範からの逸脱例(捕虜虐待、拷問、政治指導者の暗殺など)が増えていることから、この問題が注目されています(Gross 2010; Banka and Quinn 2018; McKeown 2009)。従来、これらの行為は国家間の了解に基づき禁止されてきましたが、相手がテロリストである場合、規範からの逸脱、あるいは消滅の可能性が議論されるようになっています。Diana PankeとUlrich Petersohnは、規範からの逸脱があった際に、強力な国家がそれを罰するかどうかが、規範の存続に影響を与えると指摘しています(Panke and Petersohn 2011, 2015)。 芸術作品の略奪に関する規範を例に、Sandholtzは、ハーグ条約の改訂を通じて規範の中身が変化していく過程を分析しています。イラク戦争におけるバグダッド博物館の事例は、国家による芸術作品の保護という新たな規範の必要性を示唆しています。
III.今後の課題 規範への反発 と 論争 のメカニズム
今後の研究課題として、誰がなぜ規範に反発するのか、論争を引き起こす規範とそうでない規範の違いを解明することが挙げられる。既存の研究では、最初から反対するアクターに焦点が当てられてきたが、動的な理由、すなわち当初は賛同していたアクターが、何らかのきっかけで反対するようになった理由を考察する必要がある。Deitelhoff & Zimmermannは、規範の性質(妥協を許容するか否か)が論争のタイプ(適用をめぐる論争、有効性をめぐる論争)を規定すると主張している。規範は「正しさ」に関する価値を基盤としているため、批判された側からの強い反発を引き起こしやすい。規範の中身に着目し、妥協の余地のある規範とそうでない規範の違いを分析することが重要となる。
1. 規範への反発 動的な理由の解明
これまでの研究では、特定の規範に反対するアクター(例:銃規制反対のNRA、保護する責任に反対する国々)が分析されてきました。しかし、なぜある規範に反発が生じるのか、その動的なメカニズムについては十分に解明されていません。当初は賛同していた、あるいは中立だったアクターが、何らかのきっかけで反対するようになった理由を分析する必要があります。この点に着目することで、特定の規範が論争を引き起こす理由、あるいは他の規範がそうではない理由をより深く理解できる可能性があります。 既存研究では、例えば、ブルームフィールドの言う「アンチプレナー」の存在は示唆されていますが、それらのアクターの行動の背後にある動的な要因や変化のプロセスについては、さらなる研究が必要です。 これは、規範の受容や拡散、そしてそれらを取り巻く論争の全体像を理解する上で非常に重要な未解明な領域と言えます。
2. 論争の類型と規範の性質 妥協の可能性
DeitelhoffとZimmermann(Deitelhoff and Zimmermann 2020)は、「適用をめぐる論争」と「有効性をめぐる論争」という二つの論争の類型を提示しています。「保護する責任」規範は、適用手続きや範囲に関する論争(適用をめぐる論争)を引き起こしますが、規範自体の有効性が問われることは少ないとされています。一方、「捕鯨禁止」規範のように、規範の意義自体が問われる場合(有効性をめぐる論争)、規範は弱体化する傾向があります。しかし、この分類は、論争自体が規範の性質を反映しているという循環論法(トートロジー)に陥る危険性も孕んでいます。 今後の研究では、規範の性質、具体的には妥協を許容する余地があるか否かを検討する必要があります。Wiener(Wiener 2014)が指摘するように、「保護する責任」は異なる主張の妥協点を模索する役割を持つ仲裁規範としての性格を持つ一方、「捕鯨禁止」はゼロサムゲーム的な性質を持つため、妥協が困難であるという違いが論争の性質を規定していると言えるでしょう。
3. 論争の行方と規範の将来 解決と継続
規範をめぐる論争は、常にその規範の将来を左右する重要な要素です。Acharya、Wiener、Sandholtzの研究は、論争から新たな展望が開かれる可能性を示唆しています。Acharyaは国際規範の「現地化」、Wienerは「組織化された原則」の形成、Sandholtzは規範内容の更新という形で、論争から解決への道筋を示しています。しかし、Bob(Bob 2012)やBloomfieldは、対抗活動が存在する限り、新しい規範と対抗活動のどちらかが完全に敗北するまで論争が継続する可能性を指摘しています。足立(おそらく文献参照部分)は、推進派と反対派による「接ぎ木」と「接ぎ木の切断」が繰り返される状況を指摘し、論争の行方を予測することは困難であるとしています。 これらの異なる見解を踏まえ、論争から新たな展望が開かれるケースと、論争が継続するケースの線引きを明確にすることが、今後の研究における重要な課題となります。
