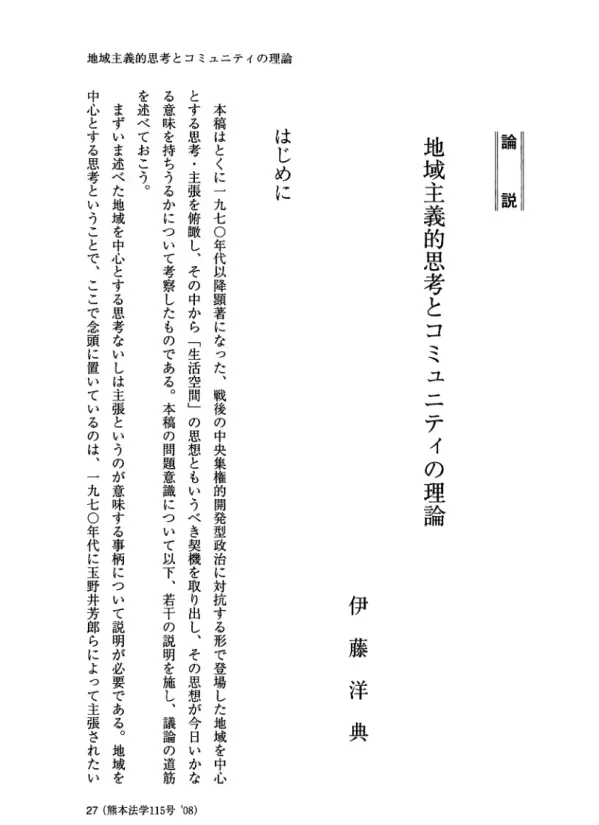
地域主義とコミュニティ論:現代社会の課題
文書情報
| 著者 | 伊藤洋典 |
| 専攻 | 地域社会論、コミュニティ論 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.40 MB |
概要
I.第一節 生活空間としての地域社会 高度経済成長期における地域主義と住民運動
本節は、高度経済成長期における「地域主義」思想の展開を、松下圭一の「地域民主主義」と石牟礼道子の思想を比較検討することで明らかにします。松下は安保闘争期における「ムラ状況」の打破を訴え、地域における民主主義の成熟を主張しました。一方、石牟礼は水俣病を通して、近代資本主義と中央集権的開発政治によって破壊された「生類の世界」(生活空間)の喪失を描き出し、地方の住民運動の土着性と地域性を強調しました。両者の思想は、生活空間の重要性という点で共通しており、現代のコミュニティ論との比較において重要な意味を持ちます。
1. 安保闘争期における地域の位置づけと松下圭一の地域民主主義
本節は、高度経済成長期以前の地域主義の萌芽として、1960年代の安保闘争における地域の位置づけから議論を始めます。 特に、松下圭一が提起した「地域民主主義」に焦点を当て、その核心概念を分析します。松下は、安保闘争を通じて露呈した地域社会、特に末端社会における民主主義の未成熟、「ムラ状況」を問題視しました。彼は、この「ムラ状況」を打破し、戦後民主主義を達成するためには、地域社会、日常生活の全領域を窓口とする自治体の改革が不可欠であると主張しました。 論文『思想』で用いられた「地域自治」という概念は、今日的な有効性を持つ視点として注目に値します。しかし、松下は「市民」と「住民」を明確に区別しており、民主主義の担い手として「市民」、統治の対象として「住民」を位置づけています。これは、後の70年代以降の地域論と比較検討する上で重要な視点となります。 彼の議論は、日本の民主化を地方ではなく地域という観点から捉え直そうとする画期的な試みでしたが、地域社会の本質を十分に捉えきれていない面もあったと指摘されています。自治体改革を通じての日本の民主化という、彼の最終目標が、地域社会そのものの理解をやや後回しにした可能性が示唆されています。
2. 高度経済成長期と住民運動 石牟礼道子の思想と 生類の世界
高度経済成長期(1960~70年代)は、開発優先型の政治が地域社会に多大なダメージを与えた時代でした。この時代に勃興した住民運動は、反公害運動や反戦・平和運動とは異なる特徴を持ち、土着性や地域性を強く強調していました。 本節では、この時代の住民運動を代表する思想家として石牟礼道子の思想を取り上げます。石牟礼は水俣病を背景に、人間の存在基盤としての「生活空間」を描き出しました。 彼女の作品において繰り返し登場する「生類の世界」という概念は、人間と自然が分離することなく共存する世界、すべての生命が通い合っている世界を表しています。これは、高度経済成長による開発によって破壊された、失われた世界でもあります。 石牟礼は「風土」や「風景」といった概念を用いながら、客観的・主観的ではない「中間的な境地」としての感性の世界を描いています。この感性の世界こそが「存在」であり、「実存」を支える基盤であると彼女は主張します。水俣病の被害者である水俣の住民の姿を通して、彼女は近代資本主義と中央集権的開発政治に対する批判を展開し、その対極にある「生類の世界」の重要性を訴えました。 石牟礼の視点は、普遍的な人権や市民権というよりも、辺境・下層民・共同体といった、近代社会の周辺に位置する人々の生活世界に深く根差しています。 彼女の作品は、近代批判を超えて、失われた「生類の世界」の到来を暗示するものとして解釈できます。
II.第二節 今日のコミュニティ論 場所性と脱場所性の葛藤
本節では、現代のコミュニティ論における「場所性」の問題を議論します。1969年の国民生活審議会報告書は、都市化による人間関係の空洞化とコミュニティの必要性を指摘し、「生活の場に立脚する集団」としてのコミュニティを定義しました。しかし、近年のコミュニティ論は、モータリゼーションや情報化による脱場所性の傾向を踏まえつつも、ソーシャル・キャピタル論や場所論的コミュニティ論が展開されています。Robert D. Putnamの『孤独なボーリング』に見られるソーシャル・キャピタルの減少傾向や、Gerard Delantyの議論に見られるコミュニティの脱空間化傾向は、従来型の場所的コミュニティの限界を示唆します。 まちづくり運動は、住民運動の消滅後、生活空間の再構築を目指したコミュニティ形成の試みとして注目されます。湯布院町におけるまちづくりは、ダム建設計画反対運動と自衛隊誘致成功を契機に、観光地としての発展を遂げました。 日本のコミュニティ論では、町内会などの従来型コミュニティの可能性と、移動型社会における新たなコミュニティの可能性が併存しています。
1. 1969年国民生活審議会報告書とコミュニティの定義
本節は、現代のコミュニティ論を考察する出発点として、1969年の国民生活審議会報告書『コミュニティー生活の場における人間性の回復』を取り上げます。この報告書は、高度経済成長期の都市化・モータリゼーションによる旧来の地域社会(村落共同体や隣保組織)の崩壊を背景に作成されました。報告書は、都市化によって人間関係が空洞化し、個人の孤独化、人間性の危機を招いていると指摘し、新しい地域社会の構築としてコミュニティ形成の必要性を訴えています。 報告書で定義されるコミュニティとは、「生活の場において、市民としての自主性と責任を自覚した個人および家庭を構成主体とし、地域性と共通目標を持ち、開放的で信頼感のある集団」です。 これは、個人を飲み込む旧来の共同体とは異なる、個人の自立と連帯を両立させた新しいコミュニティ像を示唆しています。また、報告書は行政機構の不備、特に縦割り行政や行政圏の拡大の問題も指摘しており、コミュニティ形成と行政との関係についても言及しています。昭和の大合併(1955年)以降の都市化の進展と、それに伴う地域社会の変容を踏まえた上で、報告書はコミュニティの必要性を訴えている点が重要です。
2. まちづくり運動とコミュニティ形成
本節では、住民運動から派生した「まちづくり」運動を、コミュニティ形成の試みとして考察します。1960年代の住民運動が高度経済成長期の開発型政治への批判を主眼としていたのに対し、「まちづくり」運動は、住民が主体となって生活空間を自ら形成しようとする点で、よりコミュニティ形成に近しい活動です。 住民運動が衰退していく中で、「まちづくり」は、残された住民が中心となり、地域を改善する活動を通して、生活空間に立脚したコミュニティを再構築しようとする試みとして位置づけられます。 具体例として、湯布院町のまちづくりが取り上げられています。湯布院町は、1952年のダム建設計画反対運動と自衛隊誘致成功を契機に発展しました。 その後、1964年の九州横断道路開通、そして70年代以降のまちづくり運動によって、全国的に知られる観光地へと成長を遂げました。この事例は、住民参加によるコミュニティ形成が、地域社会の再生に貢献できることを示唆するものです。 このように、70年代以降顕著になった「まちづくり」は、住民運動とは異なるアプローチでコミュニティ形成を目指しており、その成功例は現代のコミュニティ論を考える上で重要な示唆を与えてくれます。
3. コミュニティ論における場所性と脱場所性 ソーシャル キャピタル論との関連
本節では、現代のコミュニティ論における「場所性」の希薄化という問題を検討します。都市化やモータリゼーション、そしてインターネット社会の発展は、人間の生活の脱場所化を進めています。しかし、近年のコミュニティ論は、この脱場所性を自明の前提とするのではなく、場所性をめぐる議論が展開されています。 この状況を理解する上で重要なのが、国民生活白書における「つながり」という概念です。白書は、人間関係の希薄化を問題視し、「つながり」の重要性を強調しています。 これは、場所を共有するコミュニティだけでなく、関心を共有するコミュニティも存在することを示唆しています。 Robert Putnamの『孤独なボーリング』で議論されているソーシャル・キャピタルは、場所にとらわれない、脱場所的な概念であり、現代社会における人間関係の質の変化を反映しています。 Putnamは、ソーシャル・キャピタルの減少が民主主義の機能不全につながると警告していますが、同時に、近隣社会(ネイバーフッド)への参加を民主主義活性化の鍵として捉えています。 しかし、このネイバーフッドは日本の町内会のような従来型の場所的コミュニティとは異なる概念であることに注意が必要です。 現代のコミュニティ論は、場所性をめぐる複雑な状況を反映しており、場所的コミュニティと脱場所的コミュニティの双方を考慮する必要があることを示しています。
III.地域主義的思考とコミュニティの理論 共通点と今後の課題
最終節では、地域主義と現代のコミュニティ論の共通点と相違点を整理し、今後の課題を提示します。 地域主義思想、特に松下と石牟礼の思想は、生活空間の重要性を強調することで、現代のコミュニティ論と共鳴する点があります。しかし、松下の「市民」と「住民」の区別、石牟礼の「生類の世界」といった概念は、現代の脱場所的コミュニティ論とは異なる視点を提示しています。 コミュニティのあり方を探る上では、「住む」という行為の根源的な意味、個人の選択を超えた地平を再考する必要があります。 これは、地方分権やまちづくりといった政策にも影響を与え、今後のコミュニティ研究における重要な課題となっています。
1. 地域主義とコミュニティ論の共通点 生活空間の重視
本節では、1960~70年代の地域主義と現代のコミュニティ論の共通点を探ります。 特に、両者の間で共有される「生活空間」という概念に焦点を当てます。松下圭一の「地域民主主義」や石牟礼道子の「生類の世界」といった概念は、いずれも人間にとっての地域が単なる居住空間ではなく、存在基盤となる「生活空間」であることを強調しています。 石牟礼道子の思想では、高度経済成長による開発が「生類の世界」、つまり人間と自然が共存する生活空間を破壊したと批判的に捉えられています。この「生類の世界」は、近代資本主義や中央集権的開発政治の対極に位置づけられ、感性によって媒介された存在の場として描かれています。 一方、現代のコミュニティ論においても、都市化やモータリゼーションによる人間関係の希薄化、コミュニティの崩壊といった問題意識が共有されています。そして、これらの問題に対処するための方法論として、生活空間の回復や生活の場の再構築が提唱されている点で、地域主義と共通の基盤が見られます。 つまり、地域主義が重視した「生活空間」という概念は、現代のコミュニティ論においても、人間性の回復や豊かな国民生活の実現という点で、依然として重要な意味を持つと言えるでしょう。
2. 地域主義とコミュニティ論の相違点 場所性と脱場所性の問題
地域主義と現代コミュニティ論の相違点は、主に「場所性」と「脱場所性」という問題意識の違いにあります。 1960~70年代の地域主義は、具体的な地域社会、生活空間における人々の営みを重視し、その空間的な固有性を強く意識していました。石牟礼道子の作品は、水俣という特定の地域における人々の生活や文化を詳細に描き出し、その場所性の重要性を示しています。 一方、現代のコミュニティ論では、都市化や情報化の進展により、コミュニティの空間的基盤が弱体化し、脱場所的な傾向が顕著になっています。 Gerard Delantyの議論が示すように、現代社会におけるコミュニティは、場所や地域性に限定されず、ネットワークや関心の共有といった脱場所的な側面を重視する傾向が強まっています。 また、Robert Putnamのソーシャル・キャピタル論も、人間関係のネットワークを重視する点で、場所の共有という従来型のコミュニティ概念からの脱却を示しています。 しかし、脱場所的なコミュニティ論においても、民主主義の活性化のためには、近隣社会といった比較的小さな集団における社会関係の重要性が指摘されており、場所性の問題が完全に無視されているわけではありません。この点は、地域主義と現代のコミュニティ論の双方で共通して課題となっていると言えるでしょう。
3. 今後の課題 住む という行為の再考と地域の意味
本節は、地域主義とコミュニティ論の議論から導き出される今後の課題を提示します。 それは、人間にとっての「地域」や「コミュニティ」の意味を再考すること、そして「住む」という行為の本質を問い直すことです。 従来のコミュニティ論では、個人の選択や自由意志を重視する傾向がありましたが、地域主義、特に石牟礼道子の思想は、個人の選択を超える、あるいはそれを支えるより深い地平を示唆しています。「住む」という行為は、単に空間を占有する以上の意味を持ち、人間が根源的に持っている「つながり」によって支えられていると考えることができます。 現代社会では、人間関係の希薄化やコミュニティの崩壊が深刻な問題となっていますが、これに対して、単に従来型の場所的コミュニティの復元を目指すのではなく、「つながり」を回復するための新たな回路を模索することが必要です。 これは、地域主義が現代に残した重要な課題であり、今後のコミュニティ研究においても、生活空間の再構築や人間関係の質の向上といった点で、地域主義の知見を活かすことが重要となります。 地方分権やまちづくりといった政策においても、これらの課題を踏まえた上で、新たなコミュニティ形成のための取り組みが求められています。
