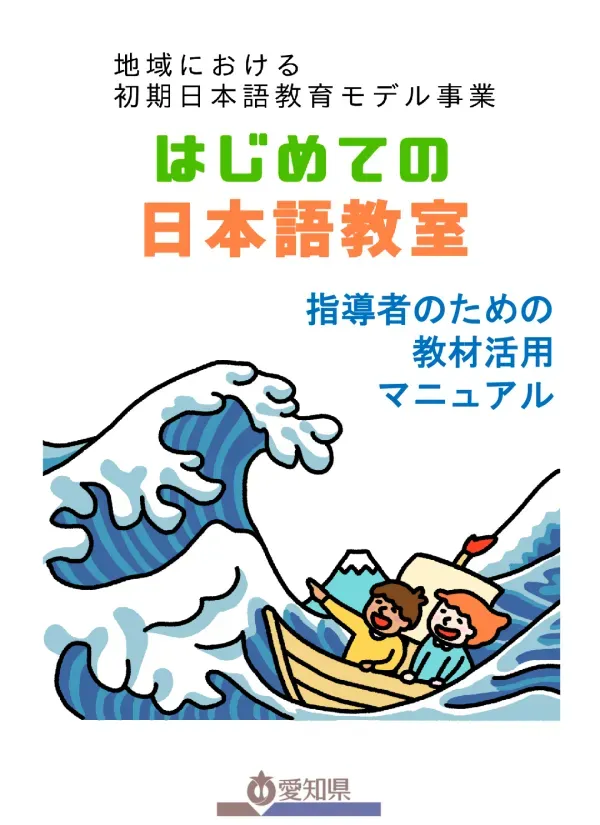
地域初期日本語教育モデル:実践ガイド
文書情報
| 著者 | 愛知県 |
| 学校 | 愛知県の関係機関(詳細不明) |
| 専攻 | 日本語教育 |
| 出版年 | 令和元年~令和2年(平成30年度~令和元年度) |
| 場所 | 愛知県 |
| 文書タイプ | マニュアル |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.23 MB |
概要
I.必要性 愛知県の 初期日本語教育 の現状と課題
愛知県では、在住外国人の増加に伴い、日本語学習の機会保障が喫緊の課題となっています。地域ボランティアによる日本語教室も存在しますが、初期日本語教育には高い専門性が求められます。そのため、平成27年度から「あいち外国人の日本語教育推進会議」を設置し、こどもとおとなの部会で課題解決に向けた検討を重ねています。特に「おとな部会」では、地域日本語教室と連携した行政・専門機関による初期日本語教育プログラムの実現可能性を、対象者、学習内容、指導者の専門性、ボランティアの役割などを中心に検討しました。このプログラムは、日本語がほとんど分からない外国人県民を対象とした、質の高い初期日本語教育を提供することを目指しています。
1. 愛知県における初期日本語教育の必要性
日本には、在住外国人の日本語学習を保障する国レベルの公的制度がありません。多文化共生社会の実現には、地域社会における外国人の受け入れ体制、ひいては効果的な日本語教育環境の整備が不可欠です。地域ボランティアによる日本語教室は生活に密着した学習機会を提供する点で意義がありますが、日本語がほとんど理解できない外国人県民を対象とした初期日本語教育は、専門性の高い指導を必要とする高度な課題です。この現状を踏まえ、愛知県では平成27年度から『あいち外国人の日本語教育推進会議』を設置。多様な関係者による意見交換や課題解決に向けた具体的な方策の検討を行っています。外国人の日本語教育における課題は、子どもと大人では大きく異なるため、『子ども部会』と『大人部会』を設け、詳細な議論を進めています。
2. 大人部会における初期日本語教育プログラムの検討
特に『大人部会』では、平成28年度から29年度にかけて、地域日本語教室と連携した行政・専門機関による初期日本語教育プログラムの実現可能性を重点的に検討しました。検討項目は、初期日本語教育の対象者、具体的な学習内容、指導者の必要とする専門性、ボランティアの役割、そして地域日本語教室との連携方法など多岐に渡ります。この検討において、効果的な初期日本語教育プログラムの設計、運営に必要な要素を明確化し、実現に向けた具体的なステップを洗い出しました。専門性の高い指導者確保の重要性や、ボランティアとの役割分担、既存の日本語教室との連携の在り方などが、特に重要な検討事項として挙げられています。
3. 初期日本語教育プログラムの実施における課題と必要な体制
初期日本語教育プログラムの実施には、様々な課題とそれらに対応できる体制の構築が不可欠です。具体的には、毎回の教室活動を担当する指導者の確保、学習者と効果的に対話できる日本語サポーターの確保、そして適切な教材の準備が挙げられます。さらに、教室運営に関わる様々な作業の調整や、予期せぬ事態への対応能力も求められます。人材養成においても、養成講座のプログラム開発、質の高い講師の選定、講座の円滑な運営、そして養成された人材の有効活用が重要となります。特に、養成講座のプログラム開発と講師選定には、地域日本語教育の高度な専門性が求められるため、適切なコーディネーターの確保が不可欠です。教室開催地域の自治体には、外国人住民コーディネーターの選定、開催場所の確保、学習者の募集など、事業実施主体者と連携して、プログラムの円滑な運営を支える役割が期待されます。
II.事業実施主体者の役割 対話型日本語教室 運営における責任
本事業の実施主体者には、地域の実情に合わせた開催場所・日時の設定と参加者の募集、教材開発、質の高い日本語教室運営のための指導者確保、人材養成など、日本語教室の継続的な運営を担う責任があります。教材開発には地域日本語教育の高い専門性が求められるため、適切な人材の確保が不可欠です。既存の日本語教室や外国人住民コーディネーターとの連携も重要です。特に、対話型日本語教室では、学習者の自律学習を促進する指導体制の構築が求められます。
1. 開催場所 日時設定と参加者募集
事業実施主体者は、地域の実情を踏まえ、適切な開催場所と日時を設定し、参加者を募集する責任を負います。この過程では、教室開催地域の自治体、既存の日本語教室、そして外国人住民コーディネーターとの連携が不可欠です。地域住民のニーズを的確に捉え、効果的な広報活動を行い、多くの参加者を確保することが求められます。 特に、外国人住民コーディネーターは、地域コミュニティとの繋がりを活かし、学習者募集に大きく貢献できる存在です。彼らの協力を得ながら、参加者にとってアクセスしやすい場所と時間帯を設定することで、より多くの学習者を確保し、教室の活性化を図ることが重要です。
2. プログラムと教材の開発
事業の成功には、質の高いプログラムと教材の開発が不可欠です。プログラム開発には、地域日本語教育における高度な専門性が求められます。そのため、この分野に精通した人材の確保が最重要課題となります。教材開発においても同様で、学習者のレベルやニーズに最適化された教材を提供することで、学習効果の最大化を目指します。単に既存の教材を使用するだけでなく、地域特有の状況や学習者の特性を考慮したオリジナル教材の開発も検討する必要があります。教材開発にあたっては、学習者の理解度を深めるための工夫、例えば視覚的な要素の活用や多様な学習方法の提示などが重要になります。
3. 教室運営と指導者の確保
事業実施主体者は、質の高い教室運営を維持するために、有能な指導者を確保する責任を負います。指導者は、毎回の教室活動を担当し、学習者と日本語サポーターを効果的にサポートする役割を担います。指導者には、学習者との円滑なコミュニケーション能力、教材の的確な活用、そして突発的な事態への対応能力などが求められます。さらに、学習者一人ひとりの学習状況を把握し、必要に応じて個別指導を行う柔軟性も必要です。日本語サポーターの確保も重要な課題であり、彼らには学習者との積極的な対話を通して、学習者の理解を深めるサポートが期待されます。
4. 人材育成と事業の継続性
日本語教室の持続可能な運営のためには、継続的な人材育成が不可欠です。そのため、事業実施主体者は、質の高い養成講座のプログラム開発、優秀な講師の選定、そして養成講座の実質的な運営に責任を持ちます。養成講座では、指導者と日本語サポーターの双方に必要なスキルを育成する必要があります。特に、地域日本語教育の高い専門性が求められるため、適切なコーディネーターを確保することが重要になります。養成された人材の活用方法についても計画的に検討し、教室運営の効率化と質の向上を図ることが求められます。これらの取り組みを通じて、地域に根付いた持続可能な日本語教育体制を構築することが重要です。
III.教材と学習方法 対話型日本語教室 のカリキュラムと 教材
本日本語教室では、日常生活で使える日本語を学ぶことを目標とした教材(ワークシートとふりかえりシート)を使用します。教材は、日常生活に密着した17の生活トピックと、学習の振り返りを促す5つのトピックから構成されています。対話を重視した学習方法を採用し、学習者はCan-do statementsを用いて自身の日本語能力を自己評価することで、自律学習を促進します。ひらがな程度の読み書き能力を目標に設定することで、既存の日本語教室へのスムーズな移行を支援します。教材は、すべて翻訳付きで、初期日本語学習者でも理解しやすいよう工夫されています。
1. 教材の概要と構成 日常生活に密着したトピックとワークシート
この対話型日本語教室で使用される教材は、ワークシートとふりかえりシートの2種類です。ワークシートは、参加者同士の対話を促すための教材で、日常生活で頻繁に使用される17個の生活関連トピックと、活動の振り返りを行うための5個のトピックで構成されています。各トピックは、学習者の理解を助けるため、母語を含む多言語で記述されています。また、ひらがな程度の読み書き能力を目標としているため、教材の表記もそれに合わせた配慮がなされています。ワークシートにはイラストが使用されており、視覚的な情報も提供することで、学習者の理解度を高める工夫が凝らされています。ローマ字表記も一部採用され、学習者にとってより親しみやすい構成となっています。
2. 学習方法 対話とCan do statementsによる自律学習の促進
本教材は、対話を重視した学習方法を採用しています。単なる会話ではなく、学習者が自身の考えや気持ちを伝え合う「対話」を重視することで、より実践的な日本語運用能力の向上を目指します。一見、おしゃべりに見える活動も、Can-do statements(到達目標)を明確に設定することで、学習目標を意識した効果的な学習活動として位置付けられています。学習者は、Can-do statementsを母語または使用言語で確認することで、自身の日本語能力を客観的に評価し、学習内容を自身の生活に結び付けることができます。この自己評価を通して、学習者は自身の学習進捗を把握し、自主的な学習を促進する「自律学習」へと繋がる仕組みが構築されています。さらに、学習者は、教室での学習を通して得た知識や経験を日常生活に活かし、不足点を自ら認識し、学習を継続していく習慣を身につけることが期待されます。
3. 教材の構成 ワークシートとふりかえりシート
教材は、ワークシートとふりかえりシートの2種類から構成されています。ワークシートは、参加者間の対話を通して情報を共有し、記録するためのツールです。ふりかえりシートは、学習者が自身の日本語能力を振り返り、学習成果を自己評価するためのものです。「日本語でできますか?」という自己評価項目や、「覚えたいことば」「感想」といった項目を通して、学習者は自身の学習を客観的に評価し、今後の学習目標を明確に設定することができます。これら二つのシートを効果的に活用することで、学習者は自身の学習を主体的に進める自律学習を促進し、日本語学習へのモチベーションを高め、継続的な学習へと繋げていくことが期待されます。日本語サポーターは、これらのシートを活用し、学習者の学習をサポートします。
IV.教室活動 対話型日本語教室 の具体的な運営方法
1回の教室活動は、ウォーミングアップ、自己紹介などの対話活動、日本語能力チェック、ふりかえりから構成されます。指導者と日本語サポーターは、学習者と対話しながら学習を支援します。日本語サポーターは、学習者との対話を通して、わかりやすい日本語を話す技術を向上させます。イベントへの参加や出前講座の活用、体験活動なども教室活動に取り入れ、学習の多様化を図ります。学習者と日本語サポーター、指導者それぞれの役割を明確に理解し、対話型日本語教室の趣旨を共有することが重要です。
1. 教室活動の全体像 ウォーミングアップからふりかえりまで
対話型日本語教室の活動は、ウォーミングアップから始まり、メインの学習活動、そしてふりかえりの3つの段階で構成されます。ウォーミングアップでは、参加者がリラックスした雰囲気の中で日本語に触れられるよう、簡単な自己紹介や雑談などを行います。メインの学習活動では、用意されたワークシートを用いて、参加者同士が対話を通して日本語を学びます。この際、指導者は学習内容の理解を助け、日本語サポーターは学習者と積極的に対話し、学習をサポートします。学習活動では、自己紹介や簡単な日常会話を通して、日本語の表現力やコミュニケーション能力の向上を目指します。最後に、ふりかえりシートを用いて、学習内容の理解度やその日の活動について振り返る時間を取ります。この振り返りの時間は、学習者が自身の学習状況を客観的に把握し、次の学習への意欲を高めるために重要です。
2. 対話活動 モデルとなる会話と自由な交流
対話活動では、まず指導者が簡単な日本語で自己紹介を行うことで、日本語サポーターと学習者にとってのモデルとなります。その後、日本語サポーターが同じように自己紹介を行い、学習者も倣って自己紹介を行います。この段階では、日本語サポーターが学習者のサポートを行い、スムーズなコミュニケーションを促します。学習者が話すことに慣れてきたら、全員が立って自由に相手を交代しながら、より実践的な交流活動を行います。自己紹介のトピックでは、ひらがな、カタカナ、漢字を用いて自分の名前を書く活動も含まれており、文字学習にも繋がる工夫がされています。活動後には、ふりかえりシートを使って、学習者自身が自身の日本語能力を自己評価する時間を設けます。この自己評価は、学習者の学習意欲を高め、自主的な学習を促進する上で重要な要素となります。
3. クラス後の日本語能力チェックと活動報告
対話活動後には、ふりかえりシートを用いて、学習者一人ひとりが自身の日本語能力を自己評価します。「日本語でできますか?」という項目にチェックを入れることで、学習者は自身の理解度を客観的に把握することができます。この自己評価は、学習者自身の学習を振り返るだけでなく、指導者や日本語サポーターにとって、今後の指導方法を考える上での重要な情報となります。また、教室活動後には、活動報告書を作成し、関係者と共有します。報告書には、当日の活動内容や学習者の様子などが記録され、今後の教室運営の改善に役立てられます。活動報告書には、各トピックに関連する素材(写真や実物など)を一覧にしてまとめることで、指導者やサポーターがより効果的な教材の準備を行う上で役立ちます。学習者との相互理解を深めるための具体的な工夫が記載されています。
4. 教室活動の充実 イベント参加 出前講座 体験活動
教室活動の充実を図るために、地域イベントへの参加、出前講座の活用、そして体験活動の3つの方法が提案されています。地域イベントへの参加は、学習者にとって、教室の外で日本語を使う機会を提供し、地域社会への参加を促します。日本語サポーターも同行することで、学習者をサポートし、安心感を高めます。出前講座は、外部講師を招いて教室で講座を行うことで、学習の幅を広げます。警察や消防、赤十字などの講座を日本語教室用にアレンジすることで、学習者にとってより理解しやすい内容となります。体験活動は、スーパー見学やカルタ・書道体験など、教室の外で直接的な経験をすることで、学習内容の理解を深めます。これらの活動を通して、教室での学習内容を日常生活に結びつけ、学習意欲を高めることができます。
V.既存の日本語教室との連携
本プログラムは、初期日本語教育修了後の学習継続を支援するため、既存の地域日本語教室との連携を重視します。ひらがな程度の読み書き能力を習得目標に含めることで、既存の日本語教室へのスムーズな移行を促進します。また、外国人住民コーディネーターとの連携により、学習者の募集や地域社会への接続を支援します。
1. 初期日本語教室の学習目標と既存教室への接続
初期日本語教室の学習目標は、日本語が全く分からなかったり、ほとんど分からなかったりする初期レベルの学習者が、あいさつや自己紹介ができるようになり、地域の人と繋がりを持つことができるようになることです。日常生活で使う簡単な表現を理解し、話すことができるようになることも重要な目標です。この教室は、学習者が既存の地域日本語教室へスムーズに移行できるよう、ひらがなをある程度読めるレベルを目指します。多くの既存教室では、ひらがなの読解能力がクラス分けの基準となっており、ひらがなを読めない学習者は参加しにくい状況があるためです。したがって、初期日本語教室では、既存教室への円滑な移行を支援する役割も担います。学習者が、初期日本語教育修了後も継続して日本語学習に取り組めるよう、橋渡しをすることが重要です。
2. 既存教室との連携による学習継続の支援
初期日本語教室は、既存の地域日本語教室との連携を強化することで、学習者の学習継続を支援することを目指しています。初期段階での学習成果を維持・発展させ、より高度な日本語学習へと繋げるための仕組み作りが重要になります。そのため、初期日本語教室のカリキュラムは、既存教室のレベル設定に配慮し、スムーズな接続を可能にするよう設計されています。具体的には、ひらがなをある程度読めるようになることを目標に設定することで、既存の日本語教室への参加を容易にすることを目指しています。さらに、学習者やサポーターからの日本語の文法や学習方法に関する質問に的確に回答できるよう、指導者には幅広い知識とリソースへのアクセス能力が求められます。この連携を通して、学習者が日本語学習を継続し、地域社会に円滑に溶け込むためのサポート体制が構築されます。
