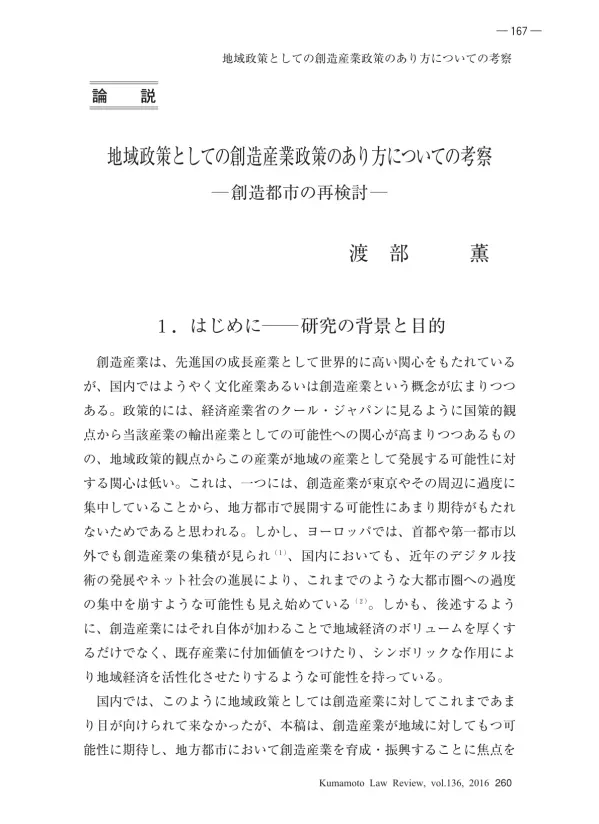
地域創造産業政策:創造都市の再検討
文書情報
| 著者 | 渡部薫 |
| 専攻 | 地域政策、文化政策、創造産業論 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 521.25 KB |
概要
I.地域における創造産業政策の現状と課題
本稿は、地方都市における創造産業政策のあり方を検討する。創造産業は先進国の成長産業として注目されているが、日本では東京への集中が著しく、地方都市での発展は期待されていない。しかし、デジタル技術の発展やネットワーク社会の進展により、地方都市での創造産業集積の可能性も生まれている。地域政策の観点からは、創造産業が地域経済の活性化に貢献する可能性(既存産業への付加価値、都市イメージ向上、観光促進など)に注目すべきである。
1. 創造産業の現状 東京一極集中と地方の遅れ
創造産業は世界的に高い関心を集める成長産業だが、日本では東京圏への集中が顕著であり、地方都市での発展は限定的である。これは、経済産業省のクールジャパン政策に見られるように、輸出産業としての可能性に注目が集まる一方で、地域政策として地方都市における創造産業の育成・振興に対する関心が低いことが原因の一つと考えられる。地方都市では、創造産業の東京圏への集中によって、地方での展開可能性に期待が持てないという現状がある。しかし、近年におけるデジタル技術の発展やネット社会の進展は、この大都市圏への過度な集中を変化させる可能性を示唆している。ヨーロッパでは、首都圏以外でも創造産業の集積が見られるという点も、この変化の可能性を示す重要な事例と言えるだろう。 創造産業は地域経済に多大な影響を与える潜在力を持っている。それは単に地域産業のボリュームを増やすだけでなく、既存産業に付加価値を与え、シンボリックな効果を通じて地域経済の活性化を促進する可能性を秘めている点にある。
2. 創造産業政策の地域的展開 海外と日本の比較
本稿では、地域政策としての創造産業政策のあり方を検討するため、まず、海外と日本の創造産業政策の地域的展開について概観する。英国では、ブレア労働党政権下で開始された創造産業政策は、輸出促進のみならず、国内地域における展開も検討され始めた。特に、80年代以降の衰退産業都市の再生において、文化による都市再生、そして創造産業の育成・振興が自治体レベルで重要な政策柱となった事例は注目に値する。創造都市という概念も、このような文化による都市再生の経験に基づいて生まれたものである。これに対し、日本においては、地域政策的な観点から創造産業が地域の産業として発展する可能性に対する関心が低い。これは、創造産業が東京やその周辺に過度に集中していることから、地方都市で展開する可能性にあまり期待がもたれないためだと考えられる。しかし、ヨーロッパ諸国では首都圏以外でも創造産業の集積が見られるなど、日本とは対照的な状況が見られる。
3. 地方都市における創造産業政策の課題と可能性
地方都市において創造産業政策を検討する場合、その都市の置かれている状況や創造産業への期待役割を考慮する必要がある。創造産業のサブセクターによって産業の性格が異なるため、一律の政策は難しい。地方都市では、創造産業自体の発展は限定的であっても、地域の実情に応じた多様な可能性を秘めている。創造産業政策を検討する際には、その都市が持つ資源、都市システム内での位置づけ、産業状況などを踏まえ、戦略的に政策を展開していく必要がある。創造産業を都市の産業においてどのように位置づけるか、どのような役割を期待するか、創造産業の中でもどの分野に重点を置くかといった点を明確にすることが重要になる。 また、創造産業の文化的側面と産業的側面、そして両者の関係性を理解することが不可欠である。地域における文化の生産をどのように捉え、支援するのかという問題も、重要な論点となる。
II.海外 国内における創造産業政策の展開
英国やEU諸国では、創造産業政策が地域レベルでも展開されている。英国では、衰退産業都市の再生に文化政策と創造産業育成が活用されている事例がある。日本では、経済産業省のクール・ジャパン政策のように輸出拡大に重点が置かれる傾向がある一方、地域政策としての展開は遅れている。横浜市、金沢市、札幌市など一部都市では、創造都市構想に基づいた文化政策と創造産業政策が推進されている。
1. 海外における創造産業政策 英国とEU諸国の事例
海外の創造産業政策の地域展開事例として、英国とEU諸国が挙げられる。英国では、クール・ブリタニア戦略のような輸出指向の国家レベルの政策に加え、ブレア政権以降、国内地域レベルでの展開も検討されている。特に注目すべきは、1980年代以降、衰退した産業都市の再生において文化による都市再生が試みられ、創造産業の育成・振興が自治体政策として重要な柱となった点である。創造都市という概念も、このような文化による都市再生の経験から生まれたものである。政策主体は、国家レベルでは中央政府が政策の方向性や支援枠組みを提示する一方、地域レベルでは基礎自治体が主体となり、広域自治体、国の地方機関、地域団体などとの連携・協調の下で政策を展開している。芸術振興団体であるアーツカウンシルも重要な役割を果たしている。多くの都市が創造都市を標榜するものの、体系的な政策展開は限られている。
2. 国内における創造産業政策 東京一極集中と地方の取り組み
日本においては、経済産業省のクール・ジャパン政策に見られるように、国家レベルでは創造産業の輸出産業としての可能性に高い関心が寄せられている。しかしながら、地域政策の観点からは、創造産業の地方都市における発展可能性に対する関心が低いのが現状である。その背景には、創造産業が東京とその周辺に過度に集中しているという現状があり、地方都市での展開には期待が持てないという認識が根強く存在する。しかし、近年におけるデジタル技術の発展やネット社会の進展によって、この状況に変化が生じる可能性も出てきている。横浜市、金沢市、札幌市など、一部の中規模都市や大都市では、創造都市の考え方に基づいた都市戦略の中で、文化・芸術の役割を重視した文化政策的な取り組みが展開され、それに関連して創造産業政策も実施されている。一方で、中規模都市以下の地域や小規模な自治体においては、アニメーション産業など特定分野への取り組みが中心で、創造産業全体を対象とした取り組みは少ない。
III.地方都市における創造産業政策のアプローチ
地方都市の創造産業政策には、大きく分けて3つのアプローチがある。① 文化政策アプローチ(芸術・文化振興によるクリエイターの育成)、② 産業政策アプローチ(ビジネス的側面の支援)、③ 都市政策アプローチ(環境整備、都市マーケティングなど)。それぞれの都市の状況や創造産業への期待に応じて、戦略的に政策を組み合わせる必要がある。札幌市の事例では、メディアコンテンツ産業が発展し、行政によるインキュベーション施設の設置や創造都市宣言などが見られる。
1. 地方都市における創造産業政策の困難と必要性
地方都市において創造産業を育成・振興することは容易ではない。政策による支援を行う際には、創造産業特有の性質を理解することが不可欠となる。地方都市における創造産業政策のあり方は、当該都市の状況や創造産業への期待する役割によって大きく異なる。また、創造産業はサブセクターごとに性質が異なり、全体を包括した議論は難しい面がある。地方都市が創造産業育成・発展のための政策を検討する際には、その都市が保有する資源、日本の都市システムにおける位置づけ、産業状況などを考慮し、戦略的に政策を立案・実行する必要がある。具体的には、創造産業を都市の産業構造においてどう位置付けるか、創造産業を通じてどのような役割を期待するのか、創造産業の中でもどの分野に重点を置くのかを明確にする必要がある。
2. 創造産業政策の3つのアプローチ 文化 産業 都市政策
地方都市における創造産業政策の取り組みは、大きく3つのアプローチに分類できる。A.文化政策アプローチ:芸術や文化の振興を通じて、創造産業の中核をなす部分を発展させると同時に、クリエイターやアーティストの創造性を刺激するアプローチである。B.産業政策アプローチ:創造産業のビジネス的側面、主に経済的な側面を支援するアプローチである。C.都市政策アプローチ:都市政策として、環境やインフラ、公共施設整備、他都市との競争における都市マーケティングなどの取り組みを含むアプローチである。これらのアプローチは、個々の都市の状況や創造産業への期待に応じて、戦略的に組み合わせて実施されるべきである。どのアプローチが適切かは、創造産業のサブセクターによっても異なるため、一概には言えない。
3. 文化的側面と地域文化生産の支援 政策的論点
創造産業政策のあり方については、様々な議論がなされており、政策の存在意義自体も問われている。地域における創造産業の育成・発展のためには、いくつかの基本的な論点を理解する必要がある。第一に、創造産業の文化的側面と産業的側面、そして両者の関係性である。第二に、地域における文化生産をどのように捉え、どのように支援するのかという問題である。創造産業政策は、これらの論点を深く理解し、検討した上で展開されるべきである。 多くの議論が積み重ねられてきたように、創造産業政策のあり方は多角的な視点からの検討が必要となる。特に、地方都市では、創造産業が地域経済の主役になることは期待できず、観光や消費と連携した活性化、シンボリックな効果による地域イメージの向上といった役割が重要となる。
IV.創造産業の文化的側面と地域文化生産の支援
創造産業政策の成功には、創造産業の文化的側面と産業的側面の両方を理解し、両者の連携を促進することが重要である。特に、地域文化の生産をどのように支援するかが課題となる。行政は、人的資本(人材育成)、文化資本(文化活動支援)、環境資本(インフラ整備)への投資を通じて、文化政策を積極的に活用すべきである。しかし、アクター間の相互作用を促進するプラットフォーム(場)の形成も不可欠である。
1. 創造産業の二面性 文化的側面と産業的側面
創造産業は、産業的側面と文化的側面の両面を持つ。文化的側面が創り出す文化的価値から経済的価値を導き出し、商業的な生産を通じて利益を生み出すことで産業として成立する。そのため、政策的に支援を行う際には、この文化的価値をどのように生み出し、育むかが重要な論点となる。 創造産業は、公的に助成を受けた非商業的なアートセクターとは異なり、経済的、商業的、個人的な次元を強調するものである。この産業的側面と文化的側面の融合が、創造産業の経済的成功の鍵となる。単に経済的な側面だけに着目するのではなく、文化的価値の創造と育成に重点を置く政策アプローチが求められる。この文化的価値とは、美学的価値、精神的価値、社会的価値、歴史的価値、象徴的価値など多様な要素から構成される複雑な概念であり、明確な定義は難しいが、その多様な側面を理解することが重要である。
2. 地域文化生産の支援 政策的アプローチの課題
地域において創造産業を育成・発展させるための政策を展開する際には、創造産業の文化的側面と産業的側面、そして両者の関係性を理解することが不可欠である。さらに、地域における文化生産をどのように捉え、支援するのかという問題も、重要な論点となる。地域文化生産を支援する政策のアプローチとしては、人的資本(人材育成)、文化資本(文化活動への支援、文化資源の獲得・蓄積)、環境資本(文化・知識インフラへの投資)への直接的な投資が考えられる。これらの要素は文化政策の基本的なメニューと言える。しかし、創造産業の文化生産は、これらの要素だけでは支えられない。文化生産に関わるアクターは都市中心部で活動することが多く、中心部の環境整備やアクセスの改善も重要となる。また、生活環境や消費環境の整備も、人材の定着に大きく影響する。
3. 文化政策の役割と総合的アプローチ 創造都市の可能性
創造産業の文化生産を支援する上で、文化政策は重要な役割を果たす。文化政策は、人的資本、文化資本、環境資本といった文化生産の構成要素に直接的に働きかける主要な政策手段である。しかし、文化政策だけでは不十分であり、文化生産を取り巻く状況全体を考慮した総合的なアプローチが必要となる。創造都市は、文化政策を中核としながら、文化生産に関わる周辺的要素も考慮した、総合的で体系的な政策スタイルと言える。制度資本や社会関係資本に関しては、行政による直接的な介入は控え、側面的支援に留めるべきとされる。多くの地方都市では、創造産業は地域経済の主役というよりも、観光や消費と連携して地域経済を活性化したり、地域イメージやブランド価値に影響を与える役割が期待されるため、創造都市が目指す都市環境の整備は重要となる。
V.創造都市と地域文化生産のプラットフォーム
創造都市は、地域文化生産を促進する重要な枠組みである。創造産業に関わるアクター(クリエイター、企業、コミュニティ)間の密接な相互作用を促すプラットフォーム(場)の形成が重要となる。札幌市の事例では、北海道マイクロコンピュータ研究会、青木塾、ネットワーク・コミュニティ・フォーラムなどが、創造産業発展の重要なコミュニティとして機能し、プラットフォームとしての役割を果たしてきた。行政は、場所・空間、プロジェクト・イベントなどを支援することで、プラットフォーム形成を支援すべきである。
1. 地域文化生産を支える社会的文脈 コミュニティの役割
地域における創造的活動を支える社会的文脈として、コミュニティの役割が重要視される。コミュニティは、地域社会の重要な構成要素であり、文化生産を支えるアクター間の関係を形成する枠組み、いわばプラットフォームとしての機能を持つ。実践的コミュニティ、認知的コミュニティ、専門家コミュニティなど、様々なタイプのコミュニティが存在し、それぞれが独自の役割を果たす。知のコミュニティにおいて創造・コード化された知識は、企業などに供給され商品化される。コミュニティは、知の創造を担う人材と企業を繋ぐ役割を担う。また、創造産業の文化的側面を担い、知識や創造的技術・様式の蓄積、共通する知識・文化形成の基盤を形成する役割も担う。
2. 文化生産のプラットフォームとしての 場 形成と機能
地域における文化生産を促進するためには、様々なアクターが相互作用し、文化生産を支える状況を創り出す枠組み、つまりプラットフォームとしての「場」の形成が不可欠である。単なるネットワークではなく、アクター間の中連結によって成り立つ「場」は、コンテクストの共有度が高く、目的が明確で、連帯感情を伴う密な相互作用が特徴である。伊丹の議論では、「場」の成立要件として、アジェンダ、解釈コード、情報キャリアー、連帯欲求の4つを挙げている。これらの要件を満たす「場」では、共通理解に基づく心理的共振や心理的エネルギーが生まれやすく、協調的・協力的行動が生み出される。創造産業のサブセクターや文化の領域・ジャンルに応じて複数の「場」が形成され、それらが有機的に繋がることで、相互刺激や文化創造への影響が期待できる。札幌の事例では、複数の場が形成されネットワーク化し、プラットフォームとして機能している。
3. 場の形成を支える道具立て 場所 空間 プロジェクト イベント
文化生産のプラットフォームとしての「場」を創り出し、支えるための道具立てとして、場所・空間とプロジェクト・イベントが挙げられる。創造的な活動の拠点となる施設(練習場、スタジオなど)や、アクターが集まり交流する空間(カフェ、レストラン、ギャラリーなど)は、情報取得、意見交換、新たなアイデア創出の場となるだけでなく、アクター間の密接な関係醸成にも貢献する。プロジェクトやイベントは、一時的・暫定的な場を生み出すが、共同の価値実現を目指した協力・協働を通じて、アクター間には単なる結びつきを超えた関係が形成される。行政は、コミュニティやアクター間の関係形成を直接支援するのではなく、場所・空間、プロジェクト・イベントなどを支援することで、間接的に「場」の形成を促進する役割を担う。札幌市のネットワーク・プラザや札幌駅前通地下歩行空間などは、この役割を担う事例と言える。
VI.札幌市の創造産業政策と創造都市戦略
札幌市は、メディア・アーツを重点とした創造都市戦略を進めている。知的クラスター創成事業への選定や、札幌デジタル創造プラザ(インタークロス・クリエイティブ・センター)の設立、札幌国際芸術祭の開催など、多様な政策が展開されている。これらの取り組みは、創造産業の活性化、人材育成、都市イメージ向上に貢献していると考えられる。しかし、政策効果の総合的な評価はまだ今後の課題である。
1. 札幌における創造産業の発展 コミュニティとプラットフォームの形成
札幌市の創造産業は、北海道マイクロコンピュータ研究会、青木塾、ネットワーク・コミュニティ・フォーラムなどのコミュニティ活動から発展してきた。これらのコミュニティは、デジタル技術に関するユーザー文化の醸成に大きく貢献し、相互扶助を通じて新たなソフトウェアやコンテンツの開発・制作を促進してきた。特に、クリプトン・フューチャー・メディアによる音楽制作支援ソフト「初音ミク」の誕生は、札幌のクリエイティブ経済を牽引する大きな要因となった。これらのコミュニティは、アクター間の関係形成の場となるだけでなく、新たなコミュニティを生み出す場としても機能してきた。行政によるネットワーク・プラザの開設も、これらのコミュニティ活動を支える役割を果たした。
2. 札幌市の創造産業支援政策 インキュベーションと都市ブランディング
札幌市は、創造産業の育成・支援のため、様々な政策を展開している。2001年には、インキュベーションやネットワーク構築を支援する札幌デジタル創造プラザ(後にインタークロス・クリエイティブ・センターへ発展)を開設した。2002年には、文部科学省の知的クラスター創成事業に選定され、デジタルコンテンツ産業の育成に力を入れている。シリコンバレーになぞらえた「札幌バレー」という地域ブランディングも展開されている。これらの政策は、クリエイターの活動を総合的に支援することを目的としており、下請け的な存在から企画・デザイン企業への転換を促進する役割を担っている。
3. 札幌市の創造都市戦略 ユネスコ創造都市ネットワーク加盟と具体的な取り組み
2006年の上田市長による「創造都市さっぽろ」宣言以降、札幌市は創造都市戦略を本格的に推進している。2008年にはクリエイティブ・コモンズに関する国際会議を開催し、2009年には創造都市さっぽろ推進会議が提言書を作成、ユネスコ創造都市ネットワーク加盟を目指した取り組みを開始した。2010年の文化庁メディア芸術祭札幌巡回展を経て、メディア・アーツ都市を目指し、2012年には国内の創造都市ネットワーク日本に、2013年にはユネスコ創造都市ネットワークにメディア・アーツ都市として加盟が承認された。具体的な取り組みとして、札幌国際短編映画祭、札幌駅前通地下歩行空間の公共メディア空間化、札幌メディア・アーツ・ラボの設立、札幌国際芸術祭などが挙げられる。札幌国際芸術祭では、文化芸術によるライフスタイル創出、人材育成、都市魅力向上などが目的とされている。
