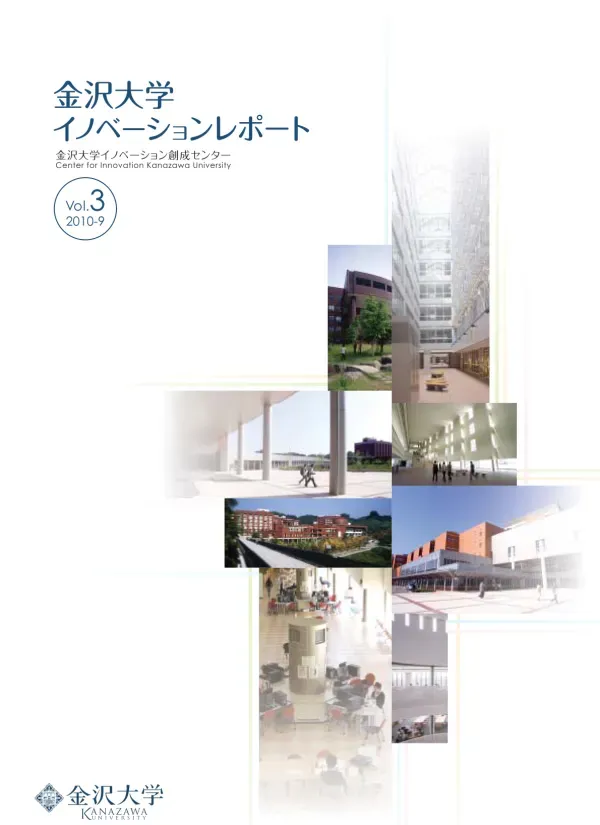
地域活性化と知的財産戦略
文書情報
| 著者 | 吉國信雄 |
| 学校 | 金沢大学イノベーション創成センター |
| 専攻 | 産学官連携 |
| 文書タイプ | パンフレット/報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.90 MB |
概要
I.産学官連携による地域活性化 根本的な問いと課題
本資料は、産学官連携による地域活性化の有効性に関する根本的な疑問から始まります。地域は疲弊しているにも関わらず、成果報告が多い現状に課題を感じ、知的財産の活用、イノベーション創出による地域活性化の具体的な方策を探っています。特に、過疎高齢化対策としての知財戦略、地域企業間の特許プールシステム構築、地域ブランド価値向上のための対策などが重要課題として挙げられています。これらを通して、地域特有の資源と技術を結びつけ、持続可能な地域経済の構築を目指します。
1. 産学官連携の効果に関する根本的な疑問
国立大学法人共同研究センター長等会議での発言を契機に、産学官連携活動の成果報告が多い一方で、地域経済の疲弊が続いているという現実が提起されています。この発言は、産学官連携活動が本当に地域の活性化に貢献しているのかという根本的な疑問を投げかけており、これが本稿の出発点となっています。多くの報告書では成功事例が強調されていますが、具体的な地域への波及効果や、住民が実感できる変化が不足しているという問題意識が背景にあります。 この疑問は、単なる成果主義的な報告ではなく、地域住民の生活水準向上や雇用創出といった具体的な効果を検証する必要があることを示唆しています。 産学官連携の取り組みが、単なる研究成果の発表や論文の出版に留まらず、地域社会に具体的な経済的・社会的利益をもたらすための戦略的な見直しが必要であるという強い問題意識が、この節全体を貫いています。
2. 知的財産を活用した地域活性化戦略の提案
地域活性化に向けた具体的な方策として、知的財産の戦略的な活用が提案されています。 具体的には、過疎高齢化問題への対応として、実施許諾の条件に金銭ではなく、地域での研修や標準化・認証システムへの参加を盛り込むことで、地域への人材育成と技術移転を促進する戦略が挙げられています。これは、単なる金銭的な利益だけでなく、地域社会への貢献を重視した新しい知的財産活用モデルと言えるでしょう。さらに、地域企業を巻き込んだプロジェクトでは、特許を共有する仕組み(地域活性化特許プールシステム)の構築が提案され、多様な分野の企業が互いに特許を活用することで、イノベーション創出と地域経済の活性化を図ることを目指しています。 地域ブランドの保護についても言及されており、グローバル化の中で、地理的表示(Geographical Indication)のような強い保護制度がない場合でも、標準化や認証システム、トレーサビリティの活用によって、地域ブランドの価値を守り、強化していくための戦略が模索されています。これらの提案は、知的財産を単なる収益源ではなく、地域社会の活性化のための重要な資源として捉えている点に特徴があります。
3. 地域ブランド価値の維持 向上と持続可能な地域経済
地域ブランドの希釈化への対策が重要な課題として取り上げられています。グローバル化の進展により、地域ブランドの保護がますます重要になっており、ワインやスピリッツのように地理的表示による絶対的な保護が難しい場合でも、その地域独自の資源と結びつき、品質を保証する仕組みの構築が求められています。この仕組みを通じて、その地域でなければ習得できない技術やノウハウを生み出すことが、究極の目標として提示されています。 これは、地域経済の持続可能性を確保するための戦略的な取り組みであり、地域独自の資源や技術を活かすことで、外部からの競争に打ち勝つための差別化を図ることを目指しています。単なる製品の生産・販売だけでなく、地域独自の技術や文化を継承・発展させるための仕組みづくりが、地域ブランドの維持・向上、ひいては地域経済の活性化に不可欠であるという認識が示されています。
II.金沢大学イノベーション創成センターの役割
金沢大学イノベーション創成センターは、産学官連携の中核組織として、将来開拓、連携研究推進、知的財産、起業支援の4部門から構成されています。技術移転促進、イノベーション創出支援、ベンチャー企業育成、特許出願促進など、多様な活動を展開しています。平成22年度には特許出願70件を目標に掲げており、技術アドバイスサービスも提供しています。センターは文部科学省の「大学等産学官連携自立化促進プログラム」も推進しています。
1. イノベーション創成センターの設立と目的
金沢大学イノベーション創成センターは、平成20年4月1日に、それまでの共同研究センター、知的財産本部、インキュベーション施設、ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーを統合して設立されました。センターの目的は、イノベーション創成による社会貢献を重視し、産学官連携・知的財産活動を推進することで、研究成果の社会還元と教育研究の活性化を図ることです。 平成19年度までの組織を統合し、将来開拓部門、連携研究推進部門、知的財産部門、起業支援部門の4部門体制を構築することで、イノベーション創出と成長を有機的に連携させる体制を整えています。文部科学省の「大学等産学官連携自立化促進プログラム(機能強化支援型)」も推進しており、各部門を横断的にサポートする体制が整備されています。センター設立の背景には、研究成果を社会に還元し、大学における研究活動を活性化させるという強い意志が読み取れます。
2. 各部門の役割と具体的な活動
イノベーション創成センターは4つの部門で構成され、それぞれが異なる役割を担っています。将来開拓部門はイノベーション創出のプランと体制構築、連携研究推進部門は企業からの技術相談や共同研究の受付けと研究者の紹介、知的財産部門は大学の知財戦略の企画立案と知財の発掘・活用、起業支援部門は学生や若手研究者の起業家精神育成とベンチャー支援を行っています。連携研究推進部門では、北陸地域内外問わず様々な業種の企業から年間多くの技術相談や共同研究を受け付けており、1000名以上の教員・研究者の中から適任者を紹介します。知的財産部門では、ロイヤリティ収入ではなく、研究成果の社会での最大限活用を目指しており、企業との連携強化に力を入れています。平成22年度には特許出願70件(平成21年度実績:59件)を目標に掲げており、積極的な知的財産権の取得を目指しています。起業支援部門では、アントレプレナーシップ教育やベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(VBL)の運営などを通して、起業を支援しています。
3. 産学連携支援体制と今後の展望
センターでは、産学連携研究助成金等の競争的研究資金応募への支援も行っています。部門担当教員は、アカデミック研究と企業研究所での経験を持つ専属の産学官連携コーディネーターとチームを組み、産学双方の立場を理解した支援を提供しています。 また、イノベーション創成センター協力会を設立し、金沢大学と地域産業界との連携を強化することで、地域社会に貢献する活動を進めています。 将来開拓部門は、シンクタンク機能を最大限に活用し、技術的要因だけでなく社会的阻害要因にも対応することで、イノベーションの創出を目指しています。 大学が持つ多様な分野の研究者を活用することで、社会システム、産業構造、ライフスタイル等の転換に貢献できる可能性を示唆しています。 これらの活動を通して、金沢大学イノベーション創成センターは、地域社会の活性化に貢献することを目指しています。
III.産学連携の成功事例と課題 医薬 バイオ分野と地域産業
金沢大学では、製薬企業、繊維企業、電子機器製造企業などとの産学連携が盛んで、MRI造影剤「リゾビスト」の世界的な成功事例があります。一方、地域活性化のためには、既存のニーズとシーズのマッチングだけでなく、未存在シーズと将来ニーズのマッチングに向けた取り組みが重要です。七尾市での農商工連携事業(親子食育講座、七尾食育カードゲーム「ななショック」)は、地域資源を活用した地域活性化の成功事例の一つと言えるでしょう。
1. 医薬 バイオ分野における産学連携の成功事例
金沢大学における産学連携の成功事例として、MRI造影剤「リゾビスト」の開発と世界的な販売が挙げられています。これは、製薬企業との共同研究による成果であり、医薬・バイオ分野における産学連携の有効性を示す好例となっています。 さらに、石川県内外の繊維企業、電子機器製造企業、文具メーカー、自動車メーカーなど、多様な企業との共同研究も盛んに行われており、幅広い分野で産学連携が推進されていることがわかります。 これらの成功事例は、大学が持つ研究力と企業の事業化ノウハウが連携することで、大きな経済的価値を生み出す可能性を示しています。 また、これらの成功体験は、大学における産学連携活動を促進し、さらなるイノベーション創出への期待を高める要因となっています。
2. 地域産業活性化に向けた産学連携の課題と展望
既存のニーズとシーズのマッチングに加え、未存在シーズと将来ニーズのマッチングに向けた取り組みが必要であると指摘されています。これは、従来型の産学連携にとどまらず、より未来を見据えた研究開発と事業化が求められていることを示唆しています。複数の企業と連携し、将来的なニーズに対応できるような研究開発を進める必要性が強調されています。 七尾市での農商工連携事業の一環として行われた「親子食育講座」と「七尾食育カードゲーム『ななショック』」は、地域資源を活用した新たな食文化の形成を目的とした取り組みであり、地域活性化のための産学連携の具体的な事例として紹介されています。 しかし、これらの事例はあくまで成功例の一部であり、地域全体の活性化を図るためには、より多くの企業との連携、そして、地域特性を活かした多様な産学連携モデルの構築が課題として残されています。 単なる研究成果の創出だけでなく、地域社会への貢献を重視した、より包括的な産学連携の推進が求められています。
IV.グローバル化時代における知財戦略と大学における役割
グローバル競争が激化する中、知的財産権は国際的な共通ルールとなりつつあり、大学は技術移転を積極的に推進する必要があります。金沢大学は、海外への技術移転や国際的な産学官連携を促進し、イノベーションの成果を世界に発信する必要があります。スタンフォード大学のOTLを参考に、知的財産を効果的に活用し、大学の自立性を高める戦略が求められます。 KUTLO (金沢大学技術移転機構)の活動強化も重要です。
1. 知的財産権の国際的な重要性と大学の役割
グローバル化が加速する中、従来のコスト、品質、納期といった競争優位性は急速に低下しています。しかし、知的財産権は国境や思想信条を超えた、侵すことのできない明白なパラダイムとなっており、国際的な共通ルールになりつつあります。そのため、知的財産権の戦略的な活用が、企業の国際競争力強化に不可欠となっています。大学は、単に国内市場だけを対象とするのではなく、世界市場に向けて知的財産を活用し、産業界の国際競争力強化に貢献する役割を担うべきであると指摘されています。既に海外での研究経験を持つ教授や海外学会での発表実績を持つ教授も存在するなど、国際的な活動へのハードルは低いとされています。 大学は、その知恵を世界規模で活用し、国際的な産学連携を積極的に進めることで、グローバルなイノベーション創出に貢献することが期待されています。
2. 知財経営と大学における新たなビジネスモデルの提案
知的財産経営を目指す企業に対し、知的財産の意識啓蒙や、具体的な活用戦略を提示し、企業と共に歩むことが重要だと述べられています。大学は、顧客企業と共に世界の産業発展に貢献する活動を行うことで、自立した事業部門(事業部のようなもの)を構築できる可能性が示唆されています。この部門は、研究・試験・提案・相談をベースに企業の利益を増大させ、その利益を企業と共有することで運営されるという、新たなビジネスモデルの提案がなされています。 スタンフォード大学のOTL(Office of Technology Licensing)の事例が紹介されており、バイ・ドール法以来30年間のライセンス活動で10億ドル以上のライセンス収入を得たものの、初期15年間はほとんど収入がなかったという経験が紹介されています。これは、大学における知的財産活用が、短期間での成果を期待できるものではなく、長期的視点での取り組みが必要であることを示唆しています。
3. 金沢大学の知財戦略と国際展開への展望
金沢大学には数多くの優れた発明があり、それらを世界の人々に役立てることが目標とされています。そのため、海外出張を積極的に行い、KUTLO(金沢大学技術移転機構)の若手人材育成にも力を入れる計画です。 KUTLOは、金沢大学における技術移転を促進する組織として設立され、これまで数々のライセンス契約実績を上げていますが、本格的なスピードアップが必要な段階にあるとされています。 さらに、青森から京都までの日本海地域11大学に所属する2600名のライフサイエンス研究者の発明の実用化に向けて技術移転を進める基盤(KUTLO-NITT)も構築されており、多くの優れた研究成果が実用化に繋がる可能性に期待が寄せられています。 これらの取り組みを通して、金沢大学は、知的財産を国際的な舞台で活用し、世界の産業発展に貢献していくことを目指しています。
V.地域行政と産学官連携 金沢市の取り組み
金沢市は、「独創性と多様性に富んだものづくり産業の振興」を重点施策に掲げており、産学官連携を重視しています。市役所は、企業誘致、雇用対策、商店街活性化、健康サービス産業育成などに力を入れており、産学官連携による地域活性化を推進しています。具体的には、中小企業への支援やベンチャー企業育成などが挙げられます。
1. 金沢市の重点施策と産学官連携の役割
金沢市は、「独創性と多様性に富んだものづくり産業の振興」を重点施策に掲げており、その中で産学官連携が重要な役割を果たすと考えています。 金沢大学と地元企業との橋渡し役として、市は積極的に産学官連携を促進し、地域の産業活性化に貢献しようとしています。 この取り組みは、金沢大学の研究開発力と地元企業の製造力、そして市による政策的支援を融合させることで、地域経済の活性化を目指しています。 市は、金沢大学との連携を強化することで、地域特有の資源や技術を活かした新しい産業の創出、そして雇用創出に繋げようとしています。 そのため、金沢大学と地元企業の双方に対するサポート体制の整備も重要視されています。
2. 金沢市における産学官連携の具体的な取り組み
産学官地域アドバイザーの視点から、企業誘致や雇用対策、商店街活性化、健康サービス産業育成といった具体的な取り組みが紹介されています。 特に、中小企業への支援が強調されており、独自技術開発や新製品開発に積極的に取り組む中小企業の存在が指摘されています。 市役所では、中心市街地活性化対策などの商業施策に加え、企業誘致や雇用対策にも力を入れており、地域経済の活性化を多角的に推進しています。 内科・小児科の急病センター設置による市民の安心確保と子育て支援、ジョブカフェ・サテライトの誘致による若者就職支援と商店街活性化、健康サービス産業育成による市民の健康寿命の伸長と温泉街活性化などが、具体的な政策として挙げられています。これらの取り組みは、地域住民の生活水準向上と地域経済の活性化を両立させることを目指しています。
