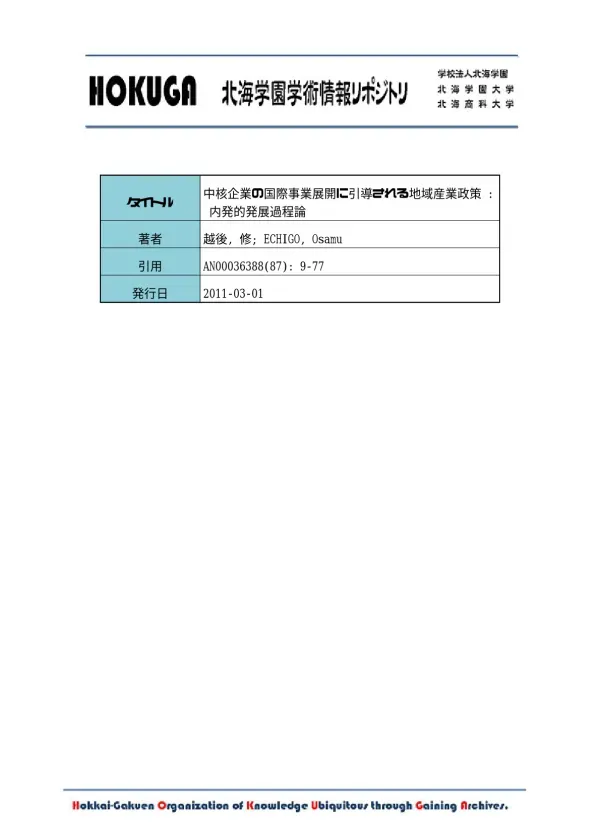
地域産業政策:内発的発展と中核企業
文書情報
| 著者 | 越後 修 |
| 学校 | 不明 |
| 専攻 | 経済学関連 |
| 出版年 | 2010年頃(推定) |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 論文(推定) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.82 MB |
概要
I.日本の地域経済と産業構造 関東 東海地方と地方格差
日本経済の低迷期において、関東・東海地方とそれ以外の地方との間に大きな経済格差が存在する。GDP成長率や家計最終消費支出の伸びにその差が顕著に表れており、関東・東海地方は安定した成長を維持する一方、その他の地方は不安定な状況にある。この格差是正と地域経済活性化が喫緊の課題となっている。
1. 日本経済の低迷と地域間の格差
本文は、日本経済全体の低迷期における地域経済の状況分析から始まります。特に、どの地域が厳しい状況にあり、逆にどの地域が活況を呈しているのかを明らかにするため、GDPの変化率に着目しています。分析の結果、関東・東海地方とその他の地方との間に大きな経済格差が存在することが示唆されています。第1図を参照することで、このGDP成長率における地域間格差を視覚的に確認できます。 さらに、GDPのおよそ半分を占め、経済に大きな影響を与える家計最終消費支出の伸び率にも注目しています。関東・東海地方の家計最終消費支出は、2001年度の小泉政権発足以降の不良債権処理や公共事業削減、ITバブル崩壊による輸出減少の影響で一時的に大きく減少しましたが、その後は安定した伸びを維持しています。一方、その他の地方は2007年度には上昇したものの、不安定感を拭えない状況にあると指摘されており、第2図がその状況を裏付けています。この地域間格差は、単なるGDPの差だけでなく、家計消費という国民経済の根幹をなす部分にも影響が及んでいることを示しており、日本経済全体の活性化を考える上で重要な問題提起となっています。 この序論部分では、地域経済の現状を端的に示すことで、続く地域経済活性化策に関する議論への導入となっています。
2. 関東 東海地方の経済状況の詳細分析
関東・東海地方の経済的強さを裏付ける具体的なデータや要因が提示されていません。しかし、2001年度の大きな下落の後、安定した伸びを維持しているという記述から、関東・東海地方が比較的強い経済基盤と回復力を持っていることが推測されます。この安定した経済成長は、他の地域と比較した際、相対的に優位な立場にあることを示唆しています。 この記述は、続く章で論じられる地域経済発展モデルの選定において、関東・東海地方が対照群として機能する事を示唆しています。つまり、他の地域が抱える経済的課題を克服する上で、関東・東海地方の成功要因やその持続可能性を分析することが、地域経済活性化政策にとって重要であることを示唆しています。 より詳細な分析、例えば、具体的な産業構造の違いや政策の効果、人口動態などの要素を分析することで、関東・東海地方の経済的強さの根拠をより明確にできる可能性があります。しかし、このセクションでは、主に地域間格差の現状を示すことに焦点が当てられています。
3. 地方経済の課題と持続可能な発展への展望
関東・東海地方以外の地域が抱える課題として、「過剰労働力の吸収」「人口流出の防止」「所得の増大」が挙げられています。これらの課題への従来の解決策として、域外からの企業誘致が盛んに行われてきましたが、その結果生まれた分工場経済の問題点も指摘されています。 具体的には、オイルショック以降のコストダウン競争の激化、アジア新興国の台頭による生産拠点の競争力低下、国内市場の縮小などが挙げられ、これらの要因によって、地方は国内市場への供給拠点、海外市場への供給拠点のいずれとしても、競争力を失いつつあると分析しています。 こうした現状を踏まえ、本文では、域外企業に依存する外発型発展ではなく、地域資源を活かした内発的発展の重要性が強調されています。これは、単に企業誘致に頼るのではなく、地域独自の資源や強みを活かし、持続可能な発展を目指す必要があるという主張です。 このセクションは、日本における地域経済発展政策の転換点とその必要性を示唆しており、続く章で論じられる地域活性化戦略の土台となっています。地方経済の自立と持続可能な成長という重要なテーマを提起しています。
II.地域発展モデル 内発的発展と外発型発展の克服
従来の外発型発展(域外企業誘致)は、分工場経済の問題(コストダウン競争の激化、アジア諸国との競争、国内市場の縮小)を引き起こし、持続可能性に欠ける。そのため、地域資源を活かした内発的発展が重要となる。新成長戦略も、地域資源の最大限活用を目標に掲げている。
1. 外発型発展の限界 域外企業誘致の功罪
これまで日本の地域経済における発展モデルは、主に域外からの企業誘致、つまり外発型発展に依存してきました。過剰労働力の吸収、人口流出の防止、所得の増大といった地域課題の解決策として、昭和30~40年代の大手電機メーカーの地方移転や、50年代後半以降のテクノポリス構想による企業誘致などが行われてきました。しかし、これらの政策は、必ずしも成功したとは言えず、むしろ問題点を生み出している側面があると指摘されています。 オイルショック以降、コストダウンを求める企業にとって日本の地方は魅力的な立地先でしたが、アジアの新興国の台頭によって、その優位性は失われつつあります。低価格競争の激化により、地方は国内市場への供給拠点としての合理性を失い、海外市場向け供給拠点としても、現地需要の拡大によって非合理的になりつつあります。有力企業は国際事業展開が一般的であり、外様企業に依存した地域経済の安定化は困難さを増しています。 このように、外発型発展は短期的には効果が見込めますが、長期的な視点で見ると、地域経済の自立性を阻害し、持続可能な発展を妨げる可能性があることが示唆されています。この点は、次の内発的発展論へと繋がる重要な論点となっています。
2. 内発的発展論 地域資源を活用した持続可能な発展
外発型発展への批判として、地域資源をベースとした持続的な地域発展を目指す「内発的発展論(endogenous development theory)」が提示されています。この理論は、域外企業に依存するのではなく、各地域が持つ固有の資源(自然資源、伝統、文化、芸術など)を最大限に活用することで、持続可能な発展を実現できると主張しています。 2020年までの目標として「地域資源を最大限活用した地域力の向上」を掲げる新成長戦略も、この内発的発展論と整合性を持ちます。過去の地域産業政策の失敗や国際競争の激化を踏まえ、今後の産業構造ビジョンを構築する上で、「地域の主体性の所有」と「模倣困難性の高い地域資源の利用」が重要であると指摘しています。 政策立案においては、域内企業と域外企業のどちらを主体とするかが重要な課題となります。テクノポリス構想の反省を踏まえ、日本立地センターの報告書(1990)では、「地場企業の技術高度化」と「外部からの先端技術産業の導入」の二本柱が提唱されていますが、本文では、外発型発展と内発的発展の動的な統合を目指した「動的折衷論」の必要性が強調されています。
3. 内発的発展のための戦略 地域特殊的な知的資源の活用
内発的発展を実現するための具体的な戦略として、地域特殊的な知的資源の活用が提案されています。地域が周辺国・地域との持続的な差別化を図るためには、イノベーションを他国・地域に先行することが重要であり、そのためには地域が独自の知的資産を創造・活用する仕組みが必要です。 地域が直面する最大の課題は雇用の改善であり、そのためには、人材育成が不可欠です。単なる労働力ではなく、経済・社会環境が求める「人財」の育成と、彼らが活躍できる地場企業の育成が求められます。関東・東海地方における工場立地の増加は、この点を示唆する事例として挙げられています。 地域経済の再生には、「地域特殊的な知的資源」、「知的資産を創造する仕組み」、「価値創造活動に用いる仕組み」の3点が重要であると強調されており、これらの要素を効果的に組み合わせることで、持続可能な地域発展が実現すると論じています。この議論は、続く章における具体的な地域活性化事例の分析につながっています。
III.自動車産業における世界最適生産と地域経済
近年、日本の自動車産業では、世界最適生産の追求が進み、海外生産比率の増加と逆輸入車の増加が見られる。円高も影響し、国内生産拠点の存亡が危ぶまれる状況にある。特に、完成車メーカーはタイなどの新興国を生産拠点とし、コスト競争力を強化している。トヨタ、日産、ホンダなど主要メーカーの生産体制見直し計画が示唆されている。東北地方と北部九州地方は自動車産業を誘致してきたが、新たな政策が必要とされている。 ホンダは2002年末にタイ生産のフィット・アリアを逆輸入開始、トヨタは2003年秋に英国からアベンシスを輸入するなど、世界戦略車への転換が顕著になっている。
1. 世界最適生産の追求 日本の自動車産業の現状
日本の自動車産業は、かつて技術力と高い貿易障壁を背景に国内生産拠点の地位を確固たるものとしてきました。しかし、近年は「世界最適生産」の追求が加速し、状況が一変しています。自動車は多数の部品から構成され、サプライヤーへの外注率が高いことから、地域経済への波及効果が大きい産業とされてきましたが、この優位性は揺らぎ始めています。 1985年以降の生産台数の推移(第6図)を見ると、バブル崩壊後、国内生産は減少傾向に転じましたが、2001年を底に回復し、2007年までは海外需要の旺盛さによって増加を続けました。しかし、総務省の調査(2009年)では、世帯当たりの自動車保有台数が初めて減少したことが示され、国内市場の縮小が明らかになっています。これは、国内景気の減速による雇用不安・所得減、少子高齢化、そして若者のクルマ離れなどが要因として挙げられます(第7図、第8図)。 こうした国内市場の縮小と、世界的な競争激化によって、日本の自動車メーカーは「世界最適生産」を追求し、生産拠点を海外に移転する傾向が強まっています。この変化は、単にコスト削減だけでなく、グローバルな需要の変化への対応という戦略的な側面も持ち合わせています。
2. 逆輸入車の増加と国内生産拠点の危機
1980年代後半以降、日本の自動車メーカーは海外拠点で生産した完成車を国内市場で販売し始めました。これは、米国との貿易摩擦緩和の狙いもありましたが、メーカー側にとっても現地生産・逆輸入が戦略的に有利であったためです。ホンダが1982年に米国でアコードの生産を開始し、1987年には米国市場専用車種の日本市場への逆輸入を検討すると表明したことが、その端緒となります。 21世紀に入ってからは、逆輸入の理由に大きな変化が見られます。コスト削減だけでなく、「世界最適生産」の追求という視点が加わったのです。ホンダのフィット・アリア(タイ生産、2002年末)、トヨタのアベンシス(英国生産、2003年秋)、三菱自工のトライトン(タイ生産、逆輸出)などの事例が示されています。 2010年7月には、日産がタイで生産したマーチを逆輸入開始しました。これは、国内市場の縮小と世界戦略車への転換、新興国活用による価格競争力強化という明確な戦略に基づくものであり、主力車生産の脱国境化を象徴する事例として注目されています。この世界戦略車への転換は、価格競争力を維持するために現地調達率の向上を必要としますが、品質重視の日本市場向け生産拠点の選定には、コストと品質のバランスが重要な課題となります。
3. 国内生産拠点の将来と地域経済への影響
円高の進行と海外市場のメイン化は、日本の自動車産業における国内生産拠点の存亡をさらに脅かしています。メーカー各社は海外向け設備投資を増やし、国内向け投資を減らす計画を発表しており、トヨタ、日産、ホンダなど主要メーカーは国内生産能力の縮小を検討しています。トヨタは「日本からモノづくりをなくしてはいけない」という考え方を持ちつつも、円高による営業利益への悪影響を懸念し、国内生産体制の見直しを迫られています。 ホンダは2009年に国内生産台数が14年ぶりに100万台を割り込みましたが、2010年末には100万台水準の維持を目指す方針を示しています。その戦略として、輸入部品の積極的利用が挙げられ、2013年をメドに部品調達先を半減、調達地域を日米欧から新興国へシフトする計画です。 しかし、海外市場向け生産比率の増加と逆輸入車の増加は、国内事業拠点の存亡を危うくしています。北部九州や東北地方など、自動車産業を誘致した地域は、この厳しい状況下で、地域経済の活性化、雇用維持、そして持続可能な発展に向けた新たな戦略を模索し、実行していく必要性に迫られています。この課題が、後の章で詳しく論じられる地域活性化策へとつながっています。
IV.地域活性化のための戦略 人材育成と高度技術の確保
地域経済の再生には、地域特殊的な知的資源の活用が不可欠である。特に、自動車産業では、カーエレクトロニクス関連技術者などの高度技術者の育成が重要となる。北部九州と東北地方では、金型産業の育成、組込み技術の高度化、CAD/CAM/CAE技術者の育成など、地域独自の戦略が展開されている。 具体的には、大分県立工科短期大学校、九州工業大学、岩手大学などの高等教育機関が人材育成の中核を担い、北部九州地域高度金型中核人材育成事業、カーエレクトロニクス設計開発中核人材育成事業などが実施されている。 また、宮城県では、セントラル自動車岩手第2工場の建設など、新たな雇用創出の取り組みが進んでいる。水素技術をベースとした次世代自動車開発拠点形成(福岡県)も期待されている。
1. 地域経済再生の鍵 地域特殊的な知的資源の活用
地域経済の再生には、地域が独自に持つ知的資源の活用が不可欠です。 単に外部からの企業誘致に頼るのではなく、地域固有の資源や技術を活かした産業育成こそが、真の活性化につながると論じています。 具体的には、「地域特殊的な知的資源」「それらを効果的に活用する仕組み」「価値創造活動に用いる仕組み」の3点が重要視されています。これらの要素が有機的に連携することで、国内事業拠点のポジション変化にも対応できる、独自の知的資産が創造され、持続可能な地域経済を実現できると考えられています。 第3図、第4図は、この考え方を視覚的に説明しているものと思われます。 この考え方は、単なる経済効果だけでなく、雇用の改善、つまりミクロレベルでの豊かさの実現という、地域住民の生活水準向上という観点からも重要であると述べられています。そのためには、地域住民自身が地域優位性の源泉となる「人財」となり、地域特殊的な技術の向上と地場企業の層厚化が不可欠です。
2. 北部九州と東北地方の事例 自動車産業を中心とした地域戦略
北部九州と東北地方を事例に、地域活性化のための具体的な取り組みが紹介されています。両地域は、自動車産業を地域経済の屋台骨として期待し、誘致してきました(第1表)。しかし、周辺国・地域での完成車工場の操業が活発化する中、新たな政策の立案・実行が急務となっています。 両地域は、中核企業の事業活動だけでなく、次世代自動車関連のR&D拠点化を目指し、海外需要を取り込むことで地域資産へのニーズを独自に増やそうとしています。具体的には、高付加価値部品の輸出、R&D成果の特許取得とライセンスビジネス、先進的知的資産を活用した海外企業誘致などが戦略として挙げられています。 これらの取り組みは、外資系企業への依存を軽減し、内発的発展を深化させる試みと言えるでしょう。 地域経済の活性化を図る上で、中核企業の事業活動に頼るだけでなく、地域独自の強みを活かした多様な戦略が必要であることを示唆しています。
3. 人材育成と高度技術の確保 具体的な取り組み
地域活性化戦略の中核として、人材育成と高度技術の確保が重要視されています。特に、自動車産業関連では、カーエレクトロニクス関連技術者や金型産業従事者など高度な専門性の高い人材育成が不可欠です。 北部九州では、「北部九州地域高度金型中核人材育成事業」が経済産業省の支援の下、九州工業大学を中心に展開されています。「先端金型センター」が中核拠点となり、高度な金型技術を持つ人材育成に力を入れています。東北地方では、岩手県が「岩手県自動車関連産業成長戦略」を策定し、2015年までに完成車生産規模を100万台とする目標を掲げています。 また、宮城県では、セントラル自動車の進出を契機に、カーエレクトロニクス関連技術者育成センターを設立し、3次元CAD(CATIA)などの最先端IT技術を習得できる人材育成に注力しています。石巻専修大学も自動車技術教育で大きな役割を担っています。岩手県では、「いわて組込み技術研究会」、「いわて組込みシステムコンソーシアム」などが設立され、組込み技術の高度化に取り組んでいます。 これらの事例は、地域独自の資源や強みを活かし、人材育成と高度技術の確保を通じて、地域経済の活性化を目指していることを示しています。大分県立工科短期大学校におけるダイハツ九州進出に伴う人材育成もその一例です。
V.既存理論へのインプリケーションと今後の展望
本研究は、内発的発展論の限界を指摘し、外発型発展と内発的発展の動的な統合を提唱する。ポーターのダイヤモンドモデルを参考に、地域独自の競争優位性を構築するための戦略を提示する。日本の地域政策における目標(雇用状況の改善)と、ポーターモデルにおける目標(貿易収支改善)の違いを考慮する必要がある。地域固有の技術・資源と人材を組み合わせ、海外市場への対応、特許取得によるライセンスビジネス展開、高付加価値部品の輸出などを戦略として推進していく必要がある。 ハイパー・メリトクラシー社会において、地域社会のオルガナイザーとしての行政の役割も重要である。
1. 内発的発展論への示唆 成功条件の明確化
このセクションでは、これまでの議論を踏まえ、内発的発展論に対する示唆をまとめています。内発的発展論は、外発型発展との二者択一を前提とし、外発型発展からの反省に基づいて内発的発展への転換を提唱していますが、「その実現・成功条件」については明確に示されていません。 外発型発展がもたらす情報流入を内発的発展の成功条件の一つと捉えることも考えられますが、それでは論理的整合性に欠けます。なぜなら、情報流入が大きすぎると、内発的発展論が問題視する「同質化」が進み、他地域との差別化が困難になるからです。 従って、内発的発展論は、単に内発的発展モデルへの移行を提唱するだけでなく、その実現条件、特に地域固有の特性を維持しつつ外部からの有益な情報を取り込むメカニズムを明確にする必要があると指摘されています。 この部分は、地域活性化戦略の策定において、地域固有の資源や能力をどのように活かし、外部との連携をどのように構築するべきかという重要な示唆を与えています。
2. 地域主導の戦略 具体的な事例からの考察
地域特殊な知的資産を基盤とした発展を目指す場合、域外企業への依存を避け、地域自身の力で未来を切り開く道を探る必要があります。このセクションでは、北部九州と東北地方の事例を分析し、地域主導の発展を実現するための具体的な戦略パターンを探っています。 従来、地域優位性の要素は自然発生的なものと捉えられがちでしたが、現代社会では、新しい価値を創造する力や変化に対応する力(ポスト近代型能力)が求められています。 この新しい社会を「ハイパー・メリトクラシー」と呼び、この能力は地域社会のオルガナイザーとしての行政にも求められると指摘されています。 北部九州と東北地方の事例では、人材育成、高度技術の開発・蓄積、そして地域独自の知的資産の活用などが具体的な戦略として挙げられています。これらの取り組みは、単に企業誘致に頼るのではなく、地域自身の力を最大限に活用しようとする試みであり、内発的発展論の実践例として示唆に富んでいます。
3. 既存理論との比較検討 ポーターのダイヤモンドモデル
最後に、分析結果を既存の関連理論に照らし合わせて考察しています。特に、ポーターのダイヤモンドモデルとの比較検討がなされています。ポーターのモデルは、貿易収支の改善とGDP向上を目的とし、中核企業の製品の技術競争力の向上が重要であると主張しています。 しかし、日本の地域政策では、雇用状況の改善が重要な課題となっており、ポーターモデルとは目的が異なる点に注意が必要です。 日本の地域政策においては、中核企業の製品技術競争力は雇用状況改善に貢献する要素の一つであり、輸出競争力はそれをさらに促進する媒介変数と捉えられます。 従って、ポーターモデルを日本の地域政策に適用する際には、米国の経済状況と日本の地域経済の現状における違い、特に政策目標の違いを考慮する必要があると結論付けています。この考察は、地域活性化政策を設計する上での理論的枠組みの選定、そして政策目標の設定において重要な示唆を与えています。マーシャルのレント理論にも触れ、地域固有の資源と能力の重要性を再確認しています。
