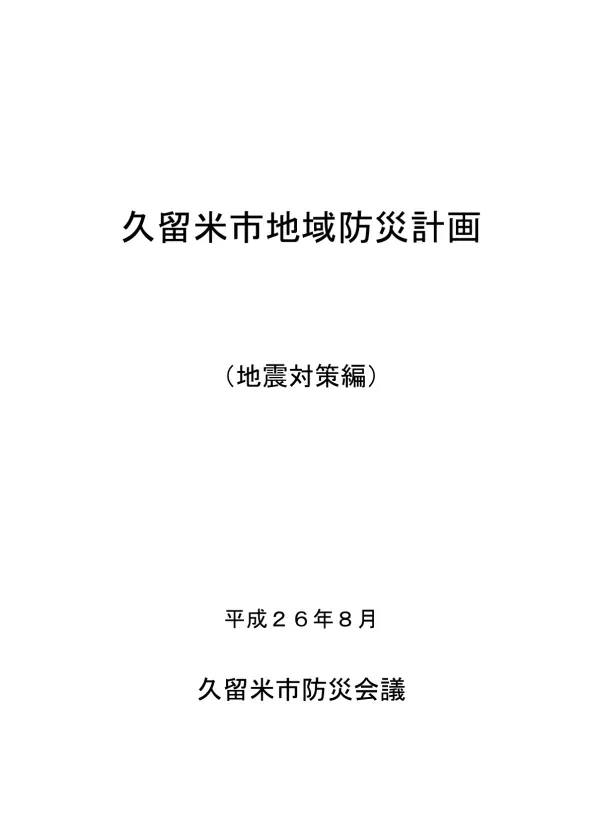
地震対策マニュアル:防災計画
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 3.86 MB |
概要
I.災害対策本部設置と機能確保
市長指示により、災害対策本部が設置されます。市庁舎が使用不可能な場合は、技術班との協力の下、代替施設が優先順位に基づき選定されます。通信機能低下時には、「災害時優先電話(102)」等の代替手段が確保されます。重要なキーワード:災害対策本部、災害応急対策、通信手段、代替施設。
1. 災害対策本部の設置
市長の指示に基づき、統括部総括班が災害対策本部の設置を担います。これは、地震などの大規模災害発生時の迅速かつ効果的な対応を目的としています。災害の規模や状況に応じて、市庁舎を災害対策本部として活用しますが、市庁舎が被災により機能不全に陥った場合、統括部総括班は技術班と連携し、事前に定められた優先順位に基づき、市内の他の公共施設などを代替拠点として選定し、災害対策本部を設置します。この選定プロセスには、各施設の被害状況の迅速かつ正確な調査と、災害対策本部としての機能を維持できるかどうかの厳格な評価が含まれます。選定された代替施設は、災害対策本部としての機能を円滑に遂行できるよう、必要な設備や人員の配置、通信手段の確保などが事前に計画され、迅速に整備されます。この計画は、災害発生時の混乱を最小限に抑え、迅速な対応を実現するための重要な戦略です。災害対策本部は、関係機関との連携を強化し、情報共有や指示伝達を効率化することで、被害の拡大防止と迅速な復旧活動に貢献します。このため、災害対策本部は、災害発生時の司令塔として重要な役割を果たし、効果的な災害対策の遂行に不可欠な組織です。
2. 市庁舎機能の点検と確保
市庁舎が災害対策本部として機能するかどうかを技術班が点検し、その機能を確保することが重要です。この点検は、建物構造、設備、通信システムなど、災害対策本部としての運用に必要なすべての要素を網羅的に行われ、災害発生前に潜在的な問題点を早期に発見し、対応策を講じることを目的としています。点検の結果、市庁舎に機能上の問題が発見された場合は、技術班は速やかにその修復や改善を行い、災害対策本部としての機能を完全に確保します。これは、災害発生時に市庁舎が重要な役割を果たすことを保証するために不可欠な手順です。さらに、点検は定期的に実施することで、市庁舎の維持管理のレベルを高め、災害発生時の対応能力の向上に貢献します。市庁舎の機能確保は、災害対策全体における基盤であり、市庁舎の安全性が確保されて初めて、効果的な災害対策が可能となります。そのため、この点検と機能確保の作業は、災害対策における最も優先度の高い項目の一つとして位置付けられています。
3. 代替通信手段の確保
市が所有する通信機能が災害によって著しく低下し、応急対策に支障が生じる可能性を考慮し、代替通信手段の確保が重要です。これは、災害発生時における情報伝達の維持を保証し、迅速な対応と被害の最小化に不可欠な要素です。具体的な代替手段として、災害時優先電話(102)の利用が挙げられており、市外局番不要でオペレーターに状況を報告することで、通信障害が発生している状況下でも重要な連絡を確保することができます。この方法は、従来の通信手段が使用できない場合でも、緊急事態において情報を伝達するための信頼性の高い手段として機能します。また、この代替通信手段の確保計画は、事前に周知徹底されているため、関係者にとって容易に利用可能な方法となっています。この計画は、災害時の情報伝達における重要なバックアップシステムとしての役割を担い、市民の安全と円滑な災害対策の遂行に大きく貢献します。さらに、この計画の継続的な見直しと改善によって、より信頼性が高く、効率的な通信手段を確保することが期待されます。
II.初期情報収集と広報活動
各部は所管施設等の危険情報・被害情報を収集し、情報収集班は人的被害、建物被害、火災等の情報を関係機関と連携して収集します。広報班は、防災行政無線、緊急速報メール、広報車等を用いて危険情報を伝達し、ドリームスエフエム株式会社にも広報協力を依頼します。重要なキーワード:初期情報収集、広報活動、防災行政無線、緊急速報メール、ドリームスエフエム株式会社。
1. 初期情報収集
災害発生直後からの迅速な情報収集が、効果的な災害対応に不可欠です。各部署は、それぞれの管轄区域内の施設やインフラに関する危険情報や被害状況の初期情報を収集します。特に、情報収集班は地震発生直後から人的被害、建物の被害状況、火災や土砂災害の発生状況といった重要な情報を、各対策部と連携して収集します。この際、自衛隊や警察が保有するヘリコプターによる情報、郵便局員や現場に駆けつけた職員からの情報など、あらゆる入手可能な情報を活用することで、より正確で迅速な情報収集を目指します。収集された情報は、災害対策本部へ迅速に報告され、被害状況の把握や適切な対応策の決定に役立てられます。この初期情報収集の正確性と迅速性は、災害対応の成功を大きく左右する重要な要素であり、関係各部署の緊密な連携と情報共有体制の確立が不可欠です。情報収集活動は、災害対応の初期段階における最も重要な活動の一つであり、その質と効率性が、後の災害対策の有効性を大きく左右します。
2. 危険情報伝達と避難誘導
延焼火災や危険物漏洩などの発生時には、迅速かつ正確な情報伝達と避難誘導が求められます。広報班、総合支所総括班、消防団班、消防本部は連携して、防災行政無線、緊急速報メール、広報車、現場広報など、可能なあらゆる手段を用いて市民に危険情報を伝え、避難を促します。これらの多様な手段を組み合わせることで、情報伝達の網羅性と信頼性を高め、情報が届きにくい地域や人々への対応も万全を期します。特に、延焼火災の危険性が高い地域では、住民の避難を最優先し、安全な避難経路の確保に全力を尽くします。広報活動は、市民の生命と安全を守る上で極めて重要であり、正確で分かりやすい情報提供が求められます。さらに、広報班は、ドリームスエフエム株式会社に広報協力を依頼することで、より広い範囲の市民に情報を届ける体制を整えています。これは、情報伝達の多様化と地域住民への迅速な情報伝達を図るための重要な戦略です。
III.広域応援要請
災害発生時には、福岡県内市町村間の相互応援協定に基づき、県知事や他市町村長に応援を要請します。また、指定地方行政機関等への職員派遣要請も行います。これらの要請事務は統括部総括班が担当します。重要なキーワード:広域応援、相互応援協定、福岡県、職員派遣。
1. 福岡県内市町村間の相互応援協定に基づく要請
災害の発生により応急措置が必要と判断された場合、本部長は「災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定」に基づき、福岡県知事または他市町村長に対して応援を要請します。これは、近隣市町村との連携強化を図り、災害発生時の人的・物的資源の不足を補うための重要な仕組みです。この協定は、地域全体の防災体制強化に大きく貢献し、広域的な災害対応能力の向上を目指しています。要請内容は、必要な支援の種類、規模、期間など具体的な事項を含み、迅速かつ明確に伝えられるよう、統括部総括班が事務手続きを担当します。この手続きの迅速性は、災害対応のタイムリーさを確保する上で不可欠であり、関係機関との円滑な情報伝達と連携が求められます。福岡県内市町村間の緊密な協力関係が、災害時における地域社会の resilience(回復力)を高める上で極めて重要です。この協定に基づく相互支援体制は、広域的な災害への対応能力を強化し、被災地域の早期復旧・復興を支援します。
2. 指定地方行政機関等への要請
災害応急対策または災害復旧に必要となる場合、本部長は指定地方行政機関または特定公共機関の長に対して職員の派遣を要請します。特定公共機関とは、内閣総理大臣が市域の災害応急対策または災害復旧に特に寄与するものとして指定した公共機関であり、その業務内容や事情を考慮して地域が限定される点が特徴です。これは、市単独では対応が困難な大規模災害時において、広域的な人的資源の確保を目的としています。職員派遣の要請は、災害の規模や必要性に応じて柔軟に対応し、迅速な対応を可能とします。また、県知事にも斡旋を依頼することで、より幅広い範囲からの支援を確保する体制を整えています。統括部総括班は、これらの要請事務を円滑に進める重要な役割を担っており、関係機関との連携を密にし、迅速かつ的確な対応を行うことが求められます。この広域的な支援体制は、災害への対応能力を高め、被災地の早期復旧・復興に貢献する重要な要素となっています。
IV.消火活動と救急活動
消火活動は風向きや市街地状況を考慮し、効率的に実施されます。救急活動では、消防本部が傷病者の搬送を行い、多数発生時にはドクターカー、ドクターヘリ、福岡県DMATの派遣を要請します。放射線関係施設火災への対応も規定されています。重要なキーワード:消火活動、救急活動、福岡県DMAT、放射線関係施設。
1. 消火活動の留意事項
消火活動は、風向き、市街地の建物分布などを考慮し、効率的で効果的な消防力の投入が求められます。延焼火災の少ない地区では、消火活動を集中して安全な地区を確保し、延焼火災が発生している地区では、住民の避難を最優先に行い、安全な方向への避難誘導を徹底します。避難経路の確保も重要な課題であり、迅速かつ適切な対応が必要です。また、建物や土砂の下敷きになっている人がいる場合は、可能な限り協力して救助活動を行います。これらの活動は、人的被害の最小化と財産の損失を抑制することを目的とし、消防隊員の高いスキルと迅速な判断、そして、状況に応じた柔軟な対応が求められます。消防隊員の安全確保も重要な要素であり、危険な状況下での活動においては、安全対策を徹底し、隊員の安全を確保しながら活動を進める必要があります。効率的な消火活動と住民の安全確保を両立させるためには、綿密な計画と迅速な情報共有、そして、関係機関との連携が不可欠です。
2. 救急活動
消防本部は、災害現場から救護所や医療機関まで、救急車などで傷病者を搬送します。これは、迅速な医療処置の提供と患者の救命率向上に繋がる重要な活動です。傷病者が多数発生した場合は、ドクターカー、ドクターヘリ、そして福岡県災害派遣医療チーム(福岡県DMAT)の派遣を要請します。これは、限られた医療資源を効果的に活用し、重症者の迅速な治療を確保するための重要な措置です。これらの医療チームは、高度な医療技術と経験を有しており、大量傷病者災害への対応能力を高めます。迅速な搬送と適切な医療処置は、被災者の生命と健康を守る上で不可欠であり、関係機関との緊密な連携と、事前の計画に基づいた迅速な対応が求められます。特に、重症者の迅速な搬送と治療は救命率を大きく左右するため、効率的な搬送システムと、医療機関との連携強化が不可欠です。この活動においては、関係機関との連携強化と、人員・資材の適切な配置、そして、状況に応じた柔軟な対応が求められます。
3. 放射線関係施設火災への対応
放射線関係施設の火災が発生した場合、施設周辺の放射線による危険を防止することが最優先事項となります。施設管理者の指示に従い、危険区域を設定し、防護装備をした者以外の立ち入りを禁止します。消火活動においては、注水消火を行う場合、消火に使用した水の汚染状況を考慮し、安全な地域に流出させるなどの対策が必要です。これは、二次災害の防止と環境保護の観点から重要な措置であり、専門的な知識と技術を要する作業です。関係機関との連携も不可欠であり、迅速かつ正確な情報共有に基づいた対応が求められます。放射線による危険性の高い状況下での消火活動は、高度な専門知識と技術、そして、関係機関との連携を必要とする非常に重要な活動であり、事前の計画と訓練が重要になります。放射線関係施設の防災対策は、周辺住民の安全確保において重要な役割を果たしており、万全な体制の構築が求められます。
V.避難支援と生活支援
災害時要援護者の避難は地域自主防災組織等が行いますが、困難な場合は地域福祉班が福祉車両等を用いて支援します。避難所では食料・生活必需品の供給体制が整備され、物資調達班がその必要量を把握します。福祉避難所も開設されます。重要なキーワード:避難支援、生活支援、災害時要援護者、物資調達、福祉避難所。
1. 災害時要援護者の避難支援
災害時要援護者の避難は、地域住民の安全確保において極めて重要な課題です。在宅の災害時要援護者の避難は、原則として地域の自主防災組織などが行います。しかし、地域での避難支援が困難な場合は、地域福祉班と避難福祉支援班が、福祉有償運送業者や福祉施設などと協力し、福祉車両などを用いて避難を支援します。これは、要援護者一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかな対応が必要であり、関係機関との連携と、適切な輸送手段の確保が不可欠です。高齢者や障害者など、移動に困難のある方々への配慮が特に重要であり、安全で快適な避難を確保するための計画と体制が求められます。この避難支援体制は、地域社会全体で要援護者を守るための仕組みであり、関係機関の連携と、地域住民の協力が不可欠です。また、避難支援の計画・実施にあたっては、要援護者の属性やニーズを的確に把握し、適切な支援を提供できるよう、事前の情報収集と準備が重要となります。
2. 避難所における生活支援
避難所では、避難者の生活を支援するための様々な対策が講じられます。学校避難所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避難所班、避難福祉支援班は、避難者数に基づいて食料や生活必需品の必要量を教育・避難班に請求します。教育・避難班は、物資調達班と輸送班に物資の調達と輸送を依頼し、避難所自主運営組織や地域住民ボランティアと協力して避難者に配給します。この過程において、食物アレルギーを持つ方や災害時要援護者への配慮も欠かせません。避難所生活の円滑化には、食料・生活必需品だけでなく、衛生管理や医療体制の整備も重要です。特に、要介護高齢者や障害者など、一般避難所で生活することが困難な方々を対象に、事前に社会福祉施設などと協定を締結し、福祉避難所を開設することで、より適切な支援を提供します。一般避難所から福祉避難所への移送は、原則として家族などが行いますが、困難な場合は地域福祉班が福祉有償運送事業者などとの連携により、福祉車両などを用いて支援を行います。
3. 生活必需品の調達と供給
被災者への食料供給は、災害後の生活を維持する上で不可欠です。物資調達班は避難所等の被災者や災害応急活動従事者への食料供給に必要な量を把握し、米穀や乾パンなどの調達を県に要請します。県知事の指示に基づき、福岡食糧事務所や倉庫から調達を行い、その手続きは「災害救助法が発動された場合における災害救助用米穀の緊急引渡要領」に従います。生活必需品についても、物資調達班が販売業者に発注しますが、不足する場合は、統括部総括班を通じて県や中核市、日赤福岡県支部、県内市町村などに供給を要請します。この際、男女のニーズの違いや、災害時要援護者への配慮も必要です。食料や生活必需品の安定供給には、関係機関との連携強化が不可欠です。また、供給体制の維持管理や、迅速かつ効率的な供給システムの構築が、被災者の生活安定に大きく貢献します。供給計画には、被災者の状況やニーズを的確に把握し、迅速かつ的確に対応できる体制づくりが不可欠です。
VI.文教 保育対策
地震発生時は、学校長が児童・生徒の安全確保のため適切な措置を講じます。授業継続が困難な場合は休講措置をとります。学校給食についても被害状況に応じて対応し、避難所としての使用と調整します。重要なキーワード:文教対策、保育対策、学校避難、学校給食。
1. 応急保育の実施
地震などによる災害発生時には、保育所の被害状況を速やかに把握し、復旧作業に努めます。保育所の建物や設備に被害があり、通常の保育が実施できない場合は、臨時的な保育施設を設け、応急保育を実施します。この応急保育は、災害による親元からの離れ離れや、保護者の不在といった状況下で、園児の安全と健康を確保するための重要な対策です。避難所への避難誘導や避難所の運営にも協力し、避難生活を送る園児や保護者へのサポート体制を整えます。交通機関の不通など、通常の送迎が困難な状況下においても、園児と職員の安全な移動と保育の継続を確保するための対策が講じられます。この応急保育体制は、災害時における園児の安全と福祉を確保するための重要な役割を果たしており、迅速な対応と関係機関との連携が不可欠です。また、保育士の安全確保についても考慮し、安全な環境下での保育活動が実施できるよう、万全の対策を講じる必要があります。
2. 応急教育活動
学校長は、地震などの災害発生時、学校施設の被害状況を調査し、学校避難所・庶務班や学校施設班と連携して応急教育のための場所を確保します。校舎が避難所として使用される場合は、避難スペースの確保と併せて、応急教育のためのスペースも確保し、学業と避難生活の両立を図ります。地震により授業継続が困難な場合は、市や県教育委員会の指導・助言に基づき、授業の休講措置などをとります。児童生徒の安全確保を最優先事項として、地震発生時には学校での待機または保護者への引き渡しなど、適切な措置をとります。また、ガス漏れや火災など危険がある場合は、安全な避難所への避難誘導を行います。被災家庭の特別支援学校の児童生徒については、就学奨励費の追加支給など、必要な支援措置が講じられます。学校給食については、給食施設・設備や物資に被害があった場合は、教育・避難班に報告し、給食実施の可否を決定します。避難所として使用されている学校では、学校給食と被災者への炊き出しとの調整に配慮します。
VII.災害復旧と復興計画
地震災害発生時には、迅速に復旧計画を策定します。社会的緊急度が高い施設を優先的に復旧し、長期化の場合は代替熱源等の提供を検討します。復興計画作成においては、被災状況、地域の特性等を勘案し、迅速な原状復旧または災害に強いまちづくりを目指します。重要なキーワード:災害復旧、復興計画、代替熱源。
1. 復旧計画の策定
地震災害発生時には、被災状況の正確な情報を迅速に収集し、復旧計画を策定することが重要です。この計画には、復旧手順と方法、復旧要員の動員と配置計画、復旧用資機材の調達計画、復旧作業工程、臨時供給の実施計画、宿泊施設の手配と食料調達計画などが含まれます。特に、病院やごみ焼却場など社会的緊急度が高い施設については、優先的な復旧を図ります。復旧作業が長期化する場合は、需要家支援のために代替熱源の提供なども検討します。この計画は、迅速かつ効率的な復旧作業の実施を目的としており、関係機関との連携と、的確な資源配分が不可欠です。復旧計画の策定にあたっては、被災状況の正確な把握と、関係者間の情報共有が重要になります。また、計画の柔軟性も重要であり、状況の変化に応じて計画を見直し、修正していく必要があります。計画策定には、専門家や関係機関の知見を積極的に活用し、科学的根拠に基づいた計画とする必要があります。
2. 復興計画作成の体制
復興計画は、被災状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向などを考慮して作成されます。迅速な原状復旧を目指すのか、災害に強いまちづくりなどの中長期的な課題解決を目指すのかについて、早急に検討し、復旧・復興の基本方針を定めます。この基本方針に基づき、具体的な復興計画を作成します。復興計画の作成には、関係各部署の連携と協力が不可欠であり、それぞれの役割分担と責任範囲を明確にする必要があります。特に、大規模な災害によって地域社会が壊滅的な被害を受けた場合は、都市構造や産業基盤の抜本的な見直しが必要となる高度で複雑な大規模事業となります。関係機関との合意形成と、計画の推進体制を構築することが、円滑な復興を進める上で重要となります。復興計画は、単なる復旧にとどまらず、将来にわたる地域社会の安全と発展を見据えた長期的な視点に立った計画でなければなりません。
VIII.その他重要な対策
女性への相談窓口、生活相談、精神的なケア、災害による保険給付への対応、簡易保険積立金による災害短期融資などが記載されています。重要なキーワード:女性支援、生活相談、精神ケア、保険給付、災害短期融資。
1. 生活相談
災害発生時には、市民からの問い合わせや要望に対応するため、広聴相談課と市民福祉課が生活相談を実施します。これは、被災者への迅速な情報提供と、生活上の困窮への対応を目的としています。相談内容は、生活物資の供給、住宅の被害状況、医療や福祉サービスの利用方法など、多岐に渡ります。相談窓口では、丁寧な対応と、的確な情報提供を行うことで、被災者の不安やストレスを軽減することに努めます。相談内容は記録・整理され、必要に応じて関係機関に情報が共有され、より効果的な支援に繋げられます。生活相談は、災害からの復旧・復興を支援する上で重要な役割を果たしており、市民の生活安定に大きく貢献します。相談体制の充実と、関係機関との連携強化が、迅速かつ適切な対応を実現するために不可欠です。相談内容の分析は、今後の災害対策の改善に役立てられます。
2. 精神的なケア
災害による精神的なストレスへの対応として、健康推進課、保健予防課、市民福祉課が、精神科医療機関などと協力し、被災者や災害時要援護者へのカウンセリングなどの精神的なケアを提供します。これは、災害によるショックや避難生活の長期化によって生じる精神的な負担を軽減することを目的としています。専門家によるサポートを通して、被災者の心の健康を守り、精神的な回復を支援します。個々の被災者の状況やニーズを的確に把握し、適切なケアを提供することが重要であり、関係機関との連携を密にする必要があります。特に、災害時要援護者など、特別な配慮が必要な方々への支援体制の構築が求められます。精神的なケアは、災害後の生活再建に不可欠な要素であり、早期の介入と継続的な支援が重要です。この精神的なケア体制は、被災者の心の健康と生活再建を支援し、地域社会全体の回復を促進します。
3. 保険給付と女性支援
災害により保険料の支払いが困難になった被保険者に対しては、保険給付の差し止めなどは行わず、必要な支援を行います。また、災害により居宅サービスや施設サービス、特定福祉用具の購入、住宅改修などに必要な費用を負担することが困難な被保険者(要介護・要支援被保険者)に対しては、介護給付や予防給付の割合を増額します。これは、被災者への経済的な負担を軽減し、生活再建を支援するための重要な措置です。さらに、災害によって生じたストレスや暴力被害など、女性の心身の健康問題への対応として、家庭子ども相談課と男女平等推進センターが電話相談や面接相談を実施します。市保健所など関係機関と協力して、避難所などに女性の相談員や保健師を派遣し、女性のための相談体制を強化します。これは、災害時における女性特有の課題への対応を目的としており、安全で安心な環境を提供することが重要です。これらの対策は、災害によって生じる様々な問題への包括的な対応を示しており、被災者への支援体制の充実が目指されています。
4. その他の支援
災害時において、被災地の実情に応じて、日本郵便株式会社は簡易保険福祉事業団に対し、加入者福祉施設が被災地の地方公共団体等関係機関と連絡を取り、救護活動に従事するよう要請します。これは、民間機関の協力を得て災害支援を強化するための重要な取り組みです。また、被災地域地方公共団体への簡易保険積立金による災害短期融資も検討されます。これは、被災地の早期復旧・復興を支援するための財政的な支援であり、市は県や関係機関と緊密に連携して、再度災害の発生防止とより快適な生活環境を目指した防災まちづくりを実施します。市街地の整備改善が必要な場合は、被災市街地復興特別措置法などを活用して、合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図ります。これらの施策は、災害からの迅速な復旧と、より安全で住みやすい街づくりを目指した、多角的な取り組みを示しています。
