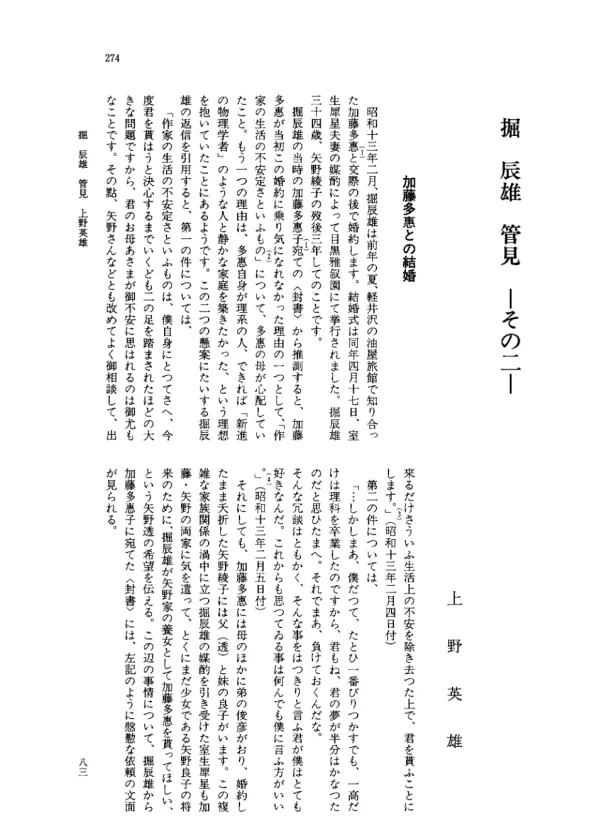
堀辰雄と王朝文学:更級日記への深い洞察
文書情報
| 著者 | 上野英雄 |
| 専攻 | 国文学 |
| 文書タイプ | エッセイ |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.48 MB |
概要
I.堀辰雄と王朝文学 折口信夫の影響
この文章は、小説家 堀辰雄 の作品世界、特に 王朝文学 (特に更級日記) への関心と、民俗学者 折口信夫 の影響を考察しています。堀辰雄は少年時代から更級日記に深い感銘を受け、その精神性を自身の作品に反映させています。折口信夫の思想や研究は、堀辰雄の文学観、特に古代への憧憬や女性の美意識といった点に大きな影響を与えたと分析されています。 彼の小説『菜穂子』などにも、これらの影響が明確に見て取れます。
1. 更級日記と堀辰雄の少年時代
文章は、堀辰雄が少年時代に『更級日記』を読んだ経験について言及している箇所から始まります。この日記を読んだことで、堀辰雄は「古い日本の女」への深い憧憬を抱いたと述べています。この記述から、堀辰雄の感性や、後の創作活動における女性像の描写に『更級日記』が大きな影響を与えたことが推察されます。特に、日記に描かれる女性の繊細な心情や内面世界が、堀辰雄の文学的感性に深く刻まれたことが伺えます。この初期の体験は、彼の作品世界を理解する上で重要な鍵となるでしょう。 続く記述では、『更級日記』のエッセイの中で、堀辰雄自身の感情や印象が語られています。この部分からは、単なる作品分析にとどまらず、堀辰雄自身の個人的な体験と作品との密接な関係が読み取れます。これは、彼の作品が単なるフィクションではなく、彼自身の内面世界を深く反映したものだったことを示唆しています。
2. 折口信夫の影響と古代文学への関心
文章は、折口信夫の『折口信夫全集』が堀辰雄の創作に与えた影響を指摘しています。『源氏物語全講会』の講義録が全集に収録されていることや、折口信夫が研究対象とした『万葉集』や『今昔物語集』といった古代文学への関心が、堀辰雄の創作活動に深く結びついていた様子が記述されています。特に『古代感愛集』が堀辰雄に寄贈されたことや、それに対する彼の批評文の存在は、両者の関係の深さを物語っています。これらの事実は、堀辰雄の作品世界における古代文学や民俗学的な要素の重要性を示しています。 また、折口信夫の論文に描かれた「葛の葉という狐」の話に堀辰雄が惹かれたという記述からも、彼の想像力や創作への着想源に、折口信夫の研究が直接的に関わっていたことがわかります。このことは、堀辰雄の作品に独特の雰囲気や奥行きを与えている重要な要素として捉えることができます。
3. 王朝文学と西洋文学の融合
文章において、堀辰雄の創作活動に、王朝文学と西洋文学、特にリルケの影響が深く関わっていたことが指摘されています。リルケの『マルテの手記』における表現が、堀辰雄の作品に影響を与えたと考察されています。これは、堀辰雄が東洋的な伝統と西洋近代文学を独自の視点で融合させていたことを示唆しています。 『かげろふ日記』への言及からも、王朝文学の女性像への深い理解と、それを独自の解釈で現代的な視点から表現しようとした堀辰雄の作家としての姿勢が見えてきます。彼の作品に、東と西の文化が調和して共存している点が、大きな魅力の一つとなっていると言えるでしょう。この融合は、堀辰雄の作品の独自性を生み出す重要な要素として、深く検討する必要があります。
II. 菜穂子 の背景と創作過程
『菜穂子』は、堀辰雄がリルケや王朝文学に傾倒していた時期に書かれた作品です。創作の動機は、堀辰雄自身の母や女性像への複雑な感情、そして現実とロマンの間で揺れる若い女性の描写にあります。物語の舞台となる信州の風景や人々の生活も、作品に深みを与えています。重要な登場人物として、主人公のおえふとその夫、そして森鷗外が挙げられます。
1. 菜穂子 の創作動機 母と現実との葛藤
『菜穂子』の創作背景として、堀辰雄自身の母との関係や、現実的な生き方とロマンティックな感情との葛藤が挙げられています。 彼は、現実的な生き方を模索する一方で、母と同様のロマンティックな感情に苦しめられる若い女性を描きたいと考えていたようです。この記述から、堀辰雄自身の内面世界や、母親との複雑な関係が、作品に投影されていることがわかります。 また、昭和9年に執筆を開始し、昭和16年に完成したという記述から、長期間にわたって作品と向き合っていたことが伺えます。この期間には、リルケや王朝文学への傾倒期も含まれており、それらの影響が『菜穂子』の創作に及ぼした影響を探るのも重要な点です。 さらに、『菜穂子』の「あの方」が森鷗外を指しているという記述も、作品理解の重要な手がかりとなります。
2. 菜穂子 の主要登場人物と物語の梗概
小説『菜穂子』の主人公であるおえふは、十九歳で蔦ホテルに嫁ぎ、生家にもどらず、やがて夫の死後、思わぬ相続問題に直面します。 この物語は、おえふの複雑な家庭環境や、彼女を取り巻く人々の関係性、そして時代の変化などが描かれているようです。 おえふの弟である五郎とその妻おしげ、蔦ホテルと牡丹屋という異なる家柄の対比なども、物語の重要な要素となっていると考えられます。 文中では、おえふが主人公として描かれ、彼女の生き方や葛藤が物語の中心となっていることがわかります。 蔦ホテルの火災や、その後の生活の変化といった具体的な出来事も、おえふの運命を大きく左右する重要な要素となっています。
3. 菜穂子 の創作における時間軸と場所設定
『菜穂子』は、昭和9年から昭和16年にかけて書かれた作品であり、この期間は堀辰雄がリルケや王朝文学に傾倒していた時期に相当します。この時代背景は、作品の世界観や登場人物の心情を理解する上で重要な要素となります。 物語の舞台は信州であり、特に八ヶ岳の麓の高原療養所は菜穂子の転地先として重要な意味を持ちます。この療養所での生活が、菜穂子の心境や物語の展開に大きな影響を与えていると考えられます。 また、文中では、信州の自然や生活が、作品に大きな影響を与えていることが示唆されています。 こうした地理的・時間的な背景を踏まえることで、『菜穂子』という作品をより深く理解できるでしょう。
III.大和への旅と古代への憧憬
堀辰雄は何度も大和(奈良)を訪れ、古代寺院を巡っています。これらの旅は、単なる観光ではなく、古代文学や折口信夫の研究にも通じる、古代美への強い憧憬に基づいたものでした。これらの旅の経験は、彼の作品世界に大きな影響を与えたと考えられます。 具体的には、新薬師寺、唐招提寺、飛鳥といった場所が彼の旅の記録に頻繁に登場します。
1. 大和への複数回の旅と古代への関心の深まり
文章からは、堀辰雄が少なくとも4回以上、大和(奈良)を訪れ、古代寺院などを巡っていたことが分かります。 これらの旅は、単に観光目的だけでなく、古代美への憧憬や、創作活動における素材収集といった目的意識が強く感じられます。 特に、新薬師寺、唐招提寺、佐保路、海龍王寺、歌姫村、法隆寺、秋篠寺といった具体的な地名が繰り返し登場することから、彼が大和の地に強い関心を抱き、綿密な取材を行っていたことが窺えます。 また、万葉集ゆかりの場所を訪れた記述もあり、古代文学への関心の高さが、大和への旅の動機の一つであったことが示唆されています。 彼の旅は、単なる観光旅行ではなく、自身の創作活動に深く結びついた、目的意識の高い行動であったと言えるでしょう。
2. 旅の記録と創作への影響 古代美と万葉集
大和への旅の記録は、単なる旅行記にとどまらず、彼の創作活動に大きな影響を与えていることが記述されています。 例えば、万葉集に縁のある場所を巡り、万葉気分を深く味わうことで、古めかしい物語の創作を構想したとあります。 これは、彼の創作が単なる想像力だけでなく、現実の体験や歴史的背景に基づいていたことを示しています。 また、旅の際に『今昔物語』『古代霊異記』といった古代文学関連の書籍を読んでいたという記述から、彼の関心の深さと、創作への真剣な姿勢がうかがえます。 天平時代の建物や彫像の素晴らしさに触れた経験は、彼の創作意欲を刺激した重要な要素と考えられます。 これらの経験が、彼の作品に独特の雰囲気や世界観を与えていると言えるでしょう。
3. ゲーテの言葉と古代研究の未熟さへの葛藤
大和への旅を通して、堀辰雄は古代研究の未熟さを自覚し、古代を題材とした小説創作に苦悩したことが記述されています。 その中で、ゲーテの「イフィゲニエ」の創作エピソードと、自身の古代研究の不完全さを重ね合わせています。 ゲーテはギリシャ研究の不完全さを認めつつも、「イフィゲニエ」を完成させたという逸話を引用することで、堀辰雄は自身の古代研究の不足を認めながらも、創作活動を継続しようとする意志を表明していると考えられます。 この葛藤は、彼の創作活動における真摯な姿勢と、自己への厳しさを示す重要な部分です。 このエピソードは、堀辰雄が単なる古代ロマンチシズムに浸っていたのではなく、歴史や文化に対する深い考察を伴った創作活動を行っていたことを示しています。
IV.晩年の堀辰雄と信濃での生活
晩年、堀辰雄は信濃(長野県)に移り住み、そこで過ごした生活が彼の作品に反映されています。 堀辰雄の最後の作品であるエッセイ『橇の上にて』は、志賀高原での雪上体験を描写したものです。病気と闘いながら執筆活動を続けた彼の、自然への深い愛情と静かな人生観が感じられます。重要な場所として、別所温泉、志賀高原などが挙げられます。
1. 軽井沢への転居と晩年の生活環境
昭和19年6月末、堀辰雄は東京から軽井沢に移り住みました。この転居は、彼の晩年の生活に大きな変化をもたらしたと考えられます。 軽井沢での生活は、彼の作品にも影響を与えていることが予想されます。 文章からは、軽井沢での生活の様子については直接的な記述が少ないものの、東京からの転居をきっかけに、彼の生活様式や創作活動に変化があったことが推測できます。 また、この転居前後には、喀血などの健康問題を抱えていたという記述があり、彼の健康状態が晩年の生活や創作活動に影響を与えていたことがわかります。 軽井沢という場所が、彼の創作活動にどのような影響を与えたのか、更なる調査が必要となるでしょう。
2. 病と闘いながらの執筆活動と 橇の上にて
晩年の堀辰雄は病魔と闘いながらも、精力的に執筆活動を行っていました。 その最後の作品として挙げられているのが、『橇の上にて』というエッセイです。 このエッセイは、昭和18年に婦人公論に掲載されたもので、雪橇で志賀高原を訪れた体験が記されています。 この記述から、晩年においても自然への深い関心を持ち続けていたことがわかります。 また、病状に関する記述からは、脳貧血などの症状に苦しみながらも、執筆活動に励んでいた様子が伺えます。 『橇の上にて』は、彼の最後の作品であることから、彼の生涯における自然観や人生観を深く理解するための重要な手がかりとなります。
3. 信濃での生活と自然描写 別所温泉 志賀高原 八ヶ岳
晩年の堀辰雄は、信濃(長野県)で生活を送っており、その様子が文章の一部で触れられています。 別所温泉、志賀高原といった具体的な地名が挙げられており、これらの場所が彼の生活や創作活動に影響を与えたことが推察されます。 特に、『斑雪』という作品では、志賀高原での体験が描かれており、自然描写の豊かさが際立っていると考えられます。 また、八ヶ岳の麓の高原療養所は、病気療養のため菜穂子が希望した場所であり、この地の自然が、彼の精神世界に安らぎを与えていた可能性も考えられます。 彼の作品における自然描写は、単なる背景描写ではなく、彼の内面世界を反映する重要な要素となっていると言えるでしょう。
4. 晩年の交流と創作活動 雑誌 四季
文章には、堀辰雄が雑誌『四季』の編集に関わっていたことや、萩原朔太郎の死を悼んだこと、また、友人知人との交流の様子が記述されています。 『四季』の編集責任者として、佐藤春夫、室生犀星、三好達治といった当時の著名な作家に執筆を依頼していたことがわかります。 このことは、彼の人脈の広さと、文学界における彼の地位の高さを示しています。 また、戦時下の厳しい状況下においても、創作活動を続けようとしていた彼の強い意志が伺えます。 彼の友人知人との手紙のやり取りなども、彼の晩年の生活や心情を理解する上で重要な資料となると考えられます。
