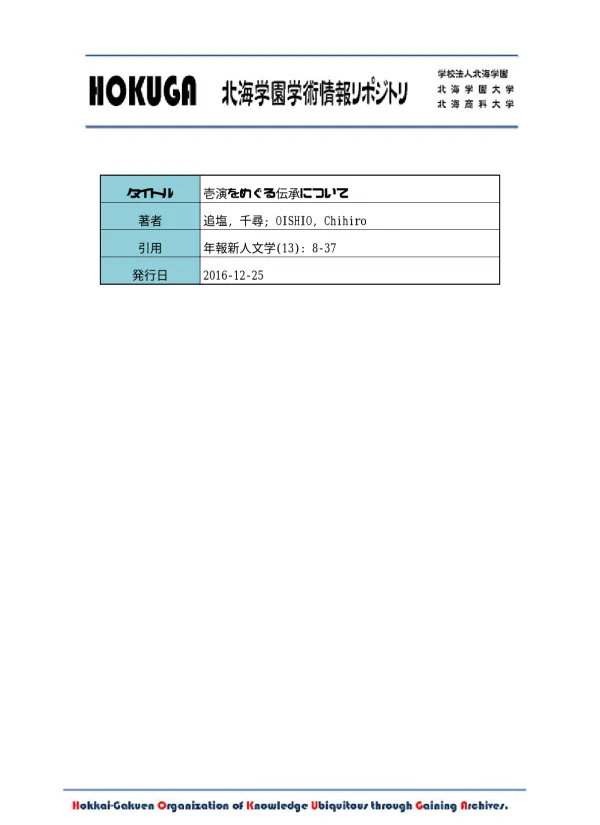
壱演:伝承と寺院創建
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 527.29 KB |
| 著者 | 追塩 千尋 |
| 文書タイプ | 論文 |
概要
I.壱演 慈済 の生涯と寺院建立に関する伝承
この記事は、平安時代後期の高僧、壱演(慈済、大中臣正棟)の生涯と、特に彼が関わったとされる寺院建立に関する伝承を検証しています。薬師寺所属の真言宗僧侶であった壱演は、権僧正や超昇寺座主を務めた高僧でしたが、その実像は史料不足から不明な点が多いです。しかし、彼の活動は相応寺、感応寺などの寺院建立譚や、皇太后の病気治療、金剛般若経の読誦などを通して、貴族社会や民衆に影響を与えたことが伺えます。淀川水系周辺に集中する寺院建立譚は、彼の遊行的行動と関係しており、船による移動が多かったことが示唆されています。また、地蔵菩薩や観音菩薩、薬師如来などへの信仰が深く関わっていたことも分かります。
1. 壱演の出自と初期の生涯
9世紀の南都僧である壱演(慈済、大中臣正棟)は、薬師寺に所属し、真如の法弟子であったことから真言宗の僧侶と見なされています。権僧正や超昇寺の座主など要職を務めた高僧であり、密教修行を通じて得た法験を貴族社会で発揮し、名を成しました。思弁的な著作は確認されていませんが、空也と並ぶ民間布教者と評される側面もありました。しかし、史料の不足から実像の解明は困難であり、特に寺院建立に関わる伝承が多く含まれている点が実像究明を阻んでいます。彼の出家時期は承和二年説と承和三年説があり、はっきりしていません。承和三年には真如より両部の灌頂を授かっています。 また、父は備中守を務めた智治麻呂、祖父は参議の諸魚、曽祖父は右大臣の清麻呂という高貴な家系に生まれた壱演は、二人の兄の夭逝をきっかけに出家したとされています。兄の死因は天長・承和期に流行した疫病であったと考えられます。授戒の師は、円仁らと共に唐へ渡った戒明であり、真如と戒明の両名が彼の師ということになります。
2. 法名 壱演 の由来と僧としての経歴
貞観七年に権僧正に任じられた際、まだ正式に得度していない沙弥であったため辞退しようとしたが、特別に得度が許され、「壱演」という法名を得たという逸話が残っています。これは、彼の「不定居処、居留任意」という遊行的で自由な行動様式を反映しているのかもしれません。権僧正への任命は律師・僧都の階梯を経ない特進であり、その異例性も注目されます。彼の年譜からは、貞観年間以降に権僧正や超昇寺座主への就任、相応寺建立など、顕著な活動が見えてきます。特に相応寺建立の伝承は、それ自体が伝承的な色彩が強いものの、彼の活動の一端を伺わせる重要な史料です。『僧綱補任抄出』には、権僧正任命時の法名由来に関する記述があり、そこには彼が沙弥の身分であるにもかかわらず、権僧正の地位に就くという異例性が記されています。また、『今昔物語集』では、相応寺の僧であり、金剛般若経の持経者としての側面が強調されており、彼の宗教的活動の多様性も示唆されています。
3. 寺院建立譚と地理的分布
壱演は、相応寺、超昇寺、感応寺、水呑地蔵院、薗光寺、清和院など多くの寺院建立に関わったとされる伝承が残っています。しかし、正史で彼の関与が確認できるのは薬師寺、超昇寺、相応寺の三ヶ寺のみです。残りは伝承に頼る部分が多く、その信憑性を検証することが重要です。これらの寺院の地理的分布は、山城国や河内国に集中しており、特に淀川水系に位置するものが目立ちます。これは、船を用いた彼の遊行的行動様式と関連づけられると考えられます。例えば相応寺は、桂川と宇治川の合流点である山崎津に近く、平安京への水上交通の要衝に位置していました。感応寺も鴨川西岸にあり、淀川水系と関連している点で相応寺と共通しています。一方、延福寺は地理的に離れた備中に位置していますが、これは壱演の父が備中守であったことに由来する伝承と考えられます。
4. 壱演と仏像製作 信仰
壱演は、地蔵菩薩像の製作にも関わっていたとされる伝承があり、特に清和院の地蔵尊製作は、清和天皇の母である藤原明子の勧めによるものと伝えられています。この伝承は、12世紀から14世紀初頭にかけて語られており、清和院の寺院化の時期とほぼ一致します。また、感応寺の縁起には、本尊の観音像に加え、牛頭天王像が祀られていることが記されています。牛頭天王は疫病除けの信仰対象でもあり、感応寺における病気平癒や安産祈願と結びついています。壱演に関わる仏菩薩像としては、観音、地蔵、薬師などが中心であり、彼の信仰の広がりを反映しています。彼の密教僧としての側面も注目され、『真言伝』には鞍馬寺や稲荷山との関わりも示唆されています。彼の活動は、単なる寺院建立だけでなく、仏像製作、そして様々な仏菩薩への信仰と深く結びついていたことが分かります。
II.相応寺と超昇寺の創建
相応寺は、現在の大山崎町付近に建立され、地中から仏像が出土したという伝承があります。壱演は晩年にこの寺を建立し、そこで坐禅修行を行ったとされています。一方、超昇寺は南都における重要な真言寺院であり、壱演との関係から南都僧との繋がりを窺い知ることができます。これらの寺院建立は、事実と伝承が混在しており、今後の更なる史料調査が必要です。
1. 相応寺の創建伝承
相応寺の創建は、壱演の最晩年にあたり、寺号や四至が定められたのは彼の死の前年であったと推測されます。創建地は、現在の京都府大山崎町付近の河陽橋周辺、桂川と宇治川が合流する山崎津であり、老女から土地の提供を受けたと伝えられています。地鎮作業中に地中から損傷した仏像が出土し、その後小堂が建てられました。この地で壱演は坐禅修行を行い、『卒伝』には「静識浪之地」と表現されています。『卒伝』によると、壱演は壇法を行い方丈の壇を築き仏像を安置したところ、「壇上変白、恰似塗粉」という霊験が現れ、多くの人が感嘆したと記されています。山崎津は桂川、宇治川、木津川の三川が合流・分岐する水陸交通の要衝であり、特に長岡京遷都後は造営物資の陸揚げ地として重要な役割を果たしていました。相応寺は、平安京から奈良に向かう水路沿いに位置しており、壱演の遊行的行動と密接な関係にあると考えられます。寺号の由来となった「因縁相応」についても、具体的な記述は本文からは読み取れません。
2. 超昇寺の意義と南都仏教との関係
超昇寺は、東大寺真言院に次ぐ南都における二番目の真言寺院とされています。その後の沿革から、南都の僧侶たちとの深い関わりがうかがえます。例えば、興福寺の僧兵であった清海(?~1017)が入寺した記録があり、その後、清海曼荼羅の作成や超昇寺大念仏などが行われ、南都における阿弥陀信仰の拠点の一つとなっていったことが知られています。壱演が超昇寺の座主を務めていた時期は晩年であり、拠点としていたわけではないと推測されますが、彼の経歴からも、超昇寺と南都仏教全体との密接な関係を理解する上で重要な寺院であることがわかります。本文では、超昇寺の創建に関する具体的な記述は少なく、その歴史や壱演との関わりについては、更なる研究が必要となります。 しかし、清海の事例に見られるように、超昇寺は阿弥陀信仰の中心地として、南都仏教界に大きな影響を与えていたことがわかります。
III.感応寺の創建と牛頭天王
感応寺の創建は、壱演が鴨川西岸で霊験を見、清原惟人という人物との関わりを経て建立されたと伝えられています。本尊は観音ですが、牛頭天王も祀られており、病気平癒や安産などの利益を祈願する寺として発展していきました。牛頭天王は疫神としての側面も持ち、後の祇園御霊会にも繋がる要素を含んでいます。感応寺の所在地は淀川に近いことから、相応寺と同様に壱演の遊行的行動と関連付けられます。
1. 感応寺の創建伝承と霊験
感応寺の創建は、壱演が寺院建立の誓願を立て、洛陽の河崎で鴨川の西岸に紫雲がたなびき蓮華が降るという霊験を目撃したことに始まります。この現象は「天地相応、感応道交」の現れとして受け止められ、寺院建立にふさわしい場所と判断されました。本尊は蓮華王にちなんで観音とされ、寺名は感応寺と名付けられました。 縁起によると、この地の本主を名乗る清原惟人という翁が現れ、自身が牛頭天王の化身であると告げ、伽藍の守護と引き換えに、清原氏を別当とすることを壱演に承諾させました。牛頭天王は、伽藍の守護、清原氏の守護、そして疫病の難患除去などを約束しており、感応寺が病気平癒や安産などの利益を祈願する寺として発展していく礎となりました。 感応寺の創建時期については、承澄の『阿娑縛抄』「諸寺略記」が比較的古い史料として挙げられており、そこでは陽成天皇の時代である元慶年間の創建とされています。 この創建縁起は、感応寺が病気平癒や安産などの霊験を持つ寺として、人々の信仰を集めていたことを示しています。
2. 牛頭天王と感応寺の信仰
感応寺には、本尊の観音像に加え、牛頭天王像が祀られていました。縁起では、本尊に関する記述が曖昧な一方、「口伝輙不云」という表現から、本来の本尊は秘仏もしくは秘仏に準ずる扱いだった可能性が示唆されます。牛頭天王は、天神堂に安置され、本尊を補完する役割を担っていました。『元亨釈書』では、牛頭天王が五月五日の端午の節句にのみ目を覚まし、その気が薬や毒、悪瘡、疾疫などになると記されています。牛頭天王が疫神として祀られ、祇園御霊会が定着し始めるのは10世紀からですが、感応寺では、平安時代末期には病気平癒や安産などの利益が牛頭天王の霊験として具体化されていたと考えられます。感応寺が鴨川の西岸に位置する点は、淀川近くの相応寺と共通しており、船による移動が多かった壱演の行動様式を反映している可能性があります。また、清原氏との関わりも指摘されており、その関係性については今後の研究課題となっています。
3. 感応寺の創建と壱演の活動との関連性
感応寺の創建伝承は、壱演の遊行的行動と密接に関連しています。 鴨川西岸という立地は、淀川に近い相応寺と類似しており、船による移動を好んだ壱演の行動様式を反映していると推測されます。 また、清原氏ゆかりの場所であり、牛頭天王が守護神として位置づけられていることも、この寺院の性格を理解する上で重要な要素です。 感応寺の創建に関する記述は伝承に頼るところが大きく、史料不足から実像の解明は困難です。しかし、養和二年(1182)の『養和二年記』には、安倍泰忠が感応寺を参詣した記録があり、少なくとも12世紀初頭には既に存在していたことが分かります。 これは、感応寺の創建が壱演によるものという伝承の信憑性を高める材料の一つと言えるでしょう。 しかし、感応寺の創建時期や壱演との関わりについては、更なる史料の発見と分析が必要不可欠です。
IV.清和院と地蔵信仰
清和院は、当初は仏心院として、清和天皇の母である染殿后(藤原明子)の勧進によって、比叡山の僧正が制作した地蔵尊が安置されたのが始まりとされています。その後、地蔵信仰の寺として発展し、鞍馬寺との関係も指摘されています。この地蔵尊に関する伝承は、寺院の宣伝活動の一環として成立した可能性も考えられます。
1. 清和院の地蔵尊と創建経緯
清和院(前身は仏心院)に安置された地蔵尊は、清和天皇の母である染殿后(藤原良房の娘、明子)の勧めにより、比叡山の一階僧正に命じて彫刻されたと伝えられています。 地蔵尊の大きさは天皇の等身大である六尺二分とされ、衣木は鞍馬寺の毘沙門天建造の余木を使用したとされています。これにより、毘沙門天は毎月五日間、寺に止住して仏法を擁護するという伝承が結びついています。 『地蔵菩薩三国霊験記』(以下『霊験記』)巻十三の七「清和院ノ像」には、この地蔵尊に関する説話が簡略化された形で記されています。『霊験記』は全14巻からなり、巻三までは11世紀中頃に三井寺の実睿によって編纂され、その後、中世の改訂・増補を経て近世初期に良観による大幅な増補が行われたとされています。清和院の地蔵伝承は、12世紀から14世紀初頭に語られ始め、清和院の寺院化の時期とほぼ一致しており、寺院側の宣伝活動の一環であった可能性も示唆されています。 この地蔵尊の伝承は、清和院が地蔵信仰の中心地として発展していく過程を理解する上で重要な要素となります。
2. 壱演と清和院地蔵尊の関連性と史料
壱演は、清和院に安置された地蔵尊の製作に関わっていたとされています。しかし、この関係性は伝承に基づくものであり、史料的な裏付けは乏しいです。 『真言伝』(1325年成立)巻四「権僧正慈済」伝の最後には、壱演と鞍馬寺の関係が記されています。 この記述から、14世紀初頭には既に壱演と鞍馬寺との関係が語られていたことが分かります。 また、『霊験記』や「勧進状」が作成された時期を考慮すると、清和院は12世紀から15世紀にかけて地蔵信仰の寺院として定着していたことがわかります。 壱演が皇太后の病気治療を行っていたという伝承があり、治療した皇太后が明子であった可能性を示唆する「勧進状」の存在も注目されます。 しかし、これらの伝承を史実と結びつけるには、さらなる検証が必要不可欠です。 『霊験記』や「勧進状」の内容は、鞍馬寺が天台化した12世紀以降の状況を反映している可能性が高いと考えられます。
3. 清和院の信仰と壱演の宗教的活動
清和院は、地蔵信仰の中心地として発展した寺院であり、本尊は十一面観音とされています。 この十一面観音は、感応寺の本尊である観音と共通点があり、密教的な要素が強いことも注目されます。 享保九年(1724)9月付の「由緒書」には、壱演筆の『大般若経』や、壱演が所持していた密教法具(鈴、五鈷、三鈷、独鈷)が記されています。 これは、壱演の密教僧としての側面が色濃く示されていると言えるでしょう。 清和院にまつわる伝承は、壱演の宗教的活動、特に地蔵信仰や密教との関わりを理解する上で重要な手がかりとなります。 しかし、これらの伝承は、後世の創作や加筆の可能性も否定できず、その成立背景や信憑性を慎重に検討していく必要があります。 特に、地蔵尊の製作に関わる伝承は、寺院側の宣伝活動として後世に作られた可能性も考慮すべきです。
V.壱演の行動様式と宗教的側面
壱演は『卒伝』によると「不定居処、居留任意」とされ、遊行的で自由な生活を送っていたと推測されます。薬師寺僧としての活動と並行して、各地を船で移動しながら寺院建立や宗教活動を行ったと考えられます。また、密教僧としての側面も強く、所持していた密教法具なども記録に残っています。彼の活動は、単なる寺院建立にとどまらず、地蔵信仰、観音信仰、そして疫病除去などの広範な領域に及んでいたことが分かります。
1. 壱演の遊行的行動様式
『卒伝』には壱演の行動様式が「不定居処、居留任意」、「乗扁舟、信波浮蕩」と表現されており、定住せず自由に各地を移動していたことがわかります。薬師寺僧であったため、通常は旧平城京の薬師寺に居住していたと考えられますが、平安京への移動には船を利用していたと推測されます。超昇寺の座主になったのは晩年であり、拠点としては機能していなかったようです。相応寺の建立年は不明ですが、寺号と四至が定められたのは彼の死の前年であることから、創建は晩年に行われたと推測されます。相応寺は平安京と奈良を結ぶ水路沿いに位置し、彼の遊行的行動の延長線上にあると考えられます。 この自由奔放な行動様式は、彼の宗教活動の広がりや、各地に伝わる多くの寺院建立譚と深く関わっていると考えられます。 彼の活動範囲の広さと、その行動様式の自由さから、当時の社会情勢や交通事情も考慮しながら、その実像を解明していく必要があります。
2. 密教僧としての側面と宗教的活動
享保九年(1724)9月付の「由緒書」には、壱演筆とされる『大般若経』と、彼が所持していた密教法具(鈴、五鈷、三鈷、独鈷)が記されています。これにより、壱演の密教僧としての側面が強く示唆されています。 また、『今昔物語集』では、相応寺の僧であり、金剛般若経の読誦に優れた霊験があったことが強調されています。 このことから、壱演は単なる寺院建立者だけでなく、金剛般若経の持経者として、宗教的な力を持って民衆に影響を与えていた可能性が考えられます。さらに、貞観七年に権僧正に任じられた際の逸話(法名「壱演」の由来)は、彼の沙弥としての身分と、遊行的行動様式を反映したものであり、彼の宗教観や社会との関わり方を示す重要なエピソードとなっています。 彼の宗教活動は、密教、金剛般若経の読誦、そして様々な寺院の建立と、多岐に渡っていたことが分かります。
3. 皇太后の病気治療と宗教的影響力
壱演は年譜に記されているように、皇太后の病気治療を行っていたと伝えられています。 しかし、治療した皇太后の特定は困難であり、正子、順子、明子の三人が候補として挙げられています。「勧進状」は、治療した皇太后が明子であった可能性を示唆する材料の一つとなるかもしれません。 この皇太后の治療という伝承は、壱演が貴族社会においても高い宗教的影響力を持っていたことを示しています。彼の活動は、寺院建立や経典の読誦、密教実践といった宗教活動だけでなく、貴族社会における医療行為にも及んでいた可能性があり、当時の社会における宗教者の役割の多様性を理解する上で重要な事例と言えるでしょう。 しかし、この伝承の信憑性を確認するためには、更なる史料の検討が必要となります。
VI.延福寺と他の寺院建立譚
延福寺は、壱演の父、智治麻呂が備中守を務めていたことと関連付けられ、創建に関わる伝承が残っています。しかし、その信憑性は低いとされています。 他の寺院建立譚も、多くの場合、事実と伝承が入り混じっており、その成立背景には南都諸寺の勢力回復の動きなども関係していた可能性が示唆されています。
1. 延福寺と壱演開基伝承の検証
延福寺は、壱演の開基とされる寺院の一つですが、その所在地は山城国や河内国に集中する他の寺院とは異なり、備中国に位置しています。これは地理的に飛び火的な位置関係であり、他の寺院と比較すると、その関係性の信憑性が低いと言えます。天長六年(829)の創建は、壱演の出家前であるため事実上あり得ません。 延福寺開基伝承が生まれた理由は不明ですが、壱演の父、智治麻呂が備中守を務めていた事実に由来する可能性が高いと考えられます。『備中誌』の縁起には「当国刺史備中守大中臣治知男也」とあり、壱演と備中国との関係性を父の官職に求める記述が見られます。 この記述は、延福寺開基伝承が、壱演の父との繋がりを強調することで、寺院の権威付けや地域社会への浸透を図ろうとした可能性を示唆しています。しかし、その真偽については、更なる史料の発見と検証が必要となります。
2. 延福寺の仏像と壱演をめぐる仏菩薩像
延福寺の本尊は薬師如来、白山権現、明王などであり、壱演をめぐる仏菩薩像の特徴を分析する上で重要な寺院です。白山権現の本地は通常十一面観音とされており、感応寺の本尊と同じ観音であることと、密教色を帯びている点は注目に値します。延福寺は、山の中腹(浄瑠璃山、標高175m)に位置しており、他の壱演と関連する寺院である薗光寺(玉祖神社、高安山、標高488m)、水呑地蔵院(十三峠、標高430m)も山間部に位置していることから、壱演の宗教活動が山岳信仰とも関わりを持っていた可能性も示唆されます。 これらの寺院の本尊や立地条件から、壱演の宗教活動は、薬師如来、地蔵菩薩、観音菩薩といった特定の仏菩薩への信仰を中心に展開していたことが推測されます。しかしながら、延福寺に関わる伝承は、他の寺院と同様に、事実と伝承が混在しており、その成立背景を多角的に考察する必要があるでしょう。
3. 他の寺院建立譚と伝承成立の背景
壱演と関連づけられる寺院建立譚は、山城国と河内国に集中しています。これらの地域は、淀川水系の川筋やその近辺に位置しており、壱演の船による移動と密接に関連していると考えられます。 しかし、これらの伝承は、壱演の死後200年以上経過した12世紀以降に語られ始めるものが多く、その成立時期は明確ではありません。 感応寺が壱演建立とされる最古の記録が養和元年(1181)である事実は、それ以前は壱演の創建を強調しても宣伝効果が薄かったことを示唆しています。 これらの伝承成立の背景としては、11世紀における南都諸寺の寺勢衰退と、その回復策として様々な伝承が作られた可能性が考えられます。薬師寺などの勢力拡大の動きも、壱演に関する伝承の成立に影響を与えた可能性があります。 これらの寺院建立譚は、壱演の実像解明のためだけでなく、当時の南都仏教界の勢力図や信仰状況を理解する上で重要な資料となります。
