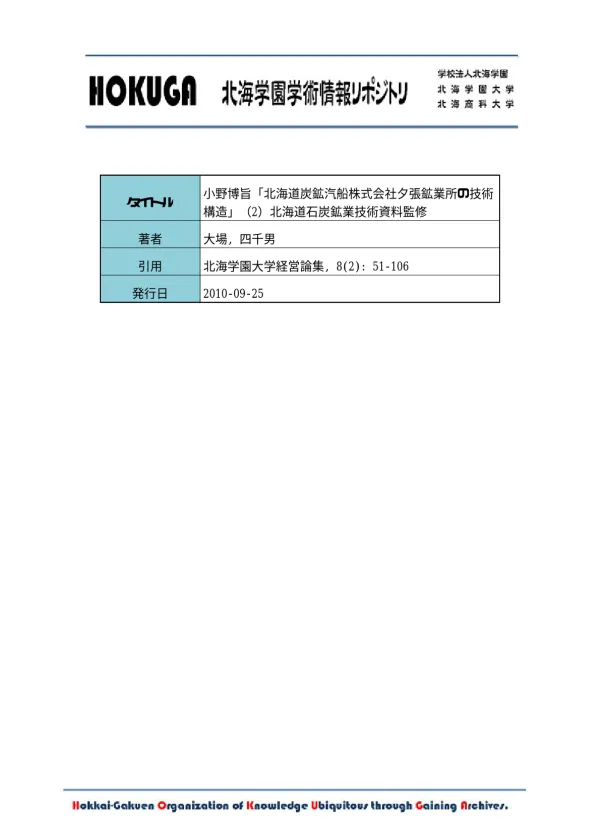
夕張鉱業所生産構造:技術と歴史
文書情報
| 著者 | 大場 四千男 |
| school/university | 北海学園大学 |
| subject/major | 経営論 |
| 文書タイプ | 技術資料 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.57 MB |
概要
I.夕張炭鉱における採炭方法と課題
本資料は、北海道夕張炭鉱、特に北炭(北海道炭礦汽船株式会社)における歴史的な採炭方法と、それに伴う課題を分析したものです。主要な炭層である本層(24尺層)はガスと炭塵が多く、自然発火の危険性が高いという特徴がありました。そのため、区画採炭法が採用され、各区画の採炭終了後は連絡坑道の密閉が徹底されました。これはガス突出や自然発火防止の重要な対策でした。採炭方法としては、長壁式採炭、片盤向長壁式総払法などが用いられ、坑内機械化も進められていました。コールカッター、ローダー、チェンコンベヤーなどの機械が導入され、連続機械採炭の効率化が図られました。しかし、山圧による天盤崩落や坑道の狭窄、機械故障などが課題として挙げられています。特に、標準作業量の設定や労働争議、安全管理の問題などが、生産性と労働者の安全性の両立という観点から詳しく分析されています。
1. 主要炭層の特徴と採炭方法
夕張炭鉱の主要炭層である本層(24尺層)は、ガスと炭塵が多く、自然発火しやすいという危険性を孕んでいました。このため、安全な採炭方法の確立が喫緊の課題となりました。資料によると、運搬や通気の主要坑道は下盤岩石中に設けられ、小立坑、小斜坑、竪坑などを用いた区画採炭法が採用されています。これは、各区画を独立させて採掘することで、ガス突出や自然発火のリスクを最小限に抑えるための工夫です。一区画の採炭が終了したら、直ちに連絡坑道を密閉することで、自然発火の誘発を防止するシステムが確立されていました。この密閉作業は、現場作業員にとって重要な役割の一つでした。さらに、本層における採掘方法として片盤向長壁式総払法が実施されており、各採炭切羽間は炭柱によって隔離されています。一区画の延長は約300メートルと記述されており、これは安全確保と効率的な採掘を両立するための、綿密な計画に基づいた数値であると考えられます。 危険性の高い炭層での採炭において、安全性を最優先した採掘方法と、その管理体制が示されています。
2. 充填と崩落防止対策
ガスや炭塵の問題に加え、山圧による天盤崩落も深刻な課題でした。坑道崩落を防ぐため、上添とゲートに幅4メートルの充填作業が行われていました。これは、人工の壁を構築することでゲート坑道や上添坑道への影響を防ぎ、同時にガスの押し出しも防ぐという重要な役割を果たしていました。しかし、この充填作業は直接的な効果が目に見えにくいことから、作業員は石炭や古材を適当に詰めたりするなど、作業の質にばらつきが生じていた可能性が示唆されています。ロングが遠くなるほど山圧の影響を受けやすく、天盤崩落や坑道の狭窄が進行し、ベルト坑道にも悪影響を及ぼしていました。このことから、効果的な充填方法の改善や、作業員の意識向上を図る必要性があったことが読み取れます。第二鉱の例では、下部から10尺、6~8尺層の炭層を採掘し、払跡には3~4メートルの帯状充填を行うなど、場所に応じた対策がとられていたことがわかります。切羽面長は約100メートルと記載されていますが、これは地質条件によって変化する可能性があり、柔軟な対応が必要だったことを示唆しています。
3. 坑内機械化の進展と課題
資料では、坑内機械化の進展と、それに伴う課題についても言及されています。鉄柱、カッペによる切羽鉄化、コールカッター、ローダー、チェンコンベヤーなどの機械の導入により、連続機械採炭が推進されました。これにより、作業効率の向上と肉体労働の軽減が図られた一方、機械の故障が多発し、標準作業量の引き下げや工数換算時間の操作といった対応を強いられたと記されています。機械化による効率化は、生産性向上に繋がったものの、機械の信頼性や保守・点検体制の整備が、さらなる生産性向上には不可欠であったことが分かります。 また、夕張第一鉱では、切羽の運搬にDCC(ダブルチェンコンベヤー)、中間運搬にBC(ベルトコンベヤー)、後方運搬にディーゼルロコや電車巻上機などが使用されていたことが記載されており、多様な運搬システムが運用されていたことがわかります。昭和30年代には選炭機の合理化も進められ、坑外選炭へと移行しています。 機械化による効率化と、それに伴う新たな課題が提示されています。
4. 標準作業量の問題点と労働問題
標準作業量の設定方法や、それに伴う労働問題も重要な課題として取り上げられています。基準作業量の0.8倍を保証するという制度でしたが、実際には125%、130%、142%と大幅に超過する状況が続き、作業量の決定方法に問題があったことが示唆されています。科学的な方法ではなく、組合の力が介入した結果、標準作業量が恣意的に操作されるようになったと記述されています。機械故障の多発も労働者側の不満につながり、標準作業量を引き下げるという悪循環が生じていました。 これは、労使関係の不透明さや、作業管理、職務管理の不備を反映しており、高能率高賃金の体制を目指しながらも、現場の実情は大きく乖離していたことがわかります。 また、半請負制の賃金制度も、労働者の意欲や責任感の低下に繋がった一因として指摘されています。高賃金が保証された結果、作業完遂への意欲や責任感が薄れてしまい、北炭の労使協調の甘さを象徴する問題として取り上げられています。
II.北炭の生産力拡充と石炭産業の変遷
明治期から昭和期にかけての北炭の生産力拡充の歴史が、石炭産業全体の変遷と絡めて記述されています。明治期は急速な発展を遂げましたが、ガス爆発災害による停滞もありました。大正期には三井物産との関係が深まり、石炭カルテルに組み込まれる形となりました。昭和前期は戦時体制下での増産、特に満州事変以降の戦争特需による急激な成長が見られます。しかし、戦後、重油の輸入増加や輸入炭との競争激化により、石炭産業は衰退へと向かいました。朝鮮戦争の特需による一時的な好況もありましたが、ドッジ・ラインによる経済政策や、労働争議(ストライキ)、高炭価問題などが、石炭産業の危機を招く要因となりました。北炭は新鉱開発や機械化による合理化に取り組んだものの、需要減少や重油への転換が進み、最終的に石炭産業の衰退という結末を迎えました。夕張炭鉱は北炭の主要な炭鉱の一つであり、その盛衰は北炭、ひいては日本の石炭産業の歴史を象徴的に表しています。日産約900トンの採炭を目標に、**DCC(ダブルチェンコンベヤー)やBC(ベルトコンベヤー)**などの運搬設備が用いられていました。
1. 明治期の北炭 躍進とガス爆発災害
明治22年(1889年)に設立された北炭は、明治期には100万トンを超える出炭高を誇り、井上角五郎の指導の下、躍進を遂げました。多角化戦略や重工業への進出も図られ、北海道における代表的な企業として発展を遂げていました。しかしながら、明治期後半には夕張鉱で二度の大規模なガス爆発事故が発生し、企業の成長に大きな影を落としました。これらの事故は、北炭の歴史において転換点となり、安全対策の強化や経営戦略の見直しを迫る事態となりました。 これらの災害は、北炭の事業展開に大きな影響を与え、安全対策の重要性を改めて認識させる契機となったと同時に、今後の発展における課題を浮き彫りにしました。 ガス爆発災害という負の側面と、生産力拡充という発展の側面が、明治期の北炭を特徴付けています。
2. 大正期の北炭 三井系への組み込みと停滞
大正期に入ると、北炭は石炭不況と、明治期末のガス爆発災害の影響を受け、経営は苦境に陥りました。その結果、大正2年の株主総会では三井物産が人事権を掌握し、団琢磨、磯村豊太郎を中心とする経営陣が誕生しました。以降、北炭は三井物産、三池鉱山との三社販売協定を結び、三井物産の石炭カルテル体制に組み込まれることになります。これは、北炭の独立性を失い、三井の下請け企業として機能することになったことを意味します。大正2年から6年にかけての出炭高は、110万トン弱から176万トンへと増加したものの、これは三井系企業としての活動を反映したものであり、自主的な生産力拡充によるものではありませんでした。 この時代は、北炭の自主性を失い、三井系企業としての枠組みの中で事業を展開していった時代であったと言えます。
3. 昭和前期の北炭 戦時体制下での増産
昭和前期は、満州事変から太平洋戦争へと続く戦時体制下で、北炭は再び大きな成長を遂げました。満州事変の拡大に伴い戦争特需が拡大し、日本のエネルギー政策において石炭の重要性が増す中、北炭は軍需産業としての役割を担うことになります。 石油統制により、日本のエネルギー市場は石炭がほぼ独占する状況となり、この「石炭革命」と呼ばれる時代に、北炭は昭和2年から19年にかけて出炭高を310万トンから530万トン弱へと大幅に増加させました。これは新鉱開発(平和鉱、天塩鉱、赤間鉱、末広鉱、羽幌鉱など)と既存炭鉱の深部開発による成果でした。 この期間の生産力拡充は、国家政策に大きく依存したものであり、北炭の自主的な経営努力というよりも、戦時体制という特殊な状況下での成果であったと言えるでしょう。
4. 昭和後期 石炭産業の衰退と北炭の対応
朝鮮戦争の特需により一時的に石炭需要が拡大したものの、昭和後期には重油の輸入増加と中近東原油の国内生産開始により、石炭産業は石油との競争に直面し、衰退への道を歩み始めます。北炭も例外ではなく、昭和26年の361万トンから30年には311万トンへと出炭高が減少しました。政府は石炭臨時措置法を制定し、石炭産業の維持に努めますが、高炭価問題、労働争議(1952年の63日間のスト)、そして重油への転換という大きな流れは止められませんでした。 北炭は、増産によるコスト削減や新鉱開発に取組みましたが、需要減少と重油への転換という大きな潮流には抗えず、石炭産業全体の衰退という厳しい現実を突きつけられました。 この時代は、石炭産業の衰退期であり、北炭もその影響を大きく受け、企業存続のための様々な努力をした時代と言えるでしょう。
III.夕張新鉱開発と労働問題
夕張新鉱の開発は、政府の石炭政策に大きく左右され、鉄鋼産業の原料炭不足を背景に推進されました。新鉱開発は、坑道整備の遅れや地質条件の悪さといった様々な困難に直面しました。ガスの問題は特に深刻で、ガス抜きの不十分さが事故の原因の一つとして分析されています。また、労働問題も大きな課題でした。請負制や標準作業量の設定、能率給の問題などが、労働者の意欲や安全意識に影響を与えていたことが指摘されています。特に、高賃金と安定した生活を確保した結果、労働者の作業完遂意欲や責任感が低下していたことが問題視されています。これは、北炭における労使関係の甘さと、安全管理体制の不備を反映しています。 夕張新鉱の従業員数は1500戸の社宅に住む従業員を含む多数にのぼりました。
1. 夕張新鉱開発の背景と経緯
夕張新鉱の開発は、昭和43年12月の調査開始から17年後の昭和60年、鉄鋼産業の原料炭不足という国家的な危機感と、政府の強い後押しによって実現しました。鉄鋼産業向け石炭の供給不足を解消するため、政府は新鉱開発に補助金を交付し、三菱南大夕張、三井有明鉱と共に北炭の夕張新鉱開発を積極的に支援する政策を打ち出しました。北炭にとって、夕張新鉱開発は企業存続を賭けた一大事業であり、まさに国策としての位置づけにあったと言えます。 開発開始当初から地質条件の悪さや、工事の遅れなど多くの困難に見舞われ、坑口設定のコンクリート工事や本格的な掘進作業においても予想以上の遅延が発生しました。 これは、夕張新鉱開発が、国家的課題として推進されたものの、技術的、地質的な困難も伴う大規模な事業であったことを示しています。
2. 夕張新鉱の生産構造と労働者の日常
資料では、夕張新鉱における1人の採炭員の1日の行動を通して、新鉱の生産構造が描かれています。国鉄清水沢駅から約800メートル離れた場所に建設された1500戸の近代的な社宅から従業員は通勤し、長さ1200メートルの通勤用隧道を通って職場へ向かいます。 採炭現場では、ロング面(面長150メートル、高さ2.5メートル)で、ダブルレンジングコールカッター、ローダー、チェンコンベヤーなどを用いた機械化された採炭作業が行われていました。1200トンの出炭計画があり、ステープル用員、枠操作組など役割分担された作業が行われています。 しかし、作業環境は決して良好ではなく、高温多湿で炭塵も多く、作業員の健康面への配慮も必要だったことがわかります。また、自走枠の操作ミスによる山の崩落や倒枠事故も頻繁に発生し、安全対策の徹底が求められていたことが分かります。 これは、夕張新鉱の生産現場が、高度な技術と安全対策を必要とする、過酷な労働環境であったことを示しています。
3. 夕張新鉱における労働問題 請負制とモチベーション
夕張新鉱の労働現場では、請負制の賃金制度が採用されており、労働者のモチベーションや作業への取り組み方に影響を与えていたことがわかります。請負支柱の職場が完成し現場がなくなった際に、請負給を支給する救済策がとられましたが、その結果、労働者の労働意欲や責任感の低下につながっていることが指摘されています。 高賃金が保証されているため生活は安定し、理由があれば休む、働いても働かなくても同じ賃金がもらえる状況は、作業完遂意欲や責任感の低下を招き、北炭の労使協調の甘さと、安全管理体制の不備を反映していると記述されています。 これは、賃金制度と労働者のモチベーション、そして安全意識との関連性を示す重要な指摘であり、夕張新鉱における労働問題の一端を示しています。 また、ガス状況や山の状況の点検・指導を行う係員の役割も記述されており、安全管理の重要性が強調されています。
4. 夕張新鉱における安全管理とガス問題
夕張新鉱では、ガス問題が大きな安全上の課題でした。盤下坑道から採炭切羽へのボーリングが断層に当たると、ガス抜きが不十分になる「ジャミング現象」が発生する危険性がありました。 このガス問題は、夕張炭鉱全体における地質条件やガス抜き体制の不備を明らかにする重要な要素であり、事故発生の潜在的なリスクを示唆しています。 さらに、発破作業における安全管理についても詳細が記されており、発破作業前のガス測定、点火作業、そして退避手順といった一連の作業手順が厳格に守られていることがわかります。 しかし、それでもなお、作業中の事故リスクは常に存在し、労働者の安全確保のための不断の努力が不可欠であったことがわかります。 これらの記述から、夕張新鉱開発において、安全管理とガス対策がいかに重要な課題であったかが読み取れます。
