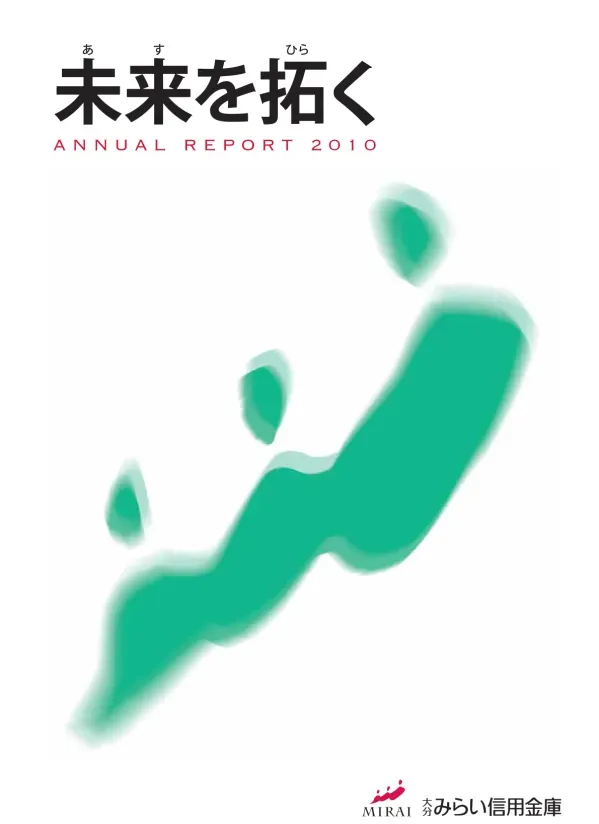
大分みらい信金:地域密着の未来戦略
文書情報
| 著者 | 大分みらい信用金庫 |
| 会社 | 大分みらい信用金庫 |
| 場所 | 大分県 |
| 文書タイプ | Annual Report |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.73 MB |
概要
I.地域密着型金融と顧客満足の向上
当信用金庫は「地域密着型金融」を経営理念の中心に据え、大分県内の中小企業支援に力を入れています。具体的には、地域力連携拠点(大分県産業創造機構、大分県中小企業団体中央会、大分県商工会連合会)との連携による課題解決支援、融資におけるきめ細やかな対応、そして顧客満足の向上を目指した取り組みを継続しています。過去には不祥事がありましたが、コンプライアンスの強化、リスク管理の徹底により信頼回復に努めています。
1. 地域密着型金融の推進
当金庫は『地域に根ざし、未来を拓く』を経営理念に掲げ、地域密着型金融の深化による顧客満足の創造に取り組んでいます。具体的には、金融円滑化法への対応、地域力連携拠点(大分県産業創造機構、大分県中小企業団体中央会、大分県商工会連合会)を活用した取引先の課題解決活動、CSRの一環としての環境ローンの推進などを実施してきました。取引先へのプラットフォーム的役割を担い、各拠点のコーディネーターと協力して、きめ細やかな課題解決支援を提供しています。資金需要や貸付条件変更の要請にも真摯に対応し、密度の濃いコミュニケーションを通じてお客様の問題を把握し、解決に向けた対応に努めています。 この地域密着型の取り組みは、単なる融資業務にとどまらず、顧客との長期的な信頼関係構築を重視したリレーションシップバンキングと言えるでしょう。顧客の事業内容を継続的にモニタリングし、様々な提案を行うことで、リスク軽減にも繋げています。
2. 顧客満足度向上のための取り組み
顧客満足度の向上は、当金庫の経営における最重要課題の一つです。そのため、お客様とのコミュニケーションを重視し、きめ細やかな対応を心がけています。具体的には、資金需要や貸付条件の変更等の要請を真摯に受け止め、十分なヒアリングを行い、お客様の抱える問題を理解した上で、最適な解決策を提案しています。また、モバイルバンキング、為替自動送金サービス、自動振替サービス、テレホンサービス・ファクシミリサービスといった便利なサービスを提供することで、利便性の向上にも努めています。これらのサービスは、お客様の負担を軽減し、よりスムーズな取引を可能にすることを目的としています。さらに、個人情報の保護に関する法律やガイドラインを遵守し、情報セキュリティ対策を徹底することで、お客様の安心・安全を確保することに尽力しています。
3. 平成21年不祥事と信頼回復への取り組み
平成21年11月に発生した2度目の不祥事を受け、九州財務局から業務改善命令を受けました。この事態を重く受け止め、多大なご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。信用金庫の原点に立ち返り、改善計画を着実に推進することで、皆さまからの信頼回復に全力を尽くしています。具体的には、コンプライアンスの徹底、内部管理体制の強化に注力しています。平成21年度には全店で1,165回のコンプライアンス勉強会を開催し、コンプライアンス検定試験の受験を奨励するなど、職員一人ひとりのコンプライアンス意識向上に努めています。また、『コンプライアンス手帳』の活用による定期的な自己チェックなども実施し、再発防止に真剣に取り組んでいます。この信頼回復への取り組みは、地域社会からの信頼を維持し、持続可能な発展を遂げるための不可欠な要素です。
II.内部管理体制の強化と信頼基盤の確保
平成21年の不祥事を受け、内部管理体制の強化は最優先事項となっています。不正防止策、規程の充実、検証態勢の強化など、コンプライアンス遵守を徹底し、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク(事務リスク、システムリスク等)といった様々なリスクへの対策を講じています。自己資本比率の維持向上にも注力し、バーゼルⅡへの対応も万全です。約1600名の会員を擁する組織として、安定した経営基盤を構築しています。
1. 不祥事への対応とコンプライアンス強化
平成21年11月の不祥事発覚とそれに続く九州財務局からの業務改善命令を受け、当金庫は内部管理体制の抜本的な強化に乗り出しました。不正を防止するための対策、諸規程の充実、検証体制と相互牽制機能の強化に重点的に取り組みました。コンプライアンス遵守の徹底は、信頼回復の第一歩として認識され、全職員を対象としたコンプライアンス研修(平成21年度は1,165回開催)や、コンプライアンス検定試験の受験奨励など、多角的な取り組みが行われました。さらに、全職員への『コンプライアンス手帳』の配布と定期的な自己チェックの義務化により、コンプライアンス意識の浸透と維持に努めています。これは、単なる法令遵守だけでなく、高い倫理観に基づいた業務遂行を目指した取り組みです。反社会的勢力への対応についても、基本方針を定め、資金提供や不適切な取引を一切行わない体制を整え、外部専門機関との連携強化も図っています。
2. リスク管理体制の構築と高度化
リスク管理体制の構築と高度化は、信頼基盤の確保に不可欠です。信用リスク、市場リスク、流動性リスクといった主要なリスクに加え、事務リスク、システムリスク等のオペレーショナルリスクについても、リスク管理基本方針、リスク管理規程に基づき、各リスクへの対策が講じられています。具体的には、牽制・検証体制の強化、リスク予防策・軽減策の策定・実施、そして万一の場合に備えたコンティンジェンシープラン(危機時対応策)の策定や業務継続計画の整備が進められています。ALM(資産負債管理)委員会による市場金利変動の影響度モニタリングや、バーゼルⅡに対応した金利リスク量の算出なども行い、総合リスク管理会議、総合リスク管理委員会、ALM会議、ALM委員会といった会議体を通じた効率的・効果的なリスクマネジメント体制を構築しています。これらのリスク管理に関する取り組みは、経営の健全性と適正な収益確保の両立を目指したものです。
3. 自己資本比率の維持向上と経営の健全性
経営の健全性を維持し、信頼基盤を強化するためには、自己資本の充実が不可欠です。当金庫は、利益準備金、特別積立金、繰越利益剰余金などを積み立て、連結自己資本額231億9千万円を確保しています。自己資本比率、基本的項目(Tier1)比率は共に国内基準の4%を大きく上回る水準に達しており、安定した経営基盤を維持しています。さらに、信用格付システム、貸出債権管理システム、不動産担保評価システム等の導入により、審査・貸出・担保評価のプロセス管理を強化し、与信運営の適正化を図っています。信用リスク管理状況については、信用リスク管理プロセス委員会において、与信状況や大口与信先等の事業内容をモニタリングし、情報共有を行う体制が確立されています。また、信用リスク管理の高度化や信用リスクの計量化についても、総合リスク管理委員会やALM委員会で協議・検討を行い、理事会への報告・付議を行う体制を整えています。
III.自己資本と財務状況
当信用金庫は、自己資本の充実を図り、健全な財務状況を維持しています。利益準備金、特別積立金、繰越利益剰余金などを積み立て、自己資本比率は国内基準を大きく上回っています。ALM(資産負債管理)についても、市場金利変動への影響をモニタリングし、適切な対応を取っています。貸出金については、貸倒引当金を適切に計上し、信用リスク管理プロセス委員会によるモニタリング、情報共有を実施しています。破綻先債権、延滞債権等の状況も定期的に開示しています。
1. 自己資本比率の状況と維持向上への取り組み
当金庫は、自己資本比率の維持向上に積極的に取り組んでおり、利益準備金2百万円、特別積立金5百万円、繰越利益剰余金27百万円を積み立て、連結基本的項目(Tier1)を算出しています。連結自己資本額は231億9千万円に達し、自己資本比率と基本的項目(Tier1)比率は共に国内基準の4%を大きく上回っており、健全な財務状況を維持しています。これは、これまでの業務推進を通じて得られた利益を主に資本積み上げに充ててきた結果です。 連結子会社である株式会社べっしん綜合サービスも含め、自己資本充実を図り、今後も収益管理強化による精緻な事業計画策定、適正利益確保による自己資本積み上げを継続することで、安定した経営基盤の維持・強化に努めていきます。 また、信用格付システム、貸出債権管理システム、不動産担保評価システムなどの導入により、審査・貸出・担保評価のプロセス管理を強化し、より厳格なリスク管理体制を構築しています。
2. 信用リスク管理とALM 資産負債管理
当金庫は、信用リスク管理についても、綿密なモニタリングと情報共有体制を構築しています。信用リスク管理プロセス委員会において、与信状況や大口与信先等の事業内容をモニタリングし、情報共有を行うことで、リスクの早期発見と適切な対応に努めています。さらに、信用リスク管理の高度化、信用リスクの計量化については、総合リスク管理委員会やALM委員会で協議・検討を行い、必要に応じて総合リスク管理会議・ALM会議(常勤理事会)や理事会に報告・付議しています。ALM(資産負債管理)に関しては、ALM委員会において市場金利が1%上昇した場合の現在価値変動額を算出し、自己資本比率への影響をモニタリングし、ALM会議に報告する体制を整備しています。バーゼルⅡのアウトライヤー基準にも対応しており、市場金利が2%上昇した場合の金利リスク量も算出しています。これらの取り組みは、適切な与信運営と経営の安定性を確保するための重要な要素です。
3. 貸倒引当金計上と債権管理
当金庫の貸倒引当金は、予め定めた償却・引当基準に則り計上されています。破綻先、実質破綻先、破綻懸念先への債権については、担保の処分可能見込額や保証による回収可能見込額を控除した上で、残額を計上しています。破綻先債権額は813百万円、延滞債権額は9,850百万円となっています。これらの数値は貸倒引当金控除前の金額であり、全てが損失となるわけではありません。貸出条件緩和債権についても、債務者の経営再建または支援を目的とした金利減免、支払猶予などの措置を行った貸出金で、破綻先債権等に該当しないものを指します。破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権、貸出条件緩和債権の合計額は12,605百万円です。 また、ローン・パーティシペーションについては、日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号に基づき会計処理を行っています。融資未実行残高は、必ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
IV.情報開示と顧客保護
当信用金庫は、法令等遵守(コンプライアンス)、顧客保護を重視し、透明性のある経営を心がけています。法定開示項目をはじめ、経営の考え方、事業計画、地域への関わりについて積極的に情報を開示しています。また、個人情報保護についても、関係法令を遵守し、継続的な改善に努めています。
1. 情報開示の取り組み
当金庫は、お客様に当金庫に対する理解を深めていただくため、法律(信用金庫法第89条で準用する銀行法第21条)の規定に基づく法定開示項目をはじめ、経営の考え方、事業計画、地域への関わりについて積極的に情報を開示しています。平成19年3月期からは、バーゼルⅡの適用、金融庁告示第16号、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針により開示項目が示されており、それらにも則り、適切な情報開示に努めています。これは、透明性のある経営体制を構築し、お客様からの信頼を維持・向上させるための重要な取り組みです。自己資本比率に関する情報も、自己資本比率告示に基づき、連結自己資本比率を算出する対象となる連結グループに関する情報を含め、適切に開示しています。これらの開示情報は、当金庫の経営状況や財務状況を把握するために役立ち、お客様の投資判断や取引判断に資するものです。
2. 顧客情報のプライバシー保護
当金庫は、お客様の個人情報の保護を社会的責任として認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、その他の関係法令等を遵守しています。従来からお客様の情報やプライバシー保護に努めてきた実績があり、コンピュータ社会の進展などの社会環境の変化にも対応し、継続的な改善と機密性・正確性の確保に努めています。 これは、お客様からの信頼を維持するために不可欠な要素であり、当金庫の事業活動において最も重要な事項の一つとして位置付けられています。個人情報保護に関する具体的な措置については、別途詳細な説明を設けていますが、基本的には、法令遵守を徹底し、不正アクセスや情報漏洩等のリスクを最小限に抑えるための体制を整えています。 お客様の個人情報は、厳重に管理され、適切な目的の範囲内でのみ利用されます。
