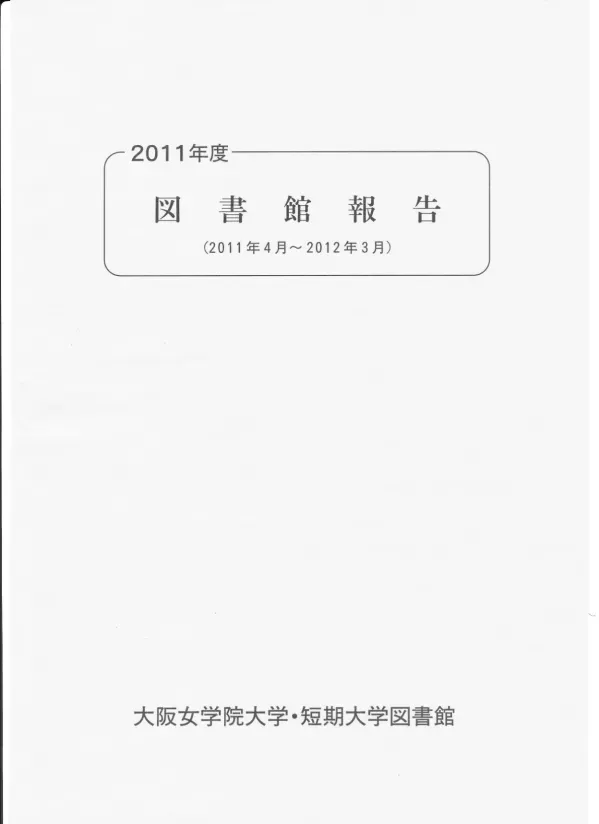
大学図書館年報:学術リポジトリ連携
文書情報
| 著者 | 大阪女学院大学・短期大学図書館職員 |
| 学校 | 大阪女学院大学・短期大学図書館 |
| 専攻 | 図書館学 |
| 文書タイプ | 図書館報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 13.42 MB |
概要
I.学生の図書館利用状況と変化する学習環境
本報告書は、近年めざましい変化を遂げている大学図書館を取り巻く環境、特に学生の学習スタイルの変化と、それに伴う図書館サービスのあり方についてまとめたものです。具体的には、学生がサーチエンジンやブログ・YouTube・Twitter等のインターネット媒体を情報収集に日常的に利用するようになったこと、大学教育が従来の講義形式からアクティブラーニングやオープン教育へとシフトしていることなどが挙げられます。これらの変化に対応するため、大学・短期大学・大学院における教育充実を支援するべく、図書館職員は情報収集、組織化、提供方法の工夫を継続していく必要があると結論付けています。貸出冊数の減少傾向も示されており、学生アンケートの結果と合わせて分析する必要があります。 特に、キャリアコーナーの資料の貸出期間の短さや延滞金制度に関する学生からの意見が多く見られました。
1. 学生の情報収集方法の変化
現代の学生は、図書館資料だけでなく、サーチエンジン、ブログ、YouTube、Twitterなどの多様な情報源を日常的に利用して情報収集を行っています。これは、学生を取り巻く情報環境が大きく変化していることを示しています。以前は図書館資料が主要な情報源でしたが、インターネットの普及により、学生は自ら能動的に、そして多角的に情報を収集できるようになりました。この変化は、図書館が提供するサービスについても、従来の情報提供方法に加えて、新たな情報アクセス方法への対応や、多様な情報源を効果的に活用できるための支援が必要であることを示唆しています。学生の主体的な学習スタイルの変化に対応するため、図書館は単なる情報提供場所から、学生の学習を支援する積極的な役割を担う必要があります。具体的には、デジタルリテラシー教育の支援や、多様な情報源の評価・活用方法の指導などが必要となるでしょう。
2. 大学教育におけるアクティブラーニングへのシフト
近年、大学教育は知識伝達型の講義中心から、学生の自主的な学習を促すアクティブラーニングやオープン教育へと大きく変化しています。アクティブラーニングでは、講義、図書、インターネットなどから得られた情報を学生自身が吟味し、他者と議論・協働しながら自身の考えを深めていくことが重視されます。この学習スタイルの変化は、図書館の役割を大きく変える可能性を持っています。従来のように、単に資料を提供するだけでなく、学生がグループワークやディスカッションを行うためのスペース提供、情報リテラシー教育、情報検索スキルに関する指導など、より積極的な学習支援が求められています。図書館は、アクティブラーニングを支援するための情報環境整備や、学生同士の協調学習を促進する場としての役割を担うことが期待されています。図書館職員は、これらの変化を踏まえ、学生の学習スタイルに合わせた柔軟な対応が求められています。
3. 減少する図書館利用と学生アンケートの結果
近年の学生の図書館貸出冊数は減少傾向にあり、本年度もさらに減少しました。短期大学生は前年比4冊減の23冊、大学生は前年比5冊減の21冊と、過去5年間で最低となりました。この減少傾向は、学生アンケートの結果からも裏付けられています。アンケートでは、「図書館をほとんど利用しない」と回答した学生が、大学4年生を除く全ての学年で増加しました。この結果から、学生の学習方法の変化や、インターネットの普及による情報アクセス方法の変化が、図書館利用の減少に大きく影響していると考えられます。図書館は、減少する貸出冊数という現状を真摯に受け止め、学生のニーズを的確に捉えたサービス提供、情報環境の整備、そして、利用促進のための積極的な広報活動などを検討する必要があります。学生の学習スタイルの変化を理解し、それに対応したサービス提供を行うことが、図書館の存続と発展に不可欠です。
II.図書館の課題と取り組み
図書館は、18歳人口減少と国公私立大学の基盤的経費削減という厳しい環境下にあります。そのため、本学図書館も、蔵書スペースの限界を超える状況に直面し、蔵書の見直しと大量の廃棄、移転作業を行いました。 また、iPad等のタブレット端末利用環境の整備や学内Wi-Fiネットワークの導入など、変化への対応策も進めています。夜間開館業務については、従来の派遣職員から大学生アルバイトへの体制変更を行いました。
1. 厳しい財政状況と図書館運営
日本の大学を取り巻く環境は、18歳人口の減少と国公私立大学の基盤的経費削減傾向により、全体として厳しさを増しています。本学も例外ではなく、学生・教職員の教育・研究支援のためには、変化を先取りする知恵が求められています。この厳しい財政状況下において、図書館は限られた予算の中で、効率的な運営と質の高いサービス提供を両立させる必要に迫られています。具体的には、蔵書点検、廃棄、移転といった、図書館運営の効率化のための作業を実施しました。また、新図書館建設の遅延により、既存の蔵書スペースの限界を超えたため、蔵書の見直しと大量の廃棄作業を行い、スペース確保に努めました。これらの課題を克服し、効果的な予算配分と、サービスの維持・向上を図るための戦略が必要とされています。
2. 蔵書スペースの限界と対応策
新図書館の完成が遅れたため、蔵書の収容冊数が限界を超え、深刻なスペース不足の問題が発生しました。そのため、当面はスペース確保を最優先課題として、蔵書の見直しと大量の廃棄作業、そして図書の総移動作業を行いました。これは、図書館運営における大きな負担となりましたが、現状を打開するための不可欠な措置でした。この経験から、将来的な蔵書スペースの確保や、デジタル化による資料保存の検討など、より長期的な視点に立った計画が必要であることが浮き彫りになりました。また、スペースの有効活用や、学生のニーズに合わせた資料の選定・配置も、今後の課題として挙げられます。限られたスペースの中で、より多くの学生が快適に利用できる図書館空間を維持・向上させていくための戦略が重要です。
3. デジタル化への対応と人員体制の変更
大学の授業にiPadなどのタブレット端末が導入されるなど、デジタル化が急速に進んでいます。本学図書館も、11月よりWi-Fiネットワークの利用を開始するなど、情報環境の整備を進めています。また、夜間開館業務については、これまで派遣会社職員に委託していた業務を、大学生アルバイトに担わせる体制に変更しました。サービスの範囲は限定されますが、大学生は図書館の業務をしっかりと果たしてくれました。この人材確保の工夫は、限られた予算の中で効率的な図書館運営を行う上で、重要な取り組みと言えます。しかしながら、デジタル化に伴う新たな課題も生まれてきており、デジタル資料へのアクセス支援や、デジタルリテラシー教育の提供など、図書館の役割はさらに広がりつつあります。今後も、変化に柔軟に対応できる体制づくりが必要となるでしょう。
III.学術情報リポジトリ構築と図書館活動
国立情報学研究所(NII)の学術機関リポジトリ構築連携支援事業に2年間携わり、研究成果物、学内出版物、大学教材を中心にデータ構築を行いました。2010年には「大阪女学院学術機関リポジトリ」を一般公開しました。委託金は、2011年度は100万円、2012年度は180万円でした。 その他、図書館活動としては、私立大学図書館協会西地区部会阪神地区協議会や私立短期大学図書館情報委員会への参加、様々な図書館関連団体との連携、レファレンスサービスの提供、利用指導の実施などが行われました。
1. 国立情報学研究所 NII 学術機関リポジトリ構築連携支援事業
本図書館は、国立情報学研究所(NII)の学術機関リポジトリ構築連携支援事業に2年間携わりました。2011年度は180万円の委託金を受け、研究成果物、学内出版物、大学教材を中心にデータ構築を行いました。2012年1月には実地調査が行われ、その経験を基に、年度末には業務完了報告書を作成しました。この事業を通して、学術情報のデジタル化と公開という、現代の大学図書館にとって重要な課題に取り組むことができました。 2010年度は100万円の委託金を受け、資料の電子化および登録業務を委託するなど、リポジトリ構築に向けた取り組みを進めており、6月7日には『大阪女学院学術機関リポジトリ』を一般公開しました。この事業は、大学における研究成果の可視化と情報共有を促進する上で重要な役割を果たしています。
2. 図書館情報システムとデジタル化への対応
図書館では、大学の授業に導入されているiPadなどのタブレット端末の利用環境整備に対応するため、11月よりWi-Fiネットワークが利用可能となりました。これは、学生が図書館内でより快適にデジタル機器を利用できる環境整備に繋がります。 また、従来、夜間開館業務は派遣会社職員に委託していましたが、今年度は大学生アルバイトに担当させることになりました。サービス範囲は限定されますが、大学生は責任感を持って業務を遂行してくれました。この取り組みは、コスト削減と学生雇用促進の両面で効果を発揮しています。これらのデジタル化への対応は、変化する学生のニーズに対応し、図書館の利用促進に繋がる重要な取り組みです。
3. 図書館関連団体との連携と図書館活動
本年度も、私立大学図書館協会西地区部会阪神地区協議会、私立短期大学図書館情報委員会など、様々な図書館関連団体との連携を積極的に行いました。8月5日には大阪クリスチャンセンターで、小松泰信先生を講師に招き、「電子書籍と図書館における学習環境」をテーマとした研究会を開催し、33校52名が参加しました。 その他、レファレンス共同データベース事業への参加、大学図書館コンソーシアム連合OUSTICEへの契約状況調査回答、日本図書館協会「大学・短期大学・高専図書館調査票」への回答など、情報共有と連携強化に努めました。また、第15回図書館散歩会を開催するなど、地域社会との連携にも積極的に取り組んでいます。これらの活動を通じて、図書館は単独の機関ではなく、広範なネットワークの中で、より効果的に機能していることを示しています。
IV.学生からの意見と今後の展望
学生アンケートの結果、蔵書の不足、必要な資料の貸出中の多さ、キャリアコーナー資料の貸出期間の短さ、延滞金の高さが課題として挙げられました。雑誌の貸出期間延長、就職関連図書の貸出期間延長、延滞金制度の変更などの要望が多く寄せられています。これらの意見を踏まえ、より良い図書館サービスの提供を目指し、改善策を検討していく必要があります。
1. 貸出冊数の減少と図書館利用状況
本年度の学生の図書館貸出冊数は、前年度に引き続き減少しました。短期大学生の平均貸出冊数は23冊(前年27冊)、大学生の平均貸出冊数は21冊(前年26冊)と、いずれも過去5年間で最低を記録しました。この減少傾向は、学生アンケートの結果からも裏付けられます。アンケートでは、「図書館をほとんど利用しない」と回答した学生が、大学4年生を除く全ての学年で増加しています。この減少傾向は、学生の学習方法の変化、インターネットの普及による情報アクセス方法の変化、そして図書館資料以外の情報源の利用増加などが要因として考えられます。 図書館は、この減少傾向を深刻に受け止め、学生のニーズに合わせたサービス改善を図る必要があります。
2. 学生からの意見と課題 蔵書 貸出期間 延滞金
学生アンケートからは、いくつかの課題が指摘されています。まず、蔵書全体が少なく、資料が充実しているテーマとそうでないテーマとの偏りがあるという指摘がありました。必須科目で必要な資料が貸出中で利用できないケースも多いようです。特に、就職活動やTOEIC対策のための資料を扱う「キャリアコーナー」では、貸出期間が短すぎるという意見が多く寄せられました。指定図書の貸出期間も短いという声もあります。さらに、延滞金が1日100円と高すぎる、という意見や、論文作成に不便を感じているという意見も出ています。これらの意見は、図書館のサービス改善、特に資料の充実、貸出期間の調整、延滞金制度の見直しなどを検討する必要があることを示しています。
3. 今後の展望 学生ニーズへの対応と図書館サービスの改善
学生からの意見を踏まえ、図書館は今後のサービス改善に向けて、いくつかの課題に取り組む必要があります。具体的には、蔵書の充実とバランスの改善、特に学生のニーズが高い分野(就職活動、TOEIC対策など)の資料の拡充が必要となります。また、貸出期間の見直し、特にキャリアコーナーの資料の貸出期間延長や、指定図書の貸出期間延長の検討が求められます。さらに、延滞金制度の見直し、例えば、期間に関わらず同額にする、数日経過してから課金するなど、より柔軟な制度への変更も検討すべきです。 また、延滞前にメールで通知するシステム導入なども検討することで、学生の利便性を向上させることができます。図書館は、これらの改善策を通じて、学生の学習を効果的に支援し、利用促進を図っていく必要があります。
