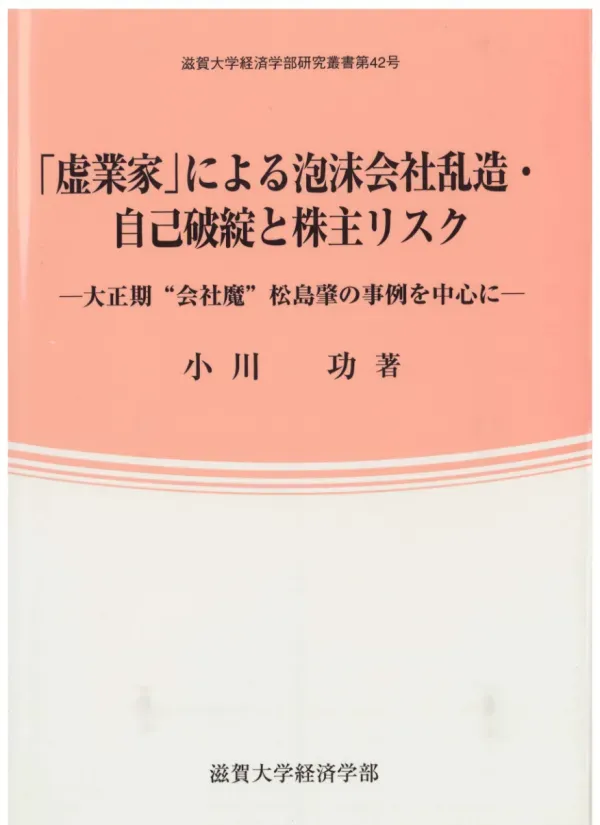
大正バブルと虚業家:松島肇の事例研究
文書情報
| 著者 | 小川功 |
| 学校 | 滋賀大学経済学部 |
| 専攻 | 経済学 |
| 出版年 | 平成17年(2005年) |
| 文書タイプ | 研究叢書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 7.97 MB |
概要
I.大正期における 虚業家 と 再建型資本家 の実態
本稿は、大正時代の日本の経済界において活躍した、特に高リスクな事業に携わり、時に不正行為に手を染めた人物、すなわち【虚業家】と、破綻企業の再建を通じて成功を収めた【再建型資本家】の実態を分析する。井上準之助(日本銀行総裁)の警告に見られるように、投機的な経済活動が日本経済に大きな影響を与えていた時代背景を踏まえ、松島肇、島徳蔵、高倉藤平といった代表的な人物の活動を中心に、その功罪を検証する。彼らの事業には、幽霊会社や泡沫会社の設立、不正な資金調達などが含まれ、リスク管理の欠如が破綻を招いたケースも分析する。
1. 大正期経済状況とリスクテイク
大正11年4月6日、井上準之助日銀総裁は銀行業者に対し、投機行為に対する警告を発した。当時、堀江貴文、三木谷浩史、孫正義といった現代でも著名な人物や、村上世彰を含む、特異な経済行動を行う人物らが、新聞や放送で大きく取り上げられていた。彼らの行動は株価のみならず、日本経済全体を揺るがす勢いがあった。政府は市場経済を重視し、自由な投資活動を容認する姿勢を示していたものの、リスク管理能力に欠ける企業家も少なくなかった。金子直吉などは、郷誠之助から「稀に見る天才肌の実業家…惜しいことには、本当の締めくくりが付かない」と評され、そのリスク管理能力の欠如が指摘されている。 成功と失敗の要因が偶然に過ぎないとするならば、健全な企業家精神と、単なる幸運に頼る投機は明確に区別されるべきである。中野梧一という人物も、その不可解な行動から「虚業家」的要素が指摘されている。 一方、島徳蔵は菅野和太郎氏によって「会社屋」と評され、不正行為の可能性も指摘されたものの、会社経営や株式会社に関する知識の普及に貢献した功績も認められている。三島康雄氏は島徳蔵を「不世出の虚業家」と評し、その奔放な行動が世間の注目を集めていたことを指摘している。日米信託の経営陣も、麻島昭一氏によって「諸欲の強い野心家」で「積極かつ放漫な経営」を行う者たちと評され、その破綻が指摘されている。このように、大正期の経済界には、旺盛な企業家精神とリスク管理能力のバランスが欠如した、様々なタイプの経営者が存在していたことが窺える。
2. 企業家精神とリスク管理 成功と失敗の要因
この節では、大正期の企業家を取り巻く状況と、成功と失敗を分ける要因について考察している。 特に、リスク管理能力の重要性が強調されており、企業家精神と投機を峻別する必要性が説かれている。 金子直吉の例では、並外れた才能を持ちながらも、統制の取れない経営が破綻につながったことが示されている。これは、リスク管理能力の欠如が、たとえ才能があっても成功を阻む可能性があることを示唆している。 一方で、島徳蔵は、不正行為の可能性はあるものの、会社経営の知識普及にも貢献した「会社屋」として評価されている。この例は、企業家精神とリスク管理能力の両面を考慮する必要性を改めて示している。 さらに、日米信託の経営陣の例では、積極的で放漫な経営が破綻を招いたことが挙げられている。これは、リスク管理の欠如が企業の存続に深刻な影響を与えることを示している。 これらの例から、大正期の企業家たちは、企業家精神とリスク管理能力のバランスが重要であったにも関わらず、そのバランスが崩れたために成功と失敗が分かれた可能性が示唆されている。
3. 虚業家 と 再建型資本家 の概念
本節では、「虚業家」という概念に加え、「再建型資本家」という新たな概念を提示し、その違いと特徴を考察している。 「虚業家」は、高リスクな投機的な事業に手を出し、多くの場合破綻を招く人物像であるのに対し、「再建型資本家」は、破綻寸前の企業を再建し、その過程で財を成した人物像として定義されている。 根津嘉一郎や河崎助太郎といった人物が「再建型資本家」の例として挙げられており、彼らは反骨精神が強く、既存の慣習に囚われず独自路線を貫いた点が特徴として挙げられている。原安三郎のようにリスク管理能力に優れた人物も含まれており、「再建型資本家」は単なる幸運ではなく、高度なリスク管理能力も備えていた可能性を示唆している。 「再建型資本家」は、「虚業家」が破綻させた企業を再建することで資本を蓄積していったという仮説も提示されている。 この節では、「虚業家」と「再建型資本家」という二つのタイプの経営者像を対比することで、大正期の多様な経済活動をより深く理解するための枠組みを提示している。
II.松島肇とその周辺 数々の新設会社設立と破綻
【虚業家】の代表例として挙げられる松島肇は、多数の会社設立に関与したものの、多くの場合、不正行為やリスク管理の欠如により破綻に至った。その手法として、ダミー株主を用いた株式募集、虚偽の報告書作成、資金の横領などが挙げられる。昌栄貯蓄銀行を【機関銀行】として利用し、自身の事業に資金を流用していた点も特徴的である。主な関連企業には、糸崎船渠(のちに海運興業と改称)、帝国毛織紡績、日洋土地興業、九州炭鉱などがある。これらの会社設立には、戸水寛人などの著名な人物が名義上関わっていた。
1. 松島肇の事業活動と手法 数々の新設会社と破綻
松島肇は、大正時代、数多くの新設会社の設立に関与した人物として知られる。しかし、その活動は必ずしも成功に終わらず、多くの会社が破綻している。 彼の事業活動の手法は、しばしば問題視されており、ダミー株主の利用による株式募集、虚偽の報告書作成、そして資金の着服などが指摘されている。 『本邦財界動揺史』は、松島を「財界の花形を気取り、大戦勃発以来企業熱旺盛の機運に乗じて新設会社の重役たり若くは発起人たる事無慮数十社、三面六管を有するも尚及ばざるかの観あり」と評している。これは、彼の活動の活発さと、同時にその行き届かなさ、つまりリスク管理能力の不足を示唆していると言える。 また、「横着なる発起人」と形容される彼の事業の解散過程は、非常に悪質なものであったことが指摘されている。 具体的な手法として、他人の氏名や印鑑を偽造して株式を募集し、株金を騙し取っていたという実態が、当時の経済誌主筆の理解をはるかに超える深刻な問題として記述されている。このような手法を用いて、彼は多くの会社を設立し、多額の資金を集めたものの、最終的には多くの会社が事業の失敗により破綻に至っている。
2. 昌栄貯蓄銀行の役割 松島肇の資金源と不正行為
松島肇の事業活動において、昌栄貯蓄銀行は重要な役割を果たしていた。昌栄貯蓄銀行は、松島が頭取を務めていた小規模な銀行であったが、地域金融機関の域を超え、松島が関与する企業への創業融資に特化していた点が特徴的である。 この銀行は、松島が設立に関与した多くの会社に対して資金を提供しており、その資金が不正な手段で流用されていた可能性が指摘されている。 『ダイヤモンド』誌や『大阪今日新聞』の「栄華物語」などでは、昌栄貯蓄銀行が松島の詐欺や横領のための機関銀行として利用されていたという記述が見られる。 具体的には、会社設立資金の着服や、空手形を用いた不正な資金調達などが行われていた可能性が指摘されている。 広島地裁公判の論告では、松島が「会社創立に関し自己の配下にある機関銀行を利用して巧みに法網を潜らんと…一時昌栄銀行の口座を潜らしただけで被告等に於て費消」したと指摘されている。このように、昌栄貯蓄銀行は、松島による不正行為を隠蔽し、事業を継続するための重要なツールとして利用されていたとみられる。
3. 松島肇と関係企業 糸崎船渠 帝国毛織紡績など
松島肇が関係した主な企業として、糸崎船渠(のちに海運興業と改称)、帝国毛織紡績などが挙げられる。糸崎船渠は、設立当初から株金の払込が不足しており、事業に着手できないまま、陽動作戦として起工式挙行広告を出稿していた。発起人や賛成者には、増田信一、星野錫といった「虚業家」的要素を感じさせる人物が含まれていた。 帝国毛織紡績は、資本金1000万円の大規模な事業であったが、これもまた問題を抱えていた。 役員には、名義上の役職者も多く、松島自身の関与は表面には出ていない部分も多い。 鈴木錠蔵は「単に名義上の副社長であって、実際上の事務に就ては何も知らない」と証言しており、多くの会社で同様の状況が存在した可能性が示唆されている。 これらの企業の活動は、松島の「黒幕」としての役割と、ダミー株主や名義上の役員といった彼の不正な手法が深く関わっていたことを示唆している。 これらの企業の設立・運営において、松島は自身の直接的な関与を隠蔽しつつ、陰で実権を握り、不正な資金調達や資金流用、虚偽の報告などを行っていたと推測できる。
III.門司築港事件 政治家としての松島肇の側面
門司築港事件は、松島の政治家としての側面を示す事例である。大規模な土地取引に関与し、利権獲得を目指した活動が見られる。事件の詳細は不明な点も多いものの、政治力と経済力を駆使した彼の活動が、このプロジェクトにも影響を与えていたことが推測される。関連人物としては、横田千之助(星亨の側近)や、多数の代議士、実業家などが挙げられる。
1. 門司築港事件の概要と松島の関与
この節では、門司築港事件の概要と、松島肇の関与について説明している。門司築港事件は、松島が石井貯蓄銀行整理の過程で関わった大規模なプロジェクトであり、彼はその陰で重要な役割を果たしていたと推測される。 事件の特徴として、関係者全員が不起訴となり、真相が未解明に終わった点が挙げられる。そのため、司法的な情報からは松島の活動の詳細を十分に把握することはできない。 しかし、この事件は、松島が代議士の肩書きを利用して大規模な土地取引に関与していたことを示す、貴重な事例と言える。特に、開発前の土地を先行取得して転売する「政商」的な行動が注目されている。 発起人には島津久賢、前島弥、安場末喜といった三男爵や、今西林三郎、蔵内次郎作、片岡直温などの新旧代議士、そして東京、大阪、神戸の実業家らが名を連ねており、その経営陣には財界の重鎮が相談役や社長として名を連ねていたとされる。 この事件を通じて、松島が政治家としての影響力と経済力を巧みに利用していたことが示唆されているが、事件の真相解明には至らなかったため、彼の活動の詳細については今後の研究が必要である。
2. フランス人ルーネンの計画と挫折 門司築港の背景
門司築港計画は、当初フランス人ロパート・ルーネンらの計画に基づいていた。しかし、設立趣意書によると、当時のフランスにおける銀行の破綻が相次いだため、ルーネンは事業を中止せざるを得なくなった。 この計画の挫折は、門司築港会社の設立に影響を与えた。 星亨の側近であった横田千之助の回想によると、増島六一郎氏がルーネン氏と共同で事業を始めたものの、ルーネンが資金を持っていなかったため、計画は挫折したという。 横田千之助自身も、星亨の知遇を得て東京法学院で学び、星氏の事務所にいた人物であり、彼の証言は門司築港事件の背景を理解する上で重要な手がかりとなる。 この計画の挫折後、松島肇がどのように関与し、プロジェクトを推進していったのか、その過程については、更なる調査と分析が必要となる。 この節は、門司築港事件の背景にある、フランス側計画の挫折と、その後松島がどのように関与したかを明らかにすることで、事件全体の理解を深めることを目的としている。
3. 松島の役割と影響力 政治力と経済力の行使
この節は、門司築港事件における松島肇の役割とその影響力を分析している。 彼は代議士の立場を利用し、大規模な土地取引に深く関与していたとされる。 門司築港会社の設立過程や経営において、松島は表には出てこない「影の役割」を果たしていたと考えられる。 関係者全員が不起訴となったため、司法的な証拠に基づいて彼の関与を完全に解明することは難しいものの、当時の世評などから、彼の政治力と経済力がこのプロジェクトに大きな影響を与えていたことが推測される。 当時の世評では、松島は「利権屋」のように見られていたと記述されており、彼の政治活動と経済活動の密接な関係を示唆している。 また、門司築港会社の設立趣意書や、関係者の回想などから、松島が計画の推進や資金調達、そして関係者との交渉などに深く関与していたことが推察される。 これらの情報から、彼は政治家としての立場を活かし、経済活動において大きな影響力を行使していたと推測できる。
IV.松島肇のパートナーと関係者 黒幕としての役割
松島は、多くの場合表舞台に立たず、大久保彦四郎などの腹心の者を前面に出して事業を展開していた。これらの関係者は、松島の指示の下、各地で活動を行い、その黒幕としての役割を支えていたと考えられる。彼らの多くは、松島との対等なパートナーというよりは、むしろダミー的な存在であったと考えられる。
1. 松島肇の 黒幕 的役割とパートナー
本節では、松島肇が多くの事業において表舞台に立つことは少なく、黒幕として陰から操っていた実態と、彼を支えたパートナーや関係者について分析している。 彼は戸水寛人といった著名な人物をダミーとして利用し、自ら表に出ることを避けていた。 この手法は、小沢武雄男爵を推戴した河村隆実の例と類似性があると指摘されている。 松島が実権を握っていた糸崎船渠の社長、男爵で貴族院議員の肝付兼行も、「自分は社長という名義ばかりで深いことは知らぬ」と発言しており、看板社長であったことを認めている。 伊豆山倍楽園の設立においても、松島は1万株のうち3000株を引き受け、12名の役員中8名までを腹心の者で固めていたとされる。 多くの企業に関与し、全国に事業を展開していた松島にとって、各地に信頼できる代理人が不可欠だった。特に当局からマークされ、行動が制限されるようになった後は、公然と行動できる社長格の人物が不可欠な存在となったと推測される。 大久保彦四郎は「松島肇の四天王の筆頭」と称され、東京、大阪、徳島といった松島の拠点ごとに代理人として活動していたと考えられている。
2. パートナーの属性と松島との関係性
松島とその周辺のパートナーたちの関係性について、共同投資の回数と資産力との関係性が分析されている。 共同投資回数が多かった人物ほど資産力が乏しく、資産力のある有力資本家との共同投資回数は少ない傾向が見られる。このことから、松島の周りの仲間の大半は、対等なパートナーというよりは、むしろ彼の持株を借受けたダミー的な人物であったと推測されている。 多くの企業に関わり、全国各地に事業を展開していた松島にとって、これらのダミーは、彼の活動を円滑に進める上で重要な役割を果たしていたと考えられる。 これらのダミーが必要であった理由として、松島の活動範囲の広さと、当局からの監視の目を逃れる必要性が挙げられる。 大久保彦四郎のように、松島を支える複数のキーパーソンが、東京、大阪、徳島など各地に存在し、それぞれが松島の代理として活動していた可能性が示唆されている。 特に当局にマークされ行動が制限されるようになった後、黒幕として陰から指示を出す松島に代わり、表向きに活動できる人物の存在が不可欠であったと推測される。
3. 九州炭鉱事件と昌栄貯蓄銀行 黒幕としての行動
九州炭鉱の例を通して、松島が黒幕としてどのように行動していたかが示されている。 彼は記者に対し「自分は九州炭鉱の創立者でもなければ重役でもない」と発言しているが、これは彼が表舞台に立つことを避け、陰で実権を握っていたことを示唆するものである。 この発言は、大正8年頃、昌栄貯蓄銀行が破産寸前に追い込まれた時のものであり、銀行の危機が、彼の事業活動に影響を与えた可能性を示唆している。 昌栄貯蓄銀行は、松島が頭取を務めていた銀行であり、彼の多くの事業に資金を提供していたとされる。 そのため、銀行の経営危機は、松島の事業活動にも深刻な影響を与えたと考えられる。 この事件では、松島は自身の関与を隠蔽しながら、昌栄貯蓄銀行を自身の不正な資金運用に利用していた可能性が強く示唆されている。 この節は、九州炭鉱事件と昌栄貯蓄銀行の破綻寸前という危機的状況を通して、松島がいかにして黒幕として事業を操り、不正行為を隠蔽しようとしたかを明らかにしている。
V.昌栄貯蓄銀行と高木一族の破綻 松島肇への間接的影響
松島と関係の深かった高木一族の経営する銀行や企業の破綻は、松島自身にも間接的な悪影響を与えた。高木一族の経営危機は、松島が利用していた昌栄貯蓄銀行の経営にも打撃を与え、その後の松島の活動にも影響を与えたと考えられる。
1. 昌栄貯蓄銀行の経営状況と問題点
この節では、松島肇が頭取を務めていた昌栄貯蓄銀行の経営状況と、その抱えていた問題点について詳述している。昌栄貯蓄銀行は、小規模な銀行であったものの、松島自身の関与する企業への創業融資に特化することで、地域金融機関の枠を超えた独自のビジネスモデルを構築していた。しかし、そのビジネスモデルには大きなリスクが潜んでいた。 無謀な代理店拡大政策の結果、昌栄貯蓄銀行は各地の代理店主から身元保証金の返還要求が殺到する事態に陥る。 銀行は支払能力がなくなり、「余儀なき者」への預金の一部返還と、残額の新株への振替という対応を余儀なくされた。 この経営悪化は、松島の事業活動と密接に関連しており、彼の事業の失敗が銀行の経営を圧迫したことが示唆されている。 さらに、計算報告書に不備のある会社には昌栄銀行の空手形を利用して表面を糊塗していたとされ、検察の論告では、松島は「会社創立に関し自己の配下にある機関銀行を利用して巧みに法網を潜らんと…一時昌栄銀行の口座を潜らしただけで被告等に於て費消」したと指摘されている。 こうした事実から、昌栄貯蓄銀行は、松島の不正行為を助長する役割を果たしていたと考えられる。
2. 高木一族の経営破綻と昌栄貯蓄銀行への影響
この節では、高木一族の経営破綻が、松島肇と昌栄貯蓄銀行に与えた間接的な影響について論じている。 高木一族は関西貯蓄銀行を経営していたが、財界不況や事業失敗によって多額の損失を出し、預金取り付け騒ぎに見舞われた。 その結果、関西貯蓄銀行は休業に追い込まれる事態となった。 高木一族の経営破綻は、松島肇にも間接的に影響を与えた。 松島の実弟である西条教部は、高木次郎氏が社長を務めていた日英興業会社に関連する事件で東京地裁に召喚されている。 高木自身の経営破綻は、吉野川水電の件で株主から告訴されるなど、様々な問題を抱えていた。 増田ブローカー銀行からの借金の返済不能により、資産差し押さえを受けるまでに追い込まれた。 これらの事実は、高木一族の破綻が、松島と深い繋がりを持つ昌栄貯蓄銀行にも深刻な影響を与え、その経営悪化の一因となった可能性を示唆している。 高木一族の経営破綻は、当時の財界の不況という時代背景と、彼らの経営判断の誤りという内的な要因が複雑に絡み合って発生したと考えられるが、松島とその関係者への間接的な影響は無視できない。
3. 松島への影響と 人心掌握の天才 としての側面
高木一族の破綻と昌栄貯蓄銀行の経営悪化は、松島肇の事業活動にも大きな影響を与えた。 しかし、その影響は直接的なものではなく、間接的なものとして現れている。 高木一族との繋がりや、昌栄貯蓄銀行の経営悪化は、松島の事業活動の基盤を揺るがし、彼の影響力低下に繋がったと考えられる。 一方、「栄華物語」では、松島は「人心掌握の天才」として描かれており、その手腕によって、多くの関係者から支持を得ていたことが示唆されている。 徳島県会の非公友派議員の多くは松島の崇拝者であり、彼と事業を共にし、政治系統を同一にしていたとされる。 篠原弥次兵衛のような「松島崇拝の熱心家」は、松島の醜聞が露呈した後も、彼への強い支持を表明している。 これらの記述から、松島は人心を掌握する高い能力を持っており、それが彼の事業活動や政治活動において大きな力となっていたことが推測できる。しかし、昌栄貯蓄銀行の経営悪化は、その影響力の低下をもたらした可能性がある。
VI.松島肇の功罪とその後 第二の岩下清周か
本稿では、大正時代の【虚業家】及び【再建型資本家】の活動、特に松島肇の事業活動とその功罪を多角的に分析した。彼の行動は、時代の経済状況や法制度の不備と深く関わっている。最終的に、松島が「第二の岩下清周」(※注:リスクテイク型の成功した実業家)と言えるかどうかは、更なる検証が必要である。
1. 松島肇の功罪 評価の複雑さ
この節では、松島肇の事業活動全体を振り返り、その功罪について総括的に考察している。 彼は多くの新設会社設立に関与し、莫大な資金を動員した一方で、多くの企業が破綻している。 彼の事業活動は、しばしば不正行為やリスク管理の欠如を伴っていたと指摘されており、そのため「虚業家」として批判されている。一方で、彼の並外れた企業家精神や、人々を動かす力も認められており、その評価は複雑で一概に断定できない。 「栄華物語」では、彼は「人心掌握の天才」と評され、その影響力は徳島県政にも及んでいたとされる。 しかし、彼の事業活動は多くの失敗に終わり、その結果として多くの関係者が被害を受けている。 彼の活動は、当時の経済状況や法制度の不備と深く関連している可能性も示唆されている。 そのため、単純な善悪の二元論で彼の功罪を評価することは困難であり、多角的な視点からの考察が必要であると結論づけている。
2. 昌栄貯蓄銀行のビジネスモデル 成功と失敗の要因
松島肇の事業活動が活発であった一因として、彼が頭取を務めていた昌栄貯蓄銀行のビジネスモデルの特異性が挙げられている。 昌栄貯蓄銀行は小規模な銀行であったが、松島が関与する企業への創業融資に特化していた。 このビジネスモデルは、リスクの高い事業への融資を積極的に行うものであった。 このモデルは、一時的に大きな預金獲得に成功するものの、無謀な代理店拡大策やリスク管理の欠如により、最終的には破綻への道を辿ることになる。 代理店主からの身元保証金返還要求や預金取り付け騒ぎが頻発し、銀行は支払能力を失った。 この銀行の破綻は、松島自身の事業活動の失敗と密接に関連しており、彼の事業活動の持続可能性を大きく損なう結果となった。 昌栄貯蓄銀行のビジネスモデルは、企業家精神を重視する一方で、リスク管理を軽視した結果、大きな失敗を招いた典型例として分析されている。
3. 松島肇のその後と 第二の岩下清周 か否か
この節では、事件後の松島の生き様と、彼が「第二の岩下清周」と呼べるかどうかについて考察している。岩下清周はリスクテイク型の成功した実業家として対比されている。 「栄華物語」は、松島を「坊主出身として世に恐らく彼れ程なまぐさいものはあるまい」と評し、その後の彼の行動は、物欲を捨てた生活を送っていたとされている。これは、リスクテイク型の成功者である岩下清周とは対照的である。 また、当時の法律や司法制度の問題点も指摘されており、発起者の不正行為に対する刑事罰が軽すぎること、民事訴訟では発起者に有利な判決になりやすいことなどが批判されている。 斎藤弁護士は、発起者の不正行為を厳しく罰する必要性を訴えている。 大浜孤舟の『暗黒面の社会・百鬼横行』では、松島は「阻劣卑劣の詐欺漢」と酷評されている。 これらのことから、松島は事業におけるリスク管理を欠き、結果的に多くの失敗を招いた人物であり、「第二の岩下清周」と呼ぶには相応しくないという結論になっている。
