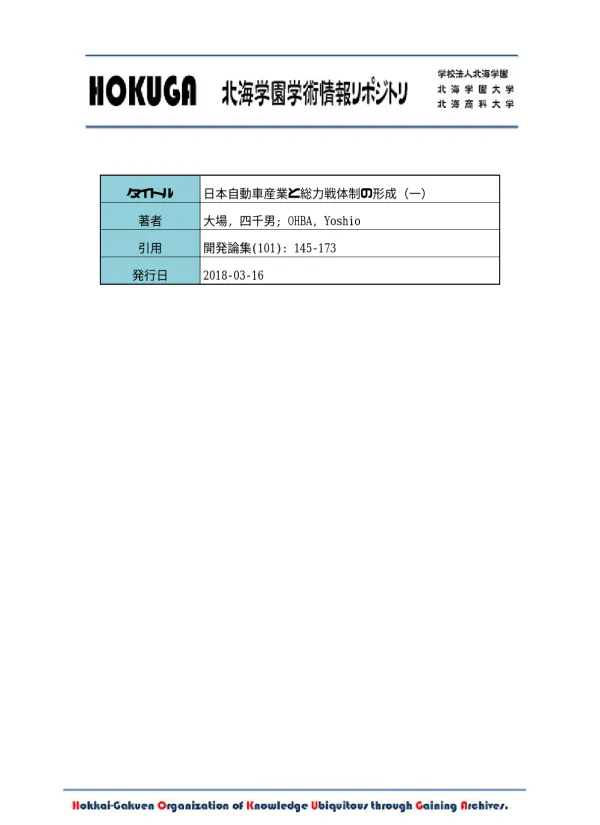
大衆車構想と日本自動車産業
文書情報
| 著者 | 大場 四千男 |
| 学校 | 北海学園大学開発研究所 |
| 専攻 | 経済学、歴史学、または関連分野 |
| 文書タイプ | 研究論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 0.99 MB |
概要
I.ナチスドイツの自動車政策と国内産業保護
ヒトラー政権下におけるドイツの自動車産業は、国家経済主義に基づき、国防と経済自給自足のために重要な役割を担いました。高い輸入関税(フランス45-55.2%、イタリア133.8-195.8%に対し、ドイツは16.7-28%と低水準)により一時的に輸入車が大量流入したため、政府は輸入許可規制などの保護政策を導入。フォード・ケルン工場への部品輸入規制もその一例です。国内産業育成のため、輸出奨励金制度も実施されました。ドイツ自動車監理会社の設立とカルテル協定による価格管理も特徴的です。オペル社はゼネラルモーターズからの資本分離を図り、民族資本系メーカーとして政府から保護を受けました。
1. 国防と経済自給自足のための自動車産業重視
ナチス政府は、自動車工業を国防上、そしてドイツ経済の自給自足主義達成において極めて重要と位置づけました。この政策は、国産車メーカーを国内経済の要として育成しようとする国家主導の強い意志を示しています。具体的には、自動車産業の保護育成、強化が国家的な目標として掲げられたことが分かります。この政策の背景には、ドイツ経済における自給自足体制の構築、そして軍事力の増強という、当時のドイツ社会の置かれた状況が大きく影響していると考えられます。この政策決定は、単なる経済政策ではなく、国家安全保障戦略の一環として位置付けられていた点が重要です。 このことは、後述する関税政策や輸入規制といった具体的な政策にも反映されています。
2. 低関税と輸入規制 国産車保護のための政策的対応
ドイツの乗用車輸入関税は、フランスやイタリアと比較して著しく低く設定されていました(フランス45~55.2%、イタリア133.8~195.8%に対し、ドイツは16.7~28%)。この低関税政策は、結果として大量の輸入車がドイツ国内に流入し、国産車メーカーを市場から駆逐する危機をもたらしました。この状況への対応として、政府は輸入商品管理権や輸入許可規制といった保護政策を積極的に導入しました。1935年7月には、輸入許可規制が公布され、ドイツ・フォードのケルン工場に必要な重要部品(モーター、ボールベアリングなど)の輸入が規制されたことで、同工場の急速貨物自動車製造に影響が出ました。このことは、政府が国産車産業の保護育成に本腰を入れたことを示す重要な出来事です。保護主義的な政策が、国家戦略として明確に打ち出されていたことがわかります。
3. 国内自動車産業の安定化 価格管理と輸出奨励
ナチス政府による国内自動車産業の安定化策として、価格管理と輸出奨励という二つの政策が挙げられます。1933年9月には、ドイツ自動車監理会社が設立され、自動車価格の監督が行われました。その目的は、不当な競争を抑制し、メーカー全体の利益を確保することであり、カルテル協定の締結なども見られます。これは、市場の安定化と国産車メーカーの保護を目的とした政策と解釈できます。また、輸出奨励金制度も導入されました。輸出車1台につき25%の奨励金(平均400マルク)を交付することで、国内自動車産業の国際競争力強化を図ろうとしたのです。この輸出奨励策は、国内市場の保護と同時に、ドイツ自動車の国際的なシェア拡大を目指す政策であったと考えられます。 これらの政策は、国内市場の安定と国際競争力の強化という二つの側面から、国家経済主義に基づいた自動車産業育成戦略の一部として位置付けられています。
4. オペル社の事例 民族資本化と政府による保護育成
インフレーション時代からの外資流入と企業支配を排除する政策の一環として、政府は外資系自動車メーカーの排除と国産部品の採用を推進しました。この政策の下、オペル社はゼネラルモーターズ社から株式を買い戻し、資本関係を再編しました。役員構成もドイツ人比率を高めることで、オペル社におけるドイツ人の経営支配を確保しました。政府はオペル社を民族資本系国産車メーカーとして位置づけ、ケルンのフォード社とは異なる扱いをして保護育成に力を入れたのです。このオペル社の事例は、ナチス政府がどのように外資系企業に対処し、自国の自動車産業を保護、育成していったかを示す、重要な事例研究となります。 このケースは、ナチスドイツの自動車政策における民族主義的な側面と国家による産業介入の現実を浮き彫りにしています。
II.戦間期の日本における自動車産業と軍需政策
日露戦争後の日本陸軍は、近代的輸送網の構築のため、自動車を重要な輸送兵器と位置付けました。軍用自動車調査委員会の設立、そして第一次世界大戦への参戦と総力戦体制構築により、軍用自動車補助法が制定され、国産車メーカーへの製造補助金交付(甲種トラック1500円、乙種トラック2000円)が開始。これはヨーロッパ諸国には見られない特異な国家経済主義政策でした。池貝鉄工所、東京瓦斯電気工業、東京石川島造船所などが、戦争特需を背景に自動車産業へ進出しました。石川島造船所はイギリスのウーズレー社と技術提携し、乗用車とトラックの生産を開始しました。
1. 陸軍の自動車政策 輸送網整備と機械化への志向
日露戦争後、日本陸軍は近代的輸送網の確立を急務と考え、自動車を重要な輸送兵器と位置づけました。明治40年(1907年)には、軍用自動車の調査研究が開始され、フランス製のノームとスナイドル社のトラックを導入、試験を行いました。その後、陸軍は国産軍用トラックの開発に着手し、大正4年(1911年)には大阪砲兵工廠で国産第1号車(甲号自動貨車)が製造されました。この初期段階においては、軍用トラックの性能や大きさの基準が明確に設定され、国産化への第一歩が踏み出されました。 陸軍による自動車政策の目的は、単なる輸送手段の確保にとどまらず、近代戦に対応するための輸送力の向上、そして将来的な軍事的展開を見据えた戦略的な側面も含まれていたと考えられます。この初期の取り組みは、後の軍用自動車補助法制定へとつながる重要な礎となりました。
2. 第一次世界大戦と軍需産業の勃興 軍用自動車補助法の制定
第一次世界大戦の勃発は、日本の自動車政策に大きな影響を与えました。大戦中、日本はドイツに宣戦布告し、山東半島や南洋諸島を占領しました。この戦争によって、日本の産業構造は農業国から工業国へと大きく変化し、第一次世界大戦の特需は輸出入の増大、そして金保有高の増加をもたらしました。大正7年(1918年)、日本陸軍は「軍需工業動員法」と「軍用自動車補助法」を公布しました。これは、総力戦体制を視野に入れた政策であり、民間工場での軍用トラック生産を促進するため、製造・保有両面で補助金を交付する、日本初の自動車産業政策でした。この法律は、甲種トラック1台につき1500円、乙種トラック2000円の補助金を支給するという、当時としては画期的なものでした。この補助金制度は、ヨーロッパ諸国には見られない特異なものであり、日本の国家経済主義的な自動車政策の出発点となりました。
3. 国産自動車産業の育成 製造補助金と企業の参入
軍用自動車補助法は、国産自動車産業の育成に大きく貢献しました。中田佐一郎は、当時の日本の自動車工業の未発達性を指摘し、製造業者への補助金の必要性を強調しています。この補助金制度により、戦争特需で発展した重化学工業の企業が、自動車産業へ進出するようになりました。池貝鉄工所、東京瓦斯電気工業、東京石川島造船所などがその代表例です。特に東京石川島造船所は、イギリスのウーズレー社と技術提携し、ウーズレーA型乗用車やCP型トラックの生産を開始しました。この技術導入と製造補助金は、国産自動車産業の基盤を築く上で重要な役割を果たしました。 しかしながら、この段階では、国産車の生産台数は輸入車に比べて圧倒的に少なく、市場における競争力は依然として弱かったことが伺えます。
4. 関東大震災と自動車の新たな役割 輸入車の台頭と国産車の苦境
大正12年(1923年)の関東大震災は、日本の輸送網を壊滅的な打撃を与えました。政府は、復興と輸送網の再建に自動車を利用し、フォードやシボレー車の緊急輸入を行いました。輸入税の免除や半減といった措置も取られ、大量の輸入完成車が日本市場に普及しました。この震災は、フォードやゼネラルモーターズといったアメリカの自動車メーカーの日本進出を促進するきっかけにもなりました。一方、国産車メーカーは、軍用自動車補助法による製造補助金に頼りながらも、輸入車との激しい競争に苦しみ、市場シェアを急速に奪われていきました。昭和恐慌期には、国産車メーカーの多くが衰退、あるいは廃業に追い込まれる状況に陥りました。関東大震災は、日本の自動車産業に大きな転換点をもたらし、輸入車の優位が明確になった重要な時期となりました。
III.国産自動車メーカーの勃興と苦境
大正7年(1918)以降、橋本増次郎(DAT)、久保田篤次郎(ダットサン)、豊川順弥(アレス号)らにより小型車が生産開始されましたが、世界恐慌や安価な輸入車との競争激化により苦境に陥りました。特にフォードとゼネラルモーターズの日本進出(日本フォード、日本ゼネラルモーターズ)は、ノックダウン生産による大量供給で国産車メーカーを圧迫しました。関東大震災後の復興需要は、輸入車の市場拡大につながりました。昭和恐慌期には、国産車は主に軍用トラック生産に頼る状況でした。
IV.満州事変と自動車政策の転換
満州事変でのフォード、シボレーの活躍は、陸軍に自動車の重要性を再認識させました。陸軍は大衆車の大量生産による自給自足体制を必要とし、商工省に自動車製造事業法の制定を働きかけました。岸信介、小金義照らが中心となり、大衆車構想に基づく政策が推進されました。この政策は、国産車メーカーの保護育成、そして将来的には対ソ連戦(将来戦)を見据えた軍需への対応を目的としていました。いすゞ自動車、日野自動車の大型トラックと、日産、トヨタの乗用車という構図が形成されていきます。
