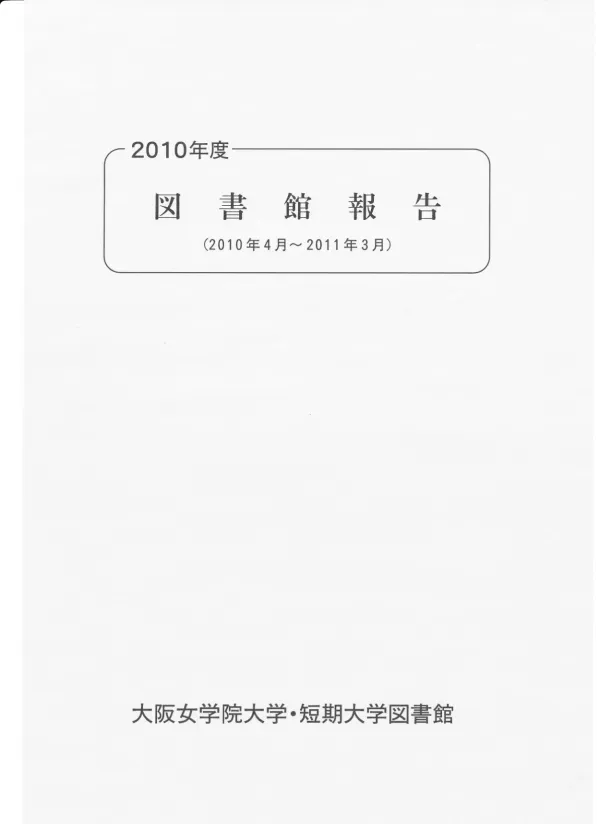
大阪女学院大学図書館年報:図書館活動報告
文書情報
| 著者 | 大阪女学院大学・短期大学図書館 |
| 学校 | 大阪女学院大学・短期大学 |
| 専攻 | 図書館学 |
| 文書タイプ | 図書館報告 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 12.50 MB |
概要
I.大阪女学院大学図書館の将来展望と現状課題 理想の学習空間の実現に向けて
2010年度の大阪女学院大学・短期大学図書館報告書を基に、図書館の現状と将来像をまとめます。報告書では、情報通信技術の急速な進歩に対応した、学生と教職員が協働で利用する新しい図書館の建設構想が示されています。理想の図書館像は、最新の情報機器を備えたラーニングコモンズ、電子メディア編集室、グループ研究室、情報リテラシー教育のための利用教育室、そして伝統的な静かな読書空間、書庫、カフェスペースなどを含む複合施設です。しかしながら、現状は予算削減による新刊書不足や、学生の学習スタイルの変化(インターネット情報の利用増加による紙媒体利用の減少)といった課題も抱えています。これらの課題を克服し、学生の学習・研究を支える、フレキシブルな設計の図書館の建設が、司書たちの願いです。大阪女学院大学図書館の今後の発展に期待がかかります。
1. 新図書館建設構想 理想の学習空間
このセクションでは、大阪女学院大学・短期大学図書館の新たな建設計画と、理想とする図書館の姿が描かれています。 知的創造を促すアカデミックな雰囲気、最新の情報を提供する空間を目指しています。具体的には、学生と教職員が協働で学習できるラーニングコモンズ、電子メディアの編集室、グループ研究室、情報リテラシー教育のための利用教育室などが挙げられています。一方、従来からの学習・研究、読書のための静かな空間、印刷メディア資料のための書庫、そして休憩のためのカフェスペースなども必要不可欠とされています。 大阪女学院大学・短期大学は伝統的に学生の勉学を重視してきたため、静かな学習空間の確保が特に重要視されています。 教職員と学生が協働で運営し、大学・短期大学の学習・教育・研究を支える図書館を目指している点が強調されています。これは単なる蔵書施設ではなく、学生と教職員の学習と研究を支援する、活気のある学習空間としての図書館像を示しています。
2. 情報化社会に対応した図書館サービスの変革
情報通信技術の急速な進歩、多様な学生、多様な学習スタイルといった変化の激しい時代において、将来を見据えた図書館のあり方が問われています。従来のように、所蔵資料数や来館者数を基準とする時代から、情報通信技術を活用したサービスを提供する図書館へと移行していくことが示唆されています。学生がわざわざ来館しなくても資料や情報にアクセスできるようになるため、来館者数は減少する可能性がありますが、一方で、図書館の設備、資料、広いスペースを利用してゆったりと滞在する学生も増加すると予想されています。この変化に対応するため、フレキシブルな設計が求められ、建物の設計だけでなく、資料の選定、司書の力量も重要な要素となります。2010年の司書たちの夢であり、数年後にはまた異なる図書館の夢が描かれるであろうと述べられています。
3. 現状の課題 予算削減と学生の学習スタイルの変化
2010年度の図書館報告書では、図書館を取り巻く現状の課題も指摘されています。最大の課題として、図書館の予算が前年度よりもさらに削減されたことが挙げられています。この結果、今年度の図書館利用調査では「新刊書がない」という意見が多く寄せられました。予算削減の影響は深刻であり、図書館の資料充実への影響が懸念されます。 また、学生の学習スタイルの変化も課題として挙げられています。具体的には、授業内容の改訂によるペーパー提出数の減少、インターネット情報利用の主流化によって、学生の図書館利用状況が変化していることが示されています。特に、短期大学2年生、大学2年生の貸出冊数が顕著に減少しており、この背景にはインターネットの普及による学習方法の変化が影響していると考えられています。これらの課題は、今後の図書館運営において重要な考慮事項となるでしょう。
II.機関リポジトリ 大阪女学院学術機関リポジトリ の公開
2008年度から取り組んできた機関リポジトリが、2010年度に「大阪女学院学術機関リポジトリ」として正式公開されました。国立情報学研究所の学術機関リポジトリ構築連携支援事業の補助金100万円を活用し、『大阪女学院大学紀要』『大阪女学院短期大学紀要』の電子化を完了、一部教材も登録しました。CiNii、JAIRO、Harvest、ハンドルシステムといったシステムを利用しています。 機関リポジトリの構築は、大学・短期大学の研究成果の発信に大きく貢献しています。
1. 機関リポジトリの公開と電子化
このセクションでは、2008年度から準備を進めてきた大阪女学院学術機関リポジトリが、2010年度に正式公開されたことが報告されています。 この機関リポジトリは、大阪女学院大学の教育・研究成果を発信するためのプラットフォームとして機能します。 公開にあたり、国立情報学研究所の学術機関リポジトリ構築連携支援事業の委託を受け、100万円の補助金を活用しました。この補助金は、大学紀要と短期大学紀要の電子化作業の委託費用、データ入力作業の人件費、機器購入費などに充てられました。その結果、「大阪女学院大学紀要」と「大阪女学院短期大学紀要」の電子化が完了し、一部教材も登録されました。ただし、紀要論文については、執筆者の許諾を得たもののみ公開されている点が重要です。 これは、著作権を尊重し、適切な情報公開を心がけていることを示しています。機関リポジトリの設立は、大学・短期大学の研究活動の成果を広く社会に発信する上で重要な役割を果たすと考えられます。
2. 機関リポジトリ構築における技術基盤
機関リポジトリの構築においては、様々な技術基盤が用いられていることが示唆されています。 文書からは、CiNii(国立情報学研究所が提供する学術論文データベース)、JAIRO(学術情報を横断的に検索できるデータベース)、Harvest(機関リポジトリのメタデータを自動的に取り込み発信するシステム)、そしてハンドルシステム(リポジトリサーバの変更後もアクセスを保証する機能)といったシステムが活用されていることが読み取れます。これらのシステムは、機関リポジトリの検索性、相互運用性、持続可能性を確保するために不可欠な役割を果たしています。 特に、ハンドルシステムは、将来的なシステム変更にも対応できる柔軟性を提供する重要な要素です。これらのシステムを効果的に活用することで、機関リポジトリの安定的な運用と、研究成果の持続的なアクセス可能性が確保されます。
III.図書館利用状況と学生からの意見 要望
学生一人当たりの貸出冊数は、短期大学1年生が過去最高を記録しましたが、2年生は減少傾向にあります。その原因として、授業内容の変更によるペーパー提出数の減少やインターネット情報の利用増加が挙げられます。学生からの意見・要望としては、新刊書や洋書の不足、貸出期間の延長、延滞金制度の見直しなどがあります。特に、大学4年生からは卒論作成における資料不足の訴えが多く上がっています。これらの意見を踏まえ、図書館のサービス向上に努める必要があります。
1. 学生一人当たりの貸出冊数
このセクションでは、学生一人当たりの貸出冊数の状況が報告されています。短期大学1年生は37冊(前年29冊)と過去6年間で最高レベルに達しており、大学1年生も29冊(前年23冊)と増加傾向にあります。 一方、短期大学2年生は22冊(前年32冊)、大学2年生は26冊(前年33冊)と、顕著な減少が見られます。この減少の原因として、授業内容の改訂によるペーパー提出数の減少と、インターネット情報の利用増加が考えられています。このデータは、学生の学習方法や情報収集手段の変化を反映しており、図書館サービスのあり方を見直す上で重要な指標となっています。特に、高学年になるにつれて貸出冊数が減少している点は、図書館が学生のニーズに十分対応できているかどうかの検証が必要であることを示唆しています。
2. 学生からの意見 要望 資料の充実とサービス改善
学生からの意見や要望は、図書館サービスの改善に繋がる貴重な情報です。多くの学生から、新刊書や洋書の不足が指摘されています。授業で紹介された書籍は複数冊用意するべきという意見もあり、資料の充実が強く求められています。 また、延滞金制度については、廃止すべきという意見と、責任感育成のために維持すべきという意見が両方存在します。 延滞金に関する具体的な要望としては、事前に連絡するなどして返却を遅らせないようにする、返却日の2,3日後までは延滞金対象としない、専門書の貸出期間を延長するなどの意見が出ています。 さらに、席数の不足、貸出期間の短さ、自習スペースでの私語など、図書館の利用環境に関する問題点も指摘されています。これらの意見は、図書館の改善計画策定やサービス向上に役立てられる重要な情報です。
IV.図書館運営の取り組みと外部活動
大阪女学院大学図書館は、私立大学図書館協会西地区部会阪神地区協議会研究会の幹事校として活動しており、2010年度には「初年次教育と図書館」をテーマに研究会を開催しました。その他、図書館システムサーバーの保守・更新、利用指導の実施、各種イベント開催など、多岐にわたる活動を展開しています。 CALISやJOINといったシステムの保守管理も重要な業務となっています。
1. 図書館システムの保守 更新とスペースの活用
このセクションでは、図書館のシステム運用と施設管理に関する取り組みが記述されています。予算削減の中、図書館システム「CALIS」のサーバー保守期間終了に伴い、新しいサーバーを2台購入しています。これは、図書館システムの安定稼働を維持するための重要な投資です。また、グループ閲覧室は、中学・高校の授業期間中は中高サポートルームとして共同利用されていることがわかります。これは、スペースの有効活用と学校全体の連携を示す事例です。さらに、派遣職員の着任や、監査法人による監査なども記載されており、図書館運営の多様な側面が垣間見えます。これらの記述は、図書館が日々の運営において、システム管理、予算管理、人的リソース管理など、様々な課題に対応しながら運営されていることを示しています。
2. 私立大学図書館協会との連携と研究活動
大阪女学院大学図書館は、学外活動にも積極的に取り組んでいます。私立大学図書館協会西地区部会阪神地区協議会研究会の幹事校として、2年間活動しており、2010年度には「初年次教育と図書館」をテーマに研究会を開催、約90名が参加しました。これは、他大学との連携強化と図書館における研究活動の積極性を示すものです。 他にも、様々なセミナーへの参加や、他大学図書館との交流(例:東京女子大学図書館ラーニングコモンズ見学)が報告されており、図書館が積極的に情報収集とネットワーク構築に努めていることが分かります。 これらの活動を通して、図書館は最新の図書館事情を把握し、他機関との連携を深め、図書館サービスの質向上に努めていると言えるでしょう。
3. 図書館の年間活動とイベント
このセクションには、年間を通して行われた図書館の様々な活動が時系列で記録されています。例えば、図書購入費・寄贈資料の報告、除却資料の申請提出、財産目録の報告提出、電子ジャーナル・データベース購読実態調査への回答、図書館報告書の発行、監査法人による決算監査など、図書館運営の様々な側面が記録されています。また、読書週間イベントや、夏休み・冬休み期間中の長期貸出、教員への利用指導案内配布なども記載されています。 さらに、外部機関との連携として、丸善TRC共催のブックフェアへの参加、国立国会図書館ツールの活用に関する研究会への参加なども挙げられています。これらの記述は、図書館が単なる資料保管施設ではなく、年間を通して様々な活動を行い、学生や教職員の学習・研究を多角的に支援していることを示しています。
V.図書館の変遷と将来への展望
1992年のCALIS導入、1998年の延滞金制度開始、2000年の改装工事など、大阪女学院大学図書館は時代に合わせて進化を遂げてきました。 2005年には坂本恭子氏が図書館長に就任(~2011年3月)。 今後の図書館は、所蔵資料数や来館者数だけでなく、情報通信技術の活用によるサービスの質が重要になります。 大阪女学院大学図書館は、これらの変化に対応し、学生のニーズに合わせた柔軟なサービスを提供していくことが求められています。
1. 大阪女学院大学図書館の変遷 技術革新とサービス拡充
このセクションは、大阪女学院大学図書館のこれまでの歴史と変遷を概観しています。1986年のコンピュータ導入(リードレックス社Data Box)を皮切りに、1989年の図書館増築、1992年のCALISシステム導入による貸出開始、1998年のOPAC(蔵書目録)愛称募集と学内LAN整備によるインターネット検索の開始などが挙げられています。 2000年には書架スペース確保のためプール下の閲覧席を撤去し書架を増設、図書館システムのバージョンアップとJOINシステム導入による学外からの検索が可能となりました。 2004年には国際・英語学部の開学に伴い、大学生・教職員を対象とした開館時間を21時まで延長、大阪女学院仕様OPACの利用開始などが行われています。これらの記述から、図書館が技術革新や大学の組織変化に柔軟に対応し、サービス拡充に努めてきたことがわかります。特に、1996年には全国1位となる学生一人当たりの館外貸出冊数を記録したことは、図書館サービスの質の高さを示す重要な実績と言えるでしょう。
2. 図書館長と重要な出来事
図書館の変遷において、図書館長が重要な役割を果たしてきたことが読み取れます。1991年には岡本言行氏、1999年には丸本郁子氏、2005年には坂本恭子氏が図書館長に就任しており、それぞれの在任期間中に図書館の整備やシステム導入などの大きな変化がありました。坂本恭子図書館長の在任期間(〜2011年3月)にも、多くのイベントやシステム導入が行われている事がわかります。 2006年には高校卒業記念品としてステンドグラスが寄贈され、図書館の入口正面に取り付けられました。 2009年には大学院が開学したことも図書館運営に影響を与えた重要な出来事でしょう。 これらの出来事は、図書館の物理的な拡張や機能の向上だけでなく、大学の教育研究活動の進化と密接に関連していることを示しています。
3. 将来像 情報通信技術を活用した図書館サービス
このセクションでは、将来の図書館像が示唆されています。 従来の所蔵資料数や来館者数を基準とする図書館運営から、情報通信技術を活用したサービス提供へと移行していく必要性が強調されています。 学生がいつでもどこでも情報にアクセスできるようになるため、来館者数は減少する可能性がありますが、一方で、図書館の設備やスペースを利用してじっくりと滞在する学生も増加すると予想されています。 この変化に対応するためには、フレキシブルな設計と、そこで働く司書の力量が重要になります。 建物の設計だけでなく、資料の選定、司書の力量も、これからの図書館運営において重要な要素となるでしょう。これは、図書館が単なる資料保管場所から、学習・研究を支援する多機能な空間へと進化していくことを示しています。
