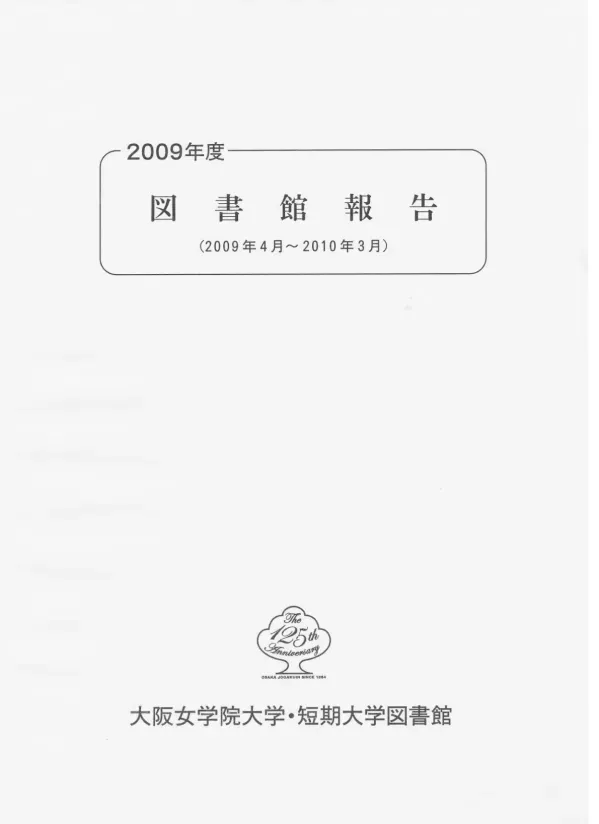
大阪女学院大学図書館年間報告
文書情報
| 著者 | 大阪女学院大学・短期大学図書館職員 |
| 学校 | 大阪女学院大学 |
| 専攻 | 図書館情報学 |
| 文書タイプ | 図書館年報 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 13.43 MB |
概要
I.大阪女学院大学 短期大学図書館の役割と活動
大阪女学院大学図書館は、大学・短期大学の教育・研究・学習を支援するため、多様なメディアの情報を収集・整理・保管・提供しています。特に情報リテラシー教育の推進に力を入れており、学生の学術研究をサポートする機関リポジトリも運営しています。2009年度の創立125周年を機に、図書館の使命を再確認し、新たな一歩を踏み出しました。 大学図書館としての機能に加え、短期大学図書館としての役割も担っており、学生一人ひとりの学習を支援する様々なサービスを提供しています。 近年は、予算削減の影響を受けつつも、レファレンスサービスの充実や、データベースの活用支援に努めています。
1. 大阪女学院大学図書館の使命と役割
大阪女学院大学・短期大学図書館は、大学の教育・研究・学習活動を支えることを第一の使命としています。あらゆるメディアの情報を収集、整理、保管、提供することで、教育・研究の達成に貢献することを目指しています。具体的には、大学における教育、研究、学習の成果を図書館が中心となって収集、蓄積し、学内外に向けて発信する役割も担っています。さらに、教職員と学生、学生同士のコミュニケーションの場を提供し、情報を「生きる力」に変える情報リテラシー教育を推進しています。これは、学生が単に情報を取得するだけでなく、批判的に評価し、効果的に活用する能力を養うことを目的としています。図書館は、単なる資料の保管場所ではなく、学習と研究を支援する中心的な拠点として機能していることがわかります。
2. 創立125周年と図書館の新たな一歩
2009年度は大阪女学院創立125周年という節目の年であり、様々な記念式典や出版物の刊行が行われました。同時に、大学のミッションステートメントも制定されました。大学院21世紀国際共生研究科の開設と国際共生研究所の設置もこの年に実現し、大学全体の体制が大きく変化しました。この変化を機に、図書館も改めてその使命を確認し、新たな一歩を踏み出しました。これは、単に既存の業務を継続するだけでなく、変化する大学環境に適応し、より効果的な情報サービスを提供していくための決意表明と言えるでしょう。125周年記念事業の一環として、卒業生から寄贈された渡辺禎男氏の版画2点が図書館に収蔵され、閲覧室に飾られるなど、図書館は大学の伝統と歴史を継承する役割も担っていることが伺えます。
3. 図書館の運営状況と課題
大学院の開設に伴い、大学院生や留学生の受入れが始まり、図書館は新たな利用者のニーズに対応する必要に迫られました。台湾のYuan Ze大学からの短期留学生の受け入れや、筑波大学図書館情報学科の学生によるインターンシップの受け入れなども行われています。しかし、大学予算の削減により、図書館の予算も大幅に減少し、特に図書購入費への影響が大きかったことが報告されています。延滞金の徴収方法がクレジット決済から現金払いへと変更されたことも、運営上の変化の一つです。さらに、新型インフルエンザの流行時には、感染拡大防止のため、図書館の利用を制限せざるを得ない状況も発生しました。これらの出来事は、図書館が予算や外部環境の変化に常に対応し、柔軟な運営を行う必要性を示唆しています。学生一人当たりの貸出冊数が減少している点も、今後のサービス改善の課題として認識されています。
4. 機関リポジトリの導入と情報発信
大阪女学院大学の教育・研究成果を発信する場として、機関リポジトリの準備が2008年度から情報委員会と協力して進められてきました。本年度は機関リポジトリシステム(dspace)を導入し、紀要のデータ登録を行いました。これは、大学の研究成果をデジタルアーカイブとして保存・公開し、学術界への貢献を図る重要な取り組みです。機関リポジトリは、学術情報の公開を促進するだけでなく、大学の研究活動の可視化にも貢献します。この取り組みは、大阪女学院大学図書館が積極的に学術情報のデジタル化を進め、世界に向けて情報発信を行う意欲を示しています。
II.図書館の主要業務とサービス
大阪女学院大学図書館では、資料の貸出・閲覧業務、レファレンスサービス(資料検索支援)、データベース検索支援などの主要業務を行っています。利用者からの質問対応や、課題研究のための資料探し支援など、情報リテラシー教育の一環として様々な支援を実施しています。また、機関リポジトリへのデータ登録や、学術情報に関する調査への協力も積極的に行っています。 新型インフルエンザの流行時には、感染拡大防止策として図書館の利用制限を実施するなど、利用者の安全確保にも配慮しています。 貸出冊数は、大学生が26冊(前年34冊)、短期大学生が31冊(前年34冊)と減少傾向にあります。延滞金は現金払いとなり、徴収方法の変更に伴い、回収に日数がかかるようになりましたが、その後、延滞金を図書購入費に充当するようになりました。
1. 資料の貸出 閲覧業務
図書館の主要業務の一つとして、資料の貸出と閲覧業務があります。これは、学生や教職員が自由に図書や雑誌などを利用できるよう、貸出、返却、予約、延滞者への督促などの手続きを円滑に行うことを指します。資料の探し方に関する案内掲示や、大学新入生向けのオリエンテーションなども実施されています。さらに、短大の保護者会への資料配布や、自宅外学生向けの資料提供など、利用者の多様なニーズに対応したサービス提供も行われています。特に、クリスマスに関する資料や新着図書案内などの企画も実施されており、図書館が単なる資料貸出場所ではないことを示しています。また、延滞金の徴収方法がクレジット決済から現金払いへと変更されたことによる影響や、新型インフルエンザ流行時の利用制限なども、この業務に関連する重要な出来事です。学生一人当たりの貸出冊数が減少しているというデータも、この業務の現状を反映しています。
2. レファレンスサービスと情報リテラシー教育
図書館では、レファレンスサービス、つまり資料の探し方や調べ方に関する質問への対応も重要な業務です。資料の探し方に関するチラシの配布や、授業時間中における図書館員による利用指導も実施されています。これは、学生の情報リテラシー向上を支援する取り組みであり、テーマや目的に合わせた資料の探し方などを個別に指導することで、学生の研究や学習活動を効果的にサポートしています。利用指導は、大学では「American Literature」、「Analysis of Speech」、「国際協力」などの授業、短期大学では「アジアの都市化とスラム」、「Studies in English Japanese Expression」、「International Public Policy」、「国際コミュニケーション」などの授業において実施されました。これらの授業内容に関連した資料検索方法を指導することで、学生の学習効果を高めることを目指しています。学生アンケートでは、利用指導が役に立ったという肯定的な意見も得られています。
3. データベース検索支援と情報資源の活用
図書館は、DIALOGやG Searchなどのオンラインデータベースへのアクセスを提供し、学生や教職員による情報検索を支援しています。 これは、文献調査や事実調査、調査方法の案内など、様々な研究活動において重要な役割を果たします。具体的な例としては、特定文献リストの作成やパスファインダーの作成、各学校の事務局や公共図書館の紹介、参考図書を用いた質問への回答などが挙げられます。図書館は、これらのサービスを通して、学生や教職員が効率的に必要な情報を収集できるよう支援しています。また、大学開放プログラム講師に関する著作の提供なども行われており、多様な情報資源の活用を促進しています。 さらに、機関リポジトリシステム(dspace)の導入による紀要のデータ登録も、デジタル時代の情報資源活用の一環として重要な役割を担っています。これらの活動を通して、図書館は情報アクセスを容易にし、研究活動を支援することで大学の教育・研究活動に貢献しています。
4. その他のサービスと図書館運営上の変化
図書館では、文献複写、図書貸借、文献調査、閲覧依頼受付などの相互協力体制も整えられています。ポスターや案内の作成・掲示なども、利用者への情報提供において重要な役割を果たしています。 さらに、英語担当者ワークショップでの図書館案内(日・英)の実施や、新図書館ホームページの案内配布なども行われています。延滞金の徴収方法の変更(クレジット決済から現金払いへ)や、新型インフルエンザ感染拡大防止のための図書館利用制限(マスク着用、利用時間制限)なども、図書館運営上の重要な変化として挙げられます。延滞金はその後、図書購入費に充当されるようになり、学生への還元にもつながるようになりました。これらの事例は、図書館が常に変化する状況に対応し、柔軟に運営されていることを示しています。
III.図書館の施設と設備
図書館は、パソコンが設置された静かな閲覧室と、個別ブースを備えています。しかし、利用者からは蔵書の充実、特に洋書や専門分野の資料の拡充、自習スペースの拡充などの要望が上がっています。また、図書館の場所が大学から離れているという意見もあります。
1. 図書館の現状と学生からの評価
図書館はパソコンが設置され、個別ブースもある静かな環境を提供しており、学生からは好意的に評価されています。しかし、大学から少し離れていると感じている学生もいるようです。 学生からは、蔵書、特に洋書や新刊、経営関連、言語、雑誌などの充実を望む声が多く上がっています。また、自習スペースの広さや快適さについても改善要望が出ています。これらの意見は、図書館の物理的な環境と、利用者の学習ニーズとの間にギャップがあることを示唆しています。 具体的な例として、洋書と和書の探しにくさ、資料の少なさ、特に洋書の不足、ジャンルの偏りなどが指摘されています。これらの点を改善することで、図書館の利用率向上に繋がる可能性があります。 また、延滞金徴収に関する学生からの意見も寄せられており、延滞金が発生する際には事前にメールで連絡してほしいという要望があります。
IV.今後の課題と展望
大阪女学院大学図書館は、予算削減などの課題を抱えながらも、利用者ニーズに対応したサービス提供に努めています。特に、洋書の充実、データベースの拡充、情報リテラシー教育の強化、そして機関リポジトリの更なる活用促進が今後の課題となっています。 学生からのフィードバックを参考に、より快適で充実した図書館環境を提供していくことを目指しています。
1. 予算削減と今後の課題
大学予算の削減は図書館にも大きな影響を与え、特に図書購入費の減少が深刻な問題となっています。この予算削減を踏まえつつ、図書館は、学生のニーズに応えるためのサービス向上を目指していく必要があります。具体的には、学生から要望の多い洋書の充実、データベースの拡充、情報リテラシー教育の強化などが挙げられます。これらの課題解決のためには、効率的な予算配分や、外部資金の獲得なども検討する必要があるでしょう。また、学生からのフィードバックを積極的に取り入れ、図書館の利用状況を分析し、サービス改善に繋げていくことが重要です。 学生一人当たりの貸出冊数が減少している現状も踏まえ、図書館の利用促進策を検討していく必要があります。
2. 機関リポジトリの更なる活用と情報発信の強化
機関リポジトリシステム(dspace)の導入は、大学の研究成果をデジタルアーカイブとして保存・公開する上で重要な一歩となりましたが、その更なる活用促進が今後の課題です。 紀要のデータ登録は開始されましたが、今後はより多くの研究成果を登録し、学術情報の公開を促進していく必要があります。 また、機関リポジトリの利便性を高めるためのシステム改善や、利用促進のための広報活動なども重要な取り組みです。 これにより、大阪女学院大学の研究活動の可視化を進め、学術界への貢献をより一層高めていくことが期待されます。 機関リポジトリの活用を通じて、大学全体の研究活動の活性化に貢献することも重要な展望です。
