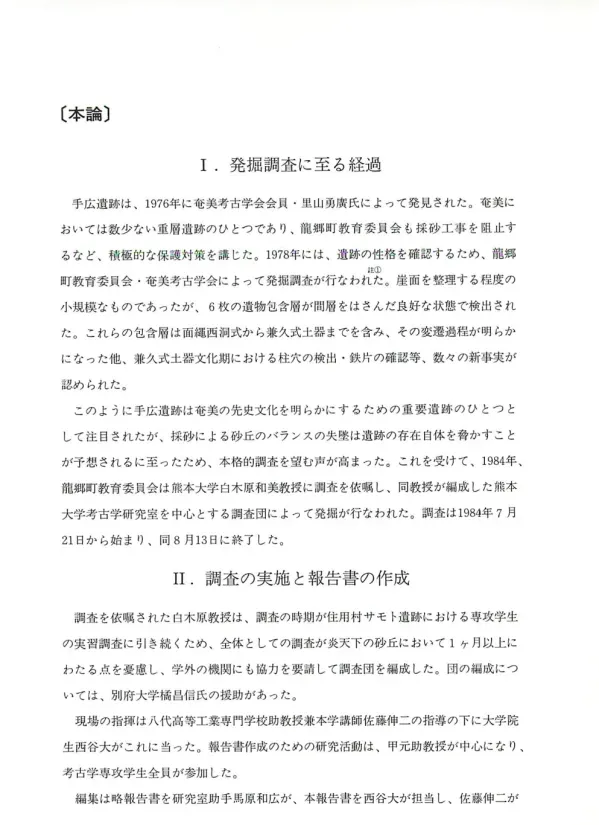
奄美手広遺跡発掘調査:縄文土器と先史文化
文書情報
| 著者 | 馬原 |
| instructor/editor | 白木原和美 教授 |
| school/university | 熊本大学考古学研究室 |
| subject/major | 考古学 |
| 文書タイプ | 発掘調査報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.50 MB |
概要
I.手広遺跡の発掘調査概要
1976年、里山勇脹氏によって発見された手広遺跡は、奄美大島の先史文化を解明する上で重要な遺跡です。採砂による遺跡への被害が懸念されたため、1984年、龍郷町教育委員会は熊本大学白木原和美教授に発掘調査を依頼しました。調査は7月21日から8月13日まで行われ、熊本大学考古学研究室を中心とした調査団が、別府大学橘昌信氏の協力を得て実施しました。現場指揮は佐藤伸二氏(当時、八代高等工業専門学校助教授)、報告書作成は甲元助教授を中心とした学生が担当しました。調査は、約250㎡の範囲で行われ、複数の遺物包含層が確認されました。
1. 手広遺跡の発見と調査の経緯
手広遺跡は1976年、奄美考古学会会員の里山勇脹氏によって発見されました。奄美においては数少ない重層遺跡の一つであり、その重要性が認識されていました。しかし、採砂による砂丘の侵食が遺跡の存続を脅かす可能性が高まったため、本格的な発掘調査が求められるようになりました。この事態を受けて、龍郷町教育委員会は1984年、熊本大学白木原和美教授に調査を依頼、熊本大学考古学研究室を中心とした調査団が編成され、発掘調査が実施されることとなりました。調査期間は1984年7月21日から8月13日までの約1ヶ月間とされました。白木原教授は、調査期間が住用村サモト遺跡での学生実習調査に続くことから、炎天下での長期間調査の困難性を懸念し、別府大学橘昌信氏など学外の機関にも協力を仰ぎ、調査体制を強化しました。これは、単なる学生実習ではなく、学際的な協働による本格的な調査であることを示しています。遺跡の保存と学術的な調査の両立が、この調査の重要な側面となっています。
2. 調査団の構成と報告書作成
調査団は熊本大学考古学研究室を母体とし、白木原和美教授をリーダーに、多様な専門家の協力を得て編成されました。現場の指揮は八代高等工業専門学校助教授兼熊本大学講師の佐藤伸二氏が担当し、大学院生である西谷大氏がその下で作業にあたりました。報告書の作成は甲元助教授をリーダーとし、考古学専攻の学生全員が参加した大規模な取り組みでした。貝類の同定には熊本大学薬学部の濱田善利氏、獣骨の分類には木村幾多郎氏がそれぞれ専門的な知見を提供しました。さらに、笠利町歴史民俗資料館の中山清美氏や、梅光女学院大学の木下尚子氏、住用村教育委員会の森田勇氏なども短期的に参加し、学生の指導にあたりました。報告書の作成においては、馬原和広氏が略報告書を、西谷大氏が本報告書を担当し、佐藤伸二氏が監修にあたりました。本報告書の完成には西谷氏の中国留学の予定との兼ね合いがあり、予定通りに完成しなかったため、馬原氏が担当していた略報告書が先行して刊行されることとなりました。このように、本報告書は、多くの研究者や学生の協働、そして困難を乗り越えた努力の結晶であると言えます。
3. 調査方法と調査範囲
発掘調査は、第一次調査区の西側、採砂や崩落の影響を受けていない約250平方メートルの範囲で行われました。調査区の設定は、第一次調査時のレンチの西壁ライン延長上に基準点を置き、5メートル×5メートルの正方形グリッドを、南から北にA、B、C…、西から東に1、2、3…と命名して設定されました。この精密なグリッドシステムによって、発掘された遺物の位置情報が正確に記録され、後の分析に役立てられました。この調査範囲は、遺跡全体の規模から見ると一部に過ぎませんが、地層の状況や遺物の分布を把握する上で、十分な広さを有していたと考えられます。この調査方法と範囲設定は、後の分析結果の精度を高めるために非常に重要であり、調査の計画性と緻密さが伺えます。 この手法は、手広遺跡のような砂丘地における発掘調査において、効率的でかつ正確なデータ収集を可能にしたと言えるでしょう。
II.出土遺物と層位
発掘調査では、土器(面縄西洞式土器、兼久式土器、字宿上層式土器、喜念I式土器、嘉徳I・II式土器など)、石器、貝製品、動物遺存体(イノシシ、ウミガメなど)が多数出土しました。各層から出土した遺物によって、縄文時代後期から弥生時代前期にかけての文化層が確認されました。特に、第3層(兼久式土器)、第5層(九州系の土器)、第11層(字宿上層式・喜念I式土器)は、奄美の土器文化の変遷を知る上で重要な層位です。また、石組遺構やピットなども発見され、当時の生活様式を推測する上で重要な手がかりとなっています。注目すべき遺物として、有孔土製円版や櫛形石製品など、奄美では初見の遺物も含まれています。
1. 各層位からの出土遺物
手広遺跡の発掘調査では、複数の遺物包含層が確認され、それぞれの層から多様な遺物が発見されました。第3層からは兼久式土器を主とする土器片、石器、貝製品、獣骨、貝殻、炭化物などが大量に出土し、ピットや柱穴と推定される遺構も多数検出されました。特に、環状に配置されたピットは注目すべき発見です。第4層からはまとまった量の土器が出土しました。第5層は、第一次調査では確認されなかった遺物包含層であり、厚さ約20cmの固く締まった黄褐色の砂層から土器片、石器、貝製品、獣骨などが発見されました。第6層は厚さ約50cmの黒褐色砂層で、石組遺構が3基、焼けた石の集積遺構が検出され、土器片、石器、貝製品、獣骨なども出土しました。第11層からは字宿上層式・喜念I式土器を主体とする土器片、石器(石斧を含む)、貝製品などが多く出土し、炭まじりのピットも検出されました。第13層からは面縄西洞式土器を含む土器片、石器、貝製品などが発見され、環状の石組遺構や、特定の種類の巻貝が集中したピットなども確認されました。第14層からは新たに遺物包含層が確認され、嘉徳I・II式を含む土器片、焼礫の集積した遺構などが発見されました。このように、各層位からは時代を反映した特徴的な遺物が発見されており、奄美の古代文化の解明に大きく貢献するものです。
2. 注目すべき遺物と遺構
手広遺跡からは、土器、石器、貝製品以外にも、いくつかの注目すべき遺物や遺構が発見されました。第6層からは、明黄褐色の有孔土製円版が出土しました。直径約7cm、厚さ約1cmの円版で、中央につまみ状の突起があり、裏面に貫通孔を持つ、この地方では初見の遺物です。同じく第6層からは、粘板岩製の櫛形石製品も発見されました。「歯」が約20本ある全面磨製の製品で、磨耗痕が見られます。用途については諸説ありますが、いずれもこの地域では初めての発見であり、当時の生活様式や技術レベルを知る上で重要な手がかりとなります。さらに、クガニ石と呼ばれる、卵形の礫を加工した石製品も第6層と第13層から出土しました。敲打の後、研磨が施されており、その用途は不明ですが、独特の加工技術が注目されます。第6層からは、全面になめらかな調整が施された骨製針も出土し、先端に糸を通す穴があったと推測されます。これらの遺物は、いずれもこの地方では稀なものであり、手広遺跡の特異性を示す重要な証拠となっています。これらの遺物や遺構の発見は、奄美地方の先史文化の理解を深める上で極めて重要な意味を持っています。
3. 遺物から読み解く奄美の文化変遷
出土遺物から、手広遺跡における文化変遷を考察することができます。例えば、第3層の兼久式土器、第5層の九州系土器、第11層の字宿上層式・喜念I式土器など、各層位から出土する土器の種類や様式は時代を示す重要な指標です。特に、第11層で大量に出土した字宿上層式・喜念I式土器は、タチバナ遺跡での九州の黒川式との共伴関係から、縄文時代晩期前半に相当すると推定されます。また、第5層の土器は九州の土器との類似性が強く、刻目凸帯付土器や板付式類似丹塗磨研壺の存在は弥生時代前期の様相を示唆しています。さらに、従来奄美では喜念I式以降に出現すると考えられていた壺形土器が、第13層と第14層からも無文のものが確認されたことは、新たな知見です。これらの土器の分析から、奄美における土器文化の変遷や、周辺地域との交流関係などを明らかにすることが期待されます。尖底土器の木の葉圧痕も注目すべき点です。従来、平底の兼久式土器に多く見られたこの圧痕が、尖底土器にも見られるなら、製作技術に関する新たな知見が得られる可能性があります。
III.年代測定と考察
日本アイソトープ協会によるC14測定の結果、各層の年代が推定されました。これにより、手広遺跡における文化層の変遷がより明確になりました。出土した土器の種類や特徴、住居址の構造などから、奄美地域の先史文化の展開過程を考察することができます。特に、壺形土器の出現時期や、木の葉圧痕のある尖底土器の製作技術などは、今後の研究課題です。沖繩諸島の貝塚時代との比較検討も重要です。
1. C14年代測定による年代推定
手広遺跡の各層から採取された木炭片を日本アイソトープ協会に依頼し、C14年代測定を行いました。報告書には、測定結果がそのまま掲載され、層位との対照表も付されています。これらの数値データは、今後の研究において重要な参照資料となり、各層の年代をより正確に特定する上で欠かせない情報となります。この年代測定の結果は、出土遺物の編年や、奄美における文化変遷の解明に大きく貢献すると考えられます。得られた年代値は、各層位に含まれる遺物の年代を推定するだけでなく、層位関係や堆積過程の理解を深める上で重要な役割を果たします。特に、複数の文化層が重なっている手広遺跡においては、C14年代測定による年代特定が、正確な文化変遷の解明に不可欠です。今後の研究において、これらの年代値を基にした更なる分析が期待されます。
2. 遺物と層位からの文化変遷の考察
出土遺物と各層位の関係から、手広遺跡における文化変遷を考察することができます。第11層から出土した字宿上層式・喜念I式土器は、九州のタチバナ遺跡における黒川式土器との関連から、縄文時代晩期前半に比定されます。また、第5層の土器は九州系の土器との類似性が指摘されており、刻目凸帯付土器や板付式類似の丹塗磨研壺の存在は、弥生時代前期の様相を示唆しています。第14層からは縄文時代後期後半に比定される嘉徳I・II式土器が出土しています。さらに、奄美では喜念I式以降に出現すると考えられていた壺形土器が、第13層と第14層から無文のものが確認されたことは、従来の認識を改める重要な発見です。これらのことから、手広遺跡の各層位は、縄文時代後期から弥生時代前期にかけての広範な時期を包含していることが示唆され、奄美における先史文化の変遷を理解する上で重要な手がかりとなります。特に、第4層、第11層、第5層は、奄美の土器文化の変遷を解明する上で、重要な位置を占めています。
3. 沖縄諸島との比較検討
手広遺跡における住居址の変遷は、沖縄諸島における住居の変遷と類似している可能性が示唆されています。沖縄諸島では、平地住居が定着するのは貝塚時代後期からであり、初期の貝塚遺跡では見られないことから、奄美における住居の変遷も同様のパターンを示す可能性があると考えられます。この点は、今後の研究において、沖縄諸島の関連遺跡との比較検討を進めることで、より詳細な検証が必要となります。手広遺跡の出土遺物や層位、年代測定の結果などを、沖縄諸島の同時代の遺跡と比較検討することで、奄美と沖縄諸島における先史文化の交流や、それぞれの地域特性をより明確に解明できる可能性があります。特に、土器や住居址などの類似点・相違点を詳細に比較することで、両地域の文化交流史や、それぞれの文化独自の発展過程を明らかにすることが期待されます。
IV.動物遺存体分析
動物遺存体としては、主にウミガメとリュウキュウイノシシの骨が発見されました。特に第5層からは多数のウミガメの骨が出土しており、当時の食生活や環境を知る上で重要な情報となります。個体数の推定や年齢分析の結果も報告書に記載されています。木村幾多郎氏による詳細な分析が行われました。
1. 動物遺存体の種類と層位分布
手広遺跡から出土した動物遺存体(貝類・魚類を除く)は、主にウミガメの腹甲・背甲板の破片と、リュウキュウイノシシの骨でした。これらの動物遺存体は、第3層から第14層の各層位から発見されていますが、特に第5層からの出土量が圧倒的に多く、ウミガメの骨のほとんどが第5層から出土しました。これは、第5層の堆積環境や、当時の生業活動との関連を示唆している可能性があります。他の層からもウミガメやイノシシの骨は確認されていますが、その量や種類は第5層とは大きく異なります。各層位における動物遺存体の種類や量の違いは、当時の環境や人間の活動との関連を解明する上で重要な手がかりとなります。今後の研究では、これらの動物遺存体の分析結果と、他の出土遺物や環境データとの総合的な検討が必要不可欠です。特に、ウミガメが大量に出土した第5層の堆積環境の詳細な分析は、今後の重要な研究課題となります。
2. リュウキュウイノシシの骨格分析
リュウキュウイノシシの遺存骨は、下顎骨を中心に分析されています。第3層からは2頭分、第5層からは5頭分の下顎骨が確認されました。第5層の下顎骨5頭分については、それぞれの個体の年齢や性別の推定が行われています。乳歯が残る幼獣や、成獣、老獣など、様々な年齢の個体が含まれており、これは当時のイノシシの個体群構造を反映している可能性があります。また、犬歯の有無から性別も推定され、雌雄の比率などもわかります。これらの分析は、木村幾多郎氏によって行われ、詳細なデータが報告書にまとめられています。下顎骨の他に、四肢骨の一部も確認されていますが、数が少ないため、詳細な分析は困難です。これらの分析結果から、当時のイノシシの生息状況や、人々との関係性を解明するための重要な手がかりが得られると期待されます。今後の研究では、より多くの標本を分析することで、より詳細な知見が得られる可能性があります。
3. ウミガメ遺存体の分析と考察
ウミガメの遺存骨は、主に腹甲と背甲板の破片であり、第5層から特に多量に出土しています。それらの多くは肋骨板で、上・中・下腹甲板も確認されています。全体の遺存骨量から、少なくとも1頭分の骨格がほぼ完全に残っていたと推定されています。第6層からは、アカウミガメと推定される下顎骨も発見されており、出土したウミガメの種についても考察がなされています。ウミガメは、当時の重要な食料資源であったと考えられますが、その捕獲方法や利用方法については、今後の研究課題です。大量に出土したウミガメの骨は、当時の食生活や、沿岸部の環境を理解する上で重要な情報を与えてくれます。魚骨についても同定を行う予定でしたが、今回は鑑定が間に合わず、今後の課題となっています。これらの分析結果は、手広遺跡周辺の生態系や、人々の生活様式を復元する上で重要な役割を果たすものと期待されます。
