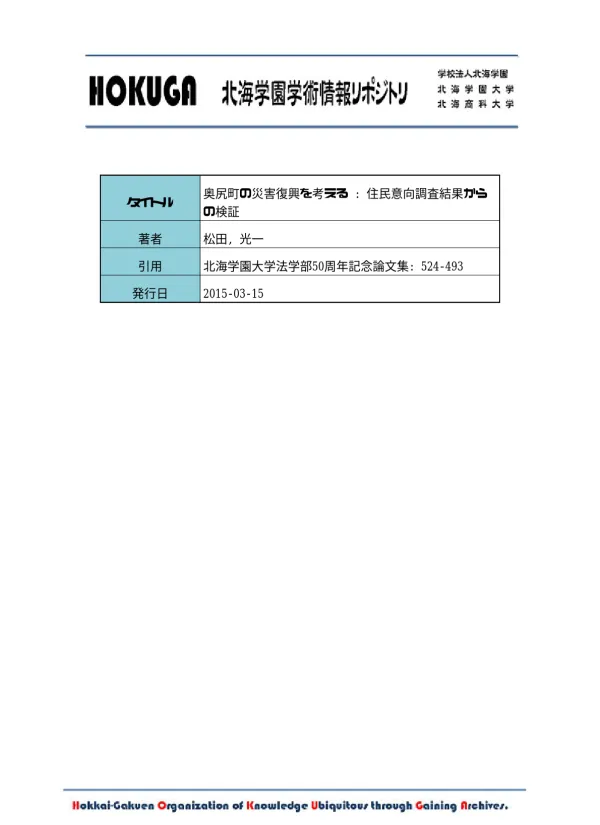
奥尻町復興:住民意向調査結果
文書情報
| 著者 | 松田 光一 |
| 文書タイプ | 調査論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 573.99 KB |
概要
I.奥尻町災害復興計画の検証 20年後の現状と課題
本稿は、1993年の北海道南西沖地震から20年以上を経た奥尻町の復興状況を検証する。災害復興計画に基づくハード面整備は進んだものの、地域活性化、過疎化対策、高齢化対策といったソフト面での課題が顕在化している。特に、地域経済の停滞、人口流出、空き家対策の必要性が指摘されている。調査結果では、住民はものの復興(ハード面)よりも人の復興、心の復興、町の復興(ソフト面)を重視していることが示された。防災、減災への意識も高く、次世代への防災経験の伝達方法が問われている。
1. 北海道南西沖地震からの復興 20年を経て
1993年の北海道南西沖地震から20年以上が経過し、奥尻町は復興の過程を歩んできた。阪神・淡路大震災や東日本大震災など、多くの災害を経験した日本において、近年は復興計画の内容が厳しく問われるようになっている。奥尻町においても、20年以上を経た現状を踏まえ、当時の復興計画が地域の将来を見据えたものであったのか、疑問視する声が高まっている。特に東日本大震災後の復興議論を機に、その疑問は顕著になった。復興計画策定においては住民の意思を反映することが重要だが、復興を急ぐあまり住民の声を十分に反映できないまま、ハードウェア中心の計画になりがちであった。奥尻町も例外ではなく、1991年度から実施されていた第3期奥尻町発展計画に沿った復興計画が優先された。バブル崩壊後の経済低迷や、地方社会の疲弊という社会情勢の変化の中で、復興計画の目指す方向性が厳しく問われる時代になったことを踏まえ、本稿では奥尻町の復興を検証する。
2. 住民意識調査 復興の実態と課題
住民意識調査の結果、奥尻町の回答者の男女比はほぼ半々であるが、地区別に見ると稲穂、宮津、湯浜地区では男女差が大きい。年代別では60歳以上が53.7%、50代が22%を占め、75.7%が高齢者層であることがわかる。平成22年国勢調査との比較では、30代、40代はほぼ同じ構成比だが、50代、60代は調査結果の方が比率が高く、70代は低くなっている。高齢者層の回答率が低いことを考慮すると、調査結果は奥尻町の年齢構成をほぼ反映していると言える。居住年数では、30年以上が73.7%、震災後19年未満が17.8%。震災後の移住者の多くは自衛隊員で、北海道外からの転入が多い。職業別では無職・専業主婦が47%を占め、有職者では農林・漁業・水産加工、公務員、会社員・団体職員が多い。10年未満の居住者は自衛隊員や転勤が多い職業に多く見られる。震災被害では、建物被害が66.6%、親戚・知人の喪失が47.4%と高く、漁業者は漁船・漁具の被害が72.8%と深刻な状況にあった。
3. 復興事業の現状と住民評価 成功と失敗の事例
奥尻町の復興基本計画は、生活再建、防災町づくり、地域振興の3本柱を立て、様々な事業が推進された。青苗地区では防災集団移転事業(高台移転)などが実施され、稲穂地区でも漁業集落環境整備事業が進められた。復興事業は国と北海道の連携のもと、1998年には復興宣言が出されるほど迅速に進められた。しかし、復興の定義は曖昧であり、住民にとっての復興とは何かを調査した。漁業者は船名を取り戻した時を、会社員や公務員は復興宣言が出された時を、経営者は借金返済完了時をそれぞれ復興と感じた時期として挙げている。町の復興については、青苗地区の大規模な区画整理などが挙げられるが、コミュニティの再構築が課題となる。ものの復興は住民評価が高くないが、これは施設の老朽化や維持管理の困難さを反映していると考えられる。住民は、ものの復興だけでなく、人の復興(新しい生命の誕生、防災人材育成)、心の復興、町の復興、組織の復興といった複合的な復興概念を持っている。
4. 奥尻町の課題と今後のまちづくりの方向性
奥尻町では震災後、様々な公共施設が整備されたが、その評価はまちまちである。奥尻空港は利用者数が伸び悩んでおり、アワビ種苗育成センターも漁業者からの評価が低い。一方、奥尻島津波館は災害学習や観光に役立っていると高い評価を得ている。ワラシャード(海洋研修センター)は、利用状況は地域によって異なる。新生ホール・青苗は住民から低い評価を受けている。これらの現状を踏まえ、住民は今後のまちづくりの方向性として、地域医療と地域福祉の進展、交通アクセスの課題克服、奥尻のブランド化などを重視している。特に、30代と70代以上の層では地域医療と地域福祉の充実への要望が高い。これらのニーズに対応するため、奥尻町と檜山振興局は2012年に奥尻島津波語り部隊を結成し、震災経験の伝承活動を行っている。語り部隊の活動範囲については、島外への拡大が必要だとする意見が多い。観光資源の開発、島内外交流の促進、学校での災害教育の充実なども重要視されている。
II.住民意識調査の結果 復興の捉え方と今後のまちづくり
住民意識調査では、男女比はほぼ半々、60代以上が53.7%を占める高齢化社会であることが判明。30年以上居住者が73.7%を占め、災害復興過程を経験した住民が多い。奥尻町住民は、災害復興を「ものの復興」「人の復興」「心の復興」「町の復興」「組織の復興」の5つの側面から捉えている。ものの復興(公共施設整備)は一定の成果があったものの、その有効活用や維持管理に課題が見られる。人の復興(次世代育成、防災意識の向上)や心の復興(トラウマ克服、心のケア)は継続的な取り組みが必要。町の復興には、地域医療・地域福祉の充実、交通アクセスの改善、観光資源の開発などが求められている。地域活性化のため、島外への情報発信の必要性も高い。
1. 回答者属性と震災被害の実態
住民意識調査の回答者属性を見ると、男女比はほぼ半々(男51.2%、女48.8%)だが、稲穂、宮津、湯浜地区では男女差が大きい。年齢構成は60歳以上が53.7%、50代が22%と高齢化が進んでおり、回答者の75.7%が50代以上である。国勢調査データとの比較では、30代、40代はほぼ同程度だが、50代、60代は調査結果の方が比率が高く、70代は低い。高齢者の回答率の低さを考慮しても、調査は奥尻町の年齢構成を十分に反映していると判断できる。居住年数は30年以上が73.7%、震災後19年未満が17.8%で、回答者の8割以上が震災後の復興過程を経験している。震災後に移住した2割の人々は、多くが北海道外からの転入者で、特に自衛隊員が多い。職業別では、無職・専業主婦が47%を占め、有職者では農林・漁業・水産加工、公務員、会社員・団体職員が多い。震災被害は、建物被害が66.6%、親戚・知人の喪失が47.4%と高く、漁業者では漁船・漁具の被害が72.8%に上るなど、甚大な被害を受けていたことがわかる。
2. 復興の捉え方 五つの復興概念
調査では、住民が災害後の復興をどのように捉えているかを明らかにするため、五つの復興概念(ものの復興、人の復興、心の復興、町の復興、組織の復興)を設定し、質問を行った。ものの復興は、震災で損傷したインフラや住宅などの物的復旧を指し、公共施設の整備などが該当する。しかし、住民にとって最も分かりやすい「ものの復興」への評価は低く、これは復興事業で整備されたものが老朽化し、維持・更新が困難になっている現状を反映していると考えられる。人の復興は、震災を乗り越えて生まれた新しい命や、子どもたちの育成、災害経験の語り継ぎ、防災人材育成などを含む。心の復興は、震災による精神的な傷の癒やしや心のケアを意味する。町の復興は、コミュニティの再生や、地域社会全体の活性化を指す。組織の復興は、災害ボランティアや、災害時の公的機関・組織間の連携の強化などを意味する。住民は、これらの五つの要素が複合的に絡み合った形で復興を捉えていると考えられる。
3. 住民の復興実感と今後のまちづくりへの期待
住民が復興を実感した時期について見ると、会社員、公務員、専業主婦などは町による復興宣言が出された時を、農林漁業、水産加工、旅館・民宿関係者は仕事や営業再開時を、経営者などは借金返済完了時を挙げている。これは職業や生活様式によって復興への意識や実感の時期が異なることを示している。町の復興、心の復興、人の復興を希求する声が多く聞かれ、震災後整備された公共施設の評価も様々である。奥尻空港は利用者数が伸び悩み、アワビ種苗育成センターは漁業者からの評価が低い一方、奥尻島津波館は観光客や住民から高い評価を得ている。これらの事例から、ハード面中心の復興だけでは不十分で、住民ニーズを反映したソフト面での取り組みが重要であることが示唆される。今後のまちづくりの方向性として、住民は地域医療と地域福祉の進展、交通アクセスの改善、奥尻のブランド化などを強く望んでおり、離島である奥尻町ならではの切実な課題であることがわかる。特に30代と70代以上の層で、地域医療と地域福祉への要望が高い。
4. 防災意識と次世代への継承 語り部と災害教育
住民の9割は、日本で生活するには常に災害と向き合う必要があると感じており、防災・減災への意識は高い。防災経験の伝承方法として、学校での災害教育の工夫が最も多く挙げられており、特に30代から50代の子育て世代でその傾向が強い。家庭での防災教育や地域社会での安心安全な生活のための取り組みも重視されている。防災・減災イベントへの参加や、被災経験者による語り部活動への期待も高い。一方、被災を記念するモニュメントや施設の設置は支持されていない。これは、自然災害の不可抗力性を認めつつ、被害を最小限にするための日頃の備えを重視する姿勢を示していると言える。住民の6割は、自然災害に比べ、人間の判断ミスによる災害が軽視されていると感じており、人為的ミスによる災害リスクへの対策も重要視する必要がある。
III.復興事業の評価 成功例と失敗例からの教訓
奥尻空港は、地域活性化に貢献するはずだったが、利用者数は伸び悩んでいる。アワビ種苗育成センターは、漁業関係者からの評価が低い。奥尻島津波館は、観光資源として一定の評価を得ている。一方、新生ホール・青苗は、住民ニーズを捉えきれず、箱物批判が出ている。これらの事例から、災害復興事業は、ハード面だけでなく、ソフト面、特に住民ニーズを踏まえた計画・運営が重要であることがわかる。持続可能なまちづくりのためには、地域住民の意見を反映した等身大の計画が必要である。
1. 奥尻空港 期待と現実のギャップ
奥尻空港は、滑走路延長(800m→1500m)やターミナルビル新築など、多額の費用を投じて整備された。中型航空機の奥尻・函館線就航も実現し、震災後の島の再生への期待が込められていた。しかし、1997年の就航以降、利用者数はピーク時の18,261人から2013年には10,126人に減少、搭乗率は40.5%と低迷している。町民補助(3,700円)を実施しているにも関わらず、利用者数の伸び悩みは、計画通りの成果が出ていないことを示している。住民へのアンケートでは、83%が「以前と変わらない」と回答、多くの島民が空港を利用していないことがわかる。利用している人の割合が高いのは30代と70代で、職業では農林漁業・水産加工関係者と公務員が多い。これは、空港整備の効果が、期待されたほど地域全体に波及していないことを示唆している。
2. アワビ種苗育成センター 漁業振興への貢献度
アワビ種苗育成センターは、漁業の底上げと発展を目指し、7億6400万円の事業費をかけて整備された。35万個の生産能力を持つが、漁業者への種苗提供数は2003年の15万個から減少している。住民へのアンケートでは、「漁業の底上げと発展に役立っている」と回答した割合は42.9%にとどまり、漁業者、水産加工業者、旅館・民宿では「あまり役立っていない」と回答する割合が高い。ウニとアワビを観光客誘致のキャッチフレーズにしている町にとって、これは懸念材料と言える。一方、公務員や自衛隊員では「役立っている」と回答する割合が高く、地区別では稲穂地区で特に高い評価を得ている。この結果は、センターの実績が十分に町民に伝わっていない可能性を示唆している。
3. 奥尻島津波館 災害学習と観光の両立
奥尻島津波館は、震災で最大の被害を受けた青苗地区に2001年にオープンした。震災からの復興の様子を後世に伝える施設として、年間2万人以上の入場者数を誇る観光スポットとなっている。慰霊碑「時空翔」も併設されている。近年は観光客数の減少に伴い、入場者数も伸び悩んでいる。しかし、町民からの評価は全体として高く、災害学習や観光に役立っていると回答した割合が6割を超えている。特に旅館・民宿では8割を超える高い評価を得ている。水産加工業や商店では「あまり役立っていない」とする回答が若干多いものの、全体的には高い評価を得ていると言える。この施設は、災害の記憶を未来へ繋ぐとともに、観光振興にも貢献している成功例と言えるだろう。
4. ワラシャード 海洋研修センター と新生ホール 青苗 成功と失敗の対比
ワラシャード(海洋研修センター)は、奥尻港フェリーターミナル近くに位置し、多目的ホール、会議室、図書室などを備えた複合施設である。教育委員会も入居しており、学びの場として活用されている。町民からの評価も高く、多様な用途で活用されている。一方、新生ホール・青苗は、激甚被災地区の施設として期待されたものの、住民からの評価は低く、7割が大切ではないと考えている。特に青苗地区と米岡地区では、その割合は2割にも満たない。これは、特殊工法による建築のため改修が困難で、現在閉鎖されていること、当初からの施設の用途、規模、地域のニーズとの整合性が疑問視されていることなどが原因と考えられる。この対比は、住民ニーズを十分に考慮した計画・運営の重要性を示している。
5. 道営住宅 町営住宅と人材育成 課題と展望
道営住宅と町営住宅の利用状況については、住民の多くがいずれも有効利用が必要と考えている。これは、奥尻町に限らず全国的に問題となっている空き家問題と関連している。人材育成については、1995年に道立奥尻高校で導入されたスクーバダイビング授業が紹介されている。これは、地域の特性を生かしたユニークな取り組みであり、漁業後継者育成にも期待されている。しかし、この様な教育活動の効果は可視化しにくく、調査結果では必ずしも高い評価には繋がっていない。潜水の資格の重要性については、30代と70代以上の層で高い評価が見られるものの、全体では4割にとどまっている。このことから、教育効果を長期的な視点で捉え、啓蒙活動を強化する必要性が示唆される。
IV.今後のまちづくりの方向性 住民の願いと課題
住民は今後のまちづくりとして、地域医療・地域福祉の充実、交通アクセスの改善、観光資源の開発・創造、島外への情報発信を重視している。防災教育の充実も強く求められており、家庭や地域社会での防災・減災意識の醸成が重要視されている。被災地サミットや島サミットの活用は、それほど重視されていない。これらの結果から、奥尻町の今後のまちづくりは、住民参加型の持続可能なまちづくりを目指し、地域課題への対応と防災意識の継承を両立させる必要がある。
1. 住民の今後のまちづくりに対する要望 地域課題の克服
災害から20年を迎え、住民は今後のまちづくりの方向性について、9項目の選択肢から3つを選択する形で回答した。その結果、地域医療と地域福祉の進展、交通アクセスの課題克服、奥尻のブランド化の工夫が上位を占めた。これらの項目は、離島である奥尻町にとって極めて切実な課題であり、緊急度の高いニーズであることがわかる。特に、地域医療と地域福祉の進展は、30代と70代以上の層で高い支持を得ており、住民全体の共通の願いであることがわかる。交通アクセスの課題克服は、奥尻町に限らず離島住民にとって共通の課題であり、江差港と瀬棚港を結ぶフェリー航路の便数や運賃の高さが、日常生活に影響を与えていることを示唆している。旅館・民宿、商店経営者などは、観光資源の開拓と創造による地域経済活性化や、島外への積極的な情報発信を重視している。島内外の交流促進も重要な要素である一方、奥尻島人会や同窓会との連携強化、島サミットや被災地サミットの活用は、それほど重視されていない。
2. 防災経験の伝承 次世代への防災意識の涵養
住民の9割は、日本で生涯を送るためには災害と常に向き合う必要があると感じており、防災・減災への意識が高い。防災経験を次世代に伝える方法として、学校での災害教育の工夫が最も多く挙げられている。特に30代から50代の子育て世代において、その割合が高い。家庭での防災教育や、地域社会における安心安全な生活のための取り組みも重要視されている。防災・減災イベントへの参加によって、新しい情報や体験を通して学習しようとする姿勢もみられる。被災経験者による語り部活動の積極的な活用も期待されており、島外への情報発信にも繋がる可能性がある。一方、被災を記念するモニュメントや施設の設置は支持が低く、自然災害の被害を最小限にするための日頃の備えを重視する傾向が強い。また、住民の6割は、自然災害に比べ、人為的ミスによる災害が軽視されていると感じており、人間の判断ミスによる災害リスクへの対策の必要性が指摘されている。
3. まとめ 持続可能なまちづくりに向けて
20年余りの歳月を経て、奥尻町は空き家の増加、商店街の衰退、施設の老朽化、人口流出、過疎化・高齢化といった問題に直面している。震災によって町は一新されたものの、復興後の一時期を除くと、震災前と比較して町の活力が失われているとの声が多い。これは奥尻町に限らず、全国の多くの地域、特に中山間地域でみられる現状である。巨費を投じた復興政策の成果が問われる中、奥尻町の復興はバブル期の意識が色濃く残る中で進められた側面があり、時代の記録と言える。ハード面整備だけでなく、住民ニーズを反映したソフト面での取り組みが重要である。住民は、交通アクセスや医療福祉の充実を強く求めており、これは現在の生活に即した現実的なニーズである。長期的な視点で見た等身大の復興計画が重要であり、住民参加型の持続可能なまちづくりこそが、今後の奥尻町の活性化の鍵となる。
V.結論 等身大の復興計画の重要性
北海道南西沖地震からの災害復興は、バブル経済期の意識が色濃く反映された面があり、ハード面整備に偏っていた。しかし、現状は地域経済の停滞、人口減少、高齢化が進んでおり、ものの復興だけでは不十分であることが明らかになった。今後は、住民ニーズを反映した等身大の復興計画、持続可能なまちづくりが重要である。地域住民の意見を踏まえ、地域医療・地域福祉、交通アクセス、観光などのソフト面を充実させることで、活力ある地域社会の構築を目指す必要がある。
1. ハード中心の復興からの転換 住民ニーズへの対応
北海道南西沖地震からの復興において、奥尻町は多額の義援金を受け、迅速な復興を実現した。しかし、20年以上経過した現在、ハード面中心の復興計画の見直しが必要となっている。住民意識調査の結果、町民は「ものの復興」(ハード面)よりも、「人の復興」、「心の復興」、「町の復興」といったソフト面を重視していることが明らかになった。震災前と比較すると、町の活性化は震災前の方が高かったと多くの人が感じていることから、ハード面の整備だけでは必ずしもまちの活性化に繋がらないという認識が根付いている。 これは、バブル期の意識が色濃く残る中、過剰な消費行動も伴った復興事業が、必ずしも持続可能な発展に繋がらなかったことを示唆している。アンケート調査でも、交通アクセスや医療福祉への要望が高いのは、現在の生活に即した現実的なニーズを反映していると言える。等身大の復興計画の重要性を改めて認識する必要がある。
2. 持続可能なまちづくり 地域課題への対応と教訓
巨費を投じた復興政策の成果が問われる現状において、奥尻町の復興は、バブル期のバラ色の未来像を投影した、ある意味「時代の記録」と言える。震災後の大規模な復旧工事は必要であったものの、当時、他にどのような選択肢があったのかは難しい問題である。今後は、奥尻町の復興の教訓を活かし、住民ニーズを踏まえた等身大の復興計画を策定することが重要である。住民は、ハード面での復興よりも、ソフト面、特に交通アクセスや医療福祉の充実を強く望んでいる。これは、離島である奥尻町の厳しい現状を反映している。 高齢化や人口減少といった課題も深刻であり、これらの問題に対応しながら、地域住民が主体的に関わる持続可能なまちづくりを進めることが不可欠である。震災から20年が経過した今、復興のあり方を改めて考え直す必要がある。
3. 住民参加型の復興 未来への展望
奥尻町の復興は、一時的に地域社会の衰退に歯止めをかける効果はあったものの、長期的な視点で見ると、地域経済の停滞、過疎化・高齢化の進行といった課題が依然として残されている。全国の市町村が策定する基本計画は、中長期的なビジョンを描いているものの、現実には地域経済の停滞や人口減少に苦しんでいるのが現状である。奥尻町においても、住民参加型の、等身大の復興計画を策定し、地域住民が主体的に関わる持続可能なまちづくりを目指す必要がある。交通アクセスや医療福祉の充実、観光資源の開発、防災教育の充実、島内外交流の促進など、住民の要望を反映した具体的な施策を推進することで、活力ある地域社会の創造を目指すことが重要となる。 これは、単なるハード面の整備ではなく、住民の生活水準の向上と安心安全な生活環境の確保に焦点を当てた、真の復興と言えるだろう。
