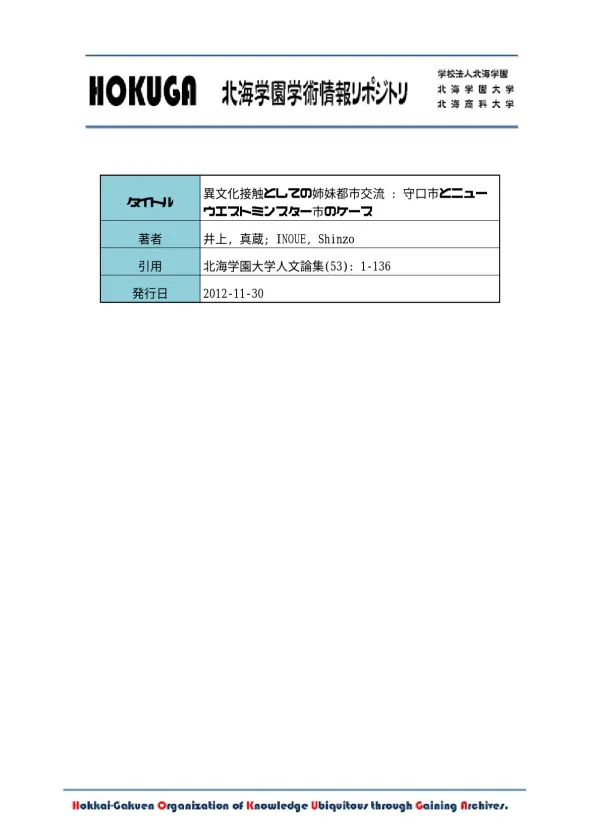
姉妹都市交流:異文化接触の考察
文書情報
| 著者 | 井上 真蔵 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.03 MB |
概要
I.守口市とニューウエストミンスター市の姉妹都市提携プログラム
1963年、守口市とカナダのニューウエストミンスター市は姉妹都市提携を結び、日本とカナダ間の最初の姉妹都市となりました。この姉妹都市交流プログラムは、約半世紀に渡り、中学生の相互派遣や一般市民の短期留学など、活発な交流を続けています。特に、1965年から続く中学生派遣プログラムは、200名以上の中学生が参加し、ホームステイを通じた異文化体験と英語学習を目的としています。選考基準は英語力よりもコミュニケーション能力を重視しており、これは他の自治体と大きく異なる点です。
1. 姉妹都市提携の背景と目的
1963年、守口市はカナダのブリティッシュコロンビア州ニューウエストミンスター市と姉妹都市提携を締結しました。これは日本とカナダ間の初めての姉妹都市提携であり、戦後復興を果たし国際社会への復帰を目指す日本の状況と重なります。1960年代は、池田首相の所得倍増計画、東海道新幹線の開通、東京オリンピック開催など、高度経済成長期であり、一方で1ドル360円の固定為替制度下で海外渡航が困難な時代でもありました。この論文では、守口市とニューウエストミンスター市間の交流プログラムを異文化接触の視点から分析し、参加者(守口市の担当者・職員、中学生、ダグラスカレッジ短期留学生)のカナダ人やカナダ文化へのイメージ、解釈、影響を明らかにすることを目的としています。約半世紀に渡る交流活動は、自治体国際化協会から姉妹自治体優良事例として評価されており、中学生の相互派遣と一般市民の短期留学が特に継続的な取り組みとして挙げられています。中学生の相互派遣は1965年から開始され、隔年で相互訪問が行われています。一方、一般市民の短期留学は3ヶ月間のプログラムで、4名程度の参加者となっています。これらのプログラムを通じて、参加者たちはどのような異文化体験をし、どのような影響を受けているのかを詳細に見ていきます。
2. 中学生派遣プログラム 選考と目的
1965年から開始された中学生派遣プログラムは、守口市国際交流協会が中心となって実施されています。守口市内の中学生をニューウエストミンスター市に派遣し、ホームステイを通じて異文化体験をさせ、英語能力の向上と将来の個性的な人材育成を目指しています。これまで200名以上の中学生が参加しており、現在では教育委員会から選考された教員1名と市職員1名が引率しています。興味深いのは、選考基準が英語力よりもコミュニケーション能力を重視している点です。定員の約2倍の応募者に対し、丸1日かけて面接を行い、コミュニケーション能力の高い生徒を選抜する独自の選考方法は、他の自治体の学校長推薦による選考方法とは対照的です。この方法は、守口市国際交流協会独自の基準による選考が非常に効果的に機能していることを示しています。このプログラムを通じて、生徒たちは異文化の中でどのようにコミュニケーションを築き、成長していくのかを考察していきます。
3. 短期留学プログラム 内容と選考基準
一般市民向けの短期留学プログラムは、夏期英語研修プログラムとして5月初めから6月末までの7週間実施されています。毎年2月頃に守口市の広報紙で募集され、3月中旬に面接試験による選考が行われます。応募資格は守口市民で高校卒業以上、英検2級以上の英語能力を持つ者とされ、選抜されるのは4名程度です。留学中は守口市の代表としてニューウエストミンスター市の公式行事への参加が求められ、留学後は市の国際交流や国際交流協会のボランティア活動への協力が期待されています。奨学金制度として授業料の半額免除とホームステイ費用の一部(C$500)の支給があります。このプログラムは、まさに異文化の中で英語漬けとなる環境を提供し、参加者への影響は非常に大きいと期待されています。プログラムの選考基準、内容、奨学金の制度、そして参加者への影響について、詳細に検討していきます。
II.中学生派遣プログラムと短期留学プログラム
中学生派遣プログラムは、守口市国際交流協会が実施。隔年で相互訪問が行われ、教員と市職員が引率します。短期留学プログラムは、7週間の夏期英語研修プログラムで、守口市民を対象に募集。選考は面接で行われ、4名程度が選抜されます。留学中はニューウエストミンスター市の公式行事への参加が求められます。
1. 中学生派遣プログラム 異文化体験と英語学習
姉妹都市提携から2年後の1965年に開始された中学生派遣プログラムは、守口市国際交流協会が主体となり、守口市内の中学生をニューウエストミンスター市に派遣するものです。このプログラムの目的は、ホームステイを通じた異文化体験と実践的な英語学習、そして将来の個性的な人材育成にあります。これまで200名以上の中学生が参加し、教育委員会から選考された教員1名と市職員1名が引率しています。選考においては、英語力よりもコミュニケーション能力を重視しており、定員の約2倍の応募者から、丸1日をかけて面接を行い選抜しています。この選考方法は、他の自治体の一般的な学校長推薦方式とは異なり、国際交流協会独自の基準による選考が効果的に機能していると言えるでしょう。プログラム参加者にとって、異文化環境での生活、そして日常生活における英語使用は、語学力向上だけでなく、コミュニケーション能力や問題解決能力の向上に大きく貢献すると考えられます。ホームステイ先の家族との交流、学校生活を通して、生徒たちはどのような経験をし、どのような成長を遂げるのか、その詳細な分析が求められます。
2. 一般市民短期留学プログラム 英語研修と国際交流
一般市民を対象とした短期留学プログラムは、7週間の夏期英語研修プログラムとして実施されています。毎年2月頃に守口市の広報紙で募集が行われ、3月中旬に面接試験による選考が行われます。応募資格は、守口市民で高校卒業以上、英検2級以上の英語能力を持つ者とされ、選抜されるのは4名程度です。このプログラムは、単なる語学研修にとどまらず、守口市の代表としてニューウエストミンスター市の公式行事への参加や、留学後の国際交流活動への協力が期待されています。奨学金制度として、授業料の半額免除とホームステイ費用の一部(C$500)が支給される点が特徴です。参加者は、3ヶ月間の滞在期間を通じて、異文化の中で英語漬けの生活を送ることになります。このプログラムが参加者に与える影響は多大であり、語学力向上のみならず、異文化理解や国際的な視野の拡大に繋がるでしょう。プログラムへの応募状況、選考基準、奨学金制度の詳細、そして参加者の留学後の活動や感想などについて、より詳細な調査が必要となります。
III.姉妹都市担当部署とコミュニケーションにおける文化差
守口市側は、財団法人守口市国際交流協会が姉妹都市交流の実務を担当しています。一方、ニューウエストミンスター市側は民間団体が担当することが多く、組織やコミュニケーションスタイルに大きな文化差が見られます。日本側の予定重視、手続き重視の文化と、カナダ側の柔軟で個人重視の文化の違いが、様々な場面で摩擦を生み、担当者はその文化差を乗り越える努力をしています。
1. 守口市とニューウエストミンスター市の担当部署の違い
守口市における姉妹都市交流の担当は、1993年設立の財団法人守口市国際交流協会が担っており、2億円の基金を活用して事業運営を行っています。国際交流協会は、中国との友好都市交流や外国人のための日本語教室なども担当しており、近年は経費面での課題を抱えているようです。これは、日本の多くの自治体でみられる、市から委託を受けて国際交流協会が実務を担当する形態です。しかし、ニューウエストミンスター市側の担当部署は、この形態とは大きく異なります。カナダには、日本の市役所の国際交流課や、守口市のような委託業務を行う国際交流協会のような組織は一般的に存在しません。姉妹都市に関する活動は、民間の友好協会やボランティア団体が担うことが多いのです。ところが、ニューウエストミンスター市にはそのような民間団体が存在しない点が、大きな違いとなっています。この組織体制の違いが、両市の交流におけるコミュニケーションにおいて、どのような影響を与えているのかが、このセクションの焦点となります。
2. コミュニケーションにおける文化差 時間感覚と意思決定
日本側担当者は、表敬訪問などにおいて時間厳守を期待しますが、カナダ側は時間に対してそれほど厳格ではなく、予定時刻より遅れてくることも珍しくありません。5分前集合・着席といった日本的な時間感覚は、カナダ側には馴染みが薄く、日本側担当者は予定の変更や省略を余儀なくされるケースも発生します。日本側が予定通りの遂行を重視するのに対し、カナダ側は予定に縛られず、その場を楽しむことを重視する傾向があることが、この文化差を浮き彫りにしています。さらに、意思決定プロセスにも大きな違いがあります。守口市側は、公的な手続きを踏んで稟議書を作成し、上司の決裁を得なければ物事が進まないのに対し、カナダ側は個人の決定で物事が進む傾向があります。この文化的な違いは、生徒の訪問や交流プログラムの運営において、何度もトラブルや誤解を生み出し、日本側担当者は文化的な溝を埋めるため、何度も説明や確認を繰り返す必要性に迫られています。これらの事例を通して、日本とカナダの文化的な違い、特に時間感覚と意思決定プロセスにおける相違が、交流活動にどのような影響を与えているのかを分析します。
3. 文化的摩擦と対応 自己主張と集団意識 そして臨機応変な対応
カナダ人学生の自己主張の強さや、個人の意思を重視する行動様式は、日本側の担当者にとっては戸惑いの原因となることがあります。日本の学生とは異なり、カナダの学生は自分の意見を積極的に発言し、集団のために感情を抑えるといったことはしません。この違いは、歓迎会での対応や、学校行事への参加など、様々な場面で摩擦を生む可能性があります。例えば、歓迎晩餐会でカナダの市会議員がエルビス・プレスリーの物真似をするなど、日本的な形式に則らない行動も、文化的な違いから生じるものです。しかし、守口市の担当者は、このような状況にも柔軟に対応し、臨機応変な対応を心がけている様子が伺えます。 担当者は、ボランティアを活用するなど、状況に合わせて対応策を講じている点も示唆されています。このセクションでは、文化的な摩擦が生じた際の具体的な事例、そして日本側担当者の対応策やその効果について、詳細に検討していきます。特に、日本とカナダの文化的な違いを理解し、効果的なコミュニケーションを築くための方法論を探求します。
IV.カナダの生活 文化と日本の比較 ホームステイを通して
ホームステイは、学生にとって大きな異文化体験の場となっています。カナダのホストファミリーは、日本の家庭とは異なり、自分の生活スタイルを崩すことなく、温かく学生を受け入れています。コミュニケーションにおいても、日本人の丁寧さとは異なる、率直で直接的なやり取りに戸惑う学生もいる一方で、身振り手振りや簡単な表現を用いるなど、言葉の壁を超える努力が見られます。また、カナダ社会の多様性、人々のオープンさ、時間に対する感覚の違いなども、学生に大きな影響を与えています。特に、異文化交流を通して、学生たちはコミュニケーション能力だけでなく、自己肯定感や問題解決能力を向上させている点が注目されます。
1. ホームステイにおける異文化交流 受け入れ側の姿勢の違い
カナダでのホームステイは、生徒たちにとって最も重要な異文化体験となっています。しかし、同時に、英語でのコミュニケーションの不安も抱えています。 ごく一部の生徒はホームステイで不自由なく過ごせたと述べていますが、ほとんどの生徒は英語でのコミュニケーションに苦労しながらも、それを乗り越えていきます。カナダのホストファミリーは、日本の家庭とは異なる受け入れ方をしています。日本の家庭では、客人を迎え入れる際には特別な準備や気遣いをするのに対し、カナダの家庭では、あくまでも自分の生活スタイルを維持したまま、気楽に客人を迎え入れる傾向があります。この違いは、引率の女性教員が「お気軽にどうぞ」という表現で説明しており、日本の「それなりの気構え」とは対照的です。 この受け入れ姿勢の違いは、日本人の参加者にとって、文化的な衝撃(カルチャーショック)となる場合もあります。例えば、市長とフランクに話し合い、一緒に昼食をとるといった経験は、日本人にとって珍しいことです。このセクションでは、ホストファミリーの受け入れ姿勢、そしてそれがもたらす文化的な差異について詳細に分析します。
2. コミュニケーションの試行錯誤 言葉と文化の壁を超えて
ホームステイ先では、言葉の壁を超えるための様々なコミュニケーションの試行錯誤が見られます。ホストファミリーは、中学生に対して優しい英語や簡単な表現を使い、ゆっくりと、何度も繰り返して理解させようとする努力をしています。これは、通常の状況では見られないほど丁寧で、時間と手間をかけたコミュニケーションです。中には、日本語で質問してくれたり、事前に日本語で書いたメモを用意してくれたりするホストファミリーもいました。この丁寧な対応は、言葉の壁を超えるだけでなく、気持ちの通い合うコミュニケーションを築く上で重要であることを示しています。 一方で、日本の英語教育では身振り手振りや絵を使った表現はあまり教えられていないため、生徒たちは異文化の中で、これらの方法を駆使してコミュニケーションをとることを学びます。この経験を通して、生徒たちは「何とか伝わった」という感覚、そして喜びと自信を身につけていくのです。このセクションでは、具体的なコミュニケーション事例を挙げ、言葉の壁を超えるための工夫や、その効果について考察します。
3. カナダの人間関係と日本の比較 個人主義と集団主義
ホームステイを通して明らかになったのは、カナダと日本の人間関係における大きな違いです。カナダでは、ホストファミリーが、親戚や知人の家にも日本の中学生を連れていくことが一般的ですが、日本では、ホストファミリーは自分の家族だけで受け入れる傾向が強く、大きな責任と負担を感じることが多いでしょう。カナダでは、他の人と共同で何かをすること、他者と接することが日常的に行われており、現代の日本社会では稀な光景です。 学校生活においても、カナダの学校では生徒たちが自由に意見を言い合える雰囲気があり、先生との距離感も日本よりも近いと感じます。日本の学校のように、規則に厳しく縛られることはなく、生徒たちはより自由に学校生活を送っている様子が伺えます。このセクションでは、カナダと日本における人間関係、特に個人主義と集団主義の対比を通して、ホームステイが参加者に与える影響について分析します。特に、カナダのオープンな人間関係が、日本の生徒たちにどのような影響を与えているのかに焦点を当てます。
V.カナダ社会の多様な側面 多言語 多文化共存
カナダでは、英語とフランス語の二言語表示が一般的です。特にケベック州ではフランス語文化が強く、多文化共存社会を垣間見ることができます。学生たちは、スーパーの二言語表示や、フランス語圏出身の人々との交流を通して、カナダの多様な文化に触れ、新たな視点を得ています。また、カナダの高齢者の生き方、家庭での役割分担、そして教育システムについても、日本との比較を通して考察されています。
1. 二言語文化 英語とフランス語の共存
カナダ社会における多様な側面の一つとして、英語とフランス語の二言語文化が挙げられます。カナダ政府の法律により、全国的に流通する商品の表示は英語とフランス語の両方で表記されなければなりません。しかし、ケベック州以外では英語しか話せない人が多く、フランス語表記は実際には読まれないケースも多いようです。このことは、カナダ社会における英語の優位性を示唆しています。一方、フランス語圏であるケベック州ではフランス語文化が強く根付いており、カナダ社会における多言語・多文化共存の複雑さを示す一例となっています。また、フランス語圏の学校であるFrench Immersionの教育を受けてバイリンガルになる人もいますが、彼らにとっての主な就職先は、バイリンガルが条件となる連邦政府の公務員や通訳といった分野に限られることが多く、民間企業では必ずしもバイリンガルであることが有利とは限らないことも示唆されています。この二言語文化が、カナダ社会にどのような影響を与えているのか、そして、それが日本人の参加者にどのように映っているのかについて考察します。
2. 多民族共存社会 多様な人種と文化の融合
カナダは多様な人種が共存する多民族国家です。スーパーマーケットでは、レジ係が次の客の商品を手元に運ぶベルトコンベアーや、日本では見慣れない大きな袋に入ったお菓子など、日本のスーパーマーケットとは異なる光景が見られます。さらに、アジア人が現地のカナダ人と同様に英語を話すことに驚くなど、多様な人種が共存し、互いにコミュニケーションをとっている様子が伺えます。また、服装についても、日本のように画一的な服装ではなく、個人が自由に服装を選択できる社会であることがわかります。 ゆったりとした街並み、自然との共存、そして多様な人種が織りなすカナダの街の風景は、日本の都市部とは大きく異なっており、参加者たちはこれらの違いを鮮明に認識しています。この多文化共存社会が、カナダ人の考え方や行動にどのような影響を与えているのか、そして、それが日本人の参加者にどのように映っているのかについて考察します。特に、カナダ社会の多様性が、参加者の価値観や世界観にどのような変化をもたらすのかに焦点を当てます。
3. ケベック文化とカナダの歴史 二つの文化の共存と葛藤
ケベック州のナンバープレートに書かれた「Je me souviens(私は忘れない)」という言葉は、ケベックの人々が自らの文化を維持しようとする強い意志を示しています。この言葉は、カナダの歴史、特にフランス文化とイギリス文化の共存と葛藤を想起させます。1608年にケベックを拠点として成立したニューフランスは、イギリスとの戦争に敗れ消滅しましたが、フランス人たちはケベックに残り、独自の文化を維持してきました。この歴史的背景を知ることによって、「Je me souviens」という言葉の意味をより深く理解することができます。 ダグラスカレッジの留学生たちは、ケベッカーとの交流を通して、カナダ社会におけるフランス語文化の存在感を認識し、カナダという国の歴史的背景や文化的多様性をより深く理解していきます。このセクションでは、ケベック文化の特質、そしてそれがカナダ社会に与える影響、さらにそれが日本人の参加者に与える印象について分析します。特に、カナダの成立過程におけるフランス文化とイギリス文化の複雑な関係性に着目し、その歴史的背景と現代社会との関連性を考察します。
