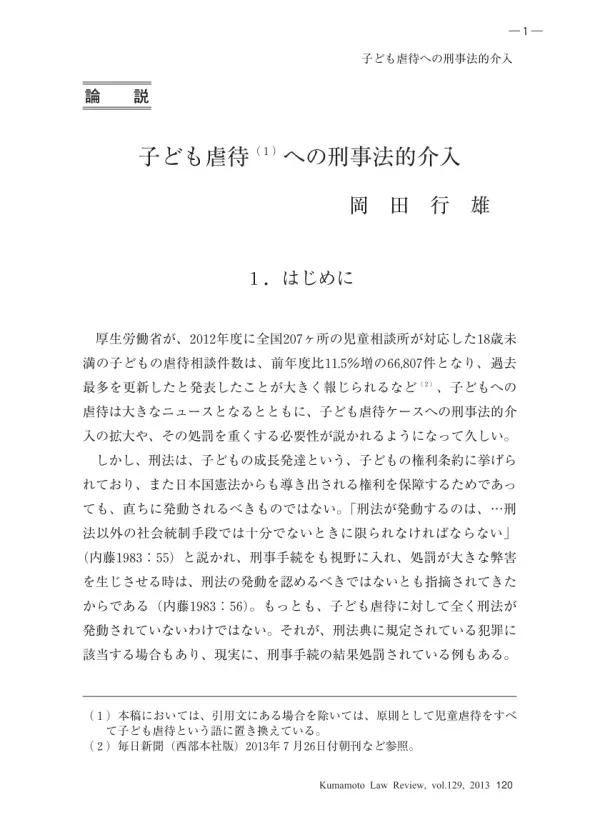
子ども虐待への刑事法的介入:現状と課題
文書情報
| 著者 | 岡田 行雄 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 529.43 KB |
概要
I.児童虐待事件への刑事法的介入の現状と課題
本論文は、児童虐待(特に身体的虐待、性的虐待、ネグレクト)に対する刑事法的介入の現状と課題を分析しています。児童相談所への相談件数は増加傾向にあり、警察の検挙件数も増加していますが、統計データには限界があり、実際の子ども虐待の発生件数を正確に把握することは困難です。刑事裁判における不作為犯の取り扱い(傷害致死幇助罪、殺人罪、保護責任者遺棄致死罪など)の判例を分析し、作為義務の範囲や故意の認定に関する問題点を指摘しています。特に、ネグレクトによる死亡事件において、不作為の殺人罪が適用される事例が増加しており、その理論的妥当性について疑問を呈しています。また、量刑のばらつきも問題視されています。
1. 児童虐待相談件数の増加と統計データの限界
厚生労働省の発表によると、2012年度の児童相談所への児童虐待相談件数は66,807件と過去最多を更新しました。しかし、この増加が必ずしも児童虐待の発生件数の激増を意味するとは限りません。戦後、社会的荒廃の中で児童虐待は認知されにくかったのに対し、現代社会では、少子化や子育てへの経済的負担増加により、保護の怠慢・拒否や子どもの暴力といった行為が顕著になり、認知度が向上した側面があるという指摘があります。竹中(2002)は、児童虐待は近年漸増している可能性はあるものの、激増しているとはいえないと推定しています。また、検挙後の刑事手続きに関するデータは公開されておらず、公訴提起状況や有罪判決後の処罰内容を統計的に把握することは困難です。 しかし、少なくとも児童虐待事件の検挙件数は1999年から2011年にかけて3倍以上に増加しており、これは児童虐待への刑事法的介入の増加を示唆しています。平成12年警察白書以降、児童虐待事件の検挙件数は身体的虐待、性的虐待、怠慢・拒否などに分類され、毎年公表されていますが、検察統計や司法統計による詳細なデータは不足しています。
2. 刑事裁判における不作為犯の取り扱いと問題点
児童虐待事件における刑事法的介入の現状を理解するために、刑事裁判における不作為犯の判例を分析します。一例として、子どもの虐待を認識しつつも止めなかった母親が傷害致死幇助罪で起訴された事例では、釧路地方裁判所は不作為による幇助の成立を否定しました。判決は、不作為による幇助犯の成立には、作為義務を有する者が犯罪実行をほぼ確実に阻止できたにも関わらず放置し、その不作為を作為による幇助と同視できる必要があると判断しました。この事例では、母親も内縁の夫からの暴行被害者であり、夫の暴力を阻止することが困難であったため、不作為による幇助は成立しないとされました。その後、1歳2ヶ月の子供を殺害した母親を制止しなかった父親が殺人の共謀共同正犯として起訴された事例では、大阪高等裁判所は、父親の不作為を殺人の共謀共同正犯と認定しました。さいたま地方裁判所と東京高等裁判所も、ネグレクトにより子供が死亡した事例で不作為の殺人罪の成立を認め、懲役8年の判決を言い渡しました。これらの判例から、児童虐待に関連する不作為犯の成立範囲が拡大し、刑法的評価が厳しくなっている傾向がわかります。しかし、不作為による傷害致死の幇助と不作為による殺人の共謀共同正犯、不作為による保護責任者遺棄致死と不作為による殺人の明確な区別基準は、必ずしも提示されていません。また、殺人の故意の認定についても、事実認識の有無だけでなく、裁判官の裁量に委ねられる傾向があり、理論的な問題点が指摘されています。
3. 量刑のばらつきと社会状況の反映
児童虐待事件の量刑にはばらつきがあり、例えば、不作為の殺人罪で有罪とされた被告人の量刑に大きな差が見られます。櫻庭(2010)は、不作為の殺人罪で懲役3年だった事例と懲役15年だった事例を比較し、その差を問題視しています。裁判員裁判では、両親による継続的な暴行により子供が死亡した事例で、両親にそれぞれ懲役15年の有罪判決が言い渡されました。この量刑は、児童虐待が社会問題として認識されている社会情勢、行為の重大性、常習性、動機などの要素を考慮した結果です。 しかし、被告人の置かれている状況(離婚、一人親家庭、経済的困窮など)が、被告人の責任能力の低さや社会的支援の欠如を示すものとして言及される一方、社会的支援を拒絶したとして責任を加重する方向で用いられる傾向もあります。被告人にとって変更が困難な状況を量刑を重くする要素とすることは、公平性の観点から問題視されます。 また、ネグレクトによる死亡事件で殺人罪が適用される事例が増加している背景には、不作為の殺人罪における作為義務の内容とその発生根拠が不明確なまま、裁判官の裁量に委ねられる傾向があるという問題点があります。
II.子ども虐待罪に関する立法提案の検討
子ども虐待に関する新たな犯罪類型(子ども虐待傷害罪、子ども虐待致死罪、子どもへの性的虐待罪など)の立法提案が検討されています。これらの提案は、既存の罪名での処罰を強化し、処罰範囲を拡大することを目的としていますが、一般予防効果や特別予防効果に関する疑問、人権制約の拡大といった問題点が指摘されています。重罰化が必ずしも子ども虐待の防止に繋がるわけではないという懸念も示されています。また、ペアレント・プログラムのような保護者向けプログラムの受講を強制することについても、その有効性や人権侵害とのバランスが問われています。
1. 子ども虐待罪に関する立法提案の現状と目的
近年、子ども虐待への刑事法的介入の拡大、処罰強化の必要性が叫ばれており、それに伴い、新たな子ども虐待罪に関する立法提案が検討されています。具体的には、既存の傷害罪や傷害致死罪で処罰されている行為をより重く処罰する「子ども虐待傷害罪」「子ども虐待致死罪」の創設、そして性的虐待に関する罪状の明確化や拡大が挙げられます。岩井・渡邊(2012)は、「幼年者への性的濫用を処罰する構成要件を設けることなども考えられる」と示唆しており、性的虐待に関する処罰範囲の拡大が目指されていることがわかります。これらの立法提案の狙いは、個別の虐待行為の日時が特定できなくても、虐待行為の継続性・常習性を包括的に処罰できるようにすること、つまり捜査機関の立証負担を軽減することにもあります。 しかし、具体的な法定刑の内容は示されておらず、保護法益の範囲(身体の安全、性的自由、健全な発達など)や、責任ある者による侵害行為への責任非難の強さなど、様々な解釈が可能です。長期にわたる虐待行為を、単発の傷害や傷害致死では評価できないという点から、虐待行為の継続性・常習性を正当に評価できる犯罪構成要件の創設も検討されています。
2. 重罰化 処罰範囲拡大の是非と予防効果
子ども虐待罪の重罰化や処罰範囲拡大は、加害者の人権制約拡大を意味します。しかし、子どもの成長発達権という憲法上の権利を保障する観点から、他の社会統制手段では十分な保障ができない場合、重罰化は理論的に必ずしも問題とは限りません。 ただし、重罰化に一般予防効果があることは実証されておらず(宮澤1991、津富2002)、重い刑事罰が再犯防止(特別予防効果)に繋がるかどうかも疑問視されています。従って、既存の罪状の刑罰を重くすること、または処罰対象範囲を拡大することが、子どもの成長発達権保障に必ずしも繋がるわけではないと考えるのが妥当です。 より幅広い範囲の虐待行為を処罰対象とするためには、児童虐待防止法やペアレント・プログラムのような、他の社会統制手段が十分に機能していることが前提となります。法定刑の設定に当たっては、加害者ケアと家族再統合を目的とした施設内・社会内処遇の整備と、効果的な運用期間の設定が重要だとされています(岩井・渡邊2012)。
3. 保護観察と特別遵守事項としてのプログラム受講の強制
立法提案に関連して、保護観察中の特別遵守事項として、ペアレント・プログラムのような、子どもの養育方法などを学ぶプログラムの受講を強制する可能性が検討されています。このプログラムは、虐待的言動やネグレクトが顕著な保護者を対象とした、セルフケアと問題解決能力向上のためのものです。 理論的には、特別遵守事項は対象者の社会復帰のために必要な範囲で自由を制限し、行動指針を示すものです(正木2012)。日本国憲法13条の人権制約最小化の原則から、自由制限は、対象者が再犯を繰り返さず、子どもの成長発達権を保障する範囲内で必要最小限でなければなりません。 ペアレント・プログラム受講者の暴言や暴力が減少したという指摘もありますが(森田2012)、これは任意受講者に関するものであり、受講強制が同様の効果を生むかは不明です。従って、受講強制が社会復帰のため、必要最小限の自由制限であり、再犯防止効果があると断言することはできません。
III.警察と児童相談所の連携強化と課題
児童虐待への対応において、警察と児童相談所の連携強化が図られていますが、行政警察活動と司法警察活動の線引きが曖昧なまま、警察の介入が拡大される傾向があります。その結果、児童相談所のケースワークが阻害され、子どもの保護や成長発達に悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。児童相談所が保有する記録の提供や押収に関しても、公務上の秘密との関係で問題が生じています。捜査機関の介入が、子ども虐待への他の対応手段(福祉的介入、民事的介入など)を阻害する可能性も指摘されています。
1. 児童虐待防止法と警察 児童相談所の連携強化
児童虐待防止法では、児童相談所長が警察署長に援助を求める規定(10条1項)があり、警察は児童相談所の職務執行を援助する役割を担っています。警察官は児童相談所職員の職務執行の現場に臨場し、保護者による妨害行為に対して警察官職務執行法に基づく警告や住居への立ち入りなどの措置をとるようになりました(高橋2012)。警察庁と厚生労働省は警察と児童相談所の連携強化に取り組んでおり、2011年4月1日時点で、警察官が児童相談所に配置された自治体は35にのぼります(高橋2012)。この連携強化は、児童相談所職員が困難を感じている親の攻撃や恫喝から解放され、子どもの処遇や次の展開を円滑に進める上でプラスに働く側面があります。しかし、行政警察活動と犯罪捜査との分離があいまいであれば、児童相談所職員との会話が警察に筒抜けとなり、親との信頼関係構築が困難になる可能性があります。黙秘権の告知なく行われた警察官とのやり取りが、後の取調べに影響を与える可能性も懸念されます。
2. 刑事法的介入が児童相談所の職務に及ぼす影響
児童虐待への対応には、刑事法的介入の他に、児童相談所を中心とした福祉法的介入、家庭裁判所を中心とした民事法的介入など複数の対応手段があります。しかし、捜査機関は様々な権限を有し、刑事訴訟法上の制約は少ないため、捜査が開始されると、他の対応手段は事実上優先順位が低くなってしまいます(津崎2005)。 このことは、児童相談所の職務の本質であるケースワークを困難にし、子どもの成長発達権保障という観点から問題となります。捜査機関が児童相談所に対して、子どもや家庭状況に関する記録の提供を刑事訴訟法197条に基づき求めても、児童相談所が職務に支障が生じるおそれがあるとして応じられない場合も考えられます。また、令状によって記録を押収しようとしても、刑事訴訟法103条の公務上の秘密を理由に拒否される可能性があります。 このように、捜査機関の介入が児童相談所の職務を困難にし、結果として子どもの成長発達を阻害するという問題が指摘されています。 独占禁止法違反のように、行政手続きや行政処分を刑事手続きに優先させている立法例もある中で、児童虐待問題においても、刑事法的介入が他の対応手段を阻害する場合は、捜査の優先順位を再考する必要があると考えられます。
3. 警察介入の拡大と人権侵害の懸念
警察の介入拡大を主張する意見には、行政警察活動と司法警察活動の区別があいまいであり、警察活動に関する理論的な問題が残されているという指摘があります。 特に、行政警察活動の名の下に事実上の司法警察活動が行われ、憲法35条などの犯罪捜査に関する規制を回避する危険性も指摘されています。 戦前・戦時中を彷彿とさせる警察による人権侵害の拡大を容認するものではないとしても、行政警察活動に名を借りた犯罪捜査の拡大は、憲法上の問題を提起します。 警察が親を逮捕・勾留した場合、児童相談所職員は親からの執拗な攻撃・恫喝から解放されるというプラス面もありますが、親が警察の捜査を知れば、児童相談所職員との信頼関係構築が困難になり、ソーシャルワーク的援助が阻害されます。 児童相談所が保有する記録の押収が児童相談所の職務を阻害する場合、刑事訴訟法103条の「国の重大な利益を害する場合」に該当する余地があると解釈される可能性もあります(大矢)。行政手続きと刑事手続きの区別を曖昧にしないよう、慎重な対応が必要です。
IV.子ども虐待への刑事法的介入の必要性と限界
子ども虐待が疑われる場合の刑事法的介入は、子どもの保護という観点から必要不可欠である一方、家族の生活状況への配慮や、児童相談所の職務への支障といった問題点も存在します。刑事的対応は、ソーシャルワーク的アプローチを困難にする可能性があり、親子関係の修復を阻害するリスクも孕んでいます。また、子どもの事情聴取における不適切な尋問も、子どもの成長発達に悪影響を与える可能性があります。さらに、親の逮捕・勾留に伴う子どもの児童福祉施設への入所も、必ずしも子どもの適切なケアを保証するものではありません。子ども虐待の要因(貧困、産後うつ、DVなど)に対処する社会的な支援体制の充実が、刑事法的介入以上に重要であるという指摘もなされています。
1. 刑事法的介入の必要性と子どもの権利
子ども虐待が疑われる事件への刑事法的介入は、子どもの保護、すなわち子どもの成長発達権保障という観点から必要不可欠な側面があります。しかし、刑事法的介入が常に最善策とは限りません。刑事的対応は家族の生活事情を斟酌せず、児童相談所のソーシャルワーク的アプローチを阻害する可能性があります。 児童相談所は、親の状況を把握・理解し、信頼関係を構築した上で必要な援助を行うことを目指していますが、警察の介入によってその信頼関係が壊れてしまう可能性があります(津崎2005)。 また、刑事法的介入は、児童虐待事件の捜査手続きや、犯罪と認定された場合に科される刑罰の両面から、子どもの成長発達権保障の観点で問題点を含んでいます。捜査手続きにおいては、子どもの事情聴取が不適切に行われることで、子どもの成長発達が直接的または間接的に阻害される可能性があります(仲2004)。 親の逮捕・勾留により子供が児童福祉施設に入所する場合、施設でのケアが不十分で、再度心の傷を負う可能性や、施設内での虐待リスクも存在します(斉藤・藤井2012)。また、刑務所に服役した親の養育能力が向上するとは限らず、親子の再統合を確実に保証する制度もありません。そのため、児童福祉施設退所後の子供の成長発達権も保障されるとは限りません。罰金刑も、経済的に苦しい家庭の生活をさらに困難にする可能性があります(石川1979)。
2. 刑事的対応とソーシャルワーク的アプローチの矛盾
児童相談所のワーカーは、虐待があったとしても、ソーシャルワーク的に親や家族を指導・改善させたいと考えている場合が多いです。しかし、刑事的対応は、そのようなソーシャルワーク的アプローチを完全に否定してしまう可能性があります。警察の介入は、児童相談所の実務にとってマイナスと受け止められる可能性も出てきます。 警察の判断や行動は独自に行われ、協議の余地が少ない上、児童相談所に対して加害者告発の手続きを要請したり、ケース資料の全面提供を求めたりするため、ソーシャルワーク的援助がさらに困難になります(津崎2005)。 児童相談所が親による虐待を疑い、信頼関係を構築しようとしている段階で、警察が捜査を開始したことが親に知られると、その信頼関係は壊れてしまい、適切な親子関係の再構築が困難になります。このため、捜査機関の関与が児童相談所の職務を困難にし、子どもの成長発達を阻害する可能性があります。
3. 刑事法的介入の限界と代替手段の重要性
児童虐待の要因として、子育ての協力者不足、産後うつ病、経済的貧困、望まない妊娠、子供の障害、世代間連鎖などが挙げられます(斉藤・藤井2012)。これらの要因が虐待行為の原因であり、加害者自身では除去できない場合、適法行為を選択することが困難であったとみなすことができます。規範的責任論の観点からは、適法行為が困難な場合には責任を問うことはできず、厳罰は妥当ではないとされます。 仮に適法行為の可能性が残されていたとしても、その可能性が大きく減じられている場合、やはり厳しい処罰は妥当ではありません。 後藤(2004)は、少年法を参考に、未成熟な親に対して再教育を行うシステムの構築が必要だと指摘しています。また、林(1991)は、異常な状況下での虐待行為に対しては、加害者を処罰する必要はないとしています。 自由刑による特別予防効果にも疑問があり、長期間の社会からの隔離を伴う厳しい刑罰は不要であると考えられます。 児童虐待の克服には、ジェンダーバイアスの見直しなども含め、根本原因への対応が不可欠であり、刑事法的介入はあくまで最終手段として、慎重に検討されるべきです(前田2008)。
V.結論 多角的なアプローチの必要性
子ども虐待の問題解決には、刑事法的介入だけでなく、児童相談所を中心とした福祉的介入、家庭裁判所を中心とした民事的介入など、多角的なアプローチが不可欠です。刑事法的介入は、他の対応手段を阻害することなく、子どもの保護と成長発達を最優先する形で、慎重かつ適切に行われるべきです。子ども虐待の根本原因に対処するための社会的な取り組み(経済的支援、子育て支援、DV防止策など)が、最も重要な課題となっています。 子ども虐待は社会全体の問題であり、継続的な取り組みが求められます。
1. 子ども虐待への対応 刑事法的介入の限界と多角的アプローチの必要性
本稿の検討により、子ども虐待への対応において刑事法的介入の拡大は必ずしも解決策ではないことが明らかになりました。刑事法的介入は、子どもの保護という観点からは重要ですが、家族の生活状況への配慮や、児童相談所のソーシャルワーク的アプローチとの整合性といった課題を抱えています。刑事的対応は、家族の生活事情を考慮せず、児童相談所のワーカーがソーシャルワーク的に親や家族を指導・改善しようとする試みを完全に否定してしまう可能性があります。警察の介入は、児童相談所と親との信頼関係構築を阻害し、ソーシャルワーク的援助を困難にするという矛盾も生じます(津崎2005)。 さらに、刑事手続きにおける子どもの事情聴取の不適切さ、児童福祉施設におけるケアの不足、親子の再統合システムの欠如など、子どもの成長発達権を保障する上で様々な問題点が指摘されています。 厳罰化による一般予防効果も実証されておらず、むしろ逆効果となる可能性も示唆されています(キャプナ弁護団有志2004)。 子ども虐待の原因となる、子育て支援の不足、経済的貧困、DVなど多様な要因への対処が、刑事法的介入以上に重要です。
2. 刑事法的介入の最終手段化と他の介入手段との連携
子ども虐待は、刑事法的介入以外にも、児童相談所を中心とした福祉法的介入、家庭裁判所を中心とした民事法的介入など、複数の対応手段が法的に制度化されています。しかし、刑事法的介入は、捜査機関の強い権限と、他の対応手段への制約が少ないことから、他の手段を阻害し、子どもの保護や成長発達を阻害する可能性があります。 捜査機関は、児童相談所の記録提供を要求したり、記録を押収したりする可能性があり、児童相談所の職務遂行を阻害する可能性があります。この場合、刑事訴訟法103条の「国の重大な利益を害する場合」に該当する可能性も指摘されています(大矢)。 刑法は謙抑性、断片性、適応性を有しており、刑法による保護が新たな弊害を生む場合は、その保護は控えられるべきです(内藤1983)。 よって、子どもを保護するための様々な制度が存在する中で、刑事法的介入は、他の手段が機能しない場合の最終手段として、可能な限り控えられるべきです。
3. 多角的アプローチによる子ども虐待問題への総合的対策
子ども虐待問題の解決には、刑事法的介入だけでなく、福祉的介入、民事的介入など、多角的なアプローチが不可欠です。刑事法的介入は、他の対応手段を阻害することなく、子どもの保護と成長発達を最優先する形で慎重かつ適切に行われるべきです。 子ども虐待の根本原因に対処するための社会的な取り組み、具体的には経済的支援、子育て支援、DV防止策などが、刑事法的介入以上に重要です。 未成熟な親に対する再教育システムの構築(後藤2004)や、ジェンダーバイアスの見直し(前田2008)、児童福祉司の労働環境改善(斉藤・藤井2012)など、多様な課題への取り組みが求められています。 これらの課題への取り組みが放置されれば、子ども虐待は増加し続け、刑法や刑事制裁の価値を損なうことになります。 子ども虐待問題への対応は、社会全体の問題であり、継続的な取り組みが不可欠です。
