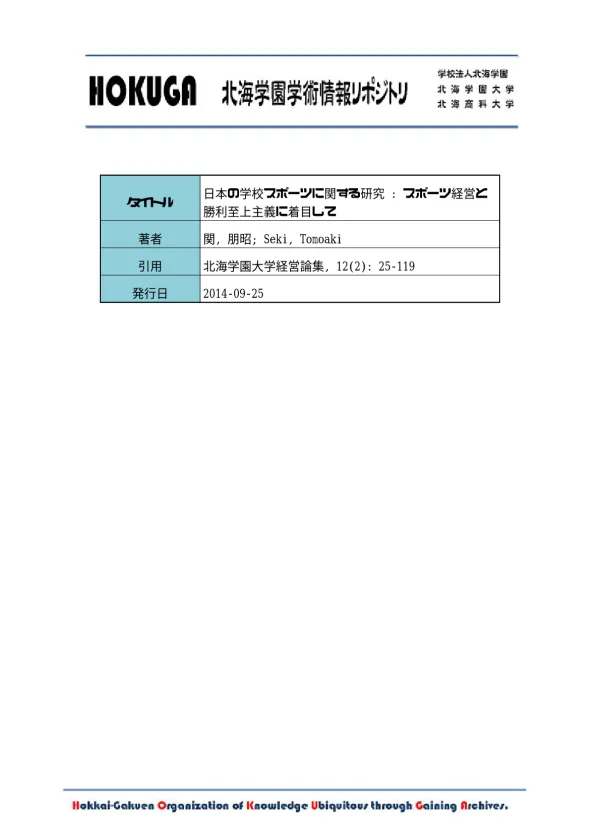
学校スポーツ経営と勝利至上主義
文書情報
| 著者 | 関 朋昭 |
| 専攻 | スポーツ経営 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.18 MB |
概要
I.日本の学校スポーツの歴史と現状 勝利至上主義 と スポーツマンシップ の葛藤
本論文は、日本の学校スポーツ、特に部活動の歴史と現状を分析しています。古代から存在したとされる相撲やボクシングに触れつつ、近代スポーツの導入、特に教育との深い関わりを考察しています。明治以降、教育勅語の影響や、戦後のアメリカの影響下での変化を辿り、現代における勝利至上主義の根強い浸透と、スポーツマンシップの欠如という課題を浮き彫りにしています。特に、高校野球における伝統校の優位性や、教師の転勤による指導体制の変化などが、勝利至上主義を助長してきた要因として指摘されています。
1. 古代から現代までの日本のスポーツ史観 スポーツマンシップ の変遷
本文は、3000年前の相撲やボクシングの存在を示唆する記述から始まりますが、その証明は困難とされています。寒川恒夫(1993)の指摘を引用し、スポーツ史の起点設定は研究者のアイデンティティにも関わる問題であり、古代ギリシャを普遍的なモデルとする見方に批判的な姿勢を示しています。しかしながら、古代ギリシャスポーツの後世への影響は依然として大きいと認めています。その後、近代化を目指す日本において、学校教育と密接に結びついたスポーツの普及が説明され、戦後の高度経済成長期には企業スポーツが誕生した経緯が述べられています。特に野球の人気の高さが強調され、戦後の鉄鋼産業の隆盛との関連性が示されています。このように、歴史的観点から、日本のスポーツ発展における重要な転換期や社会情勢との関連性が示され、現代の状況を理解するための基礎が築かれています。特に、初期のスポーツにおける「スポーツマンシップ」の概念の希薄さ、そして、後の「勝利至上主義」への移行の伏線がここに含まれています。
2. 学校スポーツにおける 勝利至上主義 の浸透 一高野球と飛田野球の系譜
明治時代の一高野球と飛田野球を取り上げ、日本の学校スポーツにおける勝利至上主義の起源と、それがいかに根付いたかを分析しています。一高では寄宿舎制度や校友会組織を通して徳育を重視した教育が行われ、そこに導入された野球は「負けは恥、勝ちを強く意識した」ものへと変容しました。これは日本の勝利至上主義の原点とされています。さらに飛田野球では、過酷な「死の練習」が一般的になり、それが広く知れ渡った背景も説明されています。これらの記述から、日本の学校スポーツにおいて、勝利への執着が、いかに厳格な規律と過酷な練習によって支えられてきたかが明らかになります。このセクションは、現代の学校スポーツにおける問題点の根源を理解する上で重要な歴史的背景を提供しています。特に、一高野球と飛田野球の厳格な規律と、結果として生まれた勝利至上主義の文化的土壌が強調されています。
3. 現代の学校スポーツを取り巻く課題 勝利至上主義 と スポーツマンシップ の対立
現代の学校スポーツが直面する問題点として、勝利至上主義、根性主義、バーンアウト現象、体罰、部活動離れ、スポーツ障害、教師の過重負担などが挙げられています。これらの問題は、長年にわたって指摘されてきたにもかかわらず、解決に至っていない現状が強調されています。また、部活動の課題解決策として「地域委譲論」が提案されているものの、学校教育における部活動の存続理由が改めて問われています。さらに、部活動に関わる利害関係者の複雑さも指摘され、教師のボランティア精神への依存や、その結果として生じるフリーライダー的な状況、そして、国民の多くが「学校には部活動がある」という前提を無意識に共有している現状も分析されています。これは、日本の学校スポーツにおける勝利至上主義とスポーツマンシップの対立を深く理解するために不可欠な、現状認識を提供するセクションです。特に、社会全体が抱える問題点と、その解決に向けた取り組みの難しさが強調されています。
II.学校スポーツのマネジメント 教師 の役割と資源の活用
戦後の高度経済成長期における学校スポーツの隆盛と、それに伴うマネジメントの変遷を分析しています。特に、教師のボランティア精神に支えられてきた部活動の運営体制、限られた資源(人材、施設、資金)の活用方法、そして、野球部における専用グランドの確保による練習効率化と、他の部活動との調整の難しさといった課題を明らかにしています。また、企業スポーツの台頭と衰退についても言及し、東京電力女子サッカー部の休部を例に、経済的側面からの課題を示しています。
III.部活動を取り巻く複雑な利害関係 地域委譲論 の検討
部活動を取り巻く利害関係者の複雑化を分析し、教師の過剰な負担や、保護者、地域社会との関係性の問題点を指摘しています。勝利至上主義、体罰、スポーツ障害、部活動離れといった現代の課題を提示し、それらへの解決策として地域委譲論が議論されていることを示しつつ、学校教育における部活動の根強い存在感を考察しています。和田中学校の事例を挙げ、部活動の改革と企業との連携の可能性、そして、外部コーチとの連携における課題について言及しています。
IV.学校スポーツの未来 生徒の 自主性 と創造性を育む
日本の学校スポーツの未来像として、生徒の自主性と創造性を育むことの重要性を強調しています。学習指導要領の改訂における部活動への言及を踏まえ、既存の勝利至上主義的な考え方からの脱却を促し、生徒自らが課題を発見し解決していく能力を育成する必要性を訴えています。X高等学校の事例を提示し、生徒主導の活動による学校スポーツの改革の試みを紹介し、協同化による新たな学校スポーツのあり方を提案しています。
