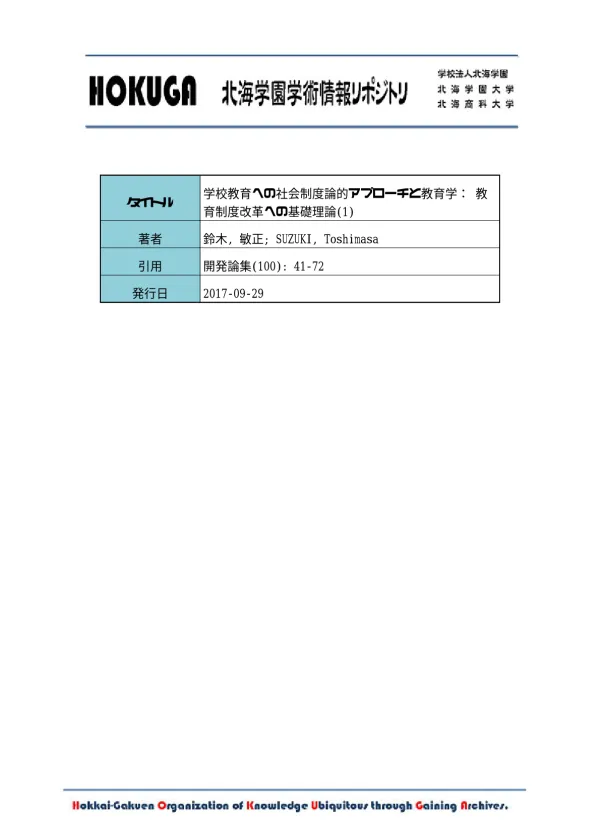
学校教育制度改革:社会制度論的アプローチ
文書情報
| 著者 | 鈴木敏正 |
| 専攻 | 教育学 |
| 会社 | 開発論集(100) |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.35 MB |
概要
I.戦後日本教育批判と教育制度論 教育の再定義と課題
本稿は、戦後日本の教育制度を社会制度論的視点から批判的に分析し、教育改革のあり方を提言する論文である。特に、高度経済成長期からポスト近代社会への移行期における教育制度の変遷と、グローバリゼーションや新自由主義の影響を考察している。教育基本法の大改定(2006年)や教育再生実行会議の動向なども重要なキーワードとなる。佐藤学の指摘する日本の学校の「15年以上の遅れ」や、シティズンシップ教育、政治教育の課題も議論されている。ユネスコの国際教育会議(1996年)の勧告や、**持続可能な開発のための教育(ESD)**の重要性も強調されている。
1. 教育の再定義と現代社会の要請
このセクションは、現代社会における教育の役割を再定義する試みから始まります。戦後改革から高度経済成長期(1960年代)、そして近代的価値観への疑念と批判が顕在化した1990年代を経て、現在(21世紀)の「ポスト産業社会」「ポスト近代」社会に求められる教育のあり方が議論の中心となっています。 佐藤学の『教育改革の中の学校』を引き合いに出し、知識基盤社会、多文化共生社会、格差リスク社会、成熟した市民社会への対応という21世紀型学校の4つの指標が提示されます。しかし、佐藤学は、日本の学校がこれらの指標において「15年以上の遅れ」を示していると指摘しています。18歳選挙権導入を機に活発化しているシティズンシップ教育や政治教育の重要性も強調され、「公共性の危機と教育の課題」という小玉重夫の論考が紹介されています。これは、公教育再建のためには「教育の再政治化」が必要であるという主張につながっています。
2. 戦後教育の変遷と新自由主義的改革
中曽根内閣時代の臨時教育審議会(1984-87年)を契機に、日本における本格的な戦後教育の再検討が始まりました。グローバリゼーションの進展に伴い、市場競争を重視する「新自由主義的改革」が進められ、社会福祉や教育制度といった戦後の社会制度に大きな影響を与えました。2006年の教育基本法(1947年)の大改定は、この改革の大きな転換点を示しています。その後、特に第2次安倍内閣の下で「教育再生実行会議」が中心となり、具体的な教育改革が推進されています。この流れの中で、教育制度の変遷と新自由主義的改革の影響が分析されています。規制緩和や民間活力導入といった具体的な政策がどのように教育制度に影響を与えたのか、その経緯と影響が詳細に検討されていると考えられます。
3. ユネスコの勧告と持続可能な開発のための教育 ESD
ユネスコの第45回国際教育会議(1996年)では、「教師の役割と地位に関する勧告」が採択され、現代社会の深刻な社会統合問題への対応として、教師の役割が再定義されています。具体的には、「好奇心、批判的思考と創造性、自発性と自己決定能力」の発達を促し、「市民性の育成と社会への積極的な統合」を支援する教育活動が求められています。さらに、教師はコミュニティにおける変革の効果的な担い手として機能することが期待されています。こうした国際的な潮流の中で、2011年の東日本大震災からの復興を踏まえ、「持続可能な発展のための教育(ESD)」が提起され、自然・人間・社会のあり方までを問う教育と教育制度のあり方が重要課題として認識されています。 また、OECDのPISA調査との関連性から、グローバルな視点を取り入れる必要性も示唆されています。
4. 既存研究の限界と社会制度論的アプローチの提唱
このセクションでは、教育法学、行政学、経営学といった既存のアプローチによる教育制度研究の限界が指摘されています。例えば、教育法学では『教育人権保証の法制度』という体系的な構想はあるものの、教育制度そのものを正面から扱っている研究は少ないとされます。代表的なテキストとして平原春好編『概説 教育行政学』や横井敏郎編『教育行政学』が挙げられていますが、これらの書籍でも「教育制度」そのものを主題とした章や定義は存在しないことが指摘されています。そこで、本稿では、教育学的な視点に加え、より広い「社会制度論」的視点を重視することで、教育実践の立場に立った教育制度理解を提示しようとしています。特に、黒崎勲と井上の著書が、この社会制度論的アプローチの具体例として挙げられ、詳細な分析が後のセクションで行われると予告されています。
II.法制度的アプローチ 経営学的アプローチ 教育行政学的アプローチの限界と社会制度論的アプローチの必要性
既存の教育制度研究(法制度的、経営学的、教育行政学的アプローチ)は、教育制度を全体像として捉えることに限界があると指摘している。西本肇『学校という制度』は、制度学校批判と関係性の回復という視点から注目される。本稿は、これらの限界を克服するために、より広い社会制度論的視点を導入し、特に教育実践の立場からの教育制度理解を提示することを目指している。重要な論者として、黒崎勲と井上(次号で詳述)の研究が取り上げられている。
1. 法制度的 経営学的 教育行政学的アプローチの限界
このセクションでは、従来の教育制度研究における法制度的、経営学的、教育行政学的アプローチの限界が論じられています。まず、教育法学の視点からは、川口・中山編著のような「教育人権保証の法制度」を体系的に扱う試みは存在するものの、教育制度全体を真正面から論じているものは少ないと指摘されています。行政学や経営学の視点からの検討もなされているものの(浜田編著など)、これらも教育制度全体を包括的に扱うには不十分であるとされています。さらに、代表的な教育行政学のテキストである平原春好編『概説 教育行政学』や横井敏郎編『教育行政学』を例に挙げ、これらの書籍でも教育改革の動向や教育行政組織、教育行政の諸問題(保育、福祉、司法を含む)は論じられていても、「教育制度」そのものを議論している章や定義が存在しないことが指摘されています。これらの既存のアプローチは、教育制度の全体像を捉える上で限界があるという結論に至ります。
2. 社会制度論的アプローチの必要性と先行研究
前述の法制度的、経営学的、教育行政学的アプローチの限界を踏まえ、本稿ではより広い「社会制度論」的アプローチの必要性が強調されています。学校制度は現代社会に広く浸透しており、多様な角度からの検討が必要であるものの、学校を社会制度として正面から位置づけ、制度論的視点から検討した研究は少ないのが現状です。西本肇『学校という制度』が、教育学以外の領域を含めて制度論的に学校制度を検討した貴重な先行研究として紹介されています。西本は学校制度の見直しに関する議論を整理し、「制度学校と教育批判の方法」、「家庭−学校−国家の関係構造の変化」、「制度から関係へ」といったテーマを論じています。特に、制度批判の方法論として「世代間の時間共同性」「他者経験と共同性」「適応と忌避」といった概念を提示し、教育制度変革の可能性として「関係のリアリティの回復」を強調しています。本稿では、こうした先行研究を踏まえつつ、特に教育実践の立場に立った教育制度理解を提示することが目指されています。黒崎と井上の著書が、このアプローチの具体例として取り上げられ、詳細な分析が続くことが予告されています。
III.地域的視点と持続可能な教育制度
教育制度は地域社会と密接に関連しており、地域格差や過疎化、限界集落問題といった地域課題と深く関わっている。そのため、地方創生政策との関連性も考慮しなければならない。**「地域を捨てる学力」ではなく、「地域を育てる学力」**を育成する教育のあり方が問われている。持続可能な教育制度は、持続可能で包容的な地域づくり教育と不可分である。オープンシステムモデルを用いて教育システム全体を捉える方法も提案されている。
1. 地域社会と教育制度の関連性 地域格差と地方創生
このセクションでは、教育制度と地域社会との密接な関係が論じられています。資本主義経済における地域間格差の問題が指摘され、戦後の高度経済成長による過疎・過密問題や、1990年代以降のグローバリゼーションによる東京一極集中現象などが例として挙げられています。21世紀に入り、これらの問題はさらに深刻化し、「限界集落」問題や「地方消滅」予測などが現実のものとなり、「地方創生」が政府の重点政策となっています。しかし、この政策は「選択と集中」を基本としており、地域格差の拡大や地方消滅を招く可能性も懸念されています。東井義雄の指摘する「地域を捨てる学力」という批判を踏まえ、「地域を育てる学力」や「地域に根ざす教育」の重要性が強調され、東日本大震災の被災地における課題や、少子高齢化と学校統廃合が進む日本の現状が示されています。持続可能な教育制度は、持続可能で包容的な地域づくり教育と不可分であるという結論に至ります。
2. 教育システム全体の捉え方 オープンシステムモデル
教育システム全体を捉える方法として、「オープンシステムモデル」が提案されています。このモデルは、教育組織をオープンシステムと捉え、組織と組織外の環境との相互作用(インプットとアウトプット)をフィードバック関係において分析しようとするものです。教育システムを全体として統合されたダイナミックな実体として捉え、オルセンの言葉を引用して「極めて一般的で、内容にとらわれない概念的な枠組み」であると説明されています。この枠組みは、多様な分析方法を取り入れることを可能にします。既存の法体系を前提としたり、教育法体系の枠内だけで議論を進める教育制度論が多い中で、このオープンシステムモデルは、生涯学習時代やグローバリゼーション時代において不可欠な視点であり、国際的な関連性を無視することなく教育制度のあり方を考える必要があることを改めて強調しています。
IV.教育社会学の視点と教育制度論
教育社会学の観点からも、教育制度は歴史的・社会的存在として分析されている。有本章ほか編『教育社会学概論』のように、教育制度を体系的に扱う試みもあるが、貧困や社会的排除といった問題への対応が、教育制度の真の意義を問う試金石となっている。教育の危機に対処するためには、批判的な教育理論と実践が必要とされている。
1. 教育社会学における教育制度の扱われ方
このセクションでは、教育社会学のテキストにおける教育制度の扱われ方が論じられています。エミール・デュルケーム以来、教育社会学は「社会的現実としての教育」を科学的に分析する学問として発展してきました。そのため、教育社会学のテキストの中には、歴史的・社会的存在としての教育制度に着目したものも存在します。しかし、多くのテキストでは、教育制度全体を体系的に扱っているとは言い難い現状が指摘されます。例として、有本章ほか編『教育社会学概論』が挙げられています。このテキストでは、第1部で「変動する社会と教育」を扱い、第2部で「学校と教育の社会学」を扱い、「教育制度」から始まり、学校、カリキュラム、教室、児童・生徒、教師、高等教育、生涯学習といった項目を各章で論じています。しかし、このテキストにおいても、教育社会学の広範な対象の中から、学校と社会構造/社会体制の領域に比重が置かれているだけで、教育制度全体を包括的に扱っているとは言えないとされています。つまり、教育社会学の立場からも、教育制度そのものを真正面から扱った研究は少ないという問題提起がなされています。
2. 教育的危機と教育制度のあり方 貧困 社会的排除問題への対応
現在の日本政府の政策は「新自由主義プラス新保守主義=大国主義」の理念に基づいており、その下で進められている教育改革は、子どもの格差・貧困・社会的排除問題をさらに深刻化させる可能性があると指摘されています。これらの問題は世界的な「教育的危機」をもたらす要因であり、これに対する批判的な教育理論と実践が必要だとされています。貧困や社会的排除問題への対応こそが、特に公共性を持つ学校制度の存在意義を問う試金石であり、学校が地域や行政と連携して問題解決に取り組む実践から学ぶことが重要だとされています。2008年改定の教育基本法で強調された「生涯学習の理念」と「学校・家庭・地域住民等の相互の連携協力」を踏まえ、教育実践の発展という視点から教育制度を問い直し、連携協力によって進められる教育制度改革に着目し、地方と全国の教育制度のあり方が検討されるべきであると主張されています。現場からの学びが、教育制度改革を進める上で不可欠であることが強調されています。
V.教育実践と教育制度改革 現場からの学び
2008年改定の教育基本法で強調された生涯学習の理念と学校・家庭・地域住民の連携協力に基づき、教育実践の視点から教育制度を問い直す必要性が指摘されている。教育制度改革は、現場の実践を踏まえたものでなければならず、単なる制度いじりは混乱を招く。子どもの最善の利益を第一に考える必要がある。各市町村・各学校の具体的な取り組みを学ぶことが重要である。
1. 教育基本法改正と生涯学習の理念 連携協力の重要性
このセクションでは、21世紀における教育制度のあり方を、教育実践の視点から問い直すことが論じられています。2008年に大幅改定された教育基本法における「生涯学習の理念」(第3条)と「学校・家庭・地域住民等の相互の連携協力」(第13条)の重要性が強調されています。これらの理念に基づき、教育実践の発展という視点から教育制度を問い直し、学校、家庭、地域住民間の連携協力によって進められる教育制度改革に注目する必要があると主張されています。 既に各市町村や学校レベルで様々な取り組みが行われていることを踏まえ、教育制度改革は現場からの学びと学び合いによって推進されるべきだと結論付けられています。単なる制度いじり、例えば選挙対策や予算争奪のための「新制度」は、現場を混乱させるだけであるという批判も含まれています。
2. 教育制度改革のあり方 子どもの最善の利益を第一に
教育改革時代において、教育制度研究の意義は大きいとされつつも、その改革の方向性は教育現場の実践を踏まえたものでなければならないと強調されています。より良い教育実践を推進するために教育制度改革を行うべきであり、現場の実践とは無関係な制度変更はかえって現場の混乱を招くと批判的に指摘されています。国連の「子どもの権利条約」(1989年、日本批准1994年)の理念に基づき、「子どもの最大限の利益」を中心においた制度改革と制度運用が必要であると結論付けられています。つまり、教育制度改革は、現場のニーズと子どもの権利を最優先に考慮して行われなければならないという主張が展開されています。現場の実態を無視した、政治的あるいは利害関係に基づく改革への警鐘が鳴らされていると言えるでしょう。
VI.戦後教育学批判と教育行政 制度論 黒崎勲の教育行政論
戦後教育学に対する批判として、他の学問分野との交流不足、実証的現状分析の不足、時代に対応した理論形成の遅れなどが挙げられる。黒崎勲は、勝田守一の思想を踏まえつつ、宮原誠一の「形成と教育の区別」論、マルクスの労働過程論、ボールズ/ギンタスの対応理論などを用いて、独自の教育行政=制度論を展開している。しかし、その理論体系には、能力主義、ロールズの正義論、商品・貨幣論との関連など、いくつかの問題点も指摘されている。
1. 戦後教育学批判と教育的価値
このセクションは、戦後教育学に対する批判から始まります。教育固有の価値(教育的価値)を基盤とする従来の教育政策や教育制度への批判枠組みそのものが批判の対象となっています。佐藤広美による批判の3点を整理すると、①他の学問分野との交流を阻害する、②実証的現状分析をおろそかにする、③今日の状況に見合う理論形成ができない、という点です。これらの批判は、教育的価値の陳腐化・硬直化が、教育の社会構造的認識を阻害し(教育の非政治化)、教育病理を生み出す要因となっているという結論につながります。しかし、教育固有の価値の重要性を主張する勝田守一の思想に立ち返るべきだという反論もあり、黒崎勲もまた、勝田の思想を起点に教育行政=制度論を展開しようとしています。勝田守一の『能力と発達と学習』と『政治と文化と教育』という二つの系譜の論理の差異と対立・矛盾をどのように克服するかが、今後の課題として提示されています。
2. 黒崎勲の教育行政 制度論 教育学の自律性と目的意識
黒崎勲は、宮原誠一の「形成と教育の区別」論を踏まえ、技術的合理主義的な経営学的研究や法学的・人権論的研究を退け、「教育学としての教育行政=制度論」を展開しようとしています。黒崎によれば、教育理論の特性は「目的意識的な人間の営みとしての教育の問題に接近すること」であり、教育制度と実践の固有性に関わる理論的究明こそが教育学の自律性の試みだと主張しています。宗像誠也の教育行政学を継承しつつも、勝田守一の構想における『政治と文化と教育』の方向に教育行政学=制度論を位置づけています。堀尾輝久の「発達教育学」は勝田の二つの系譜のうち前者の一面化に過ぎず、戦後教育学批判者が堀尾理論を戦後教育学の到達点として批判するのは誤りだと指摘しています。黒崎は、戦後教育学が「教育の固有の価値」に固執しすぎた結果、「教育の社会構造的認識を失った」と批判し、その点で戦後教育批判者と共通の認識を持つと説明しています。
3. 教育行政と教育管理 持田栄一と 教育としての教育行政
「反(アンチ)教育行政学」への対抗軸として、持田栄一が教育行政=教育制度研究に最も自覚的だった研究者として挙げられています。持田はマルクスの「労働過程論」と芝田進午の「労働の技術的過程と組織的過程」の区別を基に、「教授=生活過程と管理=経営過程」という概念を提唱し、教育労働における両者の相互関係を分析しています。宗像誠也の「教育としての教育行政」論が高く評価されており、「教育行政の活動を教育の営みそのものとして理解し、教育行政改革を通して教育改革に積極的に参加しようとするもの」と説明されています。この視点から、「教育全体を動かす人々の教育意思の組織化の方法とその教育意思の具体的表現である教育計画の究明」が、教育行政=制度論の課題として提示されています。しかし、近代以降の学校制度は非制度的教育や社会教育を前提としており、大人が変わらなければ子どもは変わらないという関係性の重要性が指摘されています。
VII.教育学4領域と教育制度論 実践論の重要性
教育制度論は、教育原論・教育本質論・教育実践論・教育計画論という教育学の4領域と関連付ける必要がある。黒崎の教育行政論は、実践論との関連が不足している点が指摘されている。**「私事の組織化」**論や教育労働論なども含めて、実践に基づいた教育制度論の構築が必要である。
1. 教育学の4領域と教育制度論の位置づけ
このセクションでは、教育制度論を教育学全体の中でどのように位置づけるべきか、その固有の意義、展開方向、可能性と限界が論じられています。教育学を教育原論、教育本質論、教育実践論、教育計画論の4領域に大別し、それらの論理レベルを区別と関連において捉える必要があると指摘しています。黒崎勲の教育行政=教育制度論を批判的に検討し、黒崎が「教育実践と教育制度」を問うならば実践論に即した検討をするべきだったこと、「私事の組織化」論を批判するならばその組織化過程の論理を問うべきだったと指摘しています。佐貫浩の指摘を引用し、「『私事の組織化』についての本格的な、ある意味で政治学的、社会学的、さらには教育運動的な側面こそが、教育行政学の課題」であると述べています。教育行政学は教育の領域に即して展開されなければならないという主張がなされています。勝田守一の「2つの系列」が媒介され、結び付けられなかったことが、黒崎の理論的枠組みにおける問題点の一つとして挙げられています。
2. 教育実践論に基づく教育制度論の構築 実践からのアプローチ
教育学における実践論の重要性が強調され、教育制度論も実践論に即した検討を行うべきだと主張されています。「私事の組織化」論への批判を例に、その組織化過程の論理を問う必要性が示されています。黒崎に対する佐貫浩の批判を引用し、「『私事の組織化』についての本格的な、ある意味で政治学的、社会学的、さらには教育運動的な側面こそが、教育行政学の課題」であると指摘されています。教育行政学は教育の領域に即して展開されなければならないという前提が示され、教育価値についての合意と実現のプロセスをシステム化・制度化するという研究(堀尾のいう「私事の組織化」過程研究)を実践論的な課題として進めることが提唱されています。その先に教育労働論、教育改革論、教育計画論といった領域への発展が期待されていることが示唆されています。つまり、教育制度論は、教育実践や社会状況を深く理解した上で、実践論に基づいたアプローチで構築されるべきであるという結論が導かれています。
VIII.今後の課題 教育の正統性と社会科学的アプローチ
教育制度論の今後の課題として、教育の正統性の問題、市場経済と資本主義の区別、市場力と非市場力の相互作用、公教育費の問題などが挙げられる。マルクスの『資本論』への深い理解も必要となる。脱工業化社会、知識基盤社会における教育労働のあり方も重要な課題である。
1. 教育の正統性と教育制度論の課題 黒崎の未完成な議論
このセクションは、教育制度論の今後の課題を論じています。黒崎勲が重視した学校選択制度に関する議論の背景には、「教育の正統性」の問題があると指摘し、市場経済と資本主義の区別、規制された市場の概念の精査、市場力と非市場力の相互作用の綿密な考察などが、今後の教育行政=教育制度論の課題として挙げられています。しかし、黒崎自身の議論にも問題点があると指摘されています。具体的には、黒崎が依拠していたロールズの正義論をめぐる批判、ロールズの正義論を教育制度論に適用する際の適否、黒崎の能力論が「個人主義的能力論」を前提としていた点などが問題視されています。ロールズを超えて世代間・世代内の公正を実現しようとする試み(斎藤純一など)や、教育の分配における公正(宮寺晃夫)の議論も紹介されていますが、これらも教育制度そのものの理解には至らないとされています。黒崎の議論は、新自由主義的教育政策に飲み込まれる傾向があったことも指摘されています。
2. 社会科学的アプローチと教育学の独自性 マルクス経済学と教育制度
教育学は実践の学でありながら、社会科学の一環でもあるため、社会科学の方法論を踏まえつつ教育学独自の課題を考える必要があると強調されています。黒崎の議論においては、マルクス『資本論』への理解が不十分であった点が指摘されています。特に、「管理労働の二重性」論を展開するには、物神性論や資本制蓄積論、原始的蓄積論などの理解が不可欠であり、黒崎の議論はそれらの理解を欠いていたと批判されています。マルクスの『資本論』第1巻全体の理解、特に「資本の生産過程」の総体的な理解が、ボールズ/ギンタスの「対応理論」を総合的に検討する上で必要だとされています。グローバリゼーションによって商品・貨幣的世界と資本・賃労働的世界が浸透した現代社会において、教育の課題や教育制度のあり方を考えるためには、こうした社会科学的な視点を取り入れることが不可欠であると結論づけられています。また、黒崎が公教育費の諸形態を論じ、「国民の教育権論者」を批判している点も触れられています。
