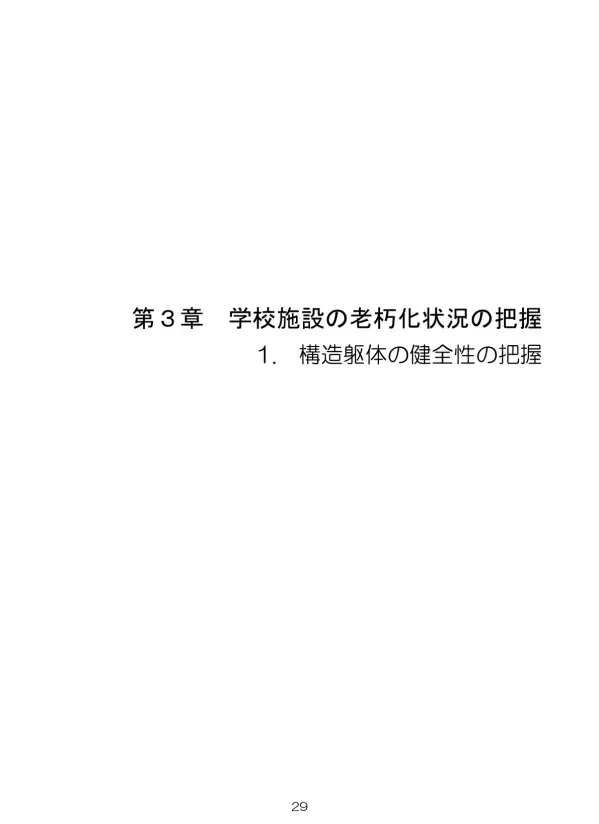
学校施設老朽化診断:耐用年数予測と対策
文書情報
| 学校 | 秋田大学 |
| 専攻 | 建築学 |
| 場所 | 秋田 |
| 文書タイプ | 報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.11 MB |
概要
I.老朽化状況調査 躯体健全性 と 劣化状況 の総合評価
本調査は、学校施設の老朽化状況を把握し、長寿命化計画策定のための基礎データを得ることを目的としています。調査は、①躯体健全性調査(耐震診断データ活用、コア抜き・はつり調査によるコンクリート圧縮強度、中性化深さ、鉄筋腐食状況の評価)と、②躯体以外の劣化状況調査(現地調査による劣化度評価、劣化問診票活用)の2段階で行われます。残存耐用年数の推定を行い、劣化の優先順位付け、改修・建替えの判断に役立てます。
1. 調査目的と概要
本調査は、学校施設の老朽化状況を詳細に把握し、長寿命化計画の策定に資することを目的としています。老朽化状況の評価は、①躯体の健全性調査と②躯体以外の劣化状況調査の2つに大別されます。躯体健全性調査では、耐震診断データやコア抜き・はつり調査による物理的調査を実施し、コンクリートの圧縮強度、中性化の進行状況、鉄筋の腐食状況などを分析することで、建物の残存耐用年数を評価します。これにより、具体的な長寿命化計画へと繋げることが期待されます。一方、躯体以外の劣化状況調査では、現地調査を通して屋根、外壁、設備機器等の劣化状況を詳細に把握し、劣化度の算定・評価、劣化優先順位付けを行います。これらの調査結果を総合的に分析することで、各施設の現状を正確に把握し、適切な維持管理、改修、または建替えの必要性を判断するための重要な根拠となります。施設保全カルテの作成を通じて、劣化状況と維持管理状況、整備レベルとの関連性を多面的に分析し、課題を抽出・整理することも重要なプロセスです。
2. 躯体健全性調査の方法と評価基準
躯体健全性調査は、建物の長期間使用可能性を判断するための重要なステップです。施工状況、使用状況、立地環境などによって建物の耐用年数は大きく異なります。そのため、長寿命化計画を策定するには、躯体の健全性を正確に評価することが不可欠です。鉄筋コンクリート構造物の劣化は、コンクリート自体の劣化(変質・組織崩壊・ひび割れなど)と鉄筋の腐食に大別され、これらの劣化現象は相互に悪影響を与え合う複雑な関係にあります。調査では、耐震診断時の既存データを利用した簡易診断を行い、必要に応じてコア抜き・はつり調査を行い、コンクリートの圧縮強度、中性化深さ、鉄筋のかぶり厚さ、鉄筋の腐食状況を測定します。これらのデータに基づき、残存耐用年数を評価し、長寿命化の可否を判断します。具体的には、圧縮強度が13.5N/mm²未満、中性化深さが30mm以上に達している場合、または中性化の進行速度が理論値より速い場合は、長寿命化に適さないと判断されます。 鉄筋腐食状況についても、腐食状況の係数が0.5以下の場合は長寿命化に適さないと判断する基準が設けられています。
3. 躯体健全性調査結果と今後の対応
耐震診断報告書のある小中学校60棟を対象に実施された簡易診断の結果、80年以上長寿命化可能な建物は49棟、60~80年は2棟、60年未満は9棟と評価されました。 残存耐用年数に基づき、40年以上残っている建物は長寿命化改修、20年以上40年未満は中規模改修、長寿命化が困難な建物は建替えを検討することになります。今後、築35年程度の建物については、長寿命化改修に先立ち、構造躯体の健全性調査を実施し、長寿命化の可否と工事内容を検討する必要があるとされています。この調査では、鉄筋腐食度調査や鉄筋かぶり厚さの調査も実施し、より詳細なデータに基づいた判断を行うことが求められます。 これらの調査結果と、躯体以外の劣化状況調査結果を統合的に分析することで、学校施設の長寿命化に向けた具体的な計画が立案されます。
4. 躯体以外の劣化状況調査の方法と評価
躯体以外の劣化状況調査は、専門家による現地調査に基づいて行われます。劣化問診票による調査結果を活用し、効率的に調査対象施設を選定することで、最小限のコストで最大の効果を上げます。劣化問診票は、施設管理者も回答可能な簡易な設問で構成されており、コストを抑えつつ、施設の劣化状況をある程度のレベルで把握することを可能にしています。毎年継続実施することで、劣化状況の進み具合も把握できます。専門家による現地調査では、10の部位に調査項目を設定し、目視を中心に仕様と劣化状況を調査します。劣化状況はA~Dの4段階で評価され、現地写真記録なども合わせて取りまとめられます。評価基準は、C評価(随所、広範囲に劣化。安全上、機能上低下の兆し)とD評価(劣化が著しく、安全上、機能上早急に対応の必要あり)で構成されており、特にD評価の建物には早急な対応が必要となります。調査対象には全小中学校、2学校給食センターが含まれ、築後経過年数、大規模改造の実施の有無、平成25年の問診表の劣化度、空調設備、高置水槽の有無なども考慮して類型化された学校が選定されています。
II.躯体健全性調査 コンクリート構造物の劣化診断
躯体健全性調査では、コンクリート構造物の劣化状況を詳細に評価します。コンクリート圧縮強度が13.5N/mm²未満、中性化深さが30mm以上、または中性化の進行速度が理論値を上回る場合は、長寿命化に適さないと判断します。鉄筋腐食状況も重要な評価項目です。調査対象は、耐震診断済みの小中学校60棟で、80年以上の長寿命化が可能な棟は49棟、60~80年は2棟、60年未満は9棟と評価されました。
1. コンクリート構造物の劣化メカニズム
鉄筋コンクリート構造物の劣化は、コンクリート自体の劣化と鉄筋の腐食の2つに大別されます。コンクリートの劣化には、変質、組織崩壊、ひび割れ、欠けなどが含まれ、鉄筋の腐食は、コンクリートの中性化や塩分の侵入などが原因となります。これらの劣化現象は独立して発生するだけでなく、相互に作用し合い、悪化を促進する傾向があります。例えば、鉄筋の腐食はコンクリートのひび割れや剥落を招き、逆にコンクリートの劣化は鉄筋の腐食を加速させるという悪循環が生じます。この複雑な劣化メカニズムを理解した上で、適切な診断と対策を行うことが重要です。文部科学省「学校施設の長寿命化改修の手引」では、建築物の使用年数の限界は、構造躯体の物理的な劣化、または社会的・技術的な変化による機能・性能の相対的な価値の低下によって規定されるとされています。長寿命化を目指す場合、構造躯体の健全性を確認することが不可欠です。
2. 躯体健全性調査の手法と評価基準
躯体健全性調査では、まず耐震診断時の既存データを用いた簡易診断を実施します。必要に応じて、コア抜きやはつり調査を行い、より詳細なデータを取得します。これらの調査により、コンクリートの圧縮強度、中性化の進行状況、鉄筋の腐食状況、かぶり厚さを測定します。これらのデータに基づき、建物の残存耐用年数を評価します。評価基準としては、コンクリートの圧縮強度が13.5N/mm²未満の場合は長寿命化に適さないと判断します。また、中性化深さが30mmに達している場合も同様です。さらに、中性化の進行速度についても、理論値よりも進行が早いと判断された場合、長寿命化に適さないと判断します。鉄筋腐食状況についても、腐食状況の係数が0.5以下であれば、長寿命化に適さないと判断されます。これらの厳格な基準を用いることで、建物の構造的な健全性を正確に評価し、安全で効果的な長寿命化計画の策定に貢献します。
3. 躯体健全性調査結果 耐震診断データからの評価
耐震診断報告書のある小中学校60棟を対象に、簡易診断を実施しました。その結果、80年以上長寿命化が可能な建物は49棟、耐用年数が60~80年と判定された建物は2棟、60年未満と判定された建物は9棟でした。この結果から、多くの建物は80年以上の長寿命化が期待できる一方、一部の建物は60年未満と評価され、早急な対応が必要であることが示唆されました。具体的な数値データは、各建物の築年数、コンクリートの中性化深さ、コンクリートの圧縮強度などを用いて評価されています。この評価結果に基づき、それぞれの建物の今後の対応(長寿命化改修、中規模改修、建替え)が決定されます。残存耐用年数が40年以上の建物は長寿命化改修を実施し、さらに40年間の使用を目指します。20年以上40年未満の建物は中規模改修を行い、約20年間の使用を計画します。長寿命化が困難と判断された建物については、建替えが検討されます。この調査結果によって、学校施設の維持管理戦略が明確になります。
III.躯体以外の劣化状況調査 屋根 外壁等の劣化状況把握
躯体以外の劣化状況調査では、屋根、外壁、設備機器等の劣化状況を現地調査により評価します。劣化問診票による事前調査と専門家による目視調査を組み合わせ、劣化度をA~Dの4段階で評価します。特に、築後35~45年の建物でD評価(早急な対応が必要)が多く、築後20年を経過した建物では年代を問わず劣化が進行していることが判明しました。屋根や外壁は築30年を経過するとD評価、20年を経過するとC評価が増加する傾向が見られました。調査対象は全小中学校と2学校給食センターです。
1. 調査方法 劣化問診票と専門家による現地調査
躯体以外の劣化状況調査は、主に現地調査によって行われます。まず、施設管理者に対して劣化の把握に直結する事象・部位について、専門知識がなくても回答可能な劣化問診票を用いた調査を実施します。この問診票による調査は、コストを抑えつつ、施設の劣化状況をある程度把握することを目的としており、毎年継続的に実施することで劣化の進行状況をモニタリングできます。問診票調査に加え、建築と設備の専門家(一級建築士等)が現地調査を行い、建物の性能・機能維持に必要な部位・設備機器について、仕様、設置年、劣化状況を詳細に把握します。調査対象は全小中学校と2つの学校給食センターで、躯体、屋根・屋上、外壁の調査が実施されています。さらに、築後経過年数から代表的な5校(築山小、大住小、飯島南小、泉中、桜中)を選定し、建築調査(内部を含む全調査)が行われています。設備の現地調査対象は、築後経過年数、大規模改造の実施の有無、平成25年の問診票の劣化度、空調設備の種類、高置水槽の有無などを基準に類型化された22校(14小、8中)と2学校給食センターです。これらの多角的な調査により、施設全体の劣化状況を総合的に把握することを目指しています。
2. 劣化状況の評価基準と結果
現地調査では、目視により10の部位をA~Dの4段階で評価します。設備の劣化度は、目視だけでは判断できないため、耐用年数からの超過年数も考慮して評価されます。評価基準は、AからDまで、劣化の程度が深刻になるに従ってランク付けされています。特にC評価は「随所、広範囲に劣化。安全上、機能上低下の兆し」、D評価は「劣化が著しく、安全上、機能上早急に対応の必要あり」と定義されており、D評価を受けた箇所は迅速な対応が求められます。調査結果では、旭南小、秋田南中、明徳小などがD評価を受けました。また、築山小、八橋小、泉小などにはC評価が付与されています。C・D評価の学校は、泉小を除いて児童生徒数の減少が顕著であるという傾向も示されています。地域別の傾向としては、中心部の学校でC・D評価が多い傾向が見られ、郊外では比較的状態が良い学校が多いものの、一部でC・D評価の学校も見られました。築30年を経過していない校舎でもC評価が4棟あるなど、築年数だけでは劣化状況を判断できないケースもあることが示唆されています。これらの結果から、学校施設の老朽化が深刻な問題であることが改めて浮き彫りになっています。
3. 部位別劣化状況と今後の対応
部位別の劣化状況については、屋上・屋根と外壁が特に重要視されています。定期的な部位改修が行われていますが、それでもD評価(早急な対応が必要)の部位が多く見られます。校舎屋上では、C評価が24.8%(一部調査では7.5%)を占め、防水シートの劣化による破れ、膨れ、しわ、雨漏りが問題となっています。A、B評価の学校でも、経年劣化による保護塗装のかすれや部分的な補修跡が見られます。校舎外壁では、C、D評価が60.5%(一部調査では11.5%、17%)を占め、コンクリートのはく落、爆裂、開口部周囲の亀裂、雨漏りが多く見られます。大規模改修済みの学校でも、外壁改修が未実施の部分にC、D評価が付くなど、全体的な改修が不十分なケースも存在します。体育館の屋上・外壁でも、金属屋根の腐食・錆、コンクリートのはく落・爆裂、雨漏りが問題となっています。特に築後40年を経過した施設では、受変電設備、給排水設備、空調設備のタンクなどでD評価が多い傾向があり、プールのろ過設備は22校中13校で耐用年数を1.4倍超過しています。これらの結果から、築30年前を目安に屋上、外壁の改修を行う必要があることが示唆されています。全体としては、築後35~45年の建物に早急な対応が必要なD評価が多く、築後20年を経過した建物は年代を問わず劣化が進んでいる状況です。
IV.劣化状況の総合評価と今後の対応
調査結果に基づき、残存耐用年数に応じて、長寿命化改修、中規模改修、建替えを検討します。今後、築35年程度の建物については、躯体健全性調査を実施し、長寿命化の可否と工事内容を検討する必要があります。劣化状況の継続的な把握とデータの一元管理が重要です。特に、コンクリート劣化(中性化、鉄筋腐食)への対策が不可欠です。
1. 劣化状況の総合評価 残存耐用年数と改修計画
本調査では、躯体健全性調査と躯体以外の劣化状況調査の結果を総合的に評価することで、学校施設全体の劣化状況を把握し、今後の維持管理計画を策定します。躯体については、コンクリートの圧縮強度、中性化深さ、鉄筋の腐食状況などを基に、残存耐用年数を算出し、長寿命化の可否を判断します。残存耐用年数が40年以上の建物は長寿命化改修、20年以上40年未満の建物は中規模改修、それ以下の建物は建替えを検討します。躯体以外の部分については、屋根、外壁、設備機器などの劣化状況をA~Dの4段階で評価し、特にD評価(劣化が著しく、早急な対応が必要)を受けた箇所は優先的に改修を行う必要があります。これらの評価結果に基づき、個々の施設の劣化状況と優先順位を明確化し、効率的な維持管理、改修計画を立案します。調査対象は全小中学校と2つの学校給食センターで、築後経過年数や設備状況なども考慮して類型化された学校を選定しています。 施設保全カルテの作成を通じて、劣化状況と維持管理状況、整備レベルとの関連性を多面的に分析することで、より効果的な維持管理体制の構築を目指します。
2. 部位別劣化状況と築年数との関係
調査結果を部位別に分析したところ、屋根と外壁の劣化が顕著であることが分かりました。特に、築30年を超えるとD評価、20年を超えるとC評価が増加する傾向が見られました。これは、屋根や外壁が建物の劣化において最も重要な部位であり、経年劣化の影響を受けやすいことを示しています。具体的には、校舎屋上では防水シートの劣化による破れ、膨れ、しわ、雨漏りが問題視され、校舎外壁ではコンクリートのはく落、爆裂、開口部周囲の亀裂、雨漏りが多く見られました。体育館の屋上や外壁でも、金属屋根の腐食・錆、コンクリートのはく落・爆裂などが確認され、雨漏りの発生も懸念されます。築後40年を経過した施設では、受変電設備、給排水設備、空調のタンクなどでD評価が多い傾向があり、プールのろ過設備は22校中13校が耐用年数を1.4倍超過しています。これらの部位別劣化状況を踏まえ、築30年前を目途に屋上、外壁の改修を行うことが推奨されます。定期的な改修を実施している部位でも、D評価の箇所が多く見られることから、更なる維持管理体制の強化が求められます。
3. 今後の対応 継続的なモニタリングとデータの一元管理
今後の対応として、築35年程度の建物については、長寿命化改修に先立ち、構造躯体の健全性調査を実施することが必要です。この調査では、コンクリートの圧縮強度、中性化深さ、鉄筋の腐食状況に加え、鉄筋腐食度調査や鉄筋かぶり厚さの調査も行うことで、より詳細なデータに基づいた判断を行います。 また、劣化状況の継続的な把握とデータの一元管理が重要です。劣化問診票による調査を毎年継続的に実施することで、劣化状況の進み具合を把握し、的確な対策を講じることが可能になります。施設保全カルテの作成を通じて、劣化事象(部位)ごとに保全優先度や個別修繕コストを検討することで、より効率的で効果的な維持管理計画を策定することができます。調査結果から、特に築後35~45年の建物に早急な対応が必要なD評価が多く見られ、築後20年を経過した建物は年代を問わず劣化している状況であるため、今後これらの早急な対策が求められています。 これらの対策によって、学校施設の安全性を確保し、長寿命化を目指した効果的な維持管理を実現することが期待されます。
