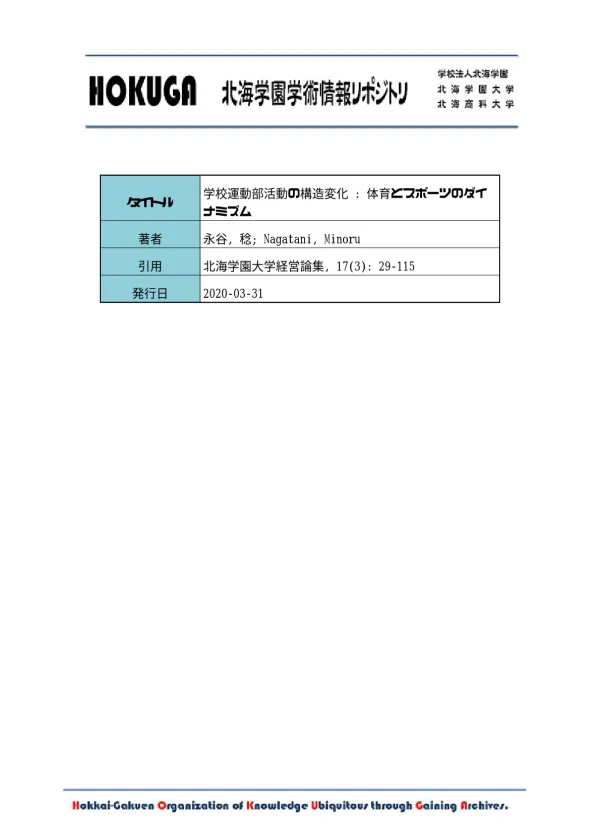
学校部活動の変遷:歴史と課題
文書情報
| 著者 | 永谷 稔 |
| 専攻 | 体育学、スポーツ史 |
| 文書タイプ | 論文、書籍 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 7.13 MB |
概要
I.明治時代の学校体育と部活動の黎明期 Meiji Era Dawn of School Athletics and Club Activities
明治維新後、西洋スポーツの導入により、一部エリート学生を中心に野球などが普及しました。Horace Wilsonなど外国人教師の貢献が大きく、初期の部活動はエリート層の嗜みでした。一方、伝統的な武術は衰退した後、近代化の過程で段級制度を取り入れ復活を図り、家元制度との連続性も指摘されています(小笠原他, 1967)。森有礼の教育改革(知育・徳育・体育)や福沢諭吉の『学問のすゝめ』における実学重視の思想が、学校体育の発展に影響を与えました。明治19年の学制改革により、学校令が公布され、学校体育の制度的基盤が整備されました。この時代は、スポーツが国民道徳や倫理教育と結びつき、近代化された西洋文化と伝統文化の融合を試みました。キーワード:明治維新、西洋スポーツ導入、学校体育、森有礼、福沢諭吉、教育改革、部活動黎明期。
1. 西洋スポーツの導入とエリート層への浸透
明治時代初期、アメリカ出身のホーレス・ウィルソンが東京大学で英語教師として勤務し、学生に野球を教えたことが、近代スポーツが日本に伝播した初期の事例として挙げられています。この時点では、スポーツは一部のエリート学生のみに広まっていたことがわかります。明治維新後の近代化政策において、従来の武術や祭礼、神事などは一時衰退したものの、明治13年頃からは再び復活の兆しが見られました(中村,1993)。この近代化は、伝統的な価値観を踏まえたものであり、廃れかけた武術をスポーツ化することで近代社会に適合させ、段級制度を取り入れることでその存続を図ったと井上(2004)は指摘しています。これは、日本の伝統芸能における家元制度と連続性があると小笠原他(1967)は述べています。しかし、同時に近代化・西洋化による目新しさへの興味や、競技会・運動会観戦といった娯楽要素も無視できません。
2. 森有礼と福沢諭吉の教育思想と学制改革の影響
森有礼は、ハーバード・スペンサーの教育論『知育・徳育・体育論』を早くから研究しており(長谷川,1995)、福沢諭吉の『学問のすゝめ』における独立自尊と実学の必要性、そして知育・徳育・体育の重要性の主張と相まって、日本の教育制度に大きな影響を与えました。森有礼は学制改革の中心人物として日本の教育制度の骨格を作り上げ、明治19年には改正教育令を廃止し、学校段階ごとに個別の学校令を公布しました。この制度は第一次世界大戦前まで続き、これらの学校令のほとんどは森有礼が起草したものと言われています(斉藤,2017)。これらの改革は、学校体育の制度的基盤を確立し、近代日本の教育に体育を不可欠なものとして位置づける上で重要な役割を果たしました。
3. 近代スポーツと資本主義 伝統文化の融合
当時の近代スポーツはエリート層のたしなみでしたが、学校教育や体育に接続することで、資本主義と伝統文化との親和性を高め、驚くべき普遍性と日本の独自のスポーツ文化を形成することに成功しました。国語の教科書に掲載された清水善造のウィンブルドンでの活躍は、スポーツマンシップの美談として紹介され、スポーツが道徳や倫理を語る上での一つの要素として位置づけられたことを示しています(上前,1986)。これは、スポーツが単なる競技を超えて、社会規範や価値観の形成に貢献する側面を有していたことを示唆しています。しかし、森有礼の教育改革は高等師範学校に力を入れた一方、軍隊式寄宿舎生活やナショナリズム、ミリタリズムの浸透など、意図に反する結果も招きました(長谷川,2002)。これにより、従来の尊敬されていた教師像が失われ、「師範タイプ」と批判される教員も現れました(加藤,1974)。大滝(1972)は、マニュアル化された軍隊式教育を「形ばかりで魂が入らない」と批判しました。
4. 学校運動会の設立と部活動の組織化
寄宿舎管理制度の改革、生徒への自由闊達な校風の醸成、そして余暇時間の運動奨励を目的として、「運動会」という組織が設立されました。当初は柔道部、撃剣銃槍部、弓枝部、器械体操部、相撲部、ローンテニス部、フットボール部、野球部など複数の部活動が存在し、一高精神の発露の場、校風の振起を担う集団主義的な側面が強調されました。明治39年の早慶戦における過激な応援行為と学習院への脅迫状は、対外試合が各学校の威信に関わるほど重要なものになっていたことを象徴する出来事であり、大正14年まで中断される事態にまで発展しました(山本,2017)。この時代背景には、抑圧からの解放を求める民主主義の高まりがありました。この運動会設立は、学校の部活動が組織化され、発展していく重要な転換期を示しています。
II.戦前期の部活動 発展と過熱化 Pre War Period Development and Overheating of Club Activities
戦前期には、部活動は国民の愛国心や国威高揚の手段として利用され、軍国主義的な傾向も強まりました。明治神宮競技大会開催における文部省と内務省の対立は、スポーツ行政の権限争いを示しています。また、部活動の過熱化により、学業への支障や多額の費用負担などが問題となりました。1920年代には、早慶戦の過激な応援が問題となり、部活動の社会的な影響力を示しています。キーワード:軍国主義、国威高揚、明治神宮競技大会、文部省、内務省、部活動過熱化、早慶戦。
1. 部活動の愛国主義的利用と軍国主義化
戦前期の部活動は、国民の愛国心や忠君愛国心を育成し、国威高揚を図るための手段として利用される傾向が強まりました。部活動は、国家への帰属意識の醸成、心身の鍛錬、軍事教練、皇国民としての基礎的修練といった教育的効果が強調され、戦時体制下では学校報国団の組織化にもつながりました。 これは、スポーツが国家主義的なイデオロギーと結びつき、国民の統制強化に利用されたことを示しています。昭和15年の東京オリンピック開催決定と、日中戦争の激化による返上も、この時代の政治状況と深く関わっています。このように、戦前の部活動は、教育的側面と国家主義的側面が複雑に絡み合い、その発展に影響を与えていたと考えられます。
2. 明治神宮競技大会と文部省 内務省の対立
明治神宮競技大会の開催を巡っては、文部省と内務省の対立が顕在化しました。内務省は、国民の健康増進を重要な役割として捉え、スポーツ行政も管轄していました。明治神宮の創建も内務省主導で行われ、明治神宮外苑競技場の完成を記念して、大正13年10月に明治神宮競技大会を開催することを決定しました。しかし、文部省は教育行政として体育・スポーツを管轄しており、内務省による競技大会開催を快く思っていませんでした。これは、単なる権限争いではなく、スポーツ振興に対する両省庁の理念や方法論の相違による対立であったと推測されます。内務省衛生局長の山田準太郎の発言(学生以外の選手選抜)も、この対立を象徴しています(後藤,2013)。全国体育デー開催において、文部省が帝国学校衛生会からの依頼に協力する立場を取ったことも、この対立構造を理解する上で重要な要素です(後藤,2013)。
3. 部活動の過熱化と問題点
戦前期の部活動は、過熱化の一途を辿り、様々な問題を引き起こしました。早慶戦における過激な応援行為や脅迫事件(山本,2017)は、部活動の社会的な影響力の大きさと、その過剰な熱狂が招いた負の側面を示しています。文部省は、対外試合の参加制限や、勝敗にとらわれない教育的な指導方針の強調など、様々な訓令や通達を出して対応を試みました(神谷,2015)。しかし、これらの対策は不十分であり、部活動の過熱化は改善されず、学業への支障や多額の費用負担、教育上望ましくない結果などが問題となっていました。甲子園球場の建設や全国規模の大会の開催は、部活動の普及と人気拡大に貢献した一方で、その過熱化を加速させる要因にもなったと考えられます。これらの状況は、戦前の部活動が抱えていた複雑な問題を示しています。
III.戦後の部活動 復興と民主化への模索 Post War Period Reconstruction and Search for Democratization
終戦後、GHQの占領下において、部活動は軍国主義的な要素の除去と民主主義的な方向への転換が求められました。文部省は迅速な方針転換を行い、中央集権的な組織から地方自治への移行を図りました。この過程で、学校体育の民主主義化、スポーツの教育化、そして国際化が重要な課題となりました。しかし、競技志向の高まりや過熱化は依然として問題となり、文部省は度々指導を通達で制限をかけました。キーワード:戦後教育改革、GHQ、民主主義、スポーツ教育、国際化、部活動改革、文部省通達。
1. 戦後日本の教育改革と部活動の民主化
終戦後、GHQの占領下において、日本の教育制度は大きな変革を迫られました。部活動も例外ではなく、軍国主義的な要素の排除と民主主義的な方向への転換が求められました。文部省は、GHQの教育政策に沿って、迅速な方針転換を行い、軍国主義的な教育と訓練の除去、体育目的と目標の再検討、身体訓練内容の再検討、評価方法の改訂、マニュアルの改訂、教員再教育、文部省と学生競技組織・大日本体育会との関係見直し、関連法令の改訂、身体訓練の形式主義からの解放など、多岐にわたる改革に取り組みました。これらの改革は、講義録『日本の体育』において11項目にわたって指摘されており、マックロイ博士らの教育使節団の勧告も踏まえて実施されました。この改革により、スポーツ関係諸団体・組織は政府の直接支配から民間主導へと移行し、日本の民主化と体育・スポーツの将来展望に大きな期待が寄せられました。戦後日本の体育・スポーツが直ちに再出発できた背景には、GHQの教育に対する考え方と文部省の方針転換が合致したことが挙げられます。
2. 部活動の競技化 高度化と文部省の対応
戦後の「復活期」においては、スポーツの教育化を大義名分として、部活動の競技化・高度化が進みました。中学生・高校生の対外試合に関する制限も、競技団体からの要請により緩和されていきました。完全にエリートスポーツ化した部活動においては、教員による指導が中心でしたが、地域からの指導要請など、学校外との連携も見られるようになりました(中澤,2014)。終戦直後GHQの統制下では、学校教育と体育・スポーツの連携は不可欠でした。しかし、競技化・高度化の進展は、新たな問題を引き起こしました。昭和23年の文部省体育局長通達では、勝敗にこだわることによる生徒の発達阻害、施設・用具の独占、非教育的な動機による教育自主性の損なわれ、多額の費用負担など、教育上望ましくない結果を招く可能性が指摘され、中学校・高等学校での対外試合の制限が強化されました。この通達と、昭和36年のオリンピック開催を考慮した文部省通達(中学生の対外試合参加基準緩和)は、部活動の競技性と教育性のバランスを巡る綱引きを示す事例です(八木,2007)。
IV.高度経済成長期以降の部活動 多様化と課題 Post High Economic Growth Period Diversification and Challenges
高度経済成長期には、レジャーの普及や生活水準の向上に伴い、部活動を取り巻く環境は大きく変化しました。レジャー憲章制定(1970年)もこの流れを反映しています。一方で、教員の長時間労働問題や部活動における事故責任問題が顕在化しました。**教員給与特別措置法(給特法)**制定(1970年)など、教員の勤務時間管理に関する法律が制定されたのもこの頃です。キーワード:高度経済成長、レジャー、教員長時間労働、部活動事故、給特法、部活動多様化。
1. 高度経済成長とレジャーの普及
昭和35年頃からの高度経済成長期は、生産拡大と所得増加をもたらし、人々の余暇時間が増えました。スキーやボウリングなどが新たな余暇活動として盛んになり、「レジャー」という概念が浸透し始めました。新幹線や高速道路網の整備も相まって、全国旅行を楽しむ人々が増加し、余暇活動はレジャーとして広く享受されるようになりました。昭和45年には、国際レクリエーション協会によって「レジャー憲章」が制定され、個人のレジャーに対する権利と自由が明確に定義されました。この経済的豊かさによる余暇時間の増加は、部活動を取り巻く環境にも変化をもたらしました。部活動以外の選択肢が増え、部活動の在り方についても多様な意見が出てくるようになりました。
2. 教員の労働時間問題と部活動の事故責任
高度経済成長期においては、部活動における教員の労働時間問題や事故責任問題が顕在化しました。教員の勤務時間外における部活動指導のあり方が曖昧であったため、教員の長時間労働が社会問題となりました。この問題に対処するため、昭和45年には教員給与特別措置法(給特法)が制定され、勤務時間外の指導に対する調整額の支給などが規定されました。また、熊本地方裁判所では、指導教員が同席していない練習中の柔道部員の事故について、「クラブ活動は正規の教育活動に含まれるため、勤務時間外であっても指導教員は生徒の安全に配慮する義務がある」との判決が下されました(昭和45年)。これらの出来事は、部活動の指導における教員の責任と負担、そして労働時間管理の必要性を浮き彫りにしました。
V.現代の部活動 混迷と改革の時代 Contemporary Club Activities Confusion and Reform
バブル経済崩壊後は、不況や少子高齢化が部活動に影響を与えました。総合型地域スポーツクラブのモデル事業(1995年)など、学校外への部活動移行の試みもなされましたが、多くの課題が残されています。近年の学校における働き方改革やスポーツ庁の設立なども、部活動のあり方を見直す契機となっています。公立高校における部活動撤廃の試みも注目されています。また、地域との連携強化、部活動の多様化、指導方法の改善などが、今後の課題となっています。キーワード:少子高齢化、総合型地域スポーツクラブ、学校における働き方改革、スポーツ庁、部活動改革、地域連携。
1. バブル崩壊後の経済状況と部活動
平成時代に入ると、バブル経済崩壊による不況、消費税導入、企業におけるリストラ、年功序列・終身雇用制度の崩壊などにより、雇用不安定な状況が生まれました。完全失業率の上昇など、バブル経済崩壊の影響が様々な形で社会に現れました。こうした社会情勢の変化は、部活動にも影響を与えました。平成13年に出された文部省通達では、対外試合の制限が回数こそ同じでしたが、原則化され、高校生の対外試合は年1回に制限されました(国体や全日本選手権大会は除く)。これは、部活動の競技性を抑制しようとするものでしたが、むしろ、競技性への需要(PULL要因)を強める結果となった可能性があります。その後も、経済状況の悪化や社会情勢の変化が、部活動にPush・Pull要因として作用し続け、そのあり方を揺るがせました。平成30年時点で全国に3,599のクラブが設立されている状況も、こうした変動の中で理解する必要があります。
2. 総合型地域スポーツクラブの取り組みと課題
文部省は平成7年に総合型地域スポーツクラブモデル事業を開始し、全国19クラブを指定しました。しかし、中体連や高体連の大会出場には学校の部活動への所属が必須であるため、総合型地域スポーツクラブは大会参加が制限されており、地域クラブ間の交流も難しい状況がありました。活動場所の確保、指導者の不足、クラブ運営の継続性の確保など、多くの課題が山積しており、部活動の地域社会への移行は進んでいませんでした。これは、部活動が学校に依存した状態が続いていることを示しています。平成25年の運動部活動のあり方に関する調査報告書において、部活動と総合型地域スポーツクラブの連携が提唱されましたが、永谷(2015)によると、連携事例は存在するものの、人口が少ない地域や、クラブ側の強力なリーダーシップがない限り、恒常的な連携は難しい現状が示されています。
3. 学校における働き方改革と部活動
近年、学校における働き方改革が叫ばれていますが、教員の業務量や環境、人員は変わっていない状況で、ガイドラインを示しただけでは、何が変わるのか疑問が残ります。罰則規定がないため、各教育委員会は自主的に方針を策定し、検証、連携、取り組み状況の把握などを行う必要があります。タイムカードによる記録や産業医への相談、持ち帰り仕事の禁止などが推奨されていますが、平成20年の文部科学省による「脱ゆとり教育」の流れや、教育再生会議の報告(スポーツ振興に関する国の責務の明確化)、新スポーツ振興法制定プロジェクトチームの活動、2020年東京オリンピック開催なども、部活動を取り巻く環境に大きな影響を与えています(川人・渡辺,2015)。スポーツ立国調査会やスポーツ振興に関する懇談会の報告書(遠藤利明氏)でも、トップスポーツにおける国家戦略の必要性が明言されており、部活動は国家レベルの政策と密接に関連していることがわかります。
4. 部活動の多様化と公立高校における部活動撤廃の試み
近年、部活動は競技力向上のみならず、体力向上、コミュニケーション醸成、スポーツ概念の拡大など、多様な目的を持つようになってきました。競技成績を重視する部活動、大会出場をせず教育的側面を重視する部活動、競技性を追求しつつスポーツの概念を拡大する部活動など、多様化が進んでいます。しかし、公立高校においては、部活動そのものを撤廃する試みも現れています。これは、部活動の在り方について、抜本的な見直しが行われていることを示しています。ある公立高校では、部活動に代わるものとして、サークル活動やボランティア活動を導入しています。生徒の評価は高く、75~85%が肯定的な評価を示していますが、学校側はサークル活動の活性化を課題として認識しています。顧問教員の役割は、活動計画・予算管理、安全対策などに限定され、専門的な技術指導は行われません。この試みは、従来の部活動モデルからの脱却を試みるもので、その成果と課題は今後注目されるべきです。
VI.部活動の類型と課題 Types of Club Activities and Challenges
本文では、費用負担や指導者の有無、競技志向の度合いから部活動の類型を分類し、それぞれの特徴と課題を分析しています。特に、費用負担の高いエリート指向の部活動や、指導者不在による安全管理の問題点が指摘されています。キーワード:部活動類型、費用負担、指導者、競技志向、安全管理。
1. 部活動の類型 競技志向 指導者 費用負担
本文では、部活動の類型を競技志向、指導者の有無、費用負担の3つの軸で分類しています。具体的には、①競技志向が高く、専門的な指導者もいて費用負担も高いタイプ、②競技志向は高いが、専門的な指導者がおらず、費用負担は低いタイプ、③競技志向が低く、専門的な指導者もおらず、費用負担も低いタイプ、④競技志向が低く、指導者はおらず、費用負担も低いタイプ、⑤競技志向が高く、指導者もいて費用負担も高いタイプ、という5つの類型が想定できます。 それぞれの類型には、メリット・デメリット、そして課題が存在します。特に、費用負担が高いタイプでは、生徒や保護者への経済的負担が問題となります。また、指導者不在のタイプでは、安全管理の徹底が重要になります。これらの類型は、部活動の多様性を示す一方で、それぞれに固有の課題を抱えていることを示しています。特に、費用負担の高さや安全管理の不足は、多くの部活動が直面する共通の課題と言えるでしょう。
2. 各類型における課題と今後の展望
費用負担の高い部活動では、特に全国大会出場を目指すような学校では、多額の費用が必要となり、生徒や保護者への負担が大きくなっています。甲子園出場校では5000万円、サッカーやラグビーでも1000万円近い費用が集められるケースがあるとされています(関,2014)。これは、経済的な格差によって参加機会の不平等が生じる可能性を示唆しており、大きな課題と言えます。一方、指導者不在の部活動では、安全管理が重要な課題となります。専門的な指導を受けられない生徒にとって、安全な練習環境の確保は不可欠です。部活動の多様化の中で、これらの課題を解決し、全ての子どもたちが安全で充実した部活動に参加できるよう、指導体制や費用負担のあり方、そして部活動の目的や位置づけについて、更なる検討が必要です。学校だけでなく、地域社会全体で子供たちの健やかな成長を支える体制作りが求められています。
