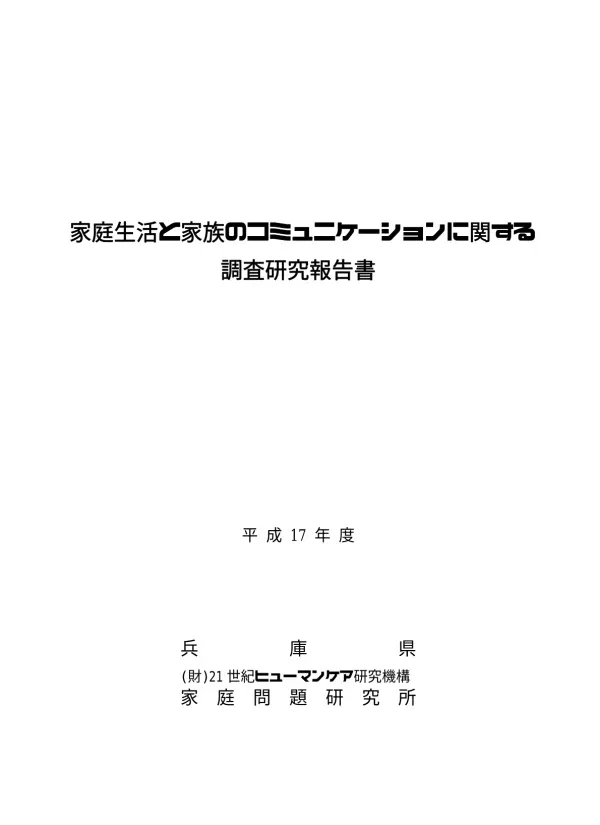
家族コミュニケーション調査報告書
文書情報
| 著者 | 野々山 久也 |
| 学校 | 甲南大学 |
| 専攻 | 文学部 (推定) |
| 出版年 | 2005 (平成17年度) |
| 会社 | 家庭問題研究所 |
| 場所 | 兵庫県 (推定) |
| 文書タイプ | 調査研究報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 546.57 KB |
概要
I.家族コミュニケーションの現状と課題 孤独感 との関連
本調査は、兵庫県における家庭生活と家族コミュニケーションに関する研究です。近年、家族の小規模化や共働き増加などにより、家族コミュニケーションの機会減少、ひいては孤独感の増大が社会問題化しています。特に、夫婦関係におけるコミュニケーションの質と量、そして孤独感との関連性を分析しました。特に、夫婦コミュニケーションの質(情緒的サポート、話題の共有)と量の両方が孤独感に影響を与えることが示唆されました。
1. 家族コミュニケーション減少と社会問題の顕在化
近年の家族の小規模化、共働き世帯の増加、長時間労働、塾通い、個室化などにより、家族間のコミュニケーション機会は減少傾向にあります。このコミュニケーション不足は、児童虐待、DV、高齢者虐待、子どもの凶悪犯罪といった深刻な社会問題の背景の一つとして懸念されています。 家族関係におけるコミュニケーションの質と量の低下が、個人の孤独感や家族間の摩擦に繋がる可能性が示唆されています。特に、女性の孤独感は、一人で過ごす時間の長さよりも、家庭内でのコミュニケーションの不足と強く関連しているという興味深い傾向も示されています。また、若い世代においても、個人間の関係性というよりも、性別役割分業に基づいた夫婦関係が維持されているケースが見られ、コミュニケーションの在り方に課題があると考えられます。本研究では、こうした現状を踏まえ、夫婦関係におけるコミュニケーションの現状と課題、そして孤独感との関連性を明らかにすることを目的としています。
2. 調査方法と分析手法
本調査は、家族関係の中でも比較的対等で自立した関係が成立しやすいとされる夫婦関係に焦点を当て、アンケート調査とインタビュー調査の両方を実施しました。アンケート調査では、家族に関する意識、夫婦間のコミュニケーションのあり方、家族内外ネットワークとその満足度に関する設問を用意し、それらの要因が個人の孤独感に与える影響を分析しました。一方、インタビュー調査では、アンケートでは捉えきれない、コミュニケーションのあり方と夫婦関係の満足度間の複雑な関係性を詳細に探ることを目指しました。 伝統的な家族規範が共有されている社会では、「阿吽の呼吸」のような非言語的なコミュニケーションが有効ですが、現代社会では、多様な価値観を持つ人々が家族を形成するため、明確で意識的なコミュニケーションが円滑な家族運営に不可欠です。本調査は、平成17年度に家庭問題研究所が兵庫県の委託を受けて実施したものです。
3. コミュニケーションと孤独感の関連性の分析
コミュニケーションやネットワークの豊かさが孤独感を低減させることは男女ともに認められています。しかし、女性においては、一人で過ごす時間が少ないほど家庭での孤独感が高いという逆説的な結果も得られました。これは、家庭内における女性の置かれた立場を反映している可能性を示唆しています。本研究では、アンケート調査で得られたデータを基に、夫婦間のコミュニケーション(会話時間、共有行動、情緒的サポート、話題の共有など)と家庭における孤独感の関連性を分析しました。その結果、コミュニケーションの量と質の両方が、孤独感に有意な影響を与えていることが明らかになりました。この傾向は、年齢層に関わらず共通して見られました。特に、情緒的なサポートや共通の話題の共有は、孤独感の軽減に大きな役割を果たしていると考えられます。
II.夫婦間の コミュニケーション と 家族規範
アンケート調査では、家族規範に関する意識(家の継承、性別役割分業など)と夫婦コミュニケーションのあり方、家族関係の安定性との関係を分析しました。若い世代ほど伝統的な家族規範からの距離が大きく、夫婦間の平等性や個人の尊重を重視する傾向が見られました。一方、家族規範が共有されている場合は「阿吽の呼吸」的なコミュニケーションが成立しやすい一方、多様な価値観を持つ現代社会においては、明確なコミュニケーションが重要になります。
1. 家族規範に関する意識と世代間の差異
本調査では、アンケートを通じて、家族に関する規範や価値観についての意識を調査しました。具体的には、「子どもは家を継ぐべきだ」「家族は血のつながりが大事だ」「子どもが3歳くらいまでは母親は仕事をもたず育児に専念するべきだ」といった項目を含め、計14項目について、回答者の年齢層による差異を分析しました。その結果、「子どもは家を継ぐべきだ」という項目では、30代から60代の3世代間で明確な格差が見られ、若い世代になるほど反対する割合が高くなっていることが分かりました。同様に、「家族は血のつながりが大事だ」や「子どもが3歳までは母親が育児に専念すべきだ」といった項目についても、若い世代ほど反対またはどちらかといえば反対の割合が高く、伝統的な家族規範からの乖離が示唆されました。これらの結果は、現代社会における家族観の変化を反映していると考えられます。 主成分分析の結果、家族意識には「近代家族」的な側面と「直系家族制」的な側面の両方が含まれていることが示され、多様な家族像が共存していることが示唆されました。
2. 夫婦コミュニケーションと家族規範の関連性
アンケート調査では、家族規範に関する意識と夫婦間のコミュニケーションのあり方、そして家族関係の安定性との関連についても分析しました。「夫婦は二人でいる時間を大切にするべき」「結婚しても自分の生き方を大切にするべき」「夫婦でもプライバシーは尊重するべき」といった項目では、年齢層による差異は小さいものの、若い世代ほど、家の継承や夫婦の姓、性別役割分業といった伝統的な家族規範からの自由度が高い傾向が見られました。これは、現代の若い世代が、個人の生き方や夫婦間の平等性をより重視していることを示唆しています。一方で、伝統的な家族規範を強く意識する世代では、暗黙の了解や以心伝心に基づいたコミュニケーションが成立しやすい傾向があります。しかし、多様な価値観が共存する現代社会においては、明確で意識的なコミュニケーションが、家族円滑化に不可欠であることがわかります。
3. 夫婦間の意思決定と役割分担
夫婦間の意思決定プロセスについても調査しました。自家用車の購入や子どもの教育方針など、長期的な視点が必要な事項については話し合って決める夫婦が多い一方、日常の家事分担や夫婦の小遣いなどは話し合わずに決めるケースが多いことが明らかになりました。特に、家事分担や夫婦の姓については、女性が家事を担い、夫の姓を名乗るという決定をしている人が約9割にのぼり、結婚当初は性別役割分業に基づいた規範が強く影響していることが示唆されます。 若い世代では、学歴は同等であっても、労働状態や収入、年齢において夫の方が優れている夫婦が多く、実際の夫婦関係には性別による非対称性が存在することが分かりました。これは、家族に関する規範意識の薄れと、男女平等意識の高まりが共存する現代社会における夫婦関係の複雑さを示しています。
III. 夫婦の勢力関係 と コミュニケーション
夫婦の勢力関係を、日常的な決定事項における意思決定プロセスから分析しました。従来の研究では夫の学歴や収入が影響すると考えられてきましたが、本調査では、夫婦関係の平等性・対等性が重視される傾向にあることが示されました。夫婦間のコミュニケーションの頻度や質は夫婦関係の満足度に大きく影響し、特に会話時間の長さが重要であることが分かりました。兵庫県における過去の調査データとの比較も行い、時代の変化を分析しました。
1. 夫婦の勢力関係の測定と分析手法
本研究では、夫婦間の勢力関係を分析するために、日常的な家庭生活における意思決定を指標として用いています。具体的には、家計、家族行動、子どもに関する決定事項など、計14項目を設定し、各項目について話し合うか否か、そして最終的な決定権がどちらにあるかを調査しました。 従来の研究では、夫の学歴や収入といった資源が夫婦の勢力関係に影響すると考えられてきましたが、本調査では、より簡便な方法を採用し、各項目の合計値を基準に夫婦の勢力類型を分類、比較分析を行いました。兵庫県内では1963年と1995年に同様の調査が行われており、本調査はその知見を踏まえつつ、現代における夫婦の勢力関係の現状を明らかにすることを目的としています。過去の調査データとの比較を通じて、時代の変化による夫婦関係の変化を分析しています。
2. 夫婦の勢力関係と夫婦関係の満足度
夫婦間の意思決定において、「話し合う」と回答した項目は、「自家用車の購入」「家族連れでの外出」「香典」など多く、一方、「日常の家事分担」「夫婦の小遣い」「貯金」「日用品の買い物」など日常的な事項については話し合わずに決める傾向が見られました。これは、日常的な事柄は暗黙の了解や習慣によって決定される一方、重要な事項については話し合いを通して合意形成を図っていることを示唆しています。 また、夫婦の勢力関係と夫婦関係の満足度との関連性についても分析しました。過去の調査結果では、「夫婦関係は対等であるべき」という考え方の浸透が夫婦の勢力関係に影響を与えているとされていますが、本調査でも、夫婦間の平等性や対等性が重視される傾向が確認されました。特に、夫婦双方が意思決定において合意している「一致型」の夫婦では、妻の満足度が高い傾向が見られました。
3. コミュニケーションと夫婦関係の満足度
本調査では、夫婦間のコミュニケーションと夫婦関係の満足度との関連性を分析しました。アンケート調査では、会話時間、夫婦の共有行動、情緒的サポート、話題の共有といった変数を用いて、男女別、年代別に孤独感との相関関係を分析しました。 その結果、会話時間や夫婦の共有行動といったコミュニケーションの「量」だけでなく、情緒的サポートや話題の共有といったコミュニケーションの「質」も、夫婦関係の満足度に大きく影響を与えていることがわかりました。この傾向は、年齢層に関わらず共通して見られました。 さらに、会話時間が長いほど夫婦関係の満足度が高いという相関関係が確認されましたが、統計的な分析では因果関係までは特定できません。そこで、自由記述欄の回答から、夫婦間のコミュニケーションと会話時間の関係性を詳細に検討しました。
IV. コミュニケーション の質と 夫婦関係 の満足度 インタビュー調査
4組の夫婦へのインタビュー調査を実施し、夫婦コミュニケーションの特徴と夫婦関係の満足度との関係を質的に分析しました。 コミュニケーションの頻度や内容だけでなく、夫婦それぞれの役割意識や精神的自立の度合いが、夫婦関係の満足度やコミュニケーションのあり方に大きく影響していることが分かりました。共働き世帯や、家事・育児を積極的に分担する夫婦では、コミュニケーションが円滑で満足度が高い傾向が見られました。一方、コミュニケーションが乏しい夫婦でも、それぞれが精神的に自立し、他の人間関係に満足していれば、夫婦関係の満足度が低いとは限らないことも示唆されました。コミュニケーションは夫婦関係の結果として現れる側面もあることが分かりました。
1. インタビュー調査の概要と対象者
本研究では、アンケート調査に加え、質的な情報を深堀りするため、4組の夫婦(男性1名、女性3名)を対象としたインタビュー調査を実施しました。当初は、コミュニケーションが少なく夫婦関係の満足度も低い事例として捉えていたケースもありましたが、インタビューを通じて、職場や友人関係、親子関係との比較において相対的に夫婦関係の満足度が低いだけであり、必ずしも夫婦関係に強い不満を抱えているわけではないことが判明しました。 そのため、最終的には全ての対象者を、夫婦関係について満足度の高い事例として捉え直す必要がありました。この修正は、コミュニケーションの質と夫婦関係の満足度に関する理解を深める上で重要でした。インタビュー調査では、アンケート調査の自由記述欄の回答を補完し、より詳細な情報を収集することを目指しました。
2. 夫婦間のコミュニケーションの特徴と夫婦関係の満足度
4組の夫婦へのインタビュー調査の結果、夫婦間のコミュニケーションにはそれぞれ特徴があり、その特徴は夫婦間の役割意識や平等性などに規定されていることがわかりました。アンケート調査の自由記述欄の分析と合わせて考察した結果、夫婦間のコミュニケーションにおいて、相手に気を遣わなければならない状況では、夫婦関係の満足度が低い傾向がある一方、気を遣う必要がない状況、つまり自然体でいられる関係では、夫婦関係の満足度が高い傾向にあることが示唆されました。 コミュニケーションの質(「聞くことを大切にしている」「思いやりを持つ」「隠し事をしない」など)や、自然体でいられる関係性を重視する夫婦ほど、夫婦関係の満足度が高い傾向が見られました。一方、コミュニケーションの頻度や時間の長さだけでは、夫婦関係の満足度を完全に説明することはできません。
3. 個々の事例分析 コミュニケーションスタイルの多様性
インタビュー調査では、4組の夫婦それぞれについて、コミュニケーションスタイルと夫婦関係の満足度、役割意識の関連性を詳細に分析しました。Aさん夫婦は共働きで、家事を外部委託するなど、役割分担が柔軟で、平等性が高く、満足度の高い関係を築いていました。Bさん夫婦は、夫が家事や育児、介護に主体的に関わり、妻は夫に対して率直に意見を言える関係性を築き、高い満足度を示していました。 Cさん夫婦は、コミュニケーションがほとんどないにもかかわらず、高い夫婦関係の満足度を示しました。これは、Cさんが仕事や友人関係に満足しており、夫への依存度が低いことが要因であると考えられます。Dさん夫婦は、家族や地域とのコミュニケーションを重視し、夫婦共に家事や育児に積極的に関与する、満足度の高い関係を築いていました。これらの事例から、夫婦間のコミュニケーションスタイルは多様であり、コミュニケーションの質・量だけでなく、夫婦それぞれの役割意識や精神的自立、そして他者との関係性が、夫婦関係の満足度に影響を与えることが示唆されました。
V.結論 夫婦コミュニケーション の多様性と 孤独感 克服への示唆
本調査の結果、現代の夫婦コミュニケーションは多様化しており、夫婦関係の満足度や孤独感への影響も多面的であることが明らかになりました。夫婦間の平等性や個人の尊重、そして役割分担の柔軟性が、良好なコミュニケーションと高い夫婦関係の満足度に繋がることが示唆されました。孤独感の軽減には、量的・質的な夫婦コミュニケーションの充実だけでなく、個人の精神的自立や多様な人間関係の構築も重要です。現代家族における家族コミュニケーションのあり方について、新たな知見を提供しています。
1. コミュニケーションの質と夫婦関係の満足度の関係性
本研究のインタビュー調査では、アンケート調査の結果を補完する形で、4組の夫婦のコミュニケーションの質と夫婦関係の満足度の関連性を詳細に検討しました。アンケートの自由記述欄の回答を分析した結果、コミュニケーションを取る際に相手に気を遣わなければならない状況では、夫婦関係の満足度が低い傾向があることがわかりました。具体的には、「相手の顔色をうかがいながら決める」「機嫌が悪い時には話しかけない」「タイミングや話し方に注意する」といったコミュニケーションの仕方は、夫婦関係の満足度を下げる要因となっている可能性が示唆されました。 これに対し、コミュニケーションの取り方や内容に配慮し、相手への思いやりや自然体でいられる関係性を重視する夫婦ほど、高い夫婦関係の満足度を示す傾向が見られました。このことは、夫婦間のコミュニケーションにおいて、質的な側面が満足度に大きな影響を与えていることを示唆しています。
2. 4組の夫婦におけるコミュニケーションスタイルの多様性
インタビュー調査では、4組の夫婦それぞれが異なるコミュニケーションスタイルを持っていることが明らかになりました。Aさん夫婦は共働きで家事を外部委託するなど、役割分担が柔軟で平等性が高く、活発なコミュニケーションと高い夫婦関係の満足度を示しました。Bさん夫婦は、夫が家事や育児、介護に主体的に関与し、妻も夫に対して率直に意見を言える関係で、満足度の高い夫婦関係を築いていました。 一方、Cさん夫婦は、コミュニケーションの頻度が非常に少ないにもかかわらず、高い夫婦関係の満足度を示しました。これは、Cさんが仕事や友人関係に充実感を感じており、夫への依存度が低いためと考えられます。Dさん夫婦は、家族や地域とのコミュニケーションを重視し、家事や育児への協調的な関与を通して、満足度の高い夫婦関係を築いていました。これらの事例から、夫婦間のコミュニケーションは多様であり、コミュニケーションの頻度や時間の長さだけでなく、夫婦間の役割意識、精神的自立の度合い、そして家族や地域との関係性が、夫婦関係の満足度に複雑に影響していることがわかりました。
3. 夫婦コミュニケーションの特質と夫婦関係の安定性
インタビュー調査を通して、夫婦間のコミュニケーションの特徴は、夫婦間の役割意識や平等性によって大きく規定されていることがわかりました。コミュニケーションは、夫婦間での意志や情報伝達のツールであると同時に、夫婦関係の質を反映する指標ともいえます。コミュニケーションの方法や内容が夫婦関係を決定づけているというよりも、むしろ夫婦関係がコミュニケーションの特徴を大きく決定づけていると言えるでしょう。 4組の夫婦の事例を比較すると、役割意識が流動的で夫婦双方のコミュニケーションへの志向が高いAさん、Bさん、Dさん夫婦では、コミュニケーションの時間や内容が濃い傾向が見られました。一方、役割意識が固定的でコミュニケーションへの志向が低いCさん夫婦では、実際にもコミュニケーションは消極的でした。夫婦関係の安定には、夫婦双方の自立とバランスの取れた関係性が重要であり、それがコミュニケーションの質を高め、満足度の高い夫婦関係へと繋がることを示唆しています。
