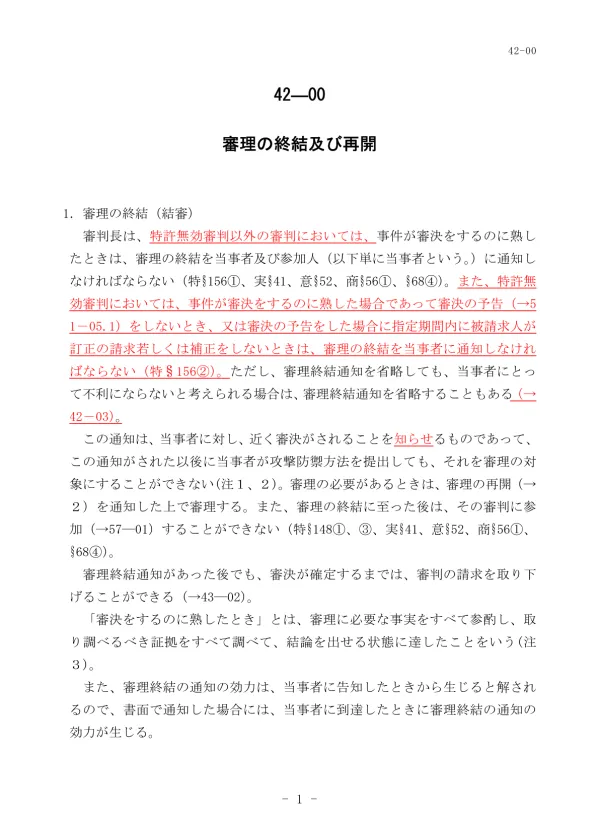
審理終結通知:特許審判手続きの解説
文書情報
| 学校 | 特許庁(Patent Office) |
| 専攻 | 工業所有権法(Industrial Property Rights Law) |
| 出版年 | 不明 (Unknown) |
| 場所 | 不明 (Unknown) |
| 文書タイプ | 審判実務解説資料 (Procedural Explanation Material for Trials) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 347.99 KB |
概要
I.審決手続きと審理の再開 特許法を中心とした解説
本資料は、特許庁における特許、実用新案、意匠、商標に関する審判手続きを解説しています。特に、審決(Shinketsu) の確定、審理(Shinri) の再開要件、**補正(Hosei)や訂正(Teisei)の取り扱い、請求(Seikyu)の却下(Kyakka)、放棄(Houki)、及び取下げ(Torisage)**について詳しく述べられています。**審理終結通知(Shinri Shuuketsu Tsuuchi)**の省略が問題となるケースや、**審判費用(Shinpan Hiyou)**の負担についても説明があります。特許法、実用新案法、意匠法、商標法、行政不服審査法などの関連法規に基づいた具体的な事例が多数紹介されており、各法条(例:特許法第156条2項)も参照されています。**特許庁(Tokkyocho)**における審判手続きを理解する上で重要な資料です。
1. 審決の予告と審理終結通知
審決が近付いていることを当事者に通知する際、その通知後、当事者が攻撃防御方法を提出しても、それは審理の対象とはならないと明記されています(注1、2)。審理の必要がある場合は、審理再開を行い、当事者に通知した上で審理を再開します。審理終結後は、その審判に参加できなくなります(特148①、③、実41、意52、商56①)。効審判においては、審決をするのに事件が熟した場合、審決の予告をしない、または予告後指定期間内に被請求人が訂正等の請求をしない場合、審理終結を当事者に通知する必要があります。ただし、特許法第156条第2項により、審理終結通知を省略しても、当事者に不利益が生じない場合もあります。 審決の予告(→51-05.1)の手続きや、その省略に関する規定が詳細に説明されています。 審理終結通知の有無が審決の有効性に影響する可能性が示唆されています。
2. 審理の再開要件と特許法との関係
当事者の申立てや職権により、審理の再開を行うことができます(特156条(注1)、実41、意52、58②③、商56①、60の2)。審理再開は、審理の完全性を期するために行われ、重大な証拠の取調べが未済である場合や、審理終結通知と入れ違いに請求理由の補充や明細書の補正などが行われた場合などが該当します。審判長が必要と認めた場合にのみ行われます。 特許庁が申し立てに応じて審理を再開しなかった事例が挙げられ、その手続き違反に関する原告主張が、特許法の補正制度と相容れないと指摘されています。特許法第156条第2項の審理再開制度は、審理の万全を期するためのものであり、補正を認めるためのものではないと解釈されています。 審理再開の要件と、その適用に関する法解釈が詳細に論じられています。
3. 審理終結通知省略の問題点と事例
審理終結通知をせずに審決が行われ、その直前に明細書等の補正や資料補充が行われた場合、それらが審理の対象にならなかったことで当事者に不利益が生じる可能性があります。この場合、審決は違法となる可能性がありますが、それは審理終結通知の怠慢ではなく、審理不尽が原因であるとされています(注1)。当事者系審判で審決却下を行う場合(請求書の副本送達漏れを含む)、当事者双方に審理終結通知を行う必要があります。 審理終結通知の省略に関する具体的な事例と、その法的影響について分析されています。審決の違法性を判断する際の基準が示唆されています。
4. 審判請求の一部取下げと注意事項
審判請求の一部取下げは、43-01及び43-02の手続きと同様ですが、取り下げた部分の申立て理由や証拠は、特許法第153条第1項の「当事者又は参加人が申し立てない理由」に該当します。また、取下げの場合も特許法第169条第1項で費用の負担について規定があり、審判が審決によらないで終了する場合は、審判による決定で職権で定めなければならないことに注意が必要です。 特許請求の範囲に1請求項として記載されているものの一部を取り下げることはできません。昭和62年12月31日以前の出願に係る特許については、特許請求の範囲に2以上の発明が記載されている場合、発明ごとに取下げることが可能です。 一部取下げに関する手続き上の注意点と、費用負担に関する規定が詳細に説明されています。
II.審判請求の適法性と却下事由
審判請求の適法性に関する重要なポイントとして、請求人・被請求人の適格要件、請求書の必要記載事項、手数料納付の期限遵守などが挙げられます。これらの要件を満たさない場合、特許法第135条に基づき**請求却下(Kyakka)の審決(Shinketsu)**が下されます。請求人または被請求人の変更が請求書の要旨を変更する場合も、同様に却下される可能性があります。 また、特許(登録)無効審判、拒絶査定不服審判、訂正審判など、審判の種類によって異なる手続きや規定が適用されます。
1. 請求人の資格と請求書の要件
審判請求の適法性に関する記述では、まず請求人の資格要件が重要視されています。特に、特許を受ける権利が共有の場合、特許法第132条第3項に基づき、共有者全員が共同で請求しなければならない点が強調されています。 この要件を満たさない場合、請求は不適法となり却下されます。 請求書には、必要な記載事項が全て含まれている必要があります。記載事項に欠陥がある場合も、却下理由通知や補正命令の手続きが行われます。 請求書への記載事項や、その審査に関する手順が示されており、請求の不適格による却下事由が明確に説明されています。 例として、共有者の一部の者のみによる請求が不適法な例が示されています。また、請求書の必要な記載事項の確認のため、特許庁の記録と照合する手順も触れられています。
2. 手数料未納付と請求却下
審判請求を行う際には、正規の手数料を納付することが義務付けられています。手数料を期日までに納付しなかった場合、特許法第133条第3項(実用新案法第41条、意匠法第52条、商標法第56条準用)に基づき、請求は却下されます。 この事例は、手数料未納付が審判請求却下の明確な理由となることを示しています。 審判長は、不足手数料の納付を命じる期間を指定しますが、その期間内に納付されなかった場合、請求は却下されるという流れが示されています。 手数料納付の重要性と、未納付による請求却下の法的根拠が明確に示されています。
3. 請求人 被請求人の変更と請求却下
審判請求後、請求人や被請求人の変更を行う場合、その変更が請求書の要旨を変更すると認められると、特許法第131条第2項に違反することになり、請求は却下されます(注2)。 請求人・被請求人の変更が、請求書の要旨変更に該当するかの判断基準が示唆されています。 このケースでは、変更後の請求内容が当初の請求内容と大きく異なる場合に、不適法と判断される可能性が示されています。 請求人や被請求人の変更に関する手続き上の注意点と、その法的根拠が示されています。変更手続きにおける要旨変更の判断基準が、重要視されています。
III.審決の確定と不服申立て
審決(Shinketsu)は、特許法第157条(他法令準用を含む)に規定されるように、審決をもって終了します。 審決の確定(Kakutei)は、取消訴訟が提起されず、または提起されても終局的に審決が支持された場合に生じます。 審決の内容に誤りがある場合、更正決定を行うことがありますが、これは表示上の明白な誤謬に限られます。不服がある場合は、行政不服審査法に基づく異議申立てを行うことができます。
1. 審決の確定条件
審決は、特許法第157条(実41、意52、商56①、68④準用)で規定されているように、審決をもって終了します。 審決の確定は、特許法第178条第3項、実用新案法第47条第2項、意匠法第59条第2項、商標法第63条第2項に則り、取消訴訟が提起されず、または提起されても終局的に審決が支持され、通常の不服申立てで取り消せない状態になった時に確定します。 拒絶査定不服審判で特許登録すべきとする審決、訂正審判で訂正が認められた場合の審決(注1)なども、不服を申し立てる法律上の利益が存在する場合、確定に関する規定が適用されます。 複数の請求項からなる特許の審決については、全てが確定する状態になった時点で、各請求項ごとに確定するとされています(注2)。 請求項を削除する訂正を認めた部分は、審決の送達と同時に確定するとされています(注5)。 審決の確定に関する法的な要件と、その具体的な適用例が、複数の法条を参照しながら説明されています。
2. 審決の更正
民事訴訟法では判決の更正が規定されていますが、特許法には同様の規定がありません。しかし、判例では審決の更正を認めています(大判昭4.10.16、大判昭9.5.8、大12.12.3)。更正決定は、表示上の誤謬を訂正する場合に限り、その誤謬が明白な場合に限られます。更正決定によって審決の内容を実質的に変更することはできません。 審決の更正に関する判例と、更正が認められる条件が説明されています。 審決の更正は、審決の発送後にも可能ですが、その範囲は表示上の誤謬の訂正に限定され、審決の内容を実質的に変更することは許されません。 審決の更正手続きと、その制限に関する重要な点が強調されています。
3. 不服申立ての方法
審決の更正決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、書面受領日の翌日から60日以内に特許庁長官に対して審査請求をすることができます。 不服申立てに関する手続きと、その期限が明示されています。 この部分では、不服申立ての方法と期限が明確に示されており、具体的な手続きに関する情報が提供されています。 行政不服審査法に基づく不服申立て手続きの案内が、明確に記載されています。
IV.審判費用と負担
審判費用は、費用負担(Hiyou Futandan)に関する規定に基づき、請求人または被請求人のいずれかが負担します。費用負担の決定は、当事者の申立ての有無にかかわらず職権で行われます。勝敗、利害関係の有無、不必要行為の有無など、様々な要因が費用負担の決定に影響します。費用計算書と意見書の提出を求める催告手続きも存在します。
1. 審判費用の負担 基本原則と職権決定
審判費用(Shinpan Hiyou)の負担については、特許(登録)無効審判(特123、実37、意48、商46、§68④)、商標登録取消審判(商50、51、52の2、53、53の2)などにおいて、当事者の申立ての有無に関わらず、職権でどちらが負担すべきかを結論で明確に表示しなければなりません。 審決、決定の結論部分には、請求や申立ての不適法却下、請求趣旨の全部または一部の容認・排斥を簡潔明瞭に記載し、審決・決定の効力と範囲が一目でわかるように記述する必要があります。 拒絶査定不服審判、意匠・商標登録出願における補正却下決定不服審判、訂正審判に関する費用は、請求人の負担となります。商標登録異議の申立てに関する費用は、異議決定の結論に関わらず、申立人の負担と定められています(特§169③、意§52、商§56①、68④)。 費用負担に関する基本原則と、具体的な審判の種類ごとの規定が示されています。 審判費用負担の決定は、当事者の主張によらず、職権で行われることが強調されています。
2. 費用の負担に関する例外事項
審判請求の利害関係について当事者間に争いがあり、証拠調べなどに費用を要した場合、その費用の負担は、利害関係について争った当事者間で、本案審理の勝敗とは別に、争いの勝敗によって決定できます。 費用負担額を決定する前に、相手方に費用計算書と疎明に必要な書類、請求人の費用計算書の内容に関する陳述書を一定期間内に提出するよう催告しなければなりません。ただし、相手方のみが費用を負担する場合で、記録上で費用負担額が明らかな場合は、催告は不要です(特施則§50の8①)。 証人尋問の結果、証人が立証に無関係だった場合、証人尋問費用を申請した当事者が勝者であっても、その当事者に費用を負担させることができます。請求項が全て削除された場合も、無効審判が却下されるため、勝者側に費用を請求させることが考えられます。 審判費用の負担に関する例外的なケースと、その処理方法が説明されています。特に、利害関係の争いがある場合や、不必要行為があった場合の費用負担について、詳細な規定が示されています。
3. 費用負担額の決定手続き
審判費用額の決定を求める申立てがあった場合、その事件の記録を工業所有権情報・研修館から借り受け、請求書の記載事項と記録を照合し、欠陥の有無を審査します。欠陥があれば、却下理由通知や補正命令の手続きを行います。 審判部長までの決裁を得て、請求書計算書と費用額を疎明する書類の副本を相手方に送達し、事情を考慮して期間を指定し、意見書提出の機会を与えます。ただし、相手方のみが費用を負担し、記録上で請求人の費用負担額が明らかな場合は、この限りではありません(特169②、実41、意52、商56①、68④、民訴則25①)。 費用負担額の決定に関する手続きが詳細に解説されています。 相手方への催告、意見書提出の機会の付与、記録上の情報に基づく例外処理など、費用負担額決定手続きにおける重要なポイントが示されています。
