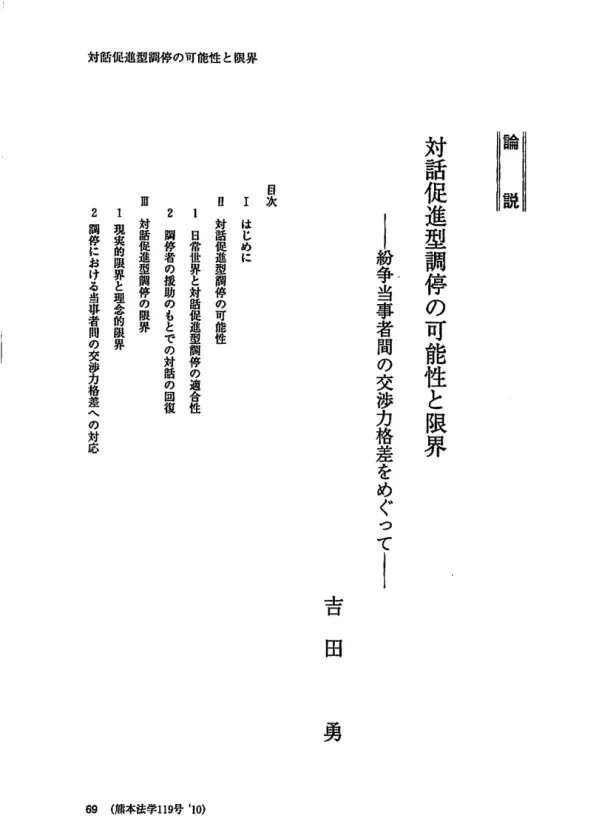
対話促進型調停:可能性と限界
文書情報
| 学校 | 熊本大学 |
| 専攻 | 法学 |
| 場所 | 熊本 |
| 文書タイプ | 論説 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.24 MB |
概要
I.対話促進型調停の可能性 可能性 Possibility of Dialogue Promoting Mediation
この章では、対話促進型調停が日常世界とどのように適合するか、そして調停者が当事者間の交渉力格差を克服し、対話を回復させるためにどのような援助を提供できるかを検討します。合意形成のプロセスにおいて、公正な第三者である調停者の役割が重要であり、紛争解決へのアプローチとして、原則立脚型交渉のような客観的な基準に基づく解決策が提示されています。水俣病事件における自主交渉派の取り組みは、対話による紛争解決の可能性を示す重要な事例として取り上げられています。川本輝夫氏率いる自主交渉派は、チッソとの直接交渉を強く主張し、長期間にわたる座り込みなどを通じて、交渉力格差を克服しようとしたのです。
1. 日常世界と対話促進型調停の適合性
この小節では、対話促進型調停が日常世界とどのように適合するのかを論じています。日常的な対話による利害調整や合意形成は、紛争解決における交渉や合意形成の基本的な営みであり、対話促進型調停は、この日常的な対話性を基礎にしている点で、社会に自然に受け入れられやすいと主張されています。調停を日常的な対話の延長線上にあるものとして捉えることで、調停の可能性を広げることができるとの考えが示されています。 具体的には、人間関係、共同体、そして法のレベルにおける対話性の回復が重要であり、対話型社会、成熟社会の形成がその前提条件として挙げられています。日常世界における多様な対話性を調停の理念に高める、あるいは調停の理念を日常的な対話性の土台に据える必要性が強調され、調停の理念を日常的な対話の上に基礎づけることが、調停の可能性を広げる鍵となると結論づけています。
2. 調停者の援助のもとでの対話の回復
この小節は、調停者が当事者間の対話可能性を回復するために、どのような援助を提供できるのかに焦点を当てています。紛争当事者は、自分の視点からしか物事を見ることができず、自己の正当性を絶対的に主張しがちです。そのため、調停者は、当事者の存在を受容し、自己相対化と自己の距離化を促す役割を担うことが重要だと述べられています。自己相対化とは、他者との関係性の中で自己の考え方の偏りを認識すること、自己反省化とは、自己を客観的に見つめ直すことを指しています。これらのプロセスを経て、当事者は相手に向き合うことができ、一方的な理解から相互的な理解へと変化していく可能性が示唆されています。調停者の援助なしでは、対話や交渉による紛争解決が困難な場合、調停者の介入が不可欠であるとされています。調停者は、当事者間に対話の可能性を開くための援助をどのように行うのかが問われています。
3. 規範の共有と法的正当化による対話可能性の拡大
この小節では、対話可能性を促進するための二つの観点を提示しています。一つ目は、規範の共有による対話可能性です。当事者間で共通の規範を共有している場合、その規範を基準にすれば対話が可能になります。中間集団や共同体における共有規範は、対話可能性の成立に重要な役割を果たすとしています。ただし、公正な第三者(調停者)は、具体的な個人ではなく、当事者が援用する抽象的な公正な基準や共同体の中で実感される規範意識として機能すると説明しています。二つ目は、主張の法的正当化による対話可能性の拡大です。日常言語と法律用語のギャップを克服するために、両者を繋ぐ言葉の形成が必要であると述べられています。これは、法的観点からの正当性を明確にすることで、対話可能性をより広げることができるという考え方です。ハーバード流交渉術における「原則立脚型交渉」が、この観点と関連付けられています。
II.対話促進型調停の限界 限界 Limitations of Dialogue Promoting Mediation
対話促進型調停は万能ではなく、限界が存在します。特に、当事者間の交渉力格差は大きな課題です。調停者は説得によって合意を目指しますが、交渉力の強い当事者の影響を完全に排除することは困難です。川島武宜氏の指摘するように、裁判所の裁判権を背景とした法的な裏付けがなければ、調停における「力の支配」を完全に破ることはできません。合意は当事者の自由意思に基づくものですが、その結果が不当なものである場合、調停は限界に直面します。レビン小林久子氏の指摘する、自己決定の相互尊重と平等な法的な調停の理念も重要な要素です。水俣病事件での見舞金契約は、交渉力格差がどのように合意に影響するかを示す例として分析されています。
1. 当事者間の交渉力格差への対応における限界
この小節では、対話促進型調停における最大の限界として、当事者間の交渉力格差が取り上げられています。交渉力格差は、調停者の努力にもかかわらず、対話を促進することを困難にする要因となります。特に、民間型や行政型の調停では、裁判所における調停のように裁判官が主宰する調停委員会による交渉力格差の相対化作用を期待することが難しく、格差が対話阻害要因となる可能性が高いと指摘されています。この限界は、当事者と調停者の現実的な能力の差による実際的な対応困難さと、対話促進型調停の理念そのものによる限界の二つの側面から分析されています。調停者がいくら対話促進に努めても、調停の理念と現実の乖離が生じる可能性があることを示唆しています。 調停が合意によって成立する以上、この交渉力格差の問題は根本的に解決できない内在的な矛盾として提示されています。
2. 調停における 当事者の力の支配 問題と川島武宜氏の指摘
調停における「当事者の力の支配」という問題について、故川島武宜氏の指摘が紹介されています。川島氏は、裁判所の調停においてさえ、裁判所の裁判権による裏付けがなければ、当事者の力の支配を破ることはできないと主張しました。この指摘は、対話促進型調停にも当てはまるとしています。裁判所における調停では調停委員会の判断が重視されますが、当事者の合意がなければ調停は成立しません。この点は、対話促進型調停においても同様であり、交渉力格差が強い当事者の「力の支配」につながる可能性を指摘しています。さらに、日本の社会では訴訟が市民にとって身近ではないため、調停におけるこの内在的な矛盾を解決することは容易ではないと分析されています。調停が当事者の力関係に左右される状況を放置すれば、国民の不満と不信が増大すると警鐘を鳴らしています。
3. 高野耕一氏 棚瀬孝雄氏 レビン小林久子氏の意見と調停モデルの多様性
この小節では、川島武宜氏の問題意識を継承・発展させた、高野耕一氏、棚瀬孝雄氏、レビン小林久子氏の考え方が紹介されています。高野氏は、調停委員会の判断と当事者の合意の両方が必要であり、合意を重視しすぎると弱者救済が軽視される危険性を指摘しています。棚瀬氏は、調停における「合意の強制」というパラドックスに着目し、近代的な枠組みの見直しを提唱しています。レビン小林氏は、調停の基本理念として自己決定の相互尊重と平等の尊重を重視し、形式的平等に加え、条件付きで実質的平等も認めるべきだと主張しています。 さらに、判断型、交渉型、教化型、治療型の4つの調停モデルが紹介され、それぞれのモデルが持つ特性と限界が示唆されています。これらの異なる調停モデルの存在は、対話促進型調停が万能ではなく、状況に応じて適切なアプローチを選択する必要があることを示唆しています。
4. 水俣病事件における自主交渉の事例分析と調停の限界
水俣病事件における自主交渉派とチッソとの交渉事例を分析することで、対話促進型調停の限界が示されています。自主交渉派は、チッソとの直接交渉を強く求めましたが、チッソは第三者機関への委託を主張し、長期にわたる対立が続きました。この事例は、交渉力格差が極めて大きい場合、調停が必ずしも効果的な紛争解決手段とはならないことを示しています。自主交渉派の努力と、世論や支援団体の支援、そして裁判所の判決によって最終的に補償協定が締結されましたが、この過程は、対話促進型調停が抱える限界と、紛争解決における困難さを浮き彫りにしています。見舞金契約と補償協定の比較分析を通じて、交渉力格差が合意形成に及ぼす影響が詳細に検討されています。この事例は、調停における合意が、必ずしも公正な解決を意味するわけではないことを示唆しています。
III.水俣病事件における相対交渉と調停 水俣病 Minamata Disease Case Study
水俣病事件における自主交渉派とチッソの交渉は、極端な交渉力格差が存在する状況下での調停可能性を探る重要な事例です。自主交渉派は、チッソとの直接交渉を求め、長期間にわたる座り込みなどの闘争を展開しました。この闘争は、対話と合意に到達するための困難さと、公正な紛争解決を実現するための社会的な支援の必要性を示しています。合意に至る過程では、世論や支援団体の支援、そして熊本地裁におけるチッソの不法行為責任の認定が重要な役割を果たしました。見舞金契約と補償協定の比較を通じて、交渉力格差が紛争解決の過程に与える影響が分析されています。
1. 水俣病被害者による自主交渉 見舞金契約と補償協定の比較
この小節では、水俣病事件における被害者側の自主交渉の取り組みを、見舞金契約と補償協定の二つの事例を通して分析しています。川本輝夫氏をリーダーとする自主交渉派は、訴訟や行政による調停ではなく、チッソとの直接交渉を強く主張しました。 当初、チッソは第三者機関による調停を主張し、長期戦を挑んできました。自主交渉派は、チッソ本社前での座り込みやハンストなど、粘り強い行動を続けました。見舞金契約は、チッソの不誠実な対応と被害者側の交渉力の弱さが際立つ結果となりました。一方、熊本地裁におけるチッソの不法行為責任が認められた後の補償協定は、自主交渉派の粘り強い闘いと、世論や支援団体の支援、そして環境庁長官と熊本県知事の仲介によって実現した画期的なものです。これらの事例を通して、交渉力格差が顕著な状況下での相対交渉の困難さと、その克服のための条件が考察されています。
2. 自主交渉派の闘争と交渉力格差の克服
自主交渉派の闘争は、圧倒的な交渉力格差に直面しながら、長期間にわたる座り込みやハンストなどの行動を通じて、徐々に世論や支援団体の支援を得ていった過程を示しています。川本氏らのリーダーシップと、各地の「水俣病を告発する会」などの支援団体の活動が、交渉力格差を克服する上で重要な役割を果たしました。 チッソ側は、自主交渉派を繰り返し切り崩そうとしたり、座り込みを排除しようとしたり、様々な妨害行為を行いました。しかし、自主交渉派は、相対交渉に応じるまで粘り強く交渉を継続するという強い意思を示し続けました。五井工場集団暴行事件などは、その闘争の過酷さを象徴的に示す出来事です。最終的に補償協定が成立した背景には、チッソの民事責任が法的に確定したこと、東京交渉団の交渉力、そして支援団体の交渉支援能力の高さが挙げられます。
3. 相対交渉成功要因と調停可能性
水俣病事件の二つの自主交渉事例の比較分析を通して、相対交渉の成否を左右する要因が考察されています。見舞金契約では、交渉力格差が大きく、チッソの不誠実な対応も加わり、被害者にとって不当な結果となりました。一方、補償協定では、熊本地裁の判決によるチッソの法的責任の確定、自主交渉派の強い意思と行動力、そして支援団体による強力な支援が相乗効果を発揮しました。環境庁長官と熊本県知事の仲介も重要な役割を果たしています。これらの成功要因を分析することで、交渉力格差が著しい紛争においても、当事者間の意思と行動力、支援団体の存在、そして社会的な要因が相対交渉の成功に大きく影響することを示唆しています。また、これらの事例は、対話促進型調停の可能性と限界を改めて考えさせるものです。
IV.今後の課題 課題 Future Challenges
今後の課題として、公共型調停の制度化と、対話促進型調停が適合する紛争事例の拡大が挙げられます。社会の成熟化に伴い、「納得のいく解決」を求めるニーズが高まっているため、対話促進型調停の重要性はますます高まると予想されます。そのためには、調停者の育成と、市民が日常的に利用できる紛争解決のインフラ整備が不可欠です。専門性の高い紛争に対しては、民間型の評価型調停モデルも検討されるべきでしょう。交渉力格差を克服し、真に公正な紛争解決を実現するためには、法的な裏付けと社会的な支援が不可欠です。
1. 公共型調停の制度化の可能性
この小節では、公共型調停の制度化の可能性について論じています。既存の司法型、行政型、民間型の調停とは異なる、市民社会に根ざした公共型調停の必要性が強調されています。 「公共型調停」という表現は一般的ではないとしながらも、紛争当事者が日常感覚で活用できる基本的なインフラとして、対話促進型調停を位置付けるべきだと主張しています。裁判所調停のように全国的に配置され、利用コストが低いという特徴を維持するために、公共的な負担による制度化が望ましいとされています。これは、対話促進型調停が、社会の成熟化に伴い高まる「納得のいく解決」志向に応えるための重要な手段となるという認識に基づいています。専門性の高い紛争については、民間型の評価型調停モデルによる対応がより適切だと示唆されています。
2. 対話促進型調停に適合する紛争の拡大傾向と課題
この小節では、社会の成熟化に伴い、対話促進型調停に適合する紛争事例が増加していく傾向と、それに伴う課題について述べられています。 今後も、当事者間の交渉力格差は様々な形で存在し続けるため、対話促進型調停の可能性は、当事者間の対話可能性に大きく依存すると指摘されています。社会の成熟化に伴い、私的自治領域の拡大と関係的な配慮の拡大が進み、「納得のいく解決」を求める当事者が増加すると予想されるため、対話促進型調停へのニーズが高まると考えられます。しかし、調停は合意によって成立するため、調停者の関与にもかかわらず、交渉力格差が強い当事者の影響力や強制力に繋がる可能性を否定できません。 そのため、調停者が強い当事者の強制力を抑制し、当事者間の対話を回復するためには、いくつかの条件を満たす必要があると結論づけています。
