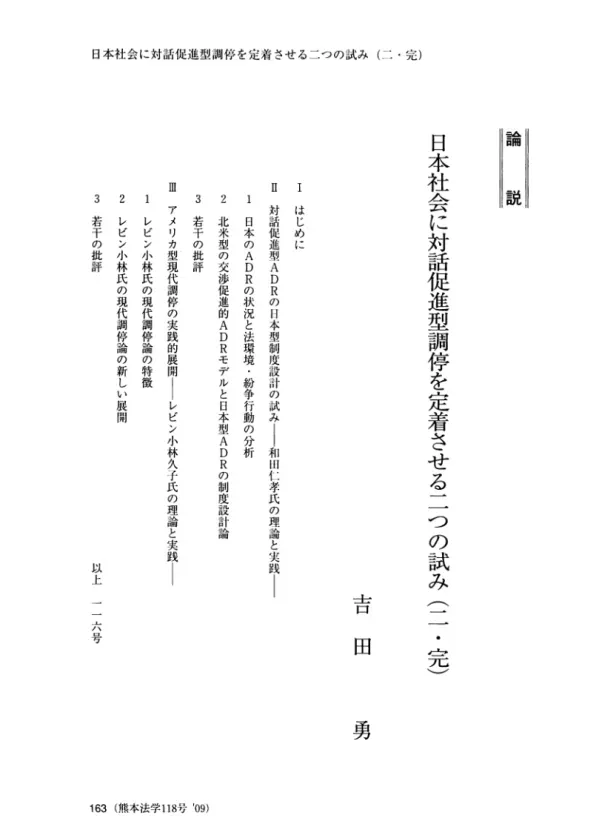
対話促進型調停:日本社会への定着
文書情報
| 著者 | 吉田勇 |
| 専攻 | 法学 (推定) |
| 文書タイプ | 論説 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.50 MB |
概要
I. 納得のいく解決 志向と対話促進型調停
本論文は、和田氏とレビン小林氏の研究を基に、日本社会における対話促進型調停の定着可能性を探る。特に、紛争当事者の「納得のいく解決」志向の高まりが、対話型調停の必要性を増しているという認識に基づいている。 両氏のADR(代替紛争解決)に関する理論と実践から学び、調停における「納得のいく解決」へのアプローチを考察する。
1. 紛争当事者の 納得のいく解決 志向
この節では、日本社会における紛争当事者の意識変化として、「納得のいく解決」志向の強まりが強調されている。従来の法的解決や非法的解決といった二元論的な枠組みを超え、当事者がより主体的に、そして感情的にも納得できる解決を求める傾向が顕著になっていると指摘する。 この「納得のいく解決」志向を、紛争解決過程における三段階の成熟プロセスとして仮説が提示されている。第一段階は法的解決と非法的解決の区別が曖昧な状態、第二段階は調停や訴訟といった専門化された手続きの意識的な利用、そして最終段階は法的解決と非法的解決の両方を反省的に統合し、当事者にとって最適な解決を選択する段階である。この三段階モデルは、単なる手続きの選択ではなく、当事者の意識や紛争へのアプローチの深まりを示している。 現代社会において、相対交渉のみで「納得のいく解決」に達することが困難になっている現状も示され、公正な第三者による援助の必要性が説かれる。この第三者介入を含めた理論モデルにより、紛争当事者の「納得のいく解決」志向の成熟過程をより深く理解しようとする試みが見られる。 この節は、単なる紛争解決方法の提示ではなく、社会全体の意識変化とそれに伴う紛争解決への新たなアプローチの必要性を明確に示している点において、重要な意味を持つ。
2. 和田氏とレビン小林氏の理論と実践 対話促進型ADRの二つのアプローチ
この節では、日本社会における対話促進型ADR(代替紛争解決)の定着可能性を探る上で、和田氏とレビン小林氏の研究が重要な示唆を与えていると述べられている。和田氏は日本型の対話促進型ADRの制度設計論、レビン小林氏はアメリカ型の現代調停の実践論を展開しており、両者のアプローチは対照的でありながらも、日本社会における対話促進型調停の定着という共通の目標に向かっている。 和田氏の理論は、制度設計の観点から、対話促進機能と法的情報提供機能を統合したシステムを提案している点が特徴的である。一方、レビン小林氏の理論は、アメリカにおける現代調停の実践に基づいており、具体的な調停技法や当事者との関わり方を重視した実践的なアプローチが示されている。 両者のアプローチは異なるものの、いずれも紛争当事者の「納得のいく解決」志向を重視しており、その点において共通している。この節は、日本社会における対話促進型調停の定着に向けた具体的な戦略やアプローチを示す上で、重要な役割を果たす。
3. 納得のいく解決 志向に適合的な対話促進型調停の要素 相互承認と関係性の重要性
この節では、「納得のいく解決」を達成するための対話促進型調停の構成要素として、相互承認と関係性の重要性が強調されている。 具体的には、紛争当事者間において、5つのレベル(主張・要求、利害関心、関係性、感情、個人の存在)での対立が存在する中で、特に「個人の存在」レベルでの相互承認が、対話と交渉の基盤となるという仮説が提示される。 この相互承認は、単に相手を認めるだけでなく、対話・交渉の相手として積極的に受け入れ、意識的に向き合うことを意味する。 さらに、ハーバード流交渉術(『続ハーバード流交渉術』『新ハーバード流交渉術』)が示す関係性の重要性も言及され、合理性、理解、コミュニケーション、信頼、説得、受容といった要素に加え、価値理解、繋がり、自律性、ステータス、役割といった核心的欲求が、関係構築に重要な役割を果たすとされる。しかし、これらの要素に加え、個人の存在レベルでの承認を重視する独自の視点を提示している点が、この節の大きな特徴である。 この節は、対話促進型調停を効果的に行うための、人間関係レベルでの基礎的な要素を明らかにすることで、より実践的なアプローチを示唆している。
II.対話促進型調停の制度化 二つのアプローチ
日本社会への対話促進型調停の定着には、二つの主要なアプローチがある。一つ目は、和田氏の提案する機能的統合システムであり、対話促進機能と法的情報提供機能を統合したシステムである。もう一つは、レビン小林氏が実践するアメリカ型の現代調停で、問題解決型調停とトランスフォーマティブ型調停の要素を融合するアプローチだ。 法的情報の提供方法についても、機能的統合システムと機能的連携システムの二つの可能性が検討されている。
1. 和田氏の機能的統合システム
この部分では、和田氏の提案する対話促進型ADRの制度設計、特に「機能的統合システム」が詳しく解説されている。このシステムは、対話促進機能と法的情報提供機能を一つのシステムとして統合することを目指している。 日本の法環境においては、紛争当事者がADR機関に法的情報や法的助言を求める傾向が強いことを踏まえ、対話促進型調停においても、これらの情報を提供する必要性を主張している。しかし、単純に法的情報を提供するだけでは、対話促進型調停の理念である当事者主体の合意形成を阻害する可能性があるため、法的情報提供を行う際には、リーガル・カウンセリング的なアプローチが不可欠だと強調されている。 これは、調停者が一方的に法的助言を行うのではなく、当事者の理解を深め、自己決定を支援する役割を果たすことを意味する。和田氏のモデルは、日本の法環境の現状を踏まえた、実践的な制度設計として提示されている。機能的統合システムは、当事者の複合的なニーズ、特に「納得のいく解決」を求めるニーズに包括的に対応できる点で優れているとされているが、その実現には、調停者が対話促進型調停の理念と技法に加えて、リーガル・カウンセリングの知識も習得する必要があるという課題も提示されている。
2. レビン小林氏のアメリカ型現代調停 問題解決と関係性の統合
対照的に、この節ではレビン小林氏のアメリカ型現代調停の実践論が紹介されている。レビン小林氏は、問題解決志向と関係志向の両方を統合したアプローチをとっている。 具体的には、「ウィン・ウィン解決」を目指す問題解決型調停の枠組みをベースとしながらも、トランスフォーマティブ型調停の「エンパワメント」と「承認」といった関係性の構築を重視した視点を積極的に取り入れている。 レビン小林氏は、トランスフォーマティブ型調停が関係性の重視に偏り、問題解決の手立てが疎かになる傾向があることを指摘し、その弱点を補う形で問題解決型と関係性の統合を図っている。 このアプローチは、アメリカの個人主義的な紛争理論を踏まえつつ、関係性の重要性を重視する点で、和田氏の機能的統合システムとは異なるアプローチを示している。 両者のアプローチを比較することで、日本社会における対話促進型調停の制度設計における多様な可能性が示唆されている。 レビン小林氏の方法は、実践的なスキル習得の重要性を強調しており、調停の理念と目的を理解した上で、具体的なトレーニングを通じてスキルを習得していくことが重要であるという点も強調されている。
3. 法的情報提供の二つのシステム 機能的統合と機能的連携
対話促進型調停における法的情報提供のあり方について、和田氏は「機能的統合システム」と「機能的連携システム」という二つの制度設計の可能性を提示している。前者は、対話促進機能と法的情報提供機能を一つのシステムとして統合するもので、日本の法環境の現状を鑑み、当事者の複合的なニーズに最も効果的に対応できるとされている。 しかし、このシステムは、調停者に高い専門性が求められるという課題がある。 これに対して、「機能的連携システム」は、対話促進機能と法的情報提供機能を別々の機関が担うことで、それぞれの専門性を活かしつつ、連携して調停を進めるシステムである。 このシステムは、将来的に法的情報へのアクセスが容易になれば、機能的統合システムに代わる有力な選択肢になると考えられる。 特に、市民型調停者のように、自ら法的情報を提供できない場合、外部機関との連携は不可欠であり、機能的連携システムがより現実的な選択肢となる。 この節では、日本の現状と将来的な展望を踏まえ、柔軟な制度設計の必要性が示唆されている。
III.調停における承認と関係性
効果的な対話促進型調停には、当事者間の相互承認と関係性の構築が不可欠である。 当事者と調停者、そして当事者同士が、互いの存在を認め合い、対話可能な関係を築くことが重要となる。 レビン小林氏は承認を重視し、和田氏は関係志向的な中立性とケアを強調している。 自己決定権の尊重と平等な扱いも、調停の重要な要素として挙げられる。
1. 相互承認の重要性 対話と交渉の基盤
この節の中心は、対話促進型調停における「承認」の概念とその重要性である。 単なるレビン小林氏が述べる承認以上の、より日常的な意味での承認、つまり当事者や調停者を「人として認め、対話するために向き合うこと」が強調されている。 具体的な言動による信頼形成以前にも、人としての存在を認め合うことが対話の前提条件として不可欠であると主張する。 この「承認」は、当事者間のみならず、調停者と当事者間にも成立する必要がある。調停者が当事者の自己解決能力を信じ、当事者が調停者を信頼することが、相互承認の成立、ひいては対話と交渉の開始に繋がる。 この相互承認モデルは、図1を用いて、調停者と当事者間の承認プロセス(当事者→調停者、調停者→当事者、当事者間)を視覚的に示しており、調停開始から相互承認に至るまでの複雑な過程が示唆されている。 この相互承認が成立することで、主張・要求、利害関心、感情、関係性の各レベルでの対立が調整され、相互理解と合意形成の可能性が高まるという論理が展開されている。
2. 自己理解と他者理解 相互理解への道程
効果的な対話による相互理解に至るプロセスとして、自己理解と他者理解の重要性が強調されている。 社会的行為の理解には、現実的理解(日常的理解)と動機理解という二つの類型があり、両者のずれを解消することが相互理解への第一歩となる。 自己理解においては、「他者との関係なしに自己を理解することはできない」というパラドックスが指摘され、自己を他者化することで初めて自己理解が可能になるという難しさが示されている。 他者理解においても、「他者の理解は困難である、むしろ不可能性だと認識している人こそが他者の理解に近づくことができる」というパラドックスが挙げられ、他者の理解を深めようとする真摯な姿勢が重要視されている。 自己と他者の違いを違いとして理解し合う「相互理解」は、存在の相互承認の上に成り立つものであり、この相互承認が、対話による交渉と合意形成を可能にする基礎となる。 この節では、相互理解のプロセスにおける複雑さと難しさ、そしてその実現のための重要な要素が論じられている。
3. 調停者による 平等の扱い とケア的援助 和田氏とレビン小林氏の対照的なアプローチ
調停者の中立性と当事者への対応について、レビン小林氏と和田氏の異なるアプローチが比較検討されている。 レビン小林氏は、自己決定の相互尊重と平等の尊重を調停の基本理念として重視し、「社会的弱者」への配慮も平等な扱いの範囲内で行うべきだと主張する。 調停者は当事者を平等に扱うだけでなく、当事者自身もそのように感じることが重要であり、この「平等な扱い」への信頼が、調停者の手続き的公正さへの信頼に繋がるという。 一方、和田氏は「関係志向的」な中立性とケア的援助を重視する。中立性を戦略的に維持し、ケアの理念に基づいて当事者の自己実現を支援するアプローチをとる。 和田氏は、中立性の概念を多角的に分析し、「規範志向性」「関係志向性」「静態構造的」「過程動態的」という二つの理念軸を設定することで、従来の裁判官や弁護士とは異なる、ADRにおける調停者の役割を明確にしている。 和田氏のケア的援助は、当事者の思いを受け止め、自立的成長を支援することを重視しており、関係性の構築を重視するアプローチとなっている。両者のアプローチは対照的であるが、いずれも「納得のいく解決」を目指す対話促進型調停において重要な視点を与えている。
IV.同席調停と別席調停 実践と理念
同席調停と別席調停の使い分けは、調停の運営方法だけでなく、その理念にも関わっている。 井垣康弘氏、上原裕之氏、梶村太市氏、坂梨喬氏といった裁判官や実務家は、当事者主役の調停を推進し、同席調停を原則とするべきだと主張している。 しかし、状況に応じて別席調停も活用することで、対話を効果的に促進できる可能性も示唆されている。 調停の成功には、調停者の傾聴、共感、調整の技法などのスキルも不可欠となる。
1. 同席調停と別席調停の比較 当事者主体の調停を目指して
この節では、対話促進型調停における同席調停と別席調停(交互面接方式)のメリット・デメリットが比較検討されている。 当事者主体の調停という観点から、原則として同席方式がより適切であると主張する意見が紹介されている。 同席方式のメリットとして、「和解の透明性と公正さを格段に高めること」が挙げられており、近年、公正さを求める当事者が増加している現状を踏まえると、同席方式の重要性が強調されている。 別席方式では、調停委員会が情報を取りまとめ、当事者には情報が不透明になる可能性があるため、当事者の信頼を失わせるリスクがあると指摘されている。 一方で、同席方式では調停者が場をコントロールすることがより困難になるため、高度な調停技法が必要となることも示唆されている。 井垣康弘氏による「交渉促進型」同席調停の実践例が紹介され、同席調停の意義や成功のための条件が説明されている。上原裕之氏、梶村太市氏、坂梨喬氏といった裁判官や実務家の意見が引用され、それぞれの立場からの同席調停、別席調停への見解が示されている。
2. 当事者主役の調停と同席調停 理念と実践の整合性
「当事者主役」の調停理念との関連において、同席調停の原則化が議論されている。 当事者間の直接対話を通じた「納得のいく解決」を目指す調停においては、同席方式が原則としてより適合的だと主張する意見が示されている。 しかし、当事者間の直接対話が必ずしも「納得のいく解決」に繋がるわけではなく、調停過程で対話が膠着した場合には、別席方式を活用する必要性も指摘されている。 同席方式への移行を阻む要因として、高度な調停技法の必要性や、調停者の負担増加などが挙げられている。 梶村太市氏は、当事者権の保障という観点から同席調停の原則化を提唱している。 調停手続が司法的手続の一環である以上、公平性が不可欠であり、同席調停がその実現に資すると考えられている。 しかし、坂梨喬氏は、同席調停と別席調停の使い分け論を展開し、事件や当事者の個性に合わせて柔軟に対応する必要性を説いている。 これらの議論を通じて、同席調停と別席調停は単なる運営方法の違いにとどまらず、調停の理念にも関わる重要な要素であることが示されている。
3. 同席調停の普及を妨げる要因と解決策 高度な技法とトレーニングの必要性
この節では、同席調停の普及を妨げる要因として、高度な調停技法の習得の必要性が指摘されている。 特に、調停者が調停の場をコントロールすることが難しい同席調停においては、高度なスキルと経験が求められる。 別席調停と比較して同席調停はより高度な技法を要するため、同席調停を効果的に行うためのトレーニングの重要性が強調されている。 同席調停と別席調停の使い分けを適切に行うためには、調停者は両方の方式に対応できる実践知を備えている必要がある。 しかし、同席調停に必要な実践知の習得には、別席調停とは異なるトレーニングが必要だと主張する意見もあり、具体的なトレーニング内容や研修体制の整備が今後の課題として挙げられている。 井垣康弘氏の同席調停の組織的実践の取り組みが紹介され、調停開始前の丁寧な説明や、調停委員の役割の重要性も示唆されている。 最終的に、同席方式は対話促進型調停に適しているものの、状況に応じて別席方式も活用する柔軟な対応が重要であると結論づけている。
V.法的情報提供と対話促進型調停の両立
対話促進型調停において、法的情報の提供は対話を阻害する可能性がある一方で、当事者の「納得のいく解決」のためには不可欠な場合もある。法的情報提供の方法として、機能的統合システム(和田氏)と機能的連携システムが考えられる。 認証を受けた民間ADRでは、弁護士の助言を受けることができる制度が設けられている。裁判所における調停では、裁判官が法的情報を提供できるメリットがある。共同調停の活用も、当事者の複合的なニーズへの対応として有効な手段となる。
1. 法的情報提供の必要性 当事者の 納得のいく解決 志向への対応
この節では、対話促進型調停において法的情報提供を行うことの必要性と、その際の課題が論じられている。 まず、当事者の「納得のいく解決」志向の中には、「法的解決」志向も含まれていると指摘する。 当事者が法的解決を期待している場合、法的情報を考慮に入れなければ、対話促進型調停の理念に沿った支援を行うことすら困難になる可能性がある。 日本の法環境の現状を鑑みると、紛争当事者はADR機関に対しても裁判を補完するような法的解決への援助を期待しているため、調停において法的情報を提供する必要があると主張する。 一方、法的助言は、一方の当事者に有利に働き、他方当事者の信頼を損なう可能性があるため、対話促進型調停の理念と両立させるためには、慎重な対応が必要であるとされている。 そのため、法的情報の提供は、当事者の「納得のいく解決」に寄与するものであり、対話促進型調停の理念を損なわないよう、適切な方法で行われなければならないという点に議論が集中している。
2. 法的情報提供のシステム 機能的統合システムと機能的連携システム
対話促進型調停における法的情報提供の方法として、和田氏が提案する「機能的統合システム」と「機能的連携システム」の二つのアプローチが提示されている。 「機能的統合システム」は、対話促進機能と法的情報提供機能を一つのシステムに統合するもので、日本の現状における当事者の複合的なニーズに最も適していると考えられている。 しかし、このシステムでは、調停者が対話促進と法的情報提供の両方の役割を担う必要があり、調停者の負担増加や理念とのずれが生じる可能性も指摘されている。 これに対し、「機能的連携システム」は、対話促進と法的情報提供をそれぞれ専門の機関が担当し、連携することで対応するシステムである。 このシステムは、特に市民型調停者のように、自ら法的情報を提供できない場合に有効であり、将来的に法的情報へのアクセスが向上すれば、有力な選択肢となりうるとしている。 アメリカ社会では交渉促進型ADRと弁護士による法的情報提供が機能的に分離されているのに対し、日本社会では機能的統合システムが必要とされるという対照的な状況も示されている。
3. 具体的な法的情報提供の方法 単独調停 共同調停 そしてADR法の認証基準
具体的な法的情報提供の方法として、民間型調停における単独調停と共同調停の二つの類型が挙げられる。 単独調停は、対話促進と法的情報提供の両方の能力を持つ専門家が単独で調停を行う方式である。 一方、共同調停は、対話促進を専門とする調停者と、法的情報を提供する法専門家が共同で調停を行う方式である。 日本社会では、共同調停が当事者の複合的なニーズへの対応策として有効だとされている。 また、ADR法による認証を受けたADR機関においては、手続実施者が弁護士でない場合でも、法令適用に関する専門的知識が必要な際に弁護士の助言を受けることができる仕組みが定められている。 裁判所における調停では、裁判官が法的情報提供を行うメリットがある一方で、対話促進型調停の理念との整合性を考慮した工夫が必要とされる。 いずれの方法も、評価型調停や説得型調停に陥ることなく、当事者の自己決定を尊重しつつ、法的情報を適切に提供することが求められている。
VI.調停技法とトレーニング
レビン小林氏は、調停のスキル習得において、理念と目的の理解が重要であると強調する。 和田氏は、調停技法を「ナラティブに埋め込まれた知」と捉え、本格的な技法論を展開している。 効果的な対話促進型調停のためには、調停者の適切なトレーニングとスキルの習得が不可欠である。
1. レビン小林氏の調停トレーニング論 理念とスキルの統合
この節では、レビン小林氏の調停トレーニングに対する考え方が紹介されている。 レビン小林氏は、調停スキルの習得は比較的容易であり、数も少ないと主張する。 重要なのは、スキルを使う目的、つまり調停の理念や目的を確実に理解することだと強調する。 理念と目的が理解されていれば、スキルは練習次第で自然と身につくとされている。 スキルを理念や目的から切り離して学ぶことは非効率的だと指摘している。 この考え方は、調停技法のトレーニングを、単なるスキルの習得ではなく、調停の理念に基づいた実践的な学習として捉えていることを示している。 アメリカで開発された現代調停のスキル・トレーニングを日本に導入した先駆者としての経験に基づいた見解であり、実践的なトレーニングの重要性を改めて強調していると言える。
2. 和田氏の調停技法論 ナラティブに埋め込まれた知 としての技法
対照的に、この部分では和田氏の調停技法に対する独自の視点が示されている。 和田氏は、調停技法を「ナラティブに埋め込まれた知」と捉えている。 これは、調停技法を単なる手続きやスキルとしてではなく、具体的な紛争の文脈(ナラティブ)の中で理解し、実践していく必要があるという考え方を示している。 和田氏の技法論は、技法論そのものを批判する立場や推進する立場から距離を置き、より中立的な立場から技法のあり方を検討している点に特徴がある。 これは、調停技法を理論的に体系化するだけでなく、実践的な文脈の中でどのように活用していくかを重視するアプローチであると言える。 この節では、レビン小林氏のより実践的なトレーニング重視の考えと、和田氏のより理論的な文脈重視の考え方が対比的に示され、それぞれのアプローチの特色が浮き彫りになっている。
3. アメリカ型ADRの理念と技法の日本社会への導入 課題と展望
最後に、アメリカで発展した交渉促進型ADRの理念と技法を日本社会に導入する際の課題と展望が論じられている。 対話促進型調停を効果的に進めるためには、法的情報を当事者同席のもとで共有することが重要だとされている。 これは、当事者の「納得のいく解決」のためには、法的情報へのアクセスと理解が不可欠であることを示している。 ADR法の制定は、日本社会の「法化」状況への司法政策的応答であり、対話促進型調停の普及は、日本社会の成熟化に適合した公共政策的応答であると位置づけられている。 裁判所における調停委員のトレーニング体制の整備や、訴訟との連携強化などが、今後の課題として挙げられている。 また、同席方式と別席方式の使い分け論が近年増加傾向にあるものの、より高度な同席方式の運営技法を習得することが、使い分けを可能にする鍵になるとされている。
VII.結論 日本社会における対話促進型調停の未来
ADR法の制定や対話促進型調停の普及は、日本社会の「法化」と成熟化を反映している。 今後、紛争当事者の「納得のいく解決」志向が強まるにつれて、対話促進型調停の社会的ニーズはますます高まるだろう。 裁判所における調停の活用、調停委員のトレーニング、訴訟との連携強化など、対話促進型調停の制度化と普及のための課題が示された。
1. 対話促進型調停の普及に向けた公共政策的課題
この結論では、日本社会における紛争解決システム全体を俯瞰した上で、対話促進型調停の今後のあり方が論じられている。 最も重要な公共政策課題として、紛争当事者間の話し合いが行き詰まった際に、公正な第三者が援助する仕組みの構築が挙げられている。 対話促進型調停は、あらゆる人が必要時に利用できるよう、全国的に制度化・配置されるべきだと主張する。 既に全国に設置されている裁判所における調停を、利用者が対話促進型調停を希望する場合には、その理念と技法に基づいて運用することが期待されている。そのためには、対話促進型調停の理念と技法を実践できる調停委員の育成が不可欠であり、裁判所において、調停委員が希望すれば対話促進型調停のトレーニングを受けられる研修制度の導入が急務であると強調している。 同席方式と別席方式の使い分けが議論されているが、特に同席方式では調停者のコントロールが困難となるため、高度な運営技法の習得が重要であると指摘されている。
2. 対話促進型調停と他の紛争解決手段との連携
対話促進型調停は、紛争解決システム全体の中で適切な位置づけが求められると論じている。 これは、当事者間の相対交渉が行き詰まった際に利用可能な紛争解決支援手続きであり、訴訟との競合関係にある一方、日常的に利用できるコストの低い選択肢でもある。 対話促進型調停の効果的な活用によって、感情的対立や関係の決裂を緩和し、対話による合意形成の可能性を高めることができる。 そして、この調停が効果的に機能することで、訴訟でなければ解決できない法的争点に焦点を当てた訴訟手続きがより適切に活用される可能性が高まる。 そのため、対話促進型調停は、当事者間の相対交渉や訴訟といった他の紛争解決手段との連携の中で位置づけられる必要があると主張する。 この連携により、より包括的で効果的な紛争解決システムの構築が可能になると示唆している。
3. 家事調停における実践知の継承と今後の展望
日本における対話促進型調停の定着可能性について、家事調停における実践例が重要な示唆を与えていると強調されている。 特に、家事調停において対話促進型調停が先駆的に実践されてきたことは、今後の発展に繋がる重要な経験となる。 同席方式を中心とした実践知だけでなく、同席と別席を組み合わせた実践知、さらには別席方式を基本とした実践知からも学ぶべき点が多いと指摘されている。 現代社会の成熟化と「納得のいく解決」志向の強まりにより、対話促進型調停へのニーズは今後ますます高まると予想される。 1990年代後半からのレビン小林氏の著作や調停トレーニングを通して、アメリカ型現代調停の理念と技法が日本に導入され、家事調停における当事者主役型の調停論にも影響を与えていると分析している。 結論として、対話促進型調停の理念と技法を実践できる調停委員の増加、そして調停と訴訟の連携強化が、今後の重要な課題として挙げられている。
