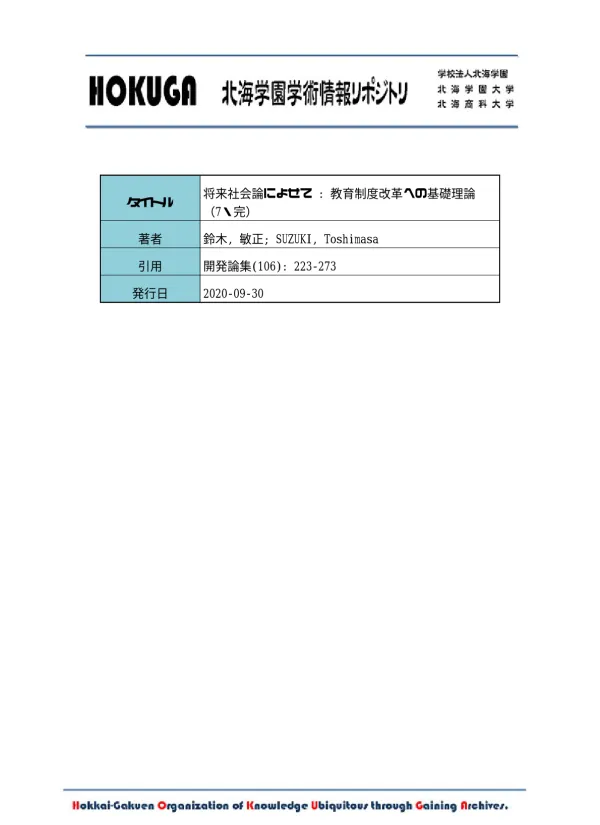
将来社会論:脱成長と教育改革
文書情報
| 著者 | 鈴木 敏正 |
| 専攻 | 教育学, 社会学, 未来学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.45 MB |
概要
I.脱成長の可能性と将来社会論 持続可能な開発への問い
本稿は、脱成長 (degrowth) 論を起点に、将来社会論 (future society theory) の課題を検討する。持続可能な開発 (sustainable development) 批判を含む脱成長論は、近代資本主義を超えた人類史的視点から定常型社会 (steady-state society) を目指す。ハラリ (Harari) の『未来を読む』、『サピエンス全史 (Sapiens)』における未来への警告(核戦争、地球温暖化、テクノロジーによる破壊)と、ダイアモンド (Diamond) の『文明崩壊』における文明崩壊の環境要因分析を踏まえ、エコ社会主義 (eco-socialism) や共産主義 (communism) の実現可能性を議論する。
1. 脱成長論と持続可能な開発への批判
本稿は、最も包括的な問題領域である「脱成長」を起点に将来社会論の課題を検討する。脱成長論は、近代や資本主義を超えた人類史的視点から未来社会としての「定常型社会」を目指し、「持続可能な開発(Sustainable Development, SD)」論への批判を含んでいる。そのため、SDやESD(Education for Sustainable Development)の位置づけを見直す必要があると主張している。脱成長社会の実現に向けて、これまでの将来社会論の再考と、新たな視点からのアプローチが求められると示唆している。
2. ハラリの未来予測と現代社会への警鐘
ユヴァル・ノア・ハラリ(Harari)の『未来を読む』と『サピエンス全史』からの引用を通して、現代社会が直面する危機が分析されている。ハラリは、核戦争、地球温暖化、テクノロジーによる破壊という3つの脅威を挙げ、特にテクノロジーの進歩による「役立たず階級」の増加を懸念している。また、現代人が失いつつある能力を取り戻すために狩猟民族に学ぶ必要性を主張し、環境への適応と五感の鋭敏さを重要視している。ハラリは学者としての使命を「危険な可能性を含む様々な可能性を示すこと」と定義し、それに対する行動を個々人に求めているが、具体的な解決策は提示していない点が特徴的である。
3. ダイアモンドの文明崩壊論と環境問題
ジェレミ・ダイアモンド(Diamond)の『文明崩壊』(2005年)における文明の盛衰分析が紹介されている。ダイアモンドは、イースター島、マヤ文明、ヴァイキング、グリーランドなど、過去の文明崩壊の主原因を環境破壊にあると指摘。現代社会が直面する環境問題を、天然資源の破壊・枯渇、天然資源の限界、有害物質、人口問題などに分類している。彼は「慎重な楽観主義者」として、深刻な問題でも解決不可能ではないこと、環境保護思想の普及、グローバル化による連結性の高まりを希望の根拠として挙げ、過去からの教訓を活かすことの重要性を強調している。日本の歴史における森林管理の成功例も紹介され、持続可能な社会の実現可能性が示唆されている。
4. アーリの気候問題分析と社会的問題への拡張
本書では、J.アーリによる気候問題の分析が紹介されている。アーリは気候問題を未来志向の問題として捉え、学際的な研究と理論の必要性を強調している。気候の未来像として「現行ビジネス」「脱成長」「エコロジー的近代化」「ジオエンジニアリング」などを挙げ、さらに「人間種の本質における変化の可能性」という厄介な問題も提示している。 アーリは「すべてを変える」必要があると主張し、民主主義的な未来志向の展開と実践が重要であると結論付けているものの、脱成長の将来像については具体的な提示はない。
II.経済成長の限界と人間の欲望 脱成長への道筋
コーエン (Cohen) は、人類史における経済成長 (economic growth) の源泉を分析し、その「中毒」からの脱却を課題とする。経済成長の持続不可能性、労働強化と気候変動リスクによる「トライアングルの地獄」(失業、ストレス、環境危機)を指摘し、人間の精神構造(競争と妬みの文化)の変革を必要とする。脱成長 (degrowth) 社会においては、アソシエーション (association) やコミュニティ (community) が重要となる。
1. 経済成長の源泉と人類史
コーエンは、前著『経済と人類のX万年史から、21世紀世界を考える』を踏まえ、「経済成長の源泉」を人類史という広大な視点から再考している。ハラリが『サピエンス全史』で示した認知革命・農業革命・科学革命という人類史観を踏襲しつつ、コーエンは「集団のインテリジェンス」の発展、つまり人類が集団で学び、知識を蓄積・拡散してきた技術(文字、貨幣からインターネットまで)に着目する。さらに、文化=「禁忌と分類をつくり出す能力」にも注目し、その中で人間は「自分は何者か、何のために生きるのか」という問いを発する存在だと説く。この視点から、現代の経済成長は人類史における長い熟成の産物であり、その「中毒」と脱却が本書の主題となる。
2. 経済成長の限界と トライアングルの地獄
コーエンは、「現代社会は経済成長なしで持続できるか」「経済は再び成長するか」という2つの問いを提示し、どちらも否定的な見解を示す。現代社会が問題解決の手段として経済成長を採用している現状を批判し、その原動力が労働強化と気候変動リスクであることを指摘する。その結果として、「トライアングルの地獄」と呼ばれる、①失業と雇用不安、②精神的なストレス、③環境危機という3つの問題が深刻化していると主張する。根本的な解決には、競争と妬みの文化といった人間の精神構造の変革が必要であり、個人の思いと社会的な欲求の一致が精神構造の変化をもたらすと考察している。
3. 脱成長社会における社会構造と課題
経済成長に依存しない社会のあり方として、「社会的族内婚」や「商品よりも社会的なつながりを消費する社会」の存在様式が想定される。しかし、こうした社会構造は「社会的閉所恐怖症」や、スケープゴートとしての外国人排斥などの問題を生み出す可能性も指摘されている。コーエンは、このような状況からの脱却のため、「寛容や他者の尊重」という別の道筋を歩む必要性を説き、そのための必要条件を提示している。それは、経済成長の不確実性への免疫力をつけること、経済成長が公的支出に必須という考えを放棄すること、そして、寛容や他者の尊重を社会基盤とすること、である。
III.生産的労働と活動社会への移行 労働の解放と生活の芸術化
飯盛信男の生産的労働論を基に、サービス・情報産業拡大期におけるマルクスの生産的労働体系的把握を再考する。ラトゥーシュ (Latouche) の脱成長プログラム(生産抑制、エネルギー消費削減、宣伝広告制限など)は、持続可能な発展 (sustainable development) 論やオルター・グローバリゼーション運動と部分的に合意可能である。トフラー (Toffler) の「第三の波」やシュー (Schumacher) の「労働から活動 (activity) へ」の移行論、アーレント (Arendt) の労働・仕事・活動の区別、そしてゴルツ (Gorz) の「楽しい労働」論、モリス (Morris) の「生活の芸術化」論を踏まえ、「労働の解放」と「活動社会」への移行を探求する。
1. 生産的労働の体系的把握と資本主義批判
飯盛信男によるマルクスの「生産的労働の体系的把握」の試みが紹介されている。飯盛は、サービス産業や情報産業の拡大期において、生産的労働を①自然と人間間の物質代謝、②資本の価値増殖、③社会的再生産、④国家機構の担い手という4つの観点から分析。生産的労働論は、人間生活における労働の機軸的位置を示し、労働生産力の成果が資本によって横領される資本主義の矛盾を批判するとともに、労働解放の必然性と階級が廃絶された真の社会の未来像を示していると結論づけている。この生産的労働論は、技術主義的な経済理論や情報化社会論に対する有効な批判となりうるとしている。
2. ラトゥーシュの脱成長プログラムと政策提言
セルジュ・ラトゥーシュ(Latouche)の脱成長に関する10の政策提言が紹介されている。ラトゥーシュは、5つの再生プログラムを「ユートピア」と位置づけ、10の政策提言を実践レベルと捉えている。脱成長への道筋を、世界の西洋化への抵抗とグローバル化した消費社会からの離反と定義し、簡素な生活と欲求の抑制に基づく文明構築を目指している。具体的な政策提言としては、生産の抑制、エネルギー消費の削減、宣伝広告の制限、科学技術研究の方向転換、貨幣の再領有化などが挙げられており、持続可能な発展論やオルター・グローバリゼーション運動、連帯経済論と部分的に合意できる点もあると分析している。
3. 労働社会から活動社会へ アーレントとシューマッハの視点
アルビン・トフラー(Toffler)の「第三の波」における「消費のための生産」と「自分のことは自分で」という生活態度の広まり、そしてE.F.シューマッハ(Schumacher)の「労働から活動(activity)への移行」論が紹介されている。シューマッハは生産様式を「労働−商品供給−商品生産」から「専門能力−社会的需要−相互サービス」への移行と捉えている。 さらに、ハンナ・アーレント(Arendt)の労働・仕事・活動の3区分に基づき、NRIが「労働社会から活動社会へ」の移行を提起したことが述べられている。アーレントのギリシャ文明とローマ文明の文化論における違い、特にローマ人が重視した自然との関わりも考慮する必要があると指摘されている。
4. 労働の解放と生活の芸術化 ゴルツとモリスの思想
アンドレ・ゴルツ(Gorz)の『労働のメタモルフォーゼ』における「楽しい労働」「魅力的労働」論と、マルクスの「労働の解放」論が議論されている。ゴルツは、マルクスの「労働のなかでの解放」という考え方を「根拠のないユートピア」と批判し、時間解放による人間の自由な開花は、政治的意志と倫理的希求を土台にする必要があると主張。ゴルツは「3種類の労働」(経済的目的の労働、家事労働、自律的活動)を区別し、自律的労働を「活動」と捉え、芸術、哲学など人間を開花させる活動の重要性を強調する。ウィリアム・モリス(Morris)の「生活の芸術化」論も紹介され、労働から仕事、そして芸術への移行、自己実現と相互承認の領域拡大が議論される。モリスの「勝ち取られた社会主義」論における「労働を喜びに」という思想が、コミュニティとアソシエーションの活性化につながると分析されている。
IV.ユートピアと現実主義 将来社会への展望
ジェイムソン (Jameson) の「ユートピア的想像力」論と、バスカー (Baskir) の弁証法的社会哲学研究から、ユートピア (utopia) 社会主義と無政府主義運動の再検討を行う。マルクスの将来社会構想(自由な個人の協同組織:アソシエーション (association))と、平子友長、尾関周二、大谷禎之助らのマルクス主義的解釈を踏まえ、社会主義 (socialism) 到達のための多様な道を提示する。ブクチン (Bookchin) の「合理的でエコロジカルな社会」への展望、長島のエコロジカル社会主義、オコーナー (O'Connor) の「維持可能な社会」論、宇沢弘文と内橋克人の「社会的共通資本 (social common capital)」論、コヴェル (Kovel) のエコ社会主義などを検討する。
1. ユートピア思想の再評価とジェイムソンの視点
この節では、F. ジェイムソン(Jameson)の『未来の考古学』(2005年)を参考に、ユートピア思想の再評価が試みられている。ジェイムソンは、従来のユートピア社会主義だけでなく、ギリシャ・ローマ演劇から現代のSF・映画まで、広範な「ユートピア・ジャンル」を考察し、「ユートピア的想像力」の今日的役割を提起する。「反ユートピア主義に反対」というスローガンが、グローバリゼーション時代の左翼(旧左翼・新左翼、社会民主主義急進派、世界各地の文化的少数派など)に広がるユートピア的スローガンの現実的な政治的役割を示していると主張。ユートピア政治の本質を「同一性と差異の弁証法」と捉え、既存システムとは根本的に異なるシステムの創造を目標とする。
2. 弁証法と具体的ユートピア主義 マルクスとモリスの将来社会像
バスカー(Baskir)の弁証法的社会哲学研究が紹介され、弁証法を「自由の弁証法」として捉え、「エウダイモニア(幸福)社会」を目指す将来社会論が展開されている。バスカーは、従来のマルクス主義がヘーゲル的弁証法を適切に発展させられなかったと批判し、W. モリス(Morris)的な「建設的な具体的ユートピア主義」の必要性を主張。マルクスの『共産党宣言』における共産主義社会像「各人の自由な発展が万人の自由な発展の条件となる結合社会(Assoziation)」が引用され、マルクスの『経済学批判要綱』、『資本論』における歴史観(人格的依存関係→物象的依存→自由な個人性)と関連付けて説明されている。社会主義に至る多様な道、特に晩期マルクスの農業共同体への関心、そして「自由な労働者の協業」や「アソシエートした労働の生産様式」が将来社会の鍵となるとされている。
3. モリスの 勝ち取られた社会主義 と生活の芸術化
ウィリアム・モリス(Morris)とE.ベル・バックス(Bax)の共著『社会主義─その成長と帰結─』における「勝ち取られた社会主義」論が分析されている。モリスは、マルクスの『資本論』の分析を踏まえつつ、ユートピア的社会主義を批判し、「科学的社会主義」を対置する。 モリスの将来社会像は、労働に起因する喜びの増大、労働時間の短縮、職種変更の自由、機械化による負担軽減、能力に応じた職業選択などから成り、建築、絵画、演劇、音楽などの芸術活動が重要な役割を果たすとされている。「生活の芸術化」という概念が強調され、都会と田舎の対立解消も提起。モリスの思想は、コミュニティとアソシエーションの両輪による社会システム構築を目指している。
4. エコロジカル社会主義と持続可能な社会 現実主義的アプローチ
本書では、ムック・ブクチン(Bookchin)のエコロジカルな社会への展望、長島によるエコロジカル社会主義の理論的基礎(資本の過剰生産と自然の過少生産)、オコーナー(O'Connor)の「維持可能な社会」論などが紹介される。オコーナーは、「維持可能な社会(Preservation First!)」において、労働がコミュニティ・環境・社会生活の増殖を目的とする自発的なものになると主張し、長島の解釈ではマルクスの展望と一致するとされている。宮本憲一の「内発的発展論」や、宇沢弘文と内橋克人の「社会的共通資本」論も関連付けて議論され、日本の地域づくり運動(菜の花プロジェクトなど)が事例として挙げられている。 一方、グレイによる現実主義的なユートピア批判、そして、現実とユートピアの両面を踏まえた将来社会論の必要性が提示される。
V.AIと労働 近代労働観の再考とポスト都市共生
稲葉はAIと労働の関係を古典的な機械化と雇用の問題の枠組みで分析する。マルクスの資本主義的「機械工業の原理」に基づき、AI機械を固定資本、労働力を可変資本と捉え、管理労働の問題を検討する。ハーバマス (Habermas) やアーレント (Arendt) の労働観批判、そして「労働社会から活動社会へ」の移行を、モリス (Morris) の「勝ち取られた社会主義」論や、吉原直樹の「ポスト都市共生」論と関連付けて考察する。マンフォード (Mumford) の「住民の知的参加」と持続可能で包容的な地域づくり教育 (Education for Sustainable and Inclusive Communities, ESIC) の重要性を強調する。
1. AIと労働 近代労働観の再考
稲葉は、AIが労働・雇用に与えるインパクトを、「経済学と機械という古くて新しい問題」として捉える。コンピュータからAI導入に至る議論は、西欧マルクス主義的な「労働の衰退」と「技能変更型技術変化」論の接近を示していると分析。AIのインパクトは、①劇的な労働生産性向上による所得増大で雇用減を相殺できるか、②その成果の分配が格差拡大につながるか、という2点に集約されるとする。つまり、古典的な「機械化と雇用の問題」の枠組み内にあると位置づける。しかし、稲葉の主張は技術主義的な側面を免れておらず、AI導入企業の労働現場の具体的な検討が必要だと指摘。マルクスの「機械工業の原理」に基づき、AI機械を固定資本、労働力を可変資本と捉え、管理労働の分析の必要性を強調する。
2. マルクス主義的労働観への批判と 活動 の重要性
マルクス主義的理解における労働重視の視点に対する批判として、J. ハーバマスの「相互行為(コミュニケーション的行為)」の強調、尾関周二の「労働と言語的コミュニケーション」の統一的把握の必要性が言及される。ハンナ・アーレント(Arendt)のマルクス批判も紹介され、アーレントは人間を「労働する動物」と捉えるマルクスの側面を批判し、「活動(action)」の重要性を強調する。アーレント研究会による労働(labor)、仕事(work)、活動(action)の3区分が紹介され、アーレントはマルクスが労働と仕事を混同したと指摘、仕事には全体主義につながる危険性があると主張している。対照的に、アーレントは自由で平等な状況での協同生活、相互承認に基づく話し合い、祭りや演劇などの「活動」こそが人間を人間たらしめるものだとする。
3. 労働から活動へ 生産様式の変化とポスト都市共生
アルビン・トフラー(Toffler)の「第三の波」論、E.F.シューマッハ(Schumacher)の「労働から活動へ」の移行論、そしてアーレントの3区分を踏まえ、「労働社会から活動社会へ」の移行が議論される。シューマッハは生産様式を「労働−商品供給−商品生産」から「専門能力−社会的需要−相互サービス」への移行と捉えている。NRIによる「労働社会から活動社会へ」の移行論も紹介され、アーレントの芸術理解におけるギリシャ文明とローマ文明の違い、ローマ人が重視した自然との関わりも考慮されるべきとされる。 さらに、稲葉によるAIと労働に関する議論、そしてマルクスの「自由な個人の協同組織(Assoziation)」という将来社会構想が紹介され、アーレントのマルクス批判の妥当性も検討されている。 吉原直樹の「ポスト都市共生」論は、近代的主体を超えた複合的な主体、創発性と接合の機制、ローカルなコミュニティを重視した都市の未来像を示している。
