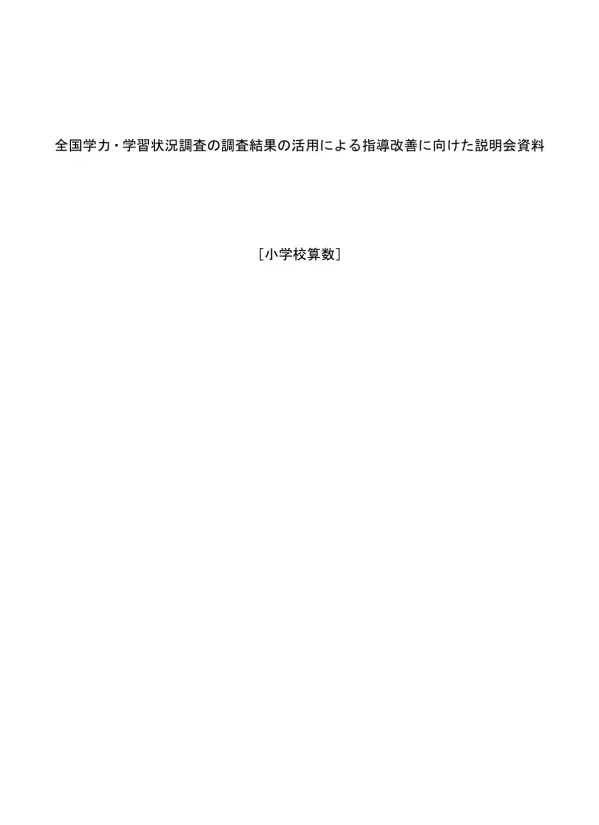
小学校算数:4年間の調査結果から見る指導改善
文書情報
| 専攻 | 小学校算数 |
| 文書タイプ | 説明会資料 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 3.06 MB |
概要
I.全国学力 学習状況調査結果を活用した小学校算数の指導改善
本資料は、過去4年間の全国学力・学習状況調査(特に小学校算数)の結果を分析し、指導改善のためのポイントを提示しています。特に、正答率が70%を下回った問題、および誤答の分析に重点が置かれています。記述式問題における課題と、その改善策が詳細に検討されています。割合や面積などの計算問題、および数量関係に関する理解度が分析されています。具体的な課題として、計算の順序の理解、図形の性質の活用、割合の意味の理解などが挙げられ、それぞれの課題に対する効果的な授業アイディア例が提案されています。
1. 4年間の調査結果から明らかになった小学校算数の課題
このセクションでは、平成19年度から22年度までの4年間の全国学力・学習状況調査の結果を分析し、小学校算数における課題を明らかにしています。正答率が70%を下回った問題を中心に、複数の年度にわたって類似の問題が出題されている点を踏まえ、課題を領域別に整理しています。具体的な課題としては、計算問題における計算の意味理解、計算の仕方、計算の習熟度、図形問題における図形の性質の理解と活用、記述式問題における論理的思考力や数学的表現力の不足などが挙げられています。これらの課題に対して、小学校学習指導要領解説算数編を参考に、学習指導のポイントが示されています。例えば、計算問題においては、「倍」という表現を含む文章題における基準量の特定、数直線や図を用いた数量関係の把握、簡単な数への置き換えによる問題解決などが挙げられています。図形問題においては、図形の性質に基づいた面積の求め方、情報過多な場面での必要な情報の抽出などが課題として示され、それぞれに対応した指導方法が提案されています。記述式問題に関しては、問題解決のプロセスを説明する能力の育成が重要視されています。
2. 計算問題に関する課題と指導改善のポイント
このセクションでは、計算問題、特に乗法と除法の意味理解、計算の順序、混合計算に関する課題が詳細に分析されています。各学年の学習内容に「計算の意味について理解すること」が明記されていることを踏まえ、乗法と除法の意味理解を2年生と3年生から系統的に指導する必要性が強調されています。調査結果からは、計算の順序についてのきまりを理解して計算すること、言葉の式を読み取り計算結果の大小を判断し根拠を説明すること、示された解決方法を理解し別の問題に応用できる能力に課題があることが示されています。指導改善のポイントとして、計算の順序についてのきまりを理解させ、最初に考えた式に括弧を書き加えて正しい式に修正する能力の育成、具体的な場面に対応させながら事柄や関係を式に表すこと、式を通して場面の意味を読み取り、言葉や図を用いて表現する能力の育成などが挙げられています。また、四則演算が混合したり括弧が使われたりする計算を確実にできるようにすること、計算の順序についてのきまりに従って計算することの重要性を理解させることなどが重要視されています。
3. 図形問題に関する課題と指導改善のポイント
このセクションでは、図形問題、特に面積を求める問題における課題が分析されています。過去4年間の調査結果から、問題解決に必要な情報を適切に選択したり、見いだしたりする能力、図形の性質を基に統合的・発展的に考える力の弱さが明らかになっています。具体的には、地図上に複数の図形があり、必要な情報を取り出して面積を比較し、説明することに課題があること、方眼上の高さが外にある三角形の面積を求めること、円の求め方を基に半円の面積の求め方を表す式を読み取ることに課題があること、三角形や長方形、四角形に関する面積の求め方やその関係性を理解することに課題があることなどが指摘されています。指導改善のポイントとして、図形の性質を基に面積の関係を捉える活動、既に分かっていることと新しい事柄との関係を把握する活動、情報過多の場面を提示し、面積を求めるために必要な情報を取り出す活動、直感的に図形を見いだしたり、図形の定義や性質を根拠に筋道を立てて図形を見いだしたりする活動などが挙げられています。小学校学習指導要領解説算数編の内容に基づき、図形の性質を見いだし、それを用いて図形を調べたり構成したりする能力の系統的な育成が強調されています。
4. 記述式問題に関する課題と指導改善のポイント
このセクションでは、記述式問題における課題とその指導改善のポイントについて述べられています。記述式問題の平均正答率が低いことから、言葉や数、式、図、表、グラフなどを用いて筋道を立てて説明したり、論理的に考えたりする能力の不足が指摘されています。特に、「事実」や「理由」を記述する問題において、説明する対象を明確にし、理由と結論を明確に述べること、複数の理由がある場合は全て記述することなどが重要です。指導改善のポイントとして、解答類型に基づいた児童の実態把握と、活用の観点に基づいた指導の工夫が挙げられています。解答類型に基づいた実態把握では、正答、予想される誤答・無解答を分類し、児童の解答状況を詳細に把握することで、きめ細やかな指導を行う必要性が示されています。活用の観点に基づいた指導の工夫では、物事を数・量・図形などに着目して観察し的確に捉えること、与えられた情報を分類整理したり必要なものを適切に選択したりすること、筋道を立てて考えたり振り返って考えたりすること、事象を数学的に解釈したり自分の考えを数学的に表現したりすることなどが重要視されています。
5. 割合に関する課題と指導改善のポイント
このセクションでは、割合(百分率)に関する課題と指導改善のポイントについて述べられています。過去4年間の調査結果から、割合の意味理解が弱いことが明らかになっています。割合が一定の場面で、比較量が最も大きくなるときの基準量を判断し、その理由を言葉や式を用いて記述することに課題があることが示されています。指導改善のポイントとして、百分率の意味を理解し、数量の関係を捉えて立式できるようにすること、日常生活の場面で百分率を用いて問題を解決する活動を通して、百分率の意味の理解を深めること、割合の学習では、比較量が、基準量と割合の積で決まることを理解できるようにすること、比較量の大小は、割合だけで決まるのではなく、基準量と割合の二つによって決まるという見方ができるようにすることが挙げられています。基準量と比較量の両方に着目して、割合の大小を判断する活動や、割引券を使うと値引きされる金額が最も大きくなる商品を選んだ理由を説明するために、説明に必要な事柄を考える活動などが具体的な授業アイディア例として提示されています。
II.計算問題における課題と指導改善
小学校算数における計算問題、特に乗法と除法の意味理解、計算の順序、混合計算に関する課題が指摘されています。平成19~22年度の調査結果から、計算の意味を理解し、計算の仕方を考えること、計算に習熟し活用できる能力の育成が重要であると結論づけられています。誤答分析に基づき、計算の順序に関するきまりを理解させるための指導法が提案されています。具体的な授業アイディア例として、簡単な数への置き換え、数直線や図の使用などが挙げられています。
1. 計算の意味理解と計算の習熟
このセクションでは、小学校算数における計算指導の目的として、計算の意味理解、計算の仕方の工夫、計算の習熟と活用が重要であると述べられています。特に「計算の意味について理解すること」は、乗法(2年生から)と除法(3年生から)の学習において重要な要素であり、各学年の内容に明記されているとされています。そのため、乗法や除法の意味理解は、2年生と3年生から系統的に指導する必要があると強調されています。過去4年間の調査結果を踏まえ、計算指導において工夫改善が必要な重点事項として、「倍」という表現を含む文章題から基準量を特定し数量関係を捉えること、数直線や図を用いたり具体的な場面に当てはめたりして数量関係を捉えること、簡単な数に置き換えて数量関係を考える活動を取り入れることが挙げられています。これらの活動を通して、児童が自ら問題を解決できる能力を育成することが重要であるとされています。
2. 計算の順序と混合計算
この部分では、計算の順序、特に加法と乗法が混合した計算における課題が示されています。平成19年度の調査問題(A1(7))では、正答率が69.1%と低く、計算の順序についてのきまりを理解して計算することに課題があることが明らかになっています。誤答分析によると、式の左から順に計算している解答が13.3%存在し、計算の順序のきまりを意識せずに計算している児童がいることがわかります。そのため、計算の順序についてのきまりを理解させ、最初に考えた式に括弧を書き加えて正しい式に修正する能力の育成が重要となります。また、言葉の式を読み取り、式の形に着目して計算結果の大小を判断し、その根拠を明確に説明する能力、示された解決方法を理解し、それを用いて別の問題を解く能力についても課題が見られます。これらの課題を解決するために、四則演算が混合したり、括弧が用いられたりする計算を確実にできるようにすること、計算の順序についてのきまりに従って計算することの重要性を理解させること、括弧を用いることで数量の関係をひとまとまりとして表せるよさを理解させることが重要だとされています。
3. 式の指導における留意点と系統的指導の必要性
計算問題に関する指導改善策として、式の指導における具体的な方法が示されています。具体的な場面に対応させながら、事柄や関係を式に表せるようにする、式を通して場面などの意味を読み取り、言葉や図を用いて表現したり、式で処理したり考えを進めたりする能力を育成する、式を言葉、図、表、グラフなどと関連付けて用いて自分の考えを説明したり、分かりやすく伝え合ったりできるようにするなどが重要だとされています。計算の順序などのきまりについての学習は4年生で行われますが、式の表現と読みについては1年生から系統的に指導を充実させることが大切だと強調されています。小学校学習指導要領解説算数編「2算数科の内容 数量関係」において、「式の表現と読み」は第1学年から系統的に指導されるようになっていることを踏まえ、四則が混合したり、括弧が用いられたりする計算を確実にできるようにするための指導の重要性が改めて示されています。問題作りの場面で作った問題を吟味して修正する活動や、四則の混合した様々な計算をする機会を継続して設けることも提案されています。
III.図形問題における課題と指導改善
面積を求める問題において、必要な情報を選択したり、図形の性質を基に統合的・発展的に考えたりする力の弱さが課題として挙げられています。特に、地図上の複数の図形から必要な情報を取り出すこと、三角形や四角形の面積計算、図形の性質に基づいた判断と説明に課題が見られました。誤答分析から、情報過多の場面での問題解決能力の育成が重要視され、図形の性質を理解させ、問題解決に必要な情報を適切に選択する活動の充実が提案されています。具体的な授業アイディア例も提示されています。
1. 面積を求める問題における課題
このセクションでは、面積を求める問題における児童の課題が分析されています。過去4年間の全国学力・学習状況調査の結果から、問題解決に必要な情報を適切に選択・抽出したり、図形の性質を基に統合的・発展的に考えたりする力が弱いことが指摘されています。具体的には、地図上に複数の図形が描かれ、必要な情報を取り出して面積を比較・説明する問題、方眼上の高さが図形の外にある三角形の面積を求める問題、円の面積の求め方を基に半円の面積の求め方を表す式を読み取る問題、三角形から長方形、長方形から四角形へと図形を変形させ、図形の性質に基づいて面積の関係を捉え、判断の理由を説明する問題などにおいて、正答率が低いことが課題として挙げられています。これらの問題を通して、児童は図形を正確に捉え、必要な情報を適切に選択し、論理的に説明する能力が不足していることが示唆されています。特に、複数の図形から必要な情報を取り出す能力、図形の性質を理解し、面積計算に応用する能力、図形を変化させながら面積の関係性を捉える能力の向上が求められています。
2. 情報の選択と図形の性質の理解
面積問題における課題をより詳細に分析すると、問題解決に必要な情報を適切に選択したり、見いだしたりする能力の低さが浮き彫りになっています。多くの面積問題は、解決に必要な情報のみが提示されていますが、過去4年間の調査結果からは、問題解決に必要な情報を選択・抽出する力が弱いことが明らかになっています。さらに、図形の性質を基に、統合的・発展的に考える力も弱いことが示されています。これは、図形の定義や性質を理解し、それを問題解決に活用する能力が不足していることを意味します。例えば、複雑な図形の問題において、図形を単純な図形に分解して考える能力、図形の性質を利用して面積を効率的に求める能力、複数の図形を比較検討する能力などが不足している可能性が考えられます。これらの能力を向上させるためには、図形の性質を基に面積の関係を捉える活動、既に分かっていることと新しい事柄との関係を把握する活動などを授業に取り入れることが重要です。
3. 指導改善のための授業アイディア例と学習指導要領との関連
図形問題における課題解決に向けた具体的な授業アイディアが提案されています。情報過多の場面を提示し、面積を求めるために必要な情報を取り出す活動、直感的に図形を見いだしたり、図形の定義や性質を根拠に筋道を立てて図形を見いだしたりする活動などが挙げられています。これらの活動を通して、児童は問題解決に必要な情報を効率的に選択・活用する能力を育成することができます。また、小学校学習指導要領解説算数編(第5学年C(1)ウ)で、「図形の性質を見いだし、それを用いて図形を調べたり構成したりすること」が明記されていることを踏まえ、図形の性質に基づいた事象の判断能力を3年生と4年生から系統的に指導していくことの重要性が強調されています。具体的には、具体物を用いた操作を振り返り、操作の数学的な意味を理解する活動、問題解決の根拠となる図形の性質を判断する活動、与えられた条件や図形の定義、性質を基に、事象から見いだした図形を判断し、その理由を選択する活動などが有効だとされています。これらの指導法を通して、児童は図形問題への対応能力を高めることができると考えられます。
IV.記述式問題における課題と指導改善
記述式問題の平均正答率が低いことから、数量や図形、数量関係を考察し、筋道を立てて説明する能力の不足が指摘されています。「事実」や「理由」を記述する問題において、論理的思考力や数学的表現力の向上が課題です。誤答分析を通して、児童の思考過程を理解し、適切な言語活動を授業に取り入れる必要性が強調されています。問題解決に必要な情報を整理・選択し、筋道を立てて考え、その過程を説明する指導法の改善が求められています。具体的な授業アイディア例も提示されています。
1. 記述式問題における課題 平均正答率の低さとその要因
このセクションでは、全国学力・学習状況調査における記述式問題の平均正答率が低いという課題が取り上げられています。過去4年間の平均正答率は35.5%と低く、大きな課題であることが示されています。この低正答率の背景には、算数科において言葉や数、式、図、表、グラフなどを用いて筋道を立てて説明したり、論理的に考えたり、自ら納得したり、他者を説得したりする能力の不足が考えられます。記述式問題は、「数量や図形、数量関係を考察して見いだした事実を確認したり説明したりすること」、「問題を解決するために見通しをもち、筋道を立てて考え、その考え方や解決方法を説明すること」、「論理的に考えを進めてそれを説明したり、判断や考えの正しさを説明したりすること」といった、算数科で大切にしたい学習活動に基づいて設定されています。しかし、これらの能力が十分に育成されていないことが、記述式問題の低正答率に繋がっていると推察されます。具体的な問題例として、判断の正しさを説明する問題において、理由の説明が不十分な解答が25.3%と最も多かったというデータが示されています。これは、理由として必要な事柄をもれなく示し、理由と結論を明確にして述べる能力の不足を示唆しています。
2. 記述式問題の類型と解答状況の分析
記述式問題は、「事実」を記述する問題と「理由」を記述する問題に大別できます。「事実」を記述する問題では、計算の性質、図形の性質や定義、数量の関係、表やグラフから見いだせる傾向や特徴などの記述が求められます。一方、「理由」を記述する問題では、ある事柄が成り立つ理由や判断の理由の記述が求められ、「AだからBとなる」というように、理由と結論を明確に記述することが重要です。複数の理由がある場合は、それら全てを記述する必要があります。全国学力・学習状況調査では、児童の解答状況を分析するために、正答、予想される誤答・無解答を分類し、最大で10の類型を設定しています。指導改善に当たっては、解答類型に基づいて児童の解答状況を詳細に把握し、きめ細やかな指導の方策を考える必要があります。正答・誤答の解答状況を基に、児童の問題や内容に対する理解の程度を把握したり、正答例の記述を参考にしたりして、日々の授業に計画的・継続的に言語活動を位置付けることが大切です。 記述式問題の作成においては、「物事を数・量・図形などに着目して観察し的確に捉えること」、「与えられた情報を分類整理したり必要なものを適切に選択したりすること」、「筋道を立てて考えたり振り返って考えたりすること」、「事象を数学的に解釈したり自分の考えを数学的に表現したりすること」といった観点を重視しています。
3. 指導改善のポイント 実態把握と言語活動の充実
記述式問題における課題を改善するためには、解答類型に基づいた実態把握と、活用の観点に基づいた指導の工夫が重要です。解答類型に基づいた実態把握では、児童の解答状況を詳細に分析し、個々の児童の理解度や誤答のパターンを把握することで、より効果的な指導を行うことが期待できます。誤答の解答状況を基に、児童の問題や内容に対する理解の程度を把握したり、正答例の記述を参考にしたりすることで、日々の授業に計画的・継続的に言語活動を位置付けることが大切です。活用の観点に基づいた指導の工夫としては、問題解決に必要な情報を整理・選択し、筋道を立てて考え、その過程を説明する能力の育成が挙げられます。これは、算数科の学習において、言葉や数、式、図、表、グラフなどを用いて、筋道を立てて説明したり論理的に考えたりする能力を育成することに繋がります。記述式問題を通して、児童が自身の考えを明確に表現し、論理的に説明する能力を高めることが重要であり、そのためには、日々の授業の中で、言語活動の機会を積極的に設けることが不可欠です。 具体的には、問題作りの場面で、作った問題を吟味して修正する活動などが有効です。
V.割合に関する課題と指導改善
割合(特に百分率)の意味理解の不足が、全国学力・学習状況調査の結果から明らかになっています。基準量、比較量、割合の関係を理解し、日常生活の問題に応用できる能力の育成が重要です。誤答分析に基づき、割合の概念を理解させ、数量関係を捉えて立式できるようにする指導法が提案されています。百分率を用いた問題解決を通して、割合の意味を深める活動の重要性が強調され、具体的な授業アイディア例が提示されています。
1. 割合の意味理解の不足と具体的な課題
このセクションでは、全国学力・学習状況調査の結果から明らかになった、割合(百分率)の意味理解に関する課題が取り上げられています。過去4年間の調査結果から、割合の意味理解が弱いことが指摘されています。具体的には、割合が一定の場面で、比較量が最も大きくなるときの基準量を判断し、その理由を言葉や式を用いて記述する問題において、正答率が低いという結果が出ています。これは、基準量、比較量、割合の三者の関係を正確に理解し、それらを活用して問題を解決する能力が不足していることを示唆しています。また、割引券を使った場面で、値引き額が最も大きくなる商品を選び、その理由を説明する問題でも同様の課題が見られます。これらの問題を通して、児童は割合の概念を理解し、それを用いて数量の関係を捉え、論理的に説明する能力に課題を抱えていることがわかります。単純な割合の計算はできても、具体的な場面で割合の概念を応用し、問題解決に繋げる能力の育成が重要であることが示されています。
2. 割合に関する指導改善のポイント 百分率の意味理解の深化
割合に関する指導改善のポイントとして、百分率の意味を理解し、数量の関係を捉えて立式できるようにすること、日常生活の場面で百分率を用いて問題を解決する活動を通して、百分率の意味の理解を深めることが挙げられています。 割合の学習においては、比較量が、基準量と割合の積で決まることを理解させることが重要です。さらに、比較量の大小は、割合だけで決まるのではなく、基準量と割合の両方に依存することを理解させる必要があります。これらの理解を促進するためには、具体的な場面設定を用いた問題解決を通して、割合の概念を定着させることが有効です。例えば、割引券を使った買い物や、アンケート結果の分析、地図上の縮尺など、日常生活に関連した具体的な場面を用いて、割合の考え方を練習させることが重要となります。また、基準量と比較量の両方に着目して、割合の大小を判断する活動、割引券で最も値引きされる商品を選ぶ理由を説明する活動などを通して、割合の概念の理解を深めるための具体的な授業アイディアが提案されています。これらの活動を通して、児童は割合の概念をより深く理解し、問題解決に活用できるようになることが期待されます。
3. 基準量と比較量の理解と割合の応用
割合の理解を深めるためには、基準量と比較量の概念を明確に理解させることが重要です。基準量を基準として、比較量の大きさを割合で表すという基本的な考え方をしっかりと定着させる必要があります。そのため、様々な場面で基準量と比較量を明確に区別し、それらの関係を理解する活動を取り入れることが重要になります。また、割合を用いた問題解決においては、基準量と割合から比較量を求めるだけでなく、比較量と割合、または比較量と基準量から、残りの要素を求めるといった、逆算的な思考も必要になります。これらの思考力を養うためには、様々なタイプの割合の問題に取り組ませ、それぞれの状況において、基準量、比較量、割合がどのように関係しているかを理解させる必要があります。さらに、割合の大小を比較する際には、割合だけでなく、基準量も考慮する必要があることを理解させることが重要です。割合が大きくても、基準量が小さければ比較量は小さくなるといった、割合と基準量の相互関係を理解させるための具体的な授業アイディアが提示されています。
