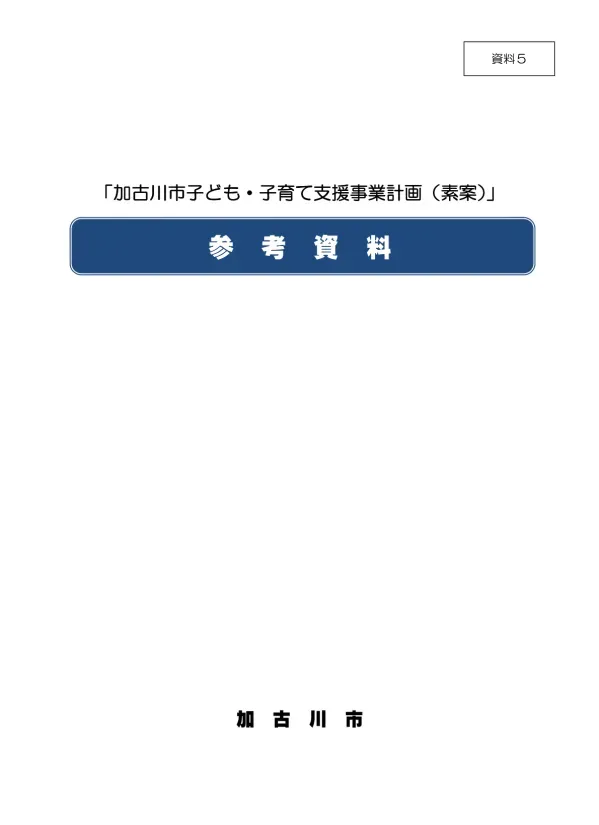
少子化対策:加古川市の人口動態分析
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.63 MB |
概要
I.日本の少子化と加古川市の現状
本資料は、日本の少子化問題と、特に加古川市における人口動態、子育て支援施策の現状を分析したものです。日本の合計特殊出生率は、過去最低の1.26を記録するなど、深刻な人口減少に直面しています。加古川市においても、15歳未満人口の割合は減少傾向にあり、少子高齢化が進行しています。出生数は近年2,300~2,500人前後で横ばいですが、人口維持に必要な合計特殊出生率2.08を大きく下回っています。このため、加古川市では、少子化対策として様々な子育て支援施策を展開しています。
1. 日本の少子化の現状
資料によると、日本の年間出生数は第1次ベビーブーム期には約270万人、第2次ベビーブーム期には約200万人でしたが、昭和59年には150万人を割り込み、その後は減少傾向が続いています。平成3年以降は増加と減少を繰り返しながらも、現在も緩やかな減少傾向にあります。合計特殊出生率は、平成12年には1.42でしたが、平成17年には1.24と過去最低を記録し、全国平均や兵庫県平均を下回りました。しかし、平成22年には1.50まで回復しています。世帯数は毎年増加傾向にあり、平成12年の89,533世帯から、平成17年には94,605世帯、平成22年には99,645世帯となっています。平成23年の出生数は105万806人で、前年より2万498人減少しており、合計特殊出生率は1.39と微増傾向ではありますが、欧米諸国と比較すると低い水準です。これらのデータは、日本の少子化が深刻な問題であることを示しています。
2. 加古川市の人口動態
近年、加古川市の人口はほぼ横ばいですが、15歳未満人口の割合は減少傾向にあります。昭和60年には25.0%だったこの割合は、平成12年には16.3%、平成22年には14.7%に低下し、少子高齢化が進んでることが分かります。一方で、平成25年の出生数は2,353人で、ここ10年間は2,300~2,500人前後で横ばいとなっています。自然増減は出生数と死亡数の差で示されますが、出生数は平成11年をピークに減少傾向にあり、近年は横ばいとなっています。一方、高齢化の影響で死亡数は増加傾向にあります。年齢3区分別人口構成比の推移を見ると、15歳未満人口の割合は減少傾向にある一方、65歳以上の割合は増加傾向にあり、少子高齢化の流れが継続していることがわかります。合計特殊出生率は、昭和60年には1.83でしたが、平成17年には過去最低の1.24まで落ち込み、国や県の平均を下回りました。平成22年には1.50まで回復しましたが、人口を維持できる水準である2.08を大きく下回っています。婚姻数は平成8年度をピークに減少傾向にありますが、近年はほぼ横ばいとなっています。離婚数は増加傾向にありましたが、近年は年間500~600件とほぼ横ばいとなっています。
3. 加古川市における子育て支援の現状と課題
加古川市では、市内幼稚園の在園児童数や認可保育所の利用状況、児童クラブの入所児童数、子育て短期支援事業(ショートステイ)の利用状況、延長保育事業の利用者数などを調査・分析しています。公立保育所の園児数は民間移管などで減少傾向にある一方で、私立保育所の園児数は増加傾向にあります。児童クラブの入所児童数は増加傾向にあり、乳児家庭全戸訪問事業の実施率は平成23年度以降95%以上に達しています。ファミリーサポートセンターの利用件数は平成21年度の8,600件をピークに減少傾向にありましたが、平成24年度からは増加傾向にあります。妊婦健康診査費助成事業の利用者は平成22年度をピークに減少傾向にあります。これらのデータは、加古川市の子育て支援施策の現状と課題を示すものであり、今後の施策検討において重要な参考資料となります。特に、保育所の待機児童問題や、病児・病後児保育のニーズの高まりなどが重要な課題として浮き彫りになっています。
II.加古川市の子育て支援施策
加古川市では、子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育所・幼稚園の整備、保育料の助成、育児休業取得支援、ファミリーサポートセンター事業など、多様な子育て支援に取り組んでいます。待機児童解消に向けた施策も重点課題です。平成25年度の調査では、小学校就学前の子を持つ保護者4,000人を対象にアンケート調査を実施し、子育て支援に関するニーズを把握しました。調査の結果、病児・病後児保育のニーズが高いことなどが明らかになっています。また、育児休業取得率向上に向けた取り組みも必要であることが示唆されました。
1. 保育所 幼稚園の状況と保育料
加古川市の子育て支援施策において、保育所と幼稚園の現状と保育料は重要な要素です。市内認可保育所の利用状況をみると、公立保育所の園児数は民間移管などで減少傾向にある一方、私立保育所の園児数は増加傾向にあります。これは、公立保育所の民間移管や施設整備による定員増によるものです。市内幼稚園の在園児童数の推移も同様に、詳細なデータ分析が必要です。 新たな子ども・子育て支援新制度では、保育料は国が定める上限額の範囲内で市町村が決定します。加古川市では、保育所(2号・3号認定)と幼稚園(1号認定)について、それぞれ保育料(案)を設定しており、平成27年3月頃に正式決定予定です。特に幼稚園については、公立・私立を問わず同額を原則としていますが、市立幼稚園の保育料は平成31年度まで段階的に引き上げ、私立施設と同額に合わせる経過措置が設けられています。新制度に基づく確認を受けない私立幼稚園は、独自の保育料を設定します。平成32年度以降は、財政状況や社会情勢を考慮し、保育料の上限額(2万円程度)まで引き上げる検討も行われています。
2. 児童クラブと子育て短期支援事業
加古川市では、放課後児童健全育成事業(児童クラブ)が実施されており、全小学校28校に32クラブが設置され、入所児童数は増加傾向にあります。子育て短期支援事業(ショートステイ)の延べ利用日数はほぼ横ばいとなっています。これらの事業は、保護者の就労支援や育児負担軽減に貢献しており、その利用状況の推移は、子育て支援施策の効果測定において重要な指標となります。今後の施策検討においては、これらの事業の更なる充実や、ニーズの変化への対応が重要となります。例えば、ショートステイの利用状況が横ばいである理由の分析や、児童クラブの増加傾向に対応した施設整備や人員配置の計画などが挙げられます。
3. その他の子育て支援施策とアンケート調査
加古川市では、乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)も実施しており、平成23年度以降、訪問実施率は95%以上を維持しています。訪問できなかった家庭については、4ヶ月児健診の受診確認などで状況把握を行っています。加古川市ファミリー・サポート・センターの会員数は増加傾向にあり、利用件数も平成24年度から増加傾向にあります。妊婦健康診査費助成事業の利用状況は平成22年度をピークに減少傾向にあります。これらの事業は、子育て家庭への様々な支援を提供していますが、それぞれの事業の利用状況やニーズの変化を把握し、効果的な施策を検討していく必要があります。平成25年12月には、加古川市子ども・子育て支援事業計画策定のため、市内の子育て家庭を対象としたアンケート調査を実施しています。この調査では、4,000人の保護者から回答を得ており、教育・保育・子育て支援の現状と今後の利用希望などを把握し、地域の実情とニーズに応じた施策の検討に役立てられています。特に、病気やけがの際の対応や、病児・病後児保育事業の利用希望、不定期の教育・保育事業の利用状況などが詳細に分析されています。
III.国の少子化対策と兵庫県の子育て支援
国レベルでは、「エンゼルプラン」「少子化社会対策大綱」「子ども・子育て応援プラン」「子ども・子育てビジョン」など、一連の少子化対策が実施されています。これらの施策は、育児休業の推進、保育所の整備、子育て支援の充実などを柱としています。兵庫県においても、「ひょうご子ども未来プラン」「新ひょうご子ども未来プラン」など、地域の実情に合わせた少子化対策を進めており、平成23年から27年までの5年間で出生数を24万人とする目標を掲げています。加古川市は、これらの国や県の施策を踏まえ、独自の子育て支援を展開しています。
1. 国の少子化対策の取り組み
日本の少子化対策は、平成2年の合計特殊出生率1.57という衝撃的な数値を契機に本格化しました。平成6年には「エンゼルプラン」が策定され、仕事と子育ての両立支援などが重点課題となりました。その後、平成16年には「少子化社会対策大綱」と「子ども・子育て応援プラン」が策定され、子どもが健やかに育つ環境づくりを目指した具体的な施策が展開されました。平成15年には「少子化社会対策基本法」が制定され、少子化対策会議が設置されるなど、国を挙げての取り組みが強化されました。同年に制定された「次世代育成支援対策推進法」では、地方公共団体や事業主による次世代育成支援の促進が定められています。平成17年には、初めて出生数が死亡数を下回り、合計特殊出生率は過去最低の1.26を記録、人口減少に転じました。これを踏まえ、「新待機児童ゼロ作戦」が開始され、保育所の待機児童解消に重点が置かれるようになりました。平成18年には少子高齢化の厳しい将来予測を踏まえ、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略が策定され、ワーク・ライフ・バランスの実現と包括的な次世代育成支援の枠組み構築が目指されました。平成21年には「子ども・子育てビジョン」が閣議決定され、3つの大切な姿勢(生命と育ちを大切にする、困っている声に応える、生活を支える)に基づく具体的な取り組みが推進されています。平成24年には子ども・子育て関連三法が成立し、平成27年度から子ども・子育て支援新制度がスタートしました。市町村は、この新制度に基づき、地域の実情に応じた子ども・子育て支援事業計画を策定することが義務付けられました。
2. 兵庫県における少子化対策
兵庫県では、平成18年に「ひょうご子ども未来プラン」を策定し、「未来の親づくりへの支援」、「子どもを生み育てることへの支援」、「子どものすこやかな育ちへの支援」、「社会システムの再構築」の4本柱で少子化対策に取り組んできました。このプランは、一人一人が生命の大切さ、家庭や子育ての大切さを考え、安心して子どもを生み育てることができる地域社会の実現を目指しています。その後、平成22年には、子育てをめぐる様々な課題に対応するため、「新ひょうご子ども未来プラン」が策定されました。このプランでは、子育て支援制度の充実、家庭・地域・職域での協働による子育て支援、家族や地域の絆の継承を3つの理念目標に掲げ、平成23年から27年までの5年間で県内の出生数を24万人とする目標を設定しています。 新ひょうご子ども未来プランは、少子化対策の更なる推進、待機児童の解消、子育て支援環境の整備、家庭・地域・職域での協働による安心で喜びのある子育て環境の創出などを目指しています。具体的には、子育て支援制度の充実や働き方の見直しによる子育て支援環境の整備、家庭・地域・職域での共感をもって子どもたちを包む安心と喜びの子育て、家族や地域の大切さを次世代につなぐ取り組みなどが推進されています。子ども・子育て支援新制度の開始に先立ち、待機児童解消に意欲的に取り組む自治体への支援も強化されています。待機児童解消加速化プランでは、平成25年から26年を緊急集中取組期間とし、2年間で約20万人分の保育の受け皿確保を目指しています。さらに、平成27年から29年度までは取組加速期間とし、潜在的な保育ニーズも含め、約40万人分の受け皿確保を目指しています。
IV.保育料と新制度
平成27年度から始まる子ども・子育て支援新制度においては、保育料の国定上限額の範囲内で、市町村が保育料を設定することになります。加古川市では、保育所(2号・3号認定)と幼稚園(1号認定)の保育料をそれぞれ設定し、段階的な引き上げを予定しています。私立幼稚園については、新制度に基づく確認を受けない場合は、各園が独自に保育料を設定します。保育料の上限額は、平成32年度以降、財政状況や社会情勢を踏まえ検討されます。
1. 新制度における保育料の決定
平成27年度から始まる子ども・子育て支援新制度では、特定教育・保育施設や特定地域型保育事業の利用にかかる保育料は、国が定める上限額の範囲内で、子どもの保護者が居住する市町村が決定することになります。そのため、加古川市に居住する子どもの保護者が、他市町村の施設を利用する場合でも、加古川市が定める保育料が適用されます。この新しい制度では、保育料の算定方法や負担軽減策などが検討されており、その内容は、利用する施設の種類や保護者の所得状況などによって異なります。保育料の決定にあたっては、国が示す基準や、加古川市独自の状況(財政状況、社会情勢など)が考慮されます。 この新制度によって、保育料の負担が軽減されるケースや、逆に増加するケースも考えられます。そのため、制度の導入にあたり、保護者への周知徹底や、制度の理解を深めるための説明会などが重要になります。加古川市では、新制度の開始に向けて、保育料の算定方法や、利用者への説明、制度の周知徹底など、準備を進めています。
2. 保育所等 2号 3号認定 と幼稚園等 1号認定 の保育料
加古川市では、新制度における保育所等(2号・3号認定)と幼稚園等(1号認定)の保育料(案)をそれぞれ設定しています。保育所等については、保育の必要性に応じて保育料が設定され、保護者の経済状況も考慮される予定です。一方、幼稚園等(1号認定)については、公立・私立を問わず全ての施設で同水準の教育が提供されると考えられるため、原則として同額の保育料を設定するとしています。しかし、現行の負担水準を考慮し、新制度開始当初は市立幼稚園の保育料の急激な上昇を緩和するため、平成31年度まで段階的に引き上げる経過措置がとられます。これは、私立施設等の保育料と同額に合わせるための措置です。新制度に基づく確認を受けずに現行制度のまま運営される私立幼稚園については、この保育料(案)は適用されず、各園が独自に保育料を設定します。平成32年度以降については、市の財政状況や社会情勢を踏まえ、国の基準により設定できる上限額(20,000円程度)まで保育料の最高額を引き上げる可能性も検討されています。
