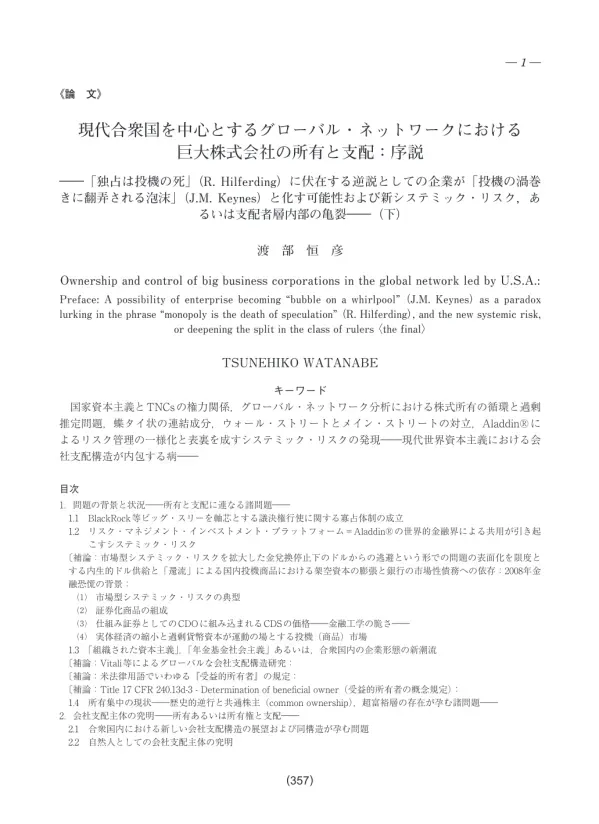
巨大企業支配構造:所有と支配の寡占化
文書情報
| 著者 | 渡部恒彦 |
| 専攻 | 経済学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 20.24 MB |
概要
I.グローバル企業ネットワークと国家資本主義の現状 所有と支配構造の解明
本稿は、グローバリゼーションと国家資本主義下における多国籍企業(TNCs)の所有と支配構造を、VeblenとPolanyiの理論を踏まえ分析しています。特に、BlackRockなどの大手資産運用会社がグローバルな企業ネットワークにおいて果たす役割、そして中国、米国、日本、フランスといった主要国の市場化の進展と国家資本主義の動向を比較検討しています。Keynesの理論も参照し、特に米国における株主資本主義の変遷と、経済格差の拡大、保護主義政策といった課題が議論されています。
1. 国家資本主義の概念と現状分析
本節では、Haberly & Wójcikが用いる「周辺の国家資本主義」という概念の曖昧さを指摘し、その範疇に中国、フランス、日本、韓国など様々な国が含まれる現状を説明しています。特に、中国を典型的な国家資本主義の例として取り上げつつも、その官僚主義的・権威主義的な国家組織が市民社会形成を通じて変化・熔解していく可能性を示唆しています。一方、日本は開発独裁とは無縁であり、韓国も既にその段階を超えていると論じています。Veblenの二重運動論とPolanyiの二重運動論を対比させながら、国家制度と市場化の動きの複雑な関係性を分析し、国家資本主義という概念そのものの再定義を提起しています。I. Bremmerによる中国の市場化への懸念も言及され、国家資本主義の多様性と概念の混乱が指摘されています。坂田幹男氏の研究成果も参照され、より明確な国家資本主義の範疇規定の必要性が示されています。
2. グローバル企業ネットワークにおける所有と支配構造
この節では、グローバルな企業ネットワークにおける所有と支配構造を分析する上で、Haberly & Wójcikの研究成果が重要な役割を果たしています。彼らが用いた、5%以上の株式保有を支配の指標とする手法、そして各投資家の経済的影響力を測る指標(5%支配のピラミッド内に横たわる全ての企業の合算ベースの売上高)が説明されています。 グローバル企業ネットワークの高度な統合、そしてそのネットワーク内における国際的な多様性が示され、特に大手資産運用会社(BlackRockなど)の支配構造と、その運用スタイル(「voice」と「exit」戦略)が詳しく分析されています。 BlackRockのLarry Fink会長兼CEOの戦略が具体的な例として取り上げられ、短期的な利益追求ではなく、長期的な投資成果を重視する姿勢が強調されています。さらに、このネットワークにおける主要プレイヤーとして、金融仲介機関の重要性が示唆されています。
3. 主要国の国家資本主義と市場化の動向 中国 米国 日本 フランスの比較
中国、米国、日本、フランスを例に、国家資本主義と市場化の現状が比較検討されています。中国は、国家資本主義の熔解(溶解)が進む段階にあると分析され、その過程で市民社会の形成が進む可能性が示唆されています。一方、日本は既に国家資本主義の段階を超え、フランスは「開発独裁」的性格を持たないものの、政府系金融機関による企業支配の側面が残っていることが指摘されています。 日本のGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の運用とコーポレート・ガバナンス改革、そして伊東光晴氏による批判(質重視の経済政策、経済格差是正の必要性など)が紹介されています。 また、フランス電力会社(EDF)や預金供託金庫(CDC)、フランス郵政公社(La Poste)の政府保有状況なども言及されています。各国の状況を比較することで、Haberly & Wójcikの国家資本主義論における概念の曖昧さが改めて強調されています。
4. グローバル化と国家戦略の緊張関係 Googleと国家安全保障
この節では、グローバル企業ネットワークにおける国家の役割と、その国際的な緊張関係が分析されています。Haberly & Wójcikが指摘する国家主導的なグローバル連携が、市場によるグローバル化の圧力と複数の政府の欲求の間の「妥協点」であると説明しています。 中国におけるGoogleの市場参入と、合衆国の国家安全保障問題との関係が例示され、「市場の脱政治化」という虚構が指摘されています。 BPとRosneft、PeugeotとDongfeng、日産とRenaultといった具体的な企業間の関係を通して、国家戦略と市場化のグローバリゼーションの複雑な相互作用が示されています。 国家資本主義の国際化が、短期的には世界経済の安定化に寄与する可能性を示唆する一方、長期的には、市場の脱政治化という虚構が崩壊し、国家間の政治的紛争が増大するリスクが指摘されています。
II.企業支配構造 閾値ルールとネットワーク支配
企業の所有と支配の関係は、株式保有比率に基づく閾値ルールによって分析されます。5%以上の株式保有を支配の指標とし、グローバル企業ネットワークにおける支配構造をグラフ理論を用いて解明。BlackRockなどの大手資産運用会社の支配力の大きさと、そのリスク管理の一様化によるシステミックリスクの発生可能性が指摘されています。 主要な金融機関のネットワーク構造と、その国際的なつながりが詳細に分析されています。
1. 株式所有と企業支配の閾値ルール
この小節では、企業支配構造を分析するための基礎として、株式所有と支配の関係を説明しています。株式の所有(Wij)と支配(Cij)の間に簡単な閾値ルールを適用し、50%以上の所有は完全な支配を意味すると定義しています。 しかし、より現実的なモデルとして、少数株主が一定の支配力を維持する可能性も考慮されています。 所有と支配の関係をグラフ理論を用いて表現することで、ネットワーク支配(cinet)という概念が導入され、これはある主体が直接的・間接的に支配する経済的価値の総量を表します。 このアプローチは、既存のコーポレート・ガバナンス研究では見過ごされてきた、グローバルな企業ネットワークにおける支配構造の解明に役立つと主張しています。図9-3:原典図1「所有と支配」が、この閾値ルールとネットワーク支配の概念を視覚的に説明するために使用されています。
2. グローバル企業ネットワークにおける支配構造の分析
本節では、グローバル企業ネットワークにおける支配構造を分析しています。Haberly & Wójcikの研究を基に、5%以上の株式保有を支配の指標として、グローバル企業ネットワークの構造を解明しようと試みています。 彼らの分析では、直接的な企業所有関係だけでなく、複数段階の所有関係を経由した間接的な支配関係も考慮されています。 分析対象として選ばれた205社の企業のうち、74%がグローバル企業ネットワークに連結しており、その統合度が高いことが示されています。 さらに、ネットワークの中枢を占める上位50社の支配力保持者(その多くが金融仲介機関)が分析され、表9-2:原典表S1「上位50の支配力保持者」が重要なデータとして提示されています。 この分析では、China Petrochemical Group Co.やかつて存在したCNCE、Lehman Brothers Holdings Inc.といった具体的な企業も例として挙げられています。図9-10:原典図2「ネットワーク・システムの構成形態」も、ネットワーク構造の理解を助けるために用いられています。
3. BlackRockを中心とするグローバル ネットワーク中枢とシステミックリスク
この小節は、BlackRockなどの大手資産運用会社がグローバル企業ネットワークにおいて中心的な役割を果たしていることを示しています。 特に、BlackRockが提供するAladdin®というリスク管理プラットフォームが、世界中の金融機関で広く利用されている現状が、リスク管理の一様化、ひいてはシステミックリスクの増大につながる可能性を指摘しています。 Aladdin®に依存しないリスク管理を行う機関も存在するものの、リスク管理の一様化が進むと、世界的な金融危機が発生する危険性が高いと警告しています。 Vitaliらの研究で明らかにされた、少数の株主にネットワーク支配が集中する構造(グローバルな蝶タイ状の最大連結成分)も参照され、BlackRockを中心とするグローバル・ネットワーク中枢の脆弱性が指摘されています。 2008年の金融危機と、合衆国における緊急経済安定化法案(Troubled Asset Relief Program)の成立も、システミックリスクの現実例として挙げられています。
III.現代資本主義の課題 金融化と経済格差
金融化の進展、特に米国における経済格差の拡大が重要な問題として取り上げられています。Keynesの理論とMarx、Kaleckiの理論を参照しながら、資本家階級内の対立、所得分配の不平等、そして有効需要の不足が経済問題の根源として議論されています。米国政府の保護主義政策(例:対中関税)とその効果・問題点が分析され、ハイテク産業への投資促進と経済格差是正が政策提言として挙げられています。 ミレニアル世代の価値観の変化も、株主第一主義からの転換を促す要因として注目されています。
1. 米国型資本主義の転換と経済格差の拡大
本節では、米国型資本主義が「株主第一主義」から転換しつつある現状と、それに伴う経済格差の拡大問題を論じています。ビジネス・ラウンドテーブルによる「株主第一主義」の見直し声明(2019年8月)が紹介され、深まる経済格差や環境問題への対応の必要性が強調されています。リーマンショック後の金融緩和や減税政策が、資産価格の上昇をもたらした一方で、経済格差を拡大させたとの批判が提示されています。 ジャック・アタリ氏の予測(世界の99%が激怒する時代)も引用され、富の集中と環境問題が社会不安につながる可能性が指摘されています。 2020年米国大統領選挙を控えた状況も言及され、エリザベス・ウォーレン氏による反資本主義的な政策提言なども紹介されています。 ミレニアル世代の価値観(社会貢献を重視する傾向)が、企業の行動原則の見直しを促す要因として注目されています。BlackRockのラリー・フィンクCEOの手紙(ミレニアル世代の6割が企業の目的を利益追求より社会貢献と考えているとの指摘)も重要な情報として取り上げられています。
2. トランプ政権の重商主義政策とKeynesの保護主義論との比較
トランプ政権の対中・対EU重商主義的な貿易政策が、Keynesの保護主義論と比較検討されています。 Keynesが一時的にせよ保護主義政策を容認した歴史的文脈と、現在の米国における状況を対比することで、両者の相違点が明確化されています。 Keynesは公共投資による経済活性化を重視した一方、トランプ政権の政策は、消費需要拡大のための経済格差是正を軽視しているとの批判がなされています。 米国経済における消費需要支出の不足が問題であり、その解消にはMarxとKaleckiが指摘した経済格差の是正が不可欠であると論じています。 Keynesの階級観に基づき、投資家階級と企業家階級、そして労働者階級間の所得格差を解消するための政策(富の再分配)の必要性が主張されています。 ジェトロの報道(対中関税の消費財への影響)、ロイター通信の見解なども参照されています。 また、Keynesの「国内で何を作り、何を輸入するか」という政策の重要性が、現代の米国経済においても依然として高いと主張されています。
3. 米国経済の構造問題 製造業の衰退とハイテク産業への投資
米国経済の構造問題として、製造業の衰退とハイテク産業への投資の必要性が論じられています。 トランプ政権が支持を得た背景には、製造業の復興を求める労働者層の期待があったものの、生産性の低い製造業の復興は困難であり、雇用回復にはつながらないと分析しています。 そのため、第4次産業革命を活かしたハイテク産業(情報通信産業、バイオテクノロジーなど)への投資を促進し、知的財産権の保護を強化すべきだと主張しています。 シリコンバレーを象徴とするハイテク産業の集積地(サンベルト地帯)と、ピッツバーグ、デトロイト、シカゴといった伝統的製造業の中心地(スノーベルト地帯)の対比を通して、雇用機会の格差が説明されています。 1990年代以降の非農業雇用者数と製造業雇用者数の推移(製造業雇用者の減少比率が12.7%)などのデータが示され、製造業の雇用回復の困難さが裏付けられています。 アップスキリングによる転職支援なども、製造業の失業者対策として提案されています。 しかし、米国経済の構造変化は後戻りできない段階にあると結論付けています。
4. 経済格差是正と有効需要拡大のための政策提言
経済格差是正と有効需要拡大のための具体的な政策提言がなされています。 MarxとKaleckiの理論に基づき、資本家階級と労働者階級間の所得格差の是正が有効需要拡大の鍵であると主張しています。 Keynesの階級観を踏まえ、「金利生活者」から成る投資家階級と「活動階級」としての企業家階級間の所得再分配の必要性が強調されています。 具体的には、累進課税の強化や法人税率の引上げを通じた富の再分配、そして超富裕層から一般投資家への所得移転が政策として提案されています。 ウォール街とメインストリートの対立(長期的戦略重視の経営者層と短期的な利益優先の大手資産運用会社間の対立)が分析され、この対立構造が経済問題の根源の一つであると指摘しています。 さらに、知的財産権保護によるハイテク産業の育成と、経済格差是正による消費需要拡大の両面からの政策対応が必要だと結論付けています。 BrownによるKaleckiの理論を基礎としたモデル推計の結果も言及されています。
IV.国家と多国籍企業の相互作用 グローバルな連携と緊張関係
国家とTNCsの相互作用が、グローバル化と国家戦略の狭間での緊張関係として捉えられています。Haberly & Wójcikの研究を基に、国家資本主義の概念の曖昧さを指摘し、中国における国家の役割と市場化の進展、そしてGoogleの事例を通して「市場の脱政治化という虚構」が論じられています。 SWFs(政府系投資ファンド)の役割、国家主導のグローバル連携、そしてその中で生じる国家間の競争が重要なテーマです。
1. 国家主導型グローバル連携と市場化の葛藤
この小節では、グローバル化が進む中で、国家と多国籍企業(MNCs)の相互作用が複雑な緊張関係を形成している点を論じています。Haberly & Wójcikの分析に基づき、国家主導型のグローバルな連携によって結ばれた資本主義は、市場によるグローバルな統合への圧力と、戦略的に重要な部門の支配権を主張する複数の政府の欲求の間の妥協点として存在すると説明しています。 この国家主導のグローバル連携は、グローバル企業ネットワークの統合に貢献する一方で、国際化を進める国民国家の資本家ネットワークは、外国企業との所有権上の連携を強いる非領土的な基盤を創出する役割も担っている、と指摘されています。 BPとロシアのRosneft、PeugeotとDongfeng、日産とRenaultの関係などが具体的な例として挙げられ、国家の政治的戦略と市場化のグローバリゼーションが複雑に絡み合っている様子が示されています。 この「妥協点」の存在は、中国におけるGoogleの「脱政治的」な市場確保という虚構を予感させるとも述べられています。
2. 市場の脱政治化という虚構と国家間の競争
本節では、「市場の脱政治化」というグローバリゼーションにおける虚構が論じられています。 新自由主義とグローバリゼーションの進展によって、投資家としての国家の市場への拡張が進んでいる一方で、グローバルな会社ネットワークの統合は、市場ルールの統一という理想から逆戻りし、不確実性と不安定性を増している、と分析されています。 グローバルな金融が国際的な事象として根本的に特徴付けられるのか疑問視され、Polanyiが指摘した統制経済下の自由放任という逆説的な状況も指摘されています。 Googleの例を通して、合衆国における準公営的な独占企業としての地位が、国家安全保障への関与などを理由に海外で歓迎されなくなっている現状が提示されています。 このGoogleの事例は、グローバリゼーションの安定性が、市場の脱政治化という曖昧な虚構に基づいていることを示唆している、と結論づけています。この虚構が崩壊すれば、国家間の政治的闘争が激化し、市場統合が脅かされると警告しています。
3. 国家と多国籍企業の対立と国際的な紛争 GoogleとOECDの事例
国家と多国籍企業(MNCs)間の対立と、それに伴う国際的な紛争の可能性が分析されています。 グローバル企業ネットワークにおけるもう一つの緊張関係として、国家によるPolanyi的な国際的紛争の増勢への対抗運動が強まる可能性が指摘されています。 Googleは、自国の国家安全保障目的とOECDによるG20行動指針(ダブルアイリッシュ・ダッチ・サンドイッチなどによる節税問題)との間で葛藤を抱えていると説明されています。 MNCsは、国家資本主義的色彩が強い国(中国、ロシアなど)との間でも、自社の待遇をめぐる対立を経験している、と指摘されています。 こうした対立は、グローバリゼーションの安定性を脅かす要因となる可能性があると論じています。Coeらが指摘するGPNs(グローバル生産ネットワーク)とGFNs(グローバル金融ネットワーク)の概念も参照され、国際的な生産・金融ネットワークの複雑性が強調されています。 OJs(オフショアリング・ジョブズ)の問題も、多国籍企業とホスト国間の関係における重要な要素として取り上げられています。
