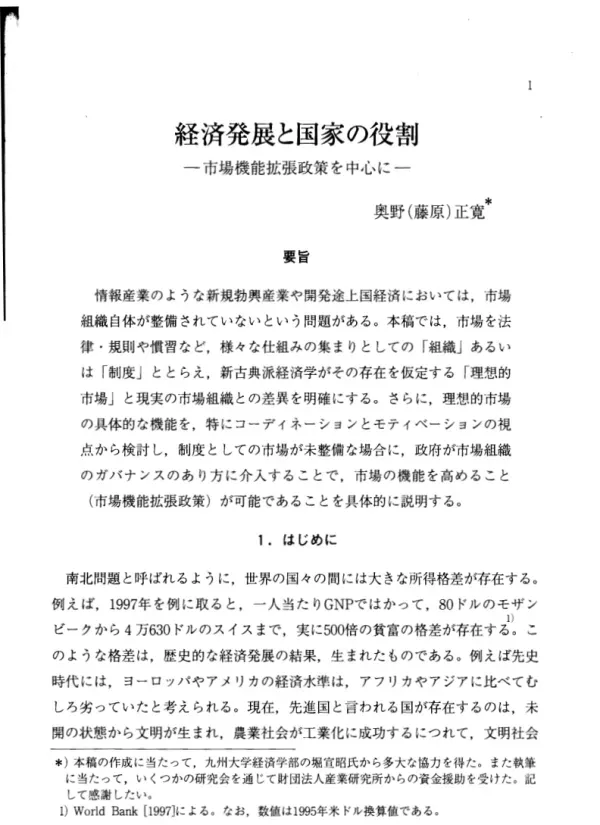
市場機能拡張政策:経済発展と国家の役割
文書情報
| 著者 | 奥野(藤原)正寛 |
| subject/major | 経済学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.04 MB |
概要
I.市場メカニズムと政府の役割 厚生経済学の基本定理からの考察
本論文は、新古典派経済学の枠組みにおいて、市場メカニズムがどのように機能し、かつ市場の失敗(外部効果、公共財、情報非対称性など)が生じる場合に政府がどのように介入すべきかを論じています。特に、開発途上国経済や新規勃興産業における市場機能拡張政策の重要性を強調し、コーディネーションとモチベーションの観点から市場機能の向上を目指した政策を提案しています。厚生経済学の基本定理に基づき、完全競争市場の下ではパレート効率的な資源配分が実現するとされますが、現実の市場は理想的な市場から乖離しており、政府による市場の補完が不可欠であると論じています。政府の役割は、所有権制度の確立・維持、独占禁止政策の実施、そして公共財の供給等を通して市場機能を強化することにあります。
1. 厚生経済学の基本定理と市場メカニズム
この節では、新古典派経済学における厚生経済学の基本定理が論じられています。この定理は、完全競争市場においては、個々の経済主体が私利私益を追求する結果として、パレート効率的な資源配分が実現するというものです。これは、すべての財・サービスに単一価格がつき、生産者は限界費用、消費者は限界効用に基づいて取引を行うという仮定に基づいています。しかし、この定理は、理想的な市場の存在を前提としており、現実の市場では必ずしも成立しない点が強調されています。現実の市場では、情報非対称性や取引コストなど、様々な要因によって、パレート効率的な資源配分が阻害される可能性があることが指摘されています。特に、情報産業のような新規勃興産業や開発途上国経済では、市場組織自体が未整備であるという問題が存在し、理想的な市場からの乖離が大きくなっています。このことから、現実の市場経済においては、政府による市場への介入、すなわち市場の補完が必要であることが示唆されています。
2. 経済システムの役割 コーディネーションとモチベーション
この節では、市場メカニズムの二つの重要な機能であるコーディネーション(資源配分の調整)とモチベーション(経済主体の行動誘因)に焦点を当てています。中央計画経済との比較を通じて、分散的な市場メカニズムが、効率的な資源配分を実現する上でいかに重要であるかが説明されています。中央計画経済では、情報収集や意思決定に大きなコストがかかり、需給の不一致による非効率性が発生するのに対し、市場メカニズムは、価格メカニズムを通じて需給を調整し、効率的な資源配分を実現します。しかし、現実の市場では、特に大量の多様な財・サービスの生産と消費を調整するコーディネーション機能が、完全競争市場の仮定下ほど容易に機能するとは限りません。 様々な経済主体間の計画を整合的に調整するためには、価格情報だけでなく、量的情報も重要であり、将来市場(先物市場)の存在が、コーディネーションを円滑にする上で不可欠であることが指摘されています。また、モチベーションに関しても、利潤というインセンティブが、効率的な資源配分を促進する重要な役割を果たしていますが、完全競争市場では長期的に利潤はゼロに収束する一方、現実の市場では、参入規制や独占力などによって超過利潤、すなわちレントが継続的に発生する可能性があり、その点が問題視されています。
3. 所有権制度の確立と維持 及び市場の失敗
この節では、市場経済が適切に機能するために必要な条件として、所有権制度の確立と維持が重要であることが強調されています。厚生経済学の基本定理が成立するためには、財・サービスの所有権や利用権が明確に規定され、国家によって保護されていることが前提となります。そうすることで、経済主体は、財・サービスの便益を享受するために対価を支払うインセンティブを持つようになり、効率的な市場取引が可能になります。しかし、外部効果や公共財といった市場の失敗が存在する場合、所有権制度だけでは市場の効率性を完全に確保できるとは限りません。これらの市場の失敗は、消費の排除コストが高すぎるために、所有権制度を設定してもその機能が十分に発揮されないという問題を抱えているためです。例えば、銀座通りの自動車通行権を設定するといった例が挙げられ、通行規制のコストが莫大であることが指摘されています。さらに、公共財、特に産業基盤型公共投資(港湾・道路網・工場用水など)は、特定産業の生産性を向上させる効果を持つ一方、その社会的生産性を事前に正確に把握することは困難であるため、政府による適切な介入が必要と結論づけています。
II.市場機能拡張政策 制度としての市場整備
市場機能拡張政策とは、制度としての市場を整備し、市場機能を拡張することを目的とした政策です。既存の市場が十分に機能しない場合、特に開発途上国や新規勃興産業において、政府は情報提供によるコーディネーション機能の強化と、準レント提供によるモチベーション機能の向上を促進する必要があります。 これは、情報非対称性やモラルハザードといった問題に対処し、より効率的な資源配分を実現するための政策です。政府は、公共投資によるインフラ整備や、金融政策を通じた市場創造、そして合理的期待への働きかけによる動学的均衡への誘導を通じて、市場機能の向上を目指します。
1. 市場機能拡張政策の定義と必要性
この節では、市場機能拡張政策(Market Enhancing View)が定義され、その必要性が論じられています。従来の新古典派経済学は、政府介入を市場の失敗に限定する立場を取ってきましたが、本論文では、特に開発途上国経済や新規勃興産業においては、市場組織自体が未整備であるため、市場メカニズムが十分に機能せず、政府による積極的な介入が必要であると主張しています。市場を法律・規則・慣習などの仕組みの集合体、すなわち制度と捉え、理想的な市場と現実の市場の差異を明確にすることで、政府が市場組織のガバナンスに介入し、市場機能を高める可能性を示しています。市場拡張的政策は、制度としての市場を整備し、市場機能を拡張することを目指す政策であり、政府による市場の補完という観点から、情報提供を通じたコーディネーション機能と、準レント提供によるモチベーション機能の向上が重要であると述べています。これは、市場の失敗だけでなく、市場組織の未整備という問題に対処するための政策です。
2. 情報提供を通じたコーディネーション機能の強化
この節では、市場機能拡張政策における情報提供を通じたコーディネーション機能の強化について論じています。 多くの経済主体間の計画を調整するためには、各財・サービスの価格と数量を決定することが必要であり、特に規模の経済性がある産業では、十分な需要がないと平均費用が下がらない問題があります。標準的な経済理論では、完全競争市場を仮定し、価格情報のみで十分としますが、現実の市場では、将来の需要予測や供給制約といった量的情報も考慮しなければなりません。 将来市場(先物市場)の存在が、コーディネーションを円滑にする上で重要であることが例示されています。造船業者が鉄板を必要とする場合、将来の鉄板価格を事前に把握することで、鉄鋼メーカーは設備投資計画を立てたり、新規参入を促すことができます。しかし、そのような将来市場が存在しない場合、需要と供給の不一致が生じ、経済全体の非効率性を招く可能性があります。従って、現実の市場が、標準的な経済学が仮定する市場と同様の機能を果たすよう制度整備を行うことが、コーディネーション問題を解決するために重要になります。
3. 準レント提供によるモチベーション機能の向上
この節は、市場機能拡張政策におけるモチベーション機能の向上、特に準レントの役割を説明しています。経済主体が生産活動や投資活動を行うインセンティブは、将来における経済的利潤、すなわち準レントです。すべての財・サービスに市場が存在し、その価格が明確であれば、各企業は利潤最大化を目指して生産活動を選択し、需要のある財・サービスの生産が促進されます。しかし、完全競争市場では、自由な参入と競争によって、長期均衡では利潤はゼロ(正常利潤)に収束します。準レントは、革新的な技術や新製品開発によって一時的に発生する超過利潤であり、模倣競争によって徐々に消滅していきます。この準レント獲得競争が、技術革新や製品開発を促進する重要な原動力となります。政府は、この準レントメカニズムをうまく活用することで、市場のモチベーション機能を高めることができます。例えば、銀行にレントを与える政策は、銀行のサービス競争を促進し、新たな市場の創出につながる可能性を示唆しています。ただし、政府が直接コントロールできない変数が資源配分の非効率性に影響している産業においてのみ効果を発揮する点に注意が必要です。
III.複数均衡経路と政府のコーディネーション機能
合理的期待を満たす動学的均衡経路が複数存在する場合、政府は財政・金融政策や貿易政策といった手段を用いて、資源配分へ一時的に介入し、望ましい長期的な均衡経路へと誘導できます。例えば、戦後日本の産業政策のように、特定産業への支援を通して、自立可能な均衡経路への移行を図ることが可能です。政府の役割は、民間セクターの将来予想に影響を与えることで、コーディネーションの失敗を防ぎ、より望ましい経済成長経路を実現することにあります。具体的には、産業合理化審議会や資金配分委員会のような政策を通して、民間セクターの情報を集約し、成長戦略を促すことが考えられます。
1. 複数均衡経路の存在と問題点
この節では、合理的期待を満たす動学的均衡経路が複数存在する場合の問題点が論じられています。 複数の均衡経路が存在するということは、経済がどの経路を辿るかによって、最終的な経済状態が大きく異なることを意味します。例えば、ある産業の将来展望について悲観的な見方が支配的になると、その産業への投資が抑制され、結果としてその産業は成長せず、悲観的な予想が自己成就する可能性があります。これは、コーディネーションの失敗による望ましくない均衡経路への陥り込みとして説明されます。自動車産業の例が挙げられており、自動車産業の成長が停滞すると、部品産業への派生需要が不足し、部品の種類や数が少なくなり、結果的に自動車の品質向上や価格低下が阻害されるという負のスパイラルが示されています。このような状況下では、望ましくない均衡経路に陥らないよう、政府による介入が必要となるのです。
2. 政府のコーディネーション機能 均衡経路の変更
この節では、政府が複数均衡経路の存在下でどのように均衡経路を変更できるかを論じています。政府は、財政・金融政策、貿易政策などを通じて、実物的な資源配分へ一時的に介入することで、長期的な均衡経路を変化させることができます。戦後初期の日本の産業政策が例として挙げられています。政府は、基幹産業に対して低利融資や政策金融を行い、立地政策や工業用水政策などを実施することで、特定産業を一時的に支援し、最終的には政府の支援なしでも自立できるような均衡経路に導くことに成功したと分析されています。この政府の介入は、民間経済主体の将来予想に影響を与え、より望ましい均衡経路への誘導を目的としています。昭和30年代初期の産業合理化審議会や資金配分委員会は、民間セクターの将来予想に影響を与え、コーディネーション機能を果たした例として紹介されています。これらの委員会は、公共投資による社会的便益に関する情報収集と、民間の戦略的情報操作の抑制に貢献したと分析されています。
IV.市場の不完全性と政府の役割 理想と現実のギャップ
本論文では、新古典派経済学が仮定する理想的な市場と、現実の市場との間に大きなギャップがあることを指摘しています。現実の市場には、情報非対称性、モラルハザード、独占力といった様々な不完全性が存在し、パレート効率的な資源配分を阻害する可能性があります。そのため、所有権制度の確立・維持に加え、政府による積極的な介入、すなわち市場機能拡張政策が、効率的な資源配分と経済発展のために不可欠であると結論付けています。特に、全ての財・サービスに市場が存在するとは限らない点や、先物市場や条件付き債権市場の発達が不十分な点が市場の不完全性を助長すると指摘しています。
1. 理想的市場と現実の市場のギャップ
この節では、新古典派経済学が仮定する理想的な市場と、現実の市場との間に存在する大きなギャップが論じられています。理想的な市場では、厚生経済学の基本定理に基づき、完全競争の下でパレート効率的な資源配分が実現するとされます。しかし、現実の市場では、情報非対称性、モラル・ハザード、独占力といった様々な不完全性によって、資源配分は非効率になる可能性が高いと指摘されています。 たとえ外部効果や公共財といった通常の市場の失敗が存在せず、厚生経済学の基本定理の条件が満たされたとしても、現実の市場が達成できるのは、情報問題などによる市場の欠陥を前提とした次善の資源配分にすぎないとされています。 この理想と現実のギャップを埋めるために、政府による積極的な介入が必要となることが示唆されています。 特に、開発途上国や新規勃興産業においては、市場機能を支える制度装置が十分に整備されていないため、このギャップはより深刻な問題となる可能性があると論じられています。
2. 現実の市場における情報問題と取引の限界
この節では、現実の市場における情報問題が、市場メカニズムの効率性を大きく阻害する要因として取り上げられています。 「すべての財・サービスに市場が存在する」という厚生経済学の基本定理の前提は、現実的には成立しないことが指摘されています。現実には、将来時点での取引を行う先物市場や、不確実性をカバーする条件付き債権市場などが不完全なため、経済全体の資源配分のコーディネーションが困難になります。 また、これらの市場が存在したとしても、市場参加者が少なく、取引主体の一部が独占力を握る場合、パレート効率的な資源配分は実現できません。 さらに、財の標準化と「一物一価の法則」の関係も重要視されており、価格メカニズムが効率的に機能するためには、財の標準化が進み、価格情報が正確に伝達される必要があると述べられています。現実の市場では、これらの条件が満たされていないことが多く、市場機能の有効性を大きく妨げていると結論づけています。
3. 市場不完全性への対応 政府の役割と政策の限界
この節では、市場の不完全性に対処するための政府の役割と、政策の限界について論じています。現実の市場組織には、情報非対称性による逆選択やモラル・ハザードといった様々な問題が存在するため、理想的な市場の成立は期待できません。所有権制度を確立・維持したとしても、市場メカニズムだけでパレート効率的な資源配分を実現することは不可能です。 そのため、政府は市場機能を改善するための政策、つまり市場機能拡張政策を実施する必要があり、その重要性が改めて強調されています。しかし、政府介入が常に有効であるとは限らない点も指摘されており、政府が直接コントロールできる変数については、補助金や税、規制などで対応できる一方、金融業の貸付リスクなど、政府が直接コントロールできない変数については、より複雑な政策対応が必要になります。 この点を踏まえ、市場機能拡張政策の効果的な実施には、政府の能力と限界を正確に認識することが不可欠であると結論づけられています。
