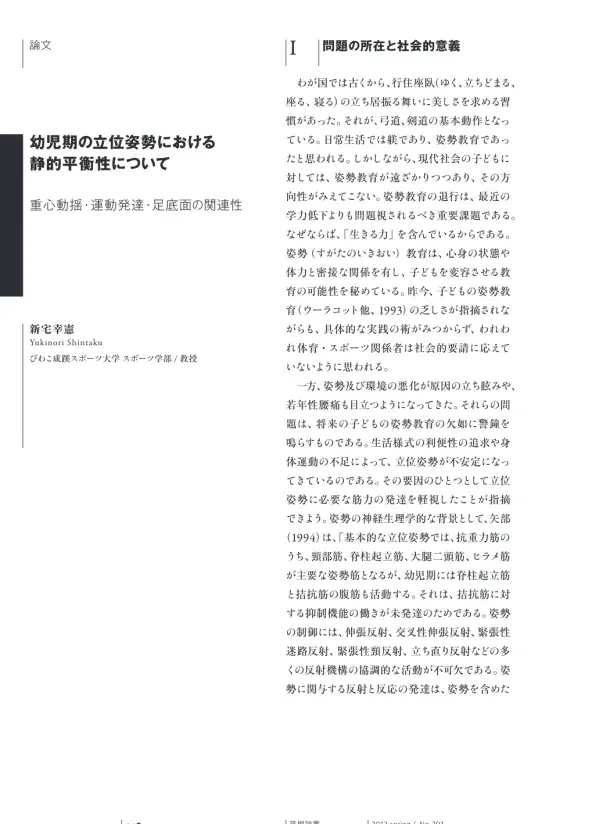
幼児立位姿勢:重心動揺と運動発達
文書情報
| 著者 | 新宅幸憲 |
| 学校 | (大学名不明) |
| 専攻 | 体育学、スポーツ科学、または関連分野 |
| 出版年 | (出版年不明) |
| 場所 | (出版地不明) |
| 文書タイプ | 論文、研究報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 3.53 MB |
概要
I.研究の背景と目的 Research Background and Objectives
本研究は、近年問題視されている幼児期の姿勢教育の不足を解消するための基礎資料を得ることを目的とする。特に、立位姿勢における静的平衡性の発達特性を明らかにすることで、効果的な姿勢教育の体系化に繋げることを目指す。重心動揺の測定を通して、運動発達との関連性、そして足底面の形態や機能との関係性を分析する。
1. 現代社会における姿勢教育の現状と課題
日本には古くから、行住坐臥における美しい立ち居振る舞いを重んじる習慣があった。これは弓道や剣道の基本動作にも繋がるものであり、日常生活における躾や姿勢教育として捉えることができる。しかし、現代社会の子どもたちにおいては、姿勢教育が軽視されつつあり、その方向性が見えないことが大きな問題となっている。学力低下よりも深刻な問題であり、「生きる力」に関わる重要な課題であると指摘されている。姿勢教育の退行は、立ち眩みや若年性腰痛といった健康問題にも繋がっており、将来への警鐘となっている。生活様式の利便性追求や身体運動不足により、立位姿勢の不安定化が進んでいる。その要因の一つとして、立位姿勢に必要な筋力の発達を軽視している点が挙げられる。矢部(1994)の研究では、立位姿勢の神経生理学的背景として、抗重力筋(頸部筋、脊柱起立筋、大腿二頭筋、ヒラメ筋など)の協調的な活動が重要であること、幼児期には拮抗筋の抑制機能が未発達であるため、脊柱起立筋と腹筋が同時に活動することが指摘されている。姿勢に関わる反射や反応の発達は、姿勢を含めた運動の発達に影響を与えるため、幼児期からの適切な姿勢教育が重要となる。
2. 本研究の目的 幼児期姿勢教育の体系化に向けた基礎研究
本研究は、発育発達段階にある幼児期の子どもの姿勢教育の体系化を目標とした基礎資料を得ることを目的とする。具体的には、立位姿勢における静的平衡性の発達特性を明らかにすることを目指す。立位姿勢は、迷路、視覚、固有受容器からの情報が中枢神経系で統合・制御され、骨格筋への出力によって維持されている。安定した立位姿勢を保つためには、重心(center of mass: COM)から垂線を支持基底内に維持することが必要であり、その平衡性は足底圧中心(center of pressure: COP)との関係で保たれる。本研究では、立位姿勢時に現れる身体の動揺を重心の動揺として捉え、視覚系、前庭・半規管、脊髄反射、そしてそれらを制御する神経・筋機能の計測を行う。猪飼(1960)や福田(1957)の研究を踏まえ、立位姿勢における重心動揺の特性(前後動揺が左右動揺より大きく、小周期と大周期が存在するなど)、反射生理学的視点からの考察を行う。Woollacottらの研究(1993)で指摘されている幼児期の姿勢教育の不足を補完し、具体的な実践方法を示唆することを目的としている。特にヒラメ筋の横断面積が重心動揺に影響することを示唆した長谷(2006)、政二(2007)らの研究も参考に、幼児期の姿勢制御における可塑性の豊かさに着目し、幼児期の子どもに対する姿勢教育の重要性を再確認する。
II.重心動揺と運動発達 Center of Gravity Sway and Motor Development
重心動揺の測定結果と、片足立ち、片足連続跳び、反復横跳びなどの運動能力テストの結果を比較分析した。その結果、重心動揺が小さい(静的平衡性が高い)幼児は、これらの運動能力も高い傾向を示した。これは、運動発達が立位姿勢の静的平衡性の向上に寄与することを示唆している。大阪市内のO短期大学附属K幼稚園の園児1038名(5歳児)を対象に10年間のデータを用いた分析結果に基づく。
1. 重心動揺計測と運動能力テスト
本研究では、幼児の立位姿勢における重心動揺と運動発達との関連性を明らかにするため、重心動揺計測と運動能力テストを実施した。重心動揺は、重心動揺計を用いて20Hzの周波数で測定し、重心動揺距離を指標とした。運動能力テストは、大阪市内のO短期大学附属K幼稚園で実施されている5種目(開眼片足立ち、片足連続跳び、反復横跳び、25m走、立ち幅跳び)を採用した。開眼片足立ちテストでは、両腕を垂らし、軸足で立ち、上げた方の脚が接地した時点で終了とし、最大120秒、2回の計測を行い、良い方の記録を採用した。被験者は、10年間のデータを用いた5歳児1038名(男女各519名)を対象とした。 1993年度の5歳児の身長体重を1980年度版の体力標準値と比較検討し、13年間の間に身長体重が増加していることを確認した。しかし、10年間の5歳児(男女別、男女合計)の身長体重には有意差が認められなかったため、1038名を対象に静的平衡性を分析した。
2. 重心動揺距離と運動能力の相関分析
重心動揺距離を基準に被験者を4つのグループに分け、各グループの運動能力を比較した。その結果、重心動揺距離が短いグループ(静的平衡性が高いグループ)は、片足立ち、片足連続跳び、反復横跳びにおいて有意に高い運動能力を示した。一方、25m走と立ち幅跳びについては、重心動揺距離との間に有意な相関は見られなかった。この結果から、重心動揺の小ささ、つまり静的平衡性の高さは、片足立ち、片足連続跳び、反復横跳びといったバランス能力と密接に関連していることが示唆された。これは、これらの運動が、立位姿勢における伸張反射や運動感覚情報の機能を高め、下腿三頭筋の働きを促進することで、静的平衡性を向上させている可能性を示唆している。 また、3歳から5歳までの同一幼児を対象とした3年間の実験でも、重心動揺と片足立ち、片足連続跳び、反復横跳びとの間に相関関係が認められた。
3. 立位姿勢の制御機構と運動発達
立位姿勢において、身体重心は足関節の前方にあるため、重力によるトルクが身体を前方へ押しやる。この前後動を補償するためには、下腿の筋群を基盤とした神経筋の働きが不可欠である。特に下腿三頭筋が重要な役割を担っている(長谷2006)。政二(2007)は立位姿勢の動揺は腓腹筋の相動的活動が中心であるとしている。体幹筋群や下腿筋群の発達、そして伸張反射や運動感覚情報の機能向上は、静的平衡性の向上に不可欠である。成人では、エアロビクスやレジスタンストレーニング、柔軟性、バランストレーニングにより重心動揺が減少することが報告されている(Judge 1993, Messier 2000)。これは身体運動が立位姿勢制御を向上させ、固有の運動感覚情報を活性化することを示唆する。幼児においても、身体運動の経験を通して動的バランスのコントロール能力が向上することにより、静的平衡性も向上すると考えられる。
III.足底面と立位姿勢の安定性 Foot Sole and Stability of Standing Posture
足底面の形態(土踏まず面積、小趾角度など)と立位姿勢における重心動揺との関連性を分析した。フットプリント法を用いて足底面を測定し、重心動揺面積や軌跡長との相関関係を調べた。その結果、土踏まず面積が大きい、小趾角度が小さいなど、足底面の特定の形態は重心動揺の小ささ(静的平衡性の高さ)と関連していた。 平沢(1978)のピドスコープによる測定法との妥当性も確認された。
1. 足底面計測方法と妥当性検証
本研究では、幼児の足底面を計測するためにフットプリント法を用いた。この方法を用いて、足底部の面積(土踏まず面積、足底前部面積、足底後部面積など)と、踵角度、小趾角度、Hライン、Xライン、Zラインを計測した。各部位の面積はデジタルプラニメータ(ウチダ機製 KP-90N)を用いて3回計測し、平均値を採用した。面積の測定においては、身長との相関が高いことから、面積の値は身長の2乗で指数化し、ラインについては身長で除して指数化した。土踏まず面積比の算出は、根本(1969)の方法に従った。フットプリント法による土踏まず面積と、平沢(1978)が開発したピドスコープ(接地足底投影器)による測定結果との間に、有意な正の相関(r=0.767, P<0.05)が認められ、フットプリント法による足底面積の測定は妥当であると判断された。
2. 足底面と重心動揺の関連性 4歳児と5歳児の分析
4歳児と5歳児を対象に、立位姿勢における重心動揺と足底面の関連性を重回帰分析によって調べた。4歳児では、重心動揺面積と足底面の土踏まず面積、足底前部面積(f部)、小趾角度との間に有意な関係(R=0.42, P<0.05)が認められた。5歳児では、重心動揺距離と足底面の土踏まず面積、足底後部面積(R部)、Xライン、小趾角度との間に有意な関係(R=0.561, p<0.05)が認められた。これらの結果から、土踏まず面積が大きいほど、また小趾角度が小さいほど、重心動揺が小さくなる(静的平衡性が向上する)傾向が示唆された。足底後部面積(R部)やXラインも重心動揺距離に影響を与えていると考えられる。臼井(1983)の研究では、発育期の児童の重心点は踵から約40%の位置にあるとされており、この位置付近にXラインがあることから、Xラインの発達が重心動揺距離を短くする安定要因となっていると推察される。
3. 足底面の特徴と立位姿勢の安定性に関する考察
足底面のアーチ(足弓)は、足の形と機能を考える上で重要である。縦と横のアーチが相互に関連し、中足部が頂点となって土踏まずを形成する。土踏まず面積の発達は、立位姿勢における前後左右の動揺を小さくする要因の一つとなる。本研究では、重心動揺距離と足底面のXライン、足底後部面積(R部)との間に有意な関係が認められた。これは、発育期の児童の重心点の位置と、Xラインの位置関係から、Xラインの発達が立位姿勢の安定性に寄与していることを示唆している。また、小趾角度が小さく、5指合計面積や小趾面積が増大すると、左右への動揺が小さくなり、立位姿勢保持に貢献する。生田ら(2004)の研究では、幼児の小指が接地しない傾向が指摘されており、足指の働きが立位姿勢の安定性に重要であることが示唆されている。同様に、足底前部面積(f部)の増大も、前後左右の重心動揺を制御し、立位姿勢の安定性に寄与すると考えられる。小宮山(2006)の研究では、足底面の皮膚反射が立位時や歩行時の姿勢制御に貢献している可能性が示唆されている。
IV.足底面と運動発達 Foot Sole and Motor Development
足底面の形態と運動能力(片足立ち、片足連続跳び、反復横跳び、25m走、立ち幅跳び)との関連性を分析した。 特に、土踏まず面積、足底前部面積、足底後部面積などが、いくつかの運動能力と有意な相関を示した。これは、足底面の発達が運動発達、ひいては立位姿勢の安定性に影響を与えることを示唆する。はだし運動教育の効果についても言及している。
1. 足底面と運動能力の相関分析 4歳児と5歳児
4歳児と5歳児を対象に、足底面の形態と運動能力との関連性を分析した。運動能力テストは、前述の開眼片足立ち、片足連続跳び、反復横跳び、25m走、立ち幅跳びの5種目で行った。 フットプリント法を用いて計測した足底面の各部位の面積(土踏まず面積、足底前部面積、足底後部面積など)、踵角度、小趾角度、Hライン、Xライン、Yラインを、運動能力テストの結果とそれぞれ相関分析した。その結果、4歳児では、Yラインと片足連続跳びとの間に有意な正の相関が認められた。また、反復横跳びと足指面積の間に有意な正の相関が認められた。5歳児においては、片足立ち、片足連続跳び、立ち幅跳びと、Hライン、Yライン、土踏まず面積の間に有意な正の相関が認められた。これらの結果から、足底面の特定の形態(特に土踏まず面積、Yラインの長さなど)の発達は、これらの運動能力に大きく影響を与えていることが示唆される。 25m走と足底後部面積(R部)の間に有意な正の相関が認められたことから、着地の衝撃吸収能力と関連している可能性が考えられる。
2. 足底面の発達と運動発達に関する考察 はだし教育との関連
本研究の結果と、先行研究を合わせて考察すると、足底面への運動刺激による足底面の発達が、運動能力、特にバランス能力の向上に有効であると考えられる。臼井他(1983)は、運動刺激の多い土踏まず形成群の子どもの運動能力が高いことを報告している。また、永田他(1986)のはだし運動教育に関する研究では、はだし教育が足底形態の発達に役立ち、重心動揺の観点からも直立姿勢の保持バランスがよくなること、抗疲労性が高まり、動揺面積が少なくなることを報告している。月村(1989)の研究では、片足立ちと支持足機能、利き手との関連性が示されている。これらの先行研究と本研究の結果を総合的に考慮すると、足底面への運動刺激、特に足指部の機能を高めることが、動的なバランス保持能力の向上に有効であると考えられる。今後、運動刺激、特に「はだし教育」の側面からの検討が必要であると結論づけられる。
V.結論 Conclusion
静的平衡性が高い幼児は、運動能力テストの結果も良好であり、立位姿勢における下腿三頭筋の働きも活発であると推察される。幼児期の姿勢教育において、片足立ち、片足連続跳び、反復横跳びなどの運動プログラムを取り入れることが重要である。足底面の発達も静的平衡性の向上に大きく貢献すると考えられる。これらの知見は、幼児期の姿勢教育の体系化に役立つ。
1. 研究結果のまとめ 足底面と運動能力の関連性
本研究では、足底面の形態と運動能力との関連性を明らかにするため、フットプリント法を用いた足底面計測と、5種類の運動能力テストを実施した。分析の結果、足底面の土踏まず面積、足底前部面積、足底後部面積、そしてXライン、Yラインといった形態的特徴と、片足立ち、片足連続跳び、反復横跳びといった運動能力との間に、有意な正の相関関係が認められた。特に、土踏まず面積が大きいほど、これらの運動能力が高い傾向を示した。これは、足底部のアーチ構造の発達が、バランス能力や下肢の筋力に影響を与えていることを示唆している。反復横跳びに関しては、足指面積との有意な相関が確認され、足指の機能が横方向への推進力に寄与している可能性を示唆している。また、立ち幅跳びのような瞬発力や脚筋力を要する運動においても、足底面の土踏まず面積、Hライン、Yラインとの関連性が認められた。
2. はだし運動教育の重要性と今後の展望
本研究の結果と、臼井他(1983)や永田他(1986)などの先行研究を踏まえると、足底面への運動刺激が運動能力、ひいてはバランス能力の向上に大きく貢献することが示唆される。特に、臼井他(1983)は、運動刺激の多い土踏まず形成群の子どもは運動能力が高く、立位姿勢保持機能の発達が顕著であると報告している。永田他(1986)は、はだし運動教育が足底形態の発達に有効であり、重心動揺面積を減少させると報告している。これらの知見から、幼児期の運動教育において、足底面への適切な刺激を与えることが重要であり、はだし運動教育も有効な手段の一つとなり得ると考えられる。 また、月村(1989)の利き手と支持足機能に関する研究も踏まえ、今後、運動刺激による足底面の発育を、はだし教育の観点からも検討していく必要がある。
