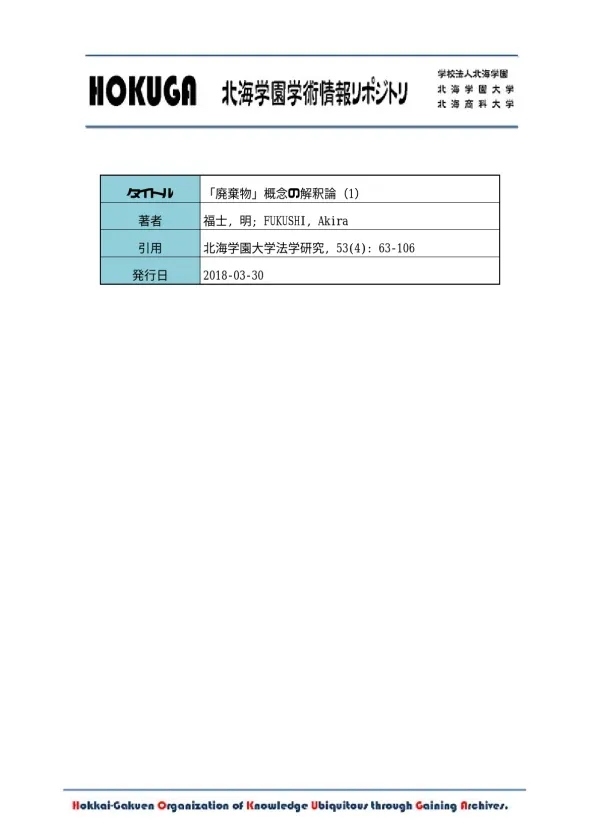
廃棄物概念の解釈:総合判断説を中心に
文書情報
| 著者 | 福士明 |
| 学校 | 大学名不明 |
| 専攻 | 法学(環境法関連) |
| 出版年 | 不明 |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 研究ノート |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 533.19 KB |
概要
I.廃棄物概念の変遷 客観説から総合判断説へ
本稿は日本の廃棄物処理法における廃棄物の定義の変遷を論じています。初期の客観説(汚物と不要物を客観的に定義)は、1977年の厚生省通知(昭和52年3月26日環計37号)により変更され、総合判断説が採用されました。総合判断説は、物の性状、排出状況、取引価値、占有者の意思などを総合的に勘案して廃棄物か否かを判断するものです。この変化は、経済活動の活発化と、新品であっても環境保全上の支障となる可能性のある物の増加が背景にあります。豊島事件やおから事件は、この定義の曖昧さが問題となった事例として挙げられています。
1. 初期の客観説 汚物と不要物の客観的定義
初期の廃棄物概念は、客観説に基づいていました。汚物と不要物はそれぞれ客観的に定義され、明確な基準が存在すると考えられていました。この考え方は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の初期の解釈に反映されています。具体的には、1971年の厚生省環境衛生局長通知(昭和46年10月16日環整第43号)において、廃棄物は「ごみ、粗大ごみ、汚泥、廃油、ふん尿その他の汚物、又は、その排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるもの」と定義されていました。この定義では、占有者の意思は考慮されておらず、物の客観的な性質のみが重視されていました。大塚直『環境法』(第三版)では、廃棄物処理法施行令第二条四号の「不要物」は、廃棄物処理法第二条一項の「廃棄物」と同じと考えられると述べられています。当時の施行令では、食料品、医薬品、香料製造業における原料使用後の動物・植物に係る固形状の不要物が規定されていました。この客観的な定義は、廃棄物の処理を客観的な基準に基づいて行うことを目指していましたが、後に限界が明らかになっていきます。
2. 1977年通知による総合判断説への転換
1977年の厚生省通知(昭和52年3月26日環計第37号)によって、廃棄物概念に関する解釈は大きな転換を迎えました。この通知は、客観説から総合判断説への変更を告げるものでした。この変更の背景には、経済活動の活発化に伴い、客観的には新品であっても廃棄されることによって環境保全上の支障が生じるケースが増加したことが挙げられます。1977年通知では、「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきである」と明記されました。この通知によって、廃棄物か否かの判断に、それまで考慮されていなかった占有者の意思が重要な要素として加えられることとなりました。これは、廃棄物に関する判断が、より複雑で、個別具体的な状況を考慮する必要があることを意味します。この総合判断説は、後の判例や行政実務にも大きな影響を与えました。
3. 総合判断説の要素と具体的な判断基準
総合判断説における判断要素としては、物の性状、保管・排出の状況、取引価値の有無、通常の取扱形態などが挙げられます。そして、これらの客観的要素に加え、社会通念上合理的に認定できる占有者の意思も考慮する必要があるとされています。2000年の厚生省通知(平成12年7月24日衛環第65号)では、この総合判断説の判断基準がより明確に定式化されました。この通知では、廃棄物該当性の判断にあたり、占有者の意思を重要な要素と位置付け、その判断基準を具体的に示しています。この通知以降、行政実務においては、これらの要素を総合的に勘案して廃棄物か否かを判断する総合判断説が定着していきました。しかしながら、占有者の意思や取引価値の有無といった要素は必ずしも明確ではなく、個別事例での判断の難しさが指摘されています。最高裁判決、特に『おから事件』最高裁決定も、この総合判断説を支持するものでした。この決定では、客観的要素と占有者の意思を総合的に勘案する判断基準が示され、行政実務の基準として広く受け継がれています。
II.総合判断説の具体化と判例の影響
総合判断説は、最高裁判決(特におから事件最高裁決定)や環境省の通知を通して具体化されてきました。判例では、物の性状、保管・排出状況、取引価値、通常の取扱形態に加え、社会通念上合理的に認定できる占有者の意思が重要な判断要素となっています。しかし、占有者の意思の解釈や、有価物か無価物かの判断の曖昧さが課題として残っています。様々な学説(古田説、中村説など)も総合判断説を支持しつつ、その解釈に若干の違いが見られます。
1. 最高裁判決と行政実務における総合判断説の定着
1977年の厚生省通知で導入された総合判断説は、その後、最高裁判決、特に「おから事件」最高裁決定によって、行政実務においても正式に採用され、定着することになりました。この決定は、廃棄物該当性の判断において、物の性状、保管・排出状況、取引価値の有無、通常の取扱形態に加え、占有者の意思を総合的に考慮することを明確に示しました。 環境省は、その後も複数の通知(例:平成25年3月29日環廃産発第1303299号)を通じて、この最高裁決定の判断基準を踏襲した行政処分の指針を示し、総合判断説に基づく実務を継続しています。ただし、行政実務上は、排出事業者が自ら利用する場合、必ずしも他人への有償譲渡の実績などを求めるものではないとされています。最高裁決定における五つの判断要素の源流については、北村喜宣氏の研究(『いんだすと』363号、2018年)で詳述されており、客観的要素と占有者の意思のバランスが議論の中心となっています。これらの要素の具体的な重み付けや、判断基準の曖昧さは、依然として課題として残されています。
2. 学説における総合判断説の展開と解釈の違い
総合判断説は、行政実務だけでなく、学説においても広く支持されています。古田説や中村説など、多くの学説が総合判断説を支持していますが、判断要素の重視度や、占有者の意思の解釈に若干の違いが見られます。例えば、古田説は、客観的要素からみて社会通念上合理的に認定できる占有者の意思を重視する一方、必ずしも占有者の主観的な意思をそのまま反映するものではありません。一方、中村説は、1990年代のリサイクル政策の高まりを背景に提唱され、リサイクルの観点も考慮した解釈を示しています。これらの学説は、総合判断説をより精緻化し、実務上の課題解決に貢献してきましたが、それぞれの学説が廃棄物該当性の判断基準をどのように捉えているのか、微妙な違いが存在します。これらの学説間の違いは、廃棄物概念の解釈における複雑性と、その適用における困難さを示しています。
3. 判例 おから事件 豊島事件 と廃棄物概念の不明確性
「おから事件」は、総合判断説が適用された代表的な判例です。この事件では、豆腐かす(おから)の廃棄物該当性が争点となりました。最高裁は、客観的要素と占有者の意思を総合的に判断し、有罪判決を下しました。しかし、この判決においても、占有者の意思の解釈や、取引価値の有無の判断の曖昧さが指摘されています。「豊島事件」は、占有者の意思を重視する1977年通知の下で発生した事件であり、シュレッダーダストの扱いをめぐる紛争となりました。この事件は、廃棄物概念の曖昧さが、不法投棄などの問題を引き起こす可能性を示した事例です。これらの判例は、総合判断説の適用において、客観的要素と主観的要素のバランス、そして具体的な判断基準の明確化が依然として課題であることを示しています。特に、有価物と無価物の境界が不明確な点が、実務上の混乱を招く原因となっていると考えられます。
III.循環型社会における廃棄物概念の課題
近年、循環型社会の構築が重視される中、廃棄物の定義の見直しが必要とされています。現状の廃棄物処理法は、循環利用を促進する観点からは過剰な規制となっている可能性が指摘されています。リサイクルに向けた廃棄物も含めた客観的な定義、及び循環基本法との整合性が課題となっています。 産業廃棄物の処理についても、地方自治体間の判断のばらつきなどが問題となっています。例えば、鉄鋼スラグの扱いを巡る自治体間の判断の違いなどが例として挙げられています。
1. 循環型社会と廃棄物処理法の課題 過剰規制の可能性
循環型社会の理念が浸透する中で、廃棄物処理法のあり方が改めて問われています。 生活環境の保全と公衆衛生の向上という目的は重要ですが、循環利用可能な資源を一旦「廃棄物」として扱う現行制度は、かえって循環型社会の実現を阻害している可能性が指摘されています。循環基本法は、廃棄物の適正処理と同時に循環的利用の促進を謳っていますが、廃棄物処理法が循環利用の促進という点において、過剰な規制を行っている側面があるのではないかという指摘があります。特に、リサイクル可能な資源についても、現行の定義では「廃棄物」に該当してしまうため、循環利用の妨げになるという問題意識が示されています。この問題意識は、廃棄物処理法と循環基本法の整合性の欠如を浮き彫りにしています。より効率的で効果的な循環的利用を促進するためには、廃棄物処理法の見直し、あるいは、循環利用を促進する新たな制度設計が必要であるという主張がなされています。
2. 廃棄物定義の国際的な整合性と客観的定義の必要性
日本の廃棄物処理法の運用と、国際的な基準との整合性も課題として挙げられています。例えば、バーゼル条約を踏襲したバーゼル国内法は客観的な定義を採用しているため、日本の廃棄物処理法の運用とは齟齬が生じているという問題が指摘されています。このことは、国際的な貿易や廃棄物処理において、混乱や摩擦を生む可能性を示唆しています。また、リサイクルに向けられた廃棄物も含めた、より客観的な廃棄物定義が必要であるという指摘もあります。大塚氏の指摘するように、現状の総合判断説は、占有者の意思という主観的な要素を含むため、客観的な基準の確立が求められています。より明確で客観的な定義は、廃棄物処理の効率化、国際的な調和の促進、そして循環型社会の構築に不可欠です。 この客観的な定義は、立法論だけでなく、解釈論の観点からも検討されるべき課題です。
3. 廃棄物定義の見直しと関連諸法への影響 個別法との整合性
廃棄物の定義の見直しは、廃棄物処理法だけでなく、リサイクル関連の個別法にも影響を与えます。現状のリサイクル関連個別法は、現行の廃棄物定義を前提としているため、定義の見直しは必然的に関連諸法の構造見直しにもつながります。浅野氏の指摘するように、定義の見直しは、関連法の抜本的な見直しを伴う大規模な法改正につながる可能性があります。そのため、廃棄物定義の見直しは慎重に進められる必要があり、関連法との整合性を考慮した上で、包括的かつ体系的な見直しを行う必要があるでしょう。また、鉄鋼スラグのように、自治体によって判断が異なる事例も存在し、廃棄物性に関する判断基準の統一化も重要な課題です。 この複雑な問題を解決するためには、関係者間の十分な議論と合意形成が必要不可欠です。法律の改正だけでなく、行政実務における具体的な判断基準の明確化も同時に求められています。
IV.客観説と総合判断説の用語の経緯
本稿では客観説と総合判断説という用語を用いていますが、これらの用語がいつから使われ始めたのかは明確ではありません。1991年の国会質問で初めてこれらの用語が使われたことが示唆されています。その後、多くの学術文献で客観説と総合判断説の対比が用いられるようになりました。しかし、その使用の経緯については、今後の研究課題として残されています。
1. 客観説 と 総合判断説 用語の初出と使用の広がり
本稿で用いられる「客観説」と「総合判断説」という用語の正確な使用開始時期は不明です。しかし、本稿で調査された文献からは、1991年の日下部禧代子議員の国会質問において、廃棄物定義の解釈が客観説から総合判断説へ変化した理由について言及されていることが確認できます。この質問は、既に「客観説」と「総合判断説」(または同様の表現)が行政実務の文脈で使用されていたことを示唆しています。その後、阿部泰隆・淡路剛久編『環境法』(第四版、有斐閣、2011年)や佐藤泉『廃棄物処理法重点整理』(TAC出版、2012年)など、多くの著作で「客観説」と「総合判断説」の対比が用いられるようになり、これらの用語は現在では広く認知されていると考えられます。ただし、大塚直氏の著作など、これらの用語を用いていない文献も存在します。本稿では、これらの用語が現在広く認知されていることを考慮し、本稿においても「客観説」と「総合判断説」を用いて記述しています。しかし、これらの用語の使用経緯の詳細は、今後の研究課題として残されています。
2. 関連文献における用語の揺らぎと今後の課題
文献調査の結果、「客観説」と「総合判断説」の用語の他に、「総合勘案説」といった類似の表現も使用されていることが分かりました。特に、北村喜宣教授の著作では、『環境法』(弘文堂)において「客観説」と「総合判断説」を明確に使い分けて説明されており、この表現は第四版まで継続して使用されています。しかしながら、大塚直・北村喜宣編『環境法ケースブック』(有斐閣、2006年)では、同様の概念を説明する際にも、用語法に微妙な違いが見られます。これらの用語の揺らぎは、廃棄物概念に関する議論の複雑さと、その解釈の多様性を反映していると考えられます。本稿では、現状では「客観説」と「総合判断説」が広く認知されているという判断からこれらの用語を使用していますが、これらの用語の正確な使用開始時期や、変遷の歴史については、さらなる研究が必要であると結論付けられます。
3. 初期文献における廃棄物概念の記述と用語法との関係
初期の文献、例えば田中正一郎『清掃法の解説』(日本環境衛生協会、1966年)では、「ごみ」の概念が極めて包括的であることが指摘され、社会通念上、人の生活環境に支障を生ずるため廃棄されるものが「ごみ」として捉えられていたことが分かります。また、木村又雄・福田勉『清掃法の解説』(第三版、日本厚生通信社、1956年)では、「ごみ」の定義がより具体的に記述されており、社会通念上の理解が強調されています。これらの初期の文献では、「客観説」や「総合判断説」といった用語は用いられていませんが、廃棄物概念の理解の変遷を理解する上で重要な資料となります。これらの初期の記述と、後年の「客観説」と「総合判断説」という用語法との関連性については、今後のより詳細な研究によって明らかにする必要があります。これらの文献を分析することで、廃棄物概念の解釈がどのように変化し、現在の用語法がどのように形成されてきたのか、より深い理解を得ることが期待できます。
