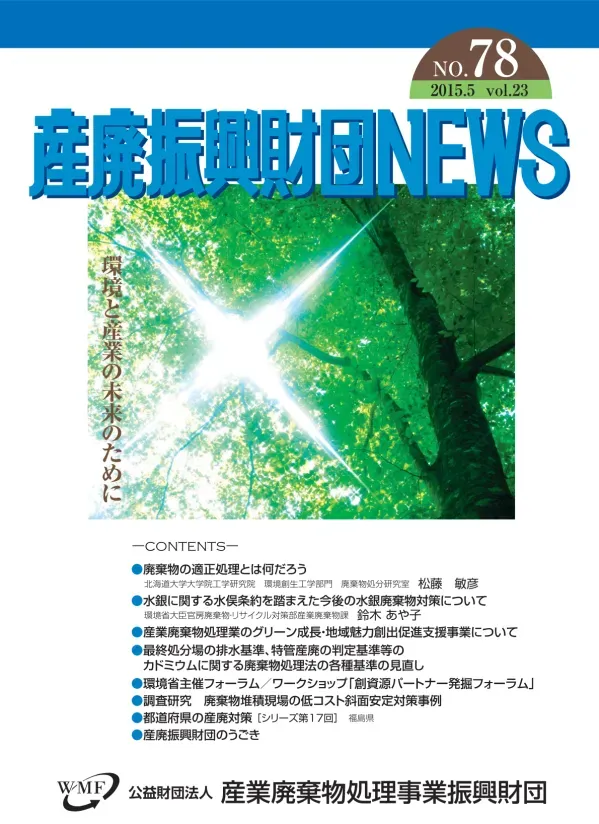
廃棄物適正処理:現状と課題
文書情報
| 著者 | 松藤敏彦 |
| 学校 | 北海道大学 |
| 専攻 | 環境工学 |
| 文書タイプ | 論文集掲載論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.81 MB |
概要
I.北海道大学における新たなゴミ分別方法と廃棄物問題
北海道大学環境保全センター長が中心となり、資源化の徹底、生活系と実験系の区別、有害物の管理を柱とした新たなゴミ分別方法が導入されました。特に、実験で使用されたプラスチック廃棄物の扱いを巡り、産業廃棄物としての処理が必要となった事例が紹介されています。これは廃棄物処理における分類の複雑さと、3Rだけでは解決できない廃棄物問題の深刻さを示しています。札幌市におけるゴミ分別の細かさ(約1000項目)と、その現実的な有効性についても議論されています。
1. 新たなゴミ分別方法の導入と課題
北海道大学環境保全センター長は昨年、新たなゴミ分別方法を策定しました。その中心は資源化の徹底、生活系ゴミと実験系ゴミの明確な分別、そして有害物質の適切な管理です。従来は、実験で使用済みのピペットや使い捨て手袋などが弁当箱と共に廃棄されていたため、実験系ゴミは廊下のごみ箱ではなく、各自で保管場所に運ぶシステムに変更されました。しかし、「実験で使用されたプラスチックは産業廃棄物に当たるため、焼却ごみではなく廃プラスチックとして処理すべきだ」という指摘を受け、分別方法を修正せざるを得ませんでした。これは、ゴミ分別における複雑さと、実践における困難さを示す一例です。さらに、5年前には古いビデオテープを燃えるゴミとして出したら×印を貼られた経験があり、分解できないプラスチックの処理は、焼却が埋立よりも望ましいにも関わらず、当時は燃やせないゴミとして分類されていたことが明らかになりました。これらの経験は、ゴミ分別と廃棄物処理の複雑さを浮き彫りにし、3Rだけでは廃棄物問題を解決できないことを示唆しています。
2. 3Rを超えた廃棄物問題への取り組みと札幌市の事例
低炭素化社会、循環型社会の実現に向け、リサイクルやバイオマス利用などが推進されていますが、本当に適切な方法なのか検証されないまま新たなごみ処理方法が導入される現状があります。平成27年度からは、ボールペンのバネは不燃ごみ、それ以外は可燃ごみといった、非常に詳細な分別基準が設けられました。特に札幌市では、約1000項目にも及ぶ分別基準があり、熱心な市民はきちんと分別することが正しいと信じていると思われます。しかし、ボールペンのバネを焼却した場合の悪影響についても考察する必要があります。分別辞典を作成した人は、素材が燃えるか燃えないかだけを考慮した可能性があり、より包括的な視点が必要であることが示唆されます。このことは、自治体におけるゴミ分別が重要であると同時に、その基準の複雑さと現実的な課題を示しています。環境負荷は処理・処分段階で大きく発生し、3Rはあくまでも下流側の対策に過ぎず、廃棄物問題は3Rだけでは決して解決できないことを改めて認識させられます。
II.水銀廃棄物の適正管理と処分方法
水銀を含む廃棄物の埋立処分に関する規制が強化されています。硫化・固型化処理済みの水銀処理物の処分方法が、管理型最終処分場と遮断型最終処分場に分類され、水銀溶出リスクの低減に向けた具体的な対策が示されています。環境省は水俣条約に基づき、廃棄物処理法の改正等を行い、水銀廃棄物の適正管理に関する国際的な議論をリードする方針です。排出事業者による水銀使用製品のリスト化や表示の推進も重要視されています。
1. 水銀廃棄物の処分方法とリスク低減
廃金属水銀等の埋立処分においては、その処理方法と処分場所が厳格に規定されています。具体的には、硫化処理のみの水銀処理物は、容器に封入した上で処分されます。一方、硫化・固型化処理後も判定基準を満たさない水銀処理物は、遮断型最終処分場での処分が義務付けられます。これに対し、硫化・固型化処理を行い、判定基準に適合する水銀処理物は、要件を満たした管理型最終処分場で処分することが可能です。管理型最終処分場では、水銀の溶出リスクを低減するため、他の廃棄物との混合埋立の禁止、埋立終了時の不透水層の敷設による雨水浸透防止措置などが厳しく規定されています。さらに、処分場廃止後も水銀処理物の安定性を維持するため、上部遮水工の機能維持も重要な要素となっています。この厳格な規制は、水銀の環境への影響を最小限に抑えるための重要な措置です。
2. 水銀排出抑制に向けた上流側対策
水銀添加廃製品の市町村等による収集と水銀回収を促進するため、排出事業者が水銀の使用を認識し、その情報を処理業者へ適切に伝えることが重要視されています。そのため、環境保健部会での検討を受け、過去に製造・販売された製品も含め、水銀添加製品のリスト化や水銀使用製品への表示などが検討されています。これは輸入品も含めた上流側での取り組みを進めることを目的としています。環境省は、水俣条約の速やかな締結に向けて、必要な廃棄物処理法政省令の改正などを予定しており、日本の知見を共有することで水銀廃棄物の適正管理に関する国際的な議論をリードしたいと考えています。廃金属水銀等の長期的な管理を徹底するため、継続的な調査研究や検証を進め、国を含めた関係者の適切な役割分担の下での処理体制と長期間の監視体制の構築が求められています。これらの取り組みは、水銀による環境汚染を抑制し、持続可能な社会の実現に貢献するものです。
III.カドミウムに関する環境基準と排水基準の見直し
カドミウムに係る環境基準及び排水基準の変更(2014年12月1日)と、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物の判定基準の見直しについて説明されています。廃棄物最終処分場からのカドミウムの溶出抑制処理の実態調査結果が示され、水質汚濁防止法に基づく排水基準値を上回る事例はあったものの、その多くは測定限界によるものであったと報告されています。
1. カドミウムに関する環境基準と排水基準の改正
中央環境審議会会長から環境大臣への答申を踏まえ、2011年10月27日、カドミウムに関する公共用水域の水質汚濁に係る環境基準と地下水の水質汚濁に係る環境基準が改正されました。そして、2014年12月1日には、水質汚濁防止法に基づく排水基準も改正されています。さらに、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物の判定基準や、廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準なども見直しが検討されました。この見直しは、循環型社会部会において2014年6月から3回にわたる審議を経て、報告書案が作成され、パブリックコメントを経て、本年4月に報告書としてまとめられました。これらの基準改正は、カドミウムによる水質汚染の防止と、環境保全の強化を目的としています。
2. カドミウム溶出抑制処理の実態調査
カドミウムに係る各種基準の見直しを検討するため、廃棄物最終処分場からの放流水等からのカドミウム排出の実態、処理技術の現状、廃棄物中のカドミウム濃度の実態などが調査されました。中間処理業者を対象とした直近5ヵ年の廃棄物からのカドミウム溶出抑制処理に関する調査では、処理後の溶出量97件のデータのうち、水質汚濁防止法に基づく排水基準値の3倍値を上回ったのは3件(最大0.12mg/L)でした。しかし、そのうち2件は定量下限値が排水基準値の3倍値を上回っていたため、明確に基準値を超えているかどうか確認できませんでした。全ての事業者において、処理後の溶出量は排水基準値の3倍値を下回ることが確認されたわけではありませんが、この調査結果が、カドミウム排出抑制のための更なる技術開発や規制強化の必要性を示唆している可能性があります。
IV.排出事業者と処理業者間の連携強化と循環型社会構築
環境省主催のフォーラム/ワークショップが開催され、排出事業者と優良産廃処理業者の連携強化、循環産業の形成が目指されています。グリーンアローズ中部(中間処理業者)の事例が紹介され、同業他社との協業の重要性が示唆されています。収集運搬における課題として、適正価格、顧客ニーズへの対応、コスト削減などが挙げられ、情報共有やネットワーク化の必要性が強調されています。 ヤマト運輸の事例が、顧客志向の重要性と社員のモチベーション向上について示唆を与えています。
1. 排出事業者と処理業者間の連携強化の重要性
環境省主催のフォーラム/ワークショップでは、排出事業者と優良産廃処理業者との連携強化・協働による循環産業の形成が目指されました。東京、名古屋、福岡の3会場で開催され、排出事業者70名、処理業者63名を含む計133名が参加しました。参加者からは、「人と人との繋がりを重視すべき」という意見が多く寄せられ、良好なコミュニケーションの重要性が再確認されました。具体的な連携事例として、中間処理業者であるグリーンアローズ中部が紹介されました。同社はダイセキ環境ソリューション、タケエイ、大栄環境といった中間処理業者だけでなく、建設会社や石膏ボードメーカーも共同出資して設立されたグリーンアローズホールディングスのグループ会社であり、排出事業者と処理業者の連携の成功例として注目されています。この事例は、廃棄物処理における人的ネットワークの重要性を示しています。
2. 収集運搬における課題と理想的な収集運搬会社像
廃棄物処理業界の収集運搬部門における勉強会・分科会では、現実的な課題が議論されました。参加者からは、運送業に比べて単価が高く時間指定が非効率、顧客への安心感の提供、修繕費・燃料費・休日稼働などのコスト対策、車両・人員の限定による非効率性、顧客要望に応える受注・運航管理の難しさなどが挙げられました。これらの課題を克服するためには、排出事業者との情報共有、優良認定の効果的な活用などが有効だとされました。また、復路のカラ便をなくす努力、産廃情報ネットなどを活用した効率的な荷物のマッチング、ネットワーク化、性状確認、発生量、単価、電子契約などを活用した効率化が提案され、安心・安全なサービスを提供する理想的な収集運搬会社像が模索されました。ヤマト運輸の事例が紹介され、顧客視点の重要性や社員のモチベーション向上、安全ルール徹底による好循環が示されました。
3. 業界の持続的発展に向けた提案
廃棄物処理業界の持続的な発展のためには、適正価格での契約、優良事業者への規制緩和、排出事業者への適正価格の理解促進、処理業者による更なるコストダウン、顧客ニーズへの対応強化などが重要だとされました。排出事業者からは、適正処理には適正価格が必要であり、処理方法や廃棄物の物性によって価格が変動することを理解してほしいという声が上がっています。また、一般廃棄物の処理価格を一律にしている自治体があり、それを根拠に値下げを要求する排出事業者もいるという現実も指摘されました。しかし、一般廃棄物の処理価格は実際には税金で補填されているケースが多く、廃棄物処理業は装置産業であり高価な施設を必要とするため、適正価格が維持されなければ廃業に追い込まれる可能性があることも理解されるべきだと強調されました。
V.廃棄物斜面の安定性評価と低コスト対策
廃棄物の不法投棄現場における斜面崩壊対策として、安息角試験による簡易な安定性評価法が提案されています。従来の三軸圧縮試験や円弧すべり解析に比べて低コストで効果的な暫定対策として、静岡県での事例が紹介されています。これは特に平地での廃棄物堆積現場に有効な方法です。長野県短期大学の土居洋一教授の考案した方法が用いられています。
1. 廃棄物斜面安定性評価の現状と課題
これまで、廃棄物斜面の安定性評価は、三軸圧縮試験や円弧すべり解析といった高度な手法に頼っており、特に小規模な不法投棄現場においても多額の費用を要していました。これは、廃棄物斜面の安定性評価法が確立されていなかったことによるものです。そのため、小規模な不法投棄現場であっても、盛土と同じように1:2勾配(27°)以下に整形する対策がとられ、多大な費用が投じられてきました。東南アジアなどでは、生ごみ等の埋立地で斜面崩壊が頻発していますが、日本の不法投棄現場では、廃棄物層に過剰な水分が存在しないため、斜面崩壊は比較的少ない傾向にあります。しかし、従来の手法では、コスト面での課題が大きく、より簡便で低コストな評価方法の開発が求められていました。
2. 安息角試験による簡易評価法の提案と静岡県での事例
本稿では、がれき類や繊維状物等を含む廃棄物層では粘着力が小さいという特性に着目し、安息角試験法を用いた簡易な安定性評価法を提案しています。この方法は、粘着力の無い粉体の評価に用いられてきた手法を廃棄物に応用したもので、長野県短期大学の土居洋一教授が考案したものです。安息角試験は、重機を用いて上方から廃棄物を撒きこぼし、形成された山の四方で安息角を計測することで行われます。静岡県での事例では、この安息角試験の結果に基づき、静岡県産業廃棄物協会伊豆支部が斜面勾配を36°以下とする暫定対策工事を平成26年7月に行いました。県は暫定対策後も行為者への全量撤去を求めており、カットされた廃棄物は現場内に敷き均されたため、場外搬出はありませんでした。この安息角試験法は、平地での廃棄物堆積事例に適用可能な簡易で低コストな対策として有効であると考えられています。本研究は平成26年度環境研究総合推進費補助金研究事業補助金の支援を受けて行われました。
VI.低濃度PCB廃棄物の無害化処理と大臣認定
低濃度PCB廃棄物の無害化処理に係る大臣認定を受けた事業者(例:エコシステム秋田、中部環境ソリューション、富士クリーン、杉田建材、神鋼環境ソリューション、光和精鉱など)とその処理方法(主に焼却)が紹介されています。処理能力や処理対象の多様性が示されています。これは、廃棄物処理業界の技術力向上と環境負荷低減への取り組みを示しています。
1. 低濃度PCB廃棄物処理の大臣認定
平成27年1月30日にはエコシステム秋田(株)、3月2日には中部環境ソリューション(株)と(株)富士クリーン、3月31日には杉田建材(株)、(株)神鋼環境ソリューション、光和精鉱(株)が、低濃度PCB廃棄物の無害化処理に関する大臣認定を取得しました。これら6社の認定内容に加え、平成27年3月末までに認定を取得した22事業者の概要が示されています。認定された事業者の処理方法は主に焼却であり、ロータリーキルン式焼却炉、固定床炉、流動床ガス化溶融炉など、様々な焼却設備が用いられています。処理対象となる低濃度PCB廃棄物には、低濃度PCB廃油、低濃度PCB汚染物、微量PCB汚染絶縁油など、様々な種類が含まれており、各事業者の処理能力も大きく異なります。この大臣認定は、低濃度PCB廃棄物の適正かつ効率的な処理を促進するための重要な施策です。
2. 低濃度PCB廃棄物の処理技術と課題
低濃度PCB廃棄物、特に微量のPCBを含む変圧器などの適正かつ合理的な処理技術に関する調査が行われています。この調査では、処理に必要な手順や課題が取りまとめられ、処理促進に資する検討が行われています。検討後の処理方法については、必要に応じて実証試験を実施し、得られた知見は現行の処理ガイドラインに反映して改訂される予定です。このことは、低濃度PCB廃棄物の処理技術の高度化と、処理ガイドラインの改善が継続的に行われていることを示しています。様々な事業者が大臣認定を取得していることから、低濃度PCB廃棄物の処理技術は一定のレベルに達しているものの、更なる効率化や安全性の向上が求められていることが示唆されます。処理能力や対象となる廃棄物の種類も多様であるため、今後も継続的な技術開発とガイドラインの見直しが必要でしょう。
VII.次世代型洗浄プラントと建設廃棄物処理
東京オリンピック開催に伴う建設廃棄物の増加に対応するため、高度洗浄リサイクル施設の整備が進められています。東京大学との共同研究により、建設泥土等の最適な洗浄方法の検討が行われ、マニュアル化を目指しています。これは産業廃棄物の適正処理とリサイクルに大きく貢献するものです。
1. 東京オリンピックと建設廃棄物処理の課題
2020年東京オリンピック・パラリンピック開催決定に伴い、東京湾岸エリアを中心に道路などのインフラ整備・開発が加速すると予測されています。これにより、大量の建設泥土などの産業廃棄物、埋設廃棄物、そして環境基準に適合しない重金属類を含む汚染土壌などが発生し、その適正処分が大きな課題となっています。大量発生が予測される建設廃棄物の処理・リサイクルのため、高度な洗浄技術を持つ次世代型洗浄プラントの整備が急務となっています。このプラントは、東京都のスーパーエコタウン事業の公募に採択され、現在整備が進められています。東京都は、首都圏の産業廃棄物問題の解決と循環型社会への変革を推進するために、この事業を推進しています。
2. 次世代型洗浄プラントの高度化と東京大学との共同研究
建設廃棄物の適正処理・リサイクルに貢献する次世代型洗浄プラントの整備にあたり、更なる処理技術の高度化が目指されています。具体的には、処理対象物に適した洗浄方法の検討、そして東京大学(藤田豊久教授、北垣亮馬講師)との共同研究による、受入対象物の物理性状・化学性状等の精密な分類と最適な洗浄方法の検討が行われています。この共同研究では、施設運用のマニュアル化も目指しており、これは、安定した高効率な廃棄物処理を実現するために不可欠な取り組みです。この次世代型洗浄プラントは、大量発生が予測される建設泥土等の適正な処理・リサイクルに大きく貢献すると期待されています。東京大学との共同研究は、学術的な知見と実践的な技術開発を融合させることで、より高度な洗浄技術の確立を目指しています。
VIII.福島県における産業廃棄物不法投棄対策
福島県では、東日本大震災と原子力発電所事故後の放射性物質による汚染廃棄物処理の促進と、産業廃棄物不法投棄の監視体制強化に力を入れています。これは、地域住民の不安解消と復興に不可欠な取り組みです。監視員の配置や監視カメラの活用、地域ぐるみの啓発活動などが行われています。
1. 東日本大震災後の汚染廃棄物処理と復興
東日本大震災と原子力発電所事故から4年以上が経過しましたが、放射性物質による汚染廃棄物の円滑な処理は、福島県の復興と環境回復にとって極めて重要です。そのため、福島県は市町村、国、関係団体、事業者等と連携し、処理の促進と地域住民の不安解消のための総合的な対策に取り組んでいます。具体的な対策として、汚染廃棄物の処理促進に向けた施策が継続的に実施されています。これは、放射性物質による環境汚染からの復興という喫緊の課題への取り組みを示しています。
2. 産業廃棄物不法投棄対策の強化と監視体制
産業廃棄物不法投棄の監視体制強化のため、福島県は様々な対策を実施しています。具体的には、各市町村に産業廃棄物不法投棄監視員、6地方振興局に産業廃棄物適正処理監視指導員(警察官OB)を配置し、各市町村独自の監視員、警察本部所管の産業廃棄物不法投棄ボランティア監視員などを活用した人的監視体制を整備しています。さらに、監視カメラによる日常的な監視体制の整備、地域ぐるみでの啓発や監視活動への支援などを通じて、県民総ぐるみで監視の輪を広げる取り組みを進めています。休日・夜間の監視業務は委託するなど、効果的な監視体制の構築に力を入れています。これは、不法投棄による環境破壊の防止と、地域社会の安全を守るための重要な取り組みです。
