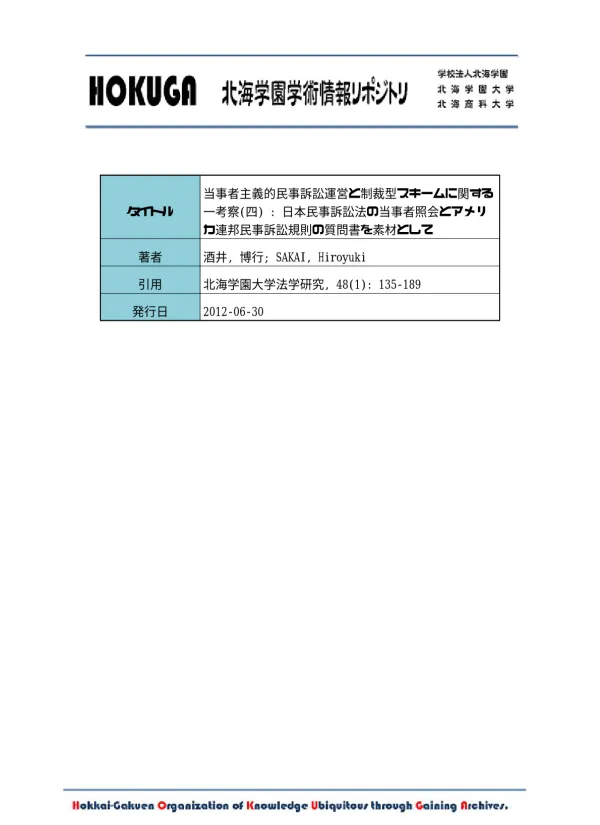
当事者主義と民事訴訟:照会制度の考察
文書情報
| 著者 | Sakai, Hiroyuki |
| 専攻 | 法学 (おそらく) |
| 文書タイプ | 論文 (おそらく) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 831.89 KB |
概要
I.当事者主義的民事訴訟運営と 当事者照会 の課題
本論文は、日本における民事訴訟における当事者主義と、特に当事者照会制度の運用上の問題点について考察しています。不当判決を防ぐためには、当事者の積極的な弁論権行使が不可欠ですが、現状では必ずしもそうはなっていない点が指摘されています。当事者照会は、当事者間の情報開示を促進し、訴訟の効率化・迅速化を目指した制度ですが、その実効性や濫用の懸念、回答義務の明確性など、様々な課題が提示されています。特に、訴訟資料提出義務との関係や、情報開示命令との整合性、準備書面における当事者照会の扱いなどが論点となっています。アメリカ連邦民事訴訟規則の質問書制度との比較検討も交えながら、当事者照会制度の改善策が模索されています。
1. 当事者主義と弁論権の行使
このセクションでは、民事訴訟における当事者主義の理念と、それに不可欠な弁論権の行使について考察しています。不当判決を回避するためには、当事者が積極的に弁論権を行使することが求められますが、現実には必ずしも積極的な行使が行われているとは限らないという問題点が指摘されています。具体的には、当事者が訴訟資料を提出できるという弁論権の積極的な側面の表現を促し、触発するという意味での当事者への協力という観点から、説明権行使を後退させるだけでは不十分であると論じています。さらに、弁論権不履行による不当判決に対する当事者の自己責任を問える前提条件も必ずしも整っているとは言い切れないと指摘しています。この問題は、当事者照会制度の有効活用と密接に関連しており、当事者の積極的な訴訟参加を促す方策が求められていることを示唆しています。裁判所による情報開示命令や回答命令の発出についても言及されており、当事者による積極的な情報開示を促す仕組みの必要性が示されています。
2. 当事者照会の濫用と制裁の問題
本セクションでは、当事者照会制度の濫用防止と、それに伴う適切な制裁について議論されています。具体的には、相手方が照会に応じない場合でも、そのことが弁論の全趣旨として斟酌されることで満足すべきであり、過剰な制裁は不要であるという意見が提示されています。しかし、同時に、具体的な濫用事例として、①具体的または個別的でない照会、②相手方を侮辱または困惑させる照会、③既にされた照会と重複する照会、④意見を求める照会、⑤相手方が回答するために不当な時間または費用を必要とする照会、⑥証言の拒絶事由などが挙げられています。これら具体的な濫用事例を明示的に列挙することで、当事者照会の濫用を抑制し、実効性を高めることを目指しています。また、回答義務を負う相手方の負担が過大になる可能性を指摘し、要証事実との関連性について裁判所のチェックが必要であると主張しています。さらに、訴訟費用負担による制裁では実効性に問題があるとの指摘を受け、より効果的な制裁方法の検討が不可欠であることが示されています。
3. 当事者照会の法的根拠と回答義務
このセクションでは、当事者照会制度の法的根拠、特に回答義務の有無について詳細な検討が行われています。当事者間に訴訟法的関係が成立していることを実質的根拠として、当事者間の回答義務を認めるべきであるという主張が展開されています。さらに、必要な訴訟手続に関連した情報を相手方から獲得できる情報請求権という概念を導入し、当事者照会制度は、この情報請求権を法的に明確化した制度であるという解釈が提示されています。一方、訴え提起前の照会については、立法者の解説中に回答義務に関する言及がないことを根拠に、回答義務がない旨を示唆する見解もあると指摘しています。 また、当事者照会における相手方の回答義務の根拠は訴訟当事者間の信義則にあるとされているものの、その信義則の具体的な内容は必ずしも明確ではないという点も指摘されています。従来の弁護士の実務慣行における情報開示のあり方と、当事者照会制度による変化についても論じられており、不利益となる情報を相手方に知らせないという従来の慣行からの転換を当事者照会制度が迫っているという見解が示されています。
4. 訴訟段階と当事者照会の可否
この部分では、訴訟の各段階における当事者照会の可能性について検討が行われています。訴状受領後、訴状送達までの間でも攻撃防御の準備を進めることに害はなく、むしろ有益であるという点を理由に、訴状受領と同時に当事者照会を行う可能性を認めるべきという意見が示されています。ただし、相手方は回答の有無、回答内容を自ら判断して決めればよいので、照会できる要件にあまり制約をかける必要もないという意見も提示されています。 また、裁判所に訴状送達の有無をいちいち問い合わせてから照会を行うべきとすることに合理性・必要性があるとも考えられないと述べています。さらに、控訴審判決までの弁論再開の可能性や上告後差戻しの可能性も考慮し、控訴審の口頭弁論終結後、上告審判決確定までの照会も可能とするべきであるという意見も提示されています。 準備書面による照会については、手続きを明確にするため避けることが望ましいものの、当事者照会としての効力を否定することは困難であると述べられており、積極的な肯定説ではないと判断されています。
II. 当事者照会 の運用と制裁
当事者照会の濫用を防ぎ、実効性を高めるための制裁についても議論されています。訴訟費用負担などの制裁では実効性に欠けるため、より効果的な制裁方法の検討が求められています。照会の内容や方法についても、具体例を挙げながら適切な範囲や限界が検討されており、要証事実との関連性、相手方への負担、私生活の侵害などを考慮する必要があるとされています。回答義務の有無、回答を強制する際の法的根拠、そして弁護士の役割や倫理的な責任についても深く掘り下げられています。 弁護士は当事者照会において重要な役割を担っており、その倫理的な責任の明確化が重要であると指摘されています。
1. 当事者照会の濫用防止と適切な制裁のあり方
このセクションでは、当事者照会制度の運用における濫用問題とその対策、特に効果的な制裁について論じています。 相手方が照会に応じない場合の対応として、弁論の全趣旨を斟酌することで対応可能であり、必ずしも制裁が必要ではないとする見解が示されています。しかし、照会が具体的でない、相手方を侮辱・困惑させる、重複する、意見を求める、不当な時間・費用を要する、あるいは証言拒絶事由に該当する場合などは、濫用とみなされる可能性が高いと指摘されています。これらの濫用事例を明確に列挙することで、当事者照会制度の適切な運用を促し、濫用を抑制する方策が模索されています。また、裁判所の関与なしに照会が行われる現状では、回答義務を負う相手方の負担が過大になる可能性があるため、要証事実との関連性について裁判所のチェックが必要であるという意見も提示されています。従来提案されていた訴訟費用負担による制裁では実効性に欠けるとの指摘から、より効果的な制裁方法の検討が求められていると結論付けられています。
2. 回答義務の根拠と弁護士の倫理的責任
当事者照会における回答義務の法的根拠と、弁護士の役割、倫理的責任についても考察されています。当事者間で訴訟法的関係が成立していることを回答義務の根拠とする一方、訴え提起前の照会については、立法上の解説に回答義務に関する言及がないため、回答義務がないとする見解も存在すると指摘しています。 さらに、訴訟当事者間の信義則を回答義務の根拠とする見解があるものの、その具体的な内容は必ずしも明確ではないと述べています。弁護士の倫理的な責任に関しては、代理人弁護士が依頼者である被照会者に対して回答義務を尽くさせ、主観的真実と異なる回答をさせないように働きかける倫理的義務があるとされています。 これは、従来の弁護士の実務慣行、すなわち不利益な情報を相手方に知らせないという姿勢からの転換を促すものであり、当事者照会制度が弁護士の訴訟観に変化を迫るものであると指摘しています。弁護士会による懲戒など、具体的な対応策についても言及されています。
3. 当事者照会の実効性と今後の課題
このセクションは、当事者照会制度の実効性、特にその利用状況の低調さ、そして今後の課題について論じています。 現行法施行後も、当事者照会の利用状況は極めて低調であると報告されており、多くの弁護士が当初期待したような効果がないため、熱意を失いつつある現状が示されています。 当事者照会制度の利用状況の低調は、制度の失敗を示唆するものであり、その原因として、弁護士の認識不足や制度の複雑さなどが挙げられています。 これらの問題を解決するためには、制度の明確化、弁護士への教育、そして当事者の意識改革が不可欠であると結論づけており、当事者照会制度の改善に向けた課題が明確に示されています。 準備書面による照会方法についても、手続きの明確化のため避けるべきであるものの、当事者照会としての効力を完全に否定することは困難であるとされています。
III. 当事者照会 の現状と今後の展望
当事者照会制度の利用状況は現状では低調であり、期待された効果が得られていないという現状認識が示されています。その原因として、弁護士の認識不足や、制度の複雑さなどが挙げられています。訴え提起前の照会、訴状受領後の照会、控訴審における照会の可否についても議論されており、制度の運用に関する様々な問題点が指摘されています。当事者照会制度の改善には、制度の明確化、弁護士に対する教育、そして当事者の意識改革が不可欠であると結論付けられています。 新民事訴訟法の施行後も、当事者照会制度の課題は依然として残っており、更なる改善策が求められています。
1. 当事者照会制度の現状と課題
このセクションでは、当事者照会制度の現状と、その運用における課題について分析しています。 論文では、当事者照会制度の利用状況が極めて低調であると指摘し、当初期待された効果が得られていない現状を問題視しています。多くの弁護士が、当事者照会制度に当初期待したような効果がないため、熱意を失いつつあると述べられています。この低調な利用状況は、当事者照会制度そのものの失敗を意味する可能性があるとさえ示唆されています。 訴訟の各段階(訴状受領前、訴状受領後、控訴審など)における当事者照会の可否についても議論されており、訴状受領と同時に当事者照会を行う可能性や、控訴審判決後、上告審判決確定までの照会可能性などが検討されています。 準備書面による照会についても言及されており、手続きの明確化のため避けるべきとする見解と、当事者照会としての効力を否定するのは困難であるとする見解が示されています。裁判所の関与を極力避け、当事者主導で効率的に情報収集を行うことを目的とする当事者照会制度の現状と課題が、多角的に分析されています。
2. 弁護士の役割と倫理的責任の再考
当事者照会制度の現状分析において、弁護士の役割と倫理的責任の再検討が重要な論点となっています。当事者照会制度は、弁護士の従来の訴訟観に大きな変化を迫るものであり、弁護士の倫理的な責任がより明確にされる必要性が強調されています。代理人弁護士は、依頼者である被照会者に対して、回答義務を尽くさせ、主観的真実と異なる回答をさせないように働きかける倫理的義務を負うとされています。 この責任を果たすための具体的な行動規範やガイドラインの提示が求められており、弁護士倫理や弁護士職務基本規程との関連性も深く検討されています。 また、代理人弁護士が回答義務に違反した場合、弁護士会による懲戒などの必要な措置が取られるべきであると述べられています。当事者照会制度の有効活用には、弁護士の倫理観と制度理解の深まりが不可欠であることが示唆されています。 特に、当事者照会制度が従来の弁護士の訴訟観を変革させるものである以上、弁護士倫理の面からの検討が重要であると強調されています。
3. 当事者照会制度の改善に向けた展望
このセクションでは、当事者照会制度の現状における問題点を踏まえた上で、今後の改善策や展望について論じています。 当事者照会制度の利用状況の低調や期待された効果の不足を克服するために、制度の明確化、弁護士への教育、そして当事者の意識改革が不可欠であると結論づけています。 具体的には、制度の複雑さや弁護士の認識不足といった問題点を解決し、当事者が積極的に制度を活用できるような環境整備が必要であると主張しています。 また、訴訟の各段階における当事者照会の可否について、より明確なガイドラインを示すことで、制度の運用をスムーズにする必要性が指摘されています。 さらに、アメリカ連邦民事訴訟規則の質問書制度との比較検討なども行われ、日本における当事者照会制度の更なる改善と発展のための具体的な方向性が模索されています。 全体的に、当事者主導の制度として構築された当事者照会制度の更なる発展のために、制度の運用における課題解決と、関係者全体の意識改革の必要性が強調されています。
