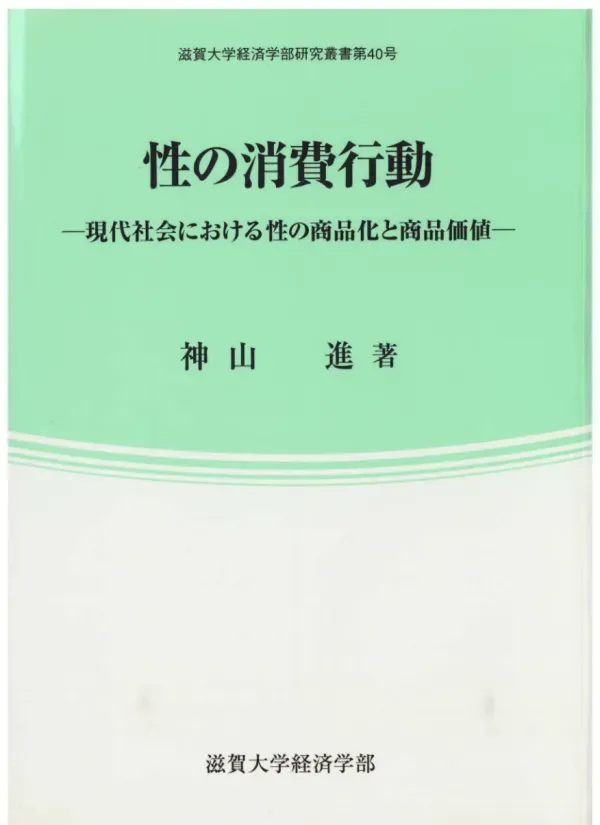
性の消費行動:商品化と商品価値
文書情報
| 著者 | 神山 進 |
| 学校 | 滋賀大学経済学部 |
| 専攻 | 経済学 |
| 出版年 | 平成14年 (2002年頃) |
| 文書タイプ | 研究叢書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.80 MB |
概要
I.製品とジェンダー 知覚された性とマーケティング戦略
様々な製品には消費者に知覚される性が存在する。企業のマーケティング戦略、特に広告ではジェンダーが巧みに利用される。従来の女性像は、若く、美しく、男性に依存するイメージで描かれてきたが、フェミニズムの影響で女性の役割や権利の拡大が求められるようになった。このジェンダー描写は、製品のポジショニング戦略に大きく影響する。
1. 知覚された性と製品
本研究では、様々な製品に消費者が知覚する性(perceived gender)が存在することが示唆されている。これは、企業のマーケティング戦略において重要な要素であり、特に広告戦略においては、この知覚された性を巧みに利用することで消費者の購買意欲を高めることが試みられている。調査結果では、製品とジェンダーの帰属を分析することで、消費者がどのように製品に性的な意味づけを行っているのかを明らかにすることが目的である。このジェンダーの知覚は、製品のポジショニングやブランドイメージの構築に大きく影響を与えるため、マーケティング担当者にとって、製品にジェンダーをどのように付与し、消費者に訴求するかという戦略は非常に重要な要素となる。
2. 従来の広告における女性像とフェミニズム
従来の広告において、女性はしばしば特定のジェンダー役割に限定されたステレオタイプ的なイメージで描かれてきた。具体的には、若く、スリムで美しく、男性の庇護を必要とする存在、家事に専念し、消費財の購買者という役割が強調されてきた。しかし、このステレオタイプな女性像は、フェミニズム(feminism)運動によって批判の対象となり、女性の役割や権利の拡大を目指す動きが強まっている。これらの社会的な変化は、広告におけるジェンダー描写に大きな影響を与え、より多様で現実的な女性像を求める声が高まっている。フェミニズムの台頭は、ジェンダー平等意識の高まりと、女性を対象とした消費市場における新たなニーズの喚起につながっている。
3. 製品ポジショニング戦略とジェンダー アイデンティティ
女性市場における製品のポジショニング戦略には、「伝統的」と「現代的」の2つのアプローチがある。伝統的なアプローチは、家庭に重きを置く女性をターゲットに、家族や家庭に関連する製品を訴求する。一方、現代的なアプローチは、職場と家庭の両方で活躍する女性をターゲットに、キャリアと両立できる製品を訴求する。興味深いことに、ジェンダー・アイデンティティ(gender identity)が強い女性は、自分のジェンダーアイデンティティと一致する製品ポジショニングの広告に、より好意的な反応を示す傾向がある。これは、ジェンダーアイデンティティに合致した商品情報は、より容易に処理され、肯定的に想起されやすいことを示唆している。しかし、この関係性は商品カテゴリーによって異なる場合もある。例えば、家事関連商品においても、消費者の自己概念(self-concept)と深く関わるものでない場合は、ジェンダーアイデンティティとは関係なく、伝統的なポジショニングを好む女性も存在する。
4. ジェンダー描写への反応と消費者の意識
女性に関するジェンダー描写に対する消費者の反応には、個人差がある。フェミニストは、教育水準が高く、女性像のジェンダー描写に敏感で、現代的な働く女性を強調する広告を好む傾向がある。一方、伝統的なジェンダーステレオタイプを保持する伝統主義者は、そうではない。この差は、個人のジェンダーに対する意識や価値観、伝統的な社会構造からの自律意識の強さなどに起因する可能性がある。広告のような社会的刺激に対する感受性は、個人のジェンダー意識や社会的な立場によって大きく異なり、広告効果を検討する際には、ジェンダーアイデンティティだけでなく、消費者の心理的な要因を理解することが重要となる。特に、伝統的な社会構造からの自律を強く表明する人ほど、広告に描かれた役割期待に敏感に反応するだろう。
II.広告におけるジェンダー描写 アメリカ映画と国際比較
近年のアメリカ映画における女性ヒロインは、男らしい消費行動(喫煙、飲酒、自動車運転など)を繰り返し、女らしい消費行動(メイク、ドレス着用など)を避け、ジェンダーの役割を逆転した描写がなされている。オーストラリア、メキシコ、アメリカのテレビ広告を比較した研究では、女性は若く未婚で非労働者、男性は中高年で就労者のイメージが共通し、ジェンダーによる役割分担が確認された。
1. アメリカ映画における女性ヒロインの消費行動分析
近年の3つのアメリカ映画(エイリアン、ターミネーター2、セルマ&ロイス)を分析した研究では、女性ヒロインの消費行動に注目している。これらの映画では、女性ヒロインが伝統的に女性とみなされる商品を一切使用せず、喫煙、飲酒、自動車運転、銃器使用など、一般的に男性的なとされる商品や行動を繰り返し選択していることが示されている。この分析は、映画におけるジェンダー描写と消費行動の関連性を示しており、ジェンダー規範を覆すような表現が、消費行動にも反映されている可能性を示唆している。男性的な消費行動と女性的な消費行動という対比を通して、映画が意図的にジェンダーの役割を逆転させている描写が、消費行動にまで影響を与えている点が注目される。
2. 国際比較 オーストラリア メキシコ アメリカのテレビ広告
オーストラリア、メキシコ、アメリカの3ヶ国のテレビ広告をジェンダー描写の観点から比較分析した研究が紹介されている。広告に含まれる製品カテゴリー、ユーザー、ナレーターの声、撮影場所などの広告情報と、登場人物の性別、年齢、職業、結婚状況、役割、活動状況などの登場人物情報が分析対象となっている。分析の結果、3ヶ国共通して、広告に登場する女性は35歳以下が大半で、男性は35~50歳が多いという傾向が見られた。また、女性は雇用されていない人が多く、男性は就業中の人が多い傾向が示されている。さらに、女性は他者に依存した役割、男性は自立した役割を演じることが多いことが明らかになった。アメリカとメキシコでは、女性は製品使用者としての信憑性で、男性は専門家としての権威で製品への信頼性を示す傾向が高いという共通点も確認されている。この比較研究は、ジェンダーステレオタイプが広告にどのように反映されているのかを、国際的な視点から明らかにしている。
III.男性像の変化と現代広告
1980年代以降、男性像は「断固たる男」から「迷える男」へと変化し、広告におけるジェンダー表現も変化を遂げている。現代の男性広告イメージは多様化しつつあるが、依然として伝統的男性像、専門的男性像、現代的男性像の3つのタイプに分類できる。
1. 1980年代以降の男性像の変化
1980年代以降、男性像は従来のステレオタイプ的なイメージから大きく変化を見せている。従来、男性は断固として決断力があり、有能で尊敬され、リーダーシップを発揮する存在として描かれてきた。しかし、近年の広告では、決断に迷う男性、能力不足の男性、敬意を得られない男性、フォロワーとしての男性といった、従来とは異なる弱みや曖昧さを含んだ男性像が描かれるようになっている。この変化は、女性が経済力や社会的な力を得るようになったことと関連している。男性も、女性と同様に、身体を露出したり、性的対象として描かれることが多くなった。1990年代以降もこの傾向は継続しており、現代の広告における男性イメージは、多様化し複雑化していると言える。このジェンダー表現の変化は、広告戦略においても、新たな表現方法の模索を促している。
2. 現代広告における男性イメージの類型化
現代の広告における男性イメージは、多様化しているものの、いくつかの類型に分類できる。研究においては、少なくとも6つのタイプが指摘されている。これらのタイプは、従来のステレオタイプ的な「男らしさ」から脱却した表現や、ジェンダー役割の変容を反映していると考えられる。それぞれのタイプは、特定の商品カテゴリーや広告戦略と結びついており、消費者のジェンダーに関する認識や価値観の変化を反映している。また、男性主人公に対する描写期待を調査した研究では、「伝統的男性像」、「専門的男性像」、「現代的男性像」の3つの類型が区別された。これは、広告におけるジェンダー表現が、時代とともに変化し、多様化していることを示している。伝統的男性像は、従来から続くステレオタイプ的なジェンダー役割を踏襲したものであり、一方、現代的男性像は、家事や育児を行う男性など、従来には少なかった男性像を含んでいる。
IV.女性のタイプと消費行動
女性像は、処女マリア型、誘惑者イブ型、貴婦人型、性的対象型に分類できる。ジェンダーアイデンティティが強い女性は、男らしさを強く自覚する女性ほど年齢が若く、独身で専門職に就いている傾向にある。伝統的ポジショニングと現代的ポジショニングの広告に対する反応は、消費者のジェンダー・アイデンティティと関連している。
1. 女性像の類型化 4つのタイプ
本研究では、広告等で描かれる女性像を4つのタイプに分類している。一つ目は「Virgin Mary型」で、母性や人間への愛情を強調し、性的魅力は控えめなタイプである。家庭や家族に責任を持つ無私無欲な母親や妻として描かれることが多い。二つ目は「Tempter Eve型」で、高い魅力度を持ち、男性を危険に誘い込むような女性像である。酒、香水、化粧品などの広告によく登場する。三つ目は「Courtly Lady型」で、裕福で高い地位を持ち、美しさや優雅さで称賛されるタイプである。高級品やリゾートなどの広告に多く見られる。そして四つ目は「Sex Object型」で、自立した力を持たず、男性の力に依存し、性的対象として男性に見つめられる女性像である。性的な要素を強調した広告に頻繁に登場する。これらの類型化は、広告におけるジェンダー表現が多様であることを示しているが、同時に、ステレオタイプ的なイメージも依然として存在することを示唆している。
2. ジェンダー アイデンティティと消費行動 自己認知と広告反応
ジェンダーアイデンティティ(gender identity)の自己認知が強い女性は、消費行動においても特徴的な傾向を示す。女らしさの自己認知が強い女性は、高年齢で既婚、子供持ち、低賃金の仕事に就いている傾向が高い。一方、男らしさの自己認知が強い女性は、若年で独身、専門職に就いている傾向が高い。広告への反応もジェンダーアイデンティティと関連している。男らしさの自己認知が強い女性は、現代的なポジショニングの広告に好意的な反応を示し、女らしさの自己認知が強い女性は、伝統的なポジショニングの広告に好意的な反応を示す傾向がある。このことは、消費者のジェンダーアイデンティティと一致する商品情報は、より容易に処理され、肯定的に評価されやすいことを意味している。しかし、この関係性は、商品カテゴリーや個人の自己概念(self-concept)にも影響を受けることが示されている。
V.服装とジェンダー 外見と消費行動
服装はジェンダーを明確に示す重要な記号である。伝統的に男性は地味な服装、女性は華やかな服装が好まれたが、現代ではジェンダーの境界が曖昧になりつつある。男らしさ・女らしさの自己認知と服装へのこだわりには関連性があることが示されている。
1. 服装とジェンダーの表現
服装はジェンダーを表現する重要な記号として機能する。アメリカのカウボーイ風ファッションは男性らしさを象徴し、若い男性に好まれる傾向がある一方、伝統的なビジネススーツも知性と男性らしさを象徴する記号として受け止められている。一方、女性の服装は、レースやリボン、明るい色使いなど、繊細で華やかなイメージがジェンダーステレオタイプとして定着している。しかし、近年のジェンダー意識の変化に伴い、働く男女の服装や外見におけるジェンダーの境界は曖昧になりつつある。このことは、消費行動においても、ジェンダーによる服装の選択が必ずしも明確ではないことを示唆している。ジェンダー表現における多様化は、消費市場におけるジェンダーニュートラルな製品やサービスの需要増加へとつながっている可能性がある。
2. 服装におけるジェンダー コードの分析
本研究では、ジェンダーをコード化した服装の特徴を分析している。女性においては、重い素材、角ばった形、パンツスタイル、ダークカラーなどは男らしい特徴として、レースやフリル、ロングヘア、明るい色使いなどは女らしい特徴としてコード化されている。男性においては、宝石などのアクセサリー、ちょうネクタイ、ロングヘアなどが女らしい特徴、ダークカラー、濃い色、ひげなどが男らしい特徴としてコード化されている。これらのコード化された特徴は、ジェンダーによる服装のステレオタイプを明確に示している。しかし、社会におけるジェンダーの変化に伴い、これらのステレオタイプ的なジェンダー表現が、必ずしも明確に区別されない状況も生じている。つまり、消費行動において、ジェンダーを明確に示す服装の選択は、必ずしも普遍的なものではないと言える。
3. 男らしさとファッション おしゃれとジェンダー アイデンティティ
伝統的に、男性らしさとオシャレは相容れないものと考えられてきた。男性の服装は、地味なスーツとネクタイに代表されるように、非常に限定的な範囲に収まっていた。この限定された服装は、男性のジェンダーアイデンティティの確認と強化に役立ってきた。しかし、ジェンダーステレオタイプに基づく服装規範からの逸脱は、男性にとって、しばしば容認されないことだった。研究によると、男らしさを強く内在化させた男性は、女性的な男性に比べて、ジェンダーステレオタイプに基づく服装規範を重視し、オシャレに消極的な傾向があることが示されている。一方、女らしさを強く内在化させた女性は、男性的な女性に比べて、服装規範をあまり重視せず、オシャレに積極的な傾向を示している。このことは、ジェンダーアイデンティティと消費行動、特にファッションに関する消費行動との間に強い関連性があることを示している。
VI.身体イメージと消費 スティグマと理想体型
理想体型への追求は、消費行動を促進する。筋肉質の男性、すらっとした女性の体型は好意的に評価される一方、スティグマ(社会的に受け入れがたい属性)を負った人々は不利益を被りやすい。消費を通して理想的な身体イメージを獲得しようとする動きが確認できる。
1. 服装によるジェンダー表現
服装はジェンダーを表現する重要な視覚的記号として機能する。アメリカにおけるカウボーイスタイルは、男性らしさ、開拓者精神といった価値観と結びつき、若い男性を中心に好まれている。また、伝統的なビジネススーツは、知性や男性的なプロフェッショナリズムを象徴する記号として認識されている。一方、女性の場合、レースやフリル、淡い色使いといった要素は、女らしさや繊細さを表現する記号として機能してきた。しかし、現代社会では、ジェンダーの境界が曖昧になりつつあり、消費行動における服装の選択も多様化している。つまり、ジェンダーステレオタイプ的な服装は必ずしも普遍的なものではなく、個人のジェンダーアイデンティティや自己表現の手段として、消費されていると言える。
2. ジェンダーコードと服装の特徴
研究では、ジェンダー表現に関する服装の特徴をコード化して分析している。女性の場合、重い素材や角張ったデザイン、パンツスタイル、ダークカラーなどは「男らしい特徴」として、レースやフリル、ロングヘア、明るい色使いなどは「女らしい特徴」として分類されている。男性の場合、「女らしい特徴」としては、宝石やアクセサリー、ちょうネクタイ、ロングヘアなどが挙げられ、「男らしい特徴」としては、ダークカラー、濃い色、ひげなどが挙げられている。これらのジェンダーコードは、社会的に共有されたジェンダーステレオタイプを反映している。しかし、現代社会のジェンダー意識の変化に伴い、こうしたコードは必ずしも明確に機能しておらず、消費行動においては、ジェンダーを超越した服装の選択も増えている。
3. 理想体型と消費行動 スティグマと社会的不利益
筋肉質で引き締まった体型や、すらっとした美しい体型は、社会的に好ましい身体イメージとされている。そのため、そのような体型を維持・獲得するために、エステティックやフィットネスなどのサービスが利用され、関連商品が消費されている。しかし、この理想体型からの逸脱は、社会的不利益につながる可能性がある。社会的に受け入れられない属性を指す「スティグマ」は、外見上の特徴によっても生じる。特に、消費行動においては、理想体型への強い憧憬と、スティグマを回避しようとする意識が、消費行動を大きく左右している。このことは、消費が、個人の自己肯定感や社会的な適応と深く結びついていることを示唆している。理想体型の追求は、消費社会における重要なジェンダー規範の一つであり、消費行動を分析する上で考慮すべき重要な要素と言える。
VII.性の商品化と過剰消費
日本の性風俗産業の隆盛は著しく、多様な性商品が氾濫している。セックスの商品化は、消費文化において重要な役割を果たしている。エロティシズム(性愛)は根源的に過剰消費され、性の過剰消費は誰の目にも明らかな社会現象である。ロマンス小説は、社会的に許容されるソフト・ポルノの一形態と言える。
1. 性の産業と過剰消費の実態
現代社会では、セックスの商品化が著しく進んでいる。日本の性風俗産業の隆盛は顕著で、ソープランド、ストリップ劇場、個室ビデオ、ラブホテルなど、様々な形態の性商品やサービスが溢れている。セックス関連商品は、避妊具や避妊薬といった実用品から、性玩具、挑発的な下着、香水など、多岐に渡る。売春禁止法が存在するにも関わらず、売春やそれに類するサービスが暗黙裏に容認され、商品化されている現状がある。これらの事実は、セックスが種の保存という生物学的機能を超えて、消費社会において記号的な意味を持つようになっていることを示唆している。エロティシズム(eroticism)を抜きにした消費文化はあり得ないと言えるほど、セックスは現代社会の消費文化に深く浸透していると言える。このセックスの過剰消費は、既存の社会規範への課題を提示している。
2. ロマンス小説とソフトポルノ 社会的に許容される性の消費
社会的に受け入れやすく、脅迫的な要素を含まないソフトポルノの一形態として、ロマンス小説(romance)がある。ソープオペラ、エロチックロマンス、ヒストリカルロマンスなどが含まれ、恋愛や求婚を主要なテーマとする。ロマンス小説は、女性を主人公とし、ヒロインの肉体的純潔を保ったまま幸せな結婚に至る物語が多い。性行為そのものは描かれず、結婚という枠組みの中でセックスの存在可能性を示唆している。エロチックロマンスの読者と非読者を比較した研究では、読者は非読者よりも若く、積極的な性生活を送っており、性的な満足を得るために性的空想を積極的に利用している傾向が見られた。このことは、ロマンス小説が、消費者の性的な空想や欲望を満たす役割を果たしている可能性を示唆している。ロマンス小説は、社会的に許容された形でセックスを消費する手段の一つとして機能していると言える。
VIII.サブリミナル広告とセックスアピール
サブリミナル広告の効果については議論があるものの、特にセックスに訴える広告は消費者の潜在意識に影響を与え、購買意欲を高める可能性が指摘されている。マスメディアによるサブリミナルな操作が懸念されており、セックスと結びつけることで商品の価値を高める試みがなされている。
1. サブリミナル広告の効果に関する相反する見解
サブリミナル広告の効果については、肯定的な見解と否定的な見解が混在している。否定的な見解としては、サブリミナル広告が実際にはほとんど実施されていない、もしくは実施されていても効果がないとする研究結果がある。これらの否定的な見解は、サブリミナル広告の効果を測定するための標準化された基準が不足していることや、「サブリミナル」という用語の定義の曖昧さを指摘している。しかしながら、従来から、サブリミナルな知覚が情緒的な反応に影響を与えたり、消費者の渇望感に影響を与えたり、製品ブランドの評価に影響を与えたりする可能性を示唆する研究結果も存在する。近年の研究では、サブリミナル広告は態度や購買意欲よりも、むしろ感覚に影響を与える可能性が高いとされている。これらの相反する研究結果は、サブリミナル広告の研究における課題を示していると言える。
2. キイの主張 マスメディアによるサブリミナル操作の可能性
キイの著書は、サブリミナル広告、特にセックスアピールを用いたサブリミナル広告に焦点を当てている。キイは、サブリミナルな埋め込みが問題となる過程で、マスメディアがサブリミナルな操作を通して、消費者の行動に影響を与え、操作・支配する潜在的な力を有しているという主張をしている。キイによれば、消費者はマスメディアや商業広告の潜在的なメッセージによって無意識のうちに操られ、その影響は、夢、記憶、意識、感情、衝動など、人間の様々な側面に及ぶという。また、マスメディアはサブリミナル技法を用いることで、人間の行動を変化させる強力なシステムへと進化しつつあり、特に人間の最も強い衝動である性衝動と結びつけることで、商品の価値に感情的な意味を与えることができると主張している。特にセックスに訴えるサブリミナル広告が、消費者の潜在意識に働きかける可能性が指摘されている。
3. セックスアピールとサブリミナル広告効果 今後の研究課題
セックスに訴えるサブリミナル広告が、実際に肯定的な広告効果をどの程度もたらすのかについては、現時点では結論が出ていない。サブリミナルな埋め込みの効果は、埋め込みの内容、広告製品の種類、表現方法など、多くの要因に依存する。セックス関連の埋め込みが効果を発揮するのは、埋め込みの内容と広告製品・メッセージとの間に高い適合性がある場合である可能性が高い。フロイト精神分析理論は、この適合性に関する情報を提供していないため、埋め込みの内容と広告製品のタイプとの相互作用を明らかにする必要がある。今後、潜在意識レベルの情報処理メカニズムをより深く理解することで、サブリミナル広告の効果をより正確に評価できるようになる可能性がある。さらに、広告における隠された言葉や絵、音だけでなく、エキストラの配置や表情、姿勢、服装、小道具の配置など、広告における様々な要素の潜在的な影響力を考慮する必要がある。
IX.恋愛とギフト贈与 消費者行動と関係構築
恋愛におけるギフト贈与は、消費者とモノの関係、そしてコミュニケーションを象徴する。バレンタインデーやホワイトデーのギフト交換は、ロマンチック・ラブの表現であり、男女間の意味づけに差異がある。ギフトの選択は、贈与者と受取人の関係性や社会的役割によって影響を受ける。
1. 恋愛における 消費者 モノ 関係とギフト贈与
恋愛関係においては、「消費者−モノ」関係が重要な役割を果たす。相手への好意を高めるためにプレゼントを選ぶ行為は、愛を得るための手段として消費行動が利用されていると言える。バレンタインデーやホワイトデーにおけるギフト交換は、愛を示したり、確認したりするための典型的な例である。現代社会の恋愛におけるギフトは、愛のシンボルとしての側面を持つ一方、経済的な要素も無視できない。ギフトに対する期待や、費用の収支への関心は、恋愛関係の安定性と関連している可能性がある。つまり、恋愛関係が安定しているほど、経済的な計算よりも愛情表現が重視される傾向が見られる一方で、不安定な関係では、経済的な要素がより強く意識される可能性がある。
2. ギフト選択戦略 贈与相手との関係性と社会的役割
ギフト贈与においては、贈る相手によって、ギフトの選択が容易なものと困難なものがある。親しい友人や子供への贈り物選びは容易だが、義理の両親や祖父母への贈り物選びは困難であることが多い。これは、贈与者と受取人との間の親近性やコミュニケーションの程度に依存する。ギフト選択は、贈与者が贈与相手に対して担う社会的役割(喜びを与える、物を供与する、償いをする、交際を促進する、感謝を表すなど)によって影響を受ける。困難な相手へのギフト選択では、過去の成功例を参考にしたり、相手と相談したり、人間関係を確認できるようなギフトを選んだりするなど、様々な戦略が用いられる。このことは、ギフト贈与が、単なる物品の交換ではなく、人間関係の構築や維持に重要な役割を果たす消費行動であることを示唆している。
3. バレンタインデーとホワイトデー 男女間の意味づけの差異
バレンタインデーとホワイトデーにおけるギフト交換は、男女間で意味づけに違いがあることを示す。バレンタインデーのギフトは、コミュニケーションを図るための戦略的な側面が強い。しかし、ホワイトデーのギフトは、お返しとしての性格が非常に強い。そのため、男性は、バレンタインデーのギフト交換に比べて、ホワイトデーのギフト交換に対して、より戸惑いや複雑な感情を抱きやすい。米国の研究では、男性がバレンタインデーのギフト交換に参加することに対して、喜びや愛情だけでなく、失望、罪悪感、怒りなどの感情が入り混じり、参加を否定的に捉える心理的圧力も存在することが報告されている。このことは、日本においても、バレンタインデーとホワイトデーのギフト交換は、消費行動としてだけでなく、男女間のコミュニケーションや関係性の構築において重要な意味を持つことを示唆している。
X.外見の印象管理と消費 出会い デート 消費行動
出会いやデートの成功には、消費が重要な役割を果たす。服装、化粧品、美容用品などの利用は、外見の印象管理と深く関わっている。消費を通して、恋愛関係を築いたり、関係を維持しようとする行動が確認される。
1. 外見の印象管理と消費行動
現代社会では、出会いやデートの成功のため、外見の印象管理が重視される。そのため、衣料品、化粧品、美容用品など、外見を磨くための様々な商品が消費されている。服装のカラーコーディネート、ペアルック、メイク、ヘアスタイル、香水、歯のホワイトニング、ダイエット商品、ネイルアート、美容整形など、消費者は様々な手段を用いて外見を演出している。これらの消費行動は、相手に好印象を与えたり、魅力を高めたり、自己肯定感を向上させたりといった目的意識に基づいている。消費を通して、理想とする外見を実現し、恋愛関係を構築・維持しようとする消費行動が確認できる。
2. 出会い デートを促進する消費行動
出会い、デートを成功させるためには、コミュニケーションや移動手段、デートの場といった要素が重要となる。携帯電話やメールなどのコミュニケーションツール、自動車やバイクなどの移動手段、食事や合コン、アルコール飲料といったデート促進手段、カラオケボックスや映画館、遊園地、ショッピングスポットといったデートの場、そしてデートにおける様々なアクティビティなどが、消費の対象となる。さらに、マッチングアプリや出会い系サービス、結婚相談所といった、出会いや結婚を目的としたサービスも、消費市場において重要な位置を占めている。これらの消費行動は、恋愛関係の成立や発展を促進するための手段として捉えることができる。つまり、消費を通して、恋愛関係という目標達成を目指す消費行動と言える。
XI.離婚と消費 自己概念の再構築と消費行動
離婚は自己概念の不安定化をもたらし、ストレスや否定的感情の克服のため、様々な消費行動がとられる。離婚経験者は、新しいライフスタイルの構築に向け、消費者としてのスキルを磨こうとする。
1. 離婚による自己概念の不安定化と消費行動
離婚は、夫・妻という役割からの離脱を意味し、一時的に自己概念を不安定にする可能性がある。この不安定な状態から生じるストレスや否定的感情を克服するために、様々な消費行動が観察される。具体的には、将来への備えとして、財産やスキル、生活資源の整理といった消費行動が見られる。また、これまで共有してきた消費経験の整理や、思い出の詰まった所有物の整理なども含まれる。さらに、心地よく過ごせる個人的な居場所の確保のための消費行動も確認できる。離婚は、従来の社会構造からの脱却を意味し、新しいライフスタイルを探求する段階である。この過程において、消費は、自己確認や自己実現のための手段として機能すると考えられる。
2. 離婚後の自己再構築と新しい消費者スキル
離婚という転換期において、個人の自己確認は重要な課題となる。そして、その自己確認のプロセスにおいて、新しい消費者スキル、つまり消費者としての能力の習得が重要な役割を果たすと考えられる。消費は、単にモノの購入や所有にとどまらず、コミュニケーションや自己表現、アイデンティティの構築といった多様な意味を持つ。離婚後、新しいライフスタイルを築き、自己の可能性を探求する中で、消費者は自身のアイデンティティを反映する消費行動を選択する。この消費行動は、単に物欲を満たすだけでなく、新しい社会構造への適応や、自己肯定的なアイデンティティの再構築に貢献する。つまり、離婚という大きな変化を経験した個人が、消費を通して自己を再定義し、新しい生活を築いていく過程において、消費が重要な役割を果たすと言える。
XII.消費の意味 文化的 象徴的意味と個人的解釈
消費は、モノの機能性だけでなく、文化的/象徴的意味を持つ記号的な行為である。ボードリヤールの理論に基づき、消費されるモノは記号になるという視点から分析されている。消費の意味は、社会的文脈や個人的経験によって異なって解釈される。
1. 消費の意味 機能性から記号性へ
現代の消費は、モノの機能的な使用や所有を超えた意味を持つ。消費されるモノは、その社会的意味や記号的な価値によって評価される。これは、人々が他者との差異化を強く求めるようになったことと関連している。ボードリヤールの有名な言葉「消費されるモノになるためには、モノは記号にならなくてはならない」は、この点を端的に示している。消費は、もはや個人の権威づけやステータスを示す手段にとどまらず、多様な社会的意味を内包した記号体系として捉える必要がある。個人が消費する商品は、その商品の機能性のみならず、記号としての意味合いも持ち、個人のアイデンティティやライフスタイルを表現する手段として機能する。
2. ボードリヤールの 物の記号化の道筋
ボードリヤールは、「物の記号化の道筋」を4つの体系に分類している。A.機能体系は、物の実用的な役割(例:自動車の低燃費、化粧品の保湿効果)を表す。B.非機能体系は、実用性以外の意味作用(例:環境に優しい車、健康的な美しさの化粧品)を表す。C.メタ機能・非機能体系は、物の言外の意味(コノテーション)(例:未来社会型自動車、自立した大人の女性のための化粧品)を表す。D.イデオロギー的体系は、物を通して提示される生き方や暮らし方(例:エコロジカルなライフスタイルを象徴する車、ジェンダーフリーな生き方を象徴する化粧品)を表す。消費者は、これらの体系を意識的または無意識的に理解し、消費行動を決定している。消費とは、単なるモノの購入ではなく、記号を消費する行為であり、消費者自身のアイデンティティや価値観を反映した行為である。
3. 文化的 象徴的意味と個人的解釈 消費の意味の多様性
消費されるモノは、社会的に共有された文化的/象徴的な意味を持つ一方、個々の消費者によって異なる意味で解釈される。例えば、青色が男性用、ピンク色が女性用というジェンダーと色彩の関連性があるものの、ファッションに敏感な男性がピンクのジャンパーを着たり、失恋した女性が青いワンピースを着るなど、個人的な解釈も存在する。個人的な意味づけは、消費者の過去の経験、個性、置かれた状況などに大きく影響される。そのため、消費の意味を分析する際には、文化的/象徴的な意味と個人の個人的な解釈の両方を考慮することが重要となる。消費の意味は、社会と個人の相互作用の結果として構築され、常に変化し続ける動的なものである。このことは、消費行動を記号論的な視点から分析する必要性を示唆している。
XIII.ジェンダー セックス ロマンチック ラブと自己構築型消費
ジェンダー、セックス、ロマンチック・ラブに関連する商品は、消費者の自己構築に貢献する。性的刺激や記号としての性を通して、自己を表現したり再構築したりしようとする動きが見られる。これらの消費は、自己構築型消費と言える。
1. ジェンダー セックス ロマンチック ラブの商品化
現代の市場では、ジェンダー、セックス、ロマンチック・ラブといった要素が商品に付与され、市場価値を高める戦略が用いられている。化粧品は、ジェンダーアイデンティティ(女らしさや男らしさ)を実現する手段として消費されている。セックスアピールは、ポルノグラフィーのように性的行為そのものを商品化したり、魅力的なモデルを使用したりすることで、直接的に消費者の欲望を刺激する。ロマンチック・ラブは、バレンタインデーなどのギフト交換といった消費行動を通して表現される。これらの消費は、単なる物品の購入ではなく、ジェンダー、セックス、ロマンチック・ラブといった記号を消費する行為と言える。これらの記号は、文化的・象徴的な意味と感覚的なイメージ的意味を同時に持ち、消費者の自己表現や自己構築に貢献している。
2. 自己構築型消費としての性の商品化
ジェンダー、セックス、ロマンチック・ラブに関連する商品の消費は、「自己構築型消費」と捉えることができる。消費者は、これらの商品を通して、自身のアイデンティティを表現・実現したり、自己を再構築したりしようとする。例えば、化粧品は消費者にとって、理想のジェンダー像を体現するための手段となる。また、アダルトビデオや風俗サービスの利用は、消費者自身の性的欲求や自由意志を満たす手段となる。恋人同士が共有するプレイスポットやアニバーサリーグッズは、互いの関係性を確かめ、自己のあり方や相手との位置関係を確認・修正する手段となる。市場で流通する「記号としての性」は、文化的・象徴的な意味と感覚的な意味を伝え、消費者の自己構築に大きく貢献している。消費社会における性の商品化は、消費者にとって、自己を表現・実現し、自己を構築するための重要な手段を提供していると言える。
XIV.消費の意味の分析方法 追体験分析と構成的分析
消費の意味を分析する際に、追体験分析と構成的分析という2つの方法が用いられる。追体験分析は消費者の行動や発言から意味を推測し、構成的分析は消費現象から時代背景や価値観を読み解く方法である。両者を組み合わせて分析することで、より客観的な分析が可能になる。
1. 消費の意味の複雑性と分析方法の必要性
現代の消費は、非常に複雑で多様な意味を持つため、客観的な分析方法が求められる。消費の意味を理解するためには、単に表面的な消費行動を観察するだけでなく、消費者自身の内面的な解釈を理解する必要がある。このため、本研究では、消費の意味を分析する2つの方法を提案している。一つは「追体験分析」で、消費者の行動や発言といった外面的な反応を手がかりに、消費の意味を推測し理解する方法である。もう一つは「構成的分析」で、最近のヒット商品やベストセラー小説などを手がかりに、分析者が様々な解釈を行う方法である。これらの2つの方法は独立しているわけではなく、追体験分析が構成的分析の補助とチェックの役割を果たすことが理想的であるとされている。構成的分析は、分析者の主観的な解釈に偏りがちであるため、一般人が消費に込める意味を丁寧に理解した上で、構成的分析を行うことが重要となる。
2. 追体験分析 消費者の視点からの理解
追体験分析は、消費者の外面的な反応(行動や発言)を手がかりに、消費の意味を出来る限り消費者の視点から理解しようとする方法である。この方法は、分析者が消費者の行動や発言を詳細に観察し、それらの行動や発言に矛盾しない解釈を構築することで、消費の意味を推測する。この分析では、消費者にとって、その消費行動がどのような意味を持つのか、どのような感情や価値観が反映されているのかを明らかにすることが重要である。分析者は、消費者と同じようにその消費を「追体験」することで、消費の意味をより深く理解することができる。ただし、この方法は、消費者の主観的な解釈に依存するため、客観性を担保するために、他の分析方法と組み合わせることが必要となる。
3. 構成的分析 社会文化的な文脈からの解釈
構成的分析は、社会文化的な文脈を踏まえて消費現象を解釈する方法である。この方法は、分析者が、最近のヒット商品やベストセラー小説など、消費社会における顕著な現象を手がかりに、消費の意味を様々な角度から解釈する。この方法では、分析者の専門知識や洞察が重要となる。しかし、消費者個人が消費に込めている意味を無視すると、客観性の低い、分析者の主観に偏った解釈になりやすいという弱点がある。そのため、構成的分析を行う際には、追体験分析によって得られた消費者の視点も考慮することが重要になる。両方の分析方法を組み合わせることで、消費の意味をより深く、より客観的に理解することが可能となる。
XV.快楽消費 3つの快楽と消費行動
快楽消費は、プラスの快楽、マイナスの快楽、到達の快楽の3種類に分類される。ジェンダー関連商品、セックス関連商品、ロマンチック・ラブ関連商品の消費には、習慣化、認識された自由、関与といった快楽の要素が強く関わっている。
1. 快楽消費の定義と3つの類型
本稿では、快楽消費を「主観的な望ましさ」と定義し、製品の獲得・使用・廃棄を通して得られる快楽経験を3つのタイプに分類している。一つ目は「プラスの快楽」で、遊びや娯楽、芸術消費などを通して得られる楽しさや快適さ、美的経験などを指す。二つ目は「マイナスからの快楽」で、身体的または精神的な痛みや苦しみから解放されることで得られる安心感や安堵感、いわゆる「癒し」系の商品消費などが該当する。三つ目は「到達の快楽」で、目標達成時の充実感や喜び、趣味や稽古事の上達感などが含まれる。消費者は、商品特性や文脈特性だけでなく、快楽的価値に基づいて消費行動を選択しており、消費における快楽の追求は、消費行動を理解する上で重要な要素である。
2. ジェンダー関連商品 セックス関連商品 ロマンチック ラブ関連商品における快楽消費
ジェンダー関連商品の消費においては、「習慣化」や「繰り返す安心感」といった快楽が重視される。例えば、男性は紺や黒といった色のアイテムを、女性は赤やピンクといった色のアイテムを好む傾向があり、こうした社会的に定着した消費パターンが快楽につながっていると考えられる。セックス関連商品の消費(アダルトビデオや風俗サービスなど)では、「認識された自由」、「自発性」、「例外的な許可や自己納得」といった快楽が重要になる。消費者は、自身の自由意志で消費しているという感覚や、特別な許可を与えられたという感覚から快楽を得ている。ロマンチック・ラブ関連商品の消費(バレンタインデーや誕生日のプレゼント交換など)では、「関与」、「計画の有無」、「デイ・ドリーミング」といった快楽が重視される。高い関与や計画性、そして消費体験を通じた空想の世界への没入が快楽体験に繋がる。
XVI.広告と感情的反応 説得プロセスと消費行動
広告は消費者に様々な感情的反応を引き起こし、それが広告商品やブランドに対する態度や行動を規定する。ペティとカシオッポの精緻化見込みモデルなど、様々なモデルが提案されている。広告商品の種類によって、効果的な感情は異なる。
1. 広告と感情的反応 複数のモデル
広告は、消費者に認知的反応と感情的反応の両方を引き起こし、それらが商品やブランドに対する態度を規定すると考えられている。ホルブルックとパトラは、広告が消費者に感情的反応を生み出し、それが広告商品やブランドに対する態度に影響するというモデルを提示している。マクニスとジャオルスキーは、認知的反応と感情的反応の両方が商品やブランドに対する態度を規定するというモデルを示している。オルネイらは、広告内容の訴求度や独自性が喜びや奮起といった感情的反応を引き起こし、それが広告に対する態度(快楽性、実用性、興味)に影響を与え、視聴時間にまで影響を与えると主張している。パビンらは、広告戦略(映像、写真、言葉など)が消費者の記憶、態度、信念、購買意図、購買行動に影響を与え、その媒介役として広告が消費者に生起させる心的イメージ、広告商品、消費者の個人差要因などを挙げている。これらのモデルは、広告と感情的反応の関係性を様々な角度から示している。
2. 広告効果と感情的反応 商品タイプと効果的な感情
広告が消費者に引き起こす感情が、商品に対する態度や行動にどのように影響するかは、商品タイプによって異なる。食品広告では、陽気さ、優しさ、楽しさといった感情が効果的であることが多い。一方、医薬品広告では、恐怖心や不安感を提示しつつ、期待感や自信といった感情を生み出すことが効果的である場合が多い。 商品タイプと効果的な感情の関連性について、「問題解決型商品:いらいらから安心へ」「問題回避型商品:恐怖心からリラックスへ」「不満解消型商品:失望から期待へ」「体力節約型商品:わずらわしさから便利さへ」「不協和解消型商品:精神的葛藤から平穏へ」「感覚満足型商品:退屈から満足へ」といった指摘がある。つまり、広告戦略においては、ターゲットとする消費者層や商品特性に合わせた適切な感情的訴求が重要となる。
3. 非言語的コミュニケーションと説得プロセス
快楽消費を促す上で、非言語的コミュニケーションも重要な役割を果たす。ペティとカシオッポの精緻化見込みモデルによると、広告の受容者がメッセージを精査する動機と能力がある場合、重要なメッセージが詳細に検討され、態度変化が起こる(中心的ルート)。しかし、動機と能力が低い場合は、タレントやBGMといった周辺的な手がかりが態度変化に影響を与える(周辺的ルート)。広告で用いられる非言語的媒体には、映像、音楽、タレント、色彩などがある。これらの非言語的手がかりは、広告商品に対する心的イメージを形成し、消費者の態度や行動に影響を与える。商品は、「実用性・機能性・合理性」と「快楽性・感覚性・情緒性」の両面を持ち、ジェンダー、セックス、ロマンチック・ラブ関連商品は後者(快楽性など)の側面が重視される傾向がある。
XVII.非言語的コミュニケーションと快楽消費
非言語的コミュニケーション(BGM、タレントなど)も快楽消費を促す効果を持つ。ペティとカシオッポの精緻化見込みモデルによれば、メッセージの精緻化が困難な場合、周辺的な手がかりが態度変化に影響を与える。
1. ペティとカシオッポの精緻化見込みモデルと態度変化
広告における非言語的コミュニケーションの効果について、ペティとカシオッポの精緻化見込みモデル(elaboration likelihood model)が紹介されている。このモデルによると、広告の受容者がメッセージを注意深く検討する動機と能力を持つ場合、重要なメッセージが精緻化され、態度変化が起こる(中心的ルート)。しかし、動機と能力が低い場合、タレントやBGMなどの周辺的な手がかりが態度変化に影響を与える(周辺的ルート)。快楽消費を促す広告においては、消費者のメッセージへの関与度によって、情報処理のルートが異なり、効果的なコミュニケーション戦略も変化することを示唆している。非言語的な要素は、消費者の注意を引きつけ、感情的な反応を誘発する上で、重要な役割を果たしている。
2. 非言語的媒体と快楽消費
広告における非言語的媒体としては、映像、音楽(BGM)、タレント、色彩などが挙げられる。これらの媒体は、広告メッセージを補完し、消費者の感情に直接的に訴えかける効果を持つ。特に、快楽性・感覚性・情緒性を重視する商品(装飾品、オシャレ用品、趣味・娯楽サービスなど)においては、非言語的なコミュニケーションが、消費者の購買行動に大きな影響を与える。広告における非言語的要素は、商品への関心を高め、好ましい感情を引き起こすことで、快楽消費を促進する効果があると考えられる。日用品などの実用的な商品と、装飾品などの快楽指向の商品では、広告における非言語的要素の重要度が異なる可能性がある。
XVIII.ライフスタイルと性の消費行動
ライフスタイルは性の消費行動に影響を与える。ジェンダー(女らしさ)消費、おしゃれ消費、ロマンチック・ラブ消費は「存在価値」感情と強く関連している。女性は男性よりジェンダー(女らしさ)消費やおしゃれ消費の度合いが高く、男性はセックス消費の度合いが高い傾向が見られる。
1. 非言語的コミュニケーションの効果 ペティとカシオッポのモデル
広告における快楽消費を促進する非言語的コミュニケーションの効果について、ペティとカシオッポの精緻化見込みモデル(elaboration likelihood model)が参照されている。このモデルは、受容者の情報処理過程における動機と能力に着目し、動機と能力が高い場合は、広告の中心的なメッセージが精緻に検討され、態度変化が起こる(中心的ルート)と説明する。一方で、動機と能力が低い場合は、タレントやBGMといった周辺的な手がかりによって態度変化が起こる(周辺的ルート)とされる。このモデルは、広告における非言語的要素が、消費者の情報処理過程にどのように影響を与えるかを理解する上で、重要な示唆を与えている。特に、快楽消費のような、合理的な判断よりも感情的な反応が重視される消費においては、周辺ルートの影響が大きくなる可能性が高い。
2. 非言語的媒体と商品の価値観
広告で使用される非言語的媒体としては、映像、音楽(BGM)、タレント、色彩などが挙げられる。これらの媒体は、商品の実用性(機能性、合理性)と快楽性(感覚性、情緒性)の両側面に影響を与える。頻繁に使用される日用品などは、実用性を重視した価値づけがなされる傾向がある一方、自動車や家電製品などは、実用性と快楽性の両方を重視した価値づけがなされる。そして、本稿で分析対象としているジェンダー、セックス、ロマンチック・ラブに関連する商品は、装飾品やオシャレ用品と同様に、快楽性・感覚性・情緒性の側面をより強く重視した価値づけがなされる傾向がある。つまり、これらの商品は、実用性よりも、快楽体験や感情的な満足感といった非言語的な要素を重視した消費行動を促しやすいと言える。
