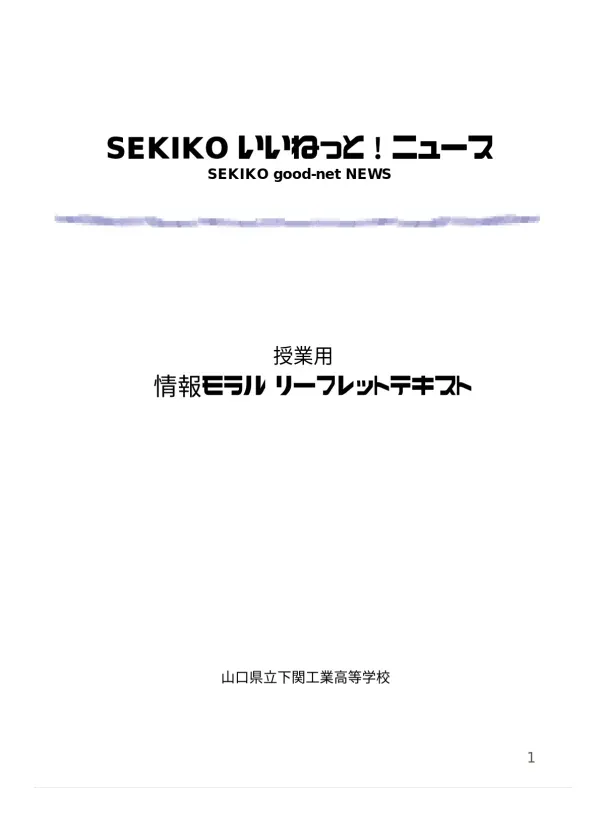
情報モラル教育リーフレット:SEKIKOいいねっと!
文書情報
| 学校 | SEKIKO |
| 専攻 | 情報モラル (Information Ethics) |
| 出版年 | 2000-2007 |
| 文書タイプ | 授業用教材 (Teaching Material) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 553.09 KB |
概要
I.著作権侵害とインターネットの脅威 違法コピー問題
本資料では、急激に発達するIT技術とインターネット社会における著作権侵害、特に【違法コピー】の問題を詳述しています。 音楽ファイル交換ソフト【ナップスター】や【Winny】の登場によって容易になった音楽ファイルやソフトウェアの不正コピー、それによる【著作権侵害】の現状と、その深刻な影響について解説しています。 具体的には、大学におけるネットワーク経由での違法コピー、ゲームソフトの不正コピーによる【損害賠償】問題、そして、違法コピーを幇助したとして逮捕された【Winny開発者】の事例などが挙げられています。 これらの行為は、【著作権法】違反として処罰の対象となり、莫大な損害賠償請求につながる可能性があることを強調しています。 さらに、インターネットラジオにおける著作権の扱い、ファイル交換ソフトの仕組み、そして、【送信可能化権】といった高度な概念についても触れられています。
1. IT技術の進歩と著作権侵害の容易化
IT技術の進歩により、素人でも高度なコンテンツ制作や大量複製が容易になり、専門家しかアクセスできなかったネットワークシステムにも容易に侵入できるようになりました。この技術の進歩は、著作権保護の観点から大きな問題を生み出しています。かつては専門家しかできなかったことが、素人でも可能になったことで、著作権侵害が急増しているのです。例えば、ネット上には爆発物製造マニュアルや自殺マニュアルといった違法な情報が氾濫しており、社会規範を変える必要性すら生じています。さらに、コンピュータソフトの不正コピー摘発は1999年頃から増加し、その対象も個人から学校や社会組織、そして公益法人へと拡大しています。 (財)日本エネルギー経済研究所が不正コピーで約1000万円の損害賠償を支払う事態も発生しています。これは、IT技術の進歩が、著作権侵害を加速させていることを如実に示しています。不正コピーは、容易に複製できるデジタルデータの特性と、インターネットによる情報拡散のスピードが合わさって、深刻な問題になっています。
2. ファイル交換ソフトと違法コピーの蔓延 ナップスターとWinny
音楽ファイル交換ソフトナップスターの登場は、著作権侵害に新たな局面を開きました。ナップスターは、膨大な音楽ファイルをユーザー間で共有できる仕組みを提供し、違法コピーを容易にしました。このシステムは、中央サーバーで音楽ファイルの所有者リストを管理し、ユーザーの要求に応じてファイル送信を指示する仕組みでした。 その後、ナップスターに似た仕組みを持つWinnyが登場し、さらに問題を複雑化させました。Winnyは高い匿名性を持つため、違法コピーの拡散元特定が困難でした。京都府警によるWinny開発者の逮捕は、違法コピー幇助の疑いによるもので、この事件は、単なる違法コピー問題にとどまらず、表現の自由や法の整備の遅れといった、ネット社会特有の課題を浮き彫りにしました。 平成15年3月には、大学の工学部学生が大学のネットワークを使って音楽ファイルを違法コピーし、日本レコード協会が大学に管理徹底を要請する事態も発生しています。これは、ファイル交換ソフトを介した違法コピーが、大学といった組織にも影響を及ぼしていることを示しています。 日本レコード協会は、インスタントメッセージによる警告文を700万通も個人に対して送付している状況です。
3. 著作権法と公衆送信権 インターネット上の著作物アップロード
日本の著作権法は、著作権者の【公衆送信権】を認めています。これは、著作権者が自分の著作物を無断でインターネット上にアップロードされない権利を持つことを意味します。そのため、自分のパソコンをインターネットに接続した時点で、パソコンにある他人の著作物が送信可能になるため、犯罪が成立する可能性があります。 このことは、インターネット上にアップロードされたコンテンツの多くが、既存コンテンツの翻案であるという事実とも関連しています。マルチメディア時代においては、コンテンツのルーツを辿り、全ての著作権者の許諾を得ることは事実上不可能に近い状況にあります。 CS放送の予備校講義を録画し、インターネットで販売した山口県内の高校2年生とその母親が著作権違反で書類送検された事例も紹介されています。 この事例は、インターネットを通じて容易に著作権侵害が行われてしまう現状を浮き彫りにしています。 また、教育目的での複製に関しても、誤解に基づく違法行為が行われている可能性が指摘されており、著作権に関する正しい理解の必要性が強調されています。
4. 違法コピーによる損害と責任 損害賠償請求と連帯責任
不正コピーソフトの違法販売から生じる損害は甚大です。 50人に不正コピーソフトが販売され、1人あたり3人に配布されると仮定した場合、5回繰り返すだけで1億2150万円もの損害が発生する可能性があります。 これは、インターネットを通じて二次的、三次的な被害が拡大する可能性を示しています。 (財)日本エネルギー経済研究所の事例のように、企業においても不正コピーによる損害賠償請求が発生しており、その責任は経営者にも及ぶ可能性があることが指摘されています。 また、個人の違法行為に関しても、莫大な損害賠償請求を招く可能性があり、安易な違法行為は決して許されないことを強調しています。 コンピュータゲームのプログラムを無断でコピーしてコンテストに出品し、賞金を獲得した事例も挙げられており、これは著作権の著しい侵害に該当すると示唆されています。さらに、連帯責任についても触れられており、借りた者がコピーした場合は、貸した者にも責任が及ぶ可能性があることを示しています。 3878万円の損害賠償請求事例も紹介されており、企業の防止義務の重要性が強調されています。
II.個人情報保護とプライバシーの侵害
インターネット社会では、個人情報の保護が重要な課題となっています。 住宅地図への【個人情報】掲載によるプライバシー侵害、容疑者の住所や顔写真のインターネット上での無断公開、そして、顔写真付きの中傷メール送信による書類送検事例など、様々な【個人情報保護法】違反が取り上げられています。 これらの事例は、インターネットの匿名性を利用した犯罪が容易に発生することを示しており、個人が発信する情報に対する責任の重要性を訴えています。 【個人データ】の第三者提供における同意の必要性も強調されています。
1. 個人情報の無断公開とプライバシー侵害 住宅地図とインターネット
個人情報の保護は、インターネット社会において極めて重要な課題です。 本資料では、個人情報が意図せず公開され、プライバシーが侵害される事例が複数紹介されています。関工生の関門橋之介さんがストーカー被害を避けるために引っ越した際、市販の住宅地図に住所が掲載されていた事例が挙げられています。これは、住宅地図業者が個人情報を適切に保護していなかった可能性を示唆しています。 また、平成14年9月には、猫を虐待する様子をデジタルカメラで撮影し、インターネット掲示板にライブで配信した男性が動物愛護法違反で逮捕されています。この事件は、インターネットの匿名性を悪用した犯罪の危険性を浮き彫りにしています。さらに、逮捕された容疑者の住所や顔写真がネット上に流出したことも問題視されており、個人情報の無断公開の深刻さが強調されています。これらの事例は、個人情報の取り扱いに関する法整備の遅れや、個人のプライバシーに対する意識の低さを示しています。 個人情報保護法の重要性と、個人情報を取り扱う事業者の責任について改めて認識する必要があります。 特にインターネット上では、一度情報が公開されると拡散が容易であり、取り返しがつかない事態になりかねないことを理解する必要があります。
2. インターネット上の誹謗中傷と個人情報保護 顔写真付き中傷メール
インターネットの匿名性を悪用した誹謗中傷は、深刻な個人情報侵害の一形態です。 本資料では、高校2年生の女子生徒が顔写真付きの中傷メールを送信したことで書類送検された事例が挙げられています(徳島県警、平成14年5月)。これは、インターネットが、特定の個人や組織を攻撃し、社会からの疎外感を解消したり、ストレスを発散するための手段として利用される危険性を示しています。 この事例は、インターネット上での匿名発信の危険性と、発信者自身の責任の重要性を改めて認識させるものです。 自分の身分がばれないことをいいことに、特定の個人や組織を攻撃することは決して許されるべきではありません。 インターネットという自己主張の手段が与えられているからこそ、意見表明を適切な方法で正しく行うことが重要です。 この事件は、携帯カメラとインターネットの普及によって、現代版「不幸の手紙」のような行為が容易に発生することを示しています。 「不幸の手紙」よりも証拠が残りにくく、被害がより広範囲に及ぶため、より悪質であると指摘されています。 これらの事例から、インターネット社会における個人情報保護の重要性と、情報発信における責任ある行動の必要性が改めて強調されます。
3. 個人データの第三者提供と同意 個人情報保護法の遵守
個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供する際には、本人の同意が必要であると本資料では明記されています。これは、個人情報保護法に基づく重要な規定です。 宮崎市内の家電販売店で店頭パソコンのIDとパスワードを不正に入手し、インターネットを利用した高校2年生と予備校生が書類送検された事例は、個人情報の不正取得と利用によるプライバシー侵害の一例として示されています。 この事例は、個人情報の重要性を改めて認識させ、個人情報保護法の遵守が企業や個人の責任であることを明確に示しています。 さらに、電子掲示板で児童ポルノ画像を販売した中学生の逮捕事例(愛知県警、平成13年4月)は、個人情報だけでなく、児童の権利や安全を守る上でのインターネット上の情報管理の重要性を示しています。 これらの事例を踏まえ、個人情報の適切な管理と保護の必要性、そして、個人情報保護法の厳格な遵守が改めて強調されています。 個人情報の漏洩は、個人のプライバシー侵害だけでなく、社会全体への悪影響を及ぼす可能性があることを認識する必要があります。 個人情報保護に関する法律やガイドラインを理解し、適切な対応を行うことが重要です。
III.コンピュータウイルスとネット社会のリスク SQLスラマーの事例
本資料では、【SQLスラマー】というワーム型ウィルスによる大規模なインターネット障害を分析しています。 このウィルスは、マイクロソフトのデータベースサーバーソフトのセキュリティホールを突いて急速に感染拡大し、世界規模のネットワーク障害を引き起こしました。 この事例は、【ワーム型ウイルス】の自己増殖能力の高さ、そしてインターネット社会における【同時性】と【大規模性】というリスクを改めて浮き彫りにしています。 また、ウィルスの種類や対策ソフト(【ワクチン】)についても触れられています。トレンドマイクロ社などの情報を参照することで、より詳細な知識を得ることができます。
1. SQLスラマーによる大規模なインターネット障害
平成15年1月25日、世界規模でインターネット障害が発生しました。原因は、SQLスラマーと呼ばれるワーム型ウイルスです。このウイルスは、マイクロソフトのデータベースサーバーソフト「SQLサーバー2000」のセキュリティホールを利用して感染し、他のSQLサーバーに自身の複製を大量に送りつけました。結果として、多数のサーバーが機能停止に陥り、日本、アメリカ、ヨーロッパなど世界中で深刻な影響が出ました。特に、ブロードバンド普及率の高い韓国では、ホームページへの接続不能や接続困難が全土で発生し、混乱が9時間も続きました。この事件は、インターネットの脆弱性と、ワーム型ウイルスの持つ自己増殖能力の高さ、そしてインターネット社会における同時性と大規模性を改めて認識させるものでした。数万ものサーバーが感染したと推定されており、その被害の大きさは計り知れません。 この事件は、インターネット社会におけるインフラの脆弱性と、大規模なサイバー攻撃に対する備えの必要性を浮き彫りにしています。
2. ワーム型ウイルスの特徴と感染拡大メカニズム
SQLスラマーはワーム型ウイルスに分類されます。ワーム型ウイルスは、ネットワークを通じて自己複製し、急速に感染を広げるのが特徴です。従来のウイルスのようにメール添付ファイルを開くことで感染するタイプとは異なり、SQLスラマーは、SQLサーバー2000のセキュリティホールを悪用して感染しました。 感染したサーバーは、他のサーバーに自身の複製を大量に送りつけるため、サーバーは本来の機能を果たせなくなり、ネットワーク全体に大きな負荷がかかります。この自己増殖能力の高さこそが、ワーム型ウイルスが短時間に大規模な被害をもたらす要因です。 ウイルスには様々な種類があり、クリスマスの日に一斉攻撃を行うものや、他人のコンピュータを破壊するものなど、その手口は多岐にわたります。 そのため、常に最新のネット情報やニュースに目を通し、適切な対策を講じる必要があります。 コンピュータウイルスの対策ソフト(ワクチン)の重要性も強調されており、トレンドマイクロ社などの情報も参考にするよう促しています。
3. インターネット社会の同時性と大規模性 リスクへの対策
ワーム型ウイルスの最も大きな特徴は、その自己増殖能力です。 インターネットを通じて瞬時に複製を送りつけ、対策ソフトが対処するまで、感染はねずみ算式に広がります。この現象が、インターネット社会の同時性と大規模性を象徴的に示しています。 短時間で広範囲に影響を及ぼす可能性があるため、迅速な対応が不可欠です。 この事例を通して、インターネット社会のリスクを理解し、適切な対策を講じる重要性が強調されています。 個人が適切なセキュリティ対策を行うこと、企業や組織がインフラの強化に努めること、そして、政府レベルでの対策も必要であることを示唆しています。 常に最新のセキュリティ情報を把握し、適切な対策ソフトを使用することが、個々のユーザー、そして社会全体の安全を守るために不可欠です。 データベースソフトなどの業務システムのセキュリティ対策も非常に重要であり、企業においては、従業員への教育や、定期的なシステムアップデートなどの対策が求められます。
IV.知的財産権と特許 パワーコントロール特許の事例
【知的財産権】の保護についても言及されています。 特に、CDMA方式の携帯電話における【パワーコントロール特許】が、クアルコム社によって取得され、多額の特許料収入をもたらした事例が紹介されています。 これは、シンプルな技術であっても、その独創性によって莫大な経済的価値を生み出すことができることを示しています。 また、特許取得の戦略、企業秘密の保護、そして、技術革新のスピードと特許の有効性のバランスについても触れられています。【キルビー特許】(集積回路特許)も重要な事例として挙げられています。
1. パワーコントロール特許とCDMA技術
本資料では、KDDIが宣伝するCDMA方式の携帯電話技術と、その中核となる「パワーコントロール特許」について解説しています。CDMA(Code Division Multiple Access)方式は、もともとアメリカで軍事用に開発された通信技術ですが、アメリカのクアルコム社が新たな技術を追加して「CDMA-One」として製品化しました。この際に追加された技術が「パワーコントロール特許」であり、世界中の多くの携帯電話会社がこの技術を利用しているため、クアルコム社は莫大な特許料収入を得ています。 CDMA技術には、CDMA2000とWCDMAという2つの主要な方式があり、それぞれに長所と短所があります。CDMA2000は設備投資が少なくサービス提供コストが低いのに対し、WCDMAは高性能ですが設備投資コストが高いという違いがあります。 このパワーコントロール特許は、シンプルな技術ゆえに強力な特許として機能しており、エリクソン社を含む日本や欧州の企業は苦慮し、ITU(国際電気通信連合)にも問題が持ち込まれましたが、クアルコム社が実質的に勝利しました。これは、高度な技術開発だけでなく、特許戦略の重要性も示す事例といえます。
2. 知的財産戦略と技術革新のスピード
アメリカ合衆国は、1980年代に海外生産の影響で国内産業が空洞化した経験から、労働コストではなく知識で競争力を高める戦略を採りました。レーガン大統領の下で知的所有権の強化を進め、それが現在のIT技術発展の基礎となっています。 日本も同様の状況を鑑み、小泉首相の下で知的財産戦略会議が設立されました。しかし、人間の思考様式は容易には変わらないため、知的財産戦略の徹底には時間がかかります。 特許は、技術革新のスピードに遅れを取ると、その価値を失う可能性があります。多くの特許は、競合他社が回避策を見つけるため、一時的な競争優位性しか確保できません。 真に重要な独自技術は、企業秘密として厳重に管理され、特許として公開されることはありません。これらの技術は、膨大な研究開発費と先端技術の蓄積を必要とするため、単なるアイデアや工夫では実現不可能です。 特許の重要性と同時に、技術革新のスピードへの対応、そして企業秘密の適切な管理の重要性が強調されています。
3. 知的財産権の重要性と誤解 特許の価値と保護
本資料では、知的財産権の重要性を強調し、その誤解についても触れています。 特に、形のない情報、ソフトウェアや画像、映像などのコンテンツが、莫大な労力と費用を要するものであることを理解する必要があると述べています。 これらのコンテンツは、デパートの商品のように価格表示がありませんが、その価値は非常に高いです。 不正コピーは、人の所有権という人権を侵害する行為であり、有形物であれば警察に突き出せますが、「無体物」である情報は、その侵害が分かりにくいため、訴えられていないだけで、実際には多くの侵害が行われていると指摘されています。 また、特許についても、その価値と保護の重要性が強調されています。20世紀最大の特許である「キルビー特許」(集積回路特許)は、2兆円の特許料を生み出した事例として挙げられ、シンプルな技術ほど強力な特許になり得ることを示しています。 しかしながら、全ての技術を特許で保護するのではなく、重要な独自技術は企業秘密として厳重に管理する必要性も示唆されています。
V.電子契約と法的リスク
【電子契約法】の重要性と、消費者の保護について解説しています。 特に、消費者の操作ミスによる契約の無効化に関する規定、そして【民法】との関係性について説明しています。 事業者には、消費者の操作ミスを防止するための措置を講じる義務があり、それを行わなかった場合、契約は無効となる可能性があることを強調しています。 【契約リスク】を軽減するための法的枠組みの重要性が示されています。
1. 電子契約法と民法 契約成立のタイミングと消費者保護
本資料では、電子契約法と民法の関連性、特に契約成立のタイミングと消費者保護について解説しています。従来の民法では、契約成立は承諾の到達主義に基づいていましたが、通信技術の発達により、意思表示の発信と到達の間の時間差が小さくなったことから、電子契約法では「承諾」の返事が相手(消費者)に届いた時点で契約が成立すると規定されています。これは、民法第527条第2項の規定を踏まえたものですが、民法の規定だけでは十分な消費者保護ができないという問題意識が背景にあります。 電子契約法の目的の一つは、消費者の操作ミスによる契約の無効化です。事業者と消費者間(BtoC)の電子契約において、消費者が申込や承諾を行う前に注文内容を確認できる措置を事業者が講じなかった場合、消費者の操作ミスによる契約は無効となります。これは、入力終了後注文内容を画面に再表示し、確認ボタンを押させるなどの措置を事業者が講じる必要があることを意味します。 この点について、クイズ形式で具体例が示されており、消費者の操作ミスを防止するための事業者の責任が強調されています。
2. 電子契約におけるリスクと対策 消費者の操作ミスと事業者の責任
電子契約は、迅速かつ効率的な契約締結を可能にする一方で、契約リスクも伴います。特に、消費者の操作ミスによる契約トラブルは、大きな問題となります。 電子契約法は、消費者の操作ミスによる損害を最小限に抑えるための規定を設けています。具体的には、事業者は、消費者が注文内容を確認できる措置を講じる必要があります。 確認画面の表示や、確認ボタンの設置などがその例として挙げられます。これらの措置を講じなかった場合、消費者の操作ミスによる契約は無効となります。 これは、事業者側に、消費者の保護のためのより大きな責任が課せられていることを示しています。 インターネットを通じた契約は、直接顔を合わせる契約とは異なり、意思疎通の誤解や、技術的なトラブルが発生する可能性があります。そのため、契約内容の明確化、確認事項の周知徹底、そして、消費者の操作ミスを防止するための対策が、事業者にとって非常に重要になります。 電子契約の利便性と安全性を両立させるためには、法的な枠組みと、事業者の責任ある対応が不可欠です。
