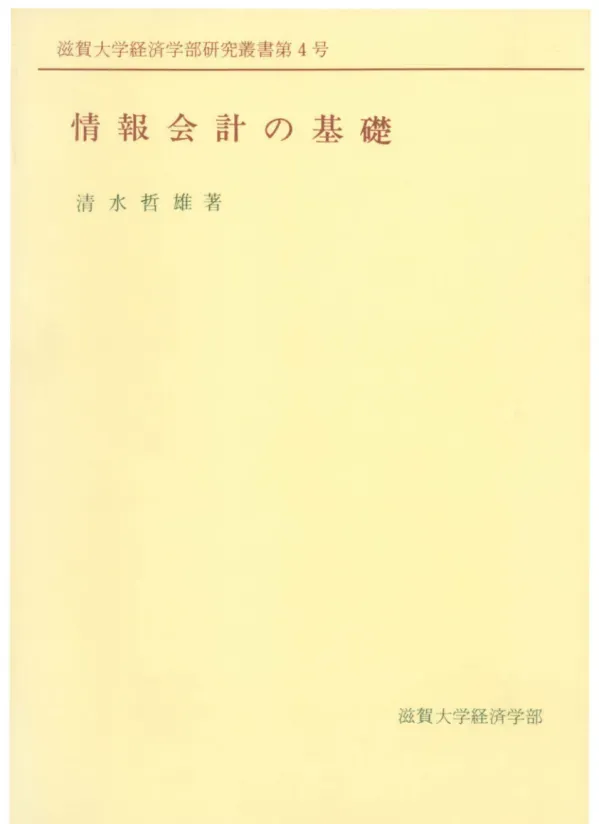
情報会計入門:会計目的の変遷
文書情報
| instructor | 木内佳市 先生 (大阪大学教授 経済学博士) |
| 学校 | 滋賀大学 |
| 専攻 | 経済学 |
| 出版年 | 昭和49年度 (1974年) |
| 場所 | (出版地は本文からは不明) |
| 文書タイプ | 書籍(推定) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 7.14 MB |
概要
I.戦後日本の 会計理論 の変遷と 情報会計 の台頭
第二次世界大戦後、急激な経済環境の変化により企業は体質改善を余儀なくされ、会計の目的も変化した。1950年代後半以降、情報理論の発展が会計に大きな影響を与え、従来の損益計算指向の伝統会計から、情報利用者の意思決定に役立つ有用性を重視する情報会計への転換が始まった。特に、1957年のAAA会計基準と1966年のASOBAT(Accounting Statements of Basic Accounting Theory)は、この転換期における重要なマイルストーンである。ASOBATでは、会計を経済情報の確認、測定、伝達のプロセスと定義し、会計領域の拡大を提唱した。会計基準は時代と企業を取り巻く環境の変化に合わせて柔軟に変化していく必要があることを示している。
1. 戦後経済環境変化と会計目的の変容
第二次世界大戦後の急激な経済環境変化は、企業体質の改善を余儀なくさせました。企業は内外の情報を迅速に得て意思決定を行う必要性に迫られ、会計そのものの目的も変化を遂げました。従来は、会計責任の履行が主な目的でしたが、次第に情報利用者の意思決定支援という側面が重要視されるようになりました。この変化は、会計情報の伝達方法や内容にも影響を与え、情報利用者の多様なニーズに応える多元的な会計情報が求められるようになりました。会計が単なる責任履行のための手段から、情報利用者の意思決定に資するツールへと転換していく過程が示されています。
2. 情報理論の発展と会計パラダイムシフト
1950年代後半からの情報理論の発展は、会計界に大きな衝撃を与えました。会計を情報理論の一環として捉える新たな視座が生まれ、伝統的な損益計算指向による会計(伝統会計)の見直しが迫られました。従来重視されていた公正性や真実性の概念は後退し、その代わりに有用性が前面に押し出されるようになりました。このパラダイムシフトは、会計情報の伝達目的を大きく変えました。会計情報は、単なる責任の解除ではなく、情報利用者の意思決定に直接貢献する手段として位置づけられるようになったのです。情報利用者の多様なニーズに応えるため、会計情報が多元化していく方向性が示唆されています。
3. AAA会計基準とASOBAT 情報会計への道標
1957年のAAA(American Accounting Association)会計基準は、従来の会計原則からの転換点を示す重要な出来事でした。この基準では、会計の主要な機能を「企業活動の理解に不可欠な情報の収集と伝達」と定義し、従来の原則とは異なる立場を明確に示しています。続く1966年のAAA基礎的会計理論(ASOBAT)では、会計を「経済的情報の確認、測定、伝達」のプロセスと位置づけ、会計領域の拡大と基本構造を体系的に提示しました。ASOBATは、情報利用者の視点を取り入れ、会計の役割を大きく拡張したことで、情報会計への道筋を明確に示したと言えます。これらの基準は、会計が単なる過去の記録にとどまらず、未来を見据えた意思決定のための情報システムとして進化していくべきことを示唆しています。
4. 伝統会計の限界と情報会計の必要性
文書では、20世紀初頭にシュマーレンバッハが提唱した動態的会計観を基盤とする伝統会計の限界が指摘されています。特に、第二次世界大戦後は、社会的・経済的基盤の急速な変化に対応できず、従来の枠組みでは処理しきれない問題が発生しました。このため、伝統会計理論が持つ限界を克服し、より包括的な枠組みで現代会計の問題を解決する必要性が生じました。その結果、情報理論の知見を取り入れ、会計領域を拡大しようとする動きが生まれ、情報会計理論が台頭してきたのです。これは、コンピュータシステムの発展と情報化社会の進展という外的要因と、株主中心の相互規制関係から経営者主導へと移行したという内的要因の両方が影響していると考えられます。
5. 会計の未来と情報システム化
激しく変化する現代の経済環境において、会計は時代の進歩に調和し、即応する必要があります。会計は、手作業による処理から機械処理、そして電子計算機を用いた情報システム化へと発展してきました。これは単なるデータ処理技術の量的変化にとどまらず、データベースの活用による質的な変化をもたらしました。迅速かつ正確な会計情報が、多様な用途に対して提供可能になったのです。会計の情報システム化とは、会計機構を通してデータを情報化し、情報ニーズに沿ってデータを処理すること、つまり情報検索の問題でもあります。この進化は、会計の機能をさらに拡張し、情報利用者の意思決定をより効果的に支援することを可能にしました。
II. 資産評価 と 測定基準 原価主義 から 時価主義 へ
資産評価方法は、歴史的原価に基づく原価主義から、時価を重視する時価主義へと変化してきた。これは、情報会計における測定基準の多様化を反映している。カレントコスト(時価の一種)は、特に減価償却計算において議論され、従来の取得原価主義との比較検討が行われた。保守主義の原則と低価法の問題点も指摘され、実現主義との整合性や意思決定への有用性が問われた。国際会計の進展も、時価主義の採用を促進する要因となった。再調達時価や正味実現可能価値といった新たな測定基準の導入が検討された。
1. 歴史的原価主義からの転換 時価主義の台頭
資産の評価方法は、長らく歴史的原価主義が主流でした。しかし、文書では、特に戦後、経済環境の激変により、この原価主義に限界が生じていることが指摘されています。時価主義、すなわち資産の時価を用いた評価方法が注目を集め始め、原価主義から時価主義への転換が議論の中心となっています。これは、企業の財政状態や経営成績をより正確に反映するため、そして情報利用者の意思決定を支援するために不可欠な変化として捉えられています。特に、1957年のAAA会計基準における「実現」概念の定義は、この転換期における重要な示唆を与えています。確定性と客観性を備えた実現概念は、取引の客観的な明確化を促し、販売の有無に関わらず実現の段階を迎えることを意味します。これにより、時価を反映したよりリアルタイムな会計情報が求められるようになりました。
2. カレントコストと時価測定の検討
時価主義の中でも、カレントコスト(当期費用)が重要な測定基準として議論されています。カレントコストは、技術革新が著しい現代において、原始取得財と同等の財を市場で求めることが困難であることを踏まえ、消費または売却によって失われた資産と同等の用役能力を持つ資産の再取得価額を考慮した測定尺度です。カレントコストは、費用計算に第一義的に用いられ、期末に残存する資産の評価にも適用されます。しかし、カレントコストの変動分には貨幣価値水準の変化分も含まれるため、架空利益と保有利益を区別する必要性が指摘されています。カレントコストを採用する目的は、営業利益と価格もしくは保有利益の差異を見極めることであり、経営者の期待に基づく個別価額による評価が重要視されます。
3. 低価法批判と時価主義への展開
伝統的に保守主義的観点から用いられてきた低価法(棚卸資産を時価と取得原価の低い方によって評価する方法)が批判の対象となっています。低価法は未実現損失を認識しないため、持分の取得者には有利だが処分者には不利な情報をもたらし、首尾一貫性と公平性に欠けるとされています。市場性のある有価証券や棚卸資産について、低価法の適用によって生じる未実現損失と認識されない利益の不一致が、企業の財政状態や経営成績に与える影響が問題視されています。しかし、低価法は時価(取替原価)を見つけて測定、評価する訓練の場として有用であり、時価主義への移行を促進する側面も持っています。実現性の欠如が時価を用いる障害とはならないという考え方が示唆されています。
4. 減価償却における時価主義 原価主義との比較
固定資産の減価償却方法についても、原価主義と時価主義の論争が展開されています。インフレ下では、取得原価を基礎とした原価主義による減価償却では、資本が食い潰されてしまうため、時価主義が提案されます。しかし、時価減価償却は損益計算における確実性の原則に反する可能性があり、比較可能性と確実性のバランスが課題となります。シュマーレンバッハは、取得原価は据え置き、時価を基準とした減価償却を行い、その調整を時価減価調節勘定で処理する手法を提案しました。この手法は、異なる時期・価格で取得された設備を同一価格水準で評価することを目指していますが、インフレ下では耐用年数を待たずに減価償却が完了してしまうという問題も抱えています。カレントコストによる減価償却も検討されていますが、評価替えの費用や複雑さといった問題点が指摘されています。
5. 棚卸資産評価と測定基準の多様化
収益の源泉となる棚卸資産の測定方法は、企業活動に大きな影響を与えます。様々な測定アプローチが存在し、単一の財務諸表による場合、複数の財務諸表を用意する場合、複合的財務諸表を用意する場合といった、相対立する見解が存在します。文書では、正味実現可能価値(予想売上手取額から完成・処分費用を差し引いた額)による評価が提案されており、これは会計公準の客観性に基づいています。ただし、商品相場が安定している場合に限定されます。異なる測定基準を採用する際には、それぞれの方法による会計情報の有用性を検証する必要があることが強調されています。また、測定基準の多様化は、情報利用者の意思決定の多様性に対応する必要性から生じていると考えられます。様々な利害関係者が、それぞれの目的に合った会計情報を求めているためです。
III. 情報会計 の特徴 目的適合性 と多元的 測定
情報会計は、情報利用者の意思決定に役立つ情報を提供することを目的とする。そのため、目的適合性が高く、検証可能性、不偏性、計量可能性を備えた測定基準が求められる。単一の財務諸表では様々な利害関係者のニーズを満たせないため、多元的測定、つまり異なる目的に対して異なる測定基準を用いることが提唱された。カレントコストや時価による測定は、その一例である。会計情報の領域は、貨幣価値だけでなく、物量情報や非計量的情報へと拡大している。
1. 情報会計の定義と目的 意思決定支援への焦点
情報会計は、情報利用者の意思決定に役立つ情報を提供することを第一の目的とする会計アプローチです。 これは、従来の会計が主に会計責任の履行を目的としていたこととは対照的です。情報会計では、意思決定に有用な基礎的データを識別、測定、伝達するプロセス全体が重視されます。単に会計責任を果たすための手段ではなく、情報利用者が状況を的確に判断し、意思決定を行うためのツールとして会計が位置づけられています。そのため、情報会計では、会計情報の有用性が最優先されます。情報利用者はそれぞれの目的に応じて異なる情報を求めるため、会計情報も多元的となることが特徴です。 1957年のAAA会計基準で示された、会計の主要な機能としての「情報の収集と伝達」という概念は、この情報会計の考え方の萌芽を示唆しています。
2. 目的適合性と多元的測定 多様なニーズへの対応
情報会計において重要な概念は「目的適合性」です。会計情報は、情報利用者の意思決定にどれだけ役立つのかという視点が最も重要視されます。そのため、目的適合性、検証可能性、不偏性、計量可能性といった基準を満たすことが求められます。しかし、単一の財務諸表では、株主、債権者、経営者など様々な利害関係者の多様なニーズを同時に満たすことは困難です。そこで情報会計では、「多元的測定」という考え方が提唱されています。これは、異なる目的のために異なる測定基準を用いることで、それぞれの利害関係者にとって有用な情報を提供しようとするアプローチです。例えば、株主は配当可能利益、債権者は支払能力、経営者は原価管理といったように、目的によって必要な情報、そして測定基準は異なってくるのです。この多元的測定の考え方は、会計情報の多様化と、情報利用者へのより高度なサービス提供を可能にすると考えられています。
3. 情報システム化と会計機能の拡張
情報会計は、単独で存在するものではなく、企業全体の情報システムの一部として機能します。そのため、効率的な情報システムの構築が不可欠です。理想的な情報システムは、情報の重複がなく、すべての意思決定に同一の情報が利用できるよう設計されるべきです。また、情報処理サイクルは企業のニーズに合致し、経営者が要求する情報(What management wants)を、いつでも利用可能な状態(on tap)にしておく必要があります。 単なるデータではなく、意思決定に有用な情報を提供することが重要です。しかし、このような情報を提供するためには、複式簿記システムを中核とする伝統会計だけでは不十分です。伝統会計は会計事象の分類と集計しか行わず、意思決定プロセスには介入しないためです。情報会計は、伝統会計を超え、より高度な情報分析と意思決定支援機能を提供するシステムとして機能する必要があるのです。
4. 伝統会計との関係 延長線上と革新の両面
情報会計は、伝統会計の延長線上にあると同時に、それからの大きな転換でもあります。アメリカの会計原則は、利益算定とアカウンタビリティの解除を目的とした伝統会計でしたが、情報理論の発展やEDP(電子データ処理)技術の進歩によって、会計領域が拡大しました。情報利用者は、リアルタイムで必要な情報を取得し、意思決定に活用しようとしています。この変化に対応するため、1966年のASOBATは、演繹的アプローチによって新しい会計の方向性を示しました。それは、情報システムの一環としての新しい会計であり、伝統会計の枠を超えた、より包括的で未来指向的な会計です。しかし、ASOBATは理論的枠組みの提示にとどまり、具体的な運用ルールまでは踏み込んでいません。このため、情報会計理論を実務に適用するための更なる検討が必要であることが示唆されています。
5. 会計情報の測定と伝達 利用者主導への転換
情報会計では、会計情報の測定と伝達の内容が利用者によって決定されます。従来の会計では、測定基準は比較的限定的でしたが、情報会計では、株主は配当可能利益、債権者は支払能力、経営者は原価管理といったように、情報ニーズの多様化に対応するため、測定基準も多様化する必要があります。 貨幣尺度だけでなく、物量的測定や非計量的情報も重視されます。情報の有用性が伝達過程の指導原理となるため、目的適合性が最も重要な基準となり、多元的測定の概念が重要になります。これは、単一の会計事実であっても、技術的に様々な角度から報告する必要があることを意味しています。 会計情報の利用者主導の視点が、情報会計における測定と伝達を規定する重要な要素となっているのです。
IV. 減価償却 における 原価主義 と 時価主義 の論争
インフレ下での減価償却計算は、原価主義と時価主義の論争の舞台となった。原価主義では、歴史的原価に基づいて減価償却を行うため、インフレ下では企業の資本維持が困難になる。時価主義は、時価に基づいて減価償却を行うことでこの問題を解決しようと試みるが、測定の困難さや、損益計算における確実性とのバランスが課題となった。カレントコストによる減価償却も提案されたが、測定の複雑さや費用対効果が議論された。シュマーレンバッハの時価減価償却に関する考え方も紹介されている。
1. インフレと減価償却 原価主義の限界
インフレ下では、取得原価主義に基づく従来の減価償却方法では、企業の資本維持が困難になるという問題点が指摘されています。固定資産の取得原価を耐用年数で費用配賦する従来の方法では、物価上昇分が考慮されないため、実際には資産価値の減少分を費用として計上できていないことになります。結果として、利益の一部が配当などで企業外に流出し、本来の資本維持という減価償却の目的が達成されないという事態が生じます。加速償却も検討されますが、取替資産のための資金を内部留保するという観点からは、耐用年数前に減価償却が完了してしまうため、十分な効果は期待できないとされています。このことから、インフレ下での減価償却計算には、取得原価主義の見直しが必要であることが強く示唆されています。
2. 時価主義の導入 比較可能性と確実性のトレードオフ
インフレ下での減価償却計算における比較可能性を維持するため、時価主義の導入が議論されています。シュマーレンバッハは、取得原価は据え置き、減価償却は時価を基準に行い、その調整を時価減価償却調節勘定で処理する手法を提案しました。しかし、この手法は損益計算における確実性の原則に反する可能性があり、比較可能性と確実性のトレードオフが課題となります。時価に基づく減価償却を行うと、インフレ時には耐用年数前に減価償却が完了し、設備に投資された資本が予定より早く回収されてしまうという問題もあります。そのため、時価主義を導入する際には、確実性とのバランスを慎重に考慮する必要があるとされています。また、時価の測定自体が困難であるという現実的な問題も指摘されています。
3. カレントコストによる減価償却 費用把握と課題
カレントコスト(当期費用)を用いた減価償却も検討されています。カレントコストとは、消費または売却によって失われた資産と同等の用役能力を持った資産の再取得価額です。この方法は、費用計算に用いられ、期末に残存する資産の評価にも適用されます。しかし、カレントコストを用いる場合、期末に残存する資産の評価額を翌期に繰り越すため、カレントコストの差額には貨幣価値水準の変化分(架空利益と保有利益)が混在します。このカレントコストによる減価償却は、営業利益と価格もしくは保有利益の差異を見極めることを目的としていますが、絶え間ない評価替えが必要となるため、費用がかさみ、その利点を上回る可能性があることが指摘されています。複雑な工場施設などでは、取替原価の正確な推定も困難であるという問題もあります。
4. 時価減価償却の代替案と会計の原則
固定資産の再評価を常に実施することは、現実的に困難であり、意味がないと主張する意見もあります。インフレーションは経済現象であり、帳簿上の手続で完全に対応することは不可能です。そのため、取替部分品や修理・改良が頻繁な設備については、その費用を固定資産に計上することで、過去の原価を現在の時価に近づけるという代替案が提示されています。しかし、この方法では、取替や改良が頻繁でない固定資産への対応が不明確です。会計は、原則として貨幣価値一定のコンベンションに基づいて構築されており、収益・費用は同じ価値尺度で測定されるべきです。貨幣価値変動への対応策として固定資産の再評価問題が取り上げられるものの、会計処理によって貨幣価値変動そのものがなくなるわけではありません。企業会計は、貨幣価値変動をくい止めるものではなく、それに対応するものであるという点が強調されています。
5. 取得原価主義と時価主義の統合 今後の課題
文書では、減価償却における原価主義と時価主義の統合が今後の課題として示唆されています。シュマーレンバッハは、動態論の立場から取得原価主義を支持しつつも、貨幣価値変動が著しい場合は時価主義を採用すべきだと主張しました。しかし、時価減価償却は確実性の原則に反する可能性を含んでいます。そのため、比較可能性と確実性の両方を考慮し、時価減価償却は特別な場合に限定的に用いるべきだとする立場も存在します。 これらの議論から、減価償却計算においては、単一の測定基準に固執するのではなく、経済環境の変化や情報利用者のニーズを考慮した柔軟なアプローチが必要であることがわかります。 インフレ下での資本維持や、正確な利益計算を実現するための最適な減価償却方法の模索は、継続的な課題として残されています。
V. 会計情報 の提供と外部利用者
会計情報は、株主だけでなく、債権者、従業員、政府機関など、様々な外部利害関係者にとって重要である。外部利用者は、企業の財政状態や経営成績を判断するために、企業が提供する財務諸表に依存している。そのため、外部利用者のニーズに合わせた、多様な会計情報を提供することが重要となる。AAA会計基準では、情報の明瞭性と比較可能性が強調され、会計情報の質を高めるための様々な工夫が提案されている。会計は、単なる記録・報告の手段ではなく、意思決定に役立つ情報を提供する情報システムとして捉え直されるべきである。
1. 会計情報の多様な利用者とニーズ
企業を取り巻く環境には、株主だけでなく、債権者(金融機関など)、仕入先、従業員、政府機関、取引先など、様々な利害関係者が存在します。これらの外部利用者は、企業の財政状態や経営成績を判断し、自己の意思決定を行うために、会計情報に依存しています。しかし、それぞれの利害関係者にとって必要な会計情報は異なっており、単一の財務諸表では、全てのニーズを満たすことは不可能です。債権者は企業の支払能力に関心を持ち、税務当局は利益に関心を持ちます。このように、異なる利用目的には異なる財務諸表が必要であり、会計情報は多元的であるべきです。会計の職能は測定と伝達ですが、情報会計では、その内容が利用者によって決定されます。そのため、単一の数値表示ではなく、複数の数値表示が求められるようになります。
2. 外部利用者への情報提供 財務諸表の役割と限界
外部利用者は、企業内部者と比べて企業の客観的環境に関する情報が少ないため、財務諸表のみで判断せざるを得ません。理想的には、外部利用者の多様な目的に応じた財務諸表を提供することが望ましいですが、現実的には不可能です。そこで、AAAステートメントでは、会計情報を「情報システム」と捉え、情報利用者の意思決定に必要な情報を提供することが強調されています。しかし、財務諸表に含まれる情報は、企業活動の全てを網羅するわけではありません。そのため、財務諸表には、利害関係者が企業に対する正しい判断を下すために必要な最低限の資料が発表されるべきであり、その他の情報は企業利益保護のため公開されないという考え方が示唆されています。それでも、各利害関係者が必要とする会計情報は異なるため、財務諸表だけでなく、計算過程や会計処理方法なども含めた詳細な情報提供が重要になります。棚卸資産の評価基準や減価償却法の変更などの注記が財務諸表の脚注に記載されることは、その意義が大きいとされています。
3. 情報の質と適切な表示 誤解防止への配慮
会計情報は、利用者にとって理解しやすく、誤解がないように提示されるべきです。AAA会計基準追補第8号(1954年)では、「表示の適切性は、部分的には掲示の形式いかんにかかっている」と述べられています。これは、利用者の理解を高め、誤解の可能性を減らすために、適切な形式を選択する必要があることを意味しています。 そのため、基礎となる明細書類や補足資料の利用が奨励されます。特に、外部利用者にとって、将来の財政状態や負債の支払能力を予想することは重要です。短期与信者や顧客、従業員にとって、これは特に重要な情報です。長期的な財政状態の予想は収益の予想と強く関連し、過去の資金運用表や資金繰り表は、取引の反復性や経営政策、環境要因などを考慮することで、有益な情報となります。会計担当者は、財政状態、資金の流れ、過去の収益情報などを報告することで、外部利用者による予想を補助する役割を担いますが、情報の提供には細心の注意が必要であることが強調されています。
4. 会計情報の限界と改善への取り組み
会計は、全ての要求を満たすことはできません。会計、金融、経済の発展、そしてそれらに関する情報の批判や議論によって、会計情報の範囲は広がり続けています。特に、歴史的取引に基づいた歴史的原価による表示には限界があり、その改善が求められています。そのため、歴史的原価に加えて現在価値を併記すること、そして利用者の目的に応じて詳細に区分された報告書を作成することが推奨されています。具体的には、損益計算書の区分計算、費用項目の固定費・変動費分類、費用の統制可能性分類、製品系列別または事業部別の損益計算などが挙げられています。これらの改善策は、より詳細かつ多様な情報を提供することで、外部利用者による企業の現状と将来性のより正確な判断を支援することを目指しています。
5. 会計と情報システム 未来への展望
文書では、会計を基本的には情報システムであり、情報の一般的理論を経済活動に効果的に応用することだと捉えています。そして、計数で表現された意思決定に関する情報を提供することが、情報システムの大きな役割であると述べられています。従来の会計機能は、過去の実績に関わる情報提供でしたが、会計は、コントロールの方法や意思決定を改善するために、過去・現在・未来のあらゆる活動データを測定し伝達する機能を持つまで進化しています。この変化は、経営学、行動科学、経済学といった隣接諸科学の方法論の変化によってもたらされました。会計学は、会計士が行う作業という伝統的な考えから脱却し、分析的なアプローチで理論モデルを構築する学問へと発展しています。この発展により、会計の領域は拡大し、アカデミックな学問としての地位を確立しつつあります。未来指向的な会計への発展が期待されています。
