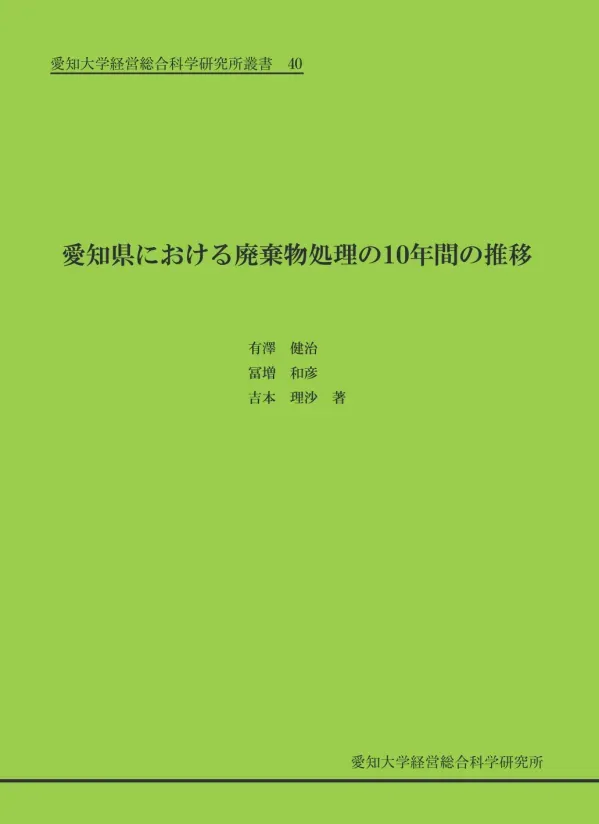
愛知廃棄物処理10年: 経費と効率性分析
文書情報
| 著者 | 有澤 健治 |
| 学校 | 愛知大学経営総合科学研究所 |
| 専攻 | 経営学 |
| 場所 | 愛知県 |
| 文書タイプ | 研究所叢書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 6.85 MB |
概要
I.愛知県下市町村における一般廃棄物処理行政の効率性に関する研究 経費と効率性の分析
本研究は、2010~2011年度の2年間、愛知県下の市町村における一般廃棄物処理行政の効率性、特にごみ処理経費と効率性の関係を分析したものです。初年度は既存データ(環境省データ)の有効性を調査。自治体ごとの情報は環境省によって集計・公表されているものの、集計方法に問題点があることが判明しました。特に、一部事務組合への組合分担金の扱いが課題でした。二年度目は、一部事務組合を訪問調査し、ごみ処理にかかる組合分担金の抽出方法や、ごみ処理経費の算定における課題を明らかにしました。分析の結果、経費効率の比較を行うためのデータ再計算を行い、その成果を以下に示します。
1. 研究目的とアプローチ
本研究は、2010~2011年度の2年間、愛知県下の市町村における一般廃棄物処理行政の効率性を評価することを目的としています。特に、平成10年度から平成20年度までの一般廃棄物処理(し尿処理を除く)の実態、経費、効率性に関する分析を行い、自治体の抱える問題点の解明と今後のごみ処理行政の方向性を検討することを目指しました。初年度は、環境省(当時環境庁)が公表している自治体ごとのデータを用いて、効率性評価の可能性を検証しました。これらのデータは基本的には問題ないように思われましたが、詳細な分析の結果、集計方法に改善の余地があることが判明しました。特に、一部事務組合への組合分担金の処理方法に問題があることが明らかになり、これが経費効率の正確な評価を阻害する要因の一つであると認識しました。そのため、次年度は、ごみ処理行政において重要な役割を果たす一部事務組合への訪問調査を実施することとしました。一部事務組合は、ごみ処理以外にもし尿処理、消防・防災など広域行政を担っており、特に小規模自治体では一般的な組織形態です。組合分担金は、構成自治体が組織運営のために拠出するものであり、ごみ処理経費も含まれています。この組合分担金を個々の自治体の処理経費に加算しなければ、正確な経費を把握し、効率性を比較することはできません。
2. データ分析における課題と修正
研究では、環境省や愛知県が提供するデータを用いて分析を進めましたが、いくつかの課題が明らかになりました。まず、経費に関する問題は、単年度のデータだけでは把握できない点が挙げられます。焼却炉の建設や最終処分場の確保など、一時的に大きな支出が発生するケースがあり、自治体では減価償却を考慮していないため、これらの支出の影響が単年度に限定されてしまいます。そのため、人口当たりの経費や排出量当たりの経費は、一時的な支出の有無に大きく左右されることになります。この問題に対処するため、本研究では平成10年度から平成20年度までの11年間のデータを用いて、経年変化を分析しました。また、愛知県庁が公開しているデータや関係自治体のウェブサイトに公開されているデータも参照しましたが、それらのデータには統一基準がなく、比較が困難でした。特に、平成10年度から平成17年度までのデータには「収集運搬施設」に関する経費が含まれておらず、平成10年度から平成16年度までのデータには「調査研究費」が含まれていませんでした。これらの欠損データは、推移グラフ作成時には0で置き換えて処理しましたが、これにより一時経費の過小評価につながる可能性も考慮する必要がありました。さらに、ごみの発生源を「生活系」と「事業系」に分けて分析する際に、環境省の定義に従った分類を試みましたが、この分類自体にも問題点があることを認識しました。特に、組合を持つ市町村については、実際の経費がさらに不透明であり、市町村の経費として「組合分担金」で処理せざるを得ない状況がありました。
3. 一部事務組合と経費算定
一部事務組合は地方自治法第284条1項に規定される地方公共団体の組合であり、その目的は事務の一部を共同処理することです。平成20年度末には1449団体存在し、衛生関係組合はその約40%を占めています。本研究では、一部事務組合への訪問調査を通じて、ごみ処理にかかる組合分担金の抽出の難しさ、およびごみ処理行政における考え方によって算入・算出されない項目が存在することを明らかにしました。組合分担金の算定方法は、人口割、昼間人口割、均等割、搬入割などがあり、自治体間の合意に基づいて決定されますが、愛知県内の一部の事務組合では、ごみ処理に関しては昼間人口割は用いられていませんでした。 経費算定においては、市町村の経費に組合歳出×分担金割合を加算する必要があることが判明しました。いくつかの事例を挙げると、幸田町は蒲郡市幸田町衛生組合でし尿処理のみ共同で行い、ごみ処理は単独のため、ごみ処理にかかる分担金は発生していません。春日町と甚目寺町は、名古屋市五条川工場にごみ処理を委託しているため、組合分担金は発生していません。これらの事例からも、組合分担金の扱いの複雑さがわかります。リサイクル率の算定においても、新聞回収やスーパーへの直接持ち込みなど、自治体のデータに含まれないリサイクル量が存在するため、正確なリサイクル率の算出には注意が必要です。 また、飛島村の資源ごみ・不燃ごみの数値が突出して高いのは、港湾・工場の立地、固定資産税収入の多さ、昼間人口の多さなどが影響していると考えられます。
II.経費分析における課題 データの限界と改善策
ごみ処理経費の分析においては、単年度データだけでは焼却炉建設や最終処分場確保といった一時的な大型支出の影響を適切に捉えられないという課題がありました。そこで、平成10年度から平成20年度までの11年間のデータを分析することで、経年変化を捉え、より正確な経費効率の評価を試みました。愛知県庁や自治体ウェブサイトのデータも参照しましたが、データの統一基準がなく比較が困難だったため、独自にデータを収集・整理しました。特に、環境省データにおける収集運搬施設費や調査研究費の扱いを修正し、一部事務組合への組合分担金を適切に反映させるための工夫を行いました。 平成10年度と平成20年度のごみ処理経費の分布を比較することで、市町村合併の影響なども考慮しました。
1. 単年度データの限界と長期データ分析
ごみ処理経費の分析においては、単年度データだけでは不十分であるという課題が浮き彫りになりました。焼却炉の建設や最終処分場の確保といった、多額の一時的な支出が発生することがあり、自治体では減価償却の考え方を採用していないため、これらの支出の影響は単年度のデータに大きく反映され、人口あたりや排出量あたりの経費に歪みが生じます。そのため、本研究では、平成10年度から平成20年度までの11年間のデータを用いることで、このような一時的な支出の影響を軽減し、より長期的な視点からの経費の推移と効率性を分析することを試みました。この長期的なデータ分析によって、単年度データでは見えにくい傾向や構造的な問題点を把握することを目指しました。最終章では、11年間の調査結果をグラフで視覚的に表現することで、経費の推移をより分かりやすく提示しています。この方法により、より正確な経費効率の評価が可能になると考えました。
2. データソースの課題とデータ補正
愛知県庁や関係自治体のウェブサイトにも廃棄物処理に関するデータは公開されていますが、経費に関するデータは乏しく、また、10年程度の詳細なデータの推移は公開されているものの、統一基準がないため、市町村間での比較が困難でした。そこで、環境省が公表している「廃棄物処理技術情報」などのデータも活用しながら、全ての自治体のデータを統一的な視点で整理・分析する必要性がありました。既存データにはいくつかの欠損部分がありました。例えば、平成10年度から平成17年度までのデータには「収集運搬施設」に関する経費が含まれておらず、平成10年度から平成16年度までのデータには「調査研究費」が含まれていませんでした。これらの欠損データは、分析の精度に影響を与える可能性があるため、本研究では、これらの部分を0で置き換えて計算を行うなどの補正を行いました。しかし、この補正によって一時経費を過小評価する可能性も考慮し、結果の解釈には注意を払いました。「その他」として計上されている経費の中に「調査研究費」が含まれている可能性も検討し、データの解釈には細心の注意を払いました。これらのデータの限界を踏まえつつ、可能な限り正確な分析を行うために、データの補正や解釈に工夫を凝らしました。
3. 平成10年度と平成20年度の経費分布比較と市町村合併の影響
平成10年度と平成20年度の愛知県市町村におけるごみ処理経費の分布を比較することで、10年間における変化を分析しました。2つの年度の分布図は形は似ていますが、座標の単位が異なることに注意が必要です。単純に分布の広がりの変化から、10年間で大きく改善されたと結論づけることはできません。例えば、平成10年度の分布図で右上に位置する富山村は、平成20年度の分布図には存在しません。これは、2005年11月に豊根村と合併したためです。この事例からも分かるように、市町村合併は、仮に処理の実態に変化がなくても、分布の広がりを小さくする効果があります。この点を考慮し、経費分布の変化を解釈する必要があります。さらに、図2.18と表2.4から、運搬費割合が増えるにつれて一人当たり経常費が減少する傾向が見られました。特に、市町村を対象とした図2.19ではこの傾向がより鮮明に示されています。瀬戸市は一人当たり経費が低く、これは一人当たり経常費が少ないことが原因です。最終処分費割合が極端に低い市町村は、組合で処分しているか、既に埋立地を所有している可能性が高いです。逆に、半田市は最終処分費割合が55%と高く、これは平成20年度に最終処分場の工事費を計上していることが原因と考えられます。
III.一部事務組合の役割と財務分析 組合分担金と経費の関連性
本研究では、一部事務組合がごみ処理行政において重要な役割を果たしている点を指摘しました。小規模自治体では一般的な組織であり、組合分担金を通じてごみ処理経費が負担されています。しかし、この組合分担金の算定方法や、ごみ処理経費への算入方法に不透明な点があり、正確なごみ処理経費と経費効率の把握を阻害していることがわかりました。 いくつかの一部事務組合(例:刈谷知立環境組合、尾三衛生組合、江南丹羽環境管理組合、北設広域事務組合、衣浦衛生組合など)の事例を分析し、組合分担金の割合や、経費構成、焼却炉や最終処分場の状況、リサイクル率などを詳細に調べました。各組合におけるデータの不整合や課題を明らかにしました。
1. 一部事務組合の役割と構造
本研究は、愛知県下の一般廃棄物処理行政において、一部事務組合が果たす役割とその財務状況に焦点を当てています。一部事務組合は、地方自治法第284条1項に基づき設立され、ごみ処理だけでなく、し尿処理、消防・防災など、複数の事務を共同で処理する組織です。特に小規模な自治体においては一般的な存在であり、その運営には構成自治体からの「組合分担金」が拠出されます。この組合分担金にはごみ処理経費も含まれているため、これを個々の自治体の経費に加算しなければ、正確なごみ処理費用を把握できず、市町村間の効率性の比較も困難になります。平成22年版地方財政白書によると、平成20年度末には一部事務組合が1449団体存在し、そのうち衛生関係組合は575団体で約40%を占めています。このことから、一部事務組合が愛知県下の衛生行政、ひいてはごみ処理行政において大きな比重を占めていることがわかります。研究では、この一部事務組合を対象とした訪問調査を行い、組合分担金の実態を詳細に分析しました。
2. 組合分担金の算定と経費算定上の課題
一部事務組合における組合分担金の算定方法には、人口割、昼間人口割、均等割、搬入割などがあり、それぞれの構成自治体の合意に基づいて決定され、規約化されています。しかし、愛知県内の一部の事務組合では、ごみ処理に関しては昼間人口割が用いられていないケースもありました。このことは、組合分担金の算定方法に統一性がなく、市町村間での比較をさらに困難にしている要因の一つと考えられます。さらに、環境庁(現環境省)のデータや愛知県のデータでは、この組合分担金の扱いに問題があることが判明しました。自治体や一部事務組合への聞き取り調査から、ごみ処理にかかる組合分担金を抽出することは単純ではなく、ごみ処理行政における考え方によって、経費に算入されたりされなかったりする項目が存在することが明らかになりました。そのため、正確なごみ処理経費を算出するには、単に既存のデータをそのまま利用するのではなく、個々の組合の状況や経費算定方法を詳細に調査する必要がありました。本研究では、この課題を克服するために、聞き取り調査で得られた情報を基に、組合分担金を適切に反映させた経費の再計算を行い、より正確な分析を行いました。経費算定式は、経費 = 合計 + 組合歳出 × 分担金割合 と表現でき、平成20年度の「愛知集計結果(経費)」の「組合分担金内訳」と「廃棄物事業経費(市町村)」を基に分析しました。
3. 事例分析 刈谷知立環境組合 尾三衛生組合等の事例
研究では、複数の具体的な一部事務組合を事例として分析しています。例えば、平成20年度の清掃一部事務組合に対する市町村の分担金割合を見ると、刈谷知立環境組合の分担金割合が特に小さいのは、その年度に大きな建設改良費が発生したためです。差額は地方債、国庫支出金、特定財源から支出されました。一方、尾三衛生組合の分担金割合が100%を超えているのは、分担金には経常費だけでなく建設費分も含まれているのに対し、全支出には経常費のみが計上されているためです。これらの事例は、組合分担金の算定方法や経費計上方法の違いが、市町村間の一般廃棄物処理経費の比較を困難にしていることを示しています。この他、江南丹羽環境管理組合、北設広域事務組合、衣浦衛生組合なども事例として取り上げ、それぞれの組合におけるごみ処理経費の構成、焼却炉や最終処分場の状況、リサイクル率などについて詳細に分析し、組合分担金と経費の関連性を明らかにしました。これらの事例分析を通じて、一部事務組合におけるごみ処理経費の算定方法の多様性と、それがもたらす分析上の課題を明確化しました。これにより、より正確な一般廃棄物処理行政の効率性評価を行うための重要な知見を得ることができました。
IV.事例研究 効率的なごみ処理システムの成功事例と課題
東海市の高効率焼却炉(処理能力160t/日、焼却残渣率5.1%)や、江南丹羽環境管理組合の古い焼却炉ながら高い性能(焼却残渣率5.7%)を維持している事例を紹介。広域化だけが効率的なごみ処理の手段ではない可能性を示唆しました。一方で、飛島村のように、地理的条件や産業構造がごみ処理に影響を与えるケースも分析。また、リサイクル率の算定における課題や、最終処分場の容量、焼却灰の処理方法についても検討しました。 さらに、いくつかの市町村(例:瀬戸市、半田市など)のごみ処理経費の状況を比較分析し、経費効率に影響を与える要因について考察しました。各市町村の取り組みや課題を具体的に示しました。
1. 高効率焼却炉の事例 東海市と江南丹羽環境管理組合
本研究では、効率的なごみ処理システムの成功事例として、東海市と江南丹羽環境管理組合の焼却施設を取り上げています。東海市は、平成7年に全連続燃焼式焼却炉と灰溶融炉を各2炉運転開始し、焼却残渣率5.1%、処理能力160t/日という高い効率を実現しています。総工費は125億円でした。一方、江南丹羽環境管理組合は、昭和57年竣工の旋回流型流動床式焼却炉を運用しており、古い施設ながら焼却残渣率5.7%、処理能力150t/日という高い性能を維持しています。注目すべきは、総工費が25億円と非常に安価であった点です。この事例から、焼却炉の効率を高めるために、必ずしも広域化が必須ではないことが示唆されています。これらの事例は、ごみ処理施設の設計や運用方法によって、費用対効果に大きな違いが生じることを示すものです。また、豊川・宝飯衛生組合は、豊川市と小坂井町の合併により2010年2月1日に解散し、業務は豊川市に継承されています。この事例は、市町村合併によるごみ処理行政の再編が、効率性向上に繋がる可能性を示唆する一方で、再編に伴う課題も存在することを示しています。
2. ごみ処理における課題 飛島村の事例とリサイクル率の算定
飛島村は、資源ごみ・不燃ごみの排出量が人口あたりで極めて高い数値を示しており、この要因を分析しました。飛島村には港湾・工場が立地し、固定資産税収入が多く、昼間人口も多いことが背景にあります。また、火災発生時の可燃ごみの処理において、時間的・スペース的な余裕のある海部クリーンセンターへの搬送、分別困難なごみの飛島村への委託など、特殊な事情が影響していることが分かりました。さらに、飛島村の最終処分場はそれほど大きくないものの、自村で発生するごみは処理できる規模です。リサイクル率の算定においては、新聞回収やスーパーへの直接持ち込みなど、自治体のデータに含まれないリサイクル量があること、町内会などの自主的な集団回収量も自治体データに反映されない点などを指摘しています。これらの要素は、環境省データだけでは正確なリサイクル率を評価できないことを示しています。これらの事例は、ごみ処理システムの効率性を評価する際には、地域特性や社会状況を考慮する必要があることを示しています。
3. 広域化計画と最終処分場の課題 海部地区と東三河ブロックの事例
県の広域化計画では、海部地区は平成15年度に八穂クリーンセンターに集約されました。これは、昭和58年9月に前身の津島市ほか十一町村衛生組合で広域処理を実現した歴史的経緯と、海部津島地域でのまとまりの良さによるものです。しかし、広域化計画が必ずしも全ての地域でスムーズに進んでいるわけではありません。東三河ブロックでは、平成23年度に「東三河ごみ焼却施設広域化計画」を策定中で、パブリックコメント手続きを実施している段階でした。この計画では、第一段階として新城市と北設地区の統合を目指しており、北設広域事務組合はごみの中継施設を設けた上で焼却施設を廃止し、新城市の焼却施設に処理を委託する予定です。最終処分場についても課題があります。北設広域事務組合では、滝の入最終処分場が数年で満杯となる見込みであり、新たな候補地が見つかっていない状況でした。そのため、平成14年9月以降は、焼却灰・ガラス残渣等の処分をASECや株式会社ウィズウェイストジャパンなどに外部委託している状況です。これらの事例は、ごみ処理行政における広域化のメリットとデメリット、最終処分場の容量不足という喫緊の課題を示しており、将来的なごみ処理システムの持続可能性を考える上で重要な示唆を与えています。特に、焼却灰の処理方法や最終処分場の将来計画は、今後のごみ処理行政において重要な検討課題となっています。
V.環境マネジメントと持続可能なごみ処理行政 今後の展望
いくつかの一部事務組合へのインタビュー調査を通して、環境マネジメントの取り組み(例:エコアクション21認証取得)や、ごみ処理経費削減のための工夫(節電、エコドライブなど)について分析しました。 また、焼却炉の老朽化対策、最終処分場の将来計画、広域化計画の進捗状況なども調査しました。 特に、ダイオキシン類排出基準の遵守状況や、その管理方法についても言及。将来に向けて、持続可能なごみ処理行政を実現するための課題と展望を示しました。
1. 環境マネジメントの取り組み エコアクション21と経費削減努力
本研究では、持続可能なごみ処理行政に向けた環境マネジメントの取り組みについても考察しています。いくつかの自治体では、エコアクション21の認証を取得しており、2年間で約40万円の費用を費やしています。この取り組みは職員の意識改革に繋がり、一定の効果を上げていると評価されています。経費削減の面では、節電やエコドライブの徹底など、経費をかけずにできる対策はやり尽くしているとのことでした。しかし、節電においても、ある一定レベル以下に削減することが難しく、さらなる工夫が必要だと認識しています。例えば、建物の断熱性を高めるためにガラスフィルムを貼ることも検討されていますが、費用対効果の面から慎重に検討する必要があります。また、電力の契約方法についても、瞬間最大ワット数を下げることで経費削減を図る検討が行われています。これらの取り組みは、限られた予算の中で、環境負荷の低減と経費削減の両立を目指す自治体の努力を示しています。エコアクション21の認証取得後、市民や構成自治体からの反応は特にないものの、就職活動の志望動機にされるケースがあるなど、一定の社会的な評価は得られているようです。
2. ISO14001とエコアクション21の比較 環境マネジメント認証の選択
環境マネジメントシステムの認証取得においては、ISO14001とエコアクション21の2つの選択肢がありました。ISO14001は審査・取得費用が高く、約500万円が必要となる一方、エコアクション21は審査費用が20~30万円、登録費用が10万円と、はるかに安価です。そのため、費用対効果の観点からエコアクション21を選択した自治体もありました。ISO14001の趣旨を最大限に反映させながら、自主的に環境マネジメントを行うという考え方も示されています。エコアクション21は2年ごとの更新が必要であり、更新時にも導入時と同程度の費用がかかりますが、外部の第三者による審査を受けることで、環境マネジメントの改善に繋がると判断しているようです。あま市では、平成15年度から温暖化対策委員会が活動しており、ISO14001の認証取得も検討されましたが、費用や人員配置の課題からエコアクション21を選択しました。この選択は、費用効率性と外部評価による環境マネジメントの向上という両面を考慮した結果と言えるでしょう。
3. 焼却灰 溶融スラグの処理とリサイクル 最終処分場の将来計画
焼却灰や溶融スラグの処理方法についても、持続可能なごみ処理行政を考える上で重要なポイントとなります。一部の自治体では、溶融炉を所有し、溶融飛灰をリサイクルすることで最終処分場の延命化を図っています。溶融飛灰は塩分濃度が高いため自前の処分場では処理できないため、三菱マテリアル、住友金属、同和鉱業(青森)などの鉱山会社に委託し、山元還元を行い、鉄やマンガンなどの鉱物を析出させています。溶融スラグは路盤材や骨材として再利用する計画ですが、金属分を除去していないためリサイクルが困難なケースもあります。一部の組合では、焼却灰を中部リサイクル(株)に委託し、完全溶融によるリサイクルを行っています。しかし、このリサイクルされる溶融スラグは数字に反映されていません。最終処分場の容量についても、多くの自治体で将来的な問題を抱えています。北設広域事務組合では、滝の入最終処分場が数年で満杯となる見込みであり、新たな候補地が見つかっていないため、ASECや株式会社ウィズウェイストジャパンなどに外部委託している状況です。これらの事例は、焼却灰や溶融スラグの処理方法、最終処分場の将来計画などを検討する上で、様々な課題が存在することを示しています。
文書参照
- 一般廃棄物処理実態調査結果
- 一般廃棄物処理実態調査結果:統計表一覧
- 市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針 (環境省)
- 一般廃棄物会計基準 (環境省 大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課)
