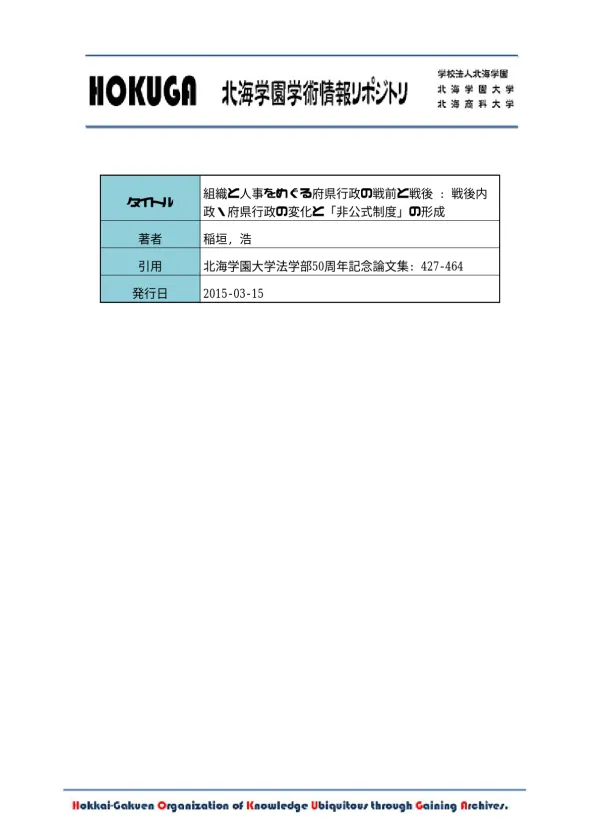
戦後府県行政の組織人事:非公式制度の形成
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 692.25 KB |
| 著者 | 稲垣 浩 |
概要
I.戦後日本における地方自治と内務省の役割 公選知事 制度導入前後
本資料は、戦後日本の地方自治における内務省(現総務省)の強い影響力と、公選知事制度導入前後における府県行政の変遷を分析しています。特に、内務省による人事権の掌握、組織改革、そして個々の省庁による府県への介入が、地方自治の自主性を阻害した側面を明らかにしています。地方分権の進展という観点から、戦後地方行政の構造と制度、そして公務員制度の変遷が、地方自治体の自主性と多様性の確保にどう影響したのかが論点となっています。主要なキーワードとして、地方自治体、内務省、公選知事、人事権、組織改革、地方分権などが挙げられます。
1. 公選知事制度導入の背景と内務省の意図
頻繁な政党人事による知事の休職・異動を抑制するため、内務省は公選知事制度導入を推進しました。これは、内務省が幹部人事権や組織編成を掌握することで、実質的に公選知事を統制できると考えたためです。しかし、中央政府レベルの制度改革と当時の府県行政の実態との関係について、十分な検討がなされていなかった可能性も示唆されています。特に、三級官吏の人事については、知事の専属的権限とされていた点が挙げられます(古井1966:75、地方自治研究資料センター1977a:169)。また、不況打開のための農村漁村再生運動推進を目的とした府県経済行政の拡張も、内務省の経済政策への関与という文脈で捉えることができます。戦時体制下における物資流通等の経済政策が重要な課題であったことも背景にあります。
2. 府県行政におけるセクショナリズムと個別省庁の介入
府県庁内部のセクショナリズムは、個別補助金の問題と結びつくことで深刻化しました。個別省庁は、出先機関設置によって府県から事務を分離しようとする動きを見せ、厚生省は衛生行政、建設省は戦後の住宅整備問題を理由に、それぞれ府県に特定の部局設置を働きかけていました。知事以下職員の公吏化を容認せざるを得なかった状況下で、内務省は府県組織や人事を実質的に統制できるような制度づくりを進めました。これにより、総合行政であったはずの府県行政は、官僚の壁、割拠主義、バラバラ政策といった問題を抱え、一環性のある政策が実現できなくなっていったのです。地方制度調査会での議論を経て、政府案では地方自治法において規定する基本的な局部の外、都道府県は左に掲げる局部を設けるものとする表現に修正されました(地方自治研究資料センター編1977b:232)。条例変更には内務大臣の許可が必要となり、府県の自主的な組織編成は地方自治法と内務大臣によって規制されることになりました。
3. 地方分権と人事交流 国と府県の協調と対立
府県と国、あるいは他府県との自由で対等な交流の必要性が指摘されました。しかし、具体的な交流制度については結論が出ませんでした。将来的な地方分権の進展に伴い交流は減少するものの、当面は内務省と知事会議との間で交流人事のための機関を設置し、交流を進める必要性が述べられています。任用制度を共通化する場合でも、全国的な一つの自治的な組織によって運用されるべきだと主張する声もありました。省の廃止や引上げによって職務を続けられなくなった職員が、戦後府県に幹部職員として就職するケースがありました。旧植民地での行政経験を持つ職員の採用は、復興開発や農業政策を抱えていた当時の府県にとって貴重な資源となりました。内務省による全国的な人事を行い、農業や土木関係の課長は戦前・戦後を通して複数の府県で勤務経験を持つ者も多かったことから、こうした経験が地方行政に一定の影響を与えたと考えられます。
4. 地方自治体の制度形成と正統性の問題 インフォーマルな制度の存在
戦後の地方自治官庁による制度形成の正統性は、自治体の首長や立場を有効に代弁しているという理解に基づいていると指摘されています(伊藤1983:8)。しかし、地方自治官庁の行動が本当に自治体の首長や立場を有効に代弁しているかどうかの府県の判断は必ずしも明確ではありませんでした。地方官人事維持を目指した法制度づくりは、公務員制度の一本化の挫折やあっせん機関の問題に見られたように、驚くほどインフォーマルな制度を生み出しました。こうした戦後府県行政をめぐる国と府県の関係構造の中で、インフォーマルな制度が形成されていったのです。例えば、山形県は人事刷新や一般行政職員の練磨の機会付与という点で人事交流の必要性を認めながらも、公選知事からの反発に遭いました。また、地方団体への送り出しについて自治庁に申し出て、自治庁がその実現を図るという方式を確立しなければならないとされました(松村1954:311)。
II.内務省による府県行政への介入 人事と組織構造への影響
内務省は、人事権を掌握することで、府県の組織編成や人事異動に強い影響力を及ぼしました。特に、幹部職員の人事や組織改編への介入を通して、事実上公選知事を統制しようとした試みが見て取れます。個別の省庁も、府県に自らの出先機関の設置を要求するなど、府県行政に深く介入していました。その結果、府県行政はセクショナリズムが深刻化し、一環性のある政策の展開が困難になるという問題が発生しました。 関連キーワードとして、人事権、組織構造、セクショナリズム、出先機関、政策の一環性などが挙げられます。
1. 人事権掌握を通じた府県行政の統制
内務省は、府県行政を掌握するため、幹部の人事権や組織編成への統制を強化しました。これは、公選知事に対しても実質的な統制力を及ぼす狙いがあったと考えられます。内務省の民政局とは異なり、人事権を握ることで府県行政の非効率化を招いたという批判も多く見られました。内務省は、部下の任免権を完全に掌握させるような性格の文書を発表し、地方制度調査会を設置して地方制度の再検討を進めました(内事局編1948:1)。この調査会では、個別省庁が出先機関を設置して府県から事務を分離することを抑制するための議論が行われました(地方自治研究資料センター編1977a:13)。知事以下職員の公吏化を受け入れざるを得なかった状況の中で、内務省は府県組織や人事を実質的に統制できるような制度づくりを積極的に進めたのです。
2. 個別省庁による府県への介入と組織構造の変化
厚生省は衛生行政、建設省は戦後の住宅整備問題を理由に、府県に特定の部局設置を働きかけるなど、個別省庁は府県行政に深く介入していました。こうした個別省庁の意向に沿った決定を公選知事が自主的に下す場合も想定されました。政府案では、地方自治法で規定する基本的な局部の外、都道府県は特定の局部を設けるものとする表現に修正されました(地方自治研究資料センター編1977b:232)。条例変更には内務大臣の許可が必要となり、府県による自主的な組織編成は地方自治法と内務大臣によって規制されることになりました。多くの府県で公選知事の権力基盤となっていた企画担当部局は、地方自治法に基づく設置規制の対象となりました。この結果、総合行政であったはずの府県行政は、官僚の障壁や割拠主義、バラバラ政策といった問題を抱え、一環性のある政策が実現できなくなっていったのです。
3. 府県組織の内部構造とセクショナリズムの悪化
府県庁内部におけるセクショナリズムは、個別補助金の問題と結びつくことで一層深刻化しました。これは、個別省庁による介入と、内務省による人事権掌握、組織改編への影響力が複雑に絡み合った結果として生じた問題です。 地方自治体の自主的な組織編成が制限されたことで、府県は状況に応じて組織を再編するなど、公式制度の外で調整を行う必要性に迫られました。 六部以内での自主的な組織決定も指摘されています(地方行政調査委員会編1952:36)。しかし、行政の簡素化という観点から、都道府県の部局を更に増設する場合には、あらかじめ協議を受けるようになっています。これらの状況は、府県行政における意思決定プロセスと構造が、政策決定に大きな影響を与えていることを示唆しています。
III.地方自治体の自主性と国との関係 改革の模索と課題
公選知事制度導入後も、地方自治体の自主性をめぐる国と地方自治体の関係は複雑でした。地方自治法の制定や改定、そして人事交流制度の導入など、地方自治体の自主性と国の統制のバランスが重要な課題となっていました。自治庁の役割や、人事交流における各省庁との連携、そして公務員制度改革の過程においても、地方自治体の立場をいかに反映させるかが焦点となりました。 重要なキーワードには、地方自治法、人事交流、自治庁、公務員制度改革、国と地方自治体の関係が含まれます。特に、地方自治体の自主性確保のための様々な改革の試みとその成果、課題が議論されています。
1. 地方自治法と府県組織の規制
地方自治法の制定・改定において、府県組織の編成は内務大臣の許可を必要とするなど、国による規制が強く反映されました。条例変更も内務大臣の許可が必要となり、府県による自主的な組織編成は大きく制限されたのです。多くの府県において公選知事の権力基盤となっていた企画担当部局も、地方自治法に基づく設置規制の対象となりました。これは、地方自治体の自主性を制限する要因の一つとなり、地方分権の進展という観点からは課題となりました。 一方、地方行政の簡素化を目的として、都道府県の部局を増設する場合にはあらかじめ協議を受けるという規定もありましたが、府県側の自主性を完全に保障するものではありませんでした。地方制度調査会での議論や、政府案の修正過程からも、国と地方自治体との間で、制度設計をめぐる様々な摩擦や調整があったことが伺えます。
2. 人事交流制度と自治庁の役割
府県と国、あるいは他府県間の自由で対等な交流の必要性は指摘されていましたが、具体的な交流制度については結論に至りませんでした。将来的な地方分権の進展を考慮し、当面は内務省と知事会議との間で人事交流のための機関を設置し、交流を進める必要性が述べられています。 しかし、自治庁はあくまで人事交流の斡旋主体にとどまり、各省庁との協力体制構築が求められるなど、地方自治体の自主的な人事運営は依然として課題を抱えていました。 人事交流の必要性を認めながらも、公選知事からの反発に遭うケースもありました。例えば、山形県は人事の刷新や一般行政職員の練磨の機会付与を目的として人事交流の必要性を認めていましたが、具体的な運用においては、国との関係調整、そして地方自治体自身の意思決定が複雑に絡み合っていました。 地方団体への職員の送り出しについても、自治庁への申し出を基に自治庁が実現を図るという方式の確立が必要とされました(松村1954:311)。
3. 地方公務員制度改革と地方自治体の対応
国家公務員の新しい恩給制度に都道府県職員を包含させることが、地方自治庁から各府県に通達されました。しかし、内務省による地方官人事のようにスムーズに進まず、実際の異動には半年以上かかったという指摘もあります(横浜市総務局市史編纂室編1993:75)。 地方自治体側は、公正な選考委員会を設置してその選考に合格した者の中から任命権者が採用するという制度を求めており、内務省主導の人事システムには強い反発がありました。大沢埼玉県知事が、地方制度調査会の公聴会でこの点を強く主張したことが示されています。 こうした状況は、地方自治体の自主性をめぐる国との関係において、法制度上の規定だけでなく、実際の運用における様々な摩擦や調整、そして地方自治体側の強い抵抗があったことを示しています。地方公務員の人事交流についても、国と地方自治体との間のバランス、そして自治体間の連携強化が重要な課題であったことが分かります。
IV.地方公務員人事と制度改革 効率性と公平性の課題
地方公務員の人事制度は、国の人事制度との整合性や、人事交流による効率性向上、そして公平な人事選考の確立という課題を抱えていました。恩給制度や任用制度の統一化、人事交流の推進、そして公正な選考委員会の設置など、様々な改革が試みられました。しかしながら、内務省による地方官人事への介入や、公選知事との摩擦、さらには地方自治体間の連携不足など、様々な問題点が浮き彫りになりました。キーワードとしては、地方公務員、人事制度、人事交流、恩給制度、任用制度、公平な選考などが挙げられます。
1. 地方公務員人事制度の課題 国との整合性と公平性
地方公務員の人事制度は、国家公務員制度との整合性、人事交流による効率性向上、そして公平な人事選考の確立といった課題を抱えていました。地方自治庁は、当時人事院で検討されていた国家公務員の新しい恩給制度に、都道府県職員を包括的に加入させることを各府県に通達しました。しかし、内務省による地方官人事のように円滑に進まず、実際の異動には半年以上かかったという報告もあります(横浜市総務局市史編纂室編1993:75)。府県側は、公正な選考委員会を設置し、その選考に合格した者の中から任命権者が採用するという制度を求めていました。大沢埼玉県知事は、地方制度調査会の公聴会でこの点を強く主張し、内務省主導の人事システムに反対しました。 香川県では恩給年限が1年から始まるなど、不合理な状況も見られました。これは、将来の生活権の問題にも関わると指摘されています。
2. 人事交流制度の推進と課題 自治体間の連携と国との関係
人事交流制度の推進においては、自治庁が人事交流の斡旋主体となる必要性、そして地方団体と各省庁の協力体制の構築が求められました。しかし、公選知事からの反発に遭うケースもありました。山形県は、人事の刷新や一般行政職員の練磨の機会付与という観点から人事交流の必要性を認めていましたが、その運用においては様々な課題がありました。 地方団体への職員の送り出しについても、自治庁に申し出て、自治庁がその実現を図るという方式を確立する必要性が指摘されています(松村1954:311)。 これらの事例から、人事交流制度の円滑な運用には、国と地方自治体間の連携、そして地方自治体間の協力体制の構築が不可欠であり、その実現には多くの課題があったことが分かります。
3. 任用制度の共通化と自治的な組織運営
任用制度の共通化についても、全国的な一つの自治的な組織によって運用されるべきだという主張がありました。これは、地方公務員人事の効率性と公平性を確保するための重要な視点でした。しかし、実際には内務省による人事権の掌握や個別省庁の介入など、地方自治体の自主性を阻害する要因が数多く存在していました。 戦前からの個別省庁による関係部局への官僚の送り込みや、府県が状況に応じて組織を再編するなどの対応は、公式制度の外で調整を行うインフォーマルな制度の存在を示唆しています。 伊藤大一が指摘するように、戦後の地方自治官庁による制度形成の正統性は、自治体の首長や立場を有効に代弁しているという理解に基づいていますが、府県側の判断は必ずしも明確ではありませんでした(伊藤1983:8)。これは、地方公務員人事制度改革における、国と地方自治体間の力関係、そして制度の透明性、公平性といった問題が複雑に絡み合っていたことを示しています。
