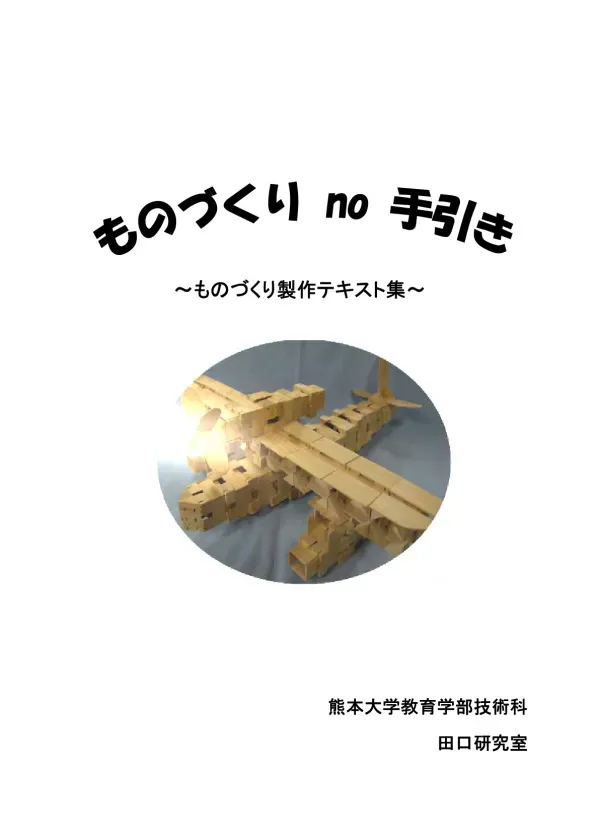
手作り工作テキスト集:材料から作品まで
文書情報
| 学校 | 熊本市内の大学(推定) |
| 専攻 | ものづくり、手工芸、技術科など(推定) |
| 場所 | 熊本市 |
| 文書タイプ | テキスト集 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.86 MB |
概要
I.安全な道具の使い方とケナフ い草を使った工作
この資料では、安全な工作のための基本的な道具の使い方を説明しています。特に、かなづちの使用や、接着剤の扱い方、カッターナイフの安全な使い方について解説しています。また、環境に配慮した材料として、ケナフやい草を使った様々な工作を紹介しています。ケナフは二酸化炭素吸収効果が高い反面、外来種であるという側面も踏まえ、環境への影響について考えるきっかけを提供する教材として活用されています。い草は熊本県山鹿市鹿本町来民の栗川商店(〒861-0331 熊本県山鹿市鹿本町来民 1648 TEL.0968-46-2051 FAX.0968-46-5175)から入手可能な、伝統工芸「来民うちわ」の材料としても使用できます。 これらの材料を用いた具体的な工作例として、紙すき、風車、ランプ、そして様々な小物作りなどが紹介されています。 ペットボトル等の廃材の活用方法も提案されています。安全な作業環境と適切な材料管理の重要性が強調されています。
1. かなづちの安全な使用方法
このセクションでは、かなづちを使用する際の安全対策について詳述しています。まず、使用前にかなづちの金属部のぐらつきを確認し、ぐらついている場合は柄を持って柄尻を台に叩きつけることで修正するよう指示しています。これは、作業中の破損や怪我を防ぐための重要な手順です。次に、釘を打つ際には必ずきり(四つ目きり)で下穴を開けるよう推奨しています。これは、釘が木材にまっすぐに打ち込まれ、割れや曲がりの発生を防ぐためです。釘を打つ位置についても、材料の中央に打つこと、端部に打つ場合は材料の端から適切な距離を空けることを強調しています。これらの手順は、正確で安全な作業を行うために不可欠です。 さらに、適切な釘の打ち込み方法も説明されています。下穴を開けることによって、釘が木材にスムーズに入り、割れや曲がりが防止できます。また、釘を打つ位置も重要で、材料の中央に打つことで強度を高めることができます。端部に打つ場合は、材料の端から適切な距離を空けることで、木材の割れを防ぎます。安全な作業環境の確保と、道具の適切な使用方法が、正確な作業と安全を確保する上で非常に重要であることがこのセクションを通して強調されています。
2. 接着剤の適切な使用方法と圧力のかけ方
接着剤の使用に関して、量が多ければ良いというわけではないことを明確に示しています。接着剤は全面に薄く一様に塗布することが重要であり、塗りすぎは接着力を弱める可能性があるため注意が必要であると説明しています。これは、接着剤の特性を理解し、適切な量を使用することで、より強い接着を実現するための重要なポイントです。さらに、接着剤を塗布した後、接着部に圧力をかけることで接着強度を向上させる方法が紹介されています。クランプなどの工具を用いて両側から挟む方法や、釘を打つことで圧力を加える方法が例として挙げられています。これらの方法は、接着剤が完全に硬化する前に適切な圧力をかけることで、より強力で耐久性のある接着を実現するために有効な手段です。接着剤の使用においては、適切な量、均一な塗布、そして十分な圧力が、成功の鍵となることがこのセクションから読み取れます。
3. プラスチックカッターの安全な使用方法
このセクションでは、プラスチックカッターの安全な使用方法について解説しています。プラスチックカッターは、定規を案内にしてアクリルを削り取るように使用し、半分程度削ったら力を加えて折る方法が示されています。材料が厚い場合は両側から削る必要があると説明しています。ペットボトルを溶かして切断する際に煙が発生する可能性もあるため、換気にも注意する必要があることを示唆しています。 また、熱を利用した切断方法の利点として、切り口が鋭くならずケガの危険性が少ない点を強調しています。これは、カッターやハサミと比較した際の大きなメリットであり、安全な作業環境を確保する上で重要な要素となっています。ホームセンターなどで100~300円程度で販売されていることも記載されており、入手性の容易さも示唆されています。 安全な使用方法と、その利点、入手方法が簡潔にまとめられています。
4. ケナフとイ草を用いた教材とEMS環境推進室
このセクションでは、ケナフやイ草を用いた教材について説明し、それらを開発したEMS環境推進室を紹介しています。EMS環境推進室は、ものづくりを通して伝統文化の継承と青少年の育成を目的として活動しており、生涯学習講座や国際交流事業なども行っていることがわかります。ケナフ教材については、正しく管理された場所でのみ育成しており、数に限りがあるため、教材提供ができない場合もあると注意書きがあります。これは、ケナフの育成管理に十分な配慮がなされていることを示しています。また、ケナフは二酸化炭素吸収効果が高い反面、外来種であるという点も考慮する必要があると述べられており、環境問題への意識を高める教材であることが分かります。イ草を用いた教材は、熊本県山鹿市の栗川商店から入手可能な来民うちわの材料を使用することで、地域との連携も強調されています。これらの教材は、環境問題への意識や伝統文化への理解を深めることを目的として開発されており、地域社会との連携を重視した取り組みであることが示唆されています。
II.ケナフを使った工作 紙すきとその他の工作
ケナフを使った工作では、ケナフの繊維を用いた紙すきが紹介されています。牛乳パックを再利用したパルプ作成方法と、ケナフ繊維のみを使ったパルプ作成方法の両方が解説されています。ミキサーの使用や乾燥方法、仕上げの成形方法などの詳細な手順が示されています。その他、ケナフの茎を使った工作も紹介されており、カッターやノコギリを用いた適切な切断方法、接着方法などが説明されています。材料の管理方法についても、適切な収穫と管理の重要性が強調されており、乱雑な育成は避けるべきだと述べられています。
1. ケナフを用いた紙すき
このセクションでは、ケナフを用いた紙すきの手順が詳細に説明されています。まず、材料として牛乳パックを活用する方法が提示されています。牛乳パックを丁寧に洗浄し、折り目に沿って切り分けてパルプを作成する工程が、段階的に解説されています。具体的には、牛乳パックの側面を8枚に切り分け、30分から1時間煮沸し、フィルムを剥がした後、水と一緒にミキサーにかけてパルプを作る方法が示されています。 一方、ケナフの繊維のみを用いた紙すきの方法も紹介されています。この方法では、漂白されたケナフの繊維と水をミキサーにかけることでパルプが完成します。きれいな紙をすくためには、パルプが均一に細かく繊維状になっていることが重要であり、必要に応じて水を足すなどの調整を行うよう指示されています。 紙すきの工程としては、パルプを型枠に入れ、空気を抜いてすき間を作らないように注意深く押さえること、しっかりと押さえた後乾燥させること、そして乾燥後にハサミで成形を行うことが説明されています。 牛乳パックとケナフ繊維、それぞれの材料を使った紙すきの方法が提示されており、材料の選択の幅が広がることがわかります。また、紙すきの工程が丁寧に解説されていることで、初心者でも比較的容易に実践できるよう工夫されていることが伺えます。
2. ケナフの茎を用いたその他の工作
ケナフの茎を使った工作についても、具体的な手順が説明されています。ケナフの茎を縦に割る方法として、カッターで切れ込みを入れ、定規などを用いて繊維に沿って割る方法が示されています。この際、カッターの刃の進行方向に手や指がないように注意するよう促しています。また、ノコギリを使用する場合は、二人一組で作業を行うことを推奨しています。 ケナフの茎の形を整える方法として、直線で大きく切り取った後、残りの部分を紙やすりで削る方法も示されています。 ケナフ同士の接着方法についても言及があり、点接着よりも面接着の方が強度が高いことから、斜めに加工するなどの工夫を促しています。 さらに、ケナフの繊維を使った工作では、繊維の配置や色、大きさなどを考慮し、完成形をイメージしながら材料を選び、作業を進めることの重要性が強調されています。 これらの説明から、ケナフの茎の加工方法、接着方法、そしてデザイン段階における創意工夫の重要性が理解できます。 安全な作業方法と、より強度を高めるための工夫が詳細に解説されている点が特徴的です。
III.い草を使った工作 ランプとその他の工作
い草を使った工作では、い草のロープを使ったランプ作りが中心です。 はさみとハンマー、接着剤のみを使用するため比較的安全に製作でき、LED を入れることでランプとして使用可能になります。地域(八代)との関連付けも図れる点が強調されています。 その他のい草を使った工作も含まれている可能性がありますが、このセクションではランプ作りが主な焦点となっています。
1. い草を使ったランプの製作
このセクションでは、い草のロープを使ってランプを作る方法が説明されています。はさみ、ハンマー、接着剤のみを使用するため、比較的安全に製作できるとされています。い草のロープを編み込んでいく工程が中心で、中にLEDを入れることでランプとして機能させることができます。難易度としては★★★★☆☆とされており、比較的容易に製作できることが示唆されています。 このランプ作りを通して、い草という身近な材料の特性を理解し、それを用いた創作活動の楽しさを体験することができます。また、材料であるい草が地域(八代)と関連付けられる点も強調されており、地域文化への理解を深める学習機会を提供する教材として位置づけられています。 安全で簡便な製作工程と、地域との関連性、そして完成後の達成感を重視した教材であることがわかります。LEDの組み込み方法や、い草のロープの編み方といった具体的な手順は、このセクションの更なる詳細な説明で明らかになるでしょう。
2. その他のい草工作の可能性
い草を使ったランプ製作以外にも、このセクションでは、い草を用いた様々な工作の可能性を示唆しています。具体的な内容は本文からは読み取れませんが、難易度が★★★★★☆~★★★★★★と幅広く設定されていることから、より高度な技術や技能を必要とする工作も含まれていると推測できます。 難易度が高い工作は、彫刻刀を使用する切削作業などが含まれる可能性があり、児童生徒の巧緻性向上に役立つ教材として設計されていると考えられます。製作や使用を通して大きな達成感を味わえるような、より複雑な構造の工作も含まれている可能性があります。 また、日常使用する道具を作ることで、達成感とともに道具を大切にする心を育むことを目的とした教材も含まれる可能性があります。 このセクションは、い草を使ったランプ製作を起点に、より多様な工作の可能性を示唆しており、児童生徒の創造性と技能を幅広く育成することを目指していることが伺えます。具体的な工作の種類や手順は、今後の詳細な説明が必要となります。
IV.その他の材料を使った工作
このセクションでは、ペットボトル、アクリル、木材など、様々な材料を使った工作が紹介されています。具体的な例として、アクリルミラーを使った万華鏡、ペットボトルを使った風車、廃油を使った石鹸作りなどが挙げられています。これらの工作では、カッター、ホットカッター、彫刻刀などの工具の安全な使用方法と、材料の加工方法、組み立て方法などの詳細な手順が記載されています。 また、ホットカッターを使用する際の火傷防止や、カッターを使う際のケガ防止など、安全面への配慮が強調されています。 さらに、接着剤やクランプの使用による強度向上、サイズ調整方法など、完成度の高い作品を作るためのコツが解説されています。
1. アクリルミラーを使った万華鏡
このセクションでは、アクリルミラーを用いた万華鏡の製作方法が記述されています。アクリルミラーを指定サイズ(縦10.5cm、横2.5cm)に3枚切り、ミラー面を下にしてテープで固定し三角形を作成します。この三角形を筒の中に入れ、のぞき穴側と三角形の端を合わせることで万華鏡の主要部分を作ります。筒との間に隙間があればすきまテープで調整します。のぞき穴側のプラスチック板は筒と同じか少し小さいサイズにし、製本テープで作るのぞき穴は塞がないように注意が必要です。仕切りのプラスチック板は筒にしっかり入るようサイズ調整し、ホットボンドを使用する場合は、プラスチック板が溶ける可能性があるため、教師が作業を行うべきです。 筒に中身を入れ、プラスチック板で蓋をする際、筒が倒れないよう注意が必要です。 この工程では、アクリルミラーの切断、接着、サイズ調整、そして安全なホットボンドの使用方法といった、精密な作業と安全対策の重要性が強調されています。
2. ペットボトルを使った風車
ペットボトルを使った風車の製作方法が説明されています。使用するペットボトルは、側面が六面あるものが製作しやすいとされています。ペットボトルの上部2/1程度を切り、土台部もホットカッターで切断します。針金を通す向きや土台などは工夫が必要であり、事前に形を構想してから製作に取り組むよう指示されています。カッターやホットカッターを使用する際は、ケガや火傷に十分注意し、安全な作業姿勢を心がける必要があります。 風車の製作においては、ペットボトルの切断、針金の取り付け、そして土台の製作など、複数の工程が含まれています。それぞれの工程において、安全に作業を行うための注意点が記述されているとともに、創意工夫によって完成度を高めることができる余地も残されています。 特に、ホットカッターを使用する際には火傷に注意し、カッターを使用する際にはケガをしないよう、指の位置に十分注意する必要があると強調されています。
3. 廃油を使った石鹸作り
このセクションでは廃油を使った石鹸作りの手順が示されています。油に不純物がない方が出来上がりが良いので、油をしっかりとこす作業が重要であると説明されています。石鹸作りにおいては、材料をしっかりと混ぜ合わせる作業が重要であり、ダマができないよう交代で休みなくかき混ぜる必要があるとされています。 廃油は、お弁当屋さんやレストランなどで無料で入手できる場合が多いですが、入手困難な場合はきれいな油でも代用可能であると説明されています。苛性ソーダと水と廃油を混ぜ合わせる工程は危険を伴うため、教師が行うべきであると強く注意喚起されています。 また、苛性ソーダと水を混ぜ合わせる際にはガスが発生するため、屋外で作業を行い、吸い込まないように注意する必要があると、安全面への配慮が強調されています。 安全な作業手順と、材料の入手方法、そして危険な工程への適切な対応方法が提示されています。
4. その他の工作例と材料
このセクションでは、様々な材料を用いたその他の工作例が簡潔に紹介されています。例えば、竹とんぼ、スプーン、フォークなどの製作方法が示唆されています。竹とんぼでは、羽根のバランスが重要であり、削り方によって飛ぶ性能が変化することを示唆しています。スプーンやフォークの製作では、使用する材料のサイズや形状、加工方法などが示唆されています。 また、これらの工作では、ホームセンターなどで容易に購入できる材料(丸棒、木のへら、L字金具など)が多く用いられていることが分かります。 これらの工作は、基本的な道具と材料を用いて製作できるものが多く、児童生徒の創造性を刺激し、達成感を味わえるよう設計されていると考えられます。 具体的な製作手順は、それぞれ個別の説明が必要となりますが、本セクションでは、多様な工作の可能性を示す導入として機能しています。
