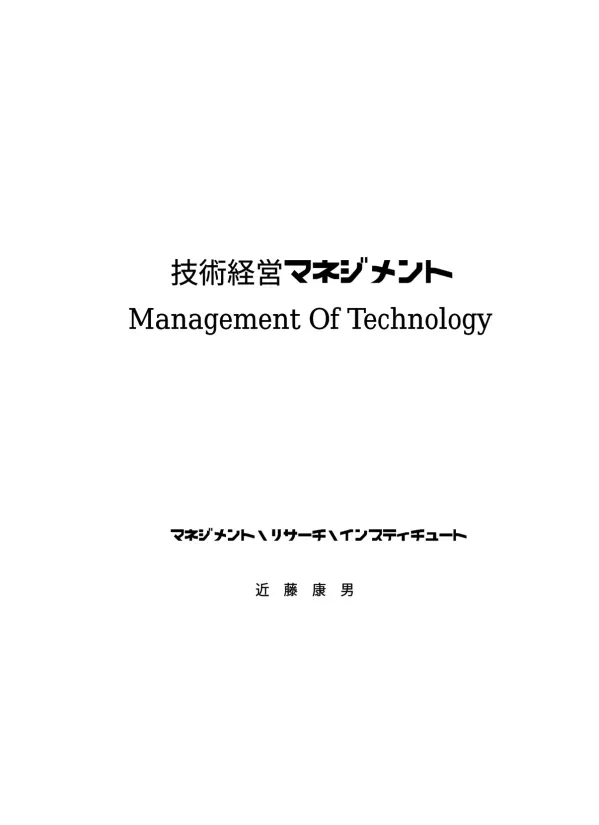
技術経営MOT入門:戦略とマネジメント
文書情報
| 学校 | マネジメント・リサーチ・インスティチュート |
| 専攻 | 技術経営マネジメント (Management Of Technology) |
| 文書タイプ | 教科書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 269.34 KB |
概要
I.MOT 技術経営 プログラムと日本の現状
本資料は、MBAと技術経営(MOT)を統合した大学院プログラムの内容と、技術経営を取り巻く日本の現状を分析しています。特に、巨額な研究開発投資にも関わらず十分な成果が上がっていない現状、System Lock-inによるプラットフォームビジネスの隆盛、そして顧客ソリューションビジネスにおけるIBMの成功例などが論点として挙げられています。米国におけるMOTプログラムの展開や、日米間の研究開発と生産技術の差、知的財産戦略大綱に基づくMOT導入の経緯なども解説されています。 MITスローンスクールのMOTプログラム創設(1981年)や、経済産業省によるMOT導入(2002年)といった重要な歴史的背景も示されています。
1. 日本の技術経営 MOT の現状と課題
日本では長らく技術が重視されてきたものの、近年は研究開発投資の巨額化にも関わらず、その効果が不十分であるという課題が指摘されています。これは「技術ただ乗り論」以降の状況を反映しており、技術開発への投資と競争力強化の間に乖離が生じていることを示唆しています。そのため、技術経営(MOT)への関心が高まっており、経済産業省は2002年度に「知的財産戦略大綱」に基づきMOTの導入を推進しました。この背景には、科学技術創造立国の復権と起業家の創出という目標があります。 また、近年注目を集めているプラットフォームビジネスやSystem Lock-inの概念も、日本の技術経営を考える上で重要な要素です。顧客の問題解決を重視するソリューションビジネスを展開するIBMは、サービス収入が既に過半数を占めるまでに成長しており、ITコンサルティングへの高いニーズを示しています。これらの現状を踏まえ、日本の技術経営における新たな戦略やアプローチが必要とされていると言えるでしょう。
2. 日米技術経営アプローチの比較
製品や商品の事業化プロセスを「発明・企画」「製品開発」「量産・生産」の3段階に分けると、米国は発明・企画、製品開発に強みを持ち、日本は量産・生産に強みを持つという日米間の違いが指摘されています。このため、米国企業は日本の高品質な生産技術を取り入れて競争力を強化してきました。しかし、日本は高品質化やコストダウン、量産技術には優れているものの、研究開発や企画開発においては必ずしも強いとは言えないという指摘があります。 この点において、米国では経営者はMBAホルダーであるケースが多く、「経営大学卒業の職能としての経営業」が存在するのに対し、日本の状況は異なるという指摘もあります。これは、日米間の経営層の育成方法や経営哲学の違いを反映している可能性があります。 こうした日米間の技術開発・事業化アプローチの違いが、技術経営における戦略や組織運営の在り方に影響を与えていると考えられます。
3. MITスローンスクールにおけるMOTプログラムと今後の展望
1981年にMITスローンスクールで創設されたMOTプログラムは、MBAの基礎科目と工学部科目を組み合わせた幅広いカリキュラムを提供しています。このプログラムは、その後全米に広がり、技術経営の教育・研究の中核となっています。 このプログラムの存在は、技術経営の専門性を高め、人材育成の重要性を示す重要な事例です。 日本の大学院においてもMBAに加え技術と戦略並びにマネジメントを統合したコースが提供されていますが、その内容は多様であり、技術を重視してきた日本の歴史的背景と関連していると考えられます。 今後、日本においても、MITスローンスクールのような専門性の高いMOTプログラムの充実や、企業における技術経営の高度化が求められるでしょう。
II.日米企業の技術戦略と競争力
米国企業は上流工程(発明・企画、製品開発)に強く、下流工程(量産・生産)は日本に劣るという現状が指摘されています。そのため、米国企業は日本の高品質な生産技術を取り入れて競争力を高めてきました。一方、日本は生産技術に強みを持つ一方で、研究開発や企画開発の強化が課題となっています。 技術ただ乗り論の問題点や、その後の多額な研究開発投資の有効性に関する議論も含まれています。 サウスウエスト航空の低価格戦略と高い顧客満足度を実現する技術と経営、ボーイングの航空機開発における国際分業とコストダウン戦略、トヨタ生産方式(TPS)のリーン生産、デルの受注生産マネジメント(BTO)などが具体的な事例として取り上げられ、それぞれの競争力の源泉が分析されています。
1. 日米企業の技術開発プロセスにおける違い
事業化プロセスを「発明や企画」「製品開発」「量産・生産」の3段階に分けると、米国企業は「発明や企画」「製品開発」の上流工程に強みを持ち、日本企業は「量産・生産」の下流工程に強みを持つという現状が示されています。このため、米国企業は日本の優れた生産技術を取り入れ、研究開発から生産まで両面で競争力を強化してきました。一方、日本企業は高品質化やコストダウン、量産技術には優れていますが、研究開発や企画開発は必ずしも強いとは言えず、多くの研究開発投資にも関わらず競争力強化に必ずしも繋がらないという課題を抱えています。この点は、日本の技術経営における重要な課題であり、技術経営(MOT)への注目が集まっている理由の一つと言えるでしょう。 この技術開発プロセスにおける日米間の違いが、それぞれの国の企業戦略や競争優位性に大きく影響を与えていることが分かります。
2. 技術ただ乗り論と研究開発投資の効果
日本では「技術ただ乗り論」と呼ばれる、他国の技術を模倣することで発展してきたという議論があります。この論争は、日本の研究開発投資の有効性を問うものであり、巨額な投資にも関わらず十分な成果が上がっていない現状を説明する重要な要素となっています。 世界に冠たるほどの研究開発投資が行われているにも関わらず、その効果が十分ではないという点に、日本の技術経営における課題が示されています。この課題に対処するために、技術経営(MOT)は研究開発管理に重点を置き、投資効果の最大化を目指しています。しかしながら、従来得意としてきた生産技術や保守技術の重要性も忘れてはならないと指摘されています。これは、研究開発のみならず、生産現場における効率化や改善も、企業の競争力強化に不可欠であることを示しています。 研究開発投資の効果を最大化し、競争力を強化していくためには、研究開発から生産、販売に至るまでの全工程における効率性と革新性が求められると言えるでしょう。
3. 成功事例からの考察 サウスウエスト航空 ボーイング トヨタ デル
本資料では、サウスウエスト航空、ボーイング、トヨタ、デルといった企業の事例が紹介され、それぞれの競争力の源泉が分析されています。サウスウエスト航空は、機種の統一による効率化、パイロットと地上スタッフの連携強化、地方空港の活用などを通して、低コスト・高効率を実現し、高い顧客ロイヤルティを獲得しています。ボーイングは、かつては経営の多角化やリスク回避のために国際分業を進めましたが、コストダウンと品質管理の向上によって復活しつつあります。トヨタは、リーン生産方式(TPS)と「カイゼン」文化によって、生産性の継続的向上を図り競争力を維持しています。デルは、BTO(Build To Order)方式による受注生産マネジメントで、在庫日数を最小限に抑えることで高い効率性を実現しています。これらの事例から、それぞれの企業が独自の戦略によって競争力を強化し、持続的な成長を達成していることが分かります。これらの成功事例から、企業がそれぞれの強みを活かし、時代に合わせて柔軟に戦略を変化させていくことが重要であることが示唆されています。
III.ベンチャービジネスの立ち上げと成功要因
米国におけるベンチャービジネスのアーリーステージからイクジット(公開)までの4段階のプロセスが解説されています。エンジェル資金、ベンチャーキャピタルの役割、マーケティング戦略の重要性などが強調されています。 シリコンバレーにおける成功例(インテル、アップル、シスコシステムズなど)や、技術移転組織(TLO)の役割、SECIモデルによる知識創造プロセス、そして3Mのイノベーションを促進する独自の組織文化と知財マネジメントが、具体的な事例として紹介されています。 3Mの成功には、ミニカンパニー制度、カールトン賞といった独自の制度が貢献していることが示唆されています。
1. 米国におけるベンチャービジネスの4段階プロセス
米国におけるベンチャービジネスの立ち上げは、大きく分けて「アーリーステージ」「開発ステージ」「販売拡大ステージ」「イクジットステージ」の4つの段階から構成されています。アーリーステージでは、自己資金やエンジェル資金を用いた創業が行われ、博士号を持つエンジニアや大学教授などが起業することが多いとされています。開発ステージではプロトタイプの完成と事業化に向けた準備が行われます。販売拡大ステージでは製品の普及を目指したマーケティング戦略が重要となります。そして、イクジットステージでは、ベンチャーキャピタルは機関投資家からの資金調達を行い、企業価値を高めて、上場や大企業への売却、合併などを目指します。このプロセスにおいて、ベンチャーキャピタルは資金提供だけでなく、マーケティングや販路開拓といった幅広い事業支援を行います。 東海岸の伝統的優良企業(ベル研、IBM、MIT、ハーバード大学など)と、西海岸のシリコンバレー(インテル、アップル、シスコシステムズ、ネットスケープなど)の成功例も示されています。1970年代にスタンフォード大学から始まった技術移転組織(TLO)や1980年のバイダール法も、大学発ベンチャーの活性化に大きく貢献しています。
2. イノベーションを実現する戦略 SECIモデルと組織構造
従来にない画期的なイノベーションを起こすためには、長期的な基礎研究や大学・国立研究所との連携による技術戦略が重要になります。 知識創造プロセスとしてSECIモデルが紹介されています。これは、暗黙知を形式知に変換し、共有・活用していく4段階のプロセス(共同化、表出化、連結化、内面化)で構成されています。ホンダの「タマ出し会」やホンダシティ開発におけるメタファー・アナロジーの活用例が示されています。 このモデルを実践するには、ミドル・アップダウンマネジメントとハイパーテキスト型組織が重要になります。ミドルマネジメントの関与が、トップのビジョンと現場の実情を融合させる知識経営に繋がるとされています。ハイパーテキスト型組織は、機能別組織とタスクフォースを組み合わせたマトリクス組織であり、共同化・表出化、連結化・内面化の両方に対応できます。 シーズ型とニーズ型のイノベーションの例も示され、レーザー光やトランジスタ、コピー機の発明が紹介されています。
3. 3Mの事例 独自の組織文化とイノベーション創出
3Mは、独自の組織文化とイノベーション創出プロセスによって成功を収めてきた企業として紹介されています。 3Mでは、社員が自由にアイデアを提案でき、承認されれば資金提供を受け、プロジェクトチーム(ミニカンパニー)を結成できます。アイデアの選定基準は「できれば特許が取れる製品・工程を生むアイデアであること」とシンプルに示され、「少し作って、少し売り、またもう少し作る」というサイクルが基本となっています。 ミニカンパニーは、マーケティング、技術、製造の3部門以上からなるチームで構成され、1年分の予算と専任メンバーが与えられ、一定の業績目標(税引前売上高収益率20~25%、ROI20~25%、年成長率10~15%)が設定されています。 3Mでは「テクニカル・フォーラム」のような技術交流の場が設けられ、社員間の連携と知識共有が促進されています。 これに加え、「カールトン賞」のような賞制度も、イノベーション創出を後押しする仕組みとなっています。3Mの事例は、企業文化とイノベーションの強い関連性を示す重要な例と言えるでしょう。
IV.知財マネジメントと日本の課題
知的所有権(特許、商標、著作権など)の重要性と、世界特許制度の動向が説明されています。 日本の知財戦略における課題として、欧米からの技術導入に依存してきた歴史的背景や、オリジナリティの不足、八木アンテナの事例に見られるように、革新的な技術が海外で評価される一方で国内では軽視される傾向などが指摘されています。青色ダイオードの発明者の事例は、日本の技術立国としての課題を浮き彫りにしています。 情報戦の重要性も強調されており、情報通信技術の急速な進化と企業におけるCRM、SFA、ERP、SCM、BIツールの活用が示されています。
1. 知的財産の種類と保護
知的財産とは、特許、実用新案、意匠、商標、著作権、企業秘密・ノウハウなどを指します。特許、実用新案、意匠は出願日または登録日から一定期間保護され、商標は登録日から一定期間保護されます。著作権は論文やソフトウェアなどの複製を保護しますが、アイデア自体は保護の対象外です。企業秘密・ノウハウは、文字通り秘密裏に保護される情報です。これらの知的財産権は、企業の競争優位性を築き、維持するために非常に重要であり、適切な知財マネジメントが不可欠となります。特に、近年では、グローバル化が加速する中で、国際的な知的財産権の保護や活用がますます重要になっています。 日本の場合、近世以降は海外からの技術導入に大きく依存してきた歴史的背景があり、独自の技術開発や知的財産権の活用において課題を抱えていることが指摘されています。
2. 世界特許制度の現状と課題
世界的な特許制度の一元化に向けた動きが加速しており、日米欧を中心にシステム化が検討されています。その背景には、日米欧で特許全体の80%にあたる106万件の特許のうち、20万件が重複して審査されているという現状があり、審査の効率化とコスト削減を目指して相互認証システムの構築が試みられています。これは、2000年に米国が世界知的所有権機関(WIPO)に提案したもので、特許出願の重複審査を解消し、審査スピードを向上させることを目的としています。世界的な特許制度の一元化は、企業の国際的な事業展開を容易にし、知的財産の保護を強化するために非常に重要です。日本の特許制度も、審査スピードの向上など、改善が期待されています。しかしながら、世界的な競争の中で、日本の知的財産戦略の強化は、国家レベルの重要な課題となっています。
3. 日本の知財戦略における課題と解決策
日本は、近世から近代にかけて大陸や欧米からの技術導入によって発展してきました。そのため、独自の技術開発や発明に対する意識が低く、オリジナリティを重視する風土が必ずしも十分に醸成されていない可能性があります。八木アンテナの例は、日本の学会では評価されなかった技術が海外で高く評価され、軍事技術として活用されたことを示す、典型的な事例と言えます。また、青色ダイオードの発明者が日本を離れた事例は、日本の技術者に対する待遇や評価システムに課題があることを示唆しています。 これらの事例から、日本の知財戦略においては、オリジナリティを重視する文化の醸成、技術者の育成と適切な評価、そして知的財産の保護と活用を強化する政策が必要であることが分かります。 単なる技術導入ではなく、独自の技術開発を促進し、知的財産を戦略的に活用していくことが、日本の技術立国としての将来にとって不可欠です。
V.企業経営のファイナンスと戦略
リアルオプション理論に基づく柔軟な意思決定、プロジェクトファイナンス、資本コストの計算方法、ROE、NPV、EVAといった経営指標などが説明されています。日本政策投資銀行(DBJ)による風力発電事業へのプロジェクトファイナンス事例が紹介されています。マクロ論として、事業部制や組織デザイン、組織論(マックス・ウェーバー、アルフレッド・チャンドラー、ヘンリー・ミンツバーグなど)も触れられています。学習する組織(センゲ)の5つの要素(自己マスタリー、メンタルモデルの克服、共有ビジョンの構築、チーム学習、システム思考)も重要事項として挙げられています。
1. 企業活動と資金調達 資本コスト
企業活動における資金調達、投資評価・実行、回収・償還、利益獲得という拡大再生産のプロセスが解説されています。この中で、資金調達コストである資本コストが重要な要素であり、利益は資本コストを上回らなければなりません。資本コストの計算には、証券市場線やβといった概念が用いられます。 MM理論やCAPMモデルといった資金調達理論も紹介されています。これらの理論は、企業が最適な資金調達戦略を策定する上で役立ちます。 企業は、事業計画に基づいて適切な資金調達を行い、投資を効果的に実行していく必要があります。 また、投資効果の最大化を図るためには、リスク管理と効率的な資金運用が重要となります。 これらのファイナンスに関する知識は、企業経営において不可欠な要素と言えるでしょう。
2. リアルオプション理論と柔軟な意思決定
米国では、ROEといった従来の経営指標から、キャッシュフローに着目したNPVやEVAといった指標への移行が進みました。1990年代以降は、リアルオプション理論に基づいた、より現実的で柔軟な意思決定の重要性が認識されています。リアルオプションとは、金融商品のオプション取引を経営上の意思決定に適用した概念です。 これは、プロジェクト投資などにおける不確実性への対応や、柔軟な意思決定を可能にするアプローチです。リアルオプション理論を有効に活用することで、企業は不確実な状況下においても、より最適な投資判断を行うことができます。 この理論は、特にプロジェクトファイナンスなどの分野において、リスクの高い案件への挑戦を可能にする重要な枠組みとなっています。
3. プロジェクトファイナンスと事例 風力発電事業
プロジェクトファイナンスは、特定のプロジェクトを対象とした資金調達スキームです。この方式では、企業はプロジェクトへの出資のみを行い、銀行団などの協力のもとに進めるため、従来よりもリスクの高い案件に挑戦することが可能になります。 PFI法の導入により、プロジェクトファイナンスの対象となる案件の範囲はさらに広がっています。地方自治体や国、独立行政法人によるPFI事業の件数は増加傾向にあり、インフラ整備などの分野で活用されています。 具体的な事例として、日本初の商業用大型風力発電事業が紹介されています。この事業では、日本政策投資銀行(DBJ)と東海銀行がプロジェクトファイナンス方式による資金調達スキームを構築し、約20億円の融資が行われました。(総事業費45億円)苫前町も積極的に協力しており、風力発電のメッカとなっています。この事例は、プロジェクトファイナンスが、大規模なインフラ整備などの分野において有効な資金調達手段であることを示しています。
4. 組織構造と経営 マクロ論と学習する組織
マクロ論では、組織構造、組織デザイン、部門組織への機能デザインが主要なテーマとなります。 組織構造に関する理論として、マックス・ウェーバーの官僚的組織論、アルフレッド・チャンドラーの事業部制組織論などが挙げられますが、現代ではコンテンジェンシー理論が主流となっており、最適な組織構造は状況に応じて変化すると考えられています。 ヘンリー・ミンツバーグの組織進化論なども重要な理論として挙げられます。 また、ピーター・センゲの提唱する「学習する組織」の5つの要素(自己マスタリー、メンタルモデルの克服、共有ビジョンの構築、チーム学習、システム思考)も、組織能力向上、知識経営実現に不可欠な要素として提示されています。これらの要素を理解し、組織構造やマネジメント手法を最適化していくことが、企業の持続的な成長に繋がるでしょう。
