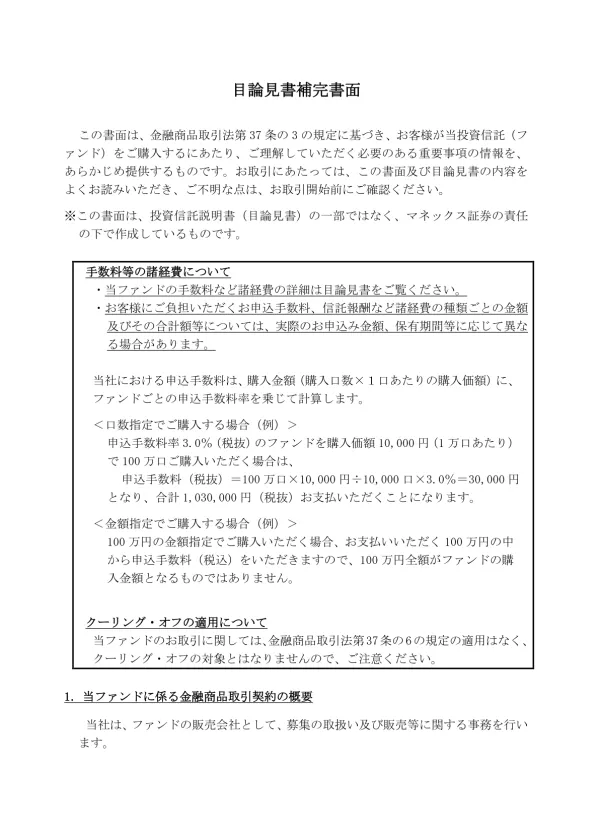
投資信託申込手数料ガイド
文書情報
| 著者 | マネックス証券株式会社 |
| 会社 | マネックス証券株式会社 |
| 場所 | 東京 |
| 文書タイプ | 目論見書補完書面 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.86 MB |
概要
I.投資概要 クレディ スイス ユニバーサル トラスト ケイマン Ⅲ ブラジル株式アルファ ファンド ツイン アルファ クラス
本外国投資信託は、ブラジル株式(iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF を含む)への投資を通じて、安定した配当収入と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。カバードコール戦略と担保付スワップ取引を用いた運用により、リスク軽減と安定的なリターンを目指していますが、為替リスク(米ドル/円、ブラジルレアル/米ドル)やオプション取引に伴う損失の可能性も存在します。基準価額は運用状況や為替変動によって変動します。分配金は元本の一部払戻しに相当する場合があり、分配金額が基準価額の上昇を下回る可能性もあります。
1. 投資戦略と運用目的
この投資信託は、主にiシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETFとブラジル株式、オプション取引、為替オプション取引への投資を通じて運用されます。 担保付スワップ取引を活用することで、ブラジル株式市場への投資リスクを軽減しつつ、安定した配当収入と中長期的な値上がり益の獲得を目指しています。具体的には、カバードコール戦略を用いて、コールオプションを売却することでプレミアム収入を得ることを目指す一方、ブラジル株式の価格上昇による利益も獲得できるよう設計されています。しかし、売却したコールオプションの価値は、ブラジル株式(ETF)の価格や変動率の上昇によって上昇し、損失を被る可能性がある点には留意が必要です。 また、このファンドは円建ですが、ブラジル株式(米ドル建てETF)への投資であるため、円/ドルの為替レート変動の影響を受けます。さらに、ブラジル株式の多くはブラジルレアル建てであるため、レアル/ドルの為替レート変動も投資パフォーマンスに影響を与えます。 カバードコール戦略を用いないブラジル株式(ETF)への直接投資と比較して、投資成果が劣る可能性があることも明記されています。
2. 分配金と基準価額
投資家の購入価額によっては、分配金の一部または全部が元本の一部払戻しに相当する場合があります。これは、ファンド購入後の運用状況、特に基準価額の値上がり幅が分配金額を下回る場合に発生する可能性があります。また、計算期間中に発生した収益を超えて分配金が支払われるケースもあり、その場合には当期決算日の基準価額が前期決算日と比較して下落します。このことは、分配金を受け取る際に、それが元本の一部返還である可能性があること、そして、分配金を受け取ったからといって必ずしも投資金額が増えているわけではないことを示唆しています。基準価額は、運用成績や為替レートの変動、市場環境などの様々な要因によって変動することを理解しておく必要があります。 そのため、分配金の受取は、必ずしも元本増加を意味するわけではないことに注意が必要です。
3. リスク要因の詳細
本ファンドの投資には、いくつかのリスクが伴います。まず、為替レートの変動リスクが挙げられます。円高傾向になれば、外貨建資産の評価額が下がり、基準価額も値下がりする可能性があります。 次に、オプション取引に伴うリスクがあります。コールオプションの売却戦略はプレミアム収入をもたらしますが、ブラジル株式の価格や変動率の上昇によって損失が発生する可能性があります。オプション料(プレミアム)収入の水準は、ブラジル株式(ETF)の価格や為替レート、変動率、権利行使価格、満期までの期間、市場の需給関係など、複数の要因によって決まるため、当初の想定通りに収入が確保できない可能性があります。 さらに、担保付スワップ取引におけるカウンターパーティーリスクも存在します。取引相手方の倒産や契約不履行などが発生した場合、運用の継続が困難となり、将来の投資成果が得られないばかりか、担保の処分価格が想定を下回ることで損失を被る可能性があります。基準価額の変動要因は、上記に挙げたもの以外にも存在する可能性があることを理解しておく必要があります。
II.リスク要因
本ファンドには、為替リスク、オプション取引に伴う損失リスク、担保付スワップ取引の相手方の倒産や契約不履行によるリスクなどが存在します。ブラジル株式(ETF)に直接投資する場合に比べ、投資成果が劣る可能性もあります。基準価額の変動要因は上記に限定されません。
1. 為替リスク
本ファンドはブラジル株式(米ドル建てETF)を主要投資対象とするため、為替レートの変動、特に円/ドルレートとブラジルレアル/ドルレートの変動が大きなリスクとなります。円高、またはレアル安の状況下では、資産の評価額が下がり、基準価額の値下がりにつながる可能性があります。ファンドでは原則として為替ヘッジを行わないため、これらの為替変動の影響を直接的に受けることになります。投資家は、為替レートの変動が投資パフォーマンスに大きな影響を与える可能性があることを理解しておく必要があります。為替レートの変動は予測不可能な要素であり、投資損失につながる可能性があることを認識しておくことが重要です。このリスクを軽減するための具体的な対策は本資料には記載されていません。
2. オプション取引リスク
本ファンドはカバードコール戦略の一環として、コールオプションを売却します。この戦略はプレミアム収入を得ることを目的としていますが、ブラジル株式の価格やボラティリティの上昇によって、売却済みのコールオプションの価値が上昇し、結果として損失を被る可能性があります。オプション取引には、市場の動向、ボラティリティ、権利行使価格、満期までの期間、市場の需給関係など多くの不確定要素が関与しており、これらの要素によって、当初想定していたプレミアム収入を確保できない可能性も否定できません。投資家は、オプション取引が潜在的に大きな損失をもたらす可能性があることを認識し、リスクを適切に評価する必要があります。このリスクは、市場状況の急激な変化によって特に顕著になる可能性があります。
3. スワップ取引に伴うリスク
ファンドは担保付スワップ取引を通じて運用されますが、カウンターパーティーリスクが存在します。スワップ取引の相手方が倒産したり、契約を履行しなかったり、その他予期せぬ事態が発生した場合、運用の継続が困難になり、将来の投資成果を得ることができなくなる可能性があります。さらに、担保を処分する際に、想定していた価格で処分できない可能性も高く、その結果、損失を被る可能性があります。このリスクを軽減するために、取引相手方から担保を受け取っていますが、それでも完全なリスク排除はできません。投資家は、担保付スワップ取引に固有のリスクを理解し、その可能性を考慮した上で投資判断を行うべきです。不測の事態に対する備えとして、このリスクを軽減する具体的な対策が委託会社によって講じられているかを確認することが重要です。
4. 投資成果に関するリスク
本ファンドの投資成果は、ブラジル株式(ETF)への直接投資と比較して劣る可能性があります。これは、カバードコール戦略や担保付スワップ取引などの手法を用いることで、リスク軽減と安定的なリターンを目指しているためです。しかし、これらの戦略は、市場環境によっては必ずしも有効に機能せず、投資成果が期待を下回る可能性も含まれています。投資家は、このファンドが必ずしも市場の動向に完全に追随するわけではないことを理解し、他の投資方法と比較した上で投資判断を行う必要があります。 過去の実績は将来の成果を保証するものではないことを銘記しておくことが重要です。
III.課税に関する事項
個人受益者に対する課税は、普通分配金が配当所得として源泉徴収され、換金時の差益は譲渡所得として課税されます。法人受益者については、普通分配金と換金時の個別元本超過額が源泉徴収の対象となります。少額投資非課税制度の適用対象です。
1. 個人の受益者に対する課税
個人の受益者に対する課税は、収益分配金と換金・償還時の差益の2種類に分けられます。収益分配金の内、課税対象となる普通分配金は、配当所得として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収されます。確定申告は不要ですが、申告分離課税または総合課税を選択することも可能です(配当控除の適用はありません)。換金時や償還時の差益(譲渡益)は譲渡所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。換金時や償還時の損益については、確定申告を行うことで、上場株式等の譲渡損益、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得、特定公社債等の利子所得や譲渡所得等と損益通算が可能です。 税制に関する詳細は、税務専門家にご相談いただくことを推奨します。
2. 法人の受益者に対する課税
法人の受益者については、収益分配金の内、課税対象となる普通分配金と、換金時および償還時の個別元本超過額に対して課税が行われます。これらの課税対象額は、15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。このファンドは、公募株式投資信託であるため、税法上、少額投資非課税制度の適用対象となります。 法人税に関する詳細な計算方法や適用される税率については、税務関係の専門家への確認が必要です。税制は変更される可能性があるため、常に最新の情報を把握しておくことが重要です。
3. 個別元本の計算方法
受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、追加信託を行うごとに受益権口数で加重平均して算出されます。ただし、複数の販売会社で購入した場合、または同一販売会社でも複数の支店で購入した場合、あるいは一般コースと自動継続投資コースの両方で購入した場合などは、販売会社ごと、支店ごと、コースごとに個別元本の算出が行われる場合があります。また、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受領した場合、その後の個別元本は、収益分配金発生時に元本払戻金相当額を控除した額となります。この複雑な計算方法は、投資家の理解を必要とするため、不明な点については販売会社に問い合わせることを推奨します。特に、複数回購入や複数の販売会社を利用する場合は、個別元本の計算方法を正確に理解しておくことが重要です。
IV.換金 償還
換金申込受付日から原則6営業日目に換金代金が支払われますが、市場の取引停止等のやむを得ない事情により遅延する可能性があります。大口の換金申込には制限が設けられる場合があります。償還金は信託終了日における基準価額に基づき、振替口座簿に記載されている受益者に支払われます。
1. 換金手続きと支払日
換金申込の受付後、原則として6営業日目から換金代金が受益者に支払われます。ただし、金融商品取引所の取引停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止などのやむを得ない事情が発生した場合は、支払開始日が遅延する可能性があります。信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込などには制限が設けられる場合があり、詳細は販売会社にお問い合わせください。換金申込は、振替受益権をもって行うものとされ、委託会社は、やむを得ない事情がある場合は換金申込の受付を中止したり、既に受付けた申込を取り消す権限を有しています。受付中止の場合、受益者は当日の換金申込を撤回できますが、撤回しない場合は、受付中止解除後の最初の基準価額計算日に換金申込を受付けたものとして計算されます。換金手続きには、振替機関等の振替口座簿への記載・記録が必須である点に留意が必要です。
2. 償還金の請求権と支払
受益者は、ファンドの償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。償還金の支払いは、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して行われます。ただし、信託終了日以前に換金が行われた受益権、または購入代金支払前で販売会社名義で記載されている受益権については、それぞれ例外的な取り扱いがあります。償還金の受領には、受益者がその口座を開設している振替機関等に対して、委託会社による償還と引き換えに、償還に係る受益権の口数と同口数の抹消申請を行う必要があります。この手続きは、社債、株式等の振替に関する法律(社振法)の規定に基づいて行われます。償還金支払に関する詳細なスケジュールや手続きについては、委託会社からの通知や販売会社への問い合わせを通じて確認する必要があります。
V.運用報告 開示
運用報告書は4月、10月、償還時に交付され、委託会社ホームページでも開示されます。
1. 運用報告書の交付
4月と10月の決算時、および償還時に運用報告書が作成され、販売会社を通じて受益者に交付されます。運用報告書(全体版)は委託会社のホームページでも公開されますが、受益者からの請求があれば、個別に交付も行われます。 運用報告書には、ファンドの運用状況、投資内容、収益状況などが詳細に記載されます。これにより、受益者はファンドの運用状況を定期的に確認することが可能となります。 報告書の内容に関するご質問などは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。 運用報告書の内容は、投資判断を行う上で重要な情報源となりますので、定期的に確認することをお勧めします。
VI.委託会社 T Dアセットマネジメント株式会社
T&Dアセットマネジメント株式会社は、定期的なモニタリングと運用計画の見直しを行い、運用リスク管理を行っています。業務管理部はパフォーマンス分析を行い、法務・コンプライアンス部は法令遵守を監視しています。詳細なリスク管理体制については、別途資料を参照ください。
1. 委託会社のリスク管理体制
T&Dアセットマネジメント株式会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準および管理体制を定めており、運用体制自体がリスク管理体制を兼ねています。ファンドマネージャーは投資環境、市況見通し、ポートフォリオ状況、運用成果などを定期的にモニタリングし、原則として月次(必要に応じて随時)、運用計画の見直しを行い、運用部長による承認を経て運用指図を行い、トレーディング部が執行します。業務管理部は運用リスク管理を所管し、ファンドのパフォーマンス分析・評価を月次で行い、運用審査委員会に報告することで運用成績の改善をサポートします。法務・コンプライアンス部は法令・約款・運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告します。この3部門によるチェック体制によって、投資リスクの管理と運用パフォーマンスの向上に努めています。
