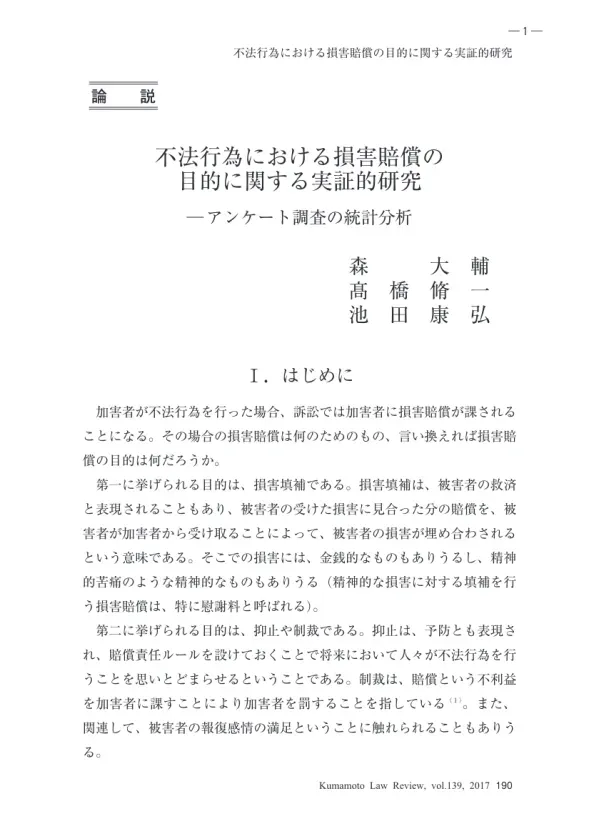
損害賠償目的:実証研究とアンケート分析
文書情報
| 著者 | 森 大輔 |
| 専攻 | 法学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.63 MB |
概要
I.日本の損害賠償制度と懲罰賠償 目的と現状
本論文は、日本の損害賠償制度における懲罰賠償の導入に関する議論を検討しています。日本の損害賠償は、被害者の現実の損害の金銭的評価と填補を目的とし、加害者への制裁や一般予防は刑事・行政上の措置に委ねられています。判例は一貫して、制裁的慰謝料を含む制裁的要素を持った損害賠償を否定しており、民事と刑事の峻別が強調されています。 萬世工業事件判決は、カリフォルニア州判決の懲罰賠償部分の執行を拒否した代表例です。
1. 日本の損害賠償制度の目的
日本の不法行為に基づく損害賠償制度の根本的な目的は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者に賠償させることで、被害者が被った不利益を補てんし、不法行為がなかった状態に回復させることにあります。これは、加害者に対する制裁や将来における同様の行為の抑止(一般予防)を目的とするものではありません。加害者への損害賠償義務によって、結果的に制裁や一般予防効果が生じる場合もあるかもしれませんが、それは被害者の不利益回復という主要目的の副次的効果に過ぎず、我が国では加害者への制裁や抑止は刑事または行政上の制裁に委ねられています。この点は、損害賠償制度の根幹をなす重要な考え方であり、民事と刑事の峻別という近代法の原則とも深く関わっています。 損害賠償請求においては、被害者の受けた損害を正確に評価することが重要であり、その評価基準も重要な論点となります。
2. 懲罰賠償と制裁的慰謝料に関する議論
懲罰賠償は、問題となる違法行為に対する懲罰として、被告の行為の非難性が強い場合に実損害を超える賠償を課すものです。課されるかどうかは被告の行為の非難性の強さに依存し、単なる過失では課されませんが、他者に害を与える目的で行われた行為や、他者の危険を顧みずに行われた行為には課される可能性があります。懲罰賠償の額も、被告行為の非難性の強さが考慮されます。薬害事件や公害事件といった社会問題を背景に、損害賠償制度の中で慰謝料に制裁的な要素を含める『制裁的慰謝料』の導入が主張されてきました。これは、刑事罰や行政上の制裁だけでは不十分であるとの認識に基づき、違法行為の抑止効果を高めることを目的としています。しかし、日本の判例は一貫して、制裁的な要素を持った損害賠償を否定しています。萬世工業事件判決は、この点を明確に示す重要な判例であり、カリフォルニア州判決の懲罰賠償部分の執行を拒否しました。制裁的慰謝料についても、同様の否定的な見解が示されています。
3. 民事と刑事の峻別と懲罰賠償への批判
日本の判例が懲罰賠償を否定的に捉える背景には、民事と刑事の峻別という考え方が強く影響しています。制裁は刑事法の役割であり、民事裁判に制裁的な要素を持ち込むことに対して消極的な姿勢が示されています。民事裁判で刑事手続きよりも緩やかな基準で制裁を課すことの問題点、刑事罰に加えて民事で制裁的な賠償が課される二重処罰の問題、実損を超えた賠償額が被害者に不当に利益をもたらす可能性など、懲罰賠償制度には様々な批判が寄せられています。これらの批判は、損害賠償制度の目的である被害者への損害填補という観点から、懲罰賠償の導入に慎重な姿勢を示す根拠となっています。 民事裁判における損害賠償の目的は、あくまでも被害者の損害を補てんすることにあり、制裁や抑止は刑事・行政手続きに委ねられるべきだという考え方が根強く存在しています。
II.懲罰賠償の課題 額のばらつきと公平性
アメリカ合衆国では、懲罰賠償の額のばらつきが大きな問題となっています。連邦最高裁は、合衆国憲法修正第8条の過大な罰金の禁止条項に抵触する可能性や、公平性の欠如を指摘し、填補賠償額との比率の上限を設定する判決を出しています。このばらつきは、陪審の裁量による予測不可能性に起因するとされています。
1. 懲罰賠償額のばらつきと予測不可能性
アメリカ合衆国の懲罰賠償制度においては、賠償額のばらつきが大きな問題となっています。連邦最高裁の判決でもこの点が議論されており、州の陪審による懲罰賠償に関する研究結果が引用されています。この研究によると、懲罰賠償額と填補賠償額の比率の中央値は0.62対1と比較的低いものの、平均値は2.90対1と高く、標準偏差は13.81にも及びます。これは、外れ値として非常に高額な懲罰賠償が課されているケースが存在することを示しています。裁判官が決定する場合でも、依然としてばらつきは大きいと指摘されています。このばらつきは、懲罰賠償額の予測不可能性につながり、公平性に欠けるという問題点を提起しています。 連邦最高裁は、この問題に対処するため、懲罰賠償額と填補賠償額の比率に上限を設定する判決を出しています。
2. 連邦最高裁の判決と上限比率設定の理由
連邦最高裁が懲罰賠償額の上限比率を設定した背景には、賠償額の予測不可能性という問題への懸念があります。同裁判所は、実証的な研究データから、懲罰賠償額と填補賠償額の比率の中央値は概ね1対1以下で安定していることを認めています。しかし、同時に、上記のような研究結果から、懲罰賠償額に大きなばらつきがあることを指摘しています。 アラスカでのタンカー座礁事故に関する判決では、海事法上の観点から、懲罰賠償額と填補賠償額の上限比率を設定しています。この上限比率を超えることはできないと判示した理由は、懲罰賠償額の予測不可能性という問題点を解消するためです。 連邦最高裁は、懲罰賠償制度に問題がないという態度をとっているわけではなく、近年抱える「真の問題」として、このばらつきを指摘している点が重要です。
3. 公平な告知と手続き上の問題点
連邦最高裁は、合衆国憲法修正第8条に基づき、過大で恣意的な懲罰の賦課を禁じています。このため、制裁が課される行為だけでなく、制裁の大きさについても公平な告知が必要だと強調しています。さらに、懲罰賠償を課す手続きについても問題点を指摘しています。刑事裁判のような保護がなく、陪審の幅広い裁量性によって偏見に基づいた判断がなされる可能性があるということです。これらの問題は、懲罰賠償制度の公平性と正当性を確保する上で重要な課題となっています。 アメリカにおける懲罰賠償制度の運用実態と、その制度設計上の問題点が示唆されています。 特に、陪審の裁量と憲法上の制約とのバランスが、議論の中心となっています。
III.一般人の損害賠償意識に関するアンケート調査
本研究では、架空の自動車事故シナリオを用いたインターネットアンケート調査を実施し、一般人の損害賠償額の評価と損害賠償の目的に関する意識を調査しました。調査対象は関東地方在住の20~60代モニター546名です。賠償評価額は、金銭的損害の填補、精神的損害の填補、制裁、将来の事件発生の抑制、報復感情の満足といった要素を考慮して決定されます。問題隠しの有無も評価に影響を与え、特に制裁や精神的損害の填補への影響が大きかったです。 国への支払い制度に関する設問では、被害者の精神的救済に役立つと捉えられていました。
1. アンケート調査の概要と方法
本研究では、一般人の損害賠償意識を調査するため、インターネットを用いたアンケート調査を実施しました。調査はNTTコムリサーチに委託され、2015年1月に実施されました。対象は関東地方7都県(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬)に居住する20~60代のモニターで、各県の男女比と年代別人口比を考慮した割り当て抽出を行い、回収目標500名に対し、546名の有効回答を得ています。調査票では、架空の自動車事故シナリオを提示し、製造会社の設計上の欠陥による事故で被害者(Aさん)が負傷、車両損壊、休業損害を被った状況を設定しました。シナリオは、「問題隠し有」と「問題隠し無」の2バージョン用意され、それぞれに回答者はB社がAさんに支払うべき損害賠償額を自由に記入する設問が設けられています。 この設問では、法律上の知識ではなく、回答者の感覚に基づく適切な賠償額を尋ねています。
2. 損害賠償額の評価と損害賠償の目的
アンケートでは、賠償評価額の算定に際し、回答者がどの程度「損害賠償の目的」を考慮したかを尋ねています。具体的には、「Aさんの金銭的損害の填補」、「B社への制裁」、「Aさんの精神的損害の填補」、「将来の同様な事件の抑制」、「Aさんの報復感情の満足」の5項目について、考慮の程度を尋ねました。 シナリオには、被害者の負った損害として、車両修理費用50万円、治療費300万円、休業損害100万円が明記されており、精神的損害については、入院1ヶ月、通院2ヶ月の期間に基づき、過去の判例から算出される慰謝料98万円を想定しています。 これらの損害賠償項目は、交通事故の事例を参考に、財産的損害(積極損害・消極損害)と精神的損害に分類されています。
3. 調査結果 損害賠償目的と賠償評価額の関係
調査結果の分析では、賠償評価額に影響を与える要素として、損害賠償の目的、法知識、裁判への態度などが検討されています。 損害賠償の目的のうち、「金銭的損害の填補」はどの回答者も考慮している一方、「制裁」、「将来の事件発生の抑制」、「報復感情の満足」は、それよりも少ないものの、一定数の回答者が考慮していました。これらの間には有意な相関関係が見られ、特に「制裁」と「将来の事件発生の抑制」は密接な関連を持つものの、完全に重なり合っているわけではないことが示唆されています。「金銭的損害の填補」は、「日本の刑罰は厳しいと思うか」との間に有意な負の相関があり、日本の刑罰を厳しいと考えるほど、金銭的損害の填補を重視する傾向が見られました。 シナリオの「問題隠し」の有無も賠償評価額に影響を与え、特に「制裁」や「精神的損害の填補」への影響が大きかったことが示唆されています。
IV.法学部生との比較と考察
熊本大学法学部生128名に対しても同様のアンケート調査を行い、一般人との比較を行いました。賠償評価額の平均、中央値、標準偏差に統計的有意差はありませんでしたが、一般人の方がばらつきが大きく、特に問題隠し有シナリオにおいて外れ値が多かったです。法学部生においても、制裁、将来の事件発生の抑制、報復感情の満足を考慮するほど賠償評価額が高くなる傾向が見られました。しかし、一般人ほど明確な傾向は見られませんでした。
1. 法学部生対象アンケート調査の概要
本研究では、一般人のアンケート調査に加え、熊本大学法学部「法社会学I」受講生128名を対象としたアンケート調査も実施しました。調査は2015年4月に行われ、一般人同様、「問題隠し有」と「問題隠し無」の2種類のシナリオを用いた調査票が無作為に配布されました。この法学部生に対する調査は、一般人の回答結果と比較することで、法学教育や法律知識が損害賠償額の評価や損害賠償の目的への影響を検討するためのものです。ただし、この調査は標本抽出を行っていないため、結果の代表性は保証されず、あくまで参考資料として位置付けられています。分析は、賠償評価額と損害賠償の目的に絞って行われています。
2. 一般人との比較 賠償評価額
一般人との比較においては、まず賠償評価額に着目しました。一般人の回答と法学部生の回答を比較した結果、評価額の平均、中央値、標準偏差のいずれにも統計的に有意な差は見られませんでした。シナリオ別(「問題隠し有」と「問題隠し無」)に比較すると、一般人の回答では「問題隠し有」シナリオの方が標準偏差が大きく、外れ値も多くなっていました。一方、法学部生の回答では、シナリオによるそのような違いは見られませんでした。 このことから、法学知識を持つ者とそうでない者では、損害賠償額の評価に際して、情報(問題隠しの有無)の影響受け方に違いがあることが示唆されます。
3. 一般人との比較 損害賠償目的と賠償評価額の関係
次に、損害賠償の目的と賠償評価額の関係について、一般人と法学部生を比較しました。法学部生においても、一般人ほど明確ではありませんが、「制裁」、「将来の事件発生の抑制」、「報復感情の満足」を考慮するほど、賠償評価額の平均が高くなる傾向が見られました。 賠償評価額のばらつき(標準偏差)については、法学部生では、「将来の事件発生の抑制」を考慮するほど大きくなり、「金銭的損害の填補」を考慮するほど小さくなる傾向が見られました。この傾向は一般人の結果と類似しており、法学知識の有無に関わらず、損害賠償額の評価においてこれらの要素が考慮されていることがわかります。 ただし、法学部生の回答におけるこれらの傾向は、一般人ほど明確ではなかった点が注目されます。
